�u�l�H����v����R�������������
�u���C���u�v�������{���_��
�u��H�p�ڑ����ށv����R���������
�u���㎥�C�Đ���ÍR�ۗp�i�v����R�������������
�n�Z�������e�u�e��v�����R���������
�u���x���V�t�^�v����R�������������
�u���ԊO�����ˑ́v�������N�Q���~�������T�i����
�u�q�[�g�V�[�����u�v����R���������
�u�L�V���g�[���������v����R���������
�u���R�@�ւ̔r�K�X���@�y�я��u�v����R���������
�u���s�ƌ�����v�����V�X�e���v�R�������������
�u�L�j��������т��̐����@�v�������������ԉ����o�^�o�苑��R���������
�u���v�������������ԉ����o�^�o�苑��R���������
�u���f�M�E���C���Z��ɂ�����[��d�͗��p�~�M�������g�[�V�X�e���v�����R���������
�u�l�H����v����R�������������
| �����ԍ� | �@����14�N(�s�P)��539�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����15�N10��08�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
��T�@���ٔ����̔��f
�P�@������R�i�����@�S�P���Q���̓K�p�̌��j�ɂ���
�@(1)�@�����@�S�P���Q���́A���@�Q�X���̂Q�̓K�p�ɌW��D�挠�咣�̌��ʂɂ��āu�E�E�E�D�挠�̎咣�������o��ɌW�锭���̂����A���Y�D�挠�̎咣�̊�b�Ƃ��ꂽ��̏o��̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʁE�E�E�ɋL�ڂ��ꂽ�����E�E�E�ɂ��ẮE�E�E��Q�X���̂Q�{���A�E�E�E�̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���Y�����o��́A���Y��̏o��̎��ɂ��ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��v�ƋK�肵�A��̏o��ɌW�锭���̂����A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�����Ɍ���A���̏o�莞�@�Q�X���̂Q�̓K�p�ɂ�����I�ɑk�y�����邱�Ƃ��߂Ă���B��̏o��ɌW�锭������̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�����͈̔͂̂��̂Ƃ����邩�ۂ��́A�P�Ɍ�̏o��̓��������͈̔͂̕����Ɛ�̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�����Ƃ�Δ䂷��̂ł͂Ȃ��A��̏o��̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�����Ɛ�̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����Ƃ̑Δ�ɂ���Č��肷�ׂ��ł��邩��A��̏o��̓��������͈̔͂̕������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ���̂Ƃ�����ꍇ�ł����Ă��A��̏o��̖����̔����̏ڍׂȐ����ɁA��̏o��̓����������ɋL�ڂ���Ă��Ȃ������Z�p�I�������L�ڂ��邱�Ƃɂ��A��̏o��̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����͈̔͂��邱�ƂɂȂ�ꍇ�ɂ́A���̒����������ɂ��Ă͗D�挠�咣�̌��ʂ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�u���C���u�v�������{���_��
| �����ԍ� | �@����20�N(�l)��10070�� |
|---|---|
| ������ | �@���Q���������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N01��28�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��Q ���Ă̊T�v
�P ���R�̌o�ܓ�
�@��T�i�l�i���R�����B�ȉ��u�����v�Ƃ����B�j�́A�T�i�l�j�i���R�퍐�B�ȉ��u�퍐�j�v�Ƃ����B�j�Ƃ̊ԂŁA�퍐�j����������L���Ă��������̖��́u�Ε��C���u�v�̓����i������R�R�X�U�V�V�U���B�ȉ��u�{�������v�Ƃ����A���̔������u�{�������v�Ƃ����B�j�ɂ��āA��p���{���ݒ�_��i�ȉ��u�{�����{�_��v�Ƃ����ꍇ������B�j��������A���_��Ɋ�Â��Ĕ퍐�j�ɑ��_����R�O�O�O���~���x���������A���̌�A�{���������Ƃ���R�����m�肵���B�����́A�퍐�j�y�ѓ��l�̌o�c����T�i�l������А̓����{���i���R�퍐�B�ȉ��u�퍐�̓����{���v�Ƃ����A�퍐�j�ƕ����āA�ȉ��u�퍐��v�Ƃ����B�j�ɑ��āA�ȉ��̂Ƃ���̐����������B
(1)�i��ʓI�咣�j�@�퍐�炪�A���d�̏�A�{�������ɖ��������̂��邱�Ƃ�m��Ȃ���A�����ɂ��̂��Ƃ��������ɖ{���������L���ł���ƌ�M�����A�܂��A�{�������̎��{�i�ł͂Ȃ��Ε��C���u���A�{�����������{�������̂ł���ƌ���Đ������A���������Ė{�����{�_�����������A�_����R�O�O�O���~���x���킹�����Ƃ������s�@�s�ׂ��\������A�A�퍐�炪�{�������̖����������A�{�������ɌW��Ε��C���u���������Ɛ�I�Ɏg�p�ł��Ȃ����������Ƃ������s�@�s�ׂ��\������i�퍐�̓����{���ɑ��Ă͗\���I�ɉ�Ж@�R�T�O���j�Ǝ咣���āA���Q���R�O�O�O���~�y�т���ɑ��镽���P�W�N�P�O���Q�V������x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߂�ƂƂ��ɁA
(2)�i�\���I�咣�j�퍐�炪�A�{�������̖��������������āA�{�������ɌW��Ε��C���u��Ɛ�I�Ɏg�p�ł��Ȃ����������Ƃ́A���s���s�ɓ�����Ǝ咣���āA�퍐�j�y�ю����I�Ȍ_���҂ł���퍐�̓����{���ɑ��A���z�̑��Q�������̎x�������߁A
(3)�i�\���I�咣�j�{�����{�_��͍���ɂ��A���͌����Ǒ��ᔽ�ɂ��A�����ł���Ǝ咣���āA�퍐��ɑ��A�s�������ԊҐ������Ɋ�Â���L�_������Ɠ��z�̕Ԋ҂𐿋������B
�@�������́A(1)�s�@�s�ׂɌW��咣�A�y��(2)���s���s�ɌW��咣����������r�˂������A(3)�v�f�̍���ɌW��咣��F�߂āA�����ɔ퍐��ɑ���A�e���_��������z�̕s���������R�O�O�O���~�y�т���ɑ��镽���P�W�N�P�Q���P���i�ԊҍÍ��̗����j����x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���i�s�����j�̎x���𖽂���|�̈ꕔ�F�e�����������B
�@�퍐��́A��������s���Ƃ��Ė{���T�i���N�����B
�i�����j
��R ���ٔ����̔��f
�@���ٔ����́A�����̎咣�ɌW��A(1)�s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������A(2)���s���s�Ɋ�Â����Q�����̐����A�y��(3)�v�f�̍��떔�͌����Ǒ��ɂ�閳�����͐M�`���ᔽ�ɂ��s�������ԊҐ����̂�������r�˂��ׂ����̂Ɣ��f����B
�@���̗��R�́A(1)�y��(2)�̐����ɂ��ẮA�������̂Ƃ���ł��邩��A�������P�Q�łP�V�s�ڂ���Q�Q�łQ�Q�s�ڂ����p����B
�P �v�f�̍���̗L���y�э���Ɋւ���d�ߎ��̗L���ɂ���
(1) �����o��
�@�{�����{�_������̑O��̎���́A�������Q�łQ�P�s�ڂ���T�łQ�T�s�ڋy�тP�Q�łP�V�s�ڂ���P�X�łP�Q�s�ڂɋL�ڂƂ���ł��邩��A�����������p����B
�@���p������v��A�ȉ��̂Ƃ���ƂȂ�i�O�L�����ҊԂɑ����̂Ȃ��������̂ق��A�؋��i�b�P�A�X�A�P�Q�Ȃ����P�S�A�Q�O�A���P�A�Q�O�Ȃ����Q�R�A�Q�X�A�R�O�A�R�T�Ȃ����R�V�A���P�Ȃ����R�A���S�̂P�y�тQ�A���T�A���W�̂P�y�тQ�A���X�Ȃ����P�S�A���P�T�̂P�y�тQ�A���P�U�Ȃ����P�W�A���R�̂e�،��A���R�̔퍐�j���q�A���R�̋����퍐�y���q�j�j�B
�A�Ε��C���u�̌����J�������Ă����퍐�j�ƁA�u���̓��v�i�����̖��̂́u�L����Ђ݂�Ȃ̐̓��v�j���o�c����y�́A�����P�T�N�R���A�{�������ɌW��Ε��C���u���A�������Ĕ̔����鎖�Ƃ�i�߂邱�ƂƂ��A�������Ƃ̐��s�ɓ������āA�퍐�j�́A�u���̓��v�ɑ��āA�{�������̒ʏ���{����ݒ肷��|�̌_�����������B
�@�y�́A�����P�T�N�R������A�Ε��C���u�̔��̃��f���ɂ��邽�߁A�퍐�j�̎w�����āA�u���̓��v�̌o�c�ɌW�鉷��h���{�݁u���т₩�������v�i�R�`���j���ɐΕ��C���u�P����ݒu�����B�܂��A�y�́A�����P�T�N�P�O������A�Ε��C���u�P���̖�Αw�ɉ������ď��C�����A�Ε��C�������̏��C�ŏ[��������\����t�������y���u�i�Ε��C���u�Q���j���u���т₩�������v���ɐݒu�����B
�C�e�i��ɐݗ�����錴���̖����j��́A�����P�T�N�P�O������A�Ε��C���u��p�����{�݂Ɋ֘A���鎖�Ƃ��s�����ƍl���āA�u���т₩�������v��K�ꂽ�B�����āA�y����A�y���u�̍\���̊T�v�A�y���u���퍐�j�̗L����{�������������{�������̂ł��铙�̐��������B
�e��́A�����P�T�N�P�P������A�Ε��C���u��p�����{�݂�����ݒu���Čo�c����ɂ͎���������Ȃ��̂ŁA�ނ���A�{�������̐�p���{���̐ݒ���āA��O�҂ɍċ�������r�W�l�X���s�����Ƃ��l�����B�����āA�����P�T�N�P�Q���ɁA�퍐�j��Ƃe�炪���c�����B���̍ۂɁA�퍐�j��́A�e��ɑ��A��L���{�_�Ă̌_������̓��e�ɂ��Đ������A���ɁA�{�����{�_�U���P���ɂ��ẮA�����������ɂȂ��Ă��_������̕Ԋ҂����Ȃ����̎�|��������A�e����A���{�_�Ă̓��e�𗹉������B���̒���̕����P�T�N�P�Q���P�Q���ɁA������������ЂƂ��Đݗ����ꂽ�B
�����P�T�N�P�Q���Q�Q���ɁA�퍐�j�A������\�ҁA�e�A�y�炪���Ȃ��Ė{���������ɂ��Đ�p���{����ݒ肷��|�̌_�����������B���{�n��͊��y�ђ��쌧�ł���A���̑���͂R�O�O�O���~�ł������B�����́A��p���{���҂ł���A�퍐�j�̏����đ��l�ɒʏ���{�����������邱�Ƃ��ł���B�܂��A�������ɂ��Ă͕Ԋ҂��Ȃ��|�̓��t����Ă���B�����P�T�N�P�Q���Q�S���A�����́A�퍐�j�ɑ��A�{�����{�_��Ɋ�Â��A�{���_����R�O�O�O���~���x�������B
�E���̌�A�퍐�j�ƁA�ʏ���{���҂ł������u���̓��v�i�퍐�y�o�c�j�Ƃ̊ԂŁA�����̗L�����̔F���ɂ��Č����̑��Ⴊ�����A�����͒ʏ���{���_�����������ƂƂ��ɁA�u���̓��v�ɑ��āA�y���u���{����������N�Q����Ǝ咣���āA�������N�Q���~�i�ׂ��N�����B�������A�퍐�j�́u���̓��v�ɑ��铯�N�Q�i�ג�N���_�@�ƂȂ�A�u���̓��v�������R���������N�����Ƃ���A�����P�V�N�S���������́A�i�����Ȃ��Ƃ̗��R�ɂ��A�{���������Ƃ���R�������A���̌㕽���P�W�N�P�O���ɓ��R���͊m�肵���B
(2) ���f
�@��L�̖{�����{�_��̒����O��̎����o�܂ɏƂ炷�Ȃ�A�{�����{�_����������ɓ�����A�y���u���{�������̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂��ƌ�������M�����_�́A�v�f�̍���ɓ�����Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��A�܂��A�����̔F�����������ɉ��炩�̓_�Ō�肪�������Ƃ��Ă��A����͏d��ȉߎ��Ɋ�Â����̂Ƃ����ׂ��ł��邩��A�����͖{�����{�_��̖������咣���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@���Ȃ킿�A�{�����{�_��́A�c����ړI�Ƃ��鎖�Ƃ𐋍s���铖���ғ��m�ɂ��������ꂽ���̂ł���A���̑Ώۂ́A�{���������i��p���{���j�ł��邩��A�_��̓����҂Ƃ��ẮA����̒ʔO�Ƃ��āA�_����������ۂɁA�_��̓��e�ł�����������ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩���������邱�Ƃ́A�K�v�s���ł���Ƃ�����B���Ȃ킿�A�����I�Ȏ��Ǝ҂Ƃ��ẮA�u�����̋Z�p�I�͈͂��ǂ̒��x�L�����̂ł��邩�v�A�u���Y���������������Ƃ����\�����ǂ̒��x�ł��邩�v�A�u���Y�������i��p���{���j���A���Ȃ̌v�悷�鎖�Ƃɂ����āA�ǂ̒��x�L�p�ōv�����邩�v���𑍍��I�Ɍ����A�l�����邱�Ƃ͓��R�ł���Ƃ�����B�����āA�u�Z�p�I�͈͂̍L���v�y�сu�����̉\���v�ɂ��ẮA��������A�o��葱�y�ѐ�s�Z�p�̏��A�������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ邪�A���ɁA���番�́A�]�����邱�Ƃ�����ł������Ƃ��Ă��A���Ƃ̈ӌ������߂铙�ɂ��A�K�X�̕]�������邱�Ƃ͉\�ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�@�{���ł́A�����́A�퍐�j����A��p���{���̐ݒ���A���̌����Ɋ�Â��āA��O�҂ɍċ����i�ʏ���{���j�����A�܂��A����{�݂��^�c���邷�邱�Ƃɂ���āA���v��}�邱�Ƃ��v�悵�Ă����̂ł��邩��A�����Ƃ��ẮA���̂悤�Ȏ��ƖړI�Ƃ̊֘A���ɂ����āA�{���������i��p���{���j�̉��l�i�����̋Z�p�I�͈͓��j�́A�]���y�ь��������ׂ��ł������Ƃ����ׂ��ł���B
�@�Ƃ���ŁA�{���������́A�����ґo�����\�����Ȃ���������ɂ���āA�����Ƃ����Ɏ��������A�{�����{�_��ł͕s�Ԋ҂̓��t����Ă������߁A�����́A�����ƂȂ������Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�x���������z�̕Ԋ҂����߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B
�@�������A���ɁA�{�������������Ƃ���鎖��������Ȃ������Ƃ���A�{���������́A���̓��������͈̔͂̋L�ڂ̂Ƃ���̋Z�p�I�͈͋y�т��̋ϓ����ɑ����L����L���Ă����̂ł���A���̐�L���́A�����̌v�悵�Ă������Ƃɂ����āA�L�v�ł������Ƃ����ׂ��ł���B���ۂɂ��A�����́A�{�����{�_��Ɋ�Â��ċ��������Ɋ�Â��āA���{�قɑ��āA�ʏ���{����t�^�������Ƃɂ��A�T�Q�T���~�̌_����̎x�����Ă����i���R�W�A�R�X�j�B��������ƁA�Z�p�I�͈͂ɂ��Ă̌����̔F���̌��́A�����̌v�悵�Ă������Ƃ̖W���ɂȂ����Ƃ͓�������邱�Ƃ͂ł����A�y���u���{�������̋Z�p�I�͈͖��͂���Ƌϓ��͈̔͂Ɋ܂܂�Ă��Ȃ����茴���ɂ����Ė{�����{�_����������ӎv�\�������邱�Ƃ��Ȃ������ł��낤�Ƃ܂ŔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�ȏ�̂Ƃ���ł����āA�����ɁA�{�����{�_��̑Ώۂ���������ɌW�锭���̋Z�p�I�͈͂ɂ��Ă̔F���̌�肪����������Ƃ����āA���̓_���A�{�����{�_��ɂ��Ắu�v�f�̍���v�ɊY������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A���ɁA���炩�̌�F���������Ƃ��Ă��A����́A���̂悤�Ȏ��Ƃ𐋍s����ߒ��Ō_����������ۂɁA���R�ɒ����������ׂ�������ӂ������Ƃɂ����̂ł����āA�d��ȉߎ��Ɋ�Â���F�ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�Q �����Ǒ��ᔽ���͐M�`���ᔽ�ɂ���
�@��������M�����_�ɂ��Ĕ퍐��ɂ����Ė{�����{�_�����爫�ӂł������ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��A�O�L�F��̖{���̎����W���l������A�{�����{�_��̒����������Ǒ��Ɉᔽ����Ƃ͂������A�܂��A�퍐��ɂ����Ė{���s�Ԋғ�������p���邱�Ƃ��M�`���ɔ�����Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ�����A���̓_�Ɋւ��錴���̎咣�����R���Ȃ��B
�R ���_
�@�ȏ�ɂ��A�����̔퍐��ɑ��鐿���́A����������R���Ȃ����炱������p���ׂ��ł���A����ƈقȂ錴�������퍐��s�i�̕������������Č����̐���������������p���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B
�u��H�p�ڑ����ށv����R���������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10096�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N01��28�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�P �������ɂ�����葱�̌o��
�@�����́A�����V�N�T���P�U���A�����̖��̂��u��H�p�ڑ����ށv�Ƃ��锭���ɂ��āA�����o�������A�����P�U�N�S���Q�V���t���Ŗ����̔����̏ڍׂȐ����ɌW��葱����������i�b�Q�j�A�����P�V�N�T���Q�V���t���ŋ��⍸��������Ƃ���A���N�V���S���A����ɑ���s���̐R���i�s���Q�O�O�T�|�P�Q�U�V�P�������j�𐿋�����ƂƂ��ɁA���N�W���R���t���葱����i�b�R�j�ɂ��葱��i�ȉ��u�{����v�Ƃ����B�j�������B
�@�������́A�����Q�O�N�P���Q�X���A�{������p������ƂƂ��ɁA�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R���i�ȉ��u�R���v�Ƃ����B�j�����A���̐R���̓��{�́A�����Q�O�N�Q���P�Q���Ɍ����ɑ��B���ꂽ�B
�Q �o�蓖���̓��������͈̔�
�@�o�蓖���̖����i�ȉ��u�{�薾���v�Ƃ����B�b�P�j�ɂ�������������͈̔͂̐������P�̋L�ڂ́A���̂Ƃ���ł���i�ȉ��A�o�蓖���̐������P�ɋL�ڂ��ꂽ�������u�{�蔭���v�Ƃ����B�j�B
�u���L(1)�`(3)�̐�����K�{�Ƃ���ڒ��ܑg�����ƁA���d�����q���Ȃ��H�p�ڑ����ށB
�@(1) �r�X�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V����
�@(2) �r�X�t�F�m�[���^�G�|�L�V����
�@(3) ���ݐ��d���܁v
�R �{�����̓��������͈̔�
�@�{�����̓��������͈̔͂̐������P�̋L�ڂ́A���̂Ƃ���ł���i�ȉ��A�{�����̐������P�ɋL�ڂ��ꂽ�������u�{�������v�Ƃ����B������ɉ������{�����B�b�R�j�B
�u�y�������P�z
�@���L(1)�`(3)�̐�����K�{�Ƃ���ڒ��ܑg�����ƁA�ܗL�ʂ��ڒ��ܑg�����P�O�O�̐ςɑ��āA�O�D�P�`�P�O�̐ρ��ł������d�����q���Ȃ��A�`�t�B������ł�����H�p�ڑ����ށB
�@(1) �r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V����
�@(2) �r�X�t�F�m�[���^�G�|�L�V����
�@(3) ���ݐ��d���܁v
�i�����j
�Q ���f
(1) �����@�Q�X���Q������߂�v���̏[�����A���Ȃ킿�A���Ǝ҂��A��s�Z�p�Ɋ�Â��ďo��ɌW�锭����e�Ղɑz�����邱�Ƃ��ł������ۂ��́A��s�Z�p����o�����āA�o��ɌW�锭���̐�s�Z�p�ɑ�������_�i��s�Z�p�Ƒ��Ⴗ��\���j�ɓ��B���邱�Ƃ��e�Ղł��������ۂ�����Ƃ��Ĕ��f�����B�Ƃ���ŁA�o��ɌW�锭���̓����_�i��s�Z�p�Ƒ��Ⴗ��\���j�́A���Y�������ړI�Ƃ����ۑ���������邽�߂̂��̂ł��邩��A�e�Ցz�����̗L�����q�ϓI�ɔ��f���邽�߂ɂ́A���Y�����̓����_��I�m�ɔc�����邱�ƁA���Ȃ킿�A���Y�������ړI�Ƃ���ۑ��I�m�ɔc�����邱�Ƃ��K�v�s���ł���B�����āA�e�Ցz�����̔��f�̉ߒ��ɂ����ẮA���㕪�͓I����_���I�v�l�͔r������Ȃ���Ȃ�Ȃ����A���̂��߂ɂ́A���Y�������ړI�Ƃ���u�ۑ�v�̔c���ɓ������āA���̒��ɖ��ӎ��I�Ɂu������i�v�Ȃ����u�������ʁv�̗v�f�����荞�ނ��Ƃ��Ȃ��悤���ӂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
�@����ɁA���Y�������e�Ցz���ł���Ɣ��f���邽�߂ɂ́A��s�Z�p�̓��e�̌����ɓ������Ă��A���Y�����̓����_�ɓ��B�ł��鎎�݂������ł��낤�Ƃ������������藧�݂̂ł͏\���ł͂Ȃ��A���Y�����̓����_�ɓ��B���邽�߂ɂ����͂��ł���Ƃ��������������݂��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ����ׂ��ł���͓̂��R�ł���B
(2) ��L�̊ϓ_�ɗ����āA�R���̔��f�̓��ۂɂ��Č�������B
�@�A�@�O�L�P�A(1)�̖{�薾���̋L�ځA���Ɋe���{��Ɣ�r��P�Ƃ̑Δ䕔���̋L�ڂɏƂ炷�Ȃ�A�{�������ɂ����ăr�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V������K�{�����Ƃ��ėp����Ƃ̍\�����̗p�����̂́A�r�X�t�F�m�[���`�^�t�F�m�L�V������p���邱�Ƃɔ�ׂāA���̐ڑ��M�����i�����ƂT�O�O���Ԍ�̂��́j�y�ѕ�C�������コ����ۑ���������邽�߂̂��̂ł���B
�@����A�O�L�P�A(2)�̈��p��ɂ́A�u�t�F�m�L�V�����́E�E�E�G�|�L�V�����ƍ\�������Ă��邱�Ƃ��瑊�n�����ǂ��A�܂��ڒ������ǍD�ȓ�����L����v�i�b�S�̒i���y�O�O�O�V�z�j�ƋL�ڂ���Ă���A�i�ʁA���n����ڒ����ɖ�肪����Ƃ̋L�ڂ͂Ȃ���A��H�p�ڑ����ޗp�̎����g����������ۂɌ������ׂ��l���v�f�Ƃ��Ă͑ϔM���A�≏���A�����A�S�x���X�̑��̗v�f�����݂���̂ł��邩��A���n���y�ѐڒ����̍X�Ȃ����݂̂ɒ��ڂ��ăr�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V������p���邱�Ƃ̎�����������Ă���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A��ʓI�ɁA�r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V�������{��o�莞�ɂ����Ċ��ɒm��ꂽ�����ł���Ƃ��Ă��i���Q�A�R�j�A���ꂪ��H�p�ڑ����ނ̐ڑ��M�������C�������コ���邱�Ƃ܂Œm���Ă������̂ƔF�߂�ɑ����؋����Ȃ��B
�@����ɁA�r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V�����́A�r�X�t�F�m�[���`�^�t�F�m�L�V�����ɔ�ׂĂ��̑ϔM�����Ⴂ�Ƃ�����肪���邱�ƁA���Ȃ킿�A�JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE VOL.7,PP.2135-2144(1963)�(�b�U�j�ɂ��A�r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V�����i���w�\������A�b�U��2138��TABLE �h��Polymer No.2�ɊY������B�j�̃K���X�]�ړ_�́u�W�O���v�ł���A�r�X�t�F�m�[���`�^�t�F�m�L�V�����i���w�\������A�b�U��2139��TABLE II��Polymer no.3�ɊY������B�j�̃K���X�]�ړ_�́u�P�O�O���v�ł���A�r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V�����̑ϔM�����Ⴂ���̂ƔF�߂���B��L�̃r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V�����̐����ɏƂ炷�ƁA�ǍD�ȑϔM�������߂����H�p�ڑ����ނɗp����t�F�m�L�V�����Ƃ��āA�i�ʂ̖��_���w�E����Ă��Ȃ��r�X�t�F�m�[���`�^�t�F�m�L�V�����i�o�j�g�`�j�i�b�S�̒i���y�O�O�Q�Q�z�j�ɑウ�āA�ϔM�������r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V������p���邱�Ƃ��A���Ǝ҂ɂ͗e�Ղł������Ƃ͂����Ȃ��B
�@�C�@�R���́A���p�����Ƀr�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V������p���邱�Ƃ��e�Ղł��鍪���Ƃ��āA�u���p��ɂ́E�E�E���{��Ƃ��āw�o�j�g�`�i�t�F�m�L�V�����A���q�ʂQ�T�O�O�O�A�q�h���L�V����U���A���j�I���J�[�o�C�h������Џ��i���j�x�E�E�E��p���邱�Ƃ��L�ڂ���Ă���v�_��������i�R�����T�łQ�W�s�`�U�łS�s�j�B�������A�R�������p����u�o�j�g�`�v�i�b�S�̒i���y�O�O�Q�Q�z�j�́A���J���X�|�Q�V�X�P�Q�P������ɂ����āA�u�o�j�g�`�i�r�X�t�F�m�[���`���U�������t�F�m�L�V�����E�E���j�I���J�[�o�C�g������А����i���E�E�E�j�v�Ƃ̋L�ڂ�����i�b�T�̂P�̒i���y�O�O�W�U�z�j�A�܂��A�č�������S�R�S�R�W�S�P�������ɂ����Ă��A�u�����̎����́A���j�I���J�[�o�C�h�Ђ���a���������������t�F�m�L�V�����E�E�o�j�g�`�E�E�Ƃ��ď��ƓI�ɓ���ł��A�����āA�r�X�t�F�m�[���`�ƃG�s�N�����q�h�������瓾���鍂���q�ʔM�Y���|���}�[�ƕ\�������B�v�i�b�T�̂Q��S���S�S�s�`�S�W�s�B�j�Ƃ̋L�ڂ�����B���������āA�R�������p����u�o�j�g�`�v�́A�r�X�t�F�m�[���u�`�^�v�̃t�F�m�L�V�����ł���A�r�X�t�F�m�[���u�e�^�v�̃t�F�m�L�V�����ł͂Ȃ�����A���p��́u�o�j�g�`�v�Ƃ̋L�ڂ́A�r�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V������p���邱�Ƃɑ��鎦���ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ��B
(3) ����
�@�ȏ�̎����𑍍��l������A���p��ɋL�ڂ��ꂽ�����̃t�F�m�L�V�����ɂ��ăr�X�t�F�m�[���e�^�t�F�m�L�V������p���邱�Ƃ����Ǝ҂ɂƂ��ėe�Ցz���ł���Ƃ������Ƃ͂ł����A�{�������������@�Q�X���Q���̋K��ɂ������o��̍ۓƗ����ē������邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���Ƃ����R���̔��f�ɂ͌�肪����A���̌��͐R���̌��_�ɉe�����y�ڂ����̂Ƃ�����B
�R ���_
�@�ȏ�̂Ƃ���A�����咣�̎�����R�Q�i����_�ɂ��Ă̗e�Ցz�������f�̌��j�ɂ͗��R������A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A�����̖{�i�����͗��R�����邩��A�����F�e���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B
�u���㎥�C�Đ���ÍR�ۗp�i�v����R�������������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10299�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N01��21�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�����������o��������Ƃ���A���⍸������̂ŁA�����s���Ƃ��ĐR���������������A�������������s�����̐R�����������Ƃ���A���̎���������߂����Ăł���B
�P �������ɂ�����葱�̌o��
�@�����́A�����V�N�U���R�O���A���̂��u���㎥�C�ۉ������i�v�Ƃ��锭���i�������̐��U�B�Ȃ��A���̌�A�����̖��̂��A�����A�u���㎥�C�ی��q���p�i�v�A�u���㎥�C�Đ���ÍR�ۗp�i�v�ɕύX����Ƃ̕������Ă���B�j�ɂ��A�D�挠�i�D����F�����V�N�Q���Q�R���y�ѓ��N�U���P�R���j���咣���������o���i���蕽�V�|�P�U�T�Q�V�R���j���������i�b�Q�j�A�������́A�����P�W�N�R���W���t���ŋ��⍸��������i�b�X�̂R�j�B
�@�����́A�����P�W�N�S���V���A��L���⍸��ɑ���s���̐R������������ƂƂ��ɁA�����t���œ��������͈̔͋y�є����̖��̂�ύX����葱��i�b�X�̂V�B�ȉ��u�{����v�Ƃ����B�j�������B
�@�������́A��L�R��������s���Q�O�O�U�|�X�R�Q�V�������Ƃ��ĐR�����A�����Q�O�N�U���Q�U���A�{������p�����錈��ƂƂ��ɁA�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R�������A���̓��{�́A���N�V���P�U���Ɍ����ɑ��B���ꂽ�B
�i�����j
��S ���ٔ����̔��f
�P �{����̓K�ۂɂ���
(1) �{����́A�������P���u�P���s�̔��㎥�C��L���Đ���Âɗp������㎥�C�Đ���ÍR�ۗp�i�B�v�ƕύX������̂ł���i�b�X�̂V�j�B
�u�Đ���Áv�Ƃ́A�u�@�\��Q��@�\�s�S�Ɋׂ������̑g�D�E����ɑ��āA�זE��ϋɓI�ɗ��p���āA���̋@�\�̍Đ���}��v���́i�u���{�Đ���Êw��v�����P�R�N�T���ɂ�����ݗ���|�A�u�����P�T�N�x�����o��Z�p�����������E�Đ���Áv���ɂ�����L�ځj�ł����āA�n������ɂ����鎩�R����͂ɂ��זE�̍Đ��Ƃ͈قȂ���̂ł���B
(2) �����ŁA�{����̓K�ۂɂ��Č�������ɁA�{��̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʁi�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j�ɂ́A���̋L�ڂ�����i�b�Q�j�B
�u�y�O�O�O�T�z�{�����͕ۉ����ɉ����A����ɍR�ې��A�B���ѐ������L����ۉ������i����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�v
�u�y�O�O�O�U�z�{�����̕ʂ̖ړI�́A�R�ې�����ɂ͍זE�Đ��\�i���ʁj�𗘗p�����ی��q���p�i�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�v
�u�y�O�O�P�V�z�{�����҂͂���ɖ{�����̂Q�`�Q�O�K�E�X�̔��㎥�C��L����ۉ������i���畆����ьċz�퓙�̊����ǂɂ����Ă悭�����ƂȂ�ێ�ɑ��čR�ې���L���邱�Ƃ��������������B�v
�u�y�O�O�P�W�z���ɁA���`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہA���F�u�h�E���ہA�咰�ۂ���їΔ^�ۂɌ��ʂ�����A�{�����ɂ��ۉ������i�͂����̋ێ�̔����j�~����@�\��L����B�v
�u�y�O�O�Q�O�z�܂��A�����ޗ���@�ۂ̓����ɊܗL�����铙�́A�{�����ɂ��R�ې���L����ۉ������i�f�ނ�p���Đ��������ѕz�A�z�c�J�o�[����ѐQ�Ԓ�������×p�Ƃ��ė��p���邱�Ƃ́A���ɐQ�����芳�҂ɂƂ��Ĕ��ɗL���ł���B�v
�u�y�O�O�Q�P�z����ɁA�R�ې��ɑ��錤���𑱂����Ƃ���Q�`�Q�O�K�E�X�̔��㎥�C�݂͂��ނ��̌����ƂȂ�ێ�i�^�ہj�ɑ���R�ې��A�B���ѐ���L���邱�Ƃ������������B�E�E�E�����ɖ{�����͏�L�̂悤�ȍR�ہA�B���ѐ��𗘗p�����݂��ނ����×p�ۉ������i�܂��͉��L����ی��q���p�i�������̂ł���B�v
�u�y�O�O�Q�S�z�Ȃ��A�{�����ɂ����㎥�C�B�Ö������i�́A�畆����ьċz�퓙�̊����ǂ̌����ƂȂ�O�L�ێ�ɑ��čR�ې������L���邽�߁A�����ɒ��p���镞���i�������ɕۂāA�q���I�ɂ��D�ꂽ���������i����邱�Ƃ��ł���B�v
�u�y�O�O�Q�T�z�܂��A�{�����ɂ����㎥�C�����i������O�i�K�̑f�ނ𐬌`���āA�R�ې��܂��͍B���ѐ��@�\�݂̂�ړI�Ƃ��ĕی��q���p�i�ɗp���Ă��悢�B�Ⴆ�A�����ی쎡��A��сA�������̑�֕��A��������A��ʂ�������юG�ЂƂ��ė��p���邱�Ƃ��ł���B�v
�u�y�O�O�Q�U�z���̏ꍇ�A�R�ې��A�B���ѐ������邽�ߋۂ̔ɐB��h�~���邱�Ƃ��ł��A���S���Ďg�p���邱�Ƃ��ł���B�܂��A�ۊǒ��ɂ��ۂ̔ɐB��h�~���邱�Ƃ��ł���B�v
�u�y�O�O�Q�V�z�{�����������p�ی��q���p�i�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�A���ȂŎ��Âł���y�����͂������A��p��̑傫�ȏ����ɑ��Ă��L�p�ŁA�����ɒ��ڂ܂��͕����悤�ɂ��Ďg�p����Ə����̉��^�h�~�ɗL�p�ł���B�E�E�E�v
�u�y�O�O�Q�X�z����ɋ��������ƂɂQ�`�Q�O�K�E�X�̔��㎥�C���A�Ⴆ�ΑO�L���`�V�����ϐ����F�u�h�E���ۓ��̋ێ�ɂ�鉻�^���ɁA��w�I�ɓK�Ƀp�b�h���̌`�ԂœK�p���邱�Ƃɂ��A���^���̉ɋɂ߂ėL���ł��邱�Ƃ��킩�����B����͂Q�`�Q�O�K�E�X�̔��㎥�C���זE�Đ��\�i���ʁj�����邱�Ƃ��������̂ł���B�E�E�E�v
�u�y�O�O�S�W�z���{��V
�@���ɁA���㎥�C���i�̍R�ې����ʂ����邽�߁A�畆����ьċz�퓙�̊����ǂɂ��Ă悭�����ƂȂ郁�`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہA���F�u�h�E���ہA�咰�ۂ���їΔ^�ۂȂ�тɃ}�O�l�b�g�o���A�V�[�g�i�s�D�z�j�i�W�`�P�O�K�E�X�j�i�ȉ��A���C�V�[�g�Ƃ����j��p���Ă��ꂼ��̋ێ�̔�����ώ@�����B�v
�u�y�O�O�S�X�z�}�b�N�t�@�[�����h����@�ɂ�肻�ꂼ��̋۔Z�x���O�D�T�~�P�O9�^ml �ɒ��������ۉt�����A�V���[���i���a�P�O�p�j�i�P�O�j�ɓ��ꂽ�a�s�a���V�|�n�ɂ��ꂼ��ڎ킵���B�����Ė�S�p�~��R�p�̑傫���̎��C�V�[�g�i�P�R�j�����ꂼ��̔|�n�ɍڂ��A�R�V���łS�W���Ԕ|�{���A����j�~�̈�̗L�����ώ@�����B�v
�u�y�O�O�T�O�z���̌��ʁA�E�E�E�S��̋ۂ̒��ŁA���`�V�����ϐ��u�h�E���ۂ��ł������Ɏ��C�V�[�g�ɂ�蔭���j�~���ꂽ�B�v
�u�y�O�O�T�P�z�{���{��ɂ��A�{�����ɂ����㎥�C�ޗ��͔畆����ьċz�퓙�̊����ǂɂ��Ă悭�����ƂȂ郁�`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہA���F�u�h�E���ہA�咰�ۂ���їΔ^�ۂɑ��čR�ۍ�p��L���邱�Ƃ������ꂽ�B�v
�u�y�O�O�T�Q�z���{��W
�@�{���{��ł͔��㎥�C���i�̍זE�Đ��\�������B�o���R�}�C�V���A�n�x�J�V���A�X���y���]���A�z�X�~�V�����A�����ǃ��`�V�����ϐ����F�u�h�E���ہi�l�q�r�`�j�ɗL���Ƃ�����܂̓��^�ɂ���R���̂��銴���ǂl�q�r�`�i�r���e���Ǐp��j���ǔ^ᇂ������A���^���̑傫���c�P�R�p�A���P�W�p�A�[���Q�p�̂l�q�r�`���ǔ^ᇂ�L���銳�҂ɑ��āA���̉��^�ӏ��ɁA�傫���c�Q�O�p�A���R�O�p�̂O�D�O�O�P�s�i�P�O�K�E�X�j���C�@�ۂ������B������A���^���͏��X�ɉ��W�O���Ō��̏�ԂɊ��S�ɉ����B���ꂾ���̑傫�ȉ��^�����ł��������P���C�h����w�nj`���������������B���̎����ɂ��זE�Đ����ʂ����邱�Ƃ����@�����B�v
(3) ��L(2)�̋L�ڂ��܂߁A���������i�b�Q�j�ɂ́A�u�P���s�̔��㎥�C��L���Đ���Âɗp������㎥�C�Đ���ÍR�ۗp�i�v�ɂ��Ă̖����I�L�ڂ͑��݂��Ȃ��B
�@�܂��A��L(2)�̂Ƃ���A���������ɂ́A���㎥�C�����i�̑f�ށi�ȉ��u���㎥�C���i�v�Ƃ����B�j�ɂ́A�R�ې��y�эR���ѐ������邽�߁A�����̉��^�h�~�ɗL���ł��邱�Ɓi�y�O�O�Q�T�z�`�y�O�O�Q�V�z�j�A���`�V�����ϐ����F�u�h�E���ۓ��̋ێ�ɂ�鉻�^���ɔ��㎥�C���i���p�b�h���̌`�Ԃŗp����ƁA���^���̎���ɗL���ł��邱�Ɓi�y�O�O�Q�X�z�j�̋L�ڂ����邪�A���̂悤�ȑn���̎���ɂ��ẮA���œ��ɂ��n���̕ی쉺�ŁA���肪���B���Ď���Ɏ�����̂ł����āA���̓���̑��B�ɂ��n���̎���́A�u�Đ����Áv�Ƃ͈قȂ���̂ł���B
�@����ɁA��L(2)�̂Ƃ���A���������y�O�O�T�Q�z�ɂ́A�����ǂl�q�r�`�i�r���e���Ǐp��j���ǔ^ᇂ����C�@�ۂ̑����ɂ�莡�䂵�A�u�זE�Đ����ʂ����邱�Ƃ����@�����v�Ƃ̋L�ڂ�����Ă��邪�A�y�O�O�P�V�z�A�y�O�O�P�W�z���тɁy�O�O�S�W�z�`�y�O�O�T�P�z�i���{��V�j�ɁA���㎥�C���i�̃��`�V�����ϐ��u�h�E���ۓ��ɑ���R�ې����ʂɂ��ďq�ׂ��Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA��L�y�O�O�T�Q�z�̋L�ڂ́A���㎥�C���i�̍R�ۍ�p�ɂ��A�n�����ۂ̊�������ی삳��A���ǔ^ᇂ�����̑��B�ɂ�莡�䂵�����Ƃ��L�ڂ���Ă�����̂ƔF�߂��A��������ƁA�y�O�O�T�Q�z�ɋL�ڂ��ꂽ�������琄�@�����u�זE�Đ����ʁv�Ƃ́A���R����ɂ��זE�Đ��̈���o�Ȃ����̂ł����āA�u�Đ���Áv�ւ̗p�r������J�����Ȃ����̂ł���B
�@�����āA���̑��̋L�ڂ��܂߁A���������̋L�ڂɂ����āA���㎥�C���i���u�Đ���Áv�ɗp��������̂ł��邱�Ƃ����Ǝ҂ɂƂ��Ď����ł���Ƃ͂����Ȃ��B
(4) �ȏ�ɂ��A�{����ɌW��u�P���s�̔��㎥�C��L���Đ���Âɗp������㎥�C�Đ���ÍR�ۗp�i�v�́A���������ɋL�ڂ��ꂽ���̂ł͂Ȃ��A�܂��A���������̋L�ڂ�莩���̂��̂ł���Ƃ��F�߂�ꂸ�A�{����́A�O�L�����O�����@�P�V���Q���̋K��ɓK�����Ȃ��̂ŁA���@�P�T�X���P���ɂ����ēǂݑւ��ď��p���铯�@�T�R���P���̋K��ɂ��p�������ׂ����̂ƂȂ�B
�@���������āA�{�����������������ɋL�ڂ���Ă���Ƃ��錴���咣�̐R��������R�͗��R���Ȃ��B
�n�Z�������e�u�e��v�����R���������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10154�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N02��04�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��Q ���Ă̊T�v
�P �{���́A�����̗L�����L�����̐������P�`�U�ɂ��Ĕ퍐�������R�������i�����Q�O�O�T�|�W�O�R�Q�V�������k<�`>�����l�y�і����Q�O�O�U�|�W�O�P�U�V�������k<�a>�����j�������Ɓl����A���������A<�`>�����ɂ��ď�L�������P�A�Q�A�S�`�U�ɌW�锭���ɂ��Ă̓������Ƃ��A<�a>�����ɂ��ď�L�������R�ɌW�锭���ɂ��Ă̓������Ƃ���|�̐R�����������Ƃ���A�������҂ł��錴�������̎���������߂����Ăł���B
�i���|�j
�C��L�A�̋L�ڂɂ��A�b�P�����́A�n�Z���������e���A�������A�������邽�߂Ɏg�p�����e��ɂ��Ă̔����ł���A���Y�Z�p����ɂ����ẮA�n���̕����h�����S�ɉ^��������@�₻�̂��߂̎�炪�]�܂�Ă������Ƃ���A�����^�����q�ɓ��ڂ���������čH��Ԃʼn^�����邱�Ƃ��ۑ�Ƃ��A���̂悤�ȉۑ���������邽�߁A��L�A(�E)�`(�L)�L�ڂ̂悤�ȉ^���p���q�ɓ��ڂ���������������ɓK�����\����L������i�e��j�ł����āA�n���͎���������Ɏ��[����A�g�p��̍H��ł́A���������J���t�H�[�N���t�g�ɂ������X�����ĕێ��F�⒒�^���ɒ�����������́A������X�����̎��i�e��j���̗p�������̂ƔF�߂���B
�E�����̎咣�ɂ���
(�A) �����́A�{�������P�́u�e��v�́A�u���������v�Ƃ��Ă̋C�����y�ёψ����R�ɔ����Ă���_�ɂ����āA���̂悤�ȋC�����y�ёψ���������Ă��Ȃ��u�X�����v�ł���b�P�����́u���v�Ƃ͑��Ⴗ��Ǝ咣���邪�A�{���R���́A�������ƌX�����Ƃ̑���͑���_�`�Ƃ��ĔF�肵�Ă���A���̏�ŁA�b�P�����́u���v�Ɩ{�������P�́u�e��v�Ƃ���v�_�Ƃ݂����̂ł����āA���Ƃ͂����Ȃ��B
(�C) �����́A�b�P�����̌X�����ł�����́u�O�k�S��v�́A�{�������P�̉������ł���e��̃t���[���Ƃ͈قȂ�A�C������ێ�����悤�ȍ\����L���Ă��Ȃ��Ǝ咣���邪�A��L(�A)�̐����Ɠ��l�̗��R�ɂ��A���咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(�E) �����́A�{�������P�́u���H�v�́A�u�������v�ł���u�e��v�́u���ꕔ�t�߁v�������ɉ��тĂ���ȂǁA�u�����v�ɂ��n�Z�������������邱�ƂɓK�����\���̂��̂ł���_�ɂ����āA�u�X�����v�ł���b�P�����́u���v�ɂ�����悤�ȁu�X���v�ɂ��n�Z�������������邱�ƂɓK�����\���̂��̂Ƃ͑��Ⴗ��Ǝ咣���邪�A�{���R���́A�������ƌX�����Ƃ̑���◬�H�̎n�܂�ʒu�̑���͑���_�`�A�a�Ƃ��ĔF�肵�Ă���A���̏�ŁA�b�P�����̂��̂Ɩ{�������P�́u���H�v�Ƃ���v�_�Ƃ݂����̂ł����āA���Ƃ͂����Ȃ��B
(3) ����_�d�̔��f�̌��Ɋւ��錟��
�@�ȏ��(1)�A(2)�܂��Ď�����R�P�i����_�d�̔��f�̌��j�̍̔ۂɂ��Č�������ɁA�b�P�����̗e��́A�O�L(2)�C�ɐ��������Ƃ���A�n���͎���������Ɏ��[����A�g�p��̍H��ł́A���������J���t�H�[�N���t�g�ɂ������X�����ĕێ��F�⒒�^���ɒ�����������́A������X�����̎��ł���ƔF�߂���Ƃ���A���̌X�����̎�炩��A������A�����ꂽ�e��ɗn�Z�����p�̔z�ǂ��݂����������p�̔z�ǂ��ڑ������Ƃ����\���i������������j�Ƃ��邱�Ǝ��̂́A�b�P�O�i���J���W�|�Q�O�W�Q�U������A�b�Q�i���J���j �U�Q�|�Q�W�X�R�U�R������j�A�b�P�P�i���菺�U�R�|�P�R�O�Q�Q�W���i���J���Q�|�T�R�W�S�V���j�̃}�C�N���t�B�����j�A�b�P�Q�i���蕽�P�|�W�X�S�V�S���i���J���R�|�R�P�O�U�R���j�̃}�C�N���t�B�����j�ɂ����āA�������̏ꍇ�A�������x�A�n���i�����̓_�ŌX���������D��Ă��邱�Ƃ��L�ڂ���Ă��邩��A���Ǝ҂������K�p���邱�Ƃ͗e�Ղɑz�N�ł�����̂ƔF�߂���B
�@�������A���̂��Ƃ́A���Ǝ҂��b�P��������o�����Ă���ɂ�����������̗e����̗p���悤�ƍl������́A�������̗e��ł���ΐ����㓖�R�������͂��̍\���̂ق����̂��ׂĂ̌X�̋�̓I�\���͓��R�ɓK�p�ł��邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B�����āA�b�P�����̌X�����̗e��ł���A���̌X�����̗e��ł���Ƃ����������̂���A�n�����o�����ꂷ�邽�߂ɒ������y�ю����K�v�ł��邱�Ƃ�������邪�A�������̗e��̏ꍇ�́A��̗��H��ʂ��ėn���̓����Ɠ��o�Ƃ��s�����������ł���������p�̔z�ǂ��e��ɐڑ�����Ă���悢�̂ł��邩��A�X�����̗e��ŕK�v�Ȏ��y�ю����W�͕K�{�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���������āA�b�P�����̌X�����̗e��ɐڂ������Ǝ҂�������������̎��ɂ��邱�Ƃ��l����ہA�����āA�K�{�Ȃ��̂ł͂Ȃ����y�ю����W����������܂܂̍\���Ƃ���̂ł���A���������\�����̗p����\���ȋ�̓I���R��������K�v������Ƃ����ׂ��ł���B
�@������ɁA��L(1)�ɋL�ڂ����悤�ɁA�{�������P�́A�e������������ėe����ɓ������ꂽ�z�ǂ���ėe����̗n�Z�ޗ����O���ɓ��o����Ƃ����\���ɂ����āA�e��{�̂̏㕔�ɂ́A�J�\�ȃn�b�`���݂����A���̃n�b�`�͗e����ɗn�Z��������������x�ɊJ�����邪�A���̃n�b�`�ɓ��������p�̊ђʍE��݂���Ƃ����\�����Ƃ邱�Ƃɂ��A�n�b�`���J���ĉ��M���e����ɑ}�����ė\�M������ۂɁA���������p�̊ђʍE�ɑ�������̕t�����m�F���邱�Ƃ��ł��A���������ɗp���邽�߂̔z�ǂ�E�̋l�܂�𖢑R�ɖh�~�ł���Ƃ�����p���ʂ�L������̂ł���B��������ƁA�{�������P�Ə�L(2)�ɋL�ڂ����悤�ȍb�P�����Ƃ�Δ䂷��ƁA�b�P�����͎����^�����q�ɓ��ڂ���������čH��Ԃʼn^������Ƃ����Z�p�I�ۑ��L���A���̉ۑ������i�Ƃ��ẮA��L(2)�A(�E)�`(�L)�L�ڂ̂悤�ȉ^���p���q�ɓ��ڂ����������������ɓK�����\�����̗p���Ă���A�Z�p����͓�����������̂́A���̋Z�p�I�ۑ�́A�X�������̈��S�ȍH��ԉ^���i�b�P�����j�Ɖ����������L�̓��������p�z�ǂ̋l�܂�̖h�~�i�{�������P�j�Ƃ����悤�Ɋ�{�I�ɈقȂ��Ă���A���̉ۑ������i���A�������A���̖���i��^���p�ԗ��ւ̌W�~��i���݂���ꂽ�\���i�b�P�����j�Ɓu�O�L�ђʍE�́A�O�L�n�b�`�c�ɐ݂����v���\���i�{�������P�̑���_�d�j�Ƃ����悤�ɈقȂ��Ă���A���̋@�\���p�ɂ��Ă��قȂ���̂ł��邩��A���̂悤�ȍb�P�����ɐڂ������Ǝ҂��A�{�������P�̑���_�d�̍\����e�Ղɑz�N���邱�Ƃ��ł����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�R���̑���_�d�ɂ��ėe�Ցz���ł���Ƃ������f�ɂ͌�肪����A�����̎�����R�P�͗��R������B
������3489678��
�@
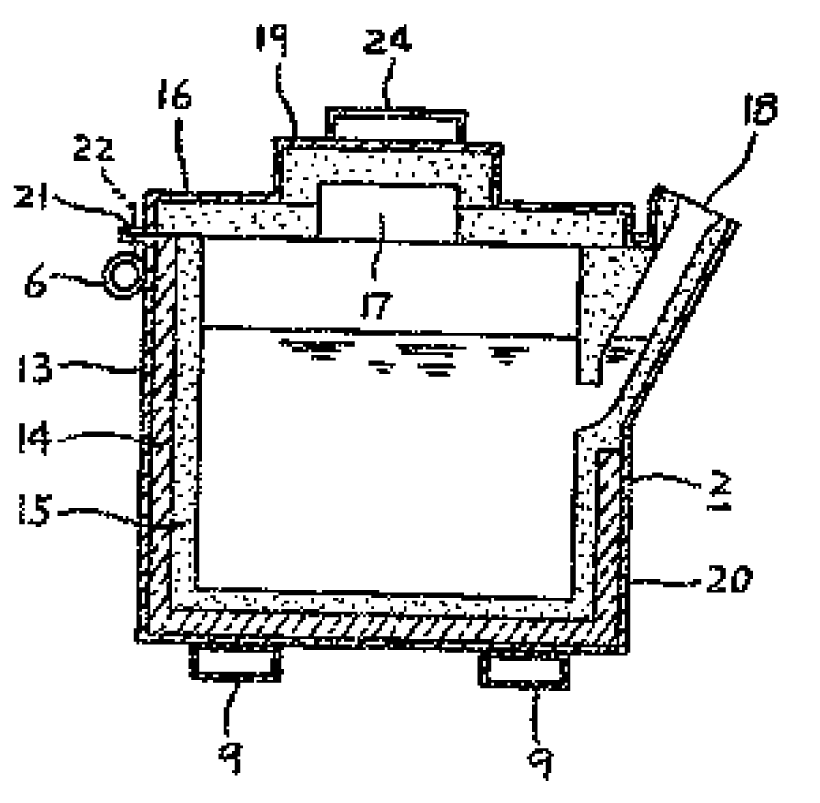 �@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@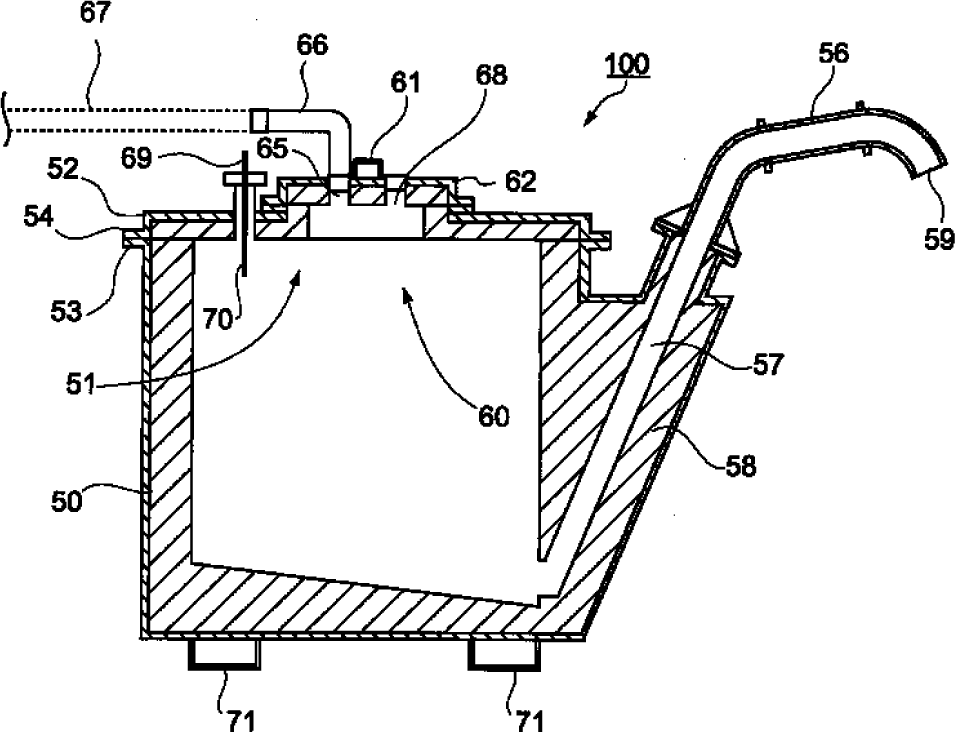
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�P�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{������
�u���x���V�t�^�v����R�������������
�����������������̌��ʂ�����ɂ́A�u���d�ʕ�����u�Ă�ꂽ�̈�Ȃ����ʒu�ɓd�E���ʃg�����W�X�^��z�u����\���v�����߂���͂��ł���ɂ�������炸�A�P�Ɂu�d�E���ʃg�����W�X�^�ɒ�d�ʕ����ڑ�����Ă���v�Ƃ̍\�����̗p����{�萿�����ɋL�ڂ̔����ɂ��ۑ肪�����������̂Ƃ͔F�߂�ꂸ�A�d�E���ʃg�����W�X�^�����d�ʕ��ɋߐڔz�u���ꂽ�{�蔭���ɂ��āA�T�|�[�g�v�����[��������̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ�B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10357�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��17�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��P �����̋��߂��ٔ�
�u���������s���Q�O�O�U�|�T�V�V�Q�������ɂ��ĕ����Q�O�N�W���P�W���ɂ����R�����������B�v�Ƃ̔���
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�x�m�d�@������Ђ�������L�����o��i�ȉ��u�{��v�Ƃ����B�j�ɂ��āA���Ђ���������錠�������p�����������A�{��ɑ��鋑�⍸���s���Ƃ��ĐR���������������A�������͐��藧���Ȃ��Ƃ̐R�������ꂽ���߁A���̎���������߂鎖�Ăł���B
�i�����j
�R �R���̗��R�̗v�|
�@�R���́A�{�蔭���͔����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ��ꂽ���̂łȂ�����A�����P�S�N�@����Q�S���ɂ������O�̓����@�i�ȉ��A�P�Ɂu�����@�v�Ƃ����B�j�R�U���U���P���ɋK�肷��v���i������T�|�[�g�v���j�����Ă��Ȃ��Ɣ��f�����B
�@�R���̗��R���A��L���f�ɌW�镔���́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) �����ŁA�{��̓��������͈̔͂̋L�ڂ��A�����@�R�U���U���P���ɋK�肷��v�������Ă��邩�ۂ��ɂ��Ĉȉ��Ɍ�������B
�@�܂��A�������P�̋L�ڂɊ�Â��ĕ��͂���ƁA�{�蔭���͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�i�\�����j�u�����̊��Ɍ`�������p���[�f�o�C�X����쓮�p�̃��x���V�t�^�v�Ɋւ��锭���ł���B
�i�\�����j�u���ԓd�ʉ�H�Ɠd�C�I�Ɉ�[���ڑ�����郌�x���V�t�g��R�v��L������̂ł���B
�i�\�����j�u�O�L���x���V�t�g��R�̑��[�Ɠd�C�I�Ɉ�[���ڑ�����鍂�ψ��s���`��R�̈�v��L������̂ł���B
�i�\�����j�u�O�L���x���V�t�g��R�̑��[�ƑO�L���ψ��s���`��R�̈�̈�[�Ƃ̊Ԃɐڑ������o�͒[�q�v��L������̂ł���B
�i�\�����j�u�O�L���ψ��s���`��R�̈�̑��[�Ɠd�C�I�Ƀh���C���̈悪�ڑ������m�`���l���̓d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v��L������̂ł���B
�i�\�����j�u�O�L�d�E���ʃg�����W�X�^�̈�̃\�[�X�̈悪��d�ʉ�H�ɐڑ������v���̂ł���B
(2) �����ɂ����āA�{�蔭���́u���x���V�t�g��R�v�ɂ��Ă݂�ƁA���Y�u���x���V�t�g��R�v�́A���̈�[���u���ԓd�ʉ�H�v�Ɠd�C�I�ɐڑ�����A���[���u���ψ��s���`��R�̈�v�ɐڑ�����Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B
�@�܂��A�{�蔭���́u���ψ��s���`��R�̈�v�ɂ��Ă݂�ƁA���Y�u���ψ��s���`��R�̈�v�́A���̈�[���u���x���V�t�g��R�v�Ɠd�C�I�ɐڑ�����A���[���u�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v�́u�h���C���̈�v�Ɠd�C�I�ɐڑ�����Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B
(3) �����ŁA�{�蔭��������u���x���V�t�g��R�v�A�u���ψ��s���`��R�̈�v�A�y�сu�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v�̐ڑ��W�ɂ��Đ�������ƁA�����R�̗v�f�́A��L(2)�ɋL�ڂ��ꂽ�d�C�I�Ȑڑ��W�����肳��Ă���݂̂ł���A���̋�ԓI�Ȕz�u�A���Ȃ킿�A�u�����̊�v�ɂ����āA�u���x���V�t�g��R�v�A�u���ψ��s���`��R�̈�v�A�y�сu�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v���ǂ̂悤�ȏꏊ�Ɍ`������A�݂��ɂǂ̂悤�Ȉʒu�W��L����̂��ɂ��Ă͓��肳��Ă��Ȃ��B
�@���������āA�u���x���V�t�g��R�v�A�u���ψ��s���`��R�̈�v�A�y�сu�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v����L(2)�ɋL�ڂ��ꂽ�d�C�I�Ȑڑ��W�����u���x���V�t�^�v�ł���A�����̊�ɂ����āu���x���V�t�g��R�v�A�u���ψ��s���`��R�̈�v�A�y�сu�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v���ǂ̂悤�ȏꏊ�Ɍ`������A�݂��ɂǂ̂悤�Ȉʒu�W��L����̂��ɊW���Ȃ��A�{�蔭���̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂�邱�Ƃ͖��炩�ł���A���̈��Ƃ��āA�u���x���V�t�g��R�v�A�u���ψ��s���`��R�̈�v�A�y�сu�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v���A��L(2)�ɋL�ڂ��ꂽ�d�C�I�Ȑڑ��W�������̂́A�����̊�ɂ����đ��݂ɕ�������Ă��Ȃ��ߐڂ����ʒu�ɑ��݂���u���x���V�t�^�v���A�{�蔭���̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂����̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���B
�i�����j
(5) �ȏ���A�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ���Ă���̂́A
�@�u�]���̍\���̃��x���V�t�^�ł͐M�������\���ł͂Ȃ��A�����A�����������ɂ����Ăl�n�r�e�d�s�ɍ��o�C�A�X����������Ƃl�n�r�e�d�s�̂������l��ቺ�����A����ɂ�背�x���V�t�^�̑ψ���ቺ�����Ă��܂��Ƃ����v�ۑ���������邽�߂ɁA
�@�u�l�n�r�e�d�s�ւ̍��o�C�A�X�����ጸ�����A�M���������コ�������x���V�t�^����邱�Ɓv��ړI�Ƃ��A
�@�u�d�E���ʃg�����W�X�^�����x���V�t�g��R�y�э��ψ��s���`��R���̍��d�ʕ�������������Ĕz�u����v�Ƃ����\����L���A
�@�u���d�ʕ�����̉e���ɂ��d�E���ʃg�����W�X�^�ւ̍��o�C�A�X�����ጸ���邱�Ƃ��\�ƂȂ�A���x���V�t�^�̒����I�ȐM���������コ���邱�Ƃ��ł���v�Ƃ������ʂ�t����u���x���V�t�^�v�Ɋւ��锭���ł���A���̎��{�̌`�ԂƂ��Ĕ����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ���Ă�����̂��A�S�āu�d�E���ʃg�����W�X�^�����x���V�t�g��R�y�э��ψ��s���`��R���̍��d�ʕ�������������Ĕz�u����v�\����L���Ă���B
�@���������āA��L(3)�ɂ����ėᎦ�����A�{�蔭���̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂��A�u���x���V�t�g��R�v�A�u���ψ��s���`��R�̈�v�A�y�сu�m�`���l���d�E���ʃg�����W�X�^�̈�v���A��L(2)�ɋL�ڂ��ꂽ�d�C�I�Ȑڑ��W�������̂́A�����̊�ɂ����đ��݂ɕ�������Ă��Ȃ��ߐڂ����ʒu�ɑ��݂���u���x���V�t�^�v�́A�ۑ�A�ړI�A�\���A���{�̌`�ԁA���ʂ̂�����̊ϓ_����݂Ă��A�����̏ڍׂȐ����̋L�ڂƑΉ����Ȃ����̂ł��邩��A���̂悤�ȁu���x���V�t�^�v�͔����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ���Ă��炸�A���A�����̏ڍׂȐ����̋L�ڂ��玩���Ȃ��̂ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āA�{�蔭���́A�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ���Ă��Ȃ��������Z�p�I�͈͂Ɋ܂ނ��̂ł��邩��A�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ��ꂽ���̂ł͂Ȃ��B
�i�����j
��T ���ٔ����̔��f
�i�����j
�E��L�C�ɂ��A�{�蔭�����������ׂ��ۑ�́A�d�E���ʃg�����W�X�^�i�l�n�r�e�d�s�j�ւ̍��o�C�A�X����̒ጸ�ł���ƔF�߂���Ƃ���A�����̏ڍׂȐ����̒i���y�O�O�S�V�z�̋L�ځi��L�C(�)�j�ɂ��A���ۑ�́A�u�d�E���ʃg�����W�X�^�����x���V�t�g��R�y�э��ψ��s���`��R���̍��d�ʕ�������������Ĕz�u���邱�ƂƂ������߁v�ɉ����������̂ł���A�܂��A�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ��ꂽ�e���{����݂Ă��A�����͂�������A���d�ʕ��ƕ�������A���͍��d�ʕ�����u�Ă�ꂽ�̈�Ȃ����ʒu�ɓd�E���ʃg�����W�X�^��z�u����\���ł���ƔF�߂���B
�@�����A�ߐڔz�u���ꂽ�{�蔭���ɂ��ẮA���Ǝ҂ɂ����ď�L�ۑ肪�����������̂ƔF�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��M�킹��L�ڂ́A��L�C���܂ߔ����̏ڍׂȐ����ɉ��瑶�݂����i�Ȃ��A�i���y�O�O�P�P�z�i��L�C(�)�j�́A�������P�̋L�ځi�{�蔭���̍\���j���Čf������A���̌��ʂ����_�I�ɏq�ׂ���̂ɂ����Ȃ��B�j�A�܂��A�{�蓖���̓��Ǝ҂̋Z�p�펯�ɏƂ炵�A���Ǝ҂ɂ����āA���̂悤�ɔF�����邱�Ƃ��ł������̂ƔF�߂�ɑ����؋����Ȃ��B
�@���������āA�ߐڔz�u���ꂽ�{�蔭���ɂ��āA�T�|�[�g�v�����[��������̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�G�����́A�{�蔭���ɂ����ẮA�d�E���ʃg�����W�X�^�ɒ�d�ʕ����ڑ�����Ă���̂ł��邩��A�{�蔭������L�ۑ������������̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���|�咣���邪�A��L�̂Ƃ���A�����̏ڍׂȐ����̒i���y�O�O�S�V�z�i��L�C(�)�j�ɂ́A��L�ۑ肪�u�d�E���ʃg�����W�X�^�����x���V�t�g��R�y�э��ψ��s���`��R���̍��d�ʕ�������������Ĕz�u���邱�ƂƂ������߁v�ɉ������ꂽ���̂ł���|���L����Ă����Ƃ���ł���A���̑��A�P�Ɂu�d�E���ʃg�����W�X�^�ɒ�d�ʕ����ڑ�����Ă���v�Ƃ̍\�����̗p���邱�Ƃɂ���L�ۑ肪�����������̂ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ�����A�����̏�L�咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(3) �ȏ�̂Ƃ���ł��邩��A������R�͗��R���Ȃ�
�u���ԊO�����ˑ́v�������N�Q���~�������T�i����
| �����ԍ� | �@����20�N(�l)��10013�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��18�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�P ���Ă̊T�v
�@�T�i�l�́A���̂��u���ԊO�����ˑ́v�Ƃ��锭���ɂ��Ė{���������i������R�O�W�T�P�W�Q���B�����W�N�Q���W���o��k���蕽�W�|�Q�Q�P�W�O���l�A�����P�Q�N�V���V���ݒ�o�^�B�������̐��T�B�ȉ��u�{�������v�j��L���Ă���Ƃ���A�{�������i�����P�U�N�X���P�S���t�������R���ɂ�������̖����B�b�R�B�ȉ��u�{�������v�j�̓��������͈̔͂̐������P�̋L�ڂ́A���̂Ƃ���ł���i�ȉ��u�{�������v�j�B
�@�u�Z���~�b�N�X���ԊO�����ˍޗ��̕����ƁA�S�̂ɑ����R���ː����f�̎_���g���E���̊ܗL�ʂƂ��Ċ��Z���ĂO.�R�ȏ�Q.�O�d�ʁ��ȉ��ɒ����������i�U�C�g�̕����Ƃ����ɂP�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�Ƃ��ĂȂ鍬�������A�Đ����A���������ĂȂ邱�Ƃ�����Ƃ��鉓�ԊO�����ˑ́B�v
�Q ���R�̑��n�قɒ�N���ꂽ�i�ׂ́A�b�����A�������y�ѕ������Ƃ��琬��A�{���������҂ł���T�i�l�i�P�R�b�E���E�����������j���A��T�i�l��i�P�R�b�����퍐�A�P�R�������퍐�y�тP�R�������퍐�j�ɑ��A��T�i�l�炪�����̔����Ă��鉓�ԊO�����ˑ̂͂�������{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ����A�����i���̔��������T�i�l��̍s�ׂ͍T�i�l�̖{����������N�Q����Ǝ咣���āA��T�i�l��ɑ��A�����i�̐����̔����y�ѓ����i�̃J�^���O�̔z�z�̍��~�߂Ɠ����i�A���̐������u�y�ѓ����i�̃J�^���O�̔p�������߂�ƂƂ��ɁA�������N�Q�̕s�@�s�ׂɂ�鑹�Q�����i�i�B�̓��̗�������x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q�����܂ށB�j�𐿋����鎖�Ăł���B
�@�������́A�{�������̖��m���v���̏[���̗L���ɂ��āA���̔��f�������A�{�������ɂ��Ă̔�T�i�l��̊e�����̍\���v���[������A�i�������̖{�������̑��̖������R�ɂ��Ă̔��f�������܂ł��Ȃ��Ƃ��āA�b�E���E�����������̐����͂���������R���Ȃ��Ƃ��Ċ��p�����̂ŁA�T�i�l���{���T�i���N�����B
�@���Ȃ킿�A�������́A�{�������i�b�Q�A���`�Q�O�̂Q�j�̓��������͈̔͂̋L�ڒ��u���ɂP�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�Ƃ��ĂȂ鍬�����v�Ƃ̋L�ڂ́A���ꂪ��̓I�ɂǂ̂悤�ȕ��ϗ��q�a��L���闱�q����Ȃ鍬�������w�������s���ł���Ƃ����ق��Ȃ�����A�����@�R�U���U���Q���̖��m���v�������Ă��炸�A���@�P�Q�R���P���S���̖������R��L����A�Ƃ������̂ł���B
�i�����j
��T ���ٔ����̔��f
�P ���ٔ������A�{�������́A�����@�̒�߂閾�m���̗v�������Ȃ��Ƃ����������R��L���邩��A�������Ɠ������A�T�i�l�̐��������p���ׂ��Ɣ��f����B
�@���̗��R�́A���ɕt������ق��A�������́u�����y�ї��R�v���́u��R ���ٔ����̔��f�v�ɋL�ڂ����Ƃ���ł��邩��A��������p����B
�Q �T�i�l�̎咣(1)�ɂ���
(1) �T�i�l�́A�{�������́u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�ɂ��ẮA�{�������i�b�Q�A���`�Q�O�̂Q�j�̒i���y�O�O�R�T�z�̋L�ڂ܂���A�u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�����E�l�Ƃ��ē��肷����̂ł͂Ȃ��A���E�l�Ƃ��ē��肵�Ă���ɂ������A�{�������i�b�Q�A���`�Q�O�̂Q�j�̋L�ڂ̉��߂Ƃ��āA�u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ����ꍇ�ɁA�u���ϗ��q�a�v�́u�a�v���u�̐ϑ����a�v���Ӗ����邱�Ƃ͖��炩�ł����āA���̏�ŁA�̐ϑ����a�ŎZ�o�������̂ɂ��āA�Z�p���ςŕ��ϗ��q�a���Z�o������̂ł���Ǝ咣����B
�@�������A�{�������̓��������͈̔͂ɂ����āA�u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ̕����ŋL�ڂ���A�����̏ڍׂȐ����i�{�������i�b�Q�A���`�Q�O�̂Q�j�̒i���y�O�O�R�T�z�j�ɂ����āA�u���ԊO�����ˑ̂́A�c���������B����ɂ���āA���ː����ޗ��͋ψ�ɕ��U�A���z�����Ƌ��ɁA���ԊO�����ˍޗ��Ƃ̗��q�Ԃ��k���������B���̂��߁A���ɁA���ԊO�����ˍޗ��ƕ��ː����ޗ��͂ł��邾���ׂ��ȗ��q�̔������Ƃ��邱�Ƃ��D�܂����A��ʂɁA�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�Ƃ��邱�Ƃ��D�܂����B�c�����āA�����̗��x���ׂ������A���R���ː����f�̕��ː�����ɂ��G�l���M���������ʓI�ɉ��ԊO�����ˍޗ��ɋz�������邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ̂悤�ɋ�̓I�ɂ��̋Z�p�I�Ӌ`����������Ă�����̂��A�ł��邾���ׂ������̂ł���悢�Ƃ������n����A���R�ɁA�P�Ȃ鋫�E�l�Ƃ��ē��肵�Ă���ɂ����Ȃ��Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ����ꍇ�́u���q�a�v�ɂ��ẮA�Z�p�I�Ɍ��āA���q���ӂ邢�̒ʉ߂̉ۓ��̌��n������I�ɑ�������A�̐ϓ��̌��n����O�����I�ɑ�����ȂǗl�X�Ȍ��n�����蓾�钆�ŁA�{�������i�b�Q�A���`�Q�O�̂Q�j�����Ă��A�u���q�a�v���ǂ̂悤�ɑ�����̂��Ƃ������n����̋L�ڂ͂Ȃ��A���ϗ��q�a�̒�`�i�Z�o���@�j��̗p�����ׂ�������@�̋L�ڂ������Ȃ��B����܂���ƁA�{�������́u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�́u�a�v���A�{�������̒i���y�O�O�R�T�z���̋L�ڂɏƂ炵�ē��R�ɁA�ӂ邢�a���̊w�I�a�Ⓤ�e�ʐω~�����a���ł͂Ȃ��̐ϑ����a�Ƃ����Ӗ��ł���Ƃ������Ƃ͍���ł��邵�A���ɑ̐ϑ����a�Ƃ݂邱�Ƃ��ł����Ƃ��Ă��A��L�Q�`�S�ɂ��Ƃ点�A�{�������́u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�������@�ɂ������m���v�������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�ȏ�ɂ��A�T�i�l�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
(2) �T�i�l�́A�v�ʖ@�́A�u���x�v����I�ɒ�`���A���茟���K���W���́A���q�̕\�ʐς���Z�o�������q�a�A���q�̒��Z���̂悤�ȑ��̕\�����֎~���Ă���A�����āA���{�H�ƋK�i�i�i�h�r �y �W�X�O�P�k�b�Q�X�l�j�́A�u(1)���a�c���U���@�ɂ�鋅�����a�A�c�ŕ\�������́B�v�A�u�U.�Q���ϗ��q�a���ϗ��q�a�́A�t�����ɂ���đ��肵�A�\�Q�R�̒l�ɓK�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȃ��A�t�����ɂ����@�Ɠ����ȑ���l�������鑼�̑�����@��p���Ă��悢�B�v�ƋK�肵�A���[�U���ɂ����U���@�ɂ�鋅�����a�ŕ��ϗ��q�a�𑪒肵�Ă��悢�Ƃ������̂ł����āA���ϗ��q�a�͈̔͂���L���{�H�ƋK�i�ɂ���Ďq�ׂɐ�������A���葕�u�̑��茋�ʂ����͈͓̔��ɓ���K�v������A��������ƁA�v�ʖ@�y�я�L���{�H�ƋK�i�ɏ]���đ��葕�u�̍Z�����s���A�u���ϗ��q�a�v������ł���A�{�������́A�v�ʖ@�����炵�A���@�Ɛ������̂�����{�H�ƋK�i�̒�`�ɏ]�����\����p������̂ł���A��@�ɂȂ蓾�Ȃ��Ǝ咣����B
�@�������A�{�������̋L�ڂ��v�ʖ@�����炵���{�H�ƋK�i�̒�`�ɏ]���Ă����Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ���A�{�������́u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ��������������@�ɂ������m���v���������Ƃ����R�ɓ�����邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A���{�H�ƋK�i�i�i�h�r �y �W�X�O�P�k�b�Q�X�l�j�ɂ��ẮA�����p���q�̗��a�i���q�a�j�ɂ��āA�u�ӂ邢�����@�ɂ���đ��肵�������p�ӂ邢�̖ڊJ���ŕ\�������́A���~�@�ɂ��X�g�[�N�X�����a�ŕ\�������́A�������@�ɂ��~�����a�ŕ\�������̋y�ь��U���@�ɂ�鋅�����a�A���тɓd�C��R�������@�ɂ�鋅�����l�ŕ\�������́v�̂����ꂩ�ƒ�`����Ă���i�b�Q�X�E�u�Q�D�p��̒�`�i�P�j���a�v�̗��j�A��`�I�ɓ��肳��Ă�����̂ł͂Ȃ��A�܂��A�����q�̕��ϗ��q�a�́A�u���w�������@���͓��ߌ^�d�q�������@�ɂ��B�e�������q�a�̒��a�̕��ϒl�v�ƒ�`����Ă���i�b�Q�X�E�u�Q�D�p��̒�`�i�V�j���ϗ��q�a�v�̗��j�B��������ƁA����������L�i�h�r�i�b�Q�X�j�������Ƃ��āA�u���ϗ��q�a�v�̈Ӌ`���A���[�U���ɂ����U���@�ɂ�鋅�����a�ɂ�鑪��Ɉ�`�I�ɓ��肳���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ����A���̑��A�{���L�^�����Ă��A�v�ʖ@�y�я�L���{�H�ƋK�i�ɏ]���čZ�����s���A������@���قȂ鑪�葕�u�ŕ��ϗ��q�a�𑪒肵���ꍇ�ɂ����Ă�����̒l�����肳���ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B
�@�ȏ�ɂ��A�T�i�l�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
(3) �T�i�l�́A�Z���~�b�N�X�ƊE�i�j���[�Z���~�b�N�X�A�t�@�C���Z���~�b�N�X�������ƊE���܂ދƊE�j�ł́A���ޗ��̗��q���~�����a�A�������l�i�i�h�r �y�W�X�O�P�u�����p���̋y�ю����p���q�v�̗p��̒�`�k�b�Q�X�l�Q�Ɓj�Ƃ��Čď̂��Ă�������A���Y���q�̌`�~�A���Ƃ͑S�������Ȃ��ٌ`�ł���ɂ�������炸,�u���q�a�v�Ƃ��ė��q���~�����a�A�������l�Ƃ���u�a�v�ŕ\�������̂ł���A���̂悤�ȁA���ƊE�ň�ʓI�Ɉ����Ă���u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�̕\���́A���葕�u���邢�͑�����@�܂œ��肷��K�v���͂Ȃ��A�ǂ̂悤�ȑ��葕�u���g�p���Ă����ϗ��q�a���P�O�ʂ��ȉ��ł��邩���m�F�ł���悢�Ƃ����Ӗ��ł���Ɖ�����Α������̂ł���Ǝ咣����B
�@�������A��L(2)�ɐ��������Ƃ���A�i�h�r �y �W�X�O�P�k�b�Q�X�l�������Ƃ��āA�u���ϗ��q�a�v�̈Ӌ`���A���[�U���ɂ����U���@�ɂ�鋅�����a�ɂ�鑪��Ɉ�`�I�ɓ��肳���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ����A�܂��A��L�R�A�S�̐����ɏƂ点�A�Z���~�b�N�X�ƊE�ɂ�����Z�p�̕��y�x�ɏƂ炵�A�u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ̕\�����A���葕�u���邢�͑�����@�܂œ��肷��K�v�̂Ȃ����̂ł������Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B����ɁA�O�L(1)�̐����ɏƂ点�A�{�������́u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ��������́A�ł��邾���ׂ������̂ł���悢�Ƃ������n����̒P�Ȃ鋫�E�l�Ƃ������Ƃ͂ł����A�����܂ŁA��̓I�ȋZ�p�I�Ӌ`��L���锭�����莖���Ƃ����ׂ��ł���B��������ƁA���̂悤�ȁu�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ̕����ɂ��āA�u�P�O�ʂ��v�Ƃ������l���̂ł͂Ȃ��A�u�P�O�ʂ��ȉ��̕��ϗ��q�a�v�Ƃ������������m�ł��邩�ǂ�������������ɓ�����A���̕����̈Ӌ`���A�ǂ̂悤�ȑ��葕�u���g�p���Ă��u���ϗ��q�a�v���P�O�ʂ��ȉ��ł��邩���m�F�ł���悢�Ƃ����Ӗ��ł���Ɖ����Ė��m���̗v�������Ƃ��邱�Ƃ́A���Ǝ҂ɉߓx�̎��s������ۂ�����̂ł����Ĕ������莖���̊J���Ƃ��đ����łȂ��A�܂��A�u���ϗ��q�a�v�ɂ��Ė��m���̗v���̏[���͗v���Ȃ��Ƃ����ɓ��������̂Ƃ����ق��Ȃ��B
�@�ȏ�ɂ��A�T�i�l�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�u�q�[�g�V�[�����u�v����R���������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10305�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��25�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@��@��
�P ���������s���Q�O�O�W�|�P�T�T�P�������ɂ��ĕ����Q�O�N�V���Q
���ɂ����R�����������B
�Q �i�ה�p�́A�퍐�̕��S�Ƃ���B
�@�@�����y�ї��R
��P ����
�@�啶���|
��Q �����ҊԂɑ����̂Ȃ�����
�P �������ɂ�����葱�̌o��
�@�����́A�������ɑ��A�����P�O�N�W���P�O���A�����̖��̂��u�q�[�g�V�[�����u�v�Ƃ��锭���ɂ��āA�����o��i���蕽�P�O�|�Q�Q�T�T�S�V���j���������A�����P�X�N�P�Q���Q�O���ɋ��⍸����A�����Q�O�N�P���P�W���A�s���̐R���i�s���Q�O�O�W�|�P�T�T�P�������j�𐿋������B
�@�������́A�����Q�O�N�V���Q���A�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R�������A�����P�S���A���̓��{�������ɑ��B�����B
�Q ���������͈͓̔�
�@�{��̊菑�ɓY�t���������i�ȉ��A�}�ʂƕ����āu�{�薾���v�Ƃ����B�j�̓��������͈̔́i�������̐��W�j�̐������P�̋L�ڂ́A���̂Ƃ���ł���i�ȉ��A�������P�ɌW�锭�����u�{�蔭���v�Ƃ����B�b�S�B�ʎ��u�{�薾���y�}�V�z�v�Q�Ɓj�B
�u�y�������P�z���������w���܂ސϑw�̂���Ȃ��ނ��`���[�u��Ƃ��A�Y�`���[�u��̕�ނ��A���M�@�\��L����J���݂Ȉ�̉������ނ�p���āA�t�ʉ��ʼn��f��Ƀq�[�g�V�[������V�[�����u�ɂ����āA�������ނ̏��Ȃ��Ƃ�����̍�p�ʂɁA�V�[���ш�̗e����ʑ��O���ɗאڂ��č����������܂���`��������a���݂����Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���q�[�g�V�[�����u�B�v
�i�����j
�E�e�Ցz�����̌���
�@�{�蔭���ƈ��p�����̑���_�́A�u�{�蔭���́A�����������܂���`��������a���A�V�[���ш�̊O���ɗאڂ��Đ݂����Ă���̂ɑ��A���p�����ł̓V�[���ш�̒[���ɐ݂����Ă���v�_�ɂ���i�����Ȃ��j�B�{�蔭���ƈ��p�����Ƃ̑���́A�����������܂���`������u�a�v�̐ݒu�ꏊ�݂̂ł����āA���̍\���ɂ����鑊��_�́A�ꌩ����ƁA�ɂ߂ċ͂��ł���Ƃ̈�ۂ�^����B
�@�������A��L�̂Ƃ���A�u�a�v�̐ݒu�ꏊ�̑���_�ɂ���āA�{�蔭���ɂ����ẮA�V�[���ш悩�痬�o�������������ŗe������ɔg�ł����n�Z�����r�[�h���`������Ȃ��悤�ɂ��������i�����̂ɑ��āA���p�����ɂ����ẮA�V�[���ш悩��̍��������̗���o�����K�����ăV�[���ш�̎����ʂ��m�ۂ��������i�������̂ł���Ƃ����_�ŁA�����ۑ�y�щ�����i�ɂ����āA�傫�ȑ��Ⴊ����Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����ŁA���p�������o���_�Ƃ��āA���m��i�b�Q�A�b�R�j��K�p���邱�Ƃɂ���āA�{�蔭�����e�Ղɑz�����邱�Ƃ��ł������ۂ�����������B
�@���p�����́A�V�[���ш���ɍ����������܂蕔��݂��āA�M�Z���Ɋ�^����|���G�`���������̗ʂ��m�ۂ��邱�Ƃɂ��A�u�ڍ����x���ێ��v����悤�ɂ������̂ł��邩��A�P�ɁA�u�a��݂��������Ɍ`������鍇���������܂蕔���n���̔M�V�[������Ȃ������Ƃ���v���Ƃ��J��������m��i�b�Q�A�R�j���w�E���邱�Ƃɂ���āA���̎��m�̋Z�p��K�p���āA���p�����Ƃ͈قȂ�����ۑ�Ɖ�����i���������{�蔭���̍\���Ɏ��邱�Ƃ��e�Ղł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���p�����́A�ڍ����x�ێ���ړI�Ƃ����Z�p�ł���̂ɑ��A���m�Z�p�́A�ڍ����x�ێ��Ɋ�^���邱�ƂƂ͊֘A���Ȃ��Z�p�ł��邩��A�{�蔭���ƌ݂��ɉۑ�̈قȂ���p�����Ɏ��m�Z�p��K�p���邱�Ƃɂ���āu�{�蔭���̍\���ɒB���邱�Ƃ��e�Ղł������v�Ƃ������ؖ����_���I�ɏؖ��ł����Ɣ��f���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(2) ����
�@�ȏ�̂Ƃ���A���p�����Ɏ��m���K�p���邱�Ƃɂ���āA�{�蔭���̑���_�ɌW��\���ɓ��B���邱�Ƃ��ł����Ƃ���R���̔��f�A���Ȃ킿�u���p�����ɂ����Ė������ɂ͂���قNJ�^���Ȃ������������܂蕔���A�V�[���ш�̊O���ɗאڂ��A�V�[���ш�Ƃ��Ă͋@�\���Ȃ������Ƃ��Ĕz�u���邱�Ƃ����Ǝ҂��e�ՂɂȂ��������̂ƔF�߂�B�v�Ƃ����R���̔��f�ɂ́A���̗]�̓_�f����܂ł��Ȃ��A��肪����Ƃ����ׂ��ł���B���̑��A�퍐���~�X�咣���邪�A����������_�ɉe�����y�ڂ��咣�Ƃ͂����Ȃ��B
�u�L�V���g�[���������v����R���������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10261�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��25�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@�@��@��
�P ���������s���Q�O�O�S�|�X�S�O�V�������ɂ��ĕ����Q�O�N�R���S���ɂ����R�����������B
�Q �i�ה�p�́A�퍐�̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�@�����y�ї��R
��P ����
�@�啶���|
��Q �����ҊԂɑ����̂Ȃ�����
�P �������ɂ�����葱�̌o��
�@�����́A�����̖��̂��u��C����Ԃ����Â��邽�߂̃L�V���g�[���������v�Ƃ��锭���ɂ��āA�����P�P�N�R���Q�S���i�p�����ɂ��D�挠�咣�O�����P�X�X�W�N�R���Q�S���i�t�r�j�A�����J���O���P�X�X�W�N�P�Q���Q�R���i�t�r�j�A�����J���O���j�����ۏo����Ƃ��ē����o��i���ۏo��ԍ��o�b�s�^�t�r�X�X�^�O�U�S�R�U�B���{�����o��ԍ�����Q�O�O�O�|�T�R�V�S�Q�V�j���������A�����P�U�N�Q���R���t���̋��⍸����A���N�T���U���A�s���̐R���i�s���Q�O�O�S�|�X�S�O�V�������j�𐿋����A���N�P�Q���Q�W���Ɏ葱��������B
�@�������́A�����Q�O�N�R���S���A�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R���i�ȉ��u�R���v�Ƃ����B�j�����A�����{�͕����Q�O�N�R���P�W���Ɍ����ɑ��B���ꂽ�B
�Q ���������͈̔�
�@�����P�X�N�P�Q���Q�W���t���葱����i�b�W�j�ɂ�����ꂽ��̖����i�ȉ��u�{�薾���v�Ƃ����B�j�ɂ�������������͈̔͂̐������P�̋L�ڂ́A���̂Ƃ���ł���i�ȉ��A�������P�ɌW�锭�����u�{�蔭���v�Ƃ����B�j�B
�@�u�y�������P�z�@�̟T���A�Ĕ������@�������A���̓o�N�e���A�ɔ����@�̊������͉��ǂ����Ö��͖h�~���邽�߂ɁA�����K�v�Ƃ��Ă���l�ɑ��ĕ@���֓��^���邽�߂̕@������ł����āA
�@�L�V���g�[���𐅗n�t�̏�ԂŊܗL���Ă���A�L�V���g�[�������n�t�P�O�Occ������P����Q�O�O�����̊����ŊܗL����Ă��钲�����B�v
�R �R���̗��R
�@�ʎ��R�����ʂ��̂Ƃ���ł���B�v����ɁA�{�蔭���́A���ی��J��X�W�^�O�R�P�U�T���p���t���b�g�i�ȉ��u���p��P�v�Ƃ����B�j�y�ѓ��\���U�|�T�O�V�S�O�S������i�ȉ��u���p��Q�v�Ƃ����B�j�ɋL�ڂ��ꂽ�����Ɋ�āA���Ǝ҂��e�Ղɔ��������邱�Ƃ��ł������̂ł���A�����@�Q�X���Q���̋K��ɂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���A�Ƃ������̂ł���B
�@��L���f�ɍۂ��A�R�����F�肵�����p��P�L�ڂ̔����i�ȉ��u���p�����v�Ƃ����B�j�̓��e���тɖ{�蔭���ƈ��p�����Ƃ̈�v�_�y�ё���_�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) ���p�����̓��e
�@���p�����́A�u���n�t�P����������S�O�O�����̃L�V���g�[�����ܗL����AS.pneumoniae�ɂ���C�����������Â��邽�߂̌o�����^�p�n�t���܁v�ł���i�R�����T�łP�s�`�R�s�Q�Ɓj�B
(2) ��v�_
�@�Ĕ������@�������A���̓o�N�e���A�ɔ����@�̊��������Ö��͖h�~���邽�߂ɁA�����K�v�Ƃ��Ă���l�ɑ��ē��^���邽�߂̃L�V���g�[���𐅗n�t�̏�ԂŊܗL���Ă��钲�����ł���_�i�R�����T�łP�O�s�`�P�R�s�Q�Ɓj
(3) ����_
�@����_�P
�@�{�蔭�����@���֓��^���邽�߂̕@������ł���̂ɑ��A���p�����͌o�����^�p�n�t���܂ł���_�i�R�����T�łP�T�s�`�P�U�s�Q�Ɓj
�@����_�Q
�@�{�蔭�����L�V���g�[�������n�t�P�O�Occ������P����Q�O�O�����̊����ŊܗL����Ă���̂ɑ��A���p�����͐��n�t�P����������S�O�O�����̃L�V���g�[�����ܗL����_�i�R�����T�łP�W�s�`�Q�O�s�Q�Ɓj
�i���|�j
(2) ���p�����ƈ��p�����Q�Ƃ̑g�����̗e�Ցz�����ɂ���
�@�R���́A���p��P�Ɉ��p��Q��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA���p��P�̃L�V���g�[���̓��^�ɂ���C�����������u����ۂɁA�o�����^�ɑウ�āA�S�g���^���Ⴂ���^�ʂœ��^�����銴�����ʂւ̓��^�A���Ȃ킿�A�@�ւ̓��^���̗p���A�@���֓��^���邽�߂̕@������Ƃ��邱�Ƃ͓��Ǝ҂��e�Ղɑz��������Ɣ��f�����B
�@�������A�R���̏�L�F��y�є��f�ɂ́A�ȉ��̂Ƃ�����ł���A���Y�F��y�є��f�̌��͐R���̌��_�ɉe�����y�ڂ��Ɖ����ׂ��ł���B
�@�����@�Q�X���Q������߂�v���́A�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ɣ��f���鑤�i�����o������₷��ꍇ�A���͋�����ێ�����ꍇ�ɂ����Ă͓��������j���A���̗v�����[�����邱�Ƃɂ��Ă̔��f�ߒ��ɂ��Ę_���邱�Ƃ�v����B�����̗v���ł���A���Ǝ҂���s�Z�p�Ɋ�Â��ďo��ɌW�锭����e�Ղɑz�����邱�Ƃ��ł����Ƃ̓_�́A��s�Z�p����o�����āA�o��ɌW�锭���̐�s�Z�p�ɑ�������_�i��s�Z�p�Ƒ��Ⴗ��\���j�ɓ��B���邱�Ƃ��e�Ղł��������ۂ�����Ƃ��Ĕ��f�����ׂ����̂ł��邩��A��s�Z�p�̓��e��I�m�ɔF�肷�邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�܂��A�o��ɌW�锭���̓����_�i��s�Z�p�Ƒ��Ⴗ��\���j�́A���Y�������ړI�Ƃ����ۑ���������邽�߂̂��̂ł��邱�Ƃ��ʏ�ł��邩��A�e�Ցz�����̗L�����q�ϓI�ɔ��f���邽�߂ɂ́A���Y�����̓����_��I�m�ɔc�����邱�ƁA���Ȃ킿�A���Y�������ړI�Ƃ���ۑ��I�m�ɔc�����邱�Ƃ��K�v�s���ł���B�����āA�e�Ցz�����̗L���̔��f�ɂ����ẮA���㕪�͓I�Ȕ��f�A�_���Ɋ�Â��Ȃ����f�y�ю�ϓI�Ȕ��f���ɗ͔r�����邽�߂ɁA���Y�������ړI�Ƃ���u�ۑ�v�̔c�����͐�s�Z�p�̓��e�̔c���ɓ������āA���̒��ɖ��ӎ��I�ɓ��Y�����́u������i�v�Ȃ����u�������ʁv�̗v�f�����荞�ނ��Ƃ̂Ȃ��悤�ɗ��ӂ��邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B����ɁA���Y�������e�Ցz���ł���Ɣ��f���邽�߂ɂ́A��s�Z�p�̓��e�̌����ɓ������Ă��A���Y�����̓����_�ɓ��B�ł��鎎�݂������ł��낤�Ƃ������������藧�݂̂ł͏\���ł͂Ȃ��A���Y�����̓����_�ɓ��B���邽�߂ɂ����͂��ł���Ƃ����������̑��݂��邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ����ׂ��ł����i�m�������ٔ��������Q�O�N(�s�P)��P�O�O�X�U���R��������������E�����Q�P�N�P���Q�W�������Q�Ɓj�B�����ŁA�ȉ��A�����̓_�܂��āA��������B
�i�����j
�� ���p��P�̊J�����e
�@�ȏ�̋L�ڂɂ��A���p��P�ɂ́A���n�t�P����������S�O�O�����̃L�V���g�[�����ܗL����AS.pneumoniae�ɂ���C�����������Â��邽�߂̌o�����^�p�n�t���܂Ɋւ�����p�����̓��e���J������Ă�����̂́A���^�ʋy�ѕ���p�ɒ��ڂ����i�ʂ̉ۑ�y�щ�����i�́A��؎�����Ă��Ȃ��Ɖ������B
(�C) ���p��Q�̋L��
�@�O�L�F��̂Ƃ���A���p��Q�́A���u�������ʁv���u�C�������v�Ƃ��鎾����ΏۂƂ������Õ��@�������̂ł���A�Y���Õ��@�̍D�܂����ԗl�ɂ����ẮA�R���Ǎ܋y�эR�����܂��������ʂł���u�C�������v�ɒ��ړI�ɃG�A���]�����q�̌`�Ԃœ��^����邱�Ƃ��L�ڊJ������Ă���B
(�E) �{�薾���̋L�ړ�
�� �{�薾���i�b�R�j�̋L��
�@�{�薾���ɂ́A���̋L�ڂ�����
�u�y�O�O�O�T�z�{�����̖ړI�́A�@�����ւ̊����y�т����̊����ɔ����Ǐ��ጸ���邽�߂̒������y�ѕ��@����邱�Ƃł���B
�@�{�����̕ʂ̖ړI�́A�@�����𐴏�ɂ��Ă����ɑ��݂���a�����o�N�e���A�̌̐���ጸ���邽�߂̎�i����邱�Ƃł���B�{�����̂���ɕʂ̖ړI�́A�����A���@�o����ጸ����ƂƂ��ɏ�C���̉��ǂɋN������b���̔��a�x��ቺ�����邽�߂̒������y�ѕ��@����邱�Ƃł���B
�y�O�O�O�U�z�{�����̂���ɕʂ̖ړI�́A�@���������ɑ���t���I���Â̂��߂ɃL�V���g�[���^�L�V���[�X�����ʓI�ɓ��^������@����邱�Ƃł���B����ɕʂ̖ړI�́A���x�Ȓ����Z�p�Ⓤ�^�Z�p��K�v�Ƃ��邱�ƂȂ��A�v���ɁA���ʓI�ɁA�����I�ɁA���R�ɁA���S�������ɏ�L�ړI��B�����邱�Ƃł���B����ɕʂ̖ړI�́A�����Ԃ̕ۑ����A���S���A���ړI���A�������A���萫�y�ѐM������L����ƂƂ��ɁA�����Œ����y�ѓ��^���\�Ȑ������ɂ���ď�L�ړI��B�����邱�Ƃł���B�v
�� �{�蔭���̉ۑ�
�@��L�{�薾���ɂ́A�{�蔭���̉ۑ�Ƃ��āA��C���̈ꕔ�ł���@�����ւ̊����y�т����̊����ɔ����Ǐ��ጸ���邽�߂̒������y�ѕ��@����邱�ƁA�@���������ɑ���t���I���Â̂��߂ɃL�V���g�[���^�L�V���[�X�����ʓI�ɓ��^������@����邱�ƁA���S���A����������B������ړI�����������邱�Ƃ����L����Ă���B
�C���p��P�y�ш��p��Q�̑g�����̗e�Ր��Ɋւ��锻�f
�@�ȉ��̂Ƃ���A���p��P�Ɉ��p��Q��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ���āA����_�P�i�{�蔭�����@���֓��^���邽�߂̕@������ł���̂ɑ��A���p�����͌o�����^�p�n�t���܂ł���Ƃ̑���_�j�ɌW��\���ɓ��B���邱�Ƃ͂Ȃ��Ɣ��f����B���Ȃ킿�A
(�A) ���p��P�ɂ́A�u���n�t�P����������S�O�O�����̃L�V���g�[�����ܗL����AS.pneumoniae�ɂ���C�����������Â��邽�߂̌o�����^�p�n�t���܁v���L�ڂ���A�܂��A�u��C�������ɂ����Ďq���ɐH�i�ł���L�V���g�[���`���[�C���K���ɂ���āA�L�V���g�[�����o���i�S�g�j���^����Տ��������ʁv��������Ă��邪�A�L�V���g�[�����u�o�����^�p�v�n�t���܂Ƃ��ėp���邱�Ƃɂ���p�A�@���A����p��̎����܂ł��i�ʊJ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B
�@���p��Q�ɂ́A�o�h�u�R�A�`���|�T�A���͑��̊������܂ɂ������N�����ꂽ�a�C�������Ă��錟�̂̋C�������ɁA�a�C���̊ɘa�A�̂��߂ɁA���������q�̃G�A���]���̌`�Ԃ̗L���ʂ̃R���`�R�X�e���C�h���͍R���ǖ�ڃf���o���[���邽�߂̎�i���܂�Ő��鎡�Ñ��u����锭�����J������Ă���B
�@���p�����i��C�������ɂ��Ďq���B�ɃL�V���g�[���`���[�C���K���̌`�ԂŌo���i�S�g�j���^������Ƃ̗Տ������Ɋ�Â��đz�������u���n�t�P����������S�O�O�����̃L�V���g�[�����ܗL����A�E�E�E��C�����������Â��邽�߂̌o�����^�p�n�t���܁v�j�ƈ��p�����Q�i�x�����̋C�����������ǂɂ����ăR���`�R�X�e���C�h�����G�A���]���̌`�ԂŋǏ����^�����鏈�u���@�j�Ƃ́A�����ۑ�A�����Ɏ���@���A���^�ʓ��ɋ��ʐ��͂Ȃ��A���Ⴗ�邩��A������g�ݍ��킹�鍇���I���R�������������Ƃ͂ł��Ȃ����A���������A�G�A���]���̌`�Ԃ̂܂܂ł͋z�C���Ȃ���@�֓��^����ƁA�L�������i�L�V���g�[���j���������ʂƂ͈قȂ�C�������ɂ܂œ��B���邱�Ƃ����邽�߁A�������ʂł���@���ւ̋Ǐ����^�̎����́A����ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���ł���A���p��P�ɐڂ������Ǝ҂́A����ɋC�������̊������ɘa���邽�߂̖ړI�ŃG�A���]���̌`�Ԃ̗L���ʂ̃R���`�R�X�e���C�h���͍R���ǖ�𓊗^������p��Q��K�p���邱�Ƃɂ���āA���S���A���ړI���A�������A���萫����L����ƂƂ��ɁA�����Œ����y�ѓ��^���\�Ƃ��邽�߂ɍ̗p���ꂽ�{�蔭���̍\���i����_�P�̍\���j�ɗe�Ղɑz���ł����Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(�C) ���̓_�ɂ��āA������p�r�ɌW����i���ɌW�锭�������݂���ꍇ�ɁA���̓��^�ʂ̌y�����A���S���̌��㓙��}�邱�Ƃ́A���Ǝ҂ł���A���R�ɖڕW�Ƃ��ׂ������ۑ�Ƃ�����ł��낤���A���̂��߂̎�i�Ƃ��Ċi�ʂ̋Z�p�I�v�f�����ƂȂ��A�ۑ���������邱�Ƃ��ł���ꍇ�����蓾�悤�B
�@�������A���̂悤�Ȏ�����邩��Ƃ����āA�R�����A�{�蔭���̑���_�P�̍\���́A���p��Q�̋L�ړ��e����e�Ղł���Ƃ̗��R�������Č��_���Ă���ꍇ�ɁA���̗��R�t���Ɍ�肪����ȏ�A��L�̂悤�Ȏ�����݂��邱�Ƃ��璼���ɐR���̂������f�F���邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�@�������A�R�����̗��R�ɁA���Y�����̍\���Ɏ��邱�Ƃ��e�Ղɑz���������Ƃ̘_�����L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ���|�́A���㕪�͓I�Ȕ��f�A�_���Ɋ�Â��Ȃ����f�ȂǁA���悻��ϓI�Ȕ��f���ɗ͔r�����A�܂��A���Y�������ړI�Ƃ���u�ۑ�v���c���ɓ������āA���̒��ɓ��Y�������̗p�����u������i�v�Ȃ����u�������ʁv�̗v�f�����荞�ނ��Ƃ�������邽�߂ł����āA�R���̂́A�{�蔭���̍\���ɓ��B���邱�Ƃ��e�Ղł���Ƃ̗����𗠕t���邽�߂̉ߒ����q�ϓI�A�_���I�Ɏ����ׂ�������ł���B
(�E) �퍐�́A���ɁA���p��Q�̓E�L�����i�f�j�̋L�ڂ��C�������̎����݂̂̊J���ł���A���p��Q�̔F��Ɋւ����肪�������Ƃ��Ă��A�@�S�g���^�ɔ�ׂċǏ����^������Ə��Ȃ������^�ʂŊ��m�̕���p��������邱�Ƃ��ł���Ƃ������_�́A�Ǐ����^�ɋN��������̂ł��邩��A�u�C�������v�̎����Ɍ��炸�A�u��C���v�̎����ɑ��Ă��Ǐ����^�����邱�Ƃɂ�蓾����ł��낤�Ɠ��Ǝ҂����R�ɗ������邱�Ƃ��ł���A�A��������A���p��Q�ɐڂ������Ǝ҂ɂƂ��āA��C�������̎��ÂɊւ�����p�����ɂ����āA�o�����^�ɑウ�āA�o�����^�ɔ�ׁA�Ⴂ�S���^�ʂŁA�������ʂɂ�荂���Z�x�̖���f���o���[�ł��A����p������ł��邱�Ƃ����҂����@���ւ̋Ǐ����^���̗p���邱�Ƃ͗e�Ղɑz��������A�B�����āA�@�����^�̌`�ԂƂ��āA�G�A���]����@����������m�ł��邩��A��̓I�ȕ@�����^�̑ԗl��@������Ƃ��邱�Ƃɉ��獢��͂Ȃ��̂ŁA�e�Ցz������F�߂��R���̔��f�ɉe�����y�ڂ��Ȃ��|���咣����B�������A��L(�A)�y��(�C)�ŏq�ׂ��Ƃ���A���p�����Ɉ��p�����Q��g�ݍ��킹�邱�Ƃɂ��A�{�蔭���̑���_�P�ɌW��\���ɓ��B���邱�Ƃ��ł����Ƃ���R���̔��f�͐��F�ł��Ȃ��̂ł��邩��A�퍐�̏�L�咣�̓��ۂɂ��ẮA�R���葱�ɂ����āA���߂ďo��l�ł��錴���ɑ��āA�{�蔭���̗e�Ցz�����̗L���Ɋւ���咣�A��������@���t�^������ŁA�R���ɂ����čēx���f����̂������ł���Ƃ�����B
�E����
�@�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��A���p��P�̃L�V���g�[���̓��^�ɂ���C�����������u����ۂɁA�o�����^�ɑウ�āA�@�ւ̓��^���̗p���A�@���֓��^���邽�߂̕@������Ƃ��邱�Ƃ́A���Ǝ҂����p�����y�ш��p�����Q�Ɋ�Â��ėe�Ղɑz��������Ƃ����R���̔��f�͌��ł���B
�u���R�@�ւ̔r�K�X���@�y�я��u�v����R���������
�����m�Z�p�ł���Ƃ������Ƃ������@��50���̋��◝�R�̒ʒm�`���ᔽ�Ƃ��ꂽ����B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10433�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N09��16�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�E�@����ɁA�R���́A���◝�R�ʒm�ɂ����ĂȂ��E������Ȃ��������m�Z�p�i���m��P�y�тQ�j��p���A�P�ɂ��ꂪ���m�Z�p�ł���Ƃ������R�����ŁA���◝�R���\�����Ă��Ȃ��Ƃ��A�����@�Q�X���P�A�Q���ɂ�����������p�����̈�ɂȂ蓾����̂Ɖ����Ă��邩�̂悤�ł���B
�@���Ȃ킿�A�R���́A����_�P�ɂ��āA�u�r�K�X�����[���̂Ƃ��ɁA�m�n���G�}�Ƃ��Ăm�n����G�}�\�ʂz��������͎̂��m�i�Ⴆ�A���m��P�y�ю��m��Q�Q�ƁB�ȉ��u���m�Z�p�P�v�Ƃ����B�j�ł��邱�Ƃ���A����_�P�ɌW��{�蔭���̔������莖���͎��m�ł���B�v�Ɛ������A�܂��A����_�Q�ɂ��Ă��A�u���R�@�ւ����[���^�]���Ă���Ƃ��A�O�L�m�n���G�}�Ŕr�K�X���̂m�n�����z�����A�z����ɁA�r�K�X�𐔕b�ԃX�g�C�L�������̓��b�`�̏�ԂƂ��A�O�L�m�n���G�}�ŋz�������m�n�����Ҍ��܂ƐڐG���������Ăm�Q�ɊҌ����Ĕr�K�X�����邱�Ƃ͎��m�i�d�d�d�j�ł���A����_�Q�ɌW��{�蔭���̂悤�Ɏ��ԋy�ѐ[�������肷�邱�Ƃ́A���m��P�y�ю��m��R�̎��m�Z�p�Q�����Ă���A�K�X�Ȃ�����v�I�����ɉ߂��Ȃ����̂ł���B�v�A�����āA�u�{�蔭���́A���p�����A���m�Z�p�P�y�ю��m�Z�p�Q�Ɋ�Â��ē��Ǝ҂��e�Ղɔ������邱�Ƃ��ł������̂ł���v�Ƃ������������Ă��邪�A���ł���B
�@�퍐�咣�̂悤�Ɏ��m�Z�p�P�y�тQ�������Ȕ����Ƃ��Ď��m�ł���Ƃ��Ă��A���m�Z�p�ł���Ƃ��������ŁA���◝�R�ɓE������Ă��Ȃ��Ƃ��A���@�Q�X���P�A�Q���̈��p�����Ƃ��ėp���邱�Ƃ��ł���Ƃ����Ȃ����Ƃ́A���@�Q�X���P�A�Q���y�тT�O���̉��ߏ㖾�炩�ł���B�m���ɁA���◝�R�ɓE������Ă��Ȃ����m�Z�p�ł����Ă��A��O�I�ɓ��@�Q�X���Q���̗e�Ցz�����̔F�蔻�f�̒��ŋ��e����邱�Ƃ����邪�A����́A���◝�R���\��������p�����̔F���̔��C����A�e�Ր��̔��f�̉ߒ��ŕ⏕�I�ɗp����ꍇ�A�Ȃ����W����Z�p����Ŏ��m���������Z�p�̗����̏�œ��R���͈Öق̑O��ƂȂ�m���Ƃ��ėp����ꍇ�Ɍ�����̂ł����āA���m�Z�p�ł��肳������A���◝�R�ɓE������Ă��Ȃ��Ă����R�Ɉ��p�ł���킯�ł͂Ȃ��B�퍐�̎咣������m�Z�p�́A�����ł���A�����̊W�҂ɒm��n���Ă��邱�Ƃ��z������邪�A�{���̗e�Ցz�����̔F�蔻�f�̎葱�ŏd�v�Ȗ������ʂ������̂ł��邱�Ƃɂ��݂�A�P�Ȃ���p�����̔F���̔��C���A�e�Ցz�����̔��f�̉ߒ��ŕ⏕�I�ɗp����ꍇ�Ȃ������R���͈Öق̑O��ƂȂ�m���Ƃ��ėp����ꍇ�ɂ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A�{���ɂ����āA�e�Ցz�������m�肷�锻�f�v�f�ɂȂ蓾��Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���̓_�Ɋւ���퍐�̎咣�͎����ł���A������̎咣�������ł���B
�G�@�ȏ�ɂ��A�R���ɂ́A��q�̂�����ɂ��Ă��A�����@�P�T�X���Q���ŏ��p���铯�@�T�O���ɔ������@������B
�u���s�ƌ�����v�����V�X�e���v�R�������������
�������ɂ��u������F�߂�B�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R�����ێ���������B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10151�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N05��25�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�Q �{���������������R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��ɊY������Ɣ��f�������i������R�Q�j�ɂ���
�@���ٔ����́A�R�����A�{�����������͎��R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��ɊY������Ƃ������f�Ɍ��͂Ȃ��A������R�Q�͗��R���Ȃ��Ɣ��f����B���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) �������P�ɌW�锭���ɂ���
�A�@�������P�ɌW�锭���́A���s�ƌ�����v�������u�̔����ł���A�o���t�@�C����ɁA�u����v�Ɓu�d���v�Ƃ��A�u�O����v�A�u�������v�A�u�O�����v�A�u�������v�Ƌ��ɁA�ꗷ�s���i�P�ʂœ����t���Ōv�コ���悤�ɂ������Ƃ�����Ƃ���i�P�o�j�B���̍\���́A�d�q�t�@�C���ł���o���t�@�C���i�P�`�j�A��P�̌v��v������i�u����v�y�сu�d���v�̓����t�v���v���j�Ƒ�Q�̌v��v������i�u�����v���́u�x���v�̌v���v���j�����������Ƃ����ꂼ�ꔻ�ʂ��鑀���ʔ����i�i�P�a�j�A�����ʔ����i�ɂ���P�̌v��v�����삠��Ɣ��肳�ꂽ�Ƃ��Ɏ��{������P�̌v�㏈����i�i�P�b�j�A�����ʔ����i�ɂ���Q�̌v��v�����삠��Ɣ��肳�ꂽ�Ƃ��Ɏ��{������Q�̌v�㏈����i�i�P�c�j��L���A��P�̌v�㏈����i�i�P�b�j�́A�O��������i�i�P�d�j�A����v�㏈����i�i�P�e�j�A�O���������i�i�P�f�j�A�d���v�㏈����i�i�P�g�j���܂݁A��Q�̌v�㏈����i�i�P�c�j�́A����d���ςݔ����i�i�P�h�j�A����d���O�v�㏈����i�i�P�i�j�A����d����v�㏈����i�i�P�j�j���܂݁A����ɁA����d���O�v�㏈����i�i�P�i�j�́A�����ʔ����i�i�P�k�j�A�O��O�����̌v�㏈����i�i�P�l�j���܂݁A����d����v�㏈����i�i�P�j�j�́A�����ʔ����i�i�P�m�j�A�����������̌v�㏈����i�i�P�n�j���܂ނ��̂ł���B�����āA��L�e��i�́A�R���s���[�^�v���O�������R���s���[�^�ɓǂݍ��܂�A�R���s���[�^���R���s���[�^�v���O�����ɏ]���č쓮���邱�Ƃɂ������������̂Ɖ�����A���ꂼ��̎�i�ɂ��āA���̎�i�ɂ���čs�����v��̏��̔����v�㏈������̓I�ɓ��肳��A��L�e��i�̑g�ݍ��킹�ɂ���āA�o���t�@�C����ɁA�u����v�Ɓu�d���v�Ƃ��A�u�O����v�A�u�������v�A�u�O�����v�A�u�������v�Ƌ��ɁA�ꗷ�s���i�P�ʂœ����t���Ōv�コ���悤�ɂ��邽�߂̉�v�������u�̓�����@�y�т��̏���������̓I�Ɏ�����Ă���B
�@��������ƁA�������P�ɌW�锭���́A�R���s���[�^�v���O�����ɂ���āA��L��v��̋�̓I�ȏ�����������锭���ł��邩��A���R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��ɓ�����ƔF�߂���B
�u�L�j��������т��̐����@�v�������������ԉ����o�^�o�苑��R���������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10477�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N05��27�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��S ���ٔ����̔��f
�P ������R�P�i�{�������ɌW����������̓��e�̔F��̌��j�ɂ���
�@�����́A�R���ɂ͖{�������ɌW����������̗v�|�F����������@������Ǝ咣����̂ŁA��������B
(1) �{�������ɌW����������̓��e�ɂ���
�A�@�{�������̏o��������̓��������͈̔͂̋L�ڂ́A�O�L��Q�A�Q(1)�̂Ƃ���ł���B
�@�؋��i�b�S�O�`�S�V�j�ɂ��A�{�������ɂ��ẮA�@�o�������A�����ًc�̐\���Ă����ꂽ���Ƃ���A�����́A�����X�N�S���V���t���葱����i�b�S�T�j�ɂ��A���������͈̔͂̋L�ڂ��������ƁA�A���̌�A�����P�O�N�Q���Q���t�������ًc�̌���i�b�S�V�j�L�ڂ̗��R�ɂ��A�����t���̋��⍸��i�b�S�U�j�������Ƃ���A�����́A���N�S���Q�Q���t���œ�����ɑ���s���̐R���𐿋����A���N�T���Q�P���t���葱����i�b�S�Q�j�ɂ��A���������͈̔͂̋L�ڂ��������ƁA�B���̌�A���N�V���R���t���œ�������i�b�S�S�j�������Ƃ��A��������F�߂���B
�@��L�e�����y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�{�������̐ݒ�o�^���̓��������͈̔͂̋L�ڂ́A�O�L��Q�A�Q(2)�̂Ƃ���ł��邱�Ƃ��F�߂���i�Ȃ��A��L�e��k���ɁA�����P�O�N�T���Q�P���t���葱����i�b�S�Q�j�ɂ���l����̗v�����������̂ł��邱�Ƃ���A���̕������Ȃ��������o��ɂ��ē��������ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����k�����T�N�@����Q�U���ɂ������O�̓����@�S�Q���Q�Ɓl�|�̎咣�A���͂Ȃ��A�܂��A�{�������̐ݒ�o�^��A�����R���������͒��������ɂ��A���������͈̔͂̋L�ڂ��������ꂽ���Ƃ���A���̒�����ɂ����閾�����ɂ��������̐ݒ�̓o�^�����ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����k�����@�P�Q�W���Q�Ɓl�|�̎咣�A�����Ȃ��B�j�B
�C�@�����@�U�V���̂R��P���P���́A�u���̓��������̎��{�ɑ�Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��B�v�ƋK�肷��B�����ɂ����u���������v�Ƃ́A�u�����@���Ă��锭���v�i�����@�Q���Q���j���Ӗ�����Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{���o��ɂ��ē����̋K�肷�鋑�◝�R�̗L���f����ɓ�����A�{�������ɌW����������̓��e�́A�o��������̓��������͈̔͂̋L�ڂł͂Ȃ��A�ݒ�o�^���̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��āA�m�肳���ׂ����Ƃ͓��R�ł���B
�E�@�R���́A�O�L��Q�A�R�̂Ƃ���A�{�������������������i�R���ɂ����u�{�����������v�j�̎��{�ɕK�v�ȏ����ł������Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�{���o��͓����@�U�V���̂R��P���P���̋K��ɂ�苑�₷�ׂ��ł���Ɣ��f�����B�R���́A�{���������{�������ɌW����������̎��{�ɕK�v�ȏ����ł��������ۂ��f����ɓ�����A�ݒ�o�^���̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��̂ł͂Ȃ��A�����������̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��āA���������̓��e��F�肵���_�ɂ����āA��肪����Ƃ����ׂ��ł���B
(2) �퍐�̎咣�ɑ�
�A�@�퍐�́A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o��̐R���y�ѐR���́A���̏o�莞�ɏo��l����o���������Ɋ�Â��čs����̂ł��邩��A�{���o��̊菑�ɓY�t���ꂽ�{����������̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��Ă����R���̔F��A���f�ɁA��@�͂Ȃ��Ǝ咣����B
�@�m���ɁA�؋��i�b�P�A�Q�A�P�R�A�P�U�A�P�X�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�����́A�{���o��̊菑�ɖ{�����������Y�t���A�܂��A���o��ɌW��R���A�R����ʂ��A�{����������̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��āA�{�������ɌW����������̎��{�ɖ{���������K�v�ł������|�����������Ƃ��F�߂���B
�@�������A��L�̌o�܂�O��Ƃ��Ă��A�ȉ��̂Ƃ���A�퍐�̏�L�咣�͎����ł���B
(�A) ���Ȃ킿�A�����@�U�V���̂Q��Q���́A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o��ɌW��菑�ɂ́A�o�ώY�Əȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A�����̗��R���L�ڂ���������Y�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��|���K�肷��B�@�����̂悤�ȋK���݂�����|�́A�o��l�ɁA�菑�Ɏ�����Y�t�����邱�Ƃ���āA�v���ȐR����R���葱�̎�����ڎw�����Ƃɂ���͖̂��炩�ł���B
�@�����̏�L�̎�|�ɏƂ炷�Ȃ�A���̂悤�ȋK�肪���邩��Ƃ����āA�R���y�ѐR���ɂ����āA�������ԉ����o�^�o��ɌW������ɌW����������̓��e��F�肷��ɓ������āA�o��l�̒�o�ɌW�鎑���݂̂Ɋ�Â��Ă���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��A�܂��A�o��l�̒�o�ɌW�鎑���Ɋ�Â��āA�R���y�ѐR�������{����������A��@�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ɖ����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
(�C) �܂��A�����@�{�s�K���R�W���̂P�U��P���́A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o��ɌW��菑�ɓY�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă�������@�U�V���̂Q��Q������́u�����̗��R���L�ڂ��������v�Ƃ��āA�u���̉����o�^�̏o��ɌW����������̎��{�ɓ����@��Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł��������Ƃ��ؖ����邽�ߕK�v�Ȏ����v�ƋK�肵�Ă���B
�@������āA�������́A�u�����E���p�V�ĐR����v���쐬�A���\���A���́u��u�h���������̑������Ԃ̉����v�́u�Q�D�T �����̗��R���L�ڂ��������̋L�ڎ����v�̍��ɂ́A�����@�{�s�K���R�W���̂P�U��P������̎����ɊY��������̂̈�Ƃ��āA�u���������ł��邱�Ɓi�o�^���A�������A�������̔[�t���j�v�Ƃ��A����𗠕t���邽�߂̎������Ꭶ����Ă���i���ٔ����Ɍ����Ȏ����j�B
�@�������A���������A��������̂悤�ɓ������ɔ������Ă�����̂܂ŁA�u�ؖ����邽�ߕK�v�Ȏ����v�ɊY������Ɖ����邱�Ƃɂ͋^�₪����݂̂Ȃ炸�A���̂��Ƃɂ���āA�R���A�R����S������������R�����A�������R�������A��������ȂǓ������ɔ������Ă��鎑���Ƃ̏ƍ����ȗ����邱�Ƃ�����������闝�R�͂Ȃ��B
�C�@�퍐�́A�u�����\�v���]�[���v�̓x���c�C�~�_�]�[�����i�ȊO�ɓ���Ȋ��\���L���鉻�����ł���Ƃ���A�o�^�������ɂ����u�x���c�C�~�_�]�[���n�v�͒P�Ƀx���c�C�~�_�]�[�����i��L���邱�Ƃ���肷����̂ɂ������A�����������ɂ����u���v�Ɠ��l�ɁA�u�����\�v���]�[���v�Ƃ̓��ꐫ��_����ɑ����L�ڂƂ͂����Ȃ�����A�{�������ɌW����������̗v�|�F��̌��́A�R���̌��_�ɉe�����Ȃ��Ǝ咣����B
�@�������A�o�^�������ɂ��āA�R���͉��画�f���Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�퍐�̏�L�咣�̓��ۂɂ��ẮA�ĊJ�����ׂ��R���葱�ɂ����āA�����Ɉӌ��q�̋@���^������ŁA�R���ɂ����Ĕ��f���ׂ����̂ł���B�퍐�̏�L�咣�́A�R����K�@�Ƃ��闝�R�Ƃ��ẮA�咣���̎����Ƃ����ׂ��ł���B
(3) ����
�@�ȏ㌟�������Ƃ���ɂ��A�R���͖{�������ɌW����������̓��e�̔F�����������̂ł���A���̌�肪�R���̌��_�ɉe�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����咣�̎�����R�P�͗��R������B
�u���v�������������ԉ����o�^�o�苑��R���������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10458�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N05��29�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��S ���ٔ����̔��f
�@���ٔ����́A�{���o��ɑ��A�{����s���������������Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�{�������̎��{�ɐ��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł������Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����R���̔��f�ɂ́A�ȉ��̂Q�_�i�u�����@�U�V���̂R��P���P���Y�����̌��v�y�сu��s�����ɌW�鉄���o�^�̌��͂̋y�Ԕ͈͂ɂ��Ă̌��v�j�ɂ����Č�肪����A���̌��́A��������R���̌��_�ɉe��������̂ł��邩��A�R�����������ׂ����̂Ɣ��f����B���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@�]���A��s�����𗝗R�Ƃ��ē������̑������Ԃ��������ꂽ��ɁA����ɏ����i��s�����j������A��s���������������Ƃ𗝗R�Ƃ��鉄���o�^�̏o��̉ۂ�����ꂽ���Ăɂ����ẮA���A��s�����𗝗R�Ƃ��đ������Ԃ��������ꂽ�������̌��͂��ǂ͈̔͂܂ŋy�Ԃ��Ƃ����ϓ_�i�����@�U�W���̂Q�j���猟������Ă����B�{���ɂ����Ă��A��O�ł͂Ȃ��A�R���́A���A��L�̘_�_���猟���������āA���_���Ă���B
�@�������A��s�����𗝗R�Ƃ��đ������Ԃ��������ꂽ�������̌��͂��ǂ͈̔͂܂ŋy�Ԃ��Ƃ����_�́A���������̎��{�ɐ��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł��������ۂ��Ƃ̓_�ƁA��ɒ��ړI�ɊW���鎖���ł���Ƃ͂����Ȃ��B�ނ���A�{�����܂ށA�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o������₷�ׂ��Ƃ����R���̔��f�̓��ۂ���������ɓ������ẮA���₷�ׂ��Ƃ̍���i�R���j�̍����@�K�ł�������@�U�V���̂R��P���P���̗v���K�������������邱�Ƃ��K�{�ł���B�����ŁA�܂��A���̊ϓ_���猟������B
�P �����@�U�V���̂R��P���P���Y�����̌��
�@�R���́A�O�L��Q�A�R�̂Ƃ���A�{����s�������{�������̑O�ɂ���Ă�������A�{�������̎��{�ɐ��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł������Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��āA�{���o�������@�U�V���̂R��P���P���̋K��ɂ�苑�₷�ׂ����̂Ɣ��f�����B
�@�������A�R���̏�L���f�ɂ́A�ȉ��̂Ƃ����肪����B
(1) �����@�U�V���̂R��P���P���̎�|��
�A�@�����@�U�V���̂R��P���P���̗v��
�@�����@�U�V���̂R��P���́A�������ɂ����āu�R�����́A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o�肪���̊e���̈�ɊY������Ƃ��́A���̏o��ɂ��ċ�������ׂ��|�̍�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƁA�P���ɂ����āA�u���̓��������̎��{�ɑ�Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��B�v�ƁA���ꂼ��K�肵�Ă���B
�@��L�K��ɂ��A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o��Ɋւ��A�����P������̋��⍸������邽�߂̏����v���i�v�������j�́A�u���̓��������̎��{�ɑ�Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈���i�������{���ɂ����ẮA�@�P�S���P������̈��i�̏��F�j���邱�Ƃ��K�v�ł����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��v�ł���A���̂�����咣�A���ؐӔC�́A�����āA���⍸�������퍐�ɂ����ĕ��S����B
�@���̓_�A�퍐�́A�������̑������ԂɊւ�������@�U�V���Q���ɂ����āA�u�������̑������Ԃ́A���̓��������̎��{�ɂ��Ĉ��S���̊m�ۓ���ړI�Ƃ���@���̋K��ɂ�鋖���̑��̏����ł��ē��Y�����̖ړI�A�葱������݂ē��Y������I�m�ɍs���ɂ͑����̊��Ԃ�v������̂Ƃ��Đ��߂Œ�߂���̂��邱�Ƃ��K�v�ł��邽�߂ɁA���̓��������̎��{�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ԃ������Ƃ��́A�T�N�����x�Ƃ��āA�����o�^�̏o��ɂ�艄�����邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肳��Ă��邱�Ƃ���A�u���Y�����̖ړI�A�葱������݂ē��Y������I�m�ɍs���ɂ͑����̊��Ԃ�v����v���Ƃ��A�t�ɁA�����o�^�����ׂ��|�̍�������邽�߂̗v���ł��邩�̂悤�Ȏ咣������B�������A�퍐�̓��咣�́A�ȉ��̂Ƃ���A�����ł���B���Ȃ킿�A�����@�U�V���Q���̏�L�����́A�ǂ̂悤�ȏ�����������̑������Ԃ̉����̗��R�Ƃ��ׂ����Ɋւ��āA�����@�����߂ɈϔC����ɓ�����A�����̖ړI�E�葱���̊ϓ_������̐����݂����K��ɂ����Ȃ��̂ł����āi�Ȃ��A�����@�{�s�߂R���ɂ����āA�@�̏��F�Ɣ_�����@�̓o�^���K�肳��Ă���B�j�A��L�̎������A�ʓI��̓I�Ȏ��Ăɂ����āA�����o�^�����ׂ��|�̍�������邽�߂̏����v���ɂȂ���̂ł͂Ȃ��B
�@�݂̂Ȃ炸�A�������̑������Ԃ̉����o�^�̐��x�����肳�ꂽ�����i���a�U�Q�N�����@���{�s���ꂽ���a�U�R�N�P���P�������j�́A���������̎��{�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ԃ��Q�N���邱�Ƃ������o�^�̗v���Ƃ��Ă������A���̌�A���v�����p�~���ꂽ�i�����P�P�N�@����S�P���j���ƂɏƂ炵�Ă��A�u���Y������I�m�ɍs���ɂ͑����̊��Ԃ�v���邱�Ɓv���A�����o�^�̗v���Ɋ܂܂��Ƃ����悤�ȉ��߂��̗p�ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B
�C�@���������̑������Ԃ̉����o�^���x�̎�|
�@�������̑������Ԃ̉����o�^�̐��x���݂���ꂽ��|�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B���Ȃ킿�A�u���̓��������̎��{�v�ɂ��āA�����@�U�V���Q������́u���߂Œ�߂鏈���v���邱�Ƃ��K�v�ȏꍇ�ɂ́A�������҂́A���Ƃ��A��������L���Ă��Ă��A�������������{���邱�Ƃ��ł����A�����I�ɓ������Ԃ��N�H����錋�ʂ������i�����Ƃ��A���̂悤�Ȋ��Ԃɂ����Ă��A�������҂��u�ƂƂ��ē��������̎��{�����錠���v���L���Ă��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��A�������҂̋��������ɓ������������{�����O�҂̍s�ׂɂ��āA���Y��O�҂ɑ��āA���~�߂⑹�Q�����𐿋����邱�Ƃ��W��������̂ł͂Ȃ��B���������āA�������҂̔��s���v�̓��e�Ƃ��āA�������̂��ׂĂ̌��͂̂����A�������������{�ł��Ȃ������Ƃ����_�ɂ̂ݒ��ڂ������̂ł���B�j�B�����āA���̂悤�Ȍ��ʂ́A�������҂ɑ��āA�����J���ɗv������p��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ铙�̕s���v�������炵�A�܂��A��ʂ̊J���ҁA�����҂ɑ��Ă��A�����J���̂��߂̃C���Z���e�B�u�����킹�邽�߁A���̂悤�ȕs�s�������������āA�����J���̂��߂̃C���Z���e�B�u�����߂�ړI�ŁA�������������{���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������ԁA�T�N�����x�Ƃ��āA�������̑������Ԃ��������邱�Ƃ��ł���悤�ɂ������̂ł���B
�i�����j
�@���̂悤�ɁA�������̑������Ԃ̉����o�^�̐��x�́A�������������{����ӎv�y�є\�͂������Ă��Ȃ��A�������������{���邱�Ƃ��ł��Ȃ������������҂ɑ��āA�u���߂Œ�߂鏈���v���邱�Ƃɂ���ċ֎~����������邱�ƂƂȂ������������̎��{�s�ׂɂ��āA���Y�u���߂Œ�߂鏈���v���邽�߂ɕK�v�ł��������ԁA�������̑������Ԃ���������Ƃ������@���u���邱�Ƃɂ���āA�������������{���邱�Ƃ��ł��Ȃ������s���v�̉�����}�������x�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����Ƃ���ƁA�u���̓��������̎��{�ɐ��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł������v�Ƃ̎��������݂���Ƃ����邽�߂ɂ́A�@�u���߂Œ�߂鏈���v�������Ƃɂ���ċ֎~���������ꂽ���ƁA�y�чA�u���߂Œ�߂鏈���v�ɂ���ċ֎~���������ꂽ���Y�s�ׂ��u���̓��������̎��{�v�ɊY������s�ׁi�Ⴆ�A���̔����ɂ����ẮA���̕��Y������s�ׁj�Ɋ܂܂�邱�Ƃ��O��ƂȂ�A���̗��҂��������邱�Ƃ��K�v�ł���Ƃ�����B
�@�ȏ�̓_��O��Ƃ��Đ�������B�����@�U�V���̂R��P���P���́A�u���̓��������̎��{�ɁE�E�E���߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��B�v�ƁA�R�����i�R�����j���A�����o�^�o������₷�邽�߂̗v���Ƃ��ċK�肳��Ă��邩��A�R�����i�R�����j���A���Y�o������₷�邽�߂ɂ́A�@�u���߂Œ�߂鏈���v�������Ƃɂ���ẮA�֎~���������ꂽ�Ƃ͂����Ȃ����ƁA���́A�A�u�w���߂Œ�߂鏈���x�������Ƃɂ���ċ֎~���������ꂽ�s�ׁv���u�w���̓��������̎��{�x�ɊY������s�ׁv�Ɋ܂܂�Ȃ����Ƃ�_����K�v������Ƃ������ƂɂȂ�i�Ȃ��A�����@�U�V���̂Q��P���S���y�ѓ����Q���̋K��ɏƂ炵�A�u���߂Œ�߂鏈���v�̑��y�т��̓��e�ɂ��ẮA�o��l���咣�A�����ׂ����̂Ɖ������B�j�B��������A�R���ɂ����āA���̂悤�ȗv���ɊY�����鎖��������|��_���Ȃ�����A��������̉����o�^�̏o������₷�ׂ��Ƃ̔��f�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�i�����j
�@�Ƃ���ŁA�{���ɂ����ẮA�{�������̑O�ł��镽���P�T�N�R���P�S���ɁA��s���i��ΏۂƂ���{����s����������Ă���B
�@�������A�{����s�����̑ΏۂƂȂ�����s���i�́A�{�������̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂�Ȃ����ƁA�{����s���������҂��A�{���������̓������҂ł��錴���ł��Ȃ��A��p���{���Җ��͓o�^���ꂽ�ʏ���{���҂ł��Ȃ����Ƃ́A�����ҊԂɑ������Ȃ��A�{����s�����ɂ���ċ֎~���������ꂽ��s���i�̐����s�ד��͖{�������̎��{�s�ׂɊY��������̂ł͂Ȃ��B�{���ɂ����ẮA�{����s���������݂�����̂́A�{����s�������邱�Ƃɂ���ċ֎~���������ꂽ�s�ׂ��A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ����A�{�������̎��{�s�ׂɊY������Ƃ����W�����݂���킯�ł͂Ȃ��B
�@���������āA�{����s�����̑��݂́A�{�������ɌW��������҂ł��錴���ɂƂ��āA�{�������̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂����i�ɂ��Ė@����̏��F���Ȃ�����A�{�����������{���邱�Ƃ��ł��Ȃ������@�I��Ԃ̉����ɑ��A���炩�̉e�����y�ڂ����̂Ƃ͂����Ȃ��B�{����s�����̑��݂́A�{�������̎��{�ɓ�����A�u���߂Œ�߂鏈���v�i�{���ł͖@����̏��F�j���邱�Ƃ��K�v�ł��������Ƃ�ے肷�闝�R�ƂȂ�Ȃ��B
(3) ����
�@��L���������Ƃ���ɂ��A�R���́A���́u�S�|�P ���i�ɂ�����w���x�Ɓw�p�r�x�̉��߁v�̍��ɂ���������̓��ۂɂ�����炸�A�{����s�����̑��݂𗝗R�Ƃ��āA�{�������̎��{�ɐ��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł������Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�{���o��͓����@�U�V���̂R��P���P���ɂ�苑�₷�ׂ��ł���Ɣ��f�����_�Ɍ�肪����A���̌�肪�R���̌��_�ɉe�����邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�Q ��s�����ɌW�鉄���o�^�̌��͂̋y�Ԕ͈͂ɂ��Ă̌��
�@���ٔ����́A�R�����A��s�����𗝗R�Ƃ���������̑������Ԃ��������ꂽ�ꍇ�̓��Y�������̌��͂��A�����̑ΏۂƂȂ����i�ڂƂ͊W�Ȃ��A�u�L�������i���j�v�A�u���\�E���ʁi�p�r�j�v��Ƃ�����i�ɋy�Ԃ��̂Ɖ����āA�����̂��������o�^�̏o��ɑ��āA���߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł������Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ɣ��f�����_�Ɋւ��A�����@�U�W���̂Q�̉��ߏ�̌�肪����Ɖ�����B���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) �����@�U�W���̂Q�̎�|�ɂ���
�@�����@�U�W���̂Q�́A�u�������̑������Ԃ��������ꂽ�ꍇ�i��Z�\�����̓��܍��̋K��ɂ�艄�����ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�ꍇ���܂ށB�j�̓��Y�������̌��͂́A���̉����o�^�̗��R�ƂȂ���Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈���̑ΏۂƂȂ����i���̏����ɂ����Ă��̕��̎g�p��������̗p�r����߂��Ă���ꍇ�ɂ��ẮA���Y�p�r�Ɏg�p����邻�̕��j�ɂ��Ă̓��Y���������̎��{�ȊO�̍s�ׂɂ́A�y�Ȃ��B�v�ƋK�肵�Ă���B
�@��L�K��́A�������̑������Ԃ��������ꂽ�ꍇ�̓��Y�������̌��͂́A���̓��������̑S�͈͂ɋy�Ԃ̂ł͂Ȃ��A�u���߂Œ�߂鏈���̑ΏۂƂȂ������i���̏����ɂ����Ă��̕��Ɏg�p��������̗p�r����߂��Ă���ꍇ�ɂ����ẮA���Y�p�r�Ɏg�p����邻�̕��j�v�ɂ��Ă̂y�Ԏ|���߂Ă���B����́A���������͈̔͂̋L�ڂɂ���ē��肳�����������̋Z�p�I�͈͂��u���߂Œ�߂鏈���v���邱�Ƃɂ���ċ֎~���������ꂽ�͈͂����L���ꍇ�ɁA�u���߂Œ�߂鏈���v���邱�Ƃ��K�v�Ȃ��߂ɓ������҂����̓������������{���邱�Ƃ��ł��Ȃ������͈́i�u���v���́u���y�їp�r�v�͈̔́j���āA�������ꂽ�������̌��͂��y�ԂƂ��邱�Ƃ́A�������҂Ƒ�O�҂̌������������ƂɂȂ邩��ł���B���Ȃ킿�A�������̑������Ԃ̉����o�^�̐��x�́A�������҂����̓������������{����ӎv�y�є\�͂�L����ɂ�������炸�A�����@�U�V���Q������́u���S���̊m�ۓ���ړI�Ƃ���@���v�̋K��ɂ�肻�̓��������̎��{���W����ꂽ�ꍇ�ɁA���{�@��̑r���ɂ��s���v�����������鐧�x�ł��邩��A���̂悤�ȕs���v�̉������āA�������҂�L���Ɉ������Ƃ́A���x�̎�|�ɔ����邱�ƂɂȂ�B
(2) �u���߂Œ�߂鏈���v���@����̏��F�ł���ꍇ�ɂ�����u���߂Œ�߂鏈���v�̑ΏۂƂȂ����u���v�ɂ���
�@�ȏ�̂Ƃ���A�����@�U�W���̂Q�́A���������̎��{�ɖ@����̏��F���K�v�ł��������Ƃ𗝗R�Ƃ��đ������Ԃ��������ꂽ�ꍇ�A���Y�������̌��͂́A�@����̏��F�̑ΏۂƂȂ������i���y�їp�r�j�ɂ��Ă̓��Y���������̎��{�ȊO�̍s�ׂɂ͋y�Ȃ��Ƃ���K��ł���B
�@�����ŁA�u���߂Œ�߂鏈���v���@����̏��F�ł���ꍇ�A�@�̏��F�̑ΏۂɂȂ������i���y�їp�r�j�ɌW����������̎��{�s�ׂ͈̔͂ɂ��āA��������B
�@�@�P�S���P�����A�u���i�E�E�E�̐����̔������悤�Ƃ���҂́A�i�ڂ��Ƃɂ��̐����̔��ɂ��Ă̌����J����b�̏��F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�ƋK�肵�Ă���A�����ɌW�鏳�F�ɕK�v�ȐR���̑ΏۂƂȂ鎖���́A�u���́A�����A���ʁA�\���A�p�@�A�p�ʁA�g�p���@�A���\�A���ʁA���\�A����p���̑��̕i���A�L�����y�ш��S���Ɋւ��鎖���v�i�@�P�S���Q���R���Q�ƁB�Ȃ��A�����P�U�N�@����P�R�T���ɂ������O�̖@�P�S���Q���������ł́A�R���̑ΏۂƂȂ鎖���́A�u���́A�����A���ʁA�\���A�p�@�A�p�ʁA�g�p���@�A���\�A���ʁA���\�A����p���v�Ƃ���Ă���B�j�Ƃ���Ă��邱�ƁA�@�P�S���X�����A�u��ꍀ�̏��F�����҂́A���Y�i�ڂɂ��ď��F���ꂽ�����̈ꕔ��ύX���悤�Ƃ���Ƃ��i���Y�ύX�������J���ȗ߂Œ�߂�y���ȕύX�ł���Ƃ��������B�j�́A���̕ύX�ɂ��Č����J����b�̏��F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ�ɂ����ẮA�����O���܂ł̋K������p����B�v�ƋK�肵�Ă��邱�Ɓi�Ȃ��A�����P�U�N�@����P�R�T���ɂ������O�̖@�P�S���V���̋K��������B�j�ɏƂ炷�Ȃ�A�@��́u�i�ځv�Ƃ́A�`���I�ɂ́A��L�̊e�v�f�ɂ���ē��肳�ꂽ���ꂼ��̕����w���A���ꂼ���P�ʂƂ��āA���F���^��������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@���ɁA�����@�U�W���̂Q�ɂ���āA�������Ԃ��������ꂽ�ꍇ�̓������̌��͈͂̔͂���肷��v�f�ɂ��āA�����I�Ȋϓ_����A�ڍׂɌ�������B
�@�܂��A�i�ڂ��\������v�f�̂����A�u���́v�͈��i�Ƃ��Ă̋q�ϓI�ȓ��ꐫ�����E������̂ł͂Ȃ��B�܂��A�u����p���̑��̕i���v�A�u�L�����v�y�сu���S���v�́A���i�Ƃ��Ă̋q�ϓI�ȓ��ꐫ������A�����̗v�f���܂�����ƂȂ鐫���̂��̂ł��邩��A����̂��߂̓Ɨ��̗v�f�Ƃ���K�v���͂Ȃ��B���ɁA�@����̏��F�ɍۂ��A���i�Ƃ��Ă̓��ꐫ�̐R���ɂ������̂́A�u�����A���ʁA�\���A�p�@�A�p�ʁA�g�p���@�A���\�A���ʁA���\���v�i�@�P�S���T���A�y�ѕ����P�U�N�@����P�R�T���ɂ������O�̖@�P�S���S���Q�Ɓj�Ƃ���Ă���B����ɁA�u�p�@�v�A�u�p�ʁv�A�u�g�p���@�v�A�u���\�v�A�u���ʁv�A�u���\�v�́A�u�p�r�����v�ɂ�����u�p�r�v�ɊY�����邱�Ƃ����蓾��Ƃ��Ă��i���̓_�A�u�p�r�v�ɊY������Ƃ������߂ɂ́A�����@��A�u�p�r�����v�Ƃ��āA�ی삳���ׂ����e������Ă��邱�ƁA���Ȃ킿�A�q�ϓI�ȁu���v���ꎩ�̂̍\���͓���ł����Ă��A�u�p�r�v���قȂ邱�Ƃɂ��A�����@��A�u���v�̔����Ƃ��āu����v�Ƃ͔F�߂��Ȃ��ƕ]������邾���̓��e������Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���B�j�A�q�ϓI�ȁu���v���ꎩ�̂̍\������肷����̂ł͂Ȃ��B
�@���������āA�u���߂Œ�߂鏈���v���@����̏��F�ł���ꍇ�A�u���߂Œ�߂鏈���v�̑ΏۂƂȂ����u���v�Ƃ́A���Y���F�ɂ��^����ꂽ���i�́u�����v�A�u���ʁv�y�сu�\���v�ɂ���ē��肳�ꂽ�u���v���Ӗ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B�Ȃ��A�@����̏��F�ɕK�v�ȐR���̑ΏۂƂȂ�u�����v�Ƃ́A��������鐬���i�L�������j�Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�������������i�ɌW����̂ł���ꍇ�ɂ́A���̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂����{�ԗl�̂����A�@����̏��F���^����ꂽ���i�́u�����v�A�u���ʁv�y�сu�\���v�ɂ���ē��肳�ꂽ�u���v�ɂ��Ă̓��Y���������̎��{�A�y�ѓ��Y���i�́u�p�r�v�ɂ���ē��肳�ꂽ�u���v�ɂ��Ă̓��Y���������̎��{�ɂ��Ă̂݁A�������ꂽ�������̌��͂��y�Ԃ��̂Ɖ�����̂������ł���i���Ƃ��A���̋ϓ���������I�ɓ���ƕ]������镨���܂܂�邱�Ƃ́A�Z�p�I�͈͂̒ʏ�̗����ɏƂ炵�āA���R�ł���Ƃ�����B�j�B
�i�����j
�G�@���P�������̉��ł̖��_�ɂ���
�@�����@�́A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o��ɂ��āA�Q�ȏ�̐������ɌW��������̏ꍇ�ɂ��Ċi�ʂ̋K���݂��Ă��Ȃ��B�����āA�Q�ȏ�̐������ɌW������ɂ��āA���������Ƃɓ��������R���𐿋����邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���i�P�Q�R���P���������j�̂ɑ��āA�����o�^�����R���ɂ��ẮA���������Ƃɐ������邱�Ƃ��ł���|�̋K���u���Ă��Ȃ����ƂɏƂ点�A�Q�ȏ�̐������ɌW��������ɂ��đ������Ԃ̉����o�^�o�肪���ꂽ�ꍇ�ɁA�ꕔ�̐������ɂ��ĉ����o�^�����A���̐������ɂ��ċ��⍸�������Ƃ����悤�ȁA���������Ƃɉ��I�Ȏ戵���͗\�肳��Ă��Ȃ����̂Ɖ������B���a�U�Q�N�����@�̖@�č쐬�ɓ�����A���t�@���ǂ̒S��������A�������̑������Ԃ̉����o�^�ɂ��āA���������ƂɔF�߂�K�v�͂Ȃ����Ƃ����w�E�����ꂽ�ɂ�������炸�A�����@�ɁA���̂悤�ȋK�肪�u����Ȃ������Ƃ����o�܂��A��L�̉��߂𗠕t������̂Ƃ�����B
�@��������ƁA�Ⴆ�A�@����̏��F�������i���A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o�肪���ꂽ�����ɌW��Q�ȏ�̐������̂����A���鐿�����ɌW�锭���̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂�Ȃ��Ƃ��́A���Y�������ɂ��ẮA�����@�U�V���̂R��P���P���́u���̓��������̎��{�ɑ�Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��B�v�ɊY�����邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ȏꍇ�A���̗]�̐������ɂ��ċ���̗��R�����Ȃ��Ƃ��ł����Ă��A�o���S�̂Ƃ��ċ��₷�ׂ��ł���Ƃ������������藧�����Ȃ��ł͂Ȃ����A���̂悤�Ȍ��_�́A�����̑��ʓI�ȕی���\�Ƃ���Ƃ������P�������̗��@��|�ɏƂ炵�A�Ó��������B��������A�������̑������Ԃ̉����o�^�̏o�肪���ꂽ�Q�ȏ�̐������ɌW������Ɋւ��ẮA�����ꂩ�̐������ɂ��āA�u���̓��������̎��{�ɑ�Z�\�����̐��߂Œ�߂鏈�����邱�Ƃ��K�v�ł����v�ꍇ�ɂ́A�����@�U�V���̂R��P���P���ɂ���ċ��₳��邱�Ƃ͂Ȃ��i���P�A�٘_�̑S��|�j�B
�@�Ƃ���ŁA���̂悤�Ȏ�����O��Ƃ�����ōl�@����ƁA���ɁA�����@�U�W���̂Q�́u���v���u�L�������v�Ɖ��߂���Ƃ����Ȃ�A�@����̏��F�������i���Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂Ȃ��������ɌW�锭���ɂ��Ă܂ŁA�������Ԃ̉����o�^�̌��ʂ��y�ڂ����ƂɂȂ�A���̂悤�Ȍ��ʂ́A�������҂ɕs���ȗ��v��^���A�{���̑������Ԃ̖�����ɓ������������{���悤�Ƃ���҂ɒ������s���v���ۂ����ƂɂȂ�A�������Ԃ̉����o�^�̐��x�̎�|�ɔ�����A�s�����Ȍ��ʂ������B
�@���̓_�A�u���߂Œ�߂鏈���v�̑ΏۂƂȂ����u���v�ɌW�鑶�����Ԃ̉����o�^�̌��ʂ��y�Ԕ͈͂��A���Y���F���^����ꂽ���i�́u�����v�A�u���ʁv�y�сu�\���v�ɂ���ĉ悳�ꂽ�u���v�ɂ��Ă̓������������{����s�ׂƉ�����Ȃ�A�u���v���u�L�������v�Ɖ����邱�Ƃɂ���Đ�����A�������̑������Ԃ̉����o�^�̐��x�̎�|�ɔ�����s���Ȍ��ʂ�����邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ����悤�B
�@�ȏ�̊ϓ_������A�����@�U�W���̂Q�ɂ����u���߂Œ�߂鏈���̑Ώہv�ƂȂ����u���v���u�L�������v�Ƃ���R���̔��f�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
���Q�l���������@PAT-H20-Gke-10459.pdf
�u���������^�}�C�N���J�v�Z���v�������������ԉ����o�^�o�苑��R���������
���Q�l���������@PAT-H20-Gke-10460.pdf
�u���o����g�����v�������������ԉ����o�^�o�苑��R���������
�u���f�M�E���C���Z��ɂ�����[��d�͗��p�~�M�������g�[�V�X�e���v�����R���������
| �����ԍ� | �@����21�N(�s�P)��10175�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����22�N01��28�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��T ���ٔ����̔��f
�P �͂��߂�
�@���ٔ����́A�u���f�M�E���C���Z��v�Ƃ̍\�����u�M�����W�����P�D�O�`�Q�D�T���������^��2 �E���E���̍��f�M�E���C���Z��v�Ƃ̍\���Ƃ����{����́A�����@�P�V���̂Q��R���̋K��ɔ�������̂ł͂Ȃ��Ɣ��f����B���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@�����@�P�V���̂Q��R���́A��ɂ��āA�菑�ɍŏ��ɓY�t���������A���������͈͖̔��͐}�ʁi�ȉ��u�o�蓖���������v�Ƃ����ꍇ������B�j�ɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��|���߂�B���K��́A�o�蓖�����甭���̊J�����\���Ȃ炵�߂�悤�ɂ����A�v���Ȍ����t�^��S�ۂ��A�����̊J�����s�\���ɂ�������Ă��Ȃ��o��Əo�蓖�����甭���̊J�����\���ɂ���Ă���o��Ƃ̊Ԃ̎戵���̌��������m�ۂ���ƂƂ��ɁA�o�莞�ɊJ�����ꂽ�����͈̔͂�O��Ƃ��čs��������O�҂��s���̕s���v���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ���Ȃǂ̎�|����݂���ꂽ���̂ł���B
�@�����āA�����Ƃ́A���R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�ł���A�ۑ���������邽�߂̋Z�p�I�����̑g�����ɂ���Đ��藧���̂ł��邱�Ƃ��炷��A�����R������̏o�蓖���������Ɂu�L�ڂ��������v�Ƃ́A�o�蓖���������ɂ���ĊJ�����ꂽ�����Ɋւ���Z�p�I�����ł��邱�Ƃ��O��ɂȂ�B���������āA���Y����A�����A���������͈͖̔��͐}�ʂ̂��ׂĂ̋L�ڂ𑍍����邱�Ƃɂ�蓱�����Z�p�I�����Ƃ̊W�ɂ����āA�V���ȋZ�p�I�������������̂Ɖ�����Ȃ��ꍇ�ł���A���Y��́A�����A���������͈̔͂̋L�ږ��͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����Ă��ꂽ���̂Ƃ����ׂ��ł����āA�����R���Ɉᔽ���Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B
�@�Ƃ���ŁA�����@�R�U���T���́A���������͈̔͂ɂ́A�u�E�E�E�����o��l���������悤�Ƃ��锭������肷�邽�߂ɕK�v�ƔF�߂鎖���̂��ׂĂ��L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肷��B���K��́A���������͈̔͂ɂ́A�u�E�E�E�������悤�Ƃ��锭���̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������݂̂��L�ځv���ׂ��Ƃ���Ă��������Q���̋K��������������̂ł���i�����U�N�@����P�P�U���j�B�]���A���������͈̔͂ɂ́A�����̍\���ɕs���Ȏ����ȊO�̋L�ڂ͂��悻������Ȃ������̂ɑ��āA�������ɂ���āA��������肷��̂ɕK�v�Ȏ�����⑫������A���������肷�鎖�����L�ڂ��邱�Ƃ����e����邱�ƂƂ��ꂽ�B�����ŁA����ɉ����āA���������͈̔͂ɌW���ɂ����Ă��A�����̍\���ɕs���ȋZ�p�I������t�������݂̂Ȃ炸�A�����⑫������A���������肷�镶����t�����邾���̕���z�肳��邱�ƂɂȂ�B
�@���������āA����A�����@�P�V���̂Q��R������̏o�蓖���������ɋL�ڂ����u�����͈͓̔��v�ł��邩�ۂ��f����ɍۂ��Ă��A��ɂ����������͈̔͂ɕt�����ꂽ�����Əo�蓖���������̋L�ڂƂ��`���I�ɑΔ䂷��̂ł͂Ȃ��A��ɂ��t�����ꂽ�������A�����̉ۑ�����Ɋ�^����Z�p�I�ȈӋ`��L���鎖���ɊY�����邩�ۂ����ᖡ���āA�V���ȋZ�p�I�������������̂Ɖ�����Ȃ��ꍇ�ł��邩�f���ׂ����ƂɂȂ�B
�m�I���Y�����T�C�g�@�s�n�o�y�[�W