�R�������������(�Ζ��̔����Y����)
�R�������������(�o�������Ȏ��Ãl�b�g���[�N�̔����Y����)
�R�������������(�u�r�b�g�̏W�܂�̒Z�k�\����������@�v�̔����Y����)
�R��������������i�����̒����ɂ����������͈̔͂̌��k�j�c�Ŕ�
�R�������������(�����ƈꕔ�����R���̎�舵��)
�����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̒����̌����c�Ŕ�
�������N�Q���~�������s���݊m�F�����T�i����
���������R�������������(�ٗ��m�@�ᔽ�u�~���p���^���N���b�v�v����)
���������Ɋ�Â��N�Q���~�������T�i����(�u�n�ڗp�Z���~�b�N�G���h�^�u�v����)
�������N�Q���~�������T�i����(�u�֎q���G�A�[�}�b�T�[�W�@�v����)
�������N�Q���~����������(�u�|�b�g�J�b�^�[�v����)
�u�Z�t�W�j���̂`�^�����v����
�������Ɋ�Â������̔��֎~����������(�u�i�C�t�̉��H���u�v����)�c�Ŕ�
�u�v���C�I�O���[���v�Ή��y��������
�u�}���`�g�[���ܖ������v����
�u���f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��v�R�������������
�u�P�N���[�����R�b�d�`�R�̂S�v�������N�Q���~��������
�u�A�C�X�N���[���[�U䕁v�������N�Q���~����������(�@�\�I�N���[���̉���)
�R�������������(�u�����N���[���v�ɂ���)
�R�������������(�u�l�H����v����)
�R�������������(�u�v���X�t�F���g�v����)
���������i�C�~�_�]�[�����̓s���]�[���U���́j
���������҂Ƃ��Ă̔F��ے莖��
�p�����ɂ��D�挠�咣�̎葱
�u�J�v�Z���x���_�[�}�V���v����
�p�����������m�F��������(�������̔[�t�����k��)
�q��@�Փ˖h�~�p�u���[�_�v�R�������������
���p�V�ċZ�p�]����������T�i����
�R�������������(�Ζ��̔����Y����)
�������̎��{�̉ߒ��ɐl�Ԃ̐��_�������ƕ]��������\�����܂ނ��̂ł����Ă��A�{�蔭�����S�̂Ƃ��āA�P�ɐl�Ԃ̐��_����������Ȃ�v�z�̑n��ɂ������A�����@�Q���P������́u�����v�ɊY�����Ȃ��Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��āA�������ɂ�鋑��R��������B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10001�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N08��26�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�o��ɌW����������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�v�z�̑n�삪���R�@���𗘗p���������ł���Ƃ����邩�ۂ��f����ɓ������ẮA�o��ɌW�锭���̍\�����ƂɌX�ʁX�ɔ��f���ׂ��ł͂Ȃ��A���������͈̔͂̋L�ڑS�̂��l�@���ׂ��ł���i�����y�ѐ}�ʂ��Q�ނ����ꍇ�̂��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�j�B�����āA���̏ꍇ�A�ۑ������ړI�Ƃ����Z�p�I�v�z�̑n��̑S�̂̍\�����ɁA���R�@���̗��p����v�Ȏ�i�Ƃ��Ď�����Ă��邩�ۂ��ɂ���āA�����@�Q���P������́u�����v�ɓ����邩�f���ׂ��ł����āA�ۑ������ړI�Ƃ����Z�p�I�v�z�̑n�삩��Ȃ�S�̂̍\�����ɁA�l�̐��_�����A�ӎv���薔�͍s���ԗl����Ȃ�\�����܂܂�Ă�����A�l�̐��_�������Ɩ��ڂȊ֘A����L����\�����܂܂�Ă�������Ƃ����āA���̂��Ƃ݂̂𗝗R�Ƃ��āA��������́u�����v�ł��邱�Ƃ�ے肷�ׂ��ł͂Ȃ��B
�@���̂悤�Ȋϓ_�ɏƂ炷�Ȃ�A�R���̔��f�́A�@�u�Ζ��̈������@�̓����Ƃ������́A�����ΏۂƂȂ�Ζ��̓����Ƃ����ׂ����̂ł����āA�E�E�E�Ζ��̓������ǂ��ł���l�Ԃ��s���ׂ��������肵���l�דI��茈�߂ɗ��܂���̂ł���v�ȂǂƏq�ׂ�悤�ɁA�����̑Ώۂ���Ζ��̋�̓I�ȓ�����S���l�����邱�ƂȂ��A�{�蔭�����u���@�̔����v�ł���Ƃ������Ƃ𗝗R�Ƃ��āA���R�@���̗��p������Ă��Ȃ��Ƃ������_���Ă���A�{�蔭���̓��������͈̔͂̋L�ڂ̑S�̓I�ȍl�@������Ă��Ȃ��_�A�y�сA�A���悻�A�u�������������@�v�́A�l�Ԃ��s���ׂ��������肵���l�דI��茈�߂ł���ƒf�肵�A���������A�Ȃɂ䂦�A��������������ł���u�l�דI�Ȏ�茈�߂��̂��́v�ɓ�����̂��ɂ��ĉ���������Ȃ��ȂǁA���R�@���̗��p�ɓ�����Ȃ��Ƃ������Ƃ̍����I�ȍ����������Ă��Ȃ��_�ɂ����āA�Ó����������B���������āA�R���̗��R�͕s���ł���A���̗]�̓_�f����܂ł��Ȃ��A�������Ƃ�Ȃ��B
�@�݂̂Ȃ炸�A�O�L�̂Ƃ���A�{��̓��������͈̔͂̋L�ڂɂ����ẮA�ΏۂƂȂ�Ζ��̓�������̓I�ɓE��������ŁA�l�ԂɎ��R�ɋ������\�͂̂�������̔F���\�́i�q���ɑ���D�ʓI�Ȏ��ʔ\�́j�𗘗p���邱�Ƃɂ���āA�p�P��̈Ӗ������m�肳����Ƃ��������ۑ���������邽�߂̕��@�������Ă���̂ł��邩��A�{�蔭���́A���R�@���𗘗p�������̂Ƃ������Ƃ��ł���B�{�蔭���ɂ́A���̎��{�̉ߒ��ɐl�Ԃ̐��_�������ƕ]��������\�����܂ނ��̂ł��邪�A���̂��Ƃ䂦�ɁA�{�蔭�����S�̂Ƃ��āA�P�ɐl�Ԃ̐��_����������Ȃ�v�z�̑n��ɂ������A�����@�Q���P������́u�����v�ɊY�����Ȃ��Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ��A�R���́A���̌��_�ɂ����Ă���肪����B
�R�������������(�o�������Ȏ��Ãl�b�g���[�N�̔����Y����)
���ʐM�l�b�g���[�N�y�уR���s���[�^�Ȃǂ�p�������Ȏ��ÃV�X�e���́A���̎��{�̂��߂ɕ]���A���f���̐��_�������K�v�ƂȂ���̂ƍl��������̂́A���R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��ɓ�������̂Ƃ������Ƃ��ł��A�����@�Q���P���Œ�`�����u�����v�ɊY������Ƃ��āA�������ɂ����鋑��R��������B��
| �����ԍ� | �@����19�N(�s�P)��10369�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N06��24�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�������P�ɋK�肳�ꂽ�u�v������鎕�ȏC���肷���i�v�y�сu�O�L���ȏC���̎��ȕ�ԍނ̃v���p���[�g�̃f�U�C���K�����܂ޏ������Ìv������肷���i�v�ɂ́A�l�̍s�ׂɂ����������v�f���܂܂�A�܂��A�{�蔭���P�����{���邽�߂ɂ́A�]���A���f���̐��_�������K�v�ƂȂ���̂ƍl��������̂́A�����ɋL�ڂ��ꂽ�����̖ړI�┭���̏ڍׂȐ����ɏƂ炷�ƁA�{�蔭���P�́A���_�������ꎩ�̂Ɍ�����ꂽ���̂Ƃ͂�����A�S�̂Ƃ��Ă݂�ƁA�ނ���A�u�f�[�^�x�[�X�������l�b�g���[�N�T�[�o�v�A�u�ʐM�l�b�g���[�N�v�A�u���Ȏ��Î��ɐݒu���ꂽ�R���s���[�^�v�y�сu�摜�\���Ə������ł��鑕�u�v�Ƃ�����A�R���s���[�^�Ɋ�Â��ċ@�\����A���Ȏ��Â��x�����邽�߂̋Z�p�I��i�������̂Ɨ������邱�Ƃ��ł���B
�@���������āA�{�蔭���P�́A�u���R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��v�ɓ�������̂Ƃ������Ƃ��ł��A�{�蔭���P�������@�Q���P���Œ�`�����u�����v�ɊY�����Ȃ��Ƃ����R���̔��f�͐��F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�R�������������(�u�r�b�g�̏W�܂�̒Z�k�\����������@�v�̔����Y����)
���������ɂ�鋑��R�����ێ��B�{�蔭���͊����̉��Z���u�ɐV���ȑn���t��������̂ł͂Ȃ��A���̎����͐��w�I�ȃA���S���Y�����̂��̂Ƃ����ق��Ȃ�����A����������āA�@�Q���P���̒�߂�u�����v�ɊY������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��
| �����ԍ� | �@����19�N(�s�P)��10239�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N02��29�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�b�V�i�R�����Z����P�́k�P�Ł`�U�Q�Łl�j�ɂ��A�R���s���[�^�E�\�t�g�E�F�A�֘A�����Ɋւ���������̐R����Ƃ��āA�������ɌW�锭���������@��́u�����v�ł��邽�߂ɂ́A���̔����͎��R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��̂������x�̂��̂ł��邱�Ƃ��K�v�ł��邪�A�u�\�t�g�E�F�A�ɂ�������A�n�[�h�E�F�A������p���ċ�̓I�Ɏ�������Ă���v�ꍇ�́A���Y�\�t�g�E�F�A�́u���R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��v�ł���Ƃ���A�����āA�u�\�t�g�E�F�A�ɂ�������n�[�h�E�F�A������p���ċ�̓I�Ɏ�������Ă���v�Ƃ́A�\�t�g�E�F�A���R���s���[�^�ɓǂݍ��܂�邱�Ƃɂ��A�\�t�g�E�F�A�ƃn�[�h�E�F�A�����Ƃ�����������̓I��i�ɂ���āA�g�p�ړI�ɉ��������̉��Z���͉��H���������邱�Ƃɂ��A�g�p�ړI�ɉ��������L�̏�����u�i�@�B�j���͂��̓�����@���\�z����邱�Ƃ������A�Ƃ���Ă���B
(����)
�@�{�蔭���P�`�R�ɂ�����u�r�b�g�̏W�܂�����鑕�u�v�Ƃ́A�E�E�E�i�����j�E�E�E�u���������̃f�[�^��Z�������̃f�[�^�Ƃ��ĕ\������Z�p�v�i��L�R(2)�A�j���p�����Ă�����̂ł���B
�@�����ŗp������n�b�V���@�́A�u���v�Ƃ����f�[�^�����̖@���ɏ]���ĒZ�k�����ĕ\�����悤�Ƃ���ꍇ�ɕs��I�ɔ�������Z�k�\���̏Փˁi���P�Ƃ����f�[�^��Z�k�����l���P�ƁA���Q�Ƃ����f�[�^��Z�k�������Q���������Ȃ��Ă��܂����Ɓj�̊m�����\�Ȍ��菬��������Ƃ������w�I�ȉۑ��L���A�{�蔭���́A���̂��߂̌v�Z�菇�i�A���S���Y���j�Ƃ��āA�E�E�E�i�����j�E�E�E�Ƃ����e���Z���܂ނ��̂ł���B���������āA�{�蔭���P�`�R�͂���������w��̌v�Z���A���Ȃ킿�n�b�V�����Ƃ��ĕ\���\�Ȃ��̂ł���A�E�E�E�i�����j�E�E�E����������w�I�Ȍv�Z���Ƃ��ĕ\������Ă���Ƃ���ł���B
(4) �Ƃ���ŁA��L���w�I�ۑ�̉�@�Ȃ������w�I�Ȍv�Z�菇�i�A���S���Y���j���̂��̂́A���R����w���̖@���ł����āA���玩�R�@���𗘗p������̂ł͂Ȃ�����A�����@�Q���P���ɂ��������Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B�܂��A�����̉��Z���u��p���Đ��������Z���邱�Ƃ́A��L���w�I�ۑ�̉�@�Ȃ������w�I�Ȍv�Z�菇������������̂ɂق��Ȃ�Ȃ�����A����ɂ�莩�R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z���t���������̂ł͂Ȃ��B
�@���������āA�{�蔭���̂悤�Ȑ��������Z���鑕�u�́A���Y���u���̂ɉ��炩�̋Z�p�I�v�z�Ɋ�Â��n�삪�F�߂��Ȃ�����A�����ƂȂ蓾����̂ł͂Ȃ��i���ɂ��ꂪ�����Ƃ����Ȃ�A���ׂĂ̐����������ƂȂ蓾�ׂ����ƂƂȂ�B�j�B
�@���̓_�A�{�蔭�������Z���u���̂ɐV�K�ȍ\����t��������̂łȂ����Ƃ́A����������F�߂�Ƃ���ł��邵�A���������͈̔͂̋L�ځi�O�L��R�A�P(2)�j���݂Ă��A�P�Ɂu�r�b�g�̏W�܂�̒Z�k�\�������鑕�u�v�ɂ���L�e�u���Z���ʂ����v������u�o�͂��Ă���v�Ƃ���݂̂ł����āA�g�p�ړI�ɉ��������Z���u�ɂ��Ă̒�߂͂Ȃ��A����Ώ�L���w�I�ȃA���S���Y���ɏ]���Čv�Z����u���u�v�Ƃ����ȏ�ɋK�肷��Ƃ��낪�Ȃ��B
�@��������ƁA�{�蔭���͊����̉��Z���u�ɐV���ȑn���t��������̂ł͂Ȃ��A���̎����͐��w�I�ȃA���S���Y�����̂��̂Ƃ����ق��Ȃ�����A����������āA�@�Q���P���̒�߂�u�����v�ɊY������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�R��������������i�����̒����ɂ����������͈̔͂̌��k�j
| �����ԍ� | �@���a62�N(�s�c)��109�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����3�N03��19�� |
| �@�얼 | �@�ō��ٔ�����O���@�� |
�@���R�́A�{�������̐ڒ��܁i�ڒ��w�j�Ɋւ��锭���̏ڍׂȐ����̍��̋L�ڂ�}�ʂȂǂ��Q�ނ��āA�Œ蕔�ނɂ͐ڒ��܁i�ڒ��w�j���܂܂����̂ƔF�蔻�f�������̂ł���A���R�̉E�F�蔻�f�́A���������͈̔͂̋L�ڕ����̋Z�p�I�Ӌ`����`�I�ɖ��m�Ƃ͂����Ȃ��ꍇ�̔����̗v�|�̔F��̎�@�ɂ�������̂Ƃ��Ď�m��������̂ł��邪�A������F�e����R���̊m��ɂ��A���������͈̔͂̋L�ڕ������̂��������ꂽ���̂ł͂Ȃ�����ǂ��A�ڒ��܁i�ڒ��w�j�Ɋւ���L�ڂ����ׂĖ����y�ѐ}�ʂ���폜���ꂽ���Ƃɂ���āA�o�莞�ɑk���āA�{�������̓��������͈̔͂̌Œ蕔�ނɐڒ��܁i�ڒ��w�j���܂܂��Ɖ��߂��Ė{�������̗v�|��F�肷��]�n�͂Ȃ��Ȃ������̂Ɖ�����̂������ł���B
�@���������āA�{�������ɂ�������F�e����R�����m�肵�����Ƃɂ��A�{�������̓��������͈̔͂̌Œ蕔�ނ̍\���́A�o��̓����ɑk���Ă���ɐڒ��܁i�ڒ��w�j���܂܂Ȃ����̂Ɍ��k���ꂽ���̂ƔF�߂���B
�R�������������(�����ƈꕔ�����R���̎�舵��)
���u�R���N���[�g���̐��H�ǖʉ��ǍH�@�v����
�@�Q�ȏ�̐������ɌW�閳���R�������ɂ����ẮA�������R�̑��ۂ͐��������ƂɓƗ����Ĕ��f�����̂ł���A�����R���̐R���ɂ����ĔF�߂�ꂽ�����̌��͂ɂ��Ă��A�X�̐��������Ƃɐ�����Ɖ�����̂������ł���B��
| �����ԍ� | �@����19�N(�s�P)��10081�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����19�N06��20�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�Q �Ȃ��A���ٔ����ɂ����āA�{����ɍۂ��čl���������_�ɂ��A�⑫���Đ�������B
�@(1) �{���̂悤�ɁA�Q�ȏ�̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓������ɂ��邱�Ƃ����߂���������R���ɂ����āA�������҂ɂ�����������F�߂���ŁA�ꕔ�̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓������Ƃ��A�c��̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓����̖���������s�����Ƃ���R�������ꂽ�ꍇ�ɁA�R���̂��������s�����Ƃ����������ɌW�镔���ɂ��Ď���i�ׂ���N����Ȃ������Ƃ��ɂ́A�R�����F�߂������̋A�������ƂȂ�B���Ȃ킿�A��L�̏ꍇ�ɂ����āA�����@�P�W�P���Q���̋K��ɂ��R���̎�����̌���ɂ��A�R���̂����������Ƃ����������ɌW�镔������������āA�R���葱���ĊJ���ꂽ�Ƃ��ɁA���@�P�R�S���̂Q��S���ɋK�肷����������݂̂Ȃ��扺���Ƃ̊W�ŁA���Y�R���ɂ����ĔF�߂�ꂽ�����̂��������s�����Ƃ��ꂽ�������Ɋւ��镔���ɂ��ẮA�������m�肵�����̂Ɖ�����̂��A���邢�͓����̋K��ɂ���艺����ꂽ���̂Ɖ�����̂������ƂȂ�B
�@�����ŁA�{����ɂ�荷���߂��ꂽ�����ɂ��āA����s����R���ɂ�����R���Ɏ����邽�߁A�{�������̋A���ɂ��t������B
�@(2) �{�������́A�{�������̓��������͈̔͂̂����������S�݂̂����������̂ł����āA���̗]�̐����������������̂ł͂Ȃ��A�܂��A�{���R���ɂ��A���������͈͈̔ȊO�̒��������i�{�������̒i���y�O�O�P�S�z�A�y�O�O�R�Q�z�A�y�O�O�V�X�z�A�y�O�O�W�O�z�ɌW����́j�͂�������������S�̒����ɔ����A���������͈̔͂̋L�ڂƔ����̏ڍׂȐ����̋L�ڂƂ̐�����}����̂Ƃ���Ă��邩��A�{���R���́A��琿�����S�Ƃ̊W�Ŗ{��������F�߂����̂Ƃ����ׂ��ł���B�����āA�{���R���́A�{���������F�߂��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�{�������̐������S�ɌW�锭���ɂ��Ă̖����R��������s�����Ƃ������̂ł��邩��A�{���R�����u������F�߂�B�v�Ƃ̕����ƁA�u������R�V�S�X�W�R�R���̐������S�ɌW�锭���ɂ��Ă̐R�������́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̕����́A��̕s���̊W�ɂ���Ƃ����ׂ��ł���B
�@������Ƃ���A�퍐�i�R�������l�j�́A�{���R�����u������R�V�S�X�W�R�R���̐������S�ɌW�锭���ɂ��Ă̐R�������́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̕����ɂ��Ă͎���i�ׂ��N���Ă��Ȃ�����A�{���R�����̏�L�����́A�o�i���Ԃ̌o�߂ɂ��m�肵���B�������A�������Q�ȏ�̐������ɌW����̂ł���Ƃ��ɂ́A�����R���͐��������Ƃɐ������邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă���̂ł��邩��i�����@�P�Q�R���P�������j�A�Q�ȏ�̐������ɂ��Ė����R������������ĐR���ɂ����Ă���ɑ��锻�f�����ꂽ�ꍇ�ɂ����ẮA���Y�R���́A�e�������ɂ��Ă̔��f���Ƃɉ��ȍs�������Ƃ��āA���ꂼ�ꂪ����i�ׂ̑ΏۂƂȂ���̂ł���A���ꂼ��ʌɊm�肷��Ƃ����ׂ��ł��邩��ł���B�R���́A�s�������ł���A���̎���������߂�i���́A���Y�����̎���������߂�ɂ��@����̗��v��L����҂Ɍ���A��N���邱�Ƃ��ł���̂ł���i�s�������i�ז@�X���Q�Ɓj�A�Q�ȏ�̐������ɌW������ɂ��Ă̖����R���ɂ����āA�ꕔ�̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓������Ƃ��A�c��̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓����̖���������s�����Ƃ���R�������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����@�P�V�W���Q���̋K�肷�铖���ҁA�Q���l���͎Q����\�����Ă��̐\�������ۂ��ꂽ�҂̂����A�R�����A�������Ƃ��ꂽ�������ɌW�镔���ɂ��Ă͔퐿���l�i�������ҁj���݂̂��A�����������s�����Ƃ��ꂽ�������ɌW�镔���ɂ��Ă͐����l���݂̂��A����i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���B�����āA�R���̂����A���ꂼ��̕����ɂ��ē����@�P�V�W���R���ɋK�肷����ԓ��ɏ�L�̎҂������i�ׂ���N����Ȃ������Ƃ��ɂ́A���Y�����͊m�肷����̂Ɖ����邱�ƂƂȂ�B
�@��������ƁA�{���R���̂����u������R�V�S�X�W�R�R���̐������S�ɌW�锭���ɂ��Ă̐R�������́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̕������m�肵�����Ƃɔ����āA�{���R�����u������F�߂�B�v�Ƃ̕������m�肵�����̂Ɖ�����̂������ł���i�����@�P�R�S���̂Q��T���ɂ����ď��p����铯�@�P�Q�W���Q�Ɓj�B
�@(3) �ȏ㌟�������Ƃ���A�{�������͂��łɊm�肵�����̂ł��邩��A�{���肪���͂�����A�{���R���̎葱���{�������̐������P�y�тQ�Ɋւ��镔���ɂ��čĊJ����A�����@�P�R�S���̂R��Q���̋K��ɂ��w�肳�ꂽ���ԓ��ɒ������������ꖔ�͓����T���̋K��ɂ�蓯���Ԃ̖����ɒ������������ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ���Ă��A�{�������Ɋւ��Ă͓��@�P�R�S���̂Q��S���̋K��ɂ��݂Ȃ��扺���̌��ʂ͐����Ȃ��B
�@�܂��A�ʌ��R���ɂ��Ă��A�{���������m�肵�Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���̐R�����s����ׂ��ł���B
�@�Ȃ��A�����́A�����R���̐������ɂ����āA�{�����������m��ł��邱�Ƃ�O��ɁA�����R���ɌW�閾���̐������S�y�ђi���y�O�O�P�S�z�A�y�O�O�R�Q�z�A�y�O�O�V�X�z�A�y�O�O�W�O�z�ɂ��A���������i�b�j�y�ђ��������i�b�|�P�j�Ȃ����i�b�|�S�j�Ƃ��Đ����������Ă��邪�A��L�̂Ƃ���A�{�������͂��łɊm�肵�����̂ł��邩��A��L�������ɂ�������������i�b�j�y�ђ��������i�b�|�P�j�Ȃ����i�b�|�S�j�̋L�ڂ͈Ӗ��̂Ȃ����̂ł���B
�R �{���Ɋւ��锻�f�͈ȏ�̂Ƃ���ł��邪�A���̋@��ɁA�����@�P�R�S���̂Q��S���̋K��ɂ��݂Ȃ��扺���̌��ʂ́A���������Ƃɐ�����Ɖ����ׂ����Ƃɂ��āA���ٔ����̌����������Ă����B
�@(1) �����@�́A���a�U�Q�N�@����Q�V���ɂ������ɂ��A��������P������������ƂƂ��ɁA�Q�ȏ�̐������ɌW������ɂ��Ă͐��������Ƃɖ����R�����������邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ������i�����@�P�Q�R���P�������j�A���̌�A�����T�N�@����Q�U���ɂ������ɂ��A�����R���̎葱�ɂ����Ē������������邱�Ƃ��ł��邱�ƂƂ��A����ɁA�����P�P�N�@����S�P���ɂ������i�ȉ��u�����P�P�N�����v�Ƃ����B�j�ɂ��A���������̓��ۂɊւ��A������̐������ɌW�锭���i�������A�����R������������Ă��Ȃ��������ɌW�锭���������B�j�ɂ��āA������Ɨ������v���̔��f���s��Ȃ����ƂƂ����B�Ȃ��A�Q�ȏ�̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓������ɂ��邱�Ƃ����߂���������R���ɂ����āA�������҂ɂ�����������F�߂���ŁA�ꕔ�̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓������Ƃ��A�c��̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓����̖���������s�����Ƃ���R���́A�����P�P�N�����ɂ����āA��L�̂Ƃ���A���������̓��ۂɊւ��Ɨ������v���̔��f���s��Ȃ����ƂƂ��ꂽ���Ƃɔ����A�����Ɏ��������̂ł���i�����P�P�N�����O�̓����@�̉��ł́A���̂悤�ȏꍇ�A�Ɨ������v���������Ƃ��Ē����������S�̂Ƃ��ĔF�߂�ꂸ�A�����O�̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��āA�e�������̖������R�̑��ۂ����f����Ă����B�j�B
�@���̂悤�ɁA�Q�ȏ�̐������ɌW�閳���R�������ɂ����ẮA�������R�̑��ۂ͐��������ƂɓƗ����Ĕ��f�����̂ł���A�X�̐��������Ƃ̐R���������ɐi�s���Ă�����̂Ƃ��čl����̂��A�����R�����x�̎�|�ɉ������̂ł���B��������ƁA�����R���̐R���ɂ����ĔF�߂�ꂽ�����̌��͂ɂ��Ă��A�X�̐��������Ƃɐ�����Ɖ�����̂������ł���B
�@�����āA�����@�P�R�S���̂Q��S���̂�����݂Ȃ��扺���̋K��́A�����P�T�N�@����S�V���ɂ������ɂ�蓱�����ꂽ���̂ł��邪�A��L�̂悤�Ȗ����R�����x��O��Ƃ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A���̌��ʂ����������Ƃɐ�����Ɖ�����̂������ł���B
�@(2) �Ȃ��A��������P����������������A���������Ƃɖ����R�������ɂ��Ă̔��f���s�����x���̗p���ꂽ���߁A��L�̂Ƃ���A�Q�ȏ�̐������ɌW�锭���ɂ��Ă̓����Ɋւ��āA�ꕔ�̐������ɂ������R�������̐R�����m�肵�A���邢�͓��������͈͓̔��̋L�ڂ���������邱�Ƃ������邪�A���̂悤�Ȍ��ʂ��A�K�����������o�^����̋L�ڂɔ��f����Ă��Ȃ��悤�ɂ�������B���ɁA�������ɂ����āA�����R���ɂ����������Ȃ��������̌��͂����������Ƃɐ�����Ƃ̎����^�p������Ă��Ȃ��Ƃ���Ȃ�A����͖@�̎�|�ɔ�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̒����̌���
���u�����_�C�I�[�h���W���[������є����_�C�I�[�h�����v����
�@�����ًc�\�������̌W�����ɕ����̐������ɌW��������������ꂽ�ꍇ�A�����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̓��������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�������ɂ��ẮA�����̑ΏۂƂȂ��Ă��鐿�������ƂɌʂɂ��̋��ۂf���ׂ��ł���B��
| �����ԍ� | �@����19�N(�s�q)��318�� |
|---|---|
| ������ | �@��������������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N07��10�� |
| �@�얼 | �@�ō��ٔ�����ꏬ�@�� |
���R(����18�N(�s�P)��10314��)
�����f�[�^�F�@PAT-H18-Gke-10314.pdf
�R ���R�́A���̂Ƃ��蔻�f���āA�{������̎���������߂�㍐�l�̐��������p�����B
�@�{������́A�����������������̗v���ɓK�����Ȃ����Ƃ𗝗R�ɁA���̒��������ɂ��Ĕ��f���邱�ƂȂ��A�{�������̑S����F�߂Ȃ��������̂ł��邪�A���̔��f�Ɉ�@������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ킿�A�菑�ɓY�t�����������͐}�ʂ̋L�ڂ��ӏ��ɂ킽���Ē������邱�Ƃ����߂�����R���̐������͒����̐����ɂ����āA���̒��������������͈̔͂Ɏ����I�e�����y�ڂ����̂ł���ꍇ�ɂ́A�����l�ɂ����Ē����i�R���j�������̒������������铙���ĕ����̒����ӏ��̂����ꕔ�̉ӏ��ɂ��Ē��������߂��|����肵�Ė������Ȃ�����A�����̒����ӏ��̑S���ɂ���̂Ƃ��Ē����������������Ȃ����̐R�����͌�������Ȃ���Ȃ炸�A���Ƃ��q�ϓI�ɂ͕����̒����ӏ��̂����̈ꕔ�����̕����ƋZ�p�I�ɂ݂Ĉ�̕s���̊W�ɂȂ��A���A�ꕔ�̒������������Ƃ������l�ɂƂ��Ď��v�̂���Ƃ��ł����Ă��A���̉ӏ��ɂ��Ă̂ݒ����������R�����͌�������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɖ�����̂������ł���i�ō��ُ��a�T�R�N�i�s�c�j��Q�V���A��Q�W�����T�T�N�T���P����ꏬ�@�씻���E���W�R�S���R���S�R�P�ŎQ�Ɓj�B�����āA���̗��́A��������P�������i���a�U�Q�N�@����Q�V���ɂ�������̓����@�R�U���T������߂鐿�����̋L�ڕ��@�j�̉��ł����l�ɑÓ�����Ƃ����ׂ��ł���B�{�������ɌW��������������݂Ă��A�����̒����ӏ��̂����ꕔ�̉ӏ��ɂ��Ē��������߂��|����肵�Ė������Ă��炸�A���̒��������͈�̕s���̂��̂ł������Ɖ�������Ȃ��B
�S �������Ȃ���A���R�̏�L���f�͐��F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̗��R�́A���̂Ƃ���ł���B
(1) �����@�́A��̓����o��ɑ��A��̍s�������Ƃ��Ă̓������薔�͓����R��������A����Ɋ�Â��Ĉ�̓������t�^����A��̓���������������Ƃ�����{�\����O��Ƃ��Ă���A���������ƂɌʂɓ������t�^�������̂ł͂Ȃ��B���̂悤�ȍ\���Ɋ�Â��A�����̐������ɌW������o��ł����Ă��A�����o��̕��������Ȃ�����A���Y�����o��̑S�̂���̕s���̂��̂Ƃ��ē������薔�͋��⍸�������ق��Ȃ��A�ꕔ�̐������ɌW������o��ɂ��ē�����������A���̐������ɌW������o��ɂ��ċ��⍸�������Ƃ����悤�ȉ��I�Ȏ戵���͗\�肳��Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�����@�S�X���A�T�P���̕����̂ق��A�����o��̕����Ƃ������x�̑��ݎ��̂ɏƂ炵�Ă����炩�ł���B����ŁA�����@�́A�����̐������ɌW������Ȃ����������̈�̕s���̎戵�����ѓO���邱�Ƃ��s�K���ƍl��������̏ꍇ�ɂ́A���ɖ����̋K��������āA���������Ƃɉ��I�Ȏ戵����F�߂�|�̗�O�K���u���Ă���A�����@�P�W�T���݂̂Ȃ��K��̂ق��A�����@���P�P�R�𒌏�����i���u��ȏ�̐������ɌW������ɂ��ẮA���������Ƃɓ����ًc�̐\���Ă����邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肷��̂́A���̂悤�ȗ�O�K��̈�ɂق��Ȃ�Ȃ��i���������R���̐����ɂ��ċK�肵�������@�P�Q�R���P����������i������|�j�B
(2) ���̂悤�ȓ����@�̊�{�\����O��Ƃ��āA�����ɂ��Ă̊W�K����݂�ƁA�����R���Ɋւ��ẮA�����@���P�P�R�𒌏�����i�A�����@�P�Q�R���P����������i�ɑ�������悤�Ȑ��������Ƃɉ��I�Ȏ戵�����߂閾���̋K�肪�����Ȃ���A�����R�������͈��̐V�K�o��Ƃ��Ă̎�����L���邱�Ɓi�����@�P�Q�U���T���A�P�Q�W���Q�Ɓj�ɂ��Ƃ炷�ƁA�����̐������ɂ��Ē��������߂�����R�������́A�����̐������ɌW������o��̎葱�Ɠ��l�A���̑S�̂���̕s���̂��̂Ƃ��Ď�舵�����Ƃ��\�肳��Ă���Ƃ�����B
�@����ɑ��A�����@���P�Q�O���̂S��Q���̋K��Ɋ�Â������̐����i�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j�́A�����ًc�\�������ɂ�����t���I�葱�ł���A�Ɨ������R���葱�ł�������R���̐����Ƃ́A�����@��̈ʒu�t�����قɂ�����̂ł���B���������̒��ł��A�{�������̂悤�ɓ����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̓��������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�����̂ɂ��ẮA������Ɨ������v�����v������Ȃ��i�����@���P�Q�O���̂S��R���A���P�Q�U���S���j�ȂǁA�����R���葱�Ƃ͈قȂ�戵�����\�肳��Ă���A�����R�������̂悤�ɐV�K�o��ɏ����������L����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�����āA�����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̓��������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�����������́A���������Ƃɐ\���Ă����邱�Ƃ��ł�������ًc�ɑ���h���i�Ƃ��Ă̎�����L������̂ł��邩��A���̂悤�Ȓ�������������������҂́A�e���������ƂɌʂɒ��������߂���̂Ɨ�������̂������ł���A�܂��A���̂悤�Ȋe���������Ƃ̌ʂ̒������F�߂��Ȃ��ƁA�����ًc�����ɂ�����U���h��̋ύt�����������ƂɂȂ�B�ȏ�̏��_�ɂ��݂�ƁA�����ًc�̐\���Ăɂ��ẮA�e���������ƂɌʂɓ����ًc�̐\���Ă����邱�Ƃ�������Ă���A�e���������Ƃɓ���������̓��ۂ��ʂɔ��f����邱�ƂɑΉ����āA�����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̓��������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�����������ɂ��Ă��A�e���������ƂɌʂɒ������������邱�Ƃ����e����A���̋��ۂ��e���������ƂɌʂɔ��f�������̂ƍl����̂������I�ł���B
�@��㍐�l�́A������\�����閾���͏�ɂ��̑S�̂���̕s���̂��̂Ƃ��Ĕc�������ׂ��ł���Ǝ咣���邪�A���a�U�Q�N�@����Q�V���ɂ������@�̉����ɂ��A������ꔭ����o��̌������߂Ă����K�肪�폜����A�������ꔭ���ɕ����̐������̋L�ڂ����邱�Ƃ��F�߂���悤�ɂȂ������Ƃ��l����ƁA��������̓����@�̉��ŁA��L�̂悤�ɉ����ׂ������������������Ƃ͂ł��Ȃ��B�O�f�ō��ُ��a�T�T�N�T���P����ꏬ�@�씻���́A������ꕔ�����������Ƃ��Ĕے肵�����̂ł��邪�A�����̐��������ϔO���邱�Ƃ��ł��Ȃ����p�V�ēo�^�����͈̔͒��ɕ����̒����������܂܂�Ă��������R���̐����Ɋւ��锻�f�ł���A���̎�|�́A���������͈̔͂̓���̐������ɂ������̒����������܂ޒ�������������Ă���ꍇ�ɂ͑Ó�������̂Ɖ�����邪�A�{���̂悤�ɁA�����̐������̂��ꂼ��ɂ��������������݂�����������ɂ����āA���������Ƃɒ����̋��ۂ��ʂɔ��f���ׂ����ǂ����Ƃ�����ʂɂ܂ł��̎�|���y�Ԃ��̂ł͂Ȃ��B
(3) �ȏ�̓_���炷��ƁA�����ًc�\�������̌W�����ɕ����̐������ɌW��������������ꂽ�ꍇ�A�����ًc�̐\���Ă�����Ă��鐿�����ɂ��Ă̓��������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�������ɂ��ẮA�����̑ΏۂƂȂ��Ă��鐿�������ƂɌʂɂ��̋��ۂf���ׂ��ł���A�ꕔ�̐������ɌW����������������̗v���ɓK�����Ȃ����Ƃ݂̂𗝗R�Ƃ��āA���̐������ɌW������������܂ޒ����̑S����F�߂Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�������N�Q���~�������s���݊m�F�����T�i����
| �����ԍ� | �@����18�N(�l)��10040���� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������s���݊m�F�����T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����19�N10��31�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�� �P�R�퍐�́A�ʏ�K�v�Ƃ���鎖�����������ڍׂȒ����E���͂����{�����|�咣���邪�A���̂悤�Ȓ����͍s���Ă��Ȃ��B
�P�R�퍐�́A�{�����i�̕��͂ɌW�鉳�R�ȊO�ɂ́A�{���������̖������R�̑��ۂ�{�����i���{�����������̋Z�p�I�͈͂ɑ����邩�ۂ��ɂ��Ē����E�������������Ƃɂ��A���痧���Ă��炸�A�P�R�퍐�̏�L�咣�͗��t�����������̂ł���B
�@�܂��A���ɂP�R�퍐�̎咣��O��Ƃ���Ƃ��Ă��A�����ɖ������R�����݂���̂́A�V�K�����Ȃ��ꍇ�Ɍ�������̂ł͂Ȃ��A�i�������Ȃ��ꍇ�A���̑��̓����v���������ꍇ������Ƃ���A�P�R�퍐�́A�ی��H�̃Q�[�g�ƃ\�[�X�y�уh���C���̈����d�C�I�ɐڑ�������ޗ��Ƃ��āA�h�s�n�ɑ�\�����_���������̖����g�p�����s�Z�p���Ȃ����Ƃ��m�F�����ɂ����Ȃ�����A�V�K���ɂ��Ă͂Ƃ������A�i�������̑��̓����v���ɂ��ẮA�S���������s��Ȃ��������ƂɂȂ�B�܂��A�����̑ΏۂƂȂ��s�Z�p�͈̔͂́A�{���������y�т��̊֘A�o��̐R���o�߂ɂ����Ĉ��p���ꂽ�����Ɍ�������̂ł͂Ȃ��B�P�R�퍐�́A�Œ���̂��̂Ƃ��ĕK�v�ȁA��ʓI�Ȍ��m�ᒲ���i���J�ς݂̊e�����y�ш�ʌ��\���ꂽ�Z�p�����̒����j���s���Ă��Ȃ��B
�@����ɁA�O�L(1)�C�y��(2)�C�̂Ƃ���A�{�����������̋L�ڂ���A�{�������������ی��H�Ƃ��ċ@�\���Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A���̂��Ƃ͂P�R�퍐�����������Ƃ݂Ȃ���Ă���B�P�R�퍐�́A�{���������\���Ăɍۂ��āA�{�����������̋L�ڂɏƂ炵�A�{�������������ی��H�Ƃ��ċ@�\���邩�ǂ����ɂ��āA�����E������ӂ������̂Ƃ�����B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�P�R�퍐�́A�ʏ�K�v�Ƃ���钍�Ӌ`����s�����Ȃ������B
�� �����R�������ɂ����Ė������f������銄����A�R������i�ׂɂ����閳���s�����R������������銄�������Ȃ��Ȃ����ƂɏƂ点�A������������Ƃ����ꎖ�������Ē����`����Ƃ�闝�R�͂Ȃ����A�ٗ��m���̐��Ƃ̈ӌ��f�̊�b�Ƃ����Ƃ�������������Ƃ��Ă��A��@����ߎ��̑��݂�ے肷�闝�R�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��B
�@�܂��A�������N�Q�Ɋւ��āA��̓I�Ȍ����s����A���������A���Y�������Ɋ֘A�����s�Z�p���������̂��ʏ�ł���B���������āA�������҂�������Ƃ̌������ۂ��邱�Ƃ́A��s�Z�p�ɂ��Ē����E��������@���������邱�Ƃ��Ӗ�����B�{���ɂ����āA�P�R�퍐�́A��A�̌��ɂ����āA�������N�Q�Ɋւ����̓I�ȍ����������Ȃ������݂̂Ȃ炸�A�P�R�����Ƃ̌��ɂ����Ē������X�g�i�b�Q�T�j�ɁA�{�����������f�ڂ��Ȃ������B���������āA�P�R�퍐�́A��s�Z�p��F���E��������@�����������������̂ł���A���̂悤�Ȍ��ԓx�ɏƂ炵�Ă��A�����҂Ƃ��Ă̒ʏ�̒��Ӌ`����s�����Ă��Ȃ��Ƃ�����B
�� �������N�Q���߂��镴���̐^�̑�����ɑ��Ăł͂Ȃ��A���̌ڋq���ɑ��������\���Ă����āA���Y�ڋq���̕������I�X���𗘗p����悤�ȏꍇ�́A���������x�����̖{���̖ړI�ɔ����ė��p������̂Ƃ�����B
�i�����j
�S ���_(5)�i�M�p���Q���鋕�U�����̍��m�s�ז��͕s�@�s�ׁj�ɂ���
�P�R�퍐�̂����{���������\�������P�R�����ɑ���W�ŁA�s�@�s�ׂ��\�����邩�ۂ��A�y�сA�s���@�Q���P���P�S������̕s�������s�ׂɊY�����邩�ۂ��ɂ��āA�ȉ���������B
(1) �s�@�s�Y�����ɂ���
�A�������\���Ă̕s�@�s�Y�����ɂ���
�@�����̓����҂����Y�����̉������ٔ����ɋ��ߓ��邱�Ƃ͖@�����Ƃ̍����ɂ������d�v�Ȏ����ł��邩��A�ٔ����錠���͍ő�����d����Ȃ���Ȃ炸�A�i���̒�N�ɂ��ĕs�@�s�ׂ̐��ۂf����ɓ������ẮA���₵�����ٔ����x�̗��p��s���ɐ������錋�ʂƂȂ�Ȃ��悤�T�d�Ȕz�����K�v�ł���B���������āA�@�I�����̉��������߂đi�����N���邱�Ƃ́A�����Ƃ��Đ����ȍs�ׂł����āA�s�@�s�ׂ��\�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�������A��i�҂����Y�i�ׂɂ����Ď咣�����������͖@���W�������I�A�@���I�������������̂ł����A���l�����̂��Ƃ�m��Ȃ��疔�͒ʏ�l�ł���Ηe�Ղɂ��̂��Ƃ�m�蓾���̂ɂ����Ē�N�����ȂǁA�ٔ����x�̎�|�ړI�ɏƂ炵�Ē������������������ꍇ�ɂ́A��@�ȍs�ׂƂ��ĕs�@�s�ׂ��\������Ƃ����ׂ��ł���(�ō��ُ��a�U�O�N(�I)��P�Q�Q�����U�R�N�P���Q�U����O���@�씻���E���W�S�Q���P���P�ŎQ��)�B
�@���̗��͉������̐\���Ăɂ����Ă��قȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A���҂����̎咣���錠�����͖@���W�������I�A�@���I�������������Ƃ�m��Ȃ��疔�͒ʏ�l�ł���Ηe�Ղɂ��̂��Ƃ�m�蓾���̂ɁA�����Ĕ̔��֎~���̉�������\�����Ă��ꍇ�ɂ́A���������̐\���Ă͈�@�ȍs�ׂƂ��ĕs�@�s�ׂ��\������Ɖ����ׂ��ł���B
�@�܂��A���Y�������\���Ăɂ����āA���҂̎咣�����������͖@���W���A�����I�A�@���I�������������̂ł��邱�Ƃ��A�ʏ�l�ł���Ηe�Ղɒm�蓾�����̂Ƃ܂ł����Ȃ��ꍇ�ł����Ă��A�����̍s�g���S�����āA���Ǝ҂̎����ɑ���M�p��ʑ����A�s��ɂ����ėD�ʂɗ����Ɠ���ړI�Ƃ��āA���Ǝ҂̎�������Ƃ��鉼�����\���Ă����ꂽ�悤�Ȏ���F�߂���ꍇ�ɂ́A���������̐\���Ă͈�@�ȍs�ׂƂ��ĕs�@�s�ׂ��\������Ƃ����ׂ��ł���B���Y�������̐\���Ă��A��@�ȍs�ׂƂȂ邩�ۂ��́A���Y�\���ĂɎ���܂ł̋��Ǝ҂Ƃ̌��̌o�܁A���Y�\���Ă̑�����̑ԓx�A�������ɑ���\������鑊����̑Ή����̎���𑍍����Ĕ��f����̂������ł���B
(�A) ��L�C�ɐ����̊e�����𑍍�����ƁA�P�R�퍐���{���������\���đO�ɁA�{�����������̋L�ڂ���������A���{�\�v���ᔽ�̖������R�����݂��邱�Ƃ�e�Ղɒm�蓾�����̂ł���A�܂��A�ʏ�K�v�Ƃ���鎖���������s���A�{���������ɐi�������@�̖������R�����݂��邱�Ƃ��e�Ղɒm�蓾�����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����āA�@�P�R�����̂ǂ̐��i���P�R�퍐�̗L����ǂ̓��������ǂ̂悤�ɐN�Q���Ă��邩����w�E���邱�ƂȂ��A���C�Z���X�_����������悤���߂Ă����P�R�퍐�̌��̑ԓx�A�A���F�ɑ��ẮA���O�Ɍx�����̑[�u���s�����`�Ղ͂��������Ȃ����ƁA�B�����i���d����Ĉ�ʏ���҂ɔ̔�����ƑԂ��̗p���Ă���ʔ̓X�ɑ��āA��������\�����Ă�A�ʔ̓X�́A�����ɔ̔��𒆎~����ł��낤���Ƃ͏\���ɗ\���ł������ƁA�C�������̐\���Ă��������Ƃ��L�҂Ɍ��\����A�}�X�R�~�����������邱�Ƃ��\���ł������Ɠ��̏�����𑍍�����A�P�R�퍐�������{���������\���ẮA��玩�Ȃ̗L���镡���̓�������w�i�ɂP�R�����Ɉ��͂������A�P�R�퍐�ɗL���ȓ��e�̕�I�ȃ��C�Z���X�_�����������邽�߂̎�i�Ƃ��āA�s��ꂽ���̂ƔF�߂���B���Ȃ킿�A�{���������\���ẮA�������N�Q�Ɋ�Â������s�g�Ƃ����O�`���Ă�����̂́A�P�R�����̎����ɑ���M�p��ʑ����A�_�������D�ʂɗ����Ɠ���ړI�Ƃ����s�ׂł���A���������������������̂ƔF�߂���B
(�C) �P�R�퍐�̂����{���L�Ҕ��\�́A�{���������\���Ă̎�����{�������������ɂ����鎩�Ȃ̐\�����e�⎖���I�咣�A�@���I�咣�̓��e������������̂ł����āA���U�̎��������\�������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�������A�{���L�Ҕ��\�́A��L�̖{���������\���Ăɑ����Ē����Ɏ��{����Ă��邱�ƂɏƂ炷�Ȃ�A�V���L�҂�ɍ��m�����������f�ڂ����L�����쐬����A����邱�Ƃɂ��A�{�����i�̎��v�҂��܂ވ�ʂ̓ǎ҂ɁA�{�����i���{����������N�Q���Ă��邩�̂悤�Ȉ�ۂ�^����W�R���������A���̂悤�ȕ����ꂽ�ꍇ�A�ʔ̓X�ł���A�̔��𒆎~������Ȃ��ƂȂ�B��������ƁA�{���L�Ҕ��\�́A�{�����i���{����������N�Q���Ă��邩�̂悤�Ȏ������L�����Ԃɒm�炵�߂邱�Ƃɂ��A�P�R�����Ɉ��͂������A�P�R�퍐�ɗL���ȓ��e�̕�I�ȃ��C�Z���X�_�������������i�Ƃ��ėp����ꂽ���̂Ƃ������Ƃ��ł��A�����Ȍ����s�g�̈�Ƃ��Ă��ꂽ���̂Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��{���������\���ĂƓ��l�ɁA���������������������̂ƔF�߂���B
(�E) �O�L(�A)�̂Ƃ���A�P�R�퍐���{���������\���đO�ɁA�{�����������̋L�ڂ���������A���{�\�v���ᔽ�̖������R�����݂��邱�Ƃ�e�Ղɒm�蓾�����̂ł���A�܂��A�������R�̗L���ɂ��Ēʏ�K�v�Ƃ���鎖���������s���A�{���������ɐi�������@�̖������R�����݂��邱�Ƃ��e�Ղɒm�蓾�����̂Ƃ����ׂ��ł���B
(�G) �ȏ�ɂ��A�P�R�퍐�ɂ��{���������\���ċy�т���Ɉ��������{���L�Ҕ��\�́A�P�R�����ɑ���s�@�s�ׂ��\������Ƃ����ׂ��ł���B
(2) �s���@�Q���P���P�S������̕s�������s�Y�����ɂ���
�A�@�{���������\���Ăɂ���
�@�P�R�����́A�P�R�퍐���A�{���������\���Ăɂ��A�����n���ٔ��������Ă��̐\�����𐼗F�ɑ��B�������s�ׂ��A�P�R�����̎����ł��鐼�F�ɑ��A�{�����i���{����������N�Q����Ƃ̋��U�̎��������m����s�ׂł���Ǝ咣����B
�@�������A�{���S�؋��ɂ����A�{�������������ɌW��\�����������n���ٔ����ɂ�萼�F�ɑ��B���ꂽ�Ƃ̎����͔F�߂��Ȃ��B�Ȃ��A���Q�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�{���������\���Č�x���Ƃ������P�U�N�P�Q���P�V���܂ł̊ԂɁA�{�������������ɌW��\�����̓��e�𐼗F���m�������Ƃ��F�߂�����̂́A�������̐\���Ă������҂��`���҂ɑ��Č������������邽�߂ɐ݂���ꂽ���̋~�ϐ��x�ł����āA������~�ϐ��x�̗��p�y�т���ɓ��R��������s�ׂ������~�߂邱�Ƃ͕s���@�̗\�肷��Ƃ���ł͂Ȃ��_�Ɋӂ݂�A�������N�Q���𗝗R�Ƃ��鍷�~�̉������Ȃlj��̒n�ʂ��߂鉼�����̐\���Ăɔ����āA�\�����̓��e����ɒm�炵�߂邱�Ƃ��A�s���@�Q���P���P�S������̍��m�s�ׂł���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA�P�R�����̎咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�C�@�{���L�Ҕ��\�ɂ���
�@�P�R�����́A�{���������\���Ă̎������L�҂Ɍ��\�������Ƃ��A�{�����i���{����������N�Q����Ƃ̋��U�̎��������m�E���z����s�ׂł���Ƃ��咣����B
�@�������A�O�L(1)�C(�C)�ŔF�肵���Ƃ���A�P�R�퍐�́A�{���L�Ҕ��\�ɂ��A�{���������\���Ă̎�����{�������������ɂ����鎩�Ȃ̐\�����e�⎖���I�咣�A�@���I�咣�̓��e������������̂ł���A���̌��\���̂ɂ��āA���U�̎��������m�E���z�������̂ƕ]�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i�Ȃ��A�P�R�����́A�P�R�퍐���A�{���L�Ҕ��\�ɂ��A�{�������ȊO�ɂ��P�R�퍐�ۗL�̓�������N�Q���Ă���Ƃ̋��U�̎��������m�E���z�������Ƃ��咣���邪�A�{���S�؋��ɂ����A��̓I�ɂ����Ȃ鎖�������m�E���z���ꂽ�Ƃ����̂����炩�łȂ��A�̗p�̌���łȂ��B�j�B
�E�@���~�����̓��ۂɂ���
�@�ȏ�̂Ƃ���A�{���������\���ċy�і{���L�Ҕ��\���A�s���@�Q���P���P�S������̕s�������s�ׂɊY�����邱�Ƃ�O��Ƃ���P�R�����̎咣�͍̗p�ł��Ȃ��B���������āA�P�R�����̕s���@�R���P���Ɋ�Â����~�����͗��R���Ȃ��B
���������R�������������(�ٗ��m�@�ᔽ�u�~���p���^���N���b�v�v����)
�����������n���̑��̌����ɂ��ړ]�������҂��ς�����Ƃ��Ă��A�ٗ��m���A����̓������ɂ��āA����Ƃ��́A���̌����̍s�g���͌����̗i��ɉ��A����Ƃ��͈�]���āA���̌����̖������咣�����̌������U������悤�ȍs�ׂɋy�ԂƂ��́A�ٗ��m�@�W���P���̋K��ɔ�����s�ׂł���B��
| �����ԍ� | �@����4�N(�s�P)��32�� |
|---|---|
| ������ | �@���������R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����4�N09��16�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�@���̂悤�ȗ���ɂ���ٗ��m���A����̓������ɂ��āA����Ƃ��́A���̌����̍s�g���͌����̗i��ɉ��A����Ƃ��͈�]���āA���̌����̖������咣�����̌������U������悤�ȍs�ׂɋy�ԂƂ��́A�����҂݂̂Ȃ炸�A�L�����l�����āA�ٗ��m��ʂɑ���M�p�����Ă����邨���ꂪ�������łȂ��A�����������߂Ƃ���H�Ə��L���̖@�I���萫�ɋ^�O��������A���̌����̎Љ�I���l��ʑ����A�Ђ��ẮA�H�Ə��L�����x�̌��S�ȉ^�c�Ɣ��W��j�Q����Ɏ��邨���ꂪ����Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�ٗ��m�����̎����K�͂Ƃ��Đ��肵���ٗ��m��Q�U�����O�������ҊԂɑ������Ȃ����e�̋K����߁A�u�o��l���n�����҃m�㗝�l�g�V�e�戵�q�^���������U���X���҃m�㗝�l�g�ׁv��s�ׂ���Ɏ��グ�āA�u�ٗ��m�@�攪���m���_�j���߃X���s�ׁv��B��Ꭶ����s�ׂƂ��ċ����A�܂��A�O�f�b��V���ɂ��A�u�ٗ��m�ϗ��v�Q�P�����A�ٗ��m�Ƃ��ċ֎~�����ׂ��s�ׂƂ��āA��L�s�ׂ��u������̑㗝�l�Ƃ��Ď�舵������������C�v����s�ׂƕ��������ċK�肵�Ă��邱�Ƃ��F�߂���B���̂��Ƃ��炷��A����������̂��̂ł������A���̌��������n���̑��̌����ɂ��ړ]�������҂��ς�����Ƃ��Ă��A��L�s�ׂ́A�ٗ��m��ʂ̐M�p�����Ă����A�H�Ə��L�����x�̌��S�ȉ^�c�A���B��j�Q����Ɏ���d��ȐE�Ɨϗ��ᔽ�s�ׂƔF������A���̂悤�ȍs�ׂ�ٗ��m�̋Ɩ��Ƃ��čs�����Ƃ��ł��֎~����@�K�͂��ٗ��m�@�̉��Ŋm�����Ă�����̂Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�ȏ�̍l�@�ɏ]���A�ٗ��m�@�W���P���̋K��́A��L�s�ׂ��܂߂��Ӗ��ɂ����ċK�肳��Ă�����̂Ɖ��߂���̂������ł���B���������āA�O�������W�̉��ŁA�a�ٗ��m���퍐�̑㗝�l�Ƃ��āA�{�������̖����R���𐿋������s�ׂ́A���K��Ɉᔽ����s�ׂƂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
���������Ɋ�Â��N�Q���~�������T�i����(�u�n�ڗp�Z���~�b�N�G���h�^�u�v����)
| �����ԍ� | �@����15�N(�l)��1901�� |
|---|---|
| ������ | �@���������Ɋ�Â��N�Q���~�������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����15�N10��29�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�S�@���_�T�i��T�i�l�̑��Q���j�ɂ���
(1)�@�����@�P�O�Q���P���̈Ӌ`
�@�{���ɂ������T�i�l�̑��Q���������́A���p�V�Ė@�Q�X���P���y�ѓ����@�P�O�Q���P���Ɋ�Â����̂ł���B�ȉ��A�����@�P�O�Q���P���ɂ��K��̎�|���������邪�A����������e�͎��p�V�Ė@�Q�X���P���ɂ��Ă����l�ł���B
�A�@�����@�P�O�Q���P���́A�r���I�Ɛ茠�Ƃ����������̖{���Ɋ�Â��A��������N�Q���鐻�i�i�ȉ��u�N�Q�i�v�Ƃ������Ƃ�����B�j�Ɠ������҂̐��i�i�ȉ��u�����Ґ��i�v�Ƃ������Ƃ�����B�j���s��ɂ����ĕ⊮�W�ɗ��Ƃ����[���̉��ɐ݂���ꂽ�K��Ƃ����ׂ��ł���B���Ȃ킿�A���������������́A�Z�p��Ɛ�I�Ɏ��{���錠���ł��邩��A���Y�Z�p�𗘗p�������i�͓������҂����̔��ł��Ȃ��͂��ł����āA���������̎��{�i�͎s��ɂ����đ�����������̂Ƃ��ĂƂ炦����ׂ��ł���A���̂悤�ȍl�����Ɋ�Â��A�N�Q�i�ƌ����Ґ��i�Ƃ͎s��ɂ����ĕ⊮�W�ɗ��Ƃ����[���̉��ɁA�����݂͐���ꂽ���̂ł���B
�@���̂悤�ȑO��̉��ɂ����ẮA�N�Q�i�̔̔��ɂ�鑹�Q�́A�������҂̎s��@��̑r���Ƃ��ĂƂ炦����ׂ����̂ł���A�N�Q�i�̔̔��́A���Y�̔����ɂ�����������҂̎s��@��ڒD�������łȂ��A�w���҂̉��ɂ����ĐN�Q�i�̎g�p�����p������邱�Ƃɂ��A�������҂̂���ȍ~�̎s��@������r����������̂ł���B
�@���������āA�����ɂ����u���{�̔\�́v�ɂ��ẮA�����N�Q�i�̔̔����Ɍ����ɑΉ����鎞���ɂ������̓I�Ȑ����\�́A�̔��\�͂ł͂Ȃ��A�������҂ɂ����āA���Z�@�֓�����Z�����Đݔ��������s���Ȃǂ��āA���Y�������̑������ԓ��Ɉ��ʂ̐��i�̐����A�̔����s�����ݓI�\�͂�����Ă���ꍇ�ɂ́A�����Ƃ��āA�u���{�̔\�́v��L������̂Ɖ�����̂������ł���B
�C�@���ɁA�����ɂ����u�N�Q�̍s�ׂ��Ȃ���Δ̔����邱�Ƃ��ł������v�Ƃ́A�N�Q�ɌW������������{������̂ł����āA�N�Q�i�Ǝs��ɂ����Ĕr���I�ȊW�ɗ����i���Ӗ�������̂ł���B
�@�؋��i�b�P�T�A�b�R�P���j�ɂ��A��T�i�l�́A�{�����p�V�Č��̎��{�i�Ƃ��āA�C�����i�̎O�̌^���ɑΉ�����`��E�傫���̊e���i�R��ށA�n�����i�ɑΉ�����`��E�傫���̐��i�A�{���������P�̎��{�i�Ƃ��āA�j���Ȃ����`�����i�ɑΉ�����`��E�傫���̊e���i���A���ꂼ�ꐻ���E�̔����Ă���A�������̐��i�ɂ��ẮA��T�i�l�ƍT�i�l�Ō^���ԍ��܂œ����ł��邱�Ƃ��F�߂���B��������ƁA�C���A�n���Ȃ����`�����i�ɂ��ẮA�������ʎ��u�������i�̔����i���ꗗ�\�v�i�����y�уk�����i�Ɋւ��镔���������B�ȉ������B�j�L�ڂ̊e��T�i�l���i�������āu�N�Q�̍s�ׂ��Ȃ���Δ̔����邱�Ƃ��ł������v�ƔF�߂�̂������ł���B
�@���̓_�Ɋւ��āA�T�i�l�́A�������i�ɂ��ẮA��T�i�l������ɑΉ����鐻�i��̔����Ă��Ȃ�����A�����@�P�O�Q���P���̓K�p���Ȃ��|���咣����B�������Ȃ���A�C���Ȃ����n�����i�́A�{���l�Ă̋Z�p�I�͈͂ɑ�������̂ł����āA�����̊Ԃɂ͋�̓I�Ȍ`�Ԃɂ����Ⴊ����Ƃ͂����A�{���l�Ă̎��{��̊Ԃł̑ԗl�̍��قɂ����Ȃ����̂ł���B�����āA�������i���A�����̃X���b�g�ɉ����ĕ������邱�ƂŁA�Q�̐��i�Ƃ��Ďg�p����邱�Ƃ��\�肳��Ă�����̂ł��邱�ƂɏƂ点�A�������i�ɑΉ������T�i�l���i�Ƃ��ẮA���̌`��E�傫����������̃������i�ɍł��ގ�����C�����i(1)�̑Ή��i�̂Q���Ƃ���̂������ł���B���������āA�������i�ɂ��Ă��A�������ʎ��u�������i�̔����i���ꗗ�\�v�L�ڂ̔�T�i�l���i�i�C�����i(1)�̑Ή��i�̂Q���j�������āu�N�Q�̍s�ׂ��Ȃ���Δ̔����邱�Ƃ��ł������v�ƔF�߂�̂������ł���B
�E�@��L�̂Ƃ���A�u���{�̔\�́v���A�K�������N�Q�i�̔����Ɍ����ɑΉ����鎞���ɂ������̓I�Ȑ����̔��\�͂��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�N�Q�i�̔̔��ɂ��e�����錠���Ґ��i�̔̔����A�N�Q�i�̔����ɑΉ����鎞���ɂ�������̂ɂƂǂ܂�Ȃ����ƂɏƂ点�A�����ɂ����u�N�Q�̍s�ׂ��Ȃ���Δ̔����邱�Ƃ��ł������̒P�ʐ��ʓ�����̗��v�̊z�v�ɂ��Ă��A�N�Q�i�̔̔����Ɍ����ɑΉ����鎞���ɂ������̓I�ȗ��v�̊z���Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�N�Q�i�̔̔��ɂ��e������̔�������ʂ��Ă̕��ϓI�ȗ��v�z�Ɖ�����̂������ł���A�܂��A�u�P�ʐ��ʓ�����̗��v�̊z�v�́A���ɓ������҂ɂ����ĐN�Q�i�̔̔����ʂɑΉ����鐔�ʂ̌����Ґ��i��lj��I�ɐ����̔������Ƃ���A���Y�lj��I�����̔��ɂ�蓾��ꂽ�ł��낤���v�̒P�ʐ��ʓ�����̊z�i���Ȃ킿�A�lj��I�����̔��ɂ�蓾��ꂽ�ł��낤����z����lj��I�ɐ����̔����邽�߂ɗv�����ł��낤�lj��I��p�i��p�̑������j���T�������z���A�lj��I�����̔����ʂŏ������P�ʐ��ʓ�����̊z�j�Ɖ����ׂ��ł���B���̂悤�ɓ����@�P�O�Q���P���ɂ����u�P�ʐ��ʓ�����̗��v�̊z�v������I�ȋ��z�ł��邱�Ƃ��l������ƁA���̋��z�́A�����ɎZ��ł�����̂ł͂Ȃ��A������x�̊T�Z�z�Ƃ��ĎZ�肳��鐫���̂��̂Ɖ�����̂������ł���B
�@��̓I�Ȏ��Ăɂ����āA�������҂��N�Q�i�̔̔����Ɍ����ɑΉ����鎞���ɂ����Č����Ɍ����Ґ��i�̐����̔����s���Ă���ꍇ�ɂ́A���Y�����ɂ����錠���Ґ��i�̒P�ʐ��ʓ�����̌����̗��v�z��Ύނ��āA�����@�P�O�Q���P���ɂ����u�P�ʐ��ʓ�����̗��v�̊z�v���Z�肷�邱�Ƃ������ł��邪�A���̏ꍇ�ɂ����Ă��A���̗��v�z����L�̂悤�Ȑ�����L���鉼��I�ȋ��z�ł��邱�ƂɏƂ点�A�u�P�ʐ��ʓ�����̗��v�̊z�v�́A�K�������A���Y�����ɂ����錻���̗��v�z�ƈ�v������̂ł͂Ȃ��A�����̗��v�z�́A�����ɂ����u�P�ʐ��ʓ�����̗��v�̊z�v��F�肷���ł̈ꉞ�̖ڈ��ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
| �����ԍ� | �@����11�N(��)��19329�� |
|---|---|
| ������ | �@���������Ɋ�Â��N�Q���~���������� |
| �ٔ��N���� | �@����15�N02��27�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
���R�����f�[�^�F�@�@PAT-H11-wa-19329.pdf�@�@PAT-H11-wa-19329-1.pdf
�������N�Q���~�������T�i����(�u�֎q���G�A�[�}�b�T�[�W�@�v����)
�������o�蓖���̌��m�Z�p���ɏƂ炵�A���Y�Ώې��i�ɌW��\����e�Ղɑz���������ɂ�������炸�A���̂悤�ȍ\������������͈̔͂Ɋ܂߂Ȃ������Ƃ��������ł́A���Y�Ώې��i�ɌW��\������������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O�����Ƃ������Ƃ͂ł����A�ϓ��N�Q�̐�����F�肵���B��
| �����ԍ� | �@����17�N(�l)��10047�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����18�N09��25�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�������Ȃ���A�����N�Q���咣����Ă���Ώې��i�ɌW��\�����A�����o��葱�ɂ����ē��������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���ꂽ�Ƃ����ɂ́A�������҂��A�o��葱�ɂ����āA���Y�Ώې��i�ɌW��\�������������͈̔͂Ɋ܂܂�Ȃ����Ƃ����F���A���邢�͕������ɂ�蓖�Y�\������������͈̔͂��珜�O����ȂǁA���Y�Ώې��i�ɌW��\���m�ɔF�����A�������������͈̔͂��珜�O�����ƊO�`�I�ɕ]��������s�����Ƃ��Ă��邱�Ƃ�v����Ɖ����ׂ��ł���A�����o�蓖���̌��m�Z�p���ɏƂ炵�A���Y�Ώې��i�ɌW��\����e�Ղɑz���������ɂ�������炸�A���̂悤�ȍ\������������͈̔͂Ɋ܂߂Ȃ������Ƃ��������ł́A���Y�Ώې��i�ɌW��\������������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@��������ƁA�T�i�l�̎咣����悤�ɁA�{�������T�̏o�蓖���A�}�b�T�[�W�@�̋r�ɒ��ԕǂ�݂��邱�Ƃ�A�g�̂̊e���Ƃ̐ڐG���ɘa����ޗ��Ƃ��ă`�b�v�E���^�������̗p���邱�Ƃ����m�̋Z�p�ł���A��T�i�l���A���̓����o��葱�ɂ����āA�r�ڒu���̑��ǂ̈���ɋ�C�܂�z�݂��A�����Ƀ`�b�v�E���^������z�݂���\������������͈̔͂Ɋ܂߂邱�Ƃ��\�ł������Ƃ��Ă��A���̂��Ƃ��璼���ɁA���̂悤�ȍ\�����{�������T�ɌW����������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���ꂽ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�{���ɂ����ẮA�{�������T�̓������҂ł����T�i�l���A�����o��葱�ɂ����āA�r�ڒu���̑��ǂ̈���݂̂ɋ�C�܂�z�݂��A�����Ƀ`�b�v�E���^������z�݂���\�����̗p���Ă��{�������T�̖ړI����ʂ�B���ł��邱�Ƃm�ɔF�����A��������Ƃ���ɏ��O�����ƕ]��������s�����Ƃ����ƔF�߂�ɑ���؋��͂Ȃ��B
�@���������āA�T�i�l�̎咣�͍̗p�ł��Ȃ��B
(2) �ϓ��N�Q�ɂ��Ă̌��_
�@�ȏ�ɂ��A�T�i�l���i�R�A�S�̋r�ڒu���̈���̑��ǂ̋�C�܂��`�b�v�E���^�����ɒu�������Ƃ��Ă��A���e���i�̍\���͖{�������T�Ƌϓ��Ȃ��̂Ƃ��āA�{�������T�̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ƃ������Ƃ��ł���B
(����)
4-2 �����@�P�O�Q���R���Ɋ�Â��咣
(1) ��T�i�l�́A�\���I�ɁA�����@�P�O�Q���R���̎��{�������z�i���i������T���j�Q�Ƃ��Ď咣���邪�A�O�L�̂Ƃ���A�{�������T�́A�֎q���}�b�T�[�W�@�̈ꕔ�̓��샂�[�h���I�����ꂽ�ꍇ�ɏ��߂Ă��̍�p���������A���ʎ��̂��t���I�Ȃ��̂ɂƂǂ܂邱�Ƃ�A�{�������T�̋@�\������Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A�r����K���̃}�b�T�[�W���͍̂s�����Ƃ��ł��A�T�i�l���i�̔̔��ւ̉e���͏��Ȃ��ƍl�����邱�ƁA����ɂ͑O�L�����̎���𑍍�����ƁA���{�������z�������@�P�O�Q���P���Ɋ�Â��ĔF�߂����L���Q�z����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(2) ��T�i�l�́A���ɁA�����i�̑��݂��l�����ē����@�P�O�Q���P������������K�p�����Ƃ��Ă��A��T�i�l�ɂ���Ĕ̔��ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ���i�X�X���j�ɂ��ẮA�����@�P�O�Q���R���̎��{�������z�Ƃ��Ĕ̔��z�̂T�������Q�Ƃ��ĔF�߂���ׂ��ł���Ǝ咣����B
�@�������Ȃ���A�����@�P�O�Q���P���́A�����N�Q�ɓ�������{�s�ׂ��Ȃ��������Ƃ�O��Ɉ편���v���Z�肷��̂ɑ��A�����@�P�O�Q���R���͓��Y���������̎��{�ɑ���ׂ����{�������z�Q�Ƃ�����̂ł��邩��A���ꂼ�ꂪ�O����قɂ���ʌ̑��Q�Z����@�Ƃ����ׂ��ł���A�܂��A�������҂ɂ���Ĕ̔��ł��Ȃ��Ƃ��ꂽ���ɂ��Ă܂ŁA���{�������z�𐿋�������Ɖ�����ƁA�������҂��N�Q�s�ׂɑ��鑹�Q�����Ƃ��Ė{������������편���v�͈̔͂��āA���Q�̓U����邱�Ƃ�e�F���邱�ƂɂȂ邪�A���̂悤�ɓ������҂̈편���v�������Q�̓U���F�߂�ׂ������I�ȗ��R�͌��o����B
�@���������āA��T�i�l�̎咣�͍̗p�ł��Ȃ��B
�������N�Q���~����������(�u�|�b�g�J�b�^�[�v����)
| �����ԍ� | ����13�N(��)��9922�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~���������� |
| �ٔ��N���� | �@����14�N12��26�� |
| �ٔ����� | �@���n���ٔ��� |
��Q�@���Ă̊T�v
�@�{���́A�u��c�|�b�g�̕�������y�ѕ������@�v�Ƃ������������ɌW���������L���錴�����A�퍐�ɑ��A�퍐�́A�@�ʎ��C�������ژ^(1)�y��(2)�L�ڂ̃|�b�g�J�b�^�[�����A�A��������ݗ^���ꂽ�|�b�g�J�b�^�[�����E�퍐�Ԃ̒��ݎ،_��ɐ݂���ꂽ�����ɔ����Č����ȊO�̐����ɌW��A����c�|�b�g�̐藣�����Ɏg�p�������A��L�e�s�ׂ͂�����������̓������̐N�Q�ɓ�����Ƃ��āA�������Ɋ�Â��A�|�b�g�J�b�^�[�̐����A�g�p�̍��~�ߋy�єp�����тɑ��Q�����𐿋��������Ăł���B
�i�����j
�Q�@���_(2)�i�퍐���{���֎~�����Ɉᔽ���āA�{���|�b�g�J�b�^�[�𑼎А��A����c�|�b�g���Ɏg�p���邱�Ƃ��A�{���������̐N�Q���\�����邩�j�ɂ���
(1)�@��L��Q�A�P(4)�ɂ��A�{���ݗ^�_��́A�{���|�b�g�J�b�^�[�Ƃ������Y�̒��ݎ،_��̌`�����̗p���Ă���B�������A���̓��e�́A�������퍐�ɑ��A�{�������̎��{�i�ł���{���|�b�g�J�b�^�[�̐�L��L���ňړ]���A�����A����c�|�b�g�̕����Ƃ����{�������̖ړI��B������悤�ȕ��@�Ŏg�p���邱�Ƃ�F�߂�Ƃ������̂ł���A����́A�{�������ɂ��Ă̓����o��l�ł��錴������c�Ǝ҂ł���퍐�ɑ��A�{���������ƂƂ��Ď��{���邱�Ƃ����{�̑ԗl�Ƃ��Ďg�p�i�����@�Q���R���j�݂̂Ɍ��肵����ŋ������邱�ƂƎ����I�ɓ��`�Ƃ�����B�����āA�������퍐�ȊO�̈�c�ƎҐ��ЂƂ̊Ԃł��A�{���ݗ^�_��Ɠ��l�̃|�b�g�J�b�^�[���ݎ،_����d���I�ɒ������Ă��邱�Ɓi�b�P�V�`�Q�O�j���l������ƁA�{���ݗ^�_��́A���E�퍐�Ԃɂ�����ʏ���{���i���@�V�W���P���j�̐ݒ�s�ׂƂ���������L���A�����́A�{���ݗ^�_��Ɋ�Â��A�퍐�ɑ��A�{���������������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�{���������ɂ��āA���{�̑ԗl���g�p�Ɍ��肵����Œʏ���{���i�ȉ��A���̒ʏ���{�����u�{���ʏ���{���v�Ƃ����B�j���������邱�Ƃ�����̂Ɖ�����̂������ł���i�{���ݗ^�_�{���������̎��{�����̐�����L���邱�Ƃ́A�����ґo�����F�߂�Ƃ���ł���B�j�B
(2)�@�����@�́A�ݒ�s�ׂŔ͈͂��߂邱�Ƃɂ��A�������̈ꕔ�ɐ������Ēʏ���{�����������邱�Ƃ��ł���|�K�肷��ƂƂ��Ɂi�����@�V�W���Q���j�A�ʏ���{���́A���̓o�^�������Ƃ��ɂ́A���̓������Ⴕ���͐�p���{�����͂��̓������ɂ��Ă̐�p���{�������̌�Ɏ擾�����҂ɑ��Ă��A���̌��͂���ƋK�肵�Ă���i�����@�X�X���P���j����A�������̈ꕔ�ɐ������Ēʏ���{�������������ꍇ���A���̓��e���o�^���ꂽ�Ƃ��́A���l�̌��͂���Ɖ������B�����A�ʏ���{���̖@�I�����́A�����҂ł���������Җ��͐�p���{���҂ƒʏ���{���҂Ƃ̊Ԃɂ�����A�������Җ��͐�p���{���҂��獷�~�������⑹�Q�����������̍s�g���Ȃ����Ƃ�{���I���e�Ƃ�����W�ł����āA���̋�̓I���e�͓����ҊԂ̌_��ɂ�茈�肳���B�ʏ���{���̋����ɓ����肢���Ȃ鐧�����t����邩�́A���Y���������̏d�v���E���l�̂ق��A�������ҋy�ђʏ���{���҂̋Z�p�E�s��ɂ����Đ�߂�n�ʁA���{���҂̐��E���{�\�͂ȂǁA�s��̏܂�����X�̗v���ɉ����ė������҂̈Ӑ}�ɂ��_�Ɍ��肳��A�����i���ԓI�A�ꏊ�I�A���e�I�j�̋�̓I���e�E���x�E���Ԃɂ��A���i�Ȃ��̂���ɂ₩�Ȃ��̂܂ōL�͂ȑԗl�����݂���B���̂悤�ɁA�@�I�ɂ͋����҂ƒʏ���{���҂Ƃ̊Ԃ̍��W�ɂ������A�����ɂ��L�͂ȑԗl�̂��̂����݂���ʏ���{���̋����̐����ɂ��āA���̂��ׂĂ̈ᔽ�s�ׂ������I�����Ƃ��Ă̓������̐N�Q���\�����A�������҂��獷�~�������i�����@�P�O�O���j�y�ё��Q�����������i���@�V�O�X���j���s�g�����ƂƂ��ɁA�Y�����i�����@�P�X�U���j�ɂ�鐧�ق̑ΏۂƂȂ蓾��Ɖ�����̂͑����łȂ��B
(3)�@�Ƃ���ŁA�����@�́A��p���{���i�����@�V�V���j�̐ݒ�ɂ��āA�o�^�����͔����v���ƒ�߂Ă���i�����@�X�W���P���Q���j�A��p���{���̐ݒ�̓o�^��\������Ƃ��́A�\�����ɐݒ肷�ׂ���p���{���͈̔͂��L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�����o�^�߂S�S���P���P���j�B���������āA��p���{���̐ݒ�ɍۂ��ĕt���ꂽ�͈͂̐����́A���ꂪ�o�^���ꂽ�ꍇ�ɂ͐�p���{���̓��e�Ƃ��Č��͂��A���͈͓̔��ł͓������҂̌�����������������A���̐����Ɉᔽ����s�ׂ͓������̐N�Q�ƂȂ�i�����@�P�O�O���j�B����ɑ��A��p���{���̐ݒ�ɍۂ��ĕt���ꂽ�����̂����o�^����Ă��Ȃ������Ɉᔽ�����ꍇ�̌��ʂɂ��āA�����@�͋K�肵�Ă��Ȃ��B�ʏ���{���ɂ��Ă����l�ł���B
�@��������ƁA�ʏ���{���҂��ʏ���{���̋����ɕt���ꂽ�����Ɉᔽ���邱�Ƃ��������N�Q���\�����邩�ۂ��f����ɓ������ẮA�ʏ���{���̋����ɂ��̂悤�Ȑ�����t���A���A���Y���������炳����s�ׂ��A�����@�ɋK�肳�ꂽ�����̖{���I�ȍs�g�i�ȉ��u�{���I�s�g�v�Ƃ����B�j�ƕ]���ł��邩�ۂ��Ƃ����ϓ_���猟������Ȃ���Ȃ炸�A�{���I�s�g�ɓ�����Ȃ�������t�����Ɓi�ȉ��u��{���I�s�g�v�Ƃ����B�j�ɂ��ẮA�����@�ɂ�錠���̍s�g�Ƃ݂͂�ꂸ�A���I�����Ɉς˂��A���̈ᔽ���_���̍��s���s���\������ɂ����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����ŁA�����@��A�������y�ђʏ���{���������Ȃ鐫���̌����Ƃ��ċK�肳��Ă��邩��������x�̎�|�ɏƂ炵�Ĕ��f����B�����@�́A�u�����̕ی�y�ї��p��}�邱�Ƃɂ��A���������サ�A�����ĎY�Ƃ̔��B�Ɋ�^���邱�Ɓv��ړI�Ƃ�����̂ł���i���@�P���j�B�����āA�����@�U�W��{���́A�u�������҂́A�ƂƂ��ē��������̎��{�����錠�����L����B�v�ƋK�肷�邪�A�ΏۂƂȂ锭���́A�{���Ɛ�I�ɐ�L���邱�Ƃ��ϔO�ł��Ȃ��Z�p�I���ł��邩��A�u���������̎��{�����錠�����L����v�Ƃ́A���ǁA���l�ɂ�閳�����ł̎��{��r�����邱�Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��B��������A�������Ƃ́A���������̋Z�p�I�͈͂ɕ�܂���镨�̐��Y�A�g�p�A���n�����͕��@�̎g�p���i�����@�Q���R���j����A�������҂����l��r��������Ƃ��������ɑ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B��������ƁA�������҂��ʏ���{���̋������s���ꍇ�ɂ����āA�����ɕt���ꂽ�����̒��ŁA�������̖{���I�s�g�Ƃ��ĕ����I���͂�L���A���̐����Ɉᔽ���邱�Ƃ��������N�Q���\��������̂Ƃ����̂́A�O�L�̓����@�̖ړI�ɂ��Ƃ炵�āA�����@���������҂ɕۏႷ����������̖��f���{���̂̋֎~�Ƃ������͂ɒ��ڊւ��A���Y���͂��������邽�߂ɕK�v�Ȕ͈͂̍s�ׂɌ�����Ƃ����ׂ��ł���B����ɑ��A���{�����ɕt���ꂽ�������A���������̎��{�s�ׂƒ��ڊւ�肪�Ȃ��A���f���{�̋֎~�����������邽�߂ɕK�v�Ȕ͈͂�����̂ƕ]�������ꍇ�ɂ́A���̂悤�Ȑ����́A���̓������̌��͂Ƃ��ē����@��F�߂�ꂽ�͈͂�����̂Ƃ��āA���͂�������̖{���I�s�g�i�����I�����j�ɂ͊Y�������A�P�Ȃ�_���̐����i���I�����j�ɂƂǂ܂�Ɖ�����̂������ł���B
(4)�@�����ŁA�ȏ�̐����Ɋ�Â��A�{���֎~�����ɂ���Ė{���ʏ���{���ɕt���ꂽ�������{���������̖{���I�s�g�ɓ����邩�ǂ����ɂ��Č�������B
�@�{���ݗ^�_��́A�������퍐�ɑ��A�i�{�����������ݒ�o�^�ɂ�蔭�������ꍇ�Ɂj���{�̑ԗl���g�p�i�����@�Q���R���j�݂̂Ɍ��肵�Ēʏ���{������������|�̒ʏ���{���ݒ�s�ׂƉ�����邪�i�O�L(1)�j�A�{���֎~�����́A�{���ʏ���{���̋����ɑ��A����ɁA�u�{�������̎g�p�ړI�i�p�r�j���A�ʌ��������ɌW�锭���̎��{�i�ł��錴���|�b�g�̐藣���Ɍ��肵�A����ȊO�̖ړI�A���Ȃ킿�A�����|�b�g�ȊO�̑��А��A����c�|�b�g�̐藣�����Ɏg�p���邱�Ƃ��֎~����v�Ƃ������e�I�Ȑ�����t�����̂Ɖ����邱�Ƃ��ł���B
�@�������A�{���������ɂ��������҂ł��錴���ɕۏႳ�ꂽ���͂́A���l���������Ŗ{�������ɌW��u��c�|�b�g�̕�������y�ѕ������@�v��A����c�|�b�g�̕����Ƃ����{�������̖ړI��B������悤�ȕ��@�Ŏg�p���邱�Ƃ�r������Ƃ������f���{�֎~�̌��͂ɒ��ڊւ��A���̖ړI����������̂ɕK�v�Ȕ͈͂ɂƂǂ܂�̂ł���B�{���֎~�����̂悤�ɁA�������҂�����{�͈͂��g�p�Ɍ��肵�Ď��{���������ʏ���{���҂����������ɌW�镨���g�p����ɍۂ��A�������҂̋��Ǝ҂̐��i�ւ̎g�p�ɋ����邱�Ƃ�r�����邱�Ƃ́A�������҂��ʏ���{���҂ɑ��āA�����i�̎g�p�����͋����Z�p�̗̍p�̐����A�Ⴕ���͌��ޗ��A���i���̍w����̐������ۂ����Ƃƌa�낪�Ȃ��A���ꎩ�̂́A���������̎��{�s�ׂɊւ��邱�Ƃł͂��邯��ǂ��A���{�̋敪�A���ԁA�n��A�Z�p���쓙�𐧌�������̂Ƃ͈قȂ�A�������҂��{�����茠��L���Ȃ��A���������̎��{�Ƃ͖��W�̐������ۂ����̂ł��邩��A�������x�̖ړI�ɏƂ炵�Ă��A�������̖{���I���͂��������邽�߂ɕK�v�Ȕ͈͂�����̂Ƃ����ׂ��ł���i��������ψ�������Ǖ����P�P�N�V�����\�́u�����E�m�E�n�E���C�Z���X�_��Ɋւ���Ɛ�֎~�@��̎w�j�v�k���Q�l���Q�Ɓj�B
�@�܂��A�{���ݗ^�_��́A���Ƃ��ƌ����|�b�g�̔̑��i�Ƃ��Ė{���|�b�g�J�b�^�[���������ڋq�ł���퍐�ɋ��^���邽�߂ɒ������ꂽ���̂ł��邪�A�{���|�b�g�J�b�^�[����������Օi�ł���A�퍐�������ɕԊ҂������_�ł́A��������R�N�T�����ɂ킽��g�p�ɂ��j�����Ă������Ɓi�b�X�j�A�{���ݗ^�_��Œ�߂�ꂽ�g�p���͂P��X�W�O�O�~���͂P���S�O�O�O�~�A�_����Ԃ��R�N�Ԃł���A���Ԃ̕ύX�i���Ԍo�ߌ�̍X�V�j���\�肳��Ă��邱�Ɓi��L��Q�A�P(4)�C�j���炷��A�{���ݗ^�_��̎����͔����ƕς��Ƃ��낪�Ȃ��A�������{���|�b�g�J�b�^�[�̔����Ƃ����ʏ�l������@�`���i�����ł���A�������͏��s���A�w���҂��w����̎g�p�ړI��������҂��琧��邢���͂Ȃ��B�j���̂炸�ɒ��ݎƂ����@�`�����̂�����Ŗ{���֎~������݂�����|�́A�����I�ɂ́A�퍐�ɕʌ��������ɌW�锭���̎��{�i�ł��錴���|�b�g�̍w���𑣂��ړI�ɂ����̂ł���ƔF�߂���B�������A��c�Ǝ҂��ǂ̂悤�ȘA����c�|�b�g��N����w�����邩�Ƃ����w�����i�y�юd����̑I���́A�{���A��c�ƎҎ��g�̌���Ɉς˂���ׂ������ł���A���Ђ̋����i���ʌ��������̐N�Q�i�ɓ�����Ƃ����悤�ȏꍇ�łȂ�����A�����ɂ���𐧖錠���͂Ȃ��B���̈Ӗ�������A�{���֎~�����ɂ�鐧���́A���f���{���̂̋֎~�Ƃ����{���������̖{���I���͂��������邽�߂ɕK�v�Ȕ͈͂̍s�ׂƂ͂����Ȃ��B
�@��������ƁA�{���֎~�����ɂ��ʏ���{���̋����ɐ�����t�����Ƃ́A�{���������̌��͂Ƃ��ē����@��F�߂�ꂽ�͈͂�����̂Ƃ��ē������̖{���I�s�g�ɊY�������A�P�Ȃ�_���̐����ɂƂǂ܂���̂Ɖ�����̂������ł���B
(5)�@�ȏ�ɂ��A�퍐���{���֎~�����Ɉᔽ���Ė{���|�b�g�J�b�^�[�𑼎А��A����c�|�b�g�̐ؒf�Ɏg�p�������Ɓi�����́A�����P�R�N�W���Q�Q���t�����e�ؖ��X�ւɂ��A�퍐���{���֎~�����Ɉᔽ���Ė{���|�b�g�J�b�^�[�𓌊C�|�b�g�̕�����ƂɎg�p�������Ƃ𗝗R�ɖ{���ݗ^�_��̉�����\�������ƂƂ��ɁA�{���|�b�g�J�b�^�[�̕Ԋ҂𐿋����A�퍐�͓����Q�W���ɖ{���|�b�g�J�b�^�[��Ԋ҂��Ă���i�O�L��Q�A�P(7)�A(8)�j����A����܂ł͖{���ݗ^�_�����������̂ł���i�{���ݗ^�_���T���j�Ƃ���A��L�\�����ɔ퍐���{���|�b�g�J�b�^�[���g�p�������Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B�j�́A�{���ݗ^�_���̍��s���s���\������ɂƂǂ܂�A�{���������̐N�Q�ɂ͓�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���i�Ȃ��A�����́A�����P�S�N�X���Q�V���̑�V��٘_�����葱�����ɂ����āA�{���̑i�ו��͓������N�Q�Ɋ�Â����~�����Ƒ��Q���������݂̂ł���ƒq���Ă���B�j�B
�R�@����āA�����̐����́A���̗]�̑��_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ����R���Ȃ�����A�啶�̂Ƃ��蔻������B
�Z�t�W�j���̂`�^��������
���T�i���p���A�������N�Q��F�肵�����������ێ��B���������ɂ�����J���ƁA��ɂ��ꂽ�V�K�����^�ɌW�锭���̓������B��
| �����ԍ� | �@����19�N(�l)��10034�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�����T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����19�N09��10�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�������́A�@�퍐���܂͖{�����������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����A�A�{�������͓��������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��A�ƔF�蔻�f���A�����̐�����F�e�����B
(����)
�i�퍐�̎咣�j
�@�{�������́u�������������悤�Ƃ�����_�v�̋L�ڂ͎����ɔ�������̂ł���A���p���{��P�S�y�тP�U�œ���ꂽ���̂́A�����ł������ƍl������Ȃ��B���p���{��P�S�y�тP�U�́A����ꂽ�������`�^�������a�^�������͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ����A�a�^�����Ƃ`�^�����Ƃ́A���������ۂ��Ƃ����_�����Ⴗ�邾���ŁA���i�̌��̂Ƃ��Ă̗L�p���A�������@�ɂ����ĂقƂ�Ǒ��Ⴗ��_�͂Ȃ�����i�b�Q�P�j�A���Ǝ҂ł���A�a�^�����邱�Ƃ��ł���A�`�^�����邱�Ƃ͋ɂ߂ėe�Ղł���B
�@�����̎���ɏƂ点�A�����́A���p�����ɌW������o��ɂ��ē������擾������A�������Ƃ͕ʌ̌����������擾���悤�Ƃ̍l������A���p���{��P�S�y�тP�U�œ�������̂������ł͂Ȃ��A�������ł���Ƃ̎����ɔ�����L�ڂ������Ɛ��F�����B
�i�ٔ����̔��f�j
�@�@�퍐���܂͖{�����������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ƃ̌����̎咣�͗��R������A�A�{�������͓��������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ��ł��铙�̔퍐�̎咣�͂�����������ł���B
�i�����j
�@�O�L�E�̂Ƃ���A�퍐���̒ǎ��ɂ���Ă͈��p���{��P�U�̎����H���𒉎��ɍČ����Ă��Z�t�W�j���̂`�^�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�����Ƃ��A�O�L�G�̂Ƃ���A�������̒ǎ����A���p���{��P�U�𒉎��ɍČ��������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ����A���̂��Ƃ������āA�퍐���̒ǎ��������ȍČ��łȂ������Ƃ̏�L�F�蔻�f�ɉe�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��B
�@����āA�{���������̗D�挠�咣�������̋Z�p�펯���Q�ނ���ƁA���Ǝ҂ɂ����ď�L���{��̋L�ڂ�ǎ����Ă��Z�t�W�j���̂`�^���������邱�Ƃ͂ł����A���������āA��L���{��ɂ����ẮA���Ǝ҂ɂ����ėe�ՂɎ��{��������x�ɃZ�t�W�j���̂`�^�����̐������@���J������Ă���Ƃ͂����Ȃ��B
�@��������ƁA�{�����������́A���̗D�挠�咣���O�ɔЕz���ꂽ���s�����̈��p���{��P�U�̋L�ړ��e����e�ՂɎ��{���邱�Ƃ��ł���Ƃ͂������A���̂��Ƃ𗝗R�Ƃ���퍐�̎咣�́A���R���Ȃ��B
�������Ɋ�Â������̔��֎~�����������@(�u�i�C�t�̉��H���u�v����)
�����R�́A�{�������O�̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��āA��T�����ɌW������ɂ͓����@�Q�X���Q���ᔽ�̖������R�����݂���|�̔��f�����āA��㍐�l��̓��@�P�O�S���̂R��P���̋K��Ɋ�Â��咣��F�߁A�㍐�l�̐��������p�������̂ł���A�������ɂ����ẮA�{��������̓��������͈̔͂�O��Ƃ���{�������ɌW�閳�����R�̑��ۂɂ��ċ�̓I�Ȍ���������Ă���킯�ł͂Ȃ����A�{���ɂ����ď㍐�l���{�������R�����m�肵�����Ƃ𗝗R�Ɍ��R�̔��f�𑈂����Ƃ́A�㍐�l�Ɣ�㍐�l��Ƃ̊Ԃ̖{���������̐N�Q�ɌW�镴���̉�����s���ɒx����������̂ł���A�����@�P�O�S���̂R�̋K��̎�|�ɏƂ炵�ċ�����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B��
| �����ԍ� | �@����18�N(��)��1772�� |
|---|---|
| ������ | �@�������Ɋ�Â������̔��֎~���������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N04��24�� |
| �@�얼 | �@�ō��ٔ�����ꏬ�@�� |
�@�@�@�@�@�@�@�@��@�@��
�@�@�@�@�{���㍐�����p����B
�@�@�@�@�㍐��p�͏㍐�l�̕��S�Ƃ���B
(���|)
�Q ���_�́A�{���̏㍐�\���ė��R���̒�o���ԓ��ɖ{�������R�����m�肵�A�������T�ɌW����������͈̔͂����k���ꂽ�Ƃ����{���̎����W�̉��ł́A�������̊�b�ƂȂ����s����������̍s�������ɂ��ύX���ꂽ���̂Ƃ��āA���i�@�R�R�W���P���W���ɋK�肷��ĐR���R������Ƃ����邩��A�������ɂ͔����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̈ᔽ������i���i�@�R�Q�T���Q���j�Ƃ����̂ł���B
�R(1) ����Č�������ɁA���R�́A�{�������O�̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��āA��T�����ɌW������ɂ͓����@�Q�X���Q���ᔽ�̖������R�����݂���|�̔��f�����āA��㍐�l��̓��@�P�O�S���̂R��P���̋K��Ɋ�Â��咣��F�߁A�㍐�l�̐��������p�������̂ł���A�������ɂ����ẮA�{��������̓��������͈̔͂�O��Ƃ���{�������ɌW�閳�����R�̑��ۂɂ��ċ�̓I�Ȍ���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����āA�{�������R�����m�肵�����Ƃɂ��A�{�������́A��������{��������̓��������͈̔͂ɂ��������肪���ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ���i�����@�P�Q�W���j�A�O�L�̂Ƃ���{�������͓��������͈̔͂̌��k�ɓ�������̂ł��邩��A����ɂ���L�������R����������Ă���\�����Ȃ��Ƃ͂������A��L�������R�����������ƂƂ��ɁA�{��������̓��������͈̔͂�O��Ƃ��Ė{�����i�����̋Z�p�I�͈͂ɑ�����ƔF�߂���Ƃ��́A�㍐�l�̐�����e��邱�Ƃ��ł�����̂ƍl������B��������ƁA�{���ɂ��ẮA���i�@�R�R�W���P���W������̍ĐR���R����������̂Ɖ������]�n������Ƃ����ׂ��ł���B
(2) �������Ȃ���A���ɍĐR���R��������Ƃ��Ă��A�ȉ��ɏq�ׂ�Ƃ���A�{���ɂ����ď㍐�l���{�������R�����m�肵�����Ƃ𗝗R�Ɍ��R�̔��f�𑈂����Ƃ́A�㍐�l�Ɣ�㍐�l��Ƃ̊Ԃ̖{���������̐N�Q�ɌW�镴���̉�����s���ɒx����������̂ł���A�����@�P�O�S���̂R�̋K��̎�|�ɏƂ炵�ċ�����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�A�@�����@�P�O�S���̂R��P���̋K�肪�A�������̐N�Q�ɌW��i�ׁi�ȉ��u�������N�Q�i�ׁv�Ƃ����B�j�ɂ����āA���Y���������������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂ƔF�߂��邱�Ƃ�������̍s�g��W���鎖�R�ƒ�߁A���Y�����̖����������咣�i�ȉ��u�����咣�v�Ƃ����B�j������̂ɓ��������R���葱�ɂ�閳���R���̊m���҂��Ƃ�v���Ȃ����̂Ƃ��Ă���̂́A�������̐N�Q�ɌW�镴�����ł������������N�Q�i�ׂ̎葱���ʼn������邱�ƁA�������v���ɉ������邱�Ƃ�}�������̂Ɖ������B�����āA�����Q���̋K�肪�A�����P���̋K��ɂ��U���h����@���R����s���ɒx�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ē�o���ꂽ���̂ƔF�߂���Ƃ��́A�ٔ����͂�����p�����邱�Ƃ��ł���Ƃ��Ă���̂́A�����咣�ɂ��ĐR���A���f���邱�Ƃɂ���đi�גx���������邱�Ƃ�h�����߂ł���Ɖ������B���̂悤�ȓ����Q���̋K��̎�|�ɏƂ炷�ƁA�����咣�݂̂Ȃ炸�A�����咣��ے肵�A���͕����咣�i�ȉ��u�R�咣�v�Ƃ����B�j���p���̑ΏۂƂȂ�A���������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�������𗝗R�Ƃ��閳���咣�ɑ���R�咣���A�R����s���ɒx�������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ē�o���ꂽ���̂ƔF�߂���A�p������邱�ƂɂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B
�C�@�����āA�O�L�P�̎����W�̊T�v���ɂ��ƁA�@��㍐�l��́A���ɑ�P�R�ɂ����āA��T�����ɌW������ɂ��Ė����咣�����Ă���A�����P�U�N�P�O���Q�P���Ɍ����n���ꂽ��P�R�����́A�����@�ɓ��@�P�O�S���̂R�̋K���V�݂��������P�U�N�@����P�Q�O���̎{�s�O�ł��������A�O�f�ō��ٕ����P�Q�N�S���P�P����O���@�씻���ɏ]���A��L�����咣���̗p���ď㍐�l�̐���������������p�������ƁA�A�㍐�l�́A�����P�U�N�P�P���Q���ɏ�L��P�R�����ɑ��čT�i���N���A�����P�V�N�P���Q�P���ɐ������T�ɂ��ē��������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�������R���������������A���N�S���P�P���ɂ������艺���A�����ēx�������T�ɂ��Ē����R���������������ƁA�B��L�ēx�̒����R�������ɂ��ẮA���N�P�P���Q�T���ɓ������͐��藧���Ȃ��|�̐R��������A�㍐�l�͓��N�P�Q���Q�Q���ɓ���������艺�������ƁA�C�����ŁA���R�͕����P�W�N�P���Q�O���Ɍ����٘_���I���������A�㍐�l�͓��N�S���P�W���ɂR�x�ڂ̒����R���������������ƁA�D���R�͓��N�T���R�P���ɏ㍐�l�̍T�i������������p�������A���̗��R�́A��P�R�����Ɠ�������㍐�l��̏�L�����咣���̗p������̂ł��������ƁA�E�㍐�l�́A���N�U���P�U���ɏ㍐�y�я㍐�̐\���Ă��������A���̌�R�x�ڂ̒����R����������艺���ĂS�x�ڂ̒����R�����������A����ɂS�x�ڂ̒����R����������艺���ĂT�x�ڂ̒����R�������������̂��{�������R�������ł��邱�ƁA�ȏ�̎��������炩�ł���B
�@��������ƁA�㍐�l�́A��P�R�ɂ����Ă��A��㍐�l��̖����咣�ɑ��đR�咣���o���邱�Ƃ��ł����̂ł���A��L�����@�P�O�S���̂R�̋K��̎�|�ɏƂ炷�ƁA���Ȃ��Ƃ���P�R�����ɂ���ď�L�����咣���̗p���ꂽ��̌��R�̐R���ɂ����ẮA���������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ�������𗝗R�Ƃ�����̂��܂߂đ����ɑR�咣���o���ׂ��ł������Ɖ������B�����āA�{�������R���̓��e��㍐�l���P�N�ȏ�ɋy�Ԍ��R�̐R�����Ԓ��ɂQ�x�ɂ킽���Ē����R�������Ƃ��̎扺�����J��Ԃ������Ƃɂ��݂�ƁA�㍐�l���{�������R�������ɌW��R�咣�����R�̌����٘_�I���O�ɒ�o���Ȃ��������Ƃ𐳓������闝�R�͉��猩���������Ƃ��ł��Ȃ��B���������āA�㍐�l���{�������R�����m�肵�����Ƃ𗝗R�Ɍ��R�̔��f�𑈂����Ƃ́A���R�̐R�����ɂ���������ɒ�o���ׂ��ł������R�咣�����������n����ɒ�o����ɓ������A�㍐�l�Ɣ�㍐�l��Ƃ̊Ԃ̖{���������̐N�Q�ɌW�镴���̉�����s���ɒx����������̂Ƃ��킴����A��L�����@�P�O�S���̂R�̋K��̎�|�ɏƂ炵�Ă�����������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�S �ȏ�ɂ��A�������ɂ͏��_�̈�@�͂Ȃ��A�_�|�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����āA�ٔ����S����v�̈ӌ��ŁA�啶�̂Ƃ��蔻������B�Ȃ��A�ٔ������̈ӌ�������B
�ٔ������̈ӌ��́A���̂Ƃ���ł���B
�@���́A�{���㍐�����p����Ƃ̑����ӌ��̌��_�ɂ͓������邪�A���̗��R���قɂ���B�{�������R�����m�肵�A���������͈̔͂����k���ꂽ���Ƃɂ��A�������肪�������猸�k��̓��������͈̔͂ɂ�肳�ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����Ɏ������Ƃ��Ă��A���i�@�R�R�W���P���W������̍ĐR���R�ɂ͊Y�����Ȃ�����A�������ɂ������ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̈ᔽ������Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƍl����B
�P ��ʂɁA�������N�Q�i�ׂɂ����āA�����̓�������N�Q�����Ƒi����ꂽ�퍐���A�����@�P�O�S���̂R��P���̋K��Ɋ�Â��A���Y�����͓��������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂ƔF�߂��邩��A�����ɂ����Ă��̌������s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��������s�g�����̍R�ق��咣�����ꍇ�ɂ́A�����́A���Y�����ɌW����������͈̔͂̂����퍐�咣�̖������R�����݂��镔���i�ȉ��u���������v�Ƃ����B�j���A�����R���𐿋����ē��������͈̔͂����k���邱�Ƃɂ��r�����邱�Ƃ��ł�����̂ł��邱�ƁA�y�сA�퍐���i�����k��̓��������͈̔͂ɌW�锭���̋Z�p�I�͈͂ɑ����邱�Ƃ��咣�����āA�����s�g�����̍R�ق̐�����W���邱�Ƃ��ł���B�����R���̐����ɂ�薳��������r�����邱�Ƃ��ł���ꍇ�ɂ́A�����@�P�O�S���̂R��P���ɂ����u���Y���������������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂ƔF�߂���v���Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��̂ł����i���Ȃ݂ɁA�ō��ٕ����P�O�N�i�I�j��R�U�S�����P�Q�N�S���P�P����O���@�씻���E���W�T�S���S���P�R�U�W�ł��A�u�����R���̐���������Ă���ȂǓ��i�̎����F�߂�ɑ���Ȃ�����v�������Ɋ�Â����Q���������������̗��p�ɓ����苖����Ȃ��|�������Ă���B�j�B�����āA�퍐�ɂ����āA�����s�g�����̍R�ق𐬗������邽�߂ɂ́A���ɓ��������R������������Ă���܂ł̕K�v�͂Ȃ��A���������R���̐��������ꂽ�ꍇ�ɂ͓��Y�����������ɂ����ׂ����̂ƔF�߂��邱�Ƃ��咣������Α����̂Ɠ��l�ɁA�����ɂ����āA���R�ق̐�����W���邽�߂ɂ́A���ɒ����R���𐿋����Ă���܂ł̕K�v�͂Ȃ��A�܂��Ē����R�����m�肵�Ă���܂ł̕K�v�͂Ȃ��̂ł���A�����R���̐����������ꍇ�ɂ͖���������r�����邱�Ƃ��ł��A���A�퍐���i�����k��̓��������͈̔͂ɌW�锭���̋Z�p�I�͈͂ɑ����邱�Ƃ��咣������Α����B
�@���Ȃ킿�A�����́A�����R���̐����������ꍇ�ɂ͖���������r�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��咣�����邱�Ƃɂ��A�����R���������Ɋm�肵���ꍇ�Ɠ��l�̖@�����ʂ�h����@�Ƃ��Ď咣���邱�Ƃ��ł���̂ł���B�����́A�����ɂ��A�����R�����٘_�I�����܂łɁA�����R���̐������s�����Ƃ��\�ł���A���������R�̂�����̂ł������A�ʏ�A�����R���̊m��邱�Ƃ��\�ł��邪�A�퍐�̌����s�g�����̍R�ق̐�����W���邽�߂ɂ́A�����ɒ����R���𐿋����A�����R�����m�肳���Ă����܂ł̕K�v�͂Ȃ��̂ł���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�����R���̐����������ꍇ�ɂ͖���������r�����邱�Ƃ��ł��邱�ƁA�y�сA�퍐���i�����k��̓��������͈̔͂ɌW�锭���̋Z�p�I�͈͂ɑ����邱�Ƃ́A�퍐�̌����s�g�����̍R�ق��������邩�ۂ��f���邽�߂̗v�f�ł����āA���̊�b�����������R�����٘_�I�����܂łɊ��ɑ��݂��A�����ɂ����Ă��̎��܂łɂ��ł��咣�����邱�Ƃ��ł������̂ł���B�����Ƃ��ẮA�����R�����٘_�I�����܂łɁA��L�̎咣����s�����Č����s�g�����̍R�ق�r�˂��ׂ��ł���A�����R���A�����ґo���̎咣���̒��x�ɉ������i��ԂɊ�Â����R�S�̌��ʂƂ��āA�����s�g�����̍R�ق̐�����F�߂��ȏ�A�����R�����٘_�I����ɂȂ��āA�����������R���𐿋��������R�����m�肵���Ƃ��Ă��A�����R���ɂ���Ă����炳���@�����ʂ͎����R�����٘_�I�����܂łɎ咣���邱�Ƃ��ł������̂ł��邩��A�����R�����m�肵�����Ƃ������Ď����R�̏�L���f����@�Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł����i�Ȃ��A�ō��ُ��a�T�T�N�i�I�j��T�W�X�����N�P�O���Q�R����ꏬ�@�씻���E���W�R�S���T���V�S�V�ŁA�ō��ُ��a�T�S�N�i�I�j��P�P�O�����T�V�N�R���R�O����O���@�씻���E���W�R�U���R���T�O�P�ŎQ�Ɓj�B
�@���i�@�R�R�W���P���W���́A�ĐR���R�̈�Ƃ��āA�u�����̊�b�ƂȂ����s����������̍s�������ɂ��ύX���ꂽ���Ɓv���f���Ă���B�����R�������@�P�O�S���̂R��P���̋K��Ɋ�Â������s�g�����̍R�ق̐��ۂɂ��čs�����f�́A�����̓������菈�������^�̂��̂Ƃ��čs�����̂ł͂Ȃ��A��L�̂Ƃ���A�����R���̐��������ꂽ�ꍇ�ɂ͂��ꂪ�F�߂���ׂ����̂ł��邩�ۂ����l���̏�A��������ƁA�����R���ɂ���Ă����炳���@�����ʂ��l���̏�ōs�����̂ł��邩��A���̌�ɒ����R�����m�肵������Ƃ����āA��L���f�̊�b�ƂȂ����s���������ύX���ꂽ�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B���ɁA�������A�����R�����٘_�I�����܂łɁA�����R���̐����������ꍇ�ɂ͂��ꂪ�F�߂���ׂ����̂ł��邱�Ƃ��咣���Ȃ��������߁A�����R�����̓_�̔��f�����Ȃ������Ƃ��Ă��A���̌�Ɍ�������L�咣���s�����Ƃ͋�����Ȃ�����A�����R�����m�肵�������L�̍ĐR���R��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�@�X�ɕt������ƁA�����R�����٘_�I����ɒ����R�����m�肵������ĐR���R�������A��������j�����ׂ��ł���Ƃ������߂ɂ́A�����R�����m�肵�����Ƃɂ��A�������ɂ������ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߈ᔽ������Ƃ������Ƃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�����R�����m�肵�Ă��A�����ɂ����āA�퍐���i�����k��̓��������͈̔͂ɌW�锭���̋Z�p�I�͈͂ɑ����邱�Ƃ��咣�����Ȃ�����A�����s�g�����̍R�ق̐�����F�߂��������Ɍ�肪����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A�퍐�ɂ����Ă��A���k��̓��������͈̔͂ɂ��������Ȃ������������R���ɂ�薳���Ƃ����ׂ����̂ł��邱�Ƃ��咣�����邱�Ƃ��ł��A���̎咣���ɐ��������Ƃ��́A�����s�g�����̍R�ق̐�����F�߂��������Ɍ�肪����Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B���Ȃ킿�A�����̌��퍐�̎咣����҂��Ȃ���A�������ɖ@�߈ᔽ������Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���A�@���R�ł���㍐�R�ł͂��̂悤�Ȍ��퍐�̎咣����R�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��������ƁA�����R���̊m��ɂ����������͈̔͂����k���ꂽ�Ƃ��Ă��A�������ɂ������ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̈ᔽ������Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��邩��A���̓_���炵�Ă��A�����R�����m�肵������ĐR���R��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B
�Q ���������āA�{���ɂ����Ă��A���R�����٘_�I����ɖ{�������R�����m�肵������Ƃ����āA���i�@�R�R�W���P���W������̍ĐR���R��������Ƃ������Ƃ͂ł����A�������ɂ������ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̈ᔽ������Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�R ���Ȃ݂ɁA�������N�Q�i�ׂɂ����Ă��A�����R���������҂̐�����F�e�����ꍇ�́A���Y�������̐����A���͂�O��Ƃ��āA���̐N�Q�s�ׂ����������Ƃ�F�肷����̂ł��邩��A�����R�����٘_�I����ɒ����R��������A���Y�������ɌW��������菈�����ύX���ꂽ�Ƃ��́A���i�@�R�R�W���P���W���ɂ����u�����̊�b�ƂȂ����s����������̍s�������ɂ��ύX���ꂽ���Ɓv�ɊY������B�������A�{���́A�������N�Q�i�ׂł͂�����̂́A���R�������s�g�����̍R�ق�F�߂ē������҂̐��������p�������Ăł��邩��A�������҂̐�����F�e�������ĂƂ͋�ʂ���K�v������B
�S �Ȃ��A�ō��ٕ����P�S�N�i�s�q�j��Q�O�O�����P�T�N�P�O���R�P����@�씻���E�ٔ��W�����Q�P�P���R�Q�T�ł́A�������҂��A�����������̎���������߂đi�����N���A�����R�Ő��������p����|�̔������A�����R�����٘_�I����ɒ����R���𐿋����A��L�i�������㍐�R�ɌW�����ɒ����R�����m�肵���Ƃ������ĂɌW����̂ł���B�����������́A�ΐ��I�ɓ��������͂��߂��瑶�݂��Ȃ��������̂Ƃ��錈��ł���B��L��@�씻���́A�㍐�R�W�����ɓ��Y�����ɂ��ē��������͈̔͂����k����|�̒����R�����m�肵���ꍇ�ɂ́A�������̊�b�ƂȂ����s����������̍s�������ɂ��ύX���ꂽ���̂Ƃ��āA�������ɂ͖��i�@�R�R�W���P���W������̍ĐR���R������|���������B��L��@�씻���́A�����������ɂ��������ꂽ�������菈����R���̑ΏۂƂ��Ă���̂ł��邩��A�R���̑Ώۂł���������菈���������R���ɂ��ύX���ꂽ���Ƃ͖��i�@�R�R�W���P���W������̍ĐR���R�ɊY������Ɣ��f�������̂ł���B�������A�������N�Q�i�ׂ́A���������̂��̂�R���̑ΏۂƂ��ē������̌��͂�ΐ��I�Ɋm�肵������ł������肷����̂ł͂Ȃ��̂ł����āA�����������̎���������߂�i�ׂƂَ͈��̂��̂ł���B���������āA��L��@�씻���̔������A�������N�Q�i�ׂɂ����Ď����R�������s�g�����̍R�ق�F�߂ē������҂̐��������p�������ĂɓK�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�u�v���C�I�O���[���v�Ή��y��������
���������N�Q��ے�B��T�i�l���i�́A���_�J���V�E���̊ܗL�ʂ��Q�R�D�W�d�ʁ��ł���A�{�������ɂ�����u���_�J���V�E���̊ܗL�ʂ��P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��͈̔͂Ɍ��肷��v�\���v���a�����[������ƔF�߂�ɂ͑���Ȃ��Ƃ���A���̕����͖{�������̖{���I�����ł��邩��A�����ł���A��T�i�l���i�����������͈̔��ɋL�ڂ��ꂽ�\���Ƌϓ��Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��
| �����ԍ� | �@����17�N(�l)��10056�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����17�N07��12�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@(�)�@�ȏ�̋L�ڂɂ��ƁA�]���̌��w��ގ�q���t���H�@�ɂ�����X�����[�q�y�́A�q�y�A��q�A�{���܁A�엿�A�y����Ǎ܁A���i�܁A�y��Ō��܁i�Ѝ܁j�Ȃǂ�����̊����ō������Đ��鍬�����𐅂Ɍ����������̂ł��邪�A�]���̃X�����[�q�y�́A�y�뗱�q��c�������邽�߂̌Ѝ܂������|���}�[����̂Ƃ��邽�߁A���̍d�����x���x���A�܂��A�Ѝ܂̍d������������ƁA�c���������q�y�̕\�ʂ͊��ŏ�ԂɂȂ��āA�ې�����ʋC���������A�S�̂Ƃ��āA�A���ޗ��̔����Ԃ͂܂���ƂȂ�A���̔��藦�͒ቺ���A����ɁA�Ѝ܂̍d�����x���x���A�P���ԂŌ������t���ʂ��`�����邱�Ƃ�����ł���Ƃ�����肪�������Ƃ���A�{�������́A�����̖����������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA�u�Y���܂����_�A���~�j�E���P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A���_�J���V�E���P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A�V���J�����P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A�Z�����g�����P�O�Ȃ����W�O�d�ʁ�����Ȃ�A�t���C�A�b�V�������P�O�O�d�ʕ��ɑ��Y���܂P�O�`�T�O�d�ʕ����������邱�Ɓv�Ƃ����\�����̗p���A����ɂ��A���t���{�H��A�P�Ȃ����R���Ԓ��x�o�߂���ƒc�������N����ʏ�̍~�J�ʂł����S���邱�Ƃ��Ȃ��A�܂��A�P�x�̐��t����ƂłWcm���x�̌��݂̐��t���ʂ��`�����邱�Ƃ��ł��A�������A�`�����ꂽ���t���ʂ́A���E���ŒʋC����ې����ɕx�݁A���t���ʑS�̂��獂�����藦�ŐA����q�萬�������邱�Ƃ��ł��A������N�������Ƃ��Ȃ��Ƃ�����p���ʂ�t������̂ł��邱�Ƃ��F�߂���B��������ƁA�{���������L�̉ۑ������i����b�Â�������I�����́A�u�Y���܂����_�A���~�j�E���P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A���_�J���V�E���P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A�V���J�����P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A�Z�����g�����P�O�Ȃ����W�O�d�ʁ�����Ȃ�A�t���C�A�b�V�������P�O�O�d�ʕ��ɑ��Y���܂P�O�`�T�O�d�ʕ����������邱�Ɓv�Ƃ�������͈͓̔��̍���������p���邱�Ƃɂ���ƔF�߂���B
�@���������āA�{�������̖{���I�����́A���_�J���V�E�����P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��͈͓̔��ɂ��邱�Ƃ��܂ށA���������̊����ō������邱�Ƃł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@(�)�@�T�i�l�́A�{�������́A�u�q�y�A��q�A�{���܁A�엿�A�y����Ǎ܁A���i�܁A�y��Ō��܁i�Ѝ܁j�Ȃǂ�����̊����ō������Đ��鍬�����𐅂Ɍ������ăX�����[�q�y�Ƃ��A����ꂽ�X�����[�q�y��Ⴆ���X�Ԃ����݂���Ă���@�ʂɐ��t���āA���Y�@�ʂ����]���݂̐��t���ʂŔ핢����H�@�v�����m�ł������Ƃ��ɁA���_�A���~�j�E���Ɨ��_�J���V�E����Y���܂Ɋ܂߂邱�Ƃɂ���āA�y������艻����悤�ɂ������̂ł��邩��A���������̊����ō������邱�Ƃ́A�{�������̖{���I�����ł͂Ȃ��Ǝ咣����B
�@�������A�T�i�l�́A���������͈̔͂ɂ����āA�Y���܂ɂ��A���_�A���~�j�E���P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A���_�J���V�E���P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A�V���J�����P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��A�Z�����g�����P�O�Ȃ����W�O�d�ʁ��ƌ��肵�A�����̏ڍׂȐ����ɂ����āA�i���y�O�O�P�U�z�Ȃ����y�O�O�Q�R�z�ɏ�L(�)�̂Ƃ���̋L�ڂ����Ă���̂ł���B�����āA���_�J���V�E���ɂ��Ă݂�ƁA�T�i�l�́A��Q�̂R(1)�C(�)�A(�)�̂Ƃ���A���_�J���V�E���̊ܗL�ʂ��Q�R�D�W�d�ʁ��ɂ��Ă��A�X�����[�ʼn��̑��x���x���Ȃ邾���ŁA�{�������̖ړI��B���邱�Ƃ��ł��A�{�������Ɠ���̍�p���ʂ�t����A���_�J���V�E���̊ܗL�ʂ��Q�R�D�W�d�ʁ��ɂ��邱�Ƃ́A���Ǝ҂��K�X�I�����邱�Ƃ��ł��鎖���ł����āA�Z�p�I�ɏd�v�ȈӋ`��L������̂ł͂Ȃ��A���Ǝ҂��e�Ղɑz�����邱�Ƃ��ł����Ǝ咣���Ă���Ƃ���A���ɂ��̎咣�̂Ƃ���ł���Ƃ���A�T�i�l���A�{�������̓����o��ɍۂ��āA���_�J���V�E���̊ܗL�ʂ��P�Ȃ����Q�O�d�ʁ��͈̔͂Ɍ��肷��Ƃ͍l������A����ɂ�������炸�A�T�i�l�͂����Č��肵�Ă���̂ł���B�����ł���A�{���������L�̉ۑ������i����b�Â�������I�����́A���_�A���~�j�E���Ɨ��_�J���V�E����Y���܂Ɋ܂߂�Ƃ����ɂƂǂ܂炸�A����̍��������̗��_�A���~�j�E���Ɨ��_�J���V�E����Y���܂Ɋ܂߂�Ƃ���ɂ���Ƃ����ׂ��ł���A���������āA���ꂪ�{�������̖{���I�����ł���B����ƈقȂ�T�i�l�̏�L�咣�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@(�)�@��T�i�l���i�́A�{�������̍\���v���a�����[������ƔF�߂�ɂ͑���Ȃ��Ƃ���A���̕����͖{�������̖{���I�����ł��邩��A�����ł���A��T�i�l���i�����������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\���Ƌϓ��Ȃ��̂ł���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�}���`�g�[���ܖ���������
���������N�Q��ے�B�u�]�����m��ꂽ���@�v�Ƃ̕�I�ȋL�ڂ����ē������擾�����ȏ�A�]�����m��ꂽ������̕��@�ɂ���đ��肵�Ă��A���������͈̔͂̋L�ڂ̐��l���[������ꍇ�łȂ�����A�������N�Q�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���Ƃ̌������̔��f�F�B��
| �����ԍ� | �@����15�N(�l)��3746�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�����T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����16�N02��10�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�@(2)�@�b�����̍\���v���a�́u���|����d�v�̏[�����ɂ���
�@(2-1)�@�T�i�l�́A�䂪���ɂ����ėB��}���`�g�[���ܖ��������H�ƓI�ɐ��Y���A���ƓI�ɔ̔����Ă����T�i�l���A�i�h�r�j�U�V�Q�P�@��p���Ă����̂ŁA���Ǝ҂́A�u�]�����m��ꂽ���@�v�Ƃ͂i�h�r�j�U�V�Q�P�@�ł���Ɨ�������̂ł���A�ًc�̌���ɂ����Ă��A�T�i�l�̎咣�ɉ����F�肪����Ă��邱�Ƃ��咣����B
�@�������A�p�E�_�[�e�X�^�[�@���܂��A�u�]�����m��ꂽ���@�v�̂P�ł���A�����}���`�g�[���̌��|����d�̑�����@�Ƃ��āA���Ǝ҂��ʏ�p�E�_�[�e�X�^�[�@�ł͂Ȃ��A�i�h�r�j�U�V�Q�P�̕��@��p���邱�Ƃ����炩�ł���ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��Ƃ����������̔F��́A���̋�������؋��ɏƂ炵�A�����Ƃ��Đ��F���邱�Ƃ��ł���B�T�i�l�́A�����������P�W�A�R�R�A�R�S���̏؋��̌���������Ă���Ƃ��咣���邪�A�������Ɍ�肪����Ƃ͂����Ȃ��B
�@���������F�肵���p�E�_�[�e�X�^�[�@�̎g�p���Ɋւ��鎖��ɏƂ点�A�T�i�l���i�h�r�j�U�V�Q�P�@��p���Ă�������Ƃ����āA��L�F����ɑ������̂ł͂Ȃ��i�T�i�l�́A�i�h�r�j�U�V�Q�P�@�̎g�p�Ƃ��čb�X�S�Ȃ����P�O�O�k�}�ԍ����܂ށl���o���邪�A��L�p�E�_�[�e�X�^�[�@�Ɋւ��鎖��̂ق��A���T�Q�Ȃ����T�T�ɂ��Ƃ点�A�i�h�r�j�U�V�Q�P�@�������̗B��̑���@�Ƃ��Ċm������Ă������͎g�p����Ă����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�j�B
�@�����āA�ًc�̌�����A�K�������A�p�E�_�[�e�X�^�[�@���p�����邱�Ƃ�ے肵�āA�i�h�r�j�U�V�Q�P�@���B��̑���@�ł���ƔF�߂���|�ł͂Ȃ����̂Ɖ�����A�������̔F��ƒ����ɖ���������̂ł͂Ȃ��B
�@(2-2)�@�T�i�l�́A���ɁA�p�E�_�[�e�X�^�[�@�ő��肷��Ƃ��Ă��A�i�h�r�j�U�V�Q�P�@��p�����ꍇ�ƃp�E�_�[�e�X�^�[�@��p�����ꍇ�Ƃł́A�O�҂����ςO�D�O�X�P�Ⴂ�l�ƂȂ�̂ŁA�p�E�_�[�e�X�^�[�@�ɂ�鑪��l�́A�b���������Ɏ����ꂽ���l�͈͂ɓ���Ȃ����A��L�̍����T������ƁA�b���������ɋL�ڂ��ꂽ���l�͈͂ɓ���̂ŁA���Ǝ҂́A�b���������ɋL�ڂ��ꂽ����l�́A�i�h�r�j�U�V�Q�P�@�ɂ����̂Ɨ������邱�ƁA��T�i�l���i�̃}���`�g�[���ܖ������́u���|����d�v���i�h�r�j�U�V�Q�P�@�ɂ�葪�肷��ƁA�\���v���a�̐��l�͈͂ɂ��邱�Ɓi�b�V�A�W�|�P�A�V�Q�A�V�R�j�A��T�i�l���咣����p�E�_�[�e�X�^�[�@�ɂ���T�i�l���i�̃}���`�g�[���ܖ������̒l�́A�O�L�̂悤�ɗ��҂̌덷���C������ƁA�\���v���a�̐��l�͈͂ɓ��邱�Ƃ��咣����B�����āA�T�i�l�́A����ɁA�Q�̈قȂ鑪����@��������ꍇ�ɁA�ʏ푪�肷�ׂ������̑���l�Ɠ����ɑ��肳���ΏƁi�R���g���[���j�̑���l����ɂ��āA�����̑���l���ǂ���̑�����@�ő��肳�ꂽ���̂��f���邱�Ƃ͋Z�p�҂̏펯�I�ȑԓx�ł���A�Q�̈قȂ鑪����@�ɂ����鑪��l�ɍ��ق�����ꍇ�̗����@�̑���l�̑Δ�́A�����@�̑���l�̑��ւ����l�����߁A����̑���l�ƕ�l�ɂ��C�����������̑���l�Ƃ��r���邱�Ƃɂ��s����̂ŁA�������̔F�肷��悤�ɁA���Ƃ��u�\���v���a�̑�����@�Ƃ��āA�i�h�r�j�U�V�Q�P�ƃp�E�_�[�e�X�^�[�@������v�Ƃ��Ă��A�O�L�̂悤�ɁA������̕��@�ɂ���Ă���T�i�l���i�̃}���`�g�[���ܖ��������\���v���a��������邱�Ƃ����炩�ł���A�������͌��ł���Ƃ��咣����B
�@�������A�T�i�l�咣�̂Ƃ���T�i�l���i�h�r�j�U�V�Q�P�@��p���Ă����Ƃ��Ă��A�T�i�l�́A�b���������ɂ����ẮA���̕��@���J�����邱�ƂȂ��A�����āu�]�����m��ꂽ���@�v�Ƃ̕�I�ȋL�ڂ��������̂ł���i�b�Q�j�B�����āA�O�L�̂Ƃ���A�i�h�r�j�U�V�Q�P�@�̂ق��ɁA�p�E�_�[�e�X�^�[�@���܂��A�u�]�����m��ꂽ���@�v�̂P�ł���A�����}���`�g�[���̌��|����d�̑�����@�Ƃ��āA���Ǝ҂��ʏ�p�E�_�[�e�X�^�[�@�ł͂Ȃ��i�h�r�j�U�V�Q�P�̕��@��p���邱�Ƃ����炩�ł���ƔF�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B
�@�T�i�l�́A��L�̂悤�ɁA�b���������ɋL�ڂ��ꂽ����l�ƁA�p�E�_�[�e�X�^�[�@�ő��肵���ꍇ�̑���l��Δ䂵�A����ɁA�i�h�r�j�U�V�Q�P�@��p�����ꍇ�ƃp�E�_�[�e�X�^�[�@��p�����ꍇ�Ƃ̑���l�̍����C�����邱�Ƃ��咣����B�������A������̕��@�ő��肵�����b���������ɋL�ڂ͂Ȃ��A�T�i�l�咣�̂悤�ȍ�Ƃ��o�Ȃ�����A�e�Ղɒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł����āA�b�����o���̎҂��A���Ǝ҂Ƃ��ē��R�ɍT�i�l�咣�̂悤�ȕK�������e�ՂƂ͎v���Ȃ���Ƃ����Ă�����ׂ��ł���Ƃ��ׂ�����͔F�߂��Ȃ��B�ނ���A�����āu�]�����m��ꂽ���@�v�Ƃ̕�I�ȋL�ڂ����ē������擾�����ȏ�A�T�i�l�́A��L�̂悤�ȍ�Ƃ̎�Ԃƃ��X�N���o���̎҂ɓ]�ł��邱�Ƃ͋����ꂸ�A�L���T�O�ŋK�肵�����Ƃɂ�闘�v�ƂƂ��ɁA���̕s���v���T�i�l�ɂ����ĕ��S���ׂ��ł���B
�@���������āA�{���ɂ����āA�]�����m��ꂽ������̕��@�ɂ���đ��肵�Ă��A���������͈̔͂̋L�ڂ̐��l���[������ꍇ�łȂ�����A�������N�Q�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���Ƃ̌������̔��f�́A���F��������̂ł���A�����O��Ƃ����A�\���v���a�̏[�����Ɋւ��錴�����̔F�蔻�f�������ł���Ƃ����ׂ��ł���B�T�i�l�̎咣�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�u���f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��v�R�������������
���v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���̉�����
| �����ԍ� | �@����13�N(�s�P)��84�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����14�N06��11�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�@�@�@�@�@�@��@��
�@�@�@�P�@�����̐��������p����B
�@�@�@�Q�@�i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�����y�ї��R
��P�@�����҂̋��߂��ٔ�
�P�@����
(1) �������������Q�O�O�O�|�R�X�O�W�P�������ɂ��ĕ����P�R�N�P���P�U���ɂ����R�����������B
�@�@(2) �i�ה�p�͔퍐�̕��S�Ƃ���B
�Q�@�퍐
�@�啶�Ɠ��|
��Q�@�����ҊԂɑ����̂Ȃ�����
�P�@�������ɂ�����葱�̌o��
�@�@�����ƃ\�j�[������Ёi�ȉ��u�\�j�[�v�Ƃ����B�j�́A�����̖��̂��u���f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��v�Ƃ��������Q�U�V�Q�O�X�S���̓����i���a�U�Q�N�N�V���Q�X�������o��A�����X�N�V���P�P���ݒ�o�^�A�ȉ��u�{�������v�Ƃ����B�j�̋��L�������҂ł������B
�@�@�{�������ɑ��A�����ًc�̐\���Ă�����A�������́A������A�����P�O�N�ًc��V�Q�O�X�X�������Ƃ��ĐR�����A���̌��ʁA�����P�P�N�P�P���P�T���A�u������Q�U�V�Q�O�X�S���̓������������B�v�Ƃ̌�������A�����P�P�N�P�P���Q�X���ɂ��̓��{�������ƃ\�j�[�ɑ��B�����B
�@�@�����ƃ\�j�[�́A�����P�P�N�P�Q���Q�V���ɁA������̎���������߂�i�ׂ𓌋������ٔ����ɒ�N�����i���ٔ��������P�P�N�i�s�P�j��S�R�V���j�B�����́A�����P�Q�N�W���V���A�\�j�[���瓯�Ђ��L����{�������̎����S��������A���̓o�^�𗹂����B
�@�@�����́A�����P�Q�N�V���Q�T���ɁA�{�������̊菑�ɓY�t�����������͐}�ʁi�ȉ��u�{�������v�Ƃ����B�j��������邱�Ɓi�ȉ��u�{�������v�Ƃ����A�{�������ɌW�閾�����u�{�����������v�Ƃ����B�j�ɂ��R���𐿋������B�������́A���������Q�O�O�O�|�R�X�O�W�P�������Ƃ��ĐR�����A���̌��ʁA�����P�R�N�P���P�U���A�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R�������A�����P�R�N�Q���T���A���̓��{�������ɑ��B�����B
�Q�@�{�������ɌW����������͈̔́i�ȉ��u�{�����������v�Ƃ����B�j
�@�u�W�N�������^����n�}�Ƃ��ăr�X�t�F�m�[���ƃz�X�Q���Ƃ̔����ɂ���ē����A��_�X�g�����ꂽ�|���J�[�{�l�[�g�����n�t�ɁA�|���J�[�{�l�[�g�����̔��͕n�n�}�Ƃ��āA���|�w�v�^���A�V�N���w�L�T���A�x���[�����̓g���G���𒾓a�������Ȃ����x�̗ʂ������A����ꂽ�ψ�n�t��45�`100���ɕۂ������a���̐����ɓH�������͕������ăQ�������A�n�}�𗯋����đ��E���̕����̂Ƃ�����A�������A�������A���o���ē�����|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��ł����āA�Y�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł����W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��B�i�����͒������������B�j
�@�@�Ȃ��A�{�������O�̓��������͈̔͂́A���̂Ƃ���ł���B
�u�n���Q�����Y�����f��n�}�Ƃ��ăr�X�t�F�m�[���ƃz�X�Q���Ƃ̔����ɂ���ē����A��_�X�g�����ꂽ�|���J�[�{�l�[�g�����n�t�ɁA�|���J�[�{�l�[�g�����̔��͕n�n�}�𒾓a�������Ȃ����x�̗ʂ������A����ꂽ�ψ�n�t���S�T�`�P�O�O���ɕۂ������a���̐����ɓH�������͕������ăQ�������A�n�}�𗯋����đ��E���̕����̂Ƃ�����A�������A�������A���o���ē�����|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��ł����āA�Y�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł���n���Q�����Y�����f���Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��B�v
�R�@�R���̗��R
�@�R���́A�ʎ��R�����̎ʂ��̂Ƃ���A�{�����������́A���s���ł�����J���U�P�|�Q�T�O�O�Q�U������i�ȉ��u���s���P�v�Ƃ����B�j�ɋL�ڂ��ꂽ�����i�ȉ��u���p�����P�v�Ƃ����B�j�A���{�v���X�`�b�N�H�ƘA�����u�v���X�`�b�N�X�v�V������R�W����V���P�S�łȂ����Q�R�ŁE���a�U�Q�N�V���P��������ЍH�ƒ�����s�i�ȉ��u���s���Q�v�Ƃ����B�j�ɋL�ڂ��ꂽ�����A���J���T�W�|�P�Q�U�P�P�X������ɋL�ڂ��ꂽ�����y�ѓ��J���S�X�|�Q�W�U�S�Q������i�ȉ��u���s���S�v�Ƃ����B�j�ɋL�ڂ��ꂽ�����Ɋ�Â��āA���Ǝ҂��e�Ղɔ��������邱�Ƃ��ł������̂ł���A�����@�Q�X���Q���ɊY�����A�����o��̍ۓƗ����ē������邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���̂ŁA�{�������́A�����@�P�Q�U���R���̋K��Ɉᔽ���A�F�߂��Ȃ��A�Ɣ��f�����B
�i�����j
��T�@���ٔ����̔��f
�P�@�{�����������ɂ���
�@�{��������������肷����������͈̔͂̋L�ڂ��A�u�W�N�������^����n�}�Ƃ��ăr�X�t�F�m�[���ƃz�X�Q���Ƃ̔����ɂ���ē����A��_�X�g�����ꂽ�|���J�[�{�l�[�g�����n�t�ɁA�|���J�[�{�l�[�g�����̔��͕n�n�}�Ƃ��āA���|�w�v�^���A�V�N���w�L�T���A�x���[�����̓g���G���𒾓a�������Ȃ����x�̗ʂ������A����ꂽ�ψ�n�t���S�T�`�P�O�O���ɕۂ������a���̐����ɓH�������͕������ăQ�������A�n�}�𗯋����đ��E���̕����̂Ƃ�����A�������A�������A���o���ē�����|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��ł����āA�v�Ƃ̕\���ɂ��A�����Ƃ����̂��|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A���̃|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��̐������@���K�肵����Łi�ȉ��u�{�����@�v���v�Ƃ����B�j�A�u�Y�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��B�v�Ƃ̕\���ɂ��A�����Ƃ����|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��̗p�r����肵�A���������̃W�N�������^���̊ܗL�ʂ��Pppm�ȉ��ł���Ƃ̍\�����K�肵�Ă�����̂ł���i�ȉ��u�{���\���v���v�Ƃ����B�j�B
�@�{�������������A�������@�̔����ł͂Ȃ��A���̔����ł��邱�Ƃ́A��L���������͈̔͂̋L�ڂ��疾�炩�ł��邩��A�{�����������̏�L���������͈̔͂́A���i�v���_�N�g�j�ɌW����̂ł���Ȃ���A���̒��ɓ��Y���Ɋւ��鐻�@�i�v���Z�X�j���܂���Ƃ����Ӗ��ŁA�L���Ӗ��ł̂�����v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���ɊY��������̂ł���B�����āA�{���������������̔����ł���ȏ�A�{�����@�v���́A���̐������@�̓��������̗v���Ƃ��ċK�肳�ꂽ���̂ł͂Ȃ��A���f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��Ƃ������̍\������肷�邽�߂ɋK�肳�ꂽ���̂Ƃ����ȏ�̈Ӗ��͗L�����Ȃ��B�����ł���ȏ�A�{�����������̓����v�����l����ɓ������ẮA�{�����@�v���ɂ��Ă��A�ʂ����Ă��ꂪ�{�����������̑Ώۂł��镨�̍\������肵���v���Ƃ��Ăǂ̂悤�ȈӖ���L���邩����������K�v�͂�����̂́A���̐������@���̂Ƃ��Ă��̓���������������K�v�͂Ȃ��B
�@�����̑Ώۂ��A����������@�Ƃ��Ȃ��ŕ����̂Ƃ��ē����悤�Ƃ���҂́A�{���Ȃ�A�����̑ΏۂƂȂ镨�̍\���ړI�ɓ��肷��ׂ��Ȃ̂ł���A����ɂ�������炸�A�v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���Ƃ����`�ɂ����肪�F�߂���̂́A�����̑ΏۂƂȂ镨�̍\�����A�������@�Ɩ��W�ɁA���ړI�ɓ��肷�邱�Ƃ��A�s�\�A����A���邢�͉��炩�̈Ӗ��ŕs�K�i�Ⴆ�A�s�\�ł�����ł��Ȃ����̂́A�������ɂ����Ȃ�x�����傫���ꍇ�Ȃǂ��l������B�j�ł���Ƃ��́A���̕��̐������@�ɂ���ĕ����̂���肷�邱�ƂɁA��O�I�ɍ��������F�߂��邪�䂦�ł���A�Ƃ����ׂ��ł��邩��A���̂悤�Ȕ����ɂ��Ă��̓����v���ƂȂ�V�K�����邢�͐i�����f����ꍇ�ɂ����ẮA���Y���@�v���ɂ��ẮA�����̑ΏۂƂȂ镨�̍\������肷�邽�߂̗v���Ƃ��āA�ǂ̂悤�ȈӖ���L���邩�Ƃ����ϓ_���猟�����āA����f����K�v�͂�����̂́A����ȏ�ɁA���̐������@���̂Ƃ��Ă̐V�K�����邢�͐i����������������K�v�͂Ȃ��̂ł���B
�@�{�����������́A���f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��ɂ����āA�ܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^�����L�^���H�����錴���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����������A�����`�ޗ����ɊܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��Ƃ���Ƃ̍\���ɂ��A�L�^���̕��H�ɂ��A�j�����ɂ����悤�ɉ��P�������̂ł����āA�{�����@�v���́A�ܗL�����W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł���Ƃ̃|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ������邽�߂̐������@�ł�����̂́A���̂��ƈȊO�ɁA�{�����������̑Ώۂł���|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��̍\���Ȃ��������A���̑��̍\�����̂���肷�邽�߂̗v���Ƃ��Ă̓��i�̈Ӗ���L������̂ł���Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂��Ƃ́A�{�����������̎��̋L�ڂ��疾�炩�ł���B
�k�Y�Ə�̗��p����l
�@�{�����́A���[�U�[���̔��˂ⓧ�߂ɂ���ĐM���̋L�^��ǂݎ����s�����f�B�X�N�p�̃|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��ł���A�L�^���̕��H�ɂ��A�j���啝�ɉ��P�������̂ł���B�i�b��Q���P���P�S�s�`�Q���R�s�A�b��P�O���B�Ȃ��A�b��P�O���́A�����������P�Q�N�Q���P�O���ɖ{�������Ɠ���|�̒��������߂ĐR���𐿋������Ƃ��̐R���������ł���i���̐����́A�������\�j�[����{�������̎����������O�ɒP�ƂŐ����������̂ł��������߁A���N�T���Q�S���ɋp�����ꂽ�B�j�A�����������P�Q�N�V���Q�T���ɖ{�����������߂ĐR���𐿋������Ƃ��̐R���������ł͂Ȃ����̂́A������̐R���������̓��e������|�̂��̂ł��邱�Ƃ́A�b��P�A��R�A��S���؋y�ѕ٘_�̑S��|���疾�炩�ł���B�j
�k�������������悤�Ƃ�����_�l
�@���̋L�^���̒����M�����̉��ǂ��ׂ��A�|���J�[�{�l�[�g�����Ɏ�X�̉�������Y�����āA�����������ł̎����i�������j�������Ƃ���A�R���p�N�g�f�B�X�N�p�̃|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��ɂ����Ă͏]�����Ƃ���Ȃ����������ł���n���Q�����Y�����f���L�^���H�j�������錴���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����o�����B
�@�n���Q�����Y�����f��F�����|���J�[�{�l�[�g������菜��������@�Ƃ��ẮA�[���Ɋ���������@�����邪�A���p�I�Ȋ������@�ɂ�肱����������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���̏�œ���ꂽ�|���J�[�{�l�[�g���������ӂ��A�������邱�Ƃ��K�{�ƂȂ邪�A�����ӂ���ƁA���ӍH���ŕK�R�I�Ɂu�_�X�g�v���������A���f�B�X�N�p�̐��`�ޗ��Ƃ��邱�Ƃ͍���ł������B���A�������H�h�~�ܗނ�z�����ĕ��H��h�~������@�����邪�A�|���J�[�{�l�[�g�����ɖ��Q�ł��L�^���̕ی���[���ɍs���Y���܂́A�������o����Ă��Ȃ��B�i�b��Q���R���T�s�`�Q�P�s�A�b��P�O���j
�k���_���������邽�߂̎�i�l
�@�{�����҂�́A���̃n���Q�����Y�����f�̒ጸ�ƁA���e���E�ɂ��Č����������ʁA�u�_�X�g�v�̑����������I�ɖh�~�����n���Q�����Y�����f�̏����@�����o���A�{�����ɓ��B�����B���Ȃ킿�A�{�����́A�W�N�������^����n�}�Ƃ��ăr�X�t�F�m�[���ƃz�X�Q���Ƃ̔����ɂ���ē����A��_�X�g�����ꂽ�|���J�[�{�l�[�g�����n�t�ɁA�|���J�[�{�l�[�g�����̔��͕n�n�}�Ƃ��āA���|�w�v�^���A�V�N���w�L�T���A�x���[�����̓g���G���𒾓a�������Ȃ����x�̗ʂ������A����ꂽ�ψ�n�t��45�`100���ɕۂ����h�a���̐����ɓH�������͕������ăQ�������A�n�}�𗯋����đ��E���̕����̂Ƃ�����A�������A�������A���o���ē�����|���J�[�{�l�[�g�����ł����āA�Y�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^����1ppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��ł���B�i�b��Q���R���Q�Q�s�`�R�V�s�A�b��P�O���j
�k�����̍�p����ь��ʁl
�@�ȏ�A�{�����̃|���J�[�{�l�[�g�������`�ޗ��ɂ����f�B�X�N�́A�L�^���̍ގ��ɂ�炸�����M�����ɗD�ꂽ���̂ƂȂ邱�Ƃ����Ăł���A�������������ɂ����Ďg�p���邱�Ƃ�]�V���������ꍇ�ɂ��A���S���Ďg�p�\�Ȃ��̂ł���A���̍H�ƓI�Ӌ`�͋ɂ߂č������̂ł���B�i�b��Q���V���R�s�`�W���S�s�A�b��P�O���j
�@�{�����������ɂ����ẮA�{�����������̑ΏۂƂȂ镨�́A�{���\���v���ɂ��\���ɓ��肳��Ă���B���̂��Ƃ́A�{�����������̏�L�L�ڂ��疾�炩�ł���B�{�����������ɂ�����{�����@�v���́A�{�������̑Ώۂł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��̍\������肷�邽�߂̗v���Ƃ��ẮA�|���J�[�{�l�[�g�������Ɋ܂܂��ʂ��Pppm�ȉ��Ƃ���Ă���W�N�������^�����A�r�X�t�F�m�[���ƃz�X�Q���Ƃ̔����ɂ���ă|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ���������ۂ̏d���n�}�ł��邱�Ƃ��Ӗ�����ȊO�ɂ́A���i�̈Ӗ���L������̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�v����ɁA�{�����@�v���́A�{�������̑Ώۂł���u�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��B�v�����邽�߂̕��@��P�ɓ��������͈̔͂ɋL�ڂ������̂ɂ������A����ȏ�ɏo����̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�����ł���ȏ�A���̔����ł���{�����������ɓ�����t�^����v���ƂȂ�V�K�����邢�͐i�������f����ɓ������ẮA�{�����@�v���́A�{�����������̍\������肷��v���Ƃ��ẮA��L�̒��x�̈Ӗ������L���Ă��Ȃ����Ƃ�O��Ƃ�����ŁA����f���ׂ����ƂɂȂ�̂́A���R�ł���B
�Q�@������R�P�i�{�����������ƈ��p�����P�Ƃ̈�v�_�̔F��̌��j�A������R�Q�i�{�����������ƈ��p�����P�Ƃ̑���_�̊ʼn߁j�A������R�R�i ����_�Q�i���E���̂̌`���̗L���j�ɂ��Ă̔��f�̌��j�y�ю�����R�T�i����_�P�i�Ō`���n�}�̑���j�ɂ��Ă̔��f�̌��j�ɂ���
(1)�@�����́A�@������R�P�Ƃ��āA�R���́A�{�����������ƈ��p�����P�Ƃ̈�v�_�ɂ��āA�u���s���P�ɂ́u�H���v�����́u�����v�Ƃ�����͋L�ڂ���Ă��Ȃ����A�u���̗n�t���A���M���i�������E�u���M���v�̌�L�ƔF�߂���B�j�̉����ɓY�����A�n�}�y�ьŌ`���p�n�}��ʏ�0.1�`1.0���ԁA�D�܂�����0.5�`1.0���Ԃŗ�������悤�ɓY������v�i�E���������j�ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ���A���s���P�ɋL�ڂ��ꂽ�������u�H���v���Ă�����̂Ɖ����邱�Ƃ������ł���A���̓_�ŁA�������͈�v����B�v�i�R�����V�łS�s�`�X�s�j�ƔF�肵�����A���ł���A���s���P�ɋL�ڂ��ꂽ�u��������悤�ɓY������v���@���u�H�������͕����v�ł���Ƃ͌���Ȃ��A���s���P�ɂ́A�ǂ��Ɠ���Ă��A�����ÂA���I�ɓ���Ă��A�܂��A�o�b�`���ɓ���Ă��A�v����Ɂu��������悤�ɓY������v���Ƃ��ł���悢���Ƃ��J������Ă���ɂ������A�ǂ̂悤�ȕ��@�œY���������Ƃ������Ƃɂ��ẮA�����L�ڂ���Ă��Ȃ��A�Ǝ咣���A�A������R�Q�Ƃ��āA�R���́A�u���s���P�ɋL�ڂ��ꂽ�����́A�Ō`���̍ۂɁA�u�Ō`���ߒ��̉t���������Ӌ@�ɏz����v�H����K�{�̍\���v���Ƃ��Ă���̂ɑ��A������̖{�������́A�Y�H����K�{�̍\���v���Ƃ��Ă��Ȃ��_�ňꉞ���Ⴗ�邪�A������̖{�������Ɂu���̐��X�����[������ۂɁA�Q�������q��K�X�A�g�U���⎼�����Ӌ@�ɂ���ĕ��ӂ��s�����Ƃ́E�E�E�D�܂������@�ł���B�v�i��������S���P�O�s�`�P�S�s�j�ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ���A�����I�ȑ���_�ł͂Ȃ��B�v�i�R�����V�łP�R�s�`�P�X�s�j�ƔF�肵�����A���ł���A�R���́A�{�����������ƈ��p�����P�Ƃ̖ړI�i�ۑ�j�̑�����ʼn߂��A���̍\���̓_�݂̂��画�f�������߁A���p�����P���u�Ō`���ߒ��̉t���������Ӌ@�ɏz����v�H����K�{�Ƃ���_���A�����I�ȑ���_�ł͂Ȃ��Ɗʼn߂������̂ł���A�Ǝ咣���Ă���B
�@�@�������Ȃ���A�{�����������́u�H�������͕����v�Ƃ̗v���i������R�P�j�A�́A�{�����@�v�����̗v���ł���A�܂��A�Ō`���ߒ��ɂ����āu�������Ӌ@�v�ɂ���ĕ��ӂ���s����K�{�̗v���Ƃ��邩�ǂ������i������R�Q�j�A�������@���̂��̂Ɋւ��鎖���ł���A��������{�����������̑ΏۂƂȂ镨�̍\���A���Ȃ킿�u�d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��v����肷���ł͓��i�̈Ӗ���L���Ȃ��v���ł��邱�Ƃ́A�{�����������̏�L�L�ڂ��疾�炩�ł���B�����̏�L�咣�́A�{�����@�v�����̑O�L�̊e�v�����A���@�Ƃ��Ċ��s���P�ɊJ������Ă��Ȃ��Ƃ̎咣�A���邢�́A���������������@�Ƃ��ĈقȂ���̂ł���Ƃ̎咣�ł���ɂ����Ȃ��B�O�ɏq�ׂ��Ƃ��납�疾�炩�Ȃ悤�ɁA���̔����ł���{�����������̓����v����_����ɓ�����A���̂悤�ȕ��̍\������肷���œ��i�̈Ӗ��̂Ȃ����@�v���Ɋւ��A�������@�Ƃ��Ă̐V�K�����邢�͐i�����������邩�ǂ����ɂ��Ă̋c�_������K�v�͑S���Ȃ��̂ł��邩��A�����̎咣�����L������R�́A��������咣���̂ɂ����Ċ��Ɏ����ł���B
�@�@�R���́A�{�����������̐i�����f����ɓ������āA�{���\���v���݂̂Ȃ炸�A�{�����@�v���ɌW���L�v���ɂ��Ă����f���Ă���B�������A�R���̂��̔��f��@���q�ϓI�ɕ]������A�R���́A�{�����f���ׂ����̘_�_�ɉ����A�{�����f����K�v�̂Ȃ��_�_�ɂ��Ă��O�̂��߂ɔ��f�����A�Ƃ������ƂɂȂ�ɂ����Ȃ��B
(2) �����́A�@������R�R�Ƃ��āA�R���́A�{�����������ƈ��p�����P�Ƃ̑���_�̈�Ƃ��āA�u������̖{�������́A�u���E���v�Ƃ���Ă��邪�A���s���P�ɂ́A�u���E���v�Ƃ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��_�v�i�R�����V�łQ�W�s�`�Q�X�s�j��F�肵�A����𑊈�_�Q�Ƃ�����ŁA���̑���_�Q�ɂ��āu���s���P�ɂ́A�u���E���v�Ƃ�����͂Ȃ����A�|���J�[�{�l�[�g�����n�t���h�a���̉������ɓY���A�n�}�𗯋����Ȃ���A�|���J�[�{�l�[�g�������Ō`�����Ă���̂ł��邩��A�Y�|���J�[�{�l�[�g�����́A�n�}�̗����ɂ�萶�������E���̕����̂ł�����̂Ɖ����邱�Ƃ������ł���B�v�i�R�����W�łV�s�`�P�O�s�j�Ɣ��f�������A���ł���A�R�����́A�{�����������ƈ��p�����P�Ƃ̊Ԃɂ́A�܂��̑���_������ƔF�肵�Ă��邱�Ƃ����������悤�ɁA���҂̕��@�͈قȂ�̂ł���B����䂦�ɂ����A���p�����P�̂��̂̓r�[�Y��ł���A�{�����������̂��̂͑��E���̕����̂ƂȂ�̂ł���A�Ǝ咣���A�A������R�T�Ƃ��āA�R���́A�{�����������ƈ��p�����P�̑���_�̈�Ƃ��āA�u������̖{�������́u���͕n�n�}�v�́A�u���|�w�v�^���A�V�N���w�L�T���A�x���[�����̓g���G���v�ƌ��肳��Ă���̂ɑ��A���s���P�ɋL�ڂ��ꂽ�����ł́A�u�Ō`���n�}�v�̋�̗�Ƃ��āA���|�w�L�T�����L�ڂ���Ă��邾���ŁA���|�w�v�^�����̏�L���肳�ꂽ�����������L�ڂ���Ă��Ȃ��_�v�i�R�����U�łQ�T�s�`�Q�W�s�j��F�肵�A����𑊈�_�P�Ƃ�����ŁA���̑���_�P�ɂ��āA�u���s���P�ɋL�ڂ��ꂽ�����ɂ����āA�u�Ō`���p�n�}�v�Ƃ��āA���|�փL�T���ȊO�̕�����p���悤�Ƃ���Ƃ��ɁA�b��S���i�������E���s���S�j�ɋL�ڂ��ꂽ�|���J�[�{�l�[�g�����̕n�n�}���A�Ȃ��ł��A���{��Ƃ��ėp�����Ă��镨�����܂��p���Ă݂邱�Ƃ́A���Ǝ҂��e�Ղɑz�����邱�Ƃł���B�v�i���X�łP�X�s�`�Q�Q�s�j�Ɣ��f�������A���ł���A���p�����P�́A�O�q�̂Ƃ���A�u�S�~�v�̏��Ȃ��|���J�[�{�l�[�g��������邱�Ƃ����̖ړI�i�ۑ�j�Ƃ�����̂ł���A�{�����������́A�W�N�������^���̏��Ȃ��|���J�[�{�l�[�g��������邱�Ƃ�ړI�i�ۑ�j�Ƃ�����̂ł��邩��A���҂͂��̖ړI�i�ۑ�j���قɂ��Ă���A���s���S�ɋ�̓I�ɋL�ڂ���Ă��钾�a�@�́A�|���J�[�{�l�[�g�����̃W�N�������^���n�t�ɂ��|�w�v�^���Ȃǂ̕n�n�}�ړY�����āA�|���J�[�{�l�[�g�����̒��a��Ƃ������̂ł���i���s���S�̎��{��P�`�S�j�̂ɑ��A�{�����������ɂ����钾�b�@�́A�|���J�[�{�l�[�g�����̃W�N�������^���n�t�ɔ邢�͕n�n�}���u���a�������Ȃ����x�̗ʁv�Y�����A���̍����n�t�������ɓH�����邢�͕������ăQ����������̂ł���A���҂̒��a�@�́A���Ⴕ�Ă���̂ł��铙�A�Ǝ咣���Ă���B
�@�@�������Ȃ���A�{�����������́u�Q�������A�n�}�𗯋����đ��E���̕����̂Ɓv����Ƃ̗v���i������R�R�j�y�сu���͕n�n�}�Ƃ��āA���|�w�v�^���A�V�N���w�L�T���A�x���[�����̓g���G�����E�E�E�����v�Ƃ̗v���i������R�T�j�́A��������A�{�����@�v�����̗v���ł����āA�{�����������̑ΏۂƂȂ�u�d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��v����肷���ł͓��i�̈Ӗ���L���Ȃ��v���ł��邱�Ƃ́A�O�q�̂Ƃ���A�{�����������̋L�ڂ��疾�炩�ł���B�����̏�L�咣�́A�{�����@�v�����̑O�L�̊e�v�����A���@�Ƃ��Ċ��s���P�ɊJ������Ă��Ȃ��Ƃ̎咣�A���邢�́A�������͐������@�Ƃ��ĈقȂ���̂ł���Ƃ̎咣�ł���ɂ����Ȃ��B���̔����ł���{�����������̓����v����_����ɓ�����A���̂悤�ȕ��̍\������肷���œ��i�̈Ӗ��̂Ȃ����@�v���Ɋւ��A�������@�Ƃ��Ă̐V�K�����邢�͐i�����������邩�ǂ����ɂ��ċc�_������K�v�͑S���Ȃ����ƁA�y�сA�R�����A�{���A���f����K�v�̂Ȃ��{�����@�v���ɌW���L�v���ɂ��Ă��O�̂��߂ɔ��f�����ɂ����Ȃ��A�ƕ]����������̂ł��邱�Ƃ́A�O�q�̂Ƃ���ł���B
�@�@�����́A������R�T�Ɋւ��A�{�����������́A���@����t���́u���v�̔����ł���A�{�����������̂悤�ȃ|���}�[�����ɂ��Ă̔����ɂ����ẮA�|���}�[�̊e��̓������A�P���Ƀ|���}�[�̌J��Ԃ��P�ʂ╪�q�ʂ݂̂ɂ����肳��邱�ƂȂ��A�|���}�[�̖��x�⌋�����◧�̓I�Ȕz�u�Ȃǂ̊e��̕��G�Ȑ���ɂ����肳��邱�Ƃ����X����A�����̕��G�Ȑ���̂��ׂĂ���ɉ𖾂����Ƃ͌���Ȃ����Ƃ���A�������@�ɂ��|���}�[��������肷��ق������D�܂����ꍇ��A�������@�ɂ��Ȃ���A�\���ȓ��肪�ł��Ȃ��ꍇ�����邱�Ƃ́A�悭�m���Ă���Ƃ���ł���A�{�����������́A�������@�ɂ����肳�ꂽ�|���}�[��������Ȃ鐬�`�ޗ��Ɋւ�����̂ł���A���̂悤�Ȑ������@���A�{�����������̃|���}�[�������Z�p�I�ɓ��肵�Ă���̂ł���A�Ǝ咣����B
�@�{�����������̌����̋L�ڂ𗣂�āA������v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���i�����̂����u���@����t���́u���v�̔����v�j�ɂ��Ă̈�ʘ_�Ƃ��Ă݂����A�{�����������̃|���}�[�����������咣�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ė�������̂������I�ł���ꍇ���\�����݂�����Ƃ������Ƃ��ł��悤�B�������A���́A�{�����������ɂ����āA�{�����@�v�����ǂ̂悤�ȈӖ���L������̂Ƃ���Ă��邩�A�Ƃ������Ƃł���B���̖��𗣂�āA��ʘ_�݂̂ɂ���āA�{�����@�v�����{�����������̃|���}�[�������Z�p�I�ɓ��肵�Ă���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł���B�����āA�{�����������ɂ́A�{�����@�v���̗L����Z�p�I�Ӌ`�Ɋւ�����̂Ƃ��ẮA�u�R���p�N�g�f�B�X�N�p�̃|���J�[�{�l�[�g���`�ޗ��ɂ����Ă͏]�����Ƃ���Ȃ����������ł���n���Q�����Y�����f���L�^���H�j�������錴���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ����o���v�i�b��Q���R���W�s�`�P�P�s�A�b��P�O���j�A�n���Q�����Y�����f��ጸ������{�����@�v���L�ڂ̐��@�ɂ��A�u�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���^�ޗ��v�i�b��Q���R���R�S�s�`�R�V�s�A�b��P�O���j�Ƃ̍\���̖{�����������Ɏ������Ƃ̋L�ڂ͂��锽�ʁA�����咣�̂悤�ɁA�{�����������̃|���J�[�{�l�[�g�������A�|���}�[�̖��x�⌋�����◧�̓I�Ȕz�u�Ȃǂ̊e��̕��G�Ȑ��ɂ�肻�̓��������肳�����̂ł��邱�Ƃ��q�ׂ��L�ڂ��A���̂��Ƃ���������L�ڂ��Ȃ��A�܂��āA���̂��Ƃ�O��ɁA�{�����������́A�u�|���J�[�{�l�[�g�������ɊܗL�����d���n�}�ł���W�N�������^�����Pppm�ȉ��ł�����f�B�X�N�p�|���J�[�{�l�[�g���^�ޗ��v���ׂĂł���킯�ł͂Ȃ��A���̒��̈ꕔ�ł���{�����@�v���ɂ�萻�����ꂽ���̂Ɍ����邱�Ƃ��q�ׂ��L�ځA���邢�́A�������������L�ڂ͂Ȃ��B������v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���̌`�ɂ������悤�Ƃ���҂́A�����̑Ώۂ@�Ƃ��Ȃ��ŕ��Ƃ��邱�Ƃ����炩�̗��R�Ŏ���I�������ȏ�A���Y���͓��Y���@�ɂ���Đ������ꂽ���̂Ɍ����邱�Ƃ��咣���悤�Ƃ���Ȃ�A���̂��Ƃ��o��ɌW�閾���ɂ����Ė������ׂ��ł���A��������Ȃ��ŁA�����̋L�ڂ𑼂̉��߂̗]�n���c�����̂Ƃ��Ă����Ȃ���i�Ⴆ�A�N�Q�i�ׂɂ����āA���Y�����̑ΏۂƂȂ镨�́A���Y���@�ɂ���Đ������ꂽ���̂ɂ͌����Ȃ��A���̎咣�����邱�Ƃ��l������B�j�A���̂悤�Ȏ咣�����邱�Ƃ́A������Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B���ǂ̂Ƃ���A�����̖{�����������Ɋւ����L�咣�́A�{�����������Ɋ�Â��Ȃ��咣�Ƃ����ׂ��ł���A���咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(3) �ȏ�ɂ��A�����̎�����R�P�A������R�Q�A������R�R�y�ю�����R�T�̊e�咣�́A�{�����������̑ΏۂƂȂ镨�̍\������肷���œ��i�̈Ӗ��̂Ȃ��{�����@�v���Ɋւ��A���@�Ƃ��Ă̐V�K���A�i�����ɂ��Ă̋c�_�����ׂ��ł���Ƃ̎咣�ł��邩��A�����̎�����R���A�R���̌��_�ɉe����^�������r�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����̂ł��邱�Ƃ́A���炩�ł���A����������̎咣���̎����ł���Ƃ����ȊO�ɂȂ��B
�Q�l�����F�@����18�N(�s�P)��10494��
�u�P�N���[�����R�b�d�`�R�̂S�v�������N�Q���~��������
��������v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���̋Z�p�I�͈͂́A��̓I�Ȑ������@���킸�A���̕��Ɠ��ꐫ��L���镨�̂��ׂĂɋy�ԂƂ͌���Ȃ��Ƃ�������B��
| �����ԍ� | �@����11�N(��)��8434�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������� |
| �ٔ��N���� | �@����12�N09��29�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
�@��@������́A�{�����������͈̔͂́A�������@�ɂ���ē��肳�ꂽ���̓����ɂ��Ă̂��́i������v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���j�ł���A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�������@�ƈقȂ鐻�����@�ɂ����̂ł����Ă��A���Ƃ��ē���ł�����̂́A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ƃ���A�퍐���i�́A���Ƃ��ē���ł��邩��{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ǝ咣����̂ŁA���f����B
�P�@���߂̎w�j
�@��ʂɁA���������͈̔͂��������@�ɂ���ē��肳�ꂽ���̂ł����Ă��A�����̑Ώۂ͖O���܂Ő������@�ɂ���ē��肳�ꂽ���ł��邩��A�����̑ΏۂY�������@�Ɍ��肵�ĉ��߂���K�R���͂Ȃ��B�������A�����̑ΏۂY�������@�Ɍ��肵�ĉ��߂��ׂ����������ꍇ�ɂ́A�����̑Ώۂ����Y�������@�Ɍ��肳���ꍇ�����蓾��Ƃ����ׂ��ł���B
�Q�@�{�����������͈̔͂̋L��
(��)�@�{�����������͈̔͂́A�u���̐������@���L�ڂ��������v�Ɓu���̐������L�ڂ��������v�i���َ����R���̌̔���ٓI�ȕ�������ѐ��핳�֍R���Q�Ƃ̔�������L���邪�A���َ����R���̌̓��ٓI�ȕ����A���핳�֍R���P����є���ٓI���������R���Ƃ̔�������L���Ȃ��P�N���[�����R�́i�R�̂S�j�B�j�ɕ������A�O�҂́u���̐������@���L�ڂ��������v�́A�X�Ɂu�Z���זE�̎擾�ߒ��v�i��P�M���������ŏ��̌̂̊��َ����R���ŖƉu���邱�Ƃɂ���āA�O�L�R���ɑ���R�̎Y���\��L����זE���Y�������A�������זE�����̚M����������̎悵�A�̎悳�ꂽ�זE���Q�M�������R���̃~�G���[�}�̊����זE�ƗZ�������A�j�A�u�P�N���[�����R�̂̉���ߒ��v�i�������ē���ꂽ�Z���זE���N���[�j���O�ɕt���A����ꂽ�P�N���[�����n�C�u���h�[�}��|�{���A����ꂽ�|�{�t���珊�]�̒P�N���[�����R�̂�������A�j�y�сu����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�i���̍�(�C)�O�L�ŏ��̌̂̊��َ����R�����P�}�[�J�[�R���Ƃ��ėp���A�O�L�P�N���[�����n�C�u���h�[�}��O�L��P�}�[�J�[�R���Ɣ�������R�̂̎Y���\����Ƃ��đI�ʂ��A(��)�O�L����H���ɂ����āA�Ɖu�����ŏ��̌̈ȊO�̌̂̊��َ����R���A���핳�֍R���P�A���핳�֍R���Q����є���ٓI���������R������Ȃ�Q����I�ꂽ�Q��ȏ�̍R����I�ʗp�}�[�J�[�R���Ƃ��ėp���āA�O�L�P�N���[�����n�C�u���h�[�}��I�ʗp�}�[�J�[�R���Ƃ̔���������Ƃ��đI�ʂ��A�����̍�(�n)���핳�֍R���Q���Q�}�[�J�[�R���Ƃ��ėp���ĒP�N���[�����n�C�u���h�[�}��I�ʂ��A���핳�֍R���Q�Ɣ�������R�́i�R�̂a�j�Y���\�����P�N���[�����R�̂����A���ɐ��핳�֍R���P���R�}�[�J�[�R���Ƃ��ėp���Đ��핳�֍R���P�Ɣ������Ȃ��R�̎Y���\�����P�N���[�����n�C�u���h�[�}�����A���ɔ���ٓI���������R�����S�}�[�J�[�R���Ƃ��ėp���Ĕ���ٓI���������R���Ƃ̔��������L���Ȃ��R�̎Y���\�����P�N���[�����n�C�u���h�[�}�����A�I�ʂ��ꂽ�P�N���[�����n�C�u���h�[�}��|�{���ď��]�̍R�̂�H������Ȃ�A���َ����R���ɑ��ē��ِ������P�N���[�����R�̂̐��@�ɂ���ē���ꂽ�A�j�ɕ�������B
(��)�@�u���̐������@���L�ڂ��������v�̂����u�Z���זE�̎擾�ߒ��v�y�сu�P�N���[�����R�̂̉���ߒ��v�ɂ���
�@�O�L��Q�ŔF�肵���{�������̋L�ڋy�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��ƁA�u���̐������@���L�ڂ��������v�̂����u�Z���זE�̎擾�ߒ��v�y�сu�P�N���[�����R�̂̉���ߒ��v�́A���m�̋Z�p�ł���ƔF�߂���B
(�O)�@�u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�Ɓu���̐������L�ڂ��������v�ɂ���
�@�O�L��Q�ŔF�肵���{�������̋L�ڂɂ��ƁA�b�d�`���q��ɂ͑����̍R���������݂��邱�ƁA������́A�E�b�d�`���q��̑����̍R����������ށi�̓��ٓI�R�������A�b�d�`���ٌ����A�m�e�`�|�P���ʌ����A�m�e�`�|�Q���ʌ����A�m�b�`���ʌ����j�ɕ��ނ����邱�Ƃ��Ă������ƁA�u���̐������L�ڂ��������v�́A�E������̒�ĂɌW�镪�ނ�O��Ƃ��锽�����ِ�����e�Ƃ�����̂ł��邱�ƁA�ȏ�̎������F�߂���B
�@�O�L��Q�ŔF�肵���{�������̋L�ڂɂ��ƁA�u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�́A�E�̌�ނ̍R�������Ƃ̔������ِ����m�F����ߒ��ł����āA�u���̐������L�ڂ��������v�ɂ���āA��ނ̍R�������Ƃ̈��̔������ِ��������Ƃ����v�f�ɂ����肳�ꂽ�P�N���[�����R�b�d�`�R�̂��A�X�ɕ��̐������قȂ���̂Ƃ��ē��肷����̂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł���i���̌��x�ł́A������̑O�L�咣�́A�����ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�j�B
�R�@�{�������̏o��o��
�@�O�L��P�̎����ɂ��ƁA�{�������́A�{�����o��ɂ��āA�������̋��⍸�������ɁA�����o�肵�A�{�����������͈̔͋L�ڂ̂��̂Ƃ��ē������ꂽ���ƁA������́A�E�o��ߒ��ɂ����āA�u����́A���@�ł���ꂽ���Ƃ��ē��肳�ꂽ�{�����̓��������Î������Ă��Ȃ��B�v�ȂǂƏq�ׂāA���m�Z�p�Ƃ̕��@�̈Ⴂ���������Ă������ƁA�{�����������͈̔͂̋L�ڂ́A�{�����o��̓��������͈̔͂̋L�ڂɔ�ׂāA�u���@�ɂ���ē���ꂽ�v���Ƃ�����ȂǁA����̐��@�ɂ����̂ł��邱�Ƃm�ɂ�����e�ɂȂ��Ă��邱�ƁA�ȏ�̎������F�߂���B
�S�@���_
�@�{�����o�肪�s��ꂽ�����̓����@�O�Z���܍��́A���������͈̔͂ɂ��āA�u�����̏ڍׂȐ����ɋL�ڂ��������̍\���Ɍ������Ƃ��ł��Ȃ������݂̂��L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肵�Ă�������A�{�����������͈̔͂̋L�ڂ��A���̂悤�Ȃ��̂ł���Ɖ������B
�@������Ƃ���A�����炪�咣����悤�ɁA�u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�́A���̐����i�������ِ��j�����@�i�I�ʕ��@�j�ɂ���Ċm�F���Ă��邾���ł��邩��A�u���̐������L�ڂ��������v�݂̂��[�����Ă���A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ƃ���ƁA�u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�͑S�����Ӗ��ȋL�ڂł���Ƃ������ƂɂȂ�A�����@�O�Z���܍��̉E�v���ɓK�����Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�́A�u���̐������L�ڂ��������v�Ƃ͕ʂ̈Ӗ���L������̂Ɖ����Ȃ���Ȃ炸�A��������ƁA�u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v�́A�u���̐������L�ڂ��������v�œ��肳��镨�̋�̓I�Ȑ������@����肵�����̂Ɖ�������Ȃ��B�����āA���̂悤�ɉ����邱�Ƃ��A�E�R�ŏq�ׂ��{�������̏o��o�߂ɂ��K������Ƃ������Ƃ��ł���B�ȏ�̂Ƃ���A�{���ɂ����ẮA�����̑ΏۂY�������@�Ɍ��肵�ĉ��߂��ׂ����������Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�@������Ƃ���A�퍐���i�̐������@���A�{�����������͈̔͒��́u���̐������@���L�ڂ��������v�́u����ꂽ�P�N���[�����R�̂̑I�ʉߒ��v���[�����邱�Ƃɂ��Ă̎咣���͂Ȃ�����A�퍐���i���{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�Q�l�����@�u�_�����^���p�N���v�������N�Q���~��������
��������v���_�N�g�E�o�C�E�v���Z�X�E�N���[���̋Z�p�I�͈͂́A��̓I�Ȑ������@���킸�A���̕��Ɠ��ꐫ��L���镨�ɋy�Ԃ��A�퍐���i�͖{�������Ɠ���̍\���Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ��ĐN�Q��ے肵������B��
| �����ԍ� | �@����9�N(��)��8955�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������� |
| �ٔ��N���� | �@����11�N09��30�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
��� ���Ă̊T�v
�@�{���́A�u�_�����^���p�N���v�ɂ��Ă̓�������L���錴�����A�퍐�̐��������`�q�g���G���X���|�G�`���y�т�����g�p�������܂́A������������̉E��������N�Q������̂ł���Ƃ��āA�퍐�ɑ��A�����̐����̍��~�ߋy�єp���A���܂̔̔��̍��~�ߓ������߂Ă��鎖�Ăł���i�ȉ��A�G���X���|�G�`�����u�d�o�n�v�Ɨ��̂��邱�Ƃ�����B�j�B
�� �����̂Ȃ�����
�P �����́A��ɓ����i�y�т��̑��̐H�i���̔����A���i���̐����̔������ƂƂ��銔����Ђł���A�퍐�́A�r�[�����̎�ށA�H���i�y�ш��i���̐����̔����ƂƂ��銔����Ђł���B
�Q �����́A���L�̓������i�ȉ��u�{���������v�Ƃ����A���̔������u�{�������v�Ƃ����B�j��L���Ă���B
�@�@�L
�����̖��� �@�_�����^���p�N��
�o��N���� �@���a�ܔ��N����
�o��ԍ� �@�@���蕽��|�O�Z�Z��Z��
�����̕\�� �@���菺�ܔ��|��Z�O��㍆�̕���
�o�^�N���� �@�������N�܌��ꎵ��
�����ԍ� �@�@���܈��ܘZ�ꍆ
�i�����j
�Q �{���ɂ����ẮA�\���v�����{�������ɌW��_�����^���p�N���̐������@���f���Ă��邱�Ƃ���A�܂��A�{�������ɌW��_�����^���p�N�������̐������@�ɂ���ē���ꂽ���̂Ɍ��肳��邩�ǂ������A��������B
�@��ʂɁA���������͈̔͂��������@�ɂ���ē��肳�ꂽ���ł����Ă��A�ΏۂƂ���镨��������������̂ł���ꍇ�ɂ́A�����̑Ώۂ͖O���܂Ő������@�ɂ���ē��肳�ꂽ���ł����āA�����̑ΏۂY�������@�ɂ���Đ������ꂽ���Ɍ��肵�ĉ��߂���K�R�͂Ȃ��A����Ɛ������@�͈قȂ邪���Ƃ��ē���ł�����̂��܂܂��Ɖ����邱�Ƃ��ł���B�E�̂悤�ɉ����ׂ����Ƃ́A�������́u�����������x�y�ё������Ɋւ���^�p��i���a�܁Z�N��Z���j�v���A���������͈̔͂̋L�ڗv�̂ɂ��A�u�i�P�j ���w�����͓��肳��ċL�ڂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���w��������肷��ɂ������ẮA�����������͉��w�\�����ɂ���ĕ\�����邱�Ƃ������Ƃ���B�����������͉��w�\�����ɂ���ē��肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��́A�����I���͉��w�I�����ɂ���ē���ł���ꍇ�Ɍ���A�����̐����ɂ���ē��肷�邱�Ƃ��ł���B�܂��A���������A���w�\�������͐����݂̂ŏ\������ł��Ȃ��Ƃ��́A�X�ɐ������@�������邱�Ƃɂ���ē���ł���ꍇ�Ɍ���A�����i�̈ꕔ�Ƃ��Đ������@�������Ă��悢�B�������A�������@�݂̂ɂ�����͔F�߂Ȃ��B�v�ƒ�߂Ă����|�ɂ����v������̂ł���B
�@�{���ɂ����ẮA�O�L�F��̂Ƃ���A�\���v�����{�������ɂ����āu�����v�̈�Ƃ��ċL�ڂ���Ă��邱�Ɠ��ɏƂ炵�Ă��A�{�������ɌW��_�����^���p�N���́A�K�������\���v���Ɍf����ꂽ�������@�ɂ���ē���ꂽ���̂Ɍ��肳�����̂ł͂Ȃ��A���̐������@�ɂ���ē��肳��镨�Ɠ���̍\���Ȃ���������L�������A�\���v�����[������Ƃ����ׂ��ł���B
�i�����j
�S �����ŁA�\���v���ɂ���Ď����ꂽ�_�����^���p�N���̍\�����ɂ��āA�퍐��`�q�g���d�o�n��������[�����邩�ǂ�������������B
�@�퍐��`�q�g���d�o�n���\���v���̍\������L���镨���ł���Ƃ������߂ɂ́A�i�P�j�퍐��`�q�g���d�o�n���\���v���̐��@�ɂ���Č��ɐ�������Ă��鎖�����F�߂��邩�A���́A�i�Q�j�퍐��`�q�g���d�o�n���\���v���̍\�����A���Ȃ킿�A�r�c�r����������A�R�̂ɑ��錋������^���p�N���̗��̍\�����V�R�̃G���X���|�G�`���ƈقȂ��Ă��邱�Ƃ��F�߂���K�v������Ƃ���A�{���ɂ����ẮA������F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B
�u�A�C�X�N���[���[�U䕁v�������N�Q���~����������(�@�\�I�N���[���̉���)
| �����ԍ� | �@����15�N(��)��19733�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~���������� |
| �ٔ��N���� | �@����16�N12��28�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
(2) ���f
�A (�)�@�{�������́u���������͈̔́v�y�������P�z�ɂ́A�u�c�̂��蔲���ꂽ�V�N��䕂̒��ɃA�C�X�N���[�����[�U����A�S�̂��Ⓚ����Ă���A�C�X�N���[���[�U䕂ł����āA�Y�A�C�X�N���[���́A�O����䕂��𓀂��ꂽ���_�ŁA�_���L�����N���[��������o�Ȃ����x�̌`�ԕێ�����L���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���A�C�X�N���[���[�U䕁v�ƋL�ڂ���Ă���B
�@�����ł����u�A�C�X�N���[���v�̌�̈Ӌ`�ɂ��ẮA�{�������ɂ́A�u���������͈̔́v�̂ق��u�����̏ڍׂȐ����v���ɂ��A���ɂ�����`�����L�ڂ͂Ȃ�����A���̕����̒ʏ�L����Ӗ��Ɋ�Â��ĉ��߂��ׂ��Ƃ���A��L(1)�C�L�ڂ̎��T���̋L�ړ��e���Q�ނ���A�u�A�C�X�N���[���v�̌�́u�����A�N���[���Ȃǂ̓����i�ɍ����Ȃǂ̓��ނ������ėⓀ�������X�َq�v���Ӗ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B
(�)�@�����āA��L�́u���������͈̔́v�̋L�ڂɂ��A�{�����������́u�A�C�X�N���[���v�́A�u�O����䕂��𓀂��ꂽ���_�ŁA�_���L�����N���[��������o�Ȃ����x�̌`�ԕێ�����L���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���v���̂Ƃ���Ă���i�\���v���a�y�тb�Q�Ɓj�B
�@�������A���́u�O����䕂��𓀂��ꂽ���_�ŁA�_���L�����N���[��������o�Ȃ����x�̌`�ԕێ�����L���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���v�Ƃ̋L�ڂ́A�u�V�N��䕂̂܂܂̊O�ςƕ������c���A䕂��H���ɉ𓀂��n�߂Ă������ɏ[�U���ꂽ�A�C�X�N���[�����J�������痬��o�����Ƃ��Ȃ��A�H����̂ɕ֗��ł��v��i�{�������y�O�O�O�W�z�B�{������R���R�W�s�Ȃ����S�P�s�j�Ƃ����{�����������̖ړI���̂��̂ł���A���A�u�_���L�����N���[��������o�Ȃ����x�̌`�ԕێ����v�Ƃ��������́A�{�����������ɂ�����A�C�X�N���[���[�U䕂̋@�\�Ȃ�����p���ʂ�\�����Ă��邾���ł����āA�{�����������̖ړI�Ȃ������ʂ�B�����邽�߂ɕK�v�ȋ�̓I�ȍ\���𖾂炩�ɂ�����̂ł͂Ȃ��B
�@���̂悤�ɁA���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̍\������p�I�A�@�\�I�ȕ\���ŋL�ڂ���Ă���ꍇ�ɂ����āA���Y�@�\�Ȃ�����p���ʂ��ʂ�������\���ł���A���ׂĂ��̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂��Ɖ�����ƁA�����ɊJ������Ă��Ȃ��Z�p�v�z�ɑ�����\���܂ł��������̋Z�p�I�͈͂Ɋ܂܂꓾�邱�ƂƂȂ�A�o��l�����������͈͂��ē������ɂ��ی��^���錋�ʂƂȂ肩�˂Ȃ��B�������A���̂悤�Ȍ��ʂ������邱�Ƃ́A�������Ɋ�Â������҂̓Ɛ茠�͓��Y���������O�ɑ��ĊJ�����邱�Ƃ̑㏞�Ƃ��ė^������Ƃ��������@�̗��O�ɔ����邱�ƂɂȂ�B
�@���������āA���������͈̔͂��A��L�̂悤�ȍ�p�I�A�@�\�I�ȕ\���ŋL�ڂ���Ă���ꍇ�ɂ́A���̋L�ڂ݂̂ɂ���Ĕ����̋Z�p�I�͈͂𖾂炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł����A���Y�L�ڂɉ����Ė����̔����̏ڍׂȐ����̋L�ڂ��Q�ނ��A�����ɊJ�����ꂽ��̓I�ȍ\���Ɏ�����Ă���Z�p�v�z�Ɋ�Â��ē��Y�����̋Z�p�I�͈͂��m�肷�ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���B
�i�����j
�@�����̋L�ڂɂ��A�A�C�X�N���[���{���̐H����L���A���A�ʏ�̃A�C�X�N���[���̉𓀉��x�ɓ��B���Ă��n���Ȃ��`�ԕێ�����L����A�C�X�N���[���́A���Ȃ��Ƃ��A�ʏ�̃A�C�X�N���[���̑g���Ɋ��V�y�у��[�X�p����܂�Y�����邱�Ƃɂ�萻�����邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��J������Ă��邪�A�{�������ɂ����ẮA����ȊO�̕��@�ɂ���āA�A�C�X�N���[���{���̐H�������킸�A���A䕂��𓀂��ꂽ���ɂ��`�ԕێ������ێ����邱�Ƃ��ł���A�C�X�N���[�������邱�Ƃ��ł��邱�Ƃɂ��āA����̋L�ڂ��Ȃ��B
�@��L�̂Ƃ���A�{�����������̖ړI�́A�A�C�X�N���[���[�U䕂ɂ��ē��x�̒Ⴂ䕂��𓀂��ꂽ���ɂ��A䕂̒��ɏ[�U���ꂽ���x�̍����A�C�X�N���[�����_��ƌ`�ԕێ�����L���邱�Ƃɂ���Ƃ���A�{�������ɂ����ẮA��������{���邽�߂ɁA�ʏ�̃A�C�X�N���[���̐����ȊO�Ɂu���V�y�у��[�X�p����܁v��Y�����邱�Ƃ����A����ȊO�̐����ɂ��ĉ��猾�y���Ă��Ȃ��B����ɁA���V���A�C�X�N���[���ɓY������_�ɂ��āA�`�ԕێ�����^���邾���̗ʂ̊��V��Y�����������ł̓A�C�X�N���[���̐H���������Ă��܂����Ɓi�y�O�O�P�P�z�{������S���P�P�s�Ȃ����P�T�s�Q�Ɓj�A�A�C�X�N���[�����̊��V�̊������O�D�P�d�ʁ������ł���ƁA䕂̉𓀎��ɃA�C�X�N���[��������o��̂ōD�܂����Ȃ��A�O�D�S�d�ʁ�����ƃA�C�X�N���[���̐H�����v���v���Ƃ����e�͐��������D�܂����Ȃ����Ɓi�y�O�O�P�Q�z�{������S���P�X�s�Ȃ����Q�R�s�Q�Ɓj���w�E���A���[�X�p����܂�Y������_�ɂ��Ă��A���[�X�p����܂��Q�D�O�d�ʁ������ł���ƁA���V�̃v���v���������E������ʂ��Ȃ��A�R�D�O�d�ʁ�����ƃA�C�X�N���[�����ł��Ȃ�A�N���[�~�[�����Ȃ��Ȃ邱�Ɓi�y�O�O�P�S�z�{������S���R�X�s�Ȃ����S�R�s�Q�Ɓj���w�E����ȂǁA���̗p�@�ɂ��ďڍׂȐ������{���Ă���B�����āA��L�Q(1)�L�ڂ̂Ƃ���A�u�c�̂��蔲���ꂽ�V�N��䕂̒��ɃA�C�X�N���[�����[�U����A�S�̂��Ⓚ����Ă���A�C�X�N���[���[�U䕁v���̂́A�{�����������̓����o��O�̕����T�N�Ɋ��ɍL���̔�����āA���m�ł��������ƂɏƂ点�A�{�����������ɐi������F�߂�Ƃ���A�[�U����Ă���A�C�X�N���[�����u�O����䕂��𓀂��ꂽ���_�ŁA�_���L�����N���[��������o�Ȃ����x�̌`�ԕێ�����L���Ă��邱�Ɓv����������ɑ����Z�p�������J�������_�ɂ���Ƃ����ׂ��ł���B
�@��L�ɂ��A�{�����������ɂ�����u�O����䕂��𓀂��ꂽ���_�ŁA�_���L�����N���[��������o�Ȃ����x�̌`�ԕێ�����L���Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���v�A�C�X�N���[���ɊY�����邽�߂ɂ́A�ʏ�̃A�C�X�N���[���̐����̂ق��A���Ȃ��Ƃ��u���V�y�у��[�X�p����܁v���ܗL���邱�Ƃ��K�v�ł���Ɖ�����̂������ł���B
�i�����j
(�)�@�����āA���W�̂Q�ɂ��A�x���Ƃ������P�R�N�U���R���ɂ́A�ɐ��O�f�p�[�g�̌ڋq����̒����Ɋ�Â��A�������G�f�Ղ͑�����Ɂu�������̎��v���o�ׂ������Ƃ��F�߂��邩��A�{�����������́A�����o��i�����P�R�N�U���U���j�O�Ɋ��Ɍ��R���{����Ă������̂Ƃ����ׂ��ł���B
(3)�@�܂Ƃ�
�@��L�ɂ��A�{�����������́A�����@�Q�X���P���P���Ȃ����Q���̋K��Ɉᔽ���ē������ꂽ���̂ł���A���@�P�Q�R���P���Q������̖������R��L���邱�Ƃ����炩�Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{���������Ɋ�Â����~�߁A���Q�������̌�����̐����́A�����̗��p�ɓ����苖����Ȃ��B
�@�R�@���_
�@�ȏ�ɂ��A�퍐���i�́A�{���������̋Z�p�I�͈͂ɑ����Ȃ����̂ł��邪�A����ɉ����āA�{�����������͖������R��L���邱�Ƃ����炩�ł��邩��A�{���������Ɋ�Â�������̐����́A�����̗��p�ɓ�������̂Ƃ��ċ�����Ȃ��B
�R�������������(�u�����N���[���v�ɂ���)
| �����ԍ� | �@����18�N(�s�P)��10563�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N05��30�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@���̂悤�ȓ����@�̎�|�܂���ƁA�����U�N�����O�̓����@�P�V���Q���ɂ����u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����āv�Ƃ̕����ɂ��ẮA���̂悤�ɉ�����ׂ��ł���B
�@���Ȃ킿�A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������v�Ƃ́A�Z�p�I�v�z�̍��x�̑n��ł��锭���ɂ��āA�������ɂ��Ɛ��O��Ƃ��āA��O�҂ɑ��ĊJ���������̂ł��邩��A�����ł����u�����v�Ƃ͖������͐}�ʂɂ���ĊJ�����ꂽ�����Ɋւ���Z�p�I�����ł��邱�Ƃ��O��ƂȂ�Ƃ���A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������v�Ƃ́A���Ǝ҂ɂ���āA�������͐}�ʂ̂��ׂĂ̋L�ڂ𑍍����邱�Ƃɂ�蓱�����Z�p�I�����ł���A����A���̂悤�ɂ��ē������Z�p�I�����Ƃ̊W�ɂ����āA�V���ȋZ�p�I���������Ȃ����̂ł���Ƃ��́A���Y��́A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����āv������̂Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����āA���@�P�R�S���Q�����������ɂ����铯�l�̕����ɂ��Ă��A���l�ɉ�����ׂ��ł���A�������A���Ǝ҂ɂ���āA�������͐}�ʂ̂��ׂĂ̋L�ڂ𑍍����邱�Ƃɂ�蓱�����Z�p�I�����Ƃ̊W�ɂ����āA�V���ȋZ�p�I���������Ȃ����̂ł���Ƃ��́A���Y�����́A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����āv������̂Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����Ƃ��A�������͐}�ʂɋL�ڂ��ꂽ�����́A�ʏ�A���Y�������͐}�ʂɂ���ĊJ�����ꂽ�Z�p�I�v�z�Ɋւ�����̂ł��邩��A�Ⴆ�A���������͈̔͂̌��k��ړI�Ƃ��āA���������͈̔͂Ɍ����t������������s���ꍇ�ɂ����āA�t�������������������Y�������͐}�ʂɖ����I�ɋL�ڂ���Ă���ꍇ��A���̋L�ڂ��玩���ł��鎖���ł���ꍇ�ɂ́A���̂悤�Ȓ����́A���i�̎���̂Ȃ�����A�V���ȋZ�p�I���������Ȃ����̂ł���ƔF�߂��A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��ꂽ�͈͓��ɂ����āv������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł���̂ł���A�����ケ�̂悤�Ȕ��f��@���Ó����鎖�Ⴊ�������̂ƍl������B
�@�Ƃ���ŁA�����U�N�@����P�P�U�������W���P���ɂ��Ȃ��]�O�̗�ɂ��Ƃ���铯�@�ɂ������O�i�ȉ��u�����U�N�����O�v�Ƃ����B�j�̓����@�Q�X���̂Q�́A�����o��ɌW�锭�������Y�����o��̓��O�̑��̓����o��ł����ē��Y�����o���ɏo����J�����ꂽ���̂̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʂɋL�ڂ��ꂽ�����i�ȉ��u��蔭���v�Ƃ����B�j�Ɠ���ł���Ƃ��́A���̔����ɂ��Ă͓������邱�Ƃ��ł��Ȃ��|��߂Ă���Ƃ���A���@�����ɊY�����邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�����T�N�@����Q�U�������Q���S���ɂ��Ȃ��]�O�̗�ɂ��Ƃ���铯�@�ɂ������O�̓����@�P�Q�R���P���P���Ɋ�Â��������������Ƃ���邱�Ƃ�������邽�߂ɁA�����R���̔퐿���l���A���������͈̔͂̋L�ڂɂ��āA�u�������A�c�������B�v�Ȃǂ̏��ɓI�\���i������u�����N���[���v�j�ɂ���ē����o��ɌW�锭���̂�����蔭���Ɠ���ł��镔�������O��������𐿋�����ꍇ������B
�@���̂悤�ȏꍇ�A�������҂́A�����o�莞�ɂ����Đ�蔭���̑��݂�F�����Ă��Ȃ�����A���Y�����o��ɌW�閾�����͐}�ʂɂ͐�蔭���ɂ��Ă̋�̓I�ȋL�ڂ����݂��Ȃ��̂��ʏ�ł��邪�A�������͐}�ʂɋ�̓I�ɋL�ڂ���Ă��Ȃ���������������Ƃ�������ɂ��Ă��A�����U�N�����O�̓����@�P�R�S���Q�������������K�p����邱�Ƃɕς��͂Ȃ��A���̂悤�Ȓ������A�������͐}�ʂ̋L�ڂɂ���ĊJ�����ꂽ�Z�p�I�����ɑ��A�V���ȋZ�p�I���������Ȃ����̂ł���ƔF�߂������A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����āv��������ł���Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�@�������A���Ǝ҂ɂ���āA�������͐}�ʂ̂��ׂĂ̋L�ڂ𑍍����邱�Ƃɂ�蓱�����Z�p�I�����Ƃ̊W�ɂ����āA�V���ȋZ�p�I���������Ȃ����̂ł���Ƃ��́A���Y�����́A�u�������͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����āv������̂Ƃ������Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��Ƃ���A��L�C�ɂ��ƁA�{���e�����ɂ�������̔����ɂ��Ă��A�����i�`�j�`�i�c�j�y�ѓ��i�`�j�`�i�d�j�̑g�����̂����A���p�����̓��e�ƂȂ��Ă������̑g���������������ׂĂ̑g�����ɌW��\���ɂ����āA�g�p�����ߍ܂ɓ�n���Ŕ�����̃G�|�L�V������M�d���������Ƃ��ėp�������Ƃ��ő�̓����Ƃ��A���̂悤�ȃG�|�L�V�����̗��q���������v���|���}�[����ݍ��ޏ�ԂƂȂ邽�߁A�������v���|���}�[�̗n�𐫂�ቺ�������A�G�|�L�V�����ƍd���܂Ƃ̔��������Ⴂ�̂Ō�������ቺ�������A�I�����������t�ɐN����ɂ����Ȃ�ƂƂ��ɑg�����̕ۑ������������Ȃ�Ƃ������ʂ�t������̂ƔF�߂��A���p�����̓��e�ƂȂ��Ă������̑g���������O���邱�Ƃɂ���āA�{�������ɋL�ڂ��ꂽ�{�������O�̊e�����Ɋւ���Z�p�I�����ɉ��炩�̕ύX�������Ă�����̂Ƃ͂����Ȃ�����A�{���e�������{�������ɊJ�����ꂽ�Z�p�I�����ɐV���ȋZ�p�I������t���������̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���A�{���e�����́A���Ǝ҂ɂ���āA�{�������̂��ׂĂ̋L�ڂ𑍍����邱�Ƃɂ�蓱�����Z�p�I�����Ƃ̊W�ɂ����āA�V���ȋZ�p�I���������Ȃ����̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@���������āA�{���e�����́A�����U�N�����O�̓����@�P�R�S���Q�����������ɂ����u�菑�ɓY�t�����������͐}�ʂɋL�ڂ��������͈͓̔��ɂ����āv������̂ł���ƔF�߂���B
�u�����N���[���v�Ɋւ���Q�l��������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10065�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��31�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�R�������������(�u�l�H����v����)
�����{��̒lj��ƍ����D�挠�咣�̌��ʂɂ��āB��
| �����ԍ� | �@����14�N(�s�P)��539�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����15�N10��08�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�@�@�@�@�@�@��@�@��
�@�@�����̐��������p����B
�@�@�i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�����y�ї��R
��P�@����
�@���������s���Q�O�O�P�|�Q�O�P�Q�O�������ɂ��ĕ����P�S�N�X���P�Q���ɂ����R�����������B
��Q�@�����ҊԂɑ����̂Ȃ�����
�@�P�@�������ɂ�����葱�̌o��
�@�����́A�����P�O�N�P�O���Q�O���̏o��i���蕽�P�O�|�R�P�U�W�X�X���A�ȉ��u��̏o��v�Ƃ����B�j�̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʁi�ȉ��u�����������v�Ƃ����B�j�ɋL�ڂ��ꂽ�����Ɋ�Â��A�����@�S�P���ɂ��D�挠���咣���āA�����P�P�N�P�O���W���A���̂��u�l�H����v�Ƃ��锭���ɂ������o���i���蕽�P�P�|�Q�W�W�T�R�T���A�ȉ��u�{���o��v�Ƃ����B�j���������A����̍��肪����A�����P�R�N�P�O���P�Q���ɂ��̓��{�̑��B�����̂ŁA���N�P�P���W���A����ɑ���s���̐R���̐��������A�s���Q�O�O�P�|�Q�O�P�Q�O�������Ƃ��ē������ɌW�������B
�@�������́A�������ɂ��ĐR���������ʁA�����P�S�N�X���P�Q���A�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R�������A���̓��{�́A�����Q�T���A�����ɑ��B���ꂽ�B
�@�Q�@���������͈̔͂̋L��
�@�@�@�@(1)�@��̏o��̓����������i�b�R�Y�t�j�ɋL�ڂ̂���
�@�@�@�@�@�y�������P�z�����ƁA���̓�������ˏo���Č`������Ă���������Ƃ�L����l�H����ł����āA��L�������y�с^���͏�L�����̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ�ɐL������L������������Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���l�H����B
�@�@�@�@�@�y�������Q�z��L�L�����ɗאڂ��āA���̐L������荄���̂��鍄�������݂����Ă��邱�Ƃ�����Ƃ��鐿�����P�ɋL�ڂ̐l�H����B
�@�@�@�@�@�y�������R�z��L�L�����Ə�L�����������݂ɔz�u����Ă��邱�Ƃ�����Ƃ��鐿�����Q�ɋL�ڂ̐l�H����B
�@�@�@�@�@�y�������S�z��L�l�H���V���R���S���ɂ��`������Ă���Ƌ��ɁA���̃V���R���S���̌��݂��A��L�L�����ł͔�r�I�����A��L�������ł͔�r�I�������Ƃ�����Ƃ��鐿�����Q���͐������R�ɋL�ڂ̐l�H����B
�@�@�@�@(2)�@�����P�R�N�W���V���t���葱����i�b�S�Y�t�j�ɂ�����ꂽ�{���o��̖����ɋL�ڂ̂���
�@�@�@�@�@�y�������P�z���c���̚M���|�ɓ��ډ\�Ȑ�[����L����������ƁA���c������ɂ��従��^�����s���ۂɐ��g���悤�Ɉړ������邱�Ƃ��ł���\�ʂ�L����������y�ѓ����ƁA�M���r�Ɛڑ����邽�߂̃x�[�X���ƁA��L����l�H����ł����āA�O�L�������y�ѓ����̃V���R���S�����琬��ǖʂ̓����ɁA���̕ǖʂ������̔����L�������`������A���̐L�����ɗאڂ��āA���̐L���������������������������݂Ɍ`������Ă��邱�Ƃ�����Ƃ���l�H����B
�@�@�@�@�@�y�������Q�z�O�L�L�����́A�O�L���������A従��^���ŐL�шՂ��`������Ă���Ƌ��ɁA���̍������́A���̐L�������ׂ��`������Ă��邱�Ƃ�����Ƃ��鐿�����P�ɋL�ڂ̐l�H����B
�@�@�@�@�@�y�������R�z�O�L�������̐�[���̒f�ʂ��~�ʏ�Ɍ`������A�O�L�����������o��Ɍ`������Ă��邱�Ƃ�����Ƃ��鐿�����P���͐������Q�ɋL�ڂ̐l�H����B
�@�@�@�@�@�y�������S�z�O�L�������ƑO�L�������ȖʂŘA�Ȃ��Ĉ�̓I�Ɍ`������Ă��邱�Ƃ�����Ƃ��鐿�����P�T���������R�̂����ꂩ�ɋL�ڂ̐l�H����B�i�ȉ��A��L(2)�́y�������P�z�ɌW�锭�����u�{�蔭���P�v�Ƃ����B�j
�R�@�R���̗��R
�@�R���́A�ʓY�R�����{�ʂ��L�ڂ̂Ƃ���A�{�蔭���P�́A��̏o��̓����������ɋL�ڂ���Ă��Ȃ��A�{���o��̓����������i�b�Q�Y�t�j�ɋL�ڂ́y�}�P�P�z�̎��{��i�ȉ��u�}�P�P���{��v�Ƃ����B�j�ɌW�锭���i�ȉ��u�}�P�P���{�ᔭ���v�Ƃ����B�j���܂��邩��A�}�P�P���{�ᔭ���̏o��ɂ��ẮA�����@�S�P���Q���ɂ���̏o��̎��ɂ��ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ����Ƃ͂ł����A�{���o��̌����̏o��������̏o����ɂȂ�Ƃ�����A�}�P�P���{�ᔭ���́A�{���o����O�̑��̏o��ł����āA���̏o���ɏo����J���ꂽ���蕽�P�P�|�W�T�R�Q�U���̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʁi�ȉ��u��薾�����v�Ƃ����j�ɋL�ڂ��ꂽ�����i�ȉ��u��蔭���v�Ƃ����B�j�Ɠ���ł���A���A�{�蔭���P�̔����҂���蔭���̔����҂Ɠ���ł���Ƃ��A�܂��A�{���o�莞�ɂ��̏o��l����L���̏o��̏o��l�Ɠ���ł���Ƃ��F�߂��Ȃ��̂ŁA�}�P�P���{�ᔭ�����܂ޖ{�蔭���P�͓����@�Q�X���̂Q�ɂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����B
��R�@�����咣�̐R��������R
�@�P�@�R���́A�{���o��ɂ��ē����@�S�P���Q���̓K�p�ɂ��D�挠�咣�̌��ʂ�����Ĕے肵���i������R�j���ʁA�{�蔭���P�͓����@�Q�X���̂Q�ɂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ̌�������_�Ɏ��������̂ł��邩��A��@�Ƃ��Ď��������ׂ��ł���B
(����)
��T�@���ٔ����̔��f
�@�@�@�P�@������R�i�����@�S�P���Q���̓K�p�̌��j�ɂ���
�@�@�@(1)�@�����@�S�P���Q���́A���@�Q�X���̂Q�̓K�p�ɌW��D�挠�咣�̌��ʂɂ��āu�E�E�E�D�挠�̎咣�������o��ɌW�锭���̂����A���Y�D�挠�̎咣�̊�b�Ƃ��ꂽ��̏o��̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʁE�E�E�ɋL�ڂ��ꂽ�����E�E�E�ɂ��ẮE�E�E��Q�X���̂Q�{���A�E�E�E�̋K��̓K�p�ɂ��ẮA���Y�����o��́A���Y��̏o��̎��ɂ��ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��v�ƋK�肵�A��̏o��ɌW�锭���̂����A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�����Ɍ���A���̏o�莞�@�Q�X���̂Q�̓K�p�ɂ�����I�ɑk�y�����邱�Ƃ��߂Ă���B��̏o��ɌW�锭������̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�����͈̔͂̂��̂Ƃ����邩�ۂ��́A�P�Ɍ�̏o��̓��������͈̔͂̕����Ɛ�̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�����Ƃ�Δ䂷��̂ł͂Ȃ��A��̏o��̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�����Ɛ�̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����Ƃ̑Δ�ɂ���Č��肷�ׂ��ł��邩��A��̏o��̓��������͈̔͂̕������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ���̂Ƃ�����ꍇ�ł����Ă��A��̏o��̖����̔����̏ڍׂȐ����ɁA��̏o��̓����������ɋL�ڂ���Ă��Ȃ������Z�p�I�������L�ڂ��邱�Ƃɂ��A��̏o��̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����͈̔͂��邱�ƂɂȂ�ꍇ�ɂ́A���̒����������ɂ��Ă͗D�挠�咣�̌��ʂ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@(2)�@�{���ɂ����āA��̏o��ɌW��{�蔭���P�̓����������i�b�Q�Y�t�j�̋L�ڂƐ�̏o��̓����������i�b�R�Y�t�j�̋L�ڂƂ�Δ䂷��ƁA��҂̐}�ʂɂ́A�u�{�����i���A��蔭���j�̎��{�̌`�Ԃɂ�����l�H����v�i�i���y�O�O�P�T�z�j�Ƃ��āy�}�P�z���L�ڂ���Ă��邾���ł������Ƃ���A�O�҂̐}�ʂɂ́A�u�{�����i���A�{�蔭���P�j�̑�S�̎��{�̌`�ԂɌW��l�H����v�i�i���y�O�O�S�Q�z�j�Ƃ��Đ�̏o��̐}�ʂɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ������y�}�P�P�z�i�}�P�P���{��j����������ƂƂ��ɁA���Y�}�ʂɊւ�������̋L�ځi�i���y�O�O�S�Q�z�j�������̔����̏ڍׂȐ������ɉ�����ꂽ���Ƃ͖��炩�ł���B
(����)
�E�E�E���ǁA�}�P�P���{�ᔭ���́A��̏o��̖{�蔭���P�̔����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�����̂��ׂĂ�������̂ł����āA�{�蔭���P�̎��{��ɑ���������̂ł���ƔF�߂���B�����āA�}�P�P���{��ɌW��l�H����́A�L�����ł���������𗆐��`��Ɍ`�����邱�Ƃɂ��A�M���^���̍ہA�l�H�����L�т₷���Ȃ�A�܂��A���̍ہA�c�����Ɉ��͂�������Ă��A�l�H���Ԃ�ē��c���̚M���^��������ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��A�����ɓ�������^���甲���₷���Ȃ�A�������₷���Ȃ�Ƃ��������`����L�̌��ʂ�t������̂ł��邱�Ƃ��F�߂���B
�@�I�@��������ƁA��̏o��̓����������ɖ{�蔭���P�̎��{��Ƃ��ċL�ڂ��ꂽ�A�L�����ł���������𗆐��`��Ɍ`�������}�P�P���{��ɌW��l�H����́A��̏o��̓����������ɖ��L����Ă��Ȃ���������łȂ��A��̏o��̓����������Ɍ����ɋL�ڂ���Ă����A�L�����ł������������Ɍ`�������y�}�P�z�̎��{��ɌW��l�H����̑t������ʂƂ͈قȂ闆���`����L�̌��ʂ�t������̂ł���B���������āA���Y�L�����ł���������𗆐��`��ɂ����l�H����̎��{��i�}�P�P���{��j����̏o��̖����ɉ����邱�Ƃɂ���āA��̏o��̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����͈̔͂��邱�ƂɂȂ邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A���̒����������ɂ��Ă͗D�挠�咣�̌��ʂ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�@�@(4)�@�����́A�܂��A�����D�挠���x�̎��{���[�^�Ƃ�������̂̂����A��̏o��̐������̔�������̏o��̎��{��ŏ\��������Ă���ꍇ�ɂ́A��̏o��Ŏ����I�ɓ���̔��������{��ŕ�[����Ă��A���̎��{��ɂ���ĉe�������A��̏o��̐������̔������A��̏o��ƌ�̏o��Ƃ̏d���͈͂ł���A�D�挠�咣�̌��ʂ͍m�肳���Ƃ�����A�}�P�P���{�ᔭ���́A��̏o��́y�}�P�z���̎��{��ŏ\���Ɏ�����Ă��邩��A�{���o��ɂ��ėD�挠�咣�̌��ʂ�ے肵���R���̔��f�͌��ł���Ǝ咣����B
�@�@�@�@�@�@�������Ȃ���A��̏o��̖����y�ѐ}�ʂɐV���Ȏ��{��������邱�Ƃɂ��A��̏o��̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�Ƃ���Z�p�I�������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����͈̔͂��邱�ƂƂȂ�ꍇ�ɂ́A���̒����������ɂ��ėD�挠�咣�̌��ʂ��F�߂��Ȃ��Ƃ���A�{���ɂ����āA�}�P�P���{�����̏o��ł���{���o��̖����ɉ����邱�Ƃɂ��A��̏o��ł���{�蔭���P�̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����̗v�|�ƂȂ�Z�p�I�������A��̏o��̓����������ɋL�ڂ��ꂽ�Z�p�I�����͈̔͂��邱�ƂɂȂ�A���̒����������ɂ��Ă͗D�挠�咣�̌��ʂ��F�߂��Ȃ����Ƃ́A��L�̂Ƃ���ł����āA�{�蔭���P����̏o��́y�}�P�z���̎��{��ŏ\��������Ă������ۂ��́A���̔��f�����E������̂ł͂Ȃ��B���������āA�R���Ɍ����咣�̌�肪����Ƃ͂����Ȃ��B
�@�@�@�@�}�P
�@�@
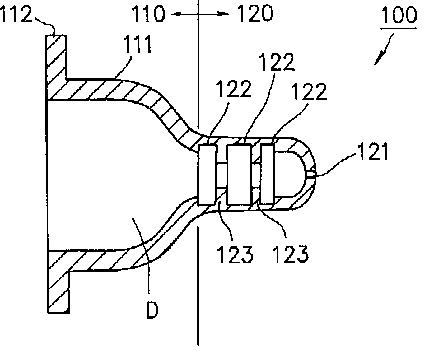
�@�@�@�@�}�P�P
�@�@
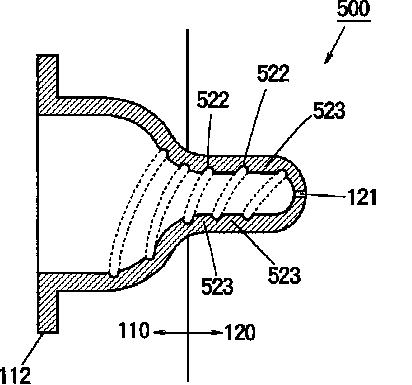
�R�������������(�u�v���X�t�F���g�v����)
| �����ԍ� | �@����19�N(�s�P)��10299�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N08��26�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�������P�ɂ����āu�Q�����ꂽ���m�t�B�������g�v�������{�ł��邱�Ƃ͖����I�Ɏ�����Ă��Ȃ��B
�@�������A��L�A�L�ڂ̂Ƃ���A�u�Q�����ꂽ���m�t�B�������g�v�́u���m�t�B�������g�v�ɔQ������������̂ł���Ƃ���A�u���m�t�B�������g�v�́u�P�{�̑@�ہv�i�b�P�A���R�j���Ӗ����A�܂��A�u�V���O���Q���v�͂P�{���͂Q�{�ȏ�̎��ŔQ��ꂽ���̂��Ӗ����邱�Ƃ͖��炩�ł���i�b�Q�A�b�R�A���Q�j�B
�@��������ƁA�u�Q�����ꂽ���m�t�B�������g�v�ɂ��āA�X�ɔQ��������āu�V���O���Q���v�Ƃ���ꍇ�A���Ɂu�Q�����ꂽ���m�t�B�������g�v���P�{�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���̂P�{�̃��m�t�B�������g��ΏۂƂ��čēx�Q���������Ƃ������Ƃ́A���悻�Z�p�펯�ɏƂ炵�āA�Ӗ��̂Ȃ����߂ƂȂ邩��A���Ǝ҂́A�������P�L�ڂ́u�V���O���Q���v�ɂ��āA�����{�́u�Q�����ꂽ���m�t�B�������g�v�ɔQ������������̂ł���Ɨ�������̂������I�ł���Ƃ�����B���Ȃ킿�A�������P���́u�V���O���Q���v�̈Ӌ`�ɂ��āA�u�Q�����ꂽ���m�t�B�������g���P�{�ł���ꍇ�v�́A���悻�Z�p�펯���痣�ꂽ���߂ł��邩��A���̂悤�ȏꍇ���܂܂Ȃ��Ɨ������č����x���Ȃ��B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�������P�L�ڂ́u�Q�����ꂽ�E�E�E�V���O���Q���v�Ƃ́A�u�Q�����ꂽ���m�t�B�������g�v���{�W�߂ĔQ��ꂽ�V���O���Q�����w�����̂Ɨ��������ׂ��ł���B
���������i�C�~�_�]�[�����̓s���]�[���U���́j
| �����ԍ� | �@����13�N(�s�P)��219�� |
|---|---|
| ������ | �@�������� |
| �ٔ��N���� | �@����15�N01��29�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�@�{���ɂ����ẮA��L�̂Ƃ���A�{���o�莞�����ɋL�ڂ���Ă��������̉������̈ꕔ�ɂ��ẮA��{���i�������ł����Ă��u����̎�ނɂ���Ă͏����������Ȃ����̂��������܂܂��Ƃ̎������������Ă����̂ł��邩��A�{�����������̏]���Z�p�Ɋւ���L�ڂɎ�����鏜�����ʂ̗\���i��L(4)�A�j�������I�ɐ��藧�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��������ƁA�p���p�|�S�ł���{���s���]�[���n�������̏��������ɂ��Ă̗��t����S�������{�����������̋L�ڂ���́A���̗L�p�������Ǝ҂ɗ��_�㖔�͌o������\���\�ł���Ƃ������Ƃ͂ł����A�����̎咣�́A��L(3)�̔F�蔻�f�����E������̂ł͂Ȃ��B
�@ (6)�@���������āA�{���s���]�[���n�������́A�������̔����Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{�����������ɂ����āA�{���s���]�[���n�������ɂ��Ă͔������������ꂽ���̂Ƃ��ċL�ڂ���Ă��炸�A�{�������́A�������������܂�����̂Ƃ��ē����@�Q�X���P�������ɋK�肷��v�������Ă��Ȃ��Ƃ����R���̔��f�Ɍ��͂Ȃ��A�����̎�����R�R�̎咣�͗��R���Ȃ��B
���������҂Ƃ��Ă̔F��ے莖��
�������n�����҂������n�����҂Ƃ̋��������҂Ƃ��ĔF�肹���B��
| �����ԍ� | �@����18�N(�l)��10074�� |
|---|---|
| ������ | �@�E�������Ή������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����19�N03��15�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�Q �{�������̔����҂ɂ���
�@�T�i�l�̐����́A��������A�T�i�l���{�������̋��������҂ł��邱�Ƃ�O��Ƃ�����̂ł���̂ŁA���̓_�ɂ��A�܂����f����B
�@�����Ƃ́A���R�@���𗘗p�����Z�p�I�v�z�̑n��̂������x�̂��̂������i�����@�Q���P���j�A���������̋Z�p�I�͈͂́A���������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��Ē�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��i���s�̓��@�V�O���P���Q�Ɓj�B���������āA�����҂ƔF�߂��邽�߂ɂ́A���Y���������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��Ē�߂�ꂽ�Z�p�I�v�z�̑n��s�ׂɌ����ɉ��S�������Ƃ��K�v�ł���A���ɁA���Y�n��s�ׂɊ֗^���A�����҂̂��߂Ɏ������s���A�f�[�^�̎��W�E���͂��s�����Ƃ��Ă��A���̖�����s�ׂ������҂̕⏕�������ɂ����Ȃ��ꍇ�ɂ́A�n��s�ׂɌ����ɉ��S�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�{�������́A���������y�ѓ��Y�����̓���̐������痘�p���镨�̔����i�p�r�����B�������Q�T�Ȃ����Q�W�j�ł���Ƃ���A�{���̗p�r�����i�������Q�T�Ȃ����Q�W�j�́A���ɑ��݂��镨���̓���̐��������A����𗘗p����Ƃ����Ӗ��ł̗p�r�����ł͂Ȃ��A���������ɌW�镨���ɂ��Ă��̗p�r�������A����Ε��������Ɋ�Â��p�r�����ł���A���̖{���́A���������̏ꍇ�Ɠ��l�ɍl���邱�Ƃ��ł���B
�@�{�������ɌW�鉻�����Ɋւ��A�T�i�l�́A�����n�����҂Ƃ��āA���̐�����������y�т��̕��͓��ɏ]�����Ă������̂́A���Y�������̍������̂��̂�S�����Ă����̂��`��a��̍����n�����҂ł��邱�Ƃ́A�����ҊԂɑ������Ȃ��B�{���ɂ����ẮA�T�i�l���{�������̋Z�p�I�v�z�̑n��s�ׂɌ����ɉ��S�����҂Ƃ����邩�ǂ����́A�@�{�������ɌW�鉻�����̍\���̌����J���ɑ���v���A�A���������̑�����@�ɑ���v���A�B�{�������ɂ�����ڕW�̐ݒ��C���ɑ���v���𑍍��I�ɍl�����A�F�肳���ׂ��ł���B
�@�ȏ�̊ϓ_���猟������ɁA���ٔ������A�T�i�l�́A�{�������̋��������҂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ɣ��f����B
�p�����ɂ��D�挠�咣�̎葱
���d�q����g�D���g�p���ăp�����ɂ��D�挠�̎咣�ɕK�v�ȏ��莖����lj������̓K�@����ے肵���B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�E)��82�� |
|---|---|
| ������ | �@�p����������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N06��27�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
��Q�@���Ă̊T�v
�@�{���́A�������ӏ��o�^�o��������ہA�����A�p�����ɂ��D�挠�咣�̎葱�������A���̌�A�������ɁA�D�挠�咣�ɕK�v�Ȏ�����lj�����葱������A����Ɍ���A�D�挠�ؖ�����o�����o�����̂ɑ��A�����������������ɑ��đO�L�̎葱�(��)�ɌW��葱���p�����鏈���y�ёO�L�̗D�挠�ؖ�����o���ɌW��葱���p�����鏈�����������Ƃ���A�������퍐�ɑ��A�����̏����ɂ��āA�ӏ��@�P�T���P���ŏ��p���������@�S�R���P���A�ӏ��@�U�O���̂R�̉��ߋy�щ^�p���������@������|�咣���āA���̎���������߂鎖�Ăł���B
(���|)
�i�P�j�����ɂ���ēd�q����g�D���g�p���čs��ꂽ�{���o��̊菑�ɂ́A�u�y�p�����ɂ��D�挠���̎咣�z�v�̗����݂����Ă��炸�A�u�y�����z�v�A�u�y�o����z�v�Ȃǂ̏��莖������؋L�^����Ă��Ȃ����̂ł��邩��i�b�P�̂P�j�A�����ɂ��o��̍ۂ̎葱�ɂ����ẮA�O�L�P�̂Ƃ���̗v�������������[�����Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ł���B
�@�Ƃ��낪�A�����́A�{���o��Ɠ����Ŗ{���o�肩��Q���ԂP�V����ɁA�{���o��̎葱�̕�Ƃ��āA�d�q����g�D���g�p���ăp�����ɂ��D�挠�̎咣�ɕK�v�ȏ��莖����lj�����{����̎葱���s���Ă��邽�߁A����ɂ���ėD�挠�̎咣�̎葱���K�@�ɍs��ꂽ���̂Ƃ������Ƃ��ł��邩�ۂ������ƂȂ�B
(����)
�i�C�j�����́A�����_�Ƃ��āA�����̈ӏ��o�^���錠���y�їD�挠�ƁA�z�肳����O�҂̔��s���v�Ƃ̊Ԃ̍l�ʂ�������A�����������̌����◘�v�̐�������ɒl����悤�ȑ�O�҂̕s���v�͂Ȃ��|�咣����B
�@�������Ȃ���A���Y�D�挠�ɂ��������̓��ŁA���Y�o����O�̓��܂łɓ��ꔭ���̏o�������������O�҂́A�o��Ɓu�����Ɂv����Ȃ������D�挠�咣�̎葱������I�ɓK�@�Ȏ葱�ƈ����邱�Ƃɂ���āA�D�揇�ʂ����邱�ƂɂȂ�s���v���邱�ƂɂȂ�B���Y�o��̌�A��������ɓ��Y�D�挠�咣�̎葱�������O�ɏo�肵����O�҂��A�����o��l�̒n�ʁi���c�����ɂ�����������n�ʁj���A�o��Ɓu�����Ɂv����Ȃ������D�挠�̎咣������I�ɓK�@�Ȏ葱�ƈ����邱�Ƃɂ���āA�����邱�ƂɂȂ�s���v���邱�ƂɂȂ�B
�@��O�҂̔�邱���̕s���v�́A����ʼn߂�����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����̎咣��������_�́A�����@�S�R���P���́u�����Ɂv���u������Ɂv�Ɖ��߂��邱�Ƃ̍����Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ����Ƃ����炩�ł���B
(����)
�i�G�j���ɁA�����̎咣�̂Ƃ�������@�S�R���P���́u�����Ɂv���u������Ɂv�Ɖ��߂���ƁA�u�����Ɂv�ƒ�߂鑼�̋K��i�Ⴆ�A�ӏ��@�S���R���A�P�S���Q���A�P�V���̂R��R���Ȃǁj�Ƃ̊W�ɂ����āA�����I�ȗ��������邱�Ƃ�����ƂȂ�B
�i�I�j�i�A�j�Ȃ����i�G�j�ŏq�ׂ��Ƃ���ɂ��A�����̏�L�咣�͂�������̗p���邱�Ƃ��ł����A�����@�S�R���P���́u�����Ɂv���u������Ɂv�Ɖ��߂��ׂ����ʂ̎������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�E�@�ȏ�̂Ƃ���ł��邩��A�{����ɂ���ėD�挠�̎咣�̎葱���K�@�ɂ��ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł����A�{���o��ɂ��ẮA�S���D�挠�̎咣�̎葱���s���Ă��Ȃ��Ƃ��킴��Ȃ��B
�@���������āA�{���e�����ɂ��A�ӏ��@�P�T���P���ŏ��p���������@�S�R���P���̉��ߋy�щ^�p�̌�肪����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
��L�����̍T�i�R����
�����������ێ���
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�R)��10002�� |
|---|---|
| ������ | �@�p��������������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��26�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�u�J�v�Z���x���_�[�}�V���v����
| �����ԍ� | �@����19�N(�l)��10098�� |
|---|---|
| ������ | �@�������N�Q���~�������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N09��29�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@���ٔ����́A�ȉ��ɏq�ׂ�Ƃ���A�J�v�Z�������Q�i�J�v�Z�������Q�|�X�j�E���R�i�J�v�Z�������R�|�P�A�R�|�Q�j�E���S�i�J�v�Z�������S�|�P�j�͕����v���ᔽ�̖������R�����邪�A�J�v�Z�������P�i�J�v�Z�������P�|�Q�j�ɖ������R�͂Ȃ����퍐�J�v�Z���x���_�[�͏�L�����̒�߂�v�����[������A�J�[�h�����Q�i�J�[�h�����Q�|�P�A�Q�|�Q�j�ɂ͐i�����ᔽ�̖������R�����邪�A�J�[�h�����R�i�J�[�h�����R�|�P�j�ɖ������R�͂Ȃ����퍐�J�[�h�x���_�[�͏�L�����̒�߂�v�����[������A�Ɣ��f����i���R�Ƃقړ����j�B
�p�����������m�F��������(�������̔[�t�����k��)
���㗝�l���ߎ��ɂ��ǔ[������k�߂����ꍇ�ɖ{�l�����̐ӂ߂��͓̂��R�ł����āA���Ƃ��{�l�ɉߎ����Ȃ������Ƃ��Ă��@�P�P�Q���̂Q��P���́u���̐ӂ߂ɋA���邱�Ƃ��ł��Ȃ����R�v������ꍇ�ɂ͊Y�����Ȃ��B��
| �����ԍ� | �@����13�N(�s�E)��285�� |
|---|---|
| ������ | �@�p�����������m�F�������� |
| �ٔ��N���� | �@����14�N06��27�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
��Q�@���Ă̊T�v
�@�@�@�{���́A�������퍐�ɑ��A�����ۗ̕L�ɌW������ԍ���Q�P�R�U�T�S�V���̓������i�ȉ��u�{���������v�Ƃ����B�j�ɂ��A�퍐�������������[�t���ɂ��Ă̋p�������������ł��邱�Ƃ̊m�F�����߂Ă��鎖�Ăł���B�����́A���p�������́A�����@�P�P�Q���̂Q��P���̉��߂�����ĂȂ��ꂽ��@�Ȃ��̂ł���A���A���̈�@�����d�匰���ł��邩�疳���ł���Ǝ咣���A�퍐�́A�������͓K�@�Ȃ��̂ł����āA�����łȂ��Ǝ咣���đ����Ă���B
(���|)
�@�������̔[�t���s���㗝�l�ٗ��m�́A���̐E���Ƃ��ĕ����U�N�����@�̓��e�ɂ��ď��m���Ă���͂��ł��邩��A�{���������̓������̔[�t���s�������̑㗝�l�ٗ��m�Ƃ��ẮA�X�̓������ɂ��āA�����U�N�����@���K�p�����̂��ǂ����ɂ��čl�����������ŁA�������̔[�t�ɂ����S�̊Ǘ������钍�Ӌ`��������Ƃ����ׂ��ł���Ƃ���A�{���ɂ����ẮA�����咣�̂悤�ȏ�L�@�`�B�̂悤�Ȏ�����݂������Ƃ��l�����Ă��A�㗝�l�ٗ��m�ɂ����āA�ʏ�̒��ӗ͂�L����҂����S�̒��ӂ��Ă��Ȃ��ǔ[�������ɔ[�t�ł��Ȃ�����������݂���Ƃ͓��ꂢ�����Ƃ��ł��Ȃ��B���̑��A�����̒�o����S�؋����܂߈ꌏ�L�^�����Ă��A�{������̉��ɂ����Č����Ɂu���̐ӂ߂ɋA���邱�Ƃ��ł��Ȃ����R�v������ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i�����̑㗝�l�ٗ��m�Ƃ��ẮA�����P�O�N�T���̐ݒ�o�^���ɑ�S�N���̓������̔[�t�������m�F���邱�Ƃ��e�Ղɂł����͂��ł���̂ɖ��R�[�t���Ԃ�k�߂��A����ɂU�����Ԃ̒ǔ[���Ԃ����k�߂������̂ł����āA���̉ߎ��͖��炩�Ƃ��킴��Ȃ��B�j�B
�@�܂��A�����́A�㗝�l�ٗ��m�̉ߎ���{�l�̉ߎ��Ƃ݂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝ咣���邪�A�㗝�l�͖{�l�ɂ��I�C����A�{�l�̈ϑ����Ė{�l�̖��������ē��������̔[�t�s�ׂ��s���̂ł��邩��A���̂悤�ȑ㗝�l���ߎ��ɂ��ǔ[������k�߂����ꍇ�ɖ{�l�����̐ӂ߂��͓̂��R�ł����āA���Ƃ��{�l�ɉߎ����Ȃ������Ƃ��Ă��@�P�P�Q���̂Q��P���́u���̐ӂ߂ɋA���邱�Ƃ��ł��Ȃ����R�v������ꍇ�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�q��@�Փ˖h�~�p�u���[�_�v�R�������������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10130�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N12��25�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�Q ���������͈̔�
�@�����P�V�N�U���Q�V���t���葱����i�b�R�j�ɂ�����ꂽ��̖{���̓��������͈̔͂̐������P�̋L�ڂ́A���̂Ƃ���ł���i�ȉ��A���̐������P�ɌW�锭�����u�{�蔭���v�Ƃ����B�܂��A��L�葱���̖������u�{�薾���v�Ƃ����B�j�B
�u�y�������P�z
�@�A���e�i�̎w�������������ς���ƂƂ��ɁA�p���X�d�g�̑���g���s���A�A���e�i���͂̒T�m�摜�̃f�[�^�����A����͈̔͂̒T�m�摜��\����ʓ��ɕ\������ړ��̂ɑ�������郌�[�_�ɂ����āA
�@�O�L�ړ��̂̈ړ����x�����m����ړ��̑��x���m��i������A
�@�\����ʓ��ɂ�����ړ��̂̕\���ʒu��O�L�\����ʓ��̊�ʒu����ړ��̂̈ړ������ɑ��Č���֏���̃V�t�g�ʂ����V�t�g�����đO�L�T�m�摜��\�����A�O�L�ړ��̑��x���m��i�ɂ�茟�m���ꂽ�ړ��̂̈ړ����x���傫���Ȃ�قǁA�O�L�V�t�g�ʂ�傫������T�m�摜�\�������i��݂������Ƃ�����Ƃ��郌�[�_�B�v
�R �R���̗��R
�@�R���̗��R�́A�ʎ��R�����ʂ��̂Ƃ���ł���B�v����ɁA�{�蔭���́A���J���U�P�|�V�X�P�V�X������i�ȉ��u���p���s���v�Ƃ����A�����s���ɋL�ڂ��ꂽ�������u���p�����v�Ƃ����B�b�P�j���тɓ��J���T�X�|�P�V�P�V�V������i�b�S�j�y�ѓ��J���T�S�|�U�S�X�X�P������i�b�T�j�̎��m�Z�p�Ɋ�Â��ē��Ǝ҂��e�Ղɔ��������邱�Ƃ��ł�������A�����@�Q�X���Q���̋K��ɂ��������邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���A�{��o��́A���̗]�̐������Q�Ȃ����S�ɌW�锭���ɂ��Č�������܂ł��Ȃ��A���₳���ׂ��ł���A�Ƃ������̂ł���B
�@��L���f�ɍۂ��A�R�����F�肵�����p�����̓��e���тɖ{�蔭���ƈ��p�����Ƃ̈�v�_�y�ё���_�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) ���p�����̓��e
�@�u���q��@�̏Փ˖h�~���u�������鎿��M���ɉ������鑼�q��@�̂`�s�b�g�����X�|���_�����M������M���A���̎�M�d�E���x�A���ʓ����瑼�q��@�̊T���ʒu��c����������b�q�s��̌x�������ɕ\������q��@�Փ˖h�~���u�ɂ����āA�C���x�v�̎w�����鎩�q��@���x�����v�Z�@�ɓ��͂��A����Ɋ�Â��āA���q��@�𒆐S�Ƃ��鏊�蔼�a�̉~�ƁA�O�L�~�̒��S��ʂ�O�L���q��@�̑��x�ɉ����Ă��̐i�s�����ɒ��a���L�k����~�Ƃ̊O�������Ԕ@���v���t�@�C����L����x�������b�q�s��ɕ\�����A���q��@�̑��x�����傷��ɏ]���đO�L���a��L�����邱�Ƃ�����Ƃ���q��@�Փ˖h�~���u�B�v
(����)
��S ���ٔ����̔��f
�@���ٔ����́A�R���̂�������_�Q�ɌW��e�Ցz�����̔��f�ɂ́A��肪����Ɖ�����B���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�P �R���̑���_�Q�ɌW��e�Ցz�������f�̓��e
�@��L�_�_�Ɋւ���R���̔��f�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�u���p�����ɂ����āA���q��@�𒆐S�Ƃ��鏊�蔼�a�̉~�ƁA�O�L�~�̒��S��ʂ�O�L���q��@�̑��x�ɉ����Ă��̐i�s�����ɒ��a���L�k����~�Ƃ̊O�������Ԕ@���v���t�@�C����L����x�������b�q�s��ɕ\�����A���q��@�̑��x�����傷��ɏ]���đO�L���a��L������悤�ɂ�����|�́A���p���s���̏�L�E�L�����R�y�тS�̋L�ڂ���݂āA�Փˉ�𑀍�ɕK�v�Ƃ���鎞�Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɁA���q��@�̑��x�����傷��ɏ]���āA���q��@�̑O���̌x�����̕\���͈͂����L���邽�߂ł���B
�@����A�q�@���u�ɂ����āA�ړ��̂̑O���̊Ď����̕\���͈͂��L���邽�߂ɁA�ړ��̂̕\���ʒu��\����ʂ̒��S�ʒu�������ւ��点�ĕ\�������邱�Ƃ́A�Ⴆ�A���J���T�X�|�P�V�P�V�V������A���J���T�S�|�U�S�X�X�P������Ɏ������悤�ɖ{��o��O���m�ł���B
�@��������ƁA���p�����ƊY���m�Z�p�́A�Ƃ��ɁA�ړ��̂̑O���̊Ď����̕\���͈͂��L������̂ł��邩��A���p�����ɊY���m�Z�p��K�p���āA���q��@�̑��x�����傷��ɏ]���āA���q��@�̕\���ʒu��\����ʂ̒��S�ʒu���������ւ��点��悤�ɂ��邱�Ƃ͓��Ǝ҂��e�Ղɑz�����������Ƃł���B
�@�����āA���̍ۂɁA���p���s���̑�P�}�i���j�Ɏ������悤�ɁA���q��@�̈ړ������̌x�������ł��L���\�����邽�߂ɂ́A���q��@�̕\���ʒu���ړ������ɑ��Č���ւ��点�悢���Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āA���p�����ɏ�L���m�Z�p��K�p���đ���_�Q�ɌW��\���Ƃ��邱�Ƃ͓��Ǝ҂��e�ՂɂȂ��������Ƃł���B�v�i�R�����T�łP�T�s�`�R�T�s�j�Ɣ��f���Ă���B
(����)
�i�{�薾���̋L�ځj
�u�y�O�O�O�V�z���̂悤�ɍ\���������Ƃɂ��A�T�m�摜�\�������i�́A�ړ��̂̈ړ����x���傫���Ȃ�قǁA�\����ʓ��ɂ�����ړ��̂̈ʒu����ʒu���ړ��̂̈ړ������ɑ��Č���փV�t�g�����ĒT�m�摜��\�����邽�߁A�ړ��̂̈ړ����x���ᑬ�ȏ�Ԃł̓V�t�g�ʂ����܂�傫���Ȃ炸�ɁA�ړ��̂̑O������������������͈͂�T�m����ъĎ��ł���悤�ɂȂ�A�ړ��̂̈ړ����x���傫���Ȃ�ƁA������O���̕\���͈͂��L������āA�O���̂��L���͈͂��Ď��ł���悤�ɂȂ�B
�y�O�O�O�W�z��L�T�m�摜�\�������i�Ƃ��āA�������Q�ɋL�ڂ̂Ƃ���A�O�L�V�t�g�ʂ�ω������Ă���A��莞�Ԃ��o�߂���܂ł͂��̃V�t�g�ʂ��ێ�����悤�ɍ\������A�ړ��̂̈ړ����x���ς�閈�ɕ\����ʂɂ�����ړ��̂̈ʒu���p�ɂɐ芷���Ƃ��������Ƃ��Ȃ��A�T�m�摜��ǂ�����肷�邱�Ƃ��Ȃ��B
�y�O�O�O�X�z�܂��A��L�T�m�摜�\�������i�Ƃ��āA�������R�ɋL�ڂ̂Ƃ���A�O�L�ړ��̂̈ړ����x�ɑ���O�L�V�t�g�ʂ�i�K�I�ɕω�������悤�ɍ\������A�ړ��̂̈ړ����x���͂��ɕς�閈�ɕ\����ʂɂ�����ړ��̂̈ʒu���p�ɂɐ芷���Ƃ��������Ƃ��Ȃ��A�T�m�摜��ǂ�����肷�邱�Ƃ��Ȃ��B
�y�O�O�P�O�z�X�ɁA���̔����̃��[�_�́A�������S�ɋL�ڂ̂Ƃ���A�O�L�V�t�g�ʂ�i�K�I�ɕω������邽�߂̈ړ��̂̈ړ����x�̂��ꂼ��̂������l���ړ��̂̈ړ����x�̏㏸���Ɖ��~���ƂňقȂ点�āA�ړ����x�ɑ���V�t�g�ʂ̕ω��Ƀq�X�e���V�X����������B����ɂ��ړ��̂̈ړ����x�̏㏸�ɂ���āA���炩���ߒ�߂��������l�������ɃV�t�g�ʂ̕ύX���s���A���̒���Ɉړ��̂̈ړ����x�����~�ɓ]���Ă������ɃV�t�g�ʂ��ύX����邱�Ƃ��Ȃ��A���l�Ɉړ��̂̈ړ����x�����~�ɂ���Ă��炩���ߒ�߂��������l������邱�Ƃɂ���ăV�t�g�ʂ��ύX���ꂽ����Ɉړ����x���Ăя㏸�ɓ]���Ă������ɃV�t�g�ʂ��ύX����邱�Ƃ��Ȃ��B
�@����ɂ��ړ��̂̈ړ����x���ς�閈�ɕ\����ʓ��ɂ�����ړ��̂̈ʒu���p�ɂɐ芷���Ƃ��������Ƃ��Ȃ��A�T�m�摜��ǂ�����肷�邱�Ƃ��Ȃ��B�v�i�b�Q�j
�@�u�y�O�O�Q�X�z�y�����̌��ʁz�������P�ɋL�ڂ̔����ɂ��A�ړ��̂̈ړ����x���傫���Ȃ�قǁA�\����ʓ��ɂ�����ړ��̂̕\���ʒu���O�L�\����ʓ��̊�ʒu����ړ��̂̈ړ������ɑ��Č���փV�t�g���ĒT�m�摜���\������邽�߁A�ړ��̂̈ړ����x���ᑬ�ȏ�Ԃł̓V�t�g�ʂ����܂�傫���Ȃ炸�ɁA�ړ��̂̑O������������������͈͂�T�m����ъĎ��ł��A�ړ��̂̈ړ����x���傫���Ȃ�ƁA������O���̕\���͈͂��L������āA�O���̂��L���͈͂��Ď��ł���悤�ɂȂ�A����҂̎��ς킹�邱�ƂȂ��A�ړ����x�ɉ����ď�ɍœK�ȃV�t�g�ʂ��m�ۂ����B�v�i�b�R�j
(2) ���p���s���i�b�P�j�ɂ́A���̋L�ڂ�����B
�u���������͈̔�
(1) �q��@�Փ˖h�~���u�̋��Ћ@�\�����u�ɉ����āA�����q��@�̏Փ˂��x�����ׂ����\�������q��@�̑��x�ɉ����ĕύX����悤�ɂ������Ƃ�����Ƃ���q��@�Փ˖h�~���u�ɉ�����x�����\�������B
(2) �O�L�����q��@�̏Փ˂��x�����ׂ����\�������q��@�̑��x�ɂ���Ď��q��@�̐i�s�����ɒ��a�̐L�k����~�ł��邱�Ƃ�����Ƃ�����������͈̔͂P�L�ڂ̍q��@�Փ˖h�~���u�ɉ�����x�����\�������B
(3) �O�L�����q��@�̏Փ˂��x�����ׂ����\�������q��@�𒆐S�Ƃ��鏊�蔼�a�̉~�ƁA�O�L�~�̒��S��ʂ�O�L���q��@�̑��x�ɉ����Ă��̐i�s�����ɒ��a���L�k����~�Ƃ̊O�������Ԕ@���v���t�@�C����L���邱�Ƃ�����Ƃ�����������͈̔͂P�L�ڂ̍q��@�Փ˖h�~���u�ɉ�����x�����\�������B�v�i�b�P�A�P�ō����T�s�`�E���Q�s�j
�u�i�]���̋Z�p�j
�@�]����ʂɎg�p���ꈽ�͍l������Ă���q��@�Փ˖h�~�V�X�e���͊�{�I�ɂ͎��q��@�̏Փ˖h�~���u�������鎿��M���ɉ������鑼�q��@�̂`�s�b�g�����X�|���_�����M������M���A���̎�M�d�E���x�A���ʓ����瑼�q�@�i�������F�u���q��@�v�̌�L�j�̊T���ʒu��c����������b�q�s��ɕ\��������̂ł��邪�A���q��@���猩�Č����ɏՓ˂̋��̋������q��@�ɑ��c�҂̒��ӂ��W�������߂�ׂ��b�q�s��Ɏ��q��@�𒆐S�Ƃ��鏊�v���a�A�Ⴆ�Q���D���D�i�\�j�ɑ�������~��\������̂���ʓI�ł������B
�@�������Ȃ���O�L�x������\������~�����a�Q���D���D�Œ�ł���ꍇ�ɉ����Ď����q��@���v�X�A�T�O�O�����i�m�b�g�j�Ő��ΐڋ߂���Ɖ��肷��A���q��@���O�L�~���ɕ\������ꂽ��Փ˂���܂ł̎��Ԃ��͂����Q�^�i�T�O�O�{�T�O�O�j���ԁ��V�D�Q�b�ł����𑀍�ɂ͂Ƃ��Ă��s�[���ł���Ƃ������ׂ��������B
�@����A�O�L�x������\������~�̔��a���Ƃ���Ή~���ɕ\������鑼�q��@�̐������債���c�҂ɂƂ��ċɂ߂Ă킸��킵���^�̋��Ћ@�ɑ���_�o�̏W��������ɂȂ邱�Ƃ͎����ł���̗p������̂ł������B
�i�����̖ړI�j
�@�{�����͏�q�̔@���]���̍q��@�Փ˖h�~���u�̌��ׂ��������ׂ��Ȃ��ꂽ���̂ł����āA���q��@�̑��x�ɉ����Čx���������v�̌`��ɕω������߂邱�Ƃɂ���Ď����q��@�̏Փˉ�𑀍�ɕK�v�Ȏ��Ԃ��m�ۂ���Ƌ��ɑ��c�҂̐^�̋��Ћ@�ɑ��钍�ӂ̎U����h�~���q���ʂ̈��S��}�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B�v�i�b�P�A�P�ʼnE���V�s�`�Q�ō��㗓�P�W�s�j
�@�u���āA��q�̔@���x�����\����������������ׂɂ͑�Q�}�Ɏ����@������M�@�v�X�s�w�y�тq�w�A�������m�@�q�d�o�k�x �c�d�s�d�b�s�n�q�A�v�Z��b�`�r �b�o�t�y�ѕ\����c�h�r�o�k�`�x�ɂ���č\������]���̍q��@�Փ˖h�~���u�P�̑��ɑC���x�v�u�d�k�n�b�h�s�x �r�d�m�r�n�q �Q�̎w����K�v�Ȃ�G���R�[�_�d�m�b�n�c�d�q �R�ŕ������������q��@���x����O�L�v�Z�@�b�`�r �b�o�t�ɓ��͂��A����Ɋ�Â��đO�q�����@�����v�̌v�Z���s�Ȃ킵�߂���A�\����c�h�r�o�k�`�x��Ɏ��q��@���x�ɑΉ������v���t�@�C����`������悢�B�v�i�b�P�A�R�ō��㗓�T�s�`�P�U�s�j
�u�i�����̌��ʁj
�@�{�����͈ȏ���������@���������̗p������̂ł��邩�玖����]���̍q��@�Փ˖h�~���u�ɊȒP�ȃ\�t�g�E�G�A��t������݂̂ōq���ʂ̎���ɑ������x���\�����\�ƂȂ�A�����Ă͑��c�҂ɑ��Փˉ�𑀍�̎��ԓI�]�T���\���ɗ^���邱�ƂɂȂ邽�ߍq��@�̏Փˎ��̂�h�~�����Œ��������ʂ�����B�v�i�b�P�A�R�ʼnE�㗓�P�s�`�W�s�j
�R �R���̑���_�Q�ɌW��e�Ցz�������f�̓��ۂɂ���
(1) ��L�̈��p���s���̋L�ڂɏƂ炷�Ȃ�A���p�����ł́A�b�q�s��i�\����c�h�r�o�k�`�x��j�ɑ��q��@�̊T���ʒu�������S�̂̕\����ʂ́A�g�喔�͏k�������邱�ƂȂ��A���͈̔͂̉摜��\�����邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă��邱�ƁA�S�̂̕\����ʒ��ɁA�Փ˂̂�����̏��Ȃ����q��@���\������邱�Ƃɂ�葀�c�҂̒��ӂ��U���ɂȂ邽�߁A�^�̋��Ћ@�ɑ��Đ_�o���W�������čq���ʂ̈��S��}��悤�ɂ�����Ƃ̉ۑ肪���݂��邱�ƁA���̉ۑ���������邽�߂ɁA�O�L���q��@�̑��x�ɉ����Ă��̐i�s�����ɒ��a���L�k����~�Ŏ������u�x�����v���b�q�s��ɏd�˂ĕ\������Ƃ̋Z�p��������Ă���B
�@����A���J���T�X�|�P�V�P�V�V������y�ѓ��J���T�S�|�U�S�X�X�P������i�b�S�A�T�j�ɂ��A�ړ��̂̕\���ʒu��\����ʂ̒��S�ʒu���������ֈړ������ĕ\������Z�p���L�ڂ���A���Z�p�́A�\����ʏ�ɕ\�������T�m�摜�̕\���ʐς�ς��邱�ƂȂ��A�T�m�摜�̕`�撆�S�ʒu��ω���������̂ł����āA���m�Z�p�ł��邱�Ƃ��F�߂���i�ȉ��u�I�t�Z���^�@�\�Ƃ����ꍇ������B�j�B
�@��L�̂Ƃ���A�I�t�Z���^�@�\�́A�T�m�摜�̕`�撆�S�ʒu������֕ω������邱�Ƃɂ��A�O���̕\����ʌ��E�ʒu�܂ł̕\���͈͂��L���āA�ω�������O�Ɍ����Ă��Ȃ��T�m���W��������悤�ɂ��A�����A����̕\����ʌ��E�ʒu�܂ł̕\���͈͂����߁A�ω�������O�ɂ͌����Ă����T�m���W�������Ȃ�����Z�p�ł���B
(2) �����ŁA���p�����ɂ����āA���m�Z�p�ł���I�t�Z���^�@�\���̗p��������ۑ�Ȃ������@�������݂��邩�ۂ��ɂ��Č�������B
�@�O�L�̂Ƃ���A���p�����́A�\����c�h�r�o�k�`�x��̑S�̂̕\����ʂɂ��āA���q��@�̑��x���ɉ����āA�O���̕\���͈͂�L�k������̂ł͂Ȃ��A�ނ���A���͈͓̔��Ɉʒu���鑼�q��@���̂��ׂĂ�\�������邱�Ƃ�O��Ȃ����z�肵�������ł���B���̂悤�ɁA���p�����́A�S�̂̕\����ʓ��ɁA�������\������邱�Ƃ����蓾�鑼�q��@���̒��ŁA���c�҂����āA�^�ɏՓ˂��x�����ׂ����q��@�����ʂ����A���̂悤�ȍq��@�ɑ��钍�ӂ����N�����邽�߂ɁA�u�x�����v���~�ŕ\�����A���A���q��@�̑��x�ɉ����āA���̔��a�̒�����L�k������Z�p�ɌW�锭���ł���B��L�̂Ƃ���A�u�x�����v�̕\����ʂ́A�S�̂̕\����ʂɊ��ɕ\������Ă��鑼�q��@���̒��ŁA�Փ˂����������K�v�̂Ȃ��q��@���ƁA�^�ɏՓ˂����������K�v�̂��鑼�q��@�����A���c�҂ɂƂ��Ď��ʂ��邱�Ƃ�e�Ղɂ��邽�߂̎�i�Ƃ��ėp�����Ă���B
�@��L�̂Ƃ���A���p�����ł́A�b�q�s��i�\����c�h�r�o�k�`�x��j�̑S�̂̕\����ʂɂ́A�Փ˂̂�����̗L���ɂ�����炸�A���q��@���\������Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���ɁA�S�̂̕\����ʂɕ\������Ă��鑼�q��@�̒��ŁA���c�҂ɑ��āA�^�ɏՓ˂��x�����ׂ����q��@�𑀏c�҂Ɏ��ʂ����āA���ӂ����₷������ړI�ŁA�u�x�����v��\��������Ƃ����ۑ�����̂��߂̋Z�p�ł��邩��A���p�������A�ۑ�����̂悤�Ȏ�i�ɂ���ĉ������锭���ł���ȏ�A�u�x�����v�̕\���͈݂͂̂��A�����I�ɕ\������ړI�ŃI�t�Z���^�@�\���̗p��������ۑ�A�D�ʐ��Ȃ������@���͑��݂��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A���ɂ���Ƃ���A����́A���p�������z�肷��ۑ�����Ƃ͑S���ʌ̉ۑ�ݒ�Ɖ�����i�Ƃ����ׂ��ł���B
�@�������A��ʓI�ɂ́A�I�t�Z���^�@�\��p���āA�T�m�摜�̕`�撆�S�ʒu������֕ω�������A�O���̕\����ʌ��E�ʒu�܂ł̕\���͈͂͊g�債�A����܂łɌ����Ă��Ȃ��T�m���W��������悤�ɂȂ�Ƃ�����ʂ̌������������ł���Ƃ������ʂ͂��邪�A���p�����́A�S�̂̕\����ʓ��Ɍx������\������Z�p�Ɋւ�����̂ł����āA����܂łɌ����Ă��Ȃ��T�m���W��������悤�ɕ\������Ƃ����ۑ�̉�����ړI�Ƃ������̂ł͂Ȃ�����A��L�̂悤�Ȉ�ʓI�Ȍ��ʂ́A���p�����Ƃ͖��W�ł���Ƃ�����B
�@���̓_�A�퍐�́A���p�����ɂ����Ă��A���q��@�̑��x�傳�����ꍇ�ɂ́A�x�����̕\���͈͂��O���Ɋg�債�A�b�q�s��̑S�̕\����ʂ���A�͂ݏo���ĕ\������邱�Ƃ����蓾����̂ł���A��ʂ̌�������K�v�Ƃ�������ۑ�A���@�������ݓI�Ɏ�����Ă���|�咣����B�������A���̂悤�Ȏ咣�́A���p�����ɂ���������ۑ�A���Ȃ킿�A�����̑��q��@���\�����꓾��b�q�s��̑S�̕\����ʂɂ����āu�x�����v�\�������邱�Ƃɂ���āA�^�ɏՓ˂��x�����ׂ����q��@�𑀏c�҂Ɏ��ʂ����邱�Ƃ�e�Ղɂ���Ƃ������p�����̉ۑ�Ƃ͑��e��Ȃ����ʂ�O��Ƃ���咣�Ƃ����ׂ��ł����āA�̗p�̌���łȂ��B
(3) �R���́A�O�L�P�̂Ƃ���A�u���p�����ɂ����āA���q��@�𒆐S�Ƃ��鏊�蔼�a�̉~�ƁA�O�L�~�̒��S��ʂ�O�L���q��@�̑��x�ɉ����Ă��̐i�s�����ɒ��a���L�k����~�Ƃ̊O�������Ԕ@���v���t�@�C����L����x�������b�q�s��ɕ\�����A���q��@�̑��x�����傷��ɏ]���đO�L���a��L������悤�ɂ�����|�́A���p���s���̏�L�E�L�����R�y�тS�̋L�ڂ���݂āA�Փˉ�𑀍�ɕK�v�Ƃ���鎞�Ԃ��m�ۂ��邽�߂ɁA���q��@�̑��x�����傷��ɏ]���āA���q��@�̑O���̌x�����̕\���͈͂����L���邽�߂ł���B�v�Ɛ�������B
�@�������A��L�ɏڏq�����Ƃ���A���p�����ɂ����ẮA���q��@���́A���ɁA�S�̂̕\����ʂɂ����āA���q��@�̑��x�𑬂�����O����\������Ă���̂ł��邩��A�u�x�����v��ʂ̕\���ԗl�Ƃ��āA�I�t�Z���^�@�\��K�p��������ۑ�Ȃ������@�t���͂Ȃ��B
�@�R���́A�{�蔭���ƈ��p�����Ƃ́A�����ۑ�y�ыZ�p�v�z���݂��Ɉقɂ�����̂ł����āA���p������O��Ƃ������́A�{�蔭���Ƌ��ʂ�������ۑ�͐������Ȃ��ɂ�������炸�A�����ۑ��z�肵����ŁA���̉�����i�Ƃ��Ď��m�Z�p��K�p���邱�Ƃ��e�Ղł���Ɣ��f���āA���p��������{�蔭���̗e�Ցz���������_�ɂ����āA��肪����Ƃ�����B
�@�����̎�����R�S�ɌW��咣�ɂ́A���R������B
�S ���_
�@�ȏ�ɂ��A���̗]�̓_�f����܂ł��Ȃ��A�����̖{�i�����͗��R�����邩��A�����F�e���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B
���p�V�ċZ�p�]����������T�i����
| �����ԍ� | �@����12�N(�s�R)��22�� |
|---|---|
| ������ | �@���p�V�ċZ�p�]����������T�i���� |
| �ٔ��N���� | �@����12�N05��17�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
��O�@���ٔ����̔��f
�@��@���ٔ������A�T�i�l�̖{�������͗��R���Ȃ����̂Ɣ��f����B
�@�@�@���̗��R�́A�T�i�l�̓��R�ɂ�����咣�ɑ���L��̂Ƃ��蔻�f����ق��́A�����������y�ї��R���́u��l�@���ٔ����̔��f�v�Ɠ����ł��邩��A��������p����B
�@�@�@�������A��������Z�ŘZ�s�ڂ��玵�s�ڂɂ����Ắu�������ƂƂ��Ă���B�v�̎��ɁA���s���āA���̂Ƃ��������B
�@�u�@�����āA���̕]���́A�u�]���P�v���A�u���̐������ɌW��l�ẮA�E���i���A���p�V�ċZ�p�]�����́u���p���������y�ѐ����v�����w���B�ȉ������B�j�̊��s���̋L�ڂ���݂āA�V�K�������@������̂Ɣ��f����邨���ꂪ����B�i���p�V�Ė@��R���P����R���j�v�Ƃ������̂ł���A�u�]���Q�v���A�u���̐������ɌW��l�ẮA�E���̊��s���̋L�ڂ���݂āA�i���������@������̂Ɣ��f����邨���ꂪ����B�i��R���Q���i�����P����R���Ɍf����l�ĂɌW����̂Ɍ���j�j�v�Ƃ������̂ł���A�u�]���R�v���A�u���̐������ɌW��l�ẮA���̏o��̓��O�̏o��ł����āA���̏o���ɓo�^����̔��s���͏o������Ⴕ���͏o����J�����ꂽ�E���̏o��̊菑�ɍŏ��ɓY�t�����������͐}�ʂɋL�ڂ��ꂽ�������͍l�ĂƓ���Ɣ��f����邨���ꂪ����B�i��R���̂Q�j�v�Ƃ������̂ł���A�u�]���S�v���A�u���̐������ɌW��l�ẮA���̏o��̓��O�ɏo�肳�ꂽ�E���̏o��ɌW�锭�����͍l�ĂƓ���Ɣ��f����邨���ꂪ����B�i��V���P���A��R���j�v�Ƃ������̂ł���A�u�]���T�v���A�u���̐������ɌW��l�ẮA���̏o��Ɠ����ɏo�肳�ꂽ�E���̏o��ɌW�锭�����͍l�ĂƓ���Ɣ��f����邨���ꂪ����B�i��V���Q���A��U���j�v�Ƃ������̂ł���A�u�]���U�v���A�u���Ɋ֘A�����s�Z�p�������ł��Ȃ��B�v�Ƃ������̂ł���B�i�b��܍��A�٘_�̑S��|�j�v
�@��@�T�i�l�̓��R�ɂ�����咣�ɂ���
�@�@�P�@�T�i�l�̎咣�P�ɂ���
�@�@�@�@�T�i�l�̎咣�́A�v����ɁA���p�V�ċZ�p�]�����u�P�v����u�T�v�܂ł̂����ꂩ�ł���A��Ɠ������Y�o�^���p�V�Ă̎��{���҂ƂȂ낤�Ƃ͂��Ȃ�����A�Y�u�P�v����u�T�v�܂ł̂����ꂩ�̕]�����A���Y���p�V�Č��������I�ɖ����Ƃ��鏈���ł���Ƃ������̂ł���Ɖ������B
�@�@�@�@�������Ȃ���A�O���i���������Ŗ��s�����ŎO�s�ڂ܂Łj�̂Ƃ���A�s�������i�ז@�O��́u�����v�Ƃ́A�����͂̎�̂��鍑���͌����c�̂��s���s�ׂ̂����A���̍s�ׂɂ���āA���ڍ����̌����`�����`�����A���͂��͈̔͂��m�肷�邱�Ƃ��@����F�߂��Ă�����̂��������̂ł���A���̂��Ƃ́A��̓I�ȍs�����̍s�ׂ��E�́u�����v�ɓ����邩�ۂ��́A���Y�s�ׂ̍����ƂȂ�s���@�K���A���Y�s�ׂ��A���ڍ����̌����`�����`�����A���͂��͈̔͂��m�肷����̂Ƃ��āA�K�肵�Ă��邩�ۂ��ɌW�邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł���B
�@�@�@�@������Ƃ���A�T�i�l�̎咣����悤�ȁA���p�V�ċZ�p�]�����u�P�v����u�T�v�܂ł̂����ꂩ�ł���A��Ɠ������Y�o�^���p�V�Ă̎��{���҂ƂȂ낤�Ƃ͂��Ȃ��Ƃ̎��p�V�Č��҂̕s���v�����ɑ��݂���Ƃ��Ă��A���ꂪ�A���p�V�Ė@�����p�V�ċZ�p�]���ɂ���Ē��ڌ`�����A���͂��͈̔͂��m�肷�邽�߂ɋK�肵�������̌����`���ɑ�������Ɖ����ׂ������́A���@��A�S�����݂��Ȃ�����A�P�Ȃ鎖����̕s���v�ł���Ƃ��킴����A������s���v�����邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA���p�V�ċZ�p�]�����s�������i�ז@�O��́u�����v�ł���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�@�@���������āA�T�i�l�̉E�咣�͎����ł���B
�@�@�Q�@�T�i�l�̎咣�Q�ɂ���
�@�@�@�@�T�i�l�̎咣�́A�v����ɁA���p�V�Ė@�����̓�ɂ���āA���p�V�Č��҂��A���Q�������������̌����s�g������ɓ������āA���p�V�ċZ�p�]���̐��������A�u�P�v����u�U�v�܂ł̂����ꂩ�̕]�����邱�ƁA�y�ьx�����Ɏ��p�V�ċZ�p�]��������āA�Y�u�P�v����u�U�v�܂ł̂�����̕]������������ɒm�点�邱�Ƃ��`���t�����Ă��邩��A���p�V�ċZ�p�]���́A���̓��e������ɂ�����炸�A���ڍ����̌����`�����`�����A���͂��͈̔͂��m�肷�邱�Ƃ��@����F�߂��Ă���u�����v�ł���Ƃ������̂ł���Ɖ������B
�@�@�@�@�������Ȃ���A���p�V�Ė@�����̓�́A�u���p�V�Č��Җ��͐�p���{���҂́A���̓o�^���p�V�ĂɌW����p�V�ċZ�p�]��������Čx����������łȂ���A���Ȃ̎��p�V�Č����͐�p���{���̐N�Q�ғ��ɑ��A���̌������s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�ƒ�߁A���p�V�ċZ�p�]��������邱�Ƃ��A���p�V�Č��҂̌����s�g�̈�v���Ƃ��Ă���ɂ����Ȃ��̂ł���A���Y���p�V�ċZ�p�]�����ɋL�ڂ��ꂽ���p�V�ċZ�p�]�����u�P�v����u�U�v�܂ł̂����ꂩ�̕]���ł��邱�Ɓi�Ⴆ�A�]���U�ł��邱�Ɓj�́A�Y�����s�g�̗v���Ƃ͂���Ă��Ȃ��B���Ȃ킿�A���p�V�ċZ�p�]�����̂́A���p�V�Č��҂̉E�����s�g�ɉ���e�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��̂ł���B
�@�@�@�@������Ƃ���A�{���ɂ����āA�T�i�l���A�s�������i�ז@�O��́u�����v�ɓ�������̂Ƃ��āA���̎���������߂Ă���̂́A�O�����̈�̂Q�L�ڂ̎��p�V�ċZ�p�]�����̂ł���i���p�V�ċZ�p�]�����́A���̎��p�V�ċZ�p�]������肷�邽�߂ɋL�ڂ���Ă���ɂ����Ȃ��B�j�A�܂��A�E�́u�����v�Ƃ́A�����͂̎�̂��鍑���͌����c�̂��s���s�ׂ̂����A���̍s�ׂɂ���āA���ڍ����̌����`�����`�����A���͂��͈̔͂��m�肷�邱�Ƃ��@����F�߂��Ă�����̂��������̂ł��邱�Ƃ͑O���̂Ƃ���ł��邩��A���p�V�Ė@�����̓�ɂ���āA���p�V�ċZ�p�]�����̒����p�V�Č��҂̌����s�g�̈�v���Ƃ���Ă��邩��Ƃ����āA�T�i�l���A�{���ɂ����āA����������߂Ă�����p�V�ċZ�p�]�����E�́u�����v�ɓ�����Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�@�@���������āA�T�i�l�̉E�咣�������ł���B
�@�O�@�ȏ�ɂ��A�������͐����ł����āA�{���T�i�͗��R���Ȃ�����A��������p���邱�ƂƂ��A�T�i��p�̕��S�ɂ��s�������i�ז@�����A�����i�ז@�Z����A�Z�����ꍀ�{����K�p���āA�啶�̂Ƃ��蔻������B