�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�m���֘A �d�v�����W�i�P�j
�C���N�^���N����T�C�N������
�c�Ŕ�
�g���̂ăJ��������
���N���g�����i���̏��W�j
�R�J�R�[�������i���̏��W�j
�}�O���C�g�����i���̏��W�j
�u�ꑾ�Y�v�������N�Q���~��������
�Ό��t�B�����̐����@�����i�p�����[�^�����j
���W�̋���R���ɑ���i���̌W�����ɂ��ꂽ�����o��̌���
�c�Ŕ�
�������̏��W����
���W���̋��L�҂̂P�l���P�ƂŒ�N���������R���ɑ������i��
�c�Ŕ�
�t���b�h�y���[�����i�^�����i�̕��s�A���̗v���j
�c�Ŕ�
�uBODYGLOVE�v���W �A�����~�������s���݊m�F����
�p�[�J�[����
�����̈�푝�B�@����
�i�����̔����\���j�c�Ŕ�
���������̌��́i�U���̂̉��j
�����n�̃p�u���V�e�B�[��
(�M�����b�v���[�T�[����)�c�Ŕ�
���ÃQ�[���\�t�g����
�c�Ŕ�
�L���r�[��������
�c�Ŕ�
�@�Ɋ�Â��������F�\���̂��߂̎���
�c�Ŕ�
������@�ɌW��������̌���
�i����������������@�j�c�Ŕ�
�{�[���X�v���C�������i�ϓ��_�j
�c�Ŕ�
���m��������
�c�Ŕ�
�a�a�r�����i�������i�̕��s�A���j
�c�Ŕ�
���[���f���^������
�c�Ŕ�
�u�k�[�u���v�s�������s���~����������
�R������i�ׂɂ�����g�p�ؖ����̒�o
�c�Ŕ�
�u�������g���v���W�s�g�p�����������
�؎��������y�т��̐������@����
�|�p�C����
�c�Ŕ�
�����E���C�j�[�E�i�C�g�E�C���E�g�[�L���[����
�c�Ŕ�
FM�M���������u�����i�����@�j
�c�Ŕ�
�f�[�^�`����������
�O���̓������錠��(�E������)
�c�Ŕ�
�X�i�b�N�V���l������
�c�Ŕ�
�v���[�c�v���[�Y����
�u���ێ��R�w���v���W����
�c�Ŕ�
�p�`�X���@�i���m�j���W���N�Q����
�c�Ŕ�
�u�m�e���v������������
�u���R�u���b�N�v�������N�Q���~����������
�����W�t�[�h�t�B���^�����i�ڋq�ɑ���x���̈�@���j
���쌠�N�Q���~�����������i�ʐ^�̒��쌠�j
�u���u�x���[�v���W���N�Q���~����������
�����ݒ�|���Q������������
�c�Ŕ�
�R����������i���ށj����
�u���t�ގ��ʑ��u�v����R���������
�R��������������i�ꎖ�s�ė��j
�c�Ŕ�
�`�F�������ړ]�o�^��������
�r�W�l�X�֘A�����̎�Ȕ�������W �i�������z�[���y�[�W�j
�����֘A�����̎�Ȕ�������W �i�������z�[���y�[�W�j
�@
���������̐N�Q��F��B�㍐�l���i�ɂ��ẮA���H�O�̔�㍐�l���i�Ɠ��ꐫ�������������i���V���ɐ������ꂽ���̂ƔF�߂�̂������ł���A�������ғ����䂪���ɂ����ď��n���A���͉䂪���̓������ғ������O�ɂ����ď��n�����������i�ł����㍐�l���i�̎g�p�ς݃C���N�^���N�{�̂𗘗p���Đ��i�����ꂽ�㍐�l���i�ɂ��ẮA�{���������̍s�g�����������ΏۂƂȂ���̂ł͂Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����18�N(��)��826��
�������F�@�@�@�@�������N�Q���~��������
�ٔ��N�����F�@����19�N11��08��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F �@
PAT-H18-Ju-826.pdf
�@�������i�̐V���Ȑ����ɓ����邩�ǂ����ɂ��ẮA���Y�������i�̑����A���������̓��e�A���H�y�ѕ��ނ̌����̑ԗl�̂ق��A����̎���������l�����Ĕ��f����̂������ł���A���Y�������i�̑����Ƃ��ẮA���i�̋@�\�A�\���y�эގ��A�p�r�A�ϗp���ԁA�g�p�ԗl���A���H�y�ѕ��ނ̌����̑ԗl�Ƃ��ẮA���H�������ꂽ�ۂ̓��Y�������i�̏�ԁA���H�̓��e�y�ђ��x�A�������ꂽ���ނ̑ϗp���ԁA���Y���ނ̓������i���ɂ�����Z�p�I�@�\�y�ьo�ϓI���l���l���̑ΏۂƂȂ�Ƃ����ׂ��ł���B(����)
�@�C���N�^���N�̎���̎���ȂǑO�L�����W���Ɍ��ꂽ����𑍍��I�ɍl������ƁA�㍐�l���i�ɂ��ẮA���H�O�̔�㍐�l���i�Ɠ��ꐫ�������������i���V���ɐ������ꂽ���̂ƔF�߂�̂������ł���B���������āA�������ғ����䂪���ɂ����ď��n���A���͉䂪���̓������ғ������O�ɂ����ď��n�����������i�ł����㍐�l���i�̎g�p�ς݃C���N�^���N�{�̂𗘗p���Đ��i�����ꂽ�㍐�l���i�ɂ��ẮA�{���������̍s�g�����������ΏۂƂȂ���̂ł͂Ȃ�����A�{���������̓������҂ł����㍐�l�́A�{���������Ɋ�Â��Ă��̗A���A�̔����̍��~�ߋy�єp�������߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�@
�T�i�R(�m�I���Y�����ٔ������ʕ�)�����f�[�^�F�@����17�N(�l)��10021���@�@�@�ʎ�
���R(�����n���ٔ���)�����f�[�^�F�@����16�N(��)��8557��
�g���̂ăJ��������
���������̐N�Q��F��B�Љ�ʔO����p���I�����ɂ�������炸�����I�ɂ͎g�p���\�ȓ������i�ɂ��ẮA���̍Ďg�p��ď��n�ɑ��āA�������҂���̌����s�g���������B��
�����ԍ��F�@�@�@�����W�N(��)��16782��
�������F�@�@�@�@ �������N�Q���~����������
�ٔ��N�����F�@ ����12�N08��31��
�ٔ������F�@�@�@�����n���ٔ���
�����f�[�^�F�@�@PAT-H08-wa-16782.pdf�@
���@���Ă̊T�v
�@�퍐��́A���������̗L����������A���p�V�Č��y�шӏ����̎��{�i�Ƃ��ē��{�����y�ё�ؖ����i�ȉ��u�؍��v�Ƃ����B�j�Ŕ̔����������Y�t���t�B�������j�b�g�i������u�g���̂ăJ�����v�j�ɂ��A������w��������ʏ���҂��g�p��Ɍ������Ɏ��������̂��t�B�������l�ߑւ���Ȃǂ��čēx�g�p���ł���悤�ɂ������i��A���A�������͔̔����Ă���B�{���́A�������A�퍐��ɂ��E���i�̗A���A�����y�є̔��͌����̗L����������A���p�V�Č��y�шӏ�����N�Q������̂ł���Ǝ咣���āA�A���A�����y�є̔����̍��~�ߋy�ё��Q�����i������N�܌��O�Z���t���i���ύX�̐\�����̑��B�̓��̗����ȍ~�̒x�����Q�����܂ށB�j�����߂Ă���̂ɑ��āA�퍐�炪�A���������̏��s�Ȃǂ��咣���āA����𑈂��Ă��鎖�Ăł���B
�i���|�j
�@��@���_�Q�i�������s�y�э��ۏ��s�̐��ہj�ɂ���
�@�P�@�������s�ɂ���
�@(1)�@�������Җ��͓������҂��狖���������{���҂��䂪���̍����ɂ����ē��Y���������ɌW�鐻�i�i�ȉ��u�������i�v�Ƃ����B�j�����n�����ꍇ�ɂ́A���Y�������i�ɂ��Ă͓������͂��̖ړI��B�������̂Ƃ��ď��s���A���͂�������̌��͂́A���Y�������i���g�p���A���n�����݂͑��n���s�ד��ɂ͋y�Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���i�ō��ٕ������N(�I)���㔪��������N���������O���@�씻���E���W��܈ꊪ�Z�������ŎQ�Ɓj�B
�@(2)�@�������Ȃ���A�������i�����̌��p���I������ɂ����ẮA�������҂́A���Y�������i�ɂ��ē��������s�g���邱�Ƃ����������̂Ɖ�����̂������ł���B�������A�@�@��ʂ̎���s�ׂɂ�����̂Ɠ��l�A�������i�ɂ��Ă��A����l���ړI���ɂ��������҂̌����s�g�𗣂�Ď��R�ɋƂƂ��Ďg�p���ď��n�������邱�Ƃ��ł��錠�����擾���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�s��ɂ��������s�ׂ��s������̂ł��邪�A�E�ɂ����g�p�Ȃ����ď��n���́A�������i�����̌��p���ʂ����Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ�����̂ł���A�N���̌o�߂ɔ������ނ̖��Ղ���̗��ɂ�肻�̌��p���ʂ����Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ܂ŏ���l�����Y���i���g�p�Ȃ����ď��n���邱�Ƃ�z�肵�Ă�����̂ł͂Ȃ�����A���̌��p���I������̓������i�ɓ������̌��͂��y�ԂƉ����Ă��A�s��ɂ����鏤�i�̎��R�ȗ��ʂ�j�Q���邱�Ƃɂ͂Ȃ炸�A�A�@�������҂́A�������i�̏��n�ɓ������āA���Y���i�����p���I����܂ł̊Ԃ̎g�p�Ȃ����ď��n���ɑΉ�������x�œ��������̌��J�̑Ή����擾���Ă�����̂ł��邩��A���p���I������̓������i�ɓ������̌��͂��y�ԂƉ����Ă��A�������҂���d�ɗ����邱�Ƃɂ͂Ȃ炸�A�����A���p���I�����������i�ɉ��H�����{�������̂��g�p�Ȃ����ď��n�����Ƃ��ɂ́A�������i�̐V���Ȏ��v�̋@���D���A�������҂��Q���邱�ƂƂȂ邩��ł���B
�@�E�ɂ����������i�����̌��p���I�����ꍇ�Ƃ́A�N���̌o�߂ɂ��������i�̕��ނ������I�ɖ��Ղ��A���邢�͂��̐��������w�I�ɕω������Ȃǂ̗��R�ɂ�蓖�Y���i�̎g�p�����ۂɕs�\�ƂȂ����ꍇ�����̓T�^�ł��邪�A�����I�ɂ͕�����̎g�p���\�ł���ɂ�������炸�ی��q����̊ϓ_����ēx�̎g�p���ւ����Ă�������i�Ⴆ�A�g���̂Ē��ˊ��g���̂ăR���^�N�g�����Y���j�ȂǁA�����I�ɂ͂Ȃ��g�p���\�ł����Ă����̎g�p�ɂ��Љ�ʔO����p���I�������̂ƕ]�������ꍇ�����܂ނ��̂Ɖ�������i�����I�Ȗ��Ղ���ω����ɂ��g�p���s�\�ƂȂ����������i�́A�ʏ�A�p�������̂ŁA�����@��̖����邱�Ƃ͂قƂ�Ǒz��ł��Ȃ����A�Љ�ʔO����p���I�����ɂ�������炸�����I�ɂ͎g�p���\�Ȑ��i�ɂ��ẮA���̍Ďg�p��ď��n�ɑ��āA�������҂���̌����s�g��������邩�ǂ��������ƂȂ蓾��B�j�B���̂悤�ȏꍇ�ɂ����āA�������i�����p���I����ׂ������́A�������҂Ȃ����������i�̐����ҁE�̔��҂̈ӎv�ɂ�茈��������̂ł͂Ȃ��A���Y���i�̋@�\�A�\���A�ގ���A�p�r�A�g�p�`�ԁA����̎���̎���𑍍��l�����Ĕ��f�����ׂ����̂ł���B
�@(3)�@�܂��A���Y�������i�ɂ����ē��������̖{���I�������\�������v�ȕ��ނ���菜���A�����V���ȕ��ނɌ��������ꍇ�ɂ��A�������҂́A���Y���i�ɂ��ē��������s�g���邱�Ƃ����������̂Ɖ�����̂������ł���B�������A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���Y���i�́A���͂�������҂����n�����������i�Ɠ���̐��i�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B�����Ƃ��A�����������\�����镔�ނł����Ă����Օi�i�Ⴆ�A�d�C�@��ɂ�����d�r��t�B���^�[�Ȃǁj��i�S�̂Ɣ�ׂđϗp���Ԃ̒Z���ꕔ�̕����i�Ⴆ�A�d�C�@��ɂ�����d���␅���p�@��ɂ�����h���p�p�b�L���O�Ȃǁj���������邱�ƁA���͑��������ꕔ�̕��ނ��������邱�Ƃɂ�萻�i�̏C�����s�����Ƃɂ���ẮA���܂������̐��i�Ƃ̓��ꐫ�͎����Ȃ����̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@(4)�@�咣���ؐӔC�Ɋւ��ẮA�������҂ɂ�錠���s�g�ɑ��āA������́A�R�َ����Ƃ��āA���̑ΏۂƂȂ��Ă��鐻�i���������ғ��ɂ����n���ꂽ�������i�ɗR�����邱�Ƃ��咣������A���s�𗝗R�Ƃ��ē������҂̌����s�g��Ƃ�邱�Ƃ��ł��A����ɑ��āA�������҂́A�čR�َ����Ƃ��āA���Y�Ώې��i���A�������i�Ƃ��Ċ��Ɍ��p���I�������̂ł��邱�Ɩ��͓������i�ɂ�������������̖{���I�������\�������v�ȕ��ނ������������̂ł��邱�Ƃ��咣�����邱�Ƃɂ��A���s�̐�����ے肷�邱�Ƃ��ł�����̂Ɖ�����̂������ł���B
(4)�@�����āA�E��(1)�Ȃ���(3)�ɏq�ׂ��Ƃ���́A�������݂̂Ȃ炸�A���p�V�Č��y�шӏ����ɂ��Ă����l�ɓ��Ă͂܂���̂ł���B
�@�Q�@���ۏ��s�ɂ���
�@�䂪���̓������Җ��͂���Ɠ���������҂����O�ɂ����ē������i�����n�����ꍇ�ɂ����ẮA�������҂́A����l�ɑ��ẮA���Y���i�ɂ��Ĕ̔���Ȃ����g�p�n�悩��䂪�������O����|������l�Ƃ̊Ԃō��ӂ����ꍇ�������A����l����������i���������O�ҋy�т��̌�̓]���҂ɑ��ẮA����l�Ƃ̊ԂʼnE�̎|�����ӂ�����������i�ɂ���m�ɕ\�������ꍇ�������āA���Y���i�ɂ��ĉ䂪���ɂ����ē��������s�g���邱�Ƃ͋�����Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���i�O�f�ō��ّ�O���@�약����N������������j�B�������Ȃ���A�E�̂悤�ȏ�ʂɂ����Ă��A���Y�������i�����̌��p���I���A���邢�͓������i�ɂ����ē��������̖{���I�������\�������v�ȕ��ނ��������ꂽ�Ƃ��ɂ́A�������҂ɂ�錠���s�g�͋������Ɖ�����̂������ł���B�������A�@�@���O�ł̌o�ώ���ɂ����Ă��A����l�͏��n�l���L���Ă������ׂĂ̌������擾���邱�Ƃ�O��Ƃ��Ď���s�ׂ��s������̂ł���A���̓_�͓������i�ɂ��Ă����l�ł��邪�A����́A�������i�����̌��p���ʂ����Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ�����̂ł��邩��A���̌��p���I������̓������i�ɓ������̌��͂��y�ԂƉ����Ă��A���ێ���ɂ����鏤�i�̎��R�ȗ��ʂ�j�Q���邱�Ƃɂ͂Ȃ炸�A�A�@����l���͏���l����������i���������O�҂��A���̌��p���I������̓������i���䂪���ɗA�����A���邢�͉䂪���ɂ����Ďg�p�Ȃ������n���邱�Ƃ́A�������҂ɂ����ē��R�ɗ\�z�����Ƃ���ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���A�܂��A�B�@���������̖{���I�������\�������v�ȕ��ނ������������i�́A���͂�������҂����n�����������i�Ɠ���̐��i�Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ�����ł���B
�@���������āA�������҂́A�������i�ɂ��Ĕ̔���Ȃ����g�p�n�悩��䂪�������O����|������l�Ƃ̊Ԃō��ӂ������Ƃ�E�̎|��������i�ɖ����������Ƃɑウ�āA���~�ߓ������߂�Ώې��i���A�������i�Ƃ��Ċ��Ɍ��p���I�������̂ł��邱�Ɩ��͓������i�ɂ�������������̖{���I�������\�������v�ȕ��ނ������������̂ł��邱�Ƃ��咣�����邱�Ƃɂ��A���Y�Ώې��i�ɂ��ē��������s�g���邱�Ƃ��ł���B�����āA�E�̓_�́A�������݂̂Ȃ炸�A���p�V�Č��y�шӏ����ɂ��Ă����l�ɓ��Ă͂܂���̂ł���B
�i�����j
�@(3)�@�������i�́A���a�Z��N�̔�����������A������u�g���̂ăJ�����v�Ƃ��Ĕ̔�����Ă���B�������i���w����������҂́A�������ꂽ�t�B�����̎B�e���I������́A������t�B�������j�b�g�{�̂��ƌ����掟�X�Ɏ������݁A�������o�Ċ������ꂽ�ʐ^�ƃl�K�t�B��������̂�����̂ł����āA�t�B�������j�b�g�{�͕̂Ԋ҂���Ȃ��B���̂悤�ɁA�B�e��A�t�B�������j�b�g�{�̂�����҂̎茳�Ɏc��Ȃ����Ƃ́A�������i���s��ɂ����čL��������A��ʂ̐��i���̔������̂ɔ����āi���Ȃ݂ɁA������N�ɂ����Ă͌܁Z�Z�Z�����锄��グ���L�^���Ă���B�j�A��ʏ���҂̊ԂōL���F�������Ɏ���A�퍐�炪�퍐���i�̔̔����n�߂������Z�N�̎��_�ɂ����Ă͊��ɎЉ��ʂɂ����鋤�ʔF���ƂȂ��Ă����B
�@(�l)�@�E�F�莖���ɂ��A�������i�́A������w����������҂��������ꂽ�t�B�����̎B�e���I���āA�����掟�X���o�R���Č������ɑ���A�������ɂ����ĎB�e�ς݂̃t�B���������o���ꂽ���_�ŁA�Љ�ʔO��A���̌��p���I�������̂Ƃ����ׂ��ł���B���������āA�{���ɂ����ẮA�������i�Ɏ��{����Ă���������@�A���p�V�Č��A�Ȃ����C�y�шӏ����D�Ȃ����F�ɂ��āA�������s�y�э��ۏ��s�̐�����W���鎖����݂���Ƃ����ׂ��ł��邩��A�������퍐���i�ɂ��Ă����̌������s�g���邱�Ƃ͋��������̂ł���B
�@(��)�@�܂��A�{���������̂����ӏ����D�Ȃ����F�Ɋւ��ẮA�O�L�̑����̂Ȃ������ɂ��A�t�B�����l�ւ���Ƃɂ����āA�������i�ɂ����ĉE�e�ӏ����̈ӏ����\�������v�ȕ����ł��鎆�J�o�[���O������A���珀���������J�o�[14�����t�����Ƃ����̂ł��邩��A�퍐���i�́A�ӏ��̖{���I�������\�������v�ȕ��ނ������������̂ŁA�������i�Ɠ���̐��i�ƕ]�����邱�Ƃ͂ł����A���̓_������A�������s�y�э��ۏ��s�̐����͔ے肳���B
�@(�Z)�@�퍐��́A�������i�͌������ɂ����ĎB�e�ς݃t�B�������������ꂽ������i�Ƃ��Ă̎������s������̂ł͂Ȃ��A�퍐�炪�������i�̎��J�o�[���O���āA���珀���������J�o�[14�����Ԃ���s�ׂ������̎��{�����f�U�C���̏C���ł���Ǝ咣���邪�A�������i�́A�������ɂ����ĎB�e�ς݃t�B�������������ꂽ���_�ɂ����āA�Љ�ʔO�セ�̌��p���I�������̂ł���A�ӏ����D�Ȃ����F�Ɋւ��ẮA�퍐�炪�������i�̎��J�o�[���O���Ď��珀���������J�o�[14�����Ԃ���s�ׂɂ��퍐���i�͌������i�Ɠ��ꐫ�������Ă��邱�Ƃ́A�O�ɐ��������Ƃ���ł���B�퍐��̎咣�́A�̗p�ł��Ȃ��B
���N���g�����i���̏��W�j
���������ɂ�鋑��R��������B�{�菤�W�ɂ��ẮA�������i���ʋ@�\���l�����Ă���A���W�@��R���Q����K�p���ׂ����̂ł���B��
�����ԍ��F�@�@ ����22�N(�s�P)��10169��
�������F�@ �@ �@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����22�N11��16��
�ٔ������F�@�@ �m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F�@�@TM-H22-Gke-10169.pdf
�E�E�E�O�L�F��̂Ƃ���A�C���^�[�l�b�g��̋L������F�߂���d�v�Ȏ����́A�퍐���咣����悤�ȁu���_�ۈ����̗e��͌������i���܂߂ǂ���F�����悤�Ȃ��̂��v�Ƃ������R�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�ނ�����_�ۈ����̗e��ɂ͖{���e��ƍ��������͕�i�����������݂���Ƃ̎��v�҂̔F���ł����āA���̎����́A�퍐�̎咣�Ƃ͋t�ɁA�ގ��̌`��̗e����g�p���鐔�����̑��Џ��i�����݂���ɂ�������炸�A���v�҂͂����e��̗��̓I�`��͖{���e��̖͕�i�ł���ƔF�����Ă���Ƃ������Ƃ������Ă���ƔF�߂���̂ł����āA����́A�{���e��̗��̓I�`��Ɏ������i���ʗ͂����邱�Ƃ��������F������Ƃ����ׂ��ł���B
�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@����Q�O�O�W�|�V�Q�R�S�X��
�R�J�R�[�������i���̏��W�j
���������ɂ�鋑��R��������B�{�菤�W�ɂ��ẮA���^�[�i�u���r�̎g�p�ɂ�鎩�����i���ʋ@�\���l�����Ă���A���W�@��R���Q����K�p���ׂ����̂ł���B��
�����ԍ��F�@�@ ����19�N(�s�P)��10215��
�������F�@ �@ �@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����20�N05��29��
�ٔ������F�@�@ �m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F�@�@TM-H19-Gke-10215.pdf
�@���^�[�i�u���r����̌������i�̌`����݂�ƁA�O�L(2)�A�ŔF�肵���Ƃ���A���Y�`��̒��N�ɂ킽���т����g�p�̎����i�A(�C)�j�A��ʂ̔̔����сi�A(�E)�j�A����̐�`�L�����̑ԗl�y�ю����i�A(�G)�j�A���Y���i�̌`�����̏o�������ʂ���@�\��L���Ă���Ƃ̒������ʁi�A(�I)�j���ɂ��A���^�[�i�u���r�̗��̓I�`��ɂ��Ē~�ς��ꂽ�������i�̎��ʗ͂́A�ɂ߂ċ����Ƃ����ׂ��ł���B��������ƁA�{���ɂ����āA���^�[�i�u���r����̌������i�Ɂu�b�������|�b�������v�Ȃǂ̕\�����t����Ă���_���A�{�菤�W�ɌW��`�������i���ʋ@�\���l�����Ă���ƔF�߂��ŏ�Q�ɂȂ�Ƃ����ׂ��ł͂Ȃ��i�Ȃ��A�{�菤�W�ɌW��`�A���i���̋@�\���m�ۂ��邽�߂ɕs���ȗ��̓I�`��݂̂���Ȃ鏤�W�Ƃ����Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�j�B
�i�����j
�G����
�@�ȏ�̂Ƃ���A�{�菤�W�ɂ��ẮA�������i�ɂ����郊�^�[�i�u���r�̎g�p�ɂ���āA�������i���ʋ@�\���l���������̂Ƃ����ׂ��ł��邩��A���W�@�R���Q���ɂ�菤�W�o�^���邱�Ƃ��ł�����̂Ɖ����ׂ��ł���B����ɔ�����퍐�̎咣�́A��������̗p�̌���łȂ��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@����Q�O�O�R�|�T�T�P�R�S��
�}�O���C�g�����i���̏��W�j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
���������ɂ�鋑��R��������B�{�����i�ɂ��ẮA��K�͂ȍL����`���s���A�����̏��i���̔����ꂽ���ʁA���v�҂ɂ����ď��i�̌`��𑼎А��i�Ƌ�ʂ���w�W�Ƃ��ĔF������Ɏ����Ă�����̂ƔF�߂��A�{�菤�W�́A���W�@��R���Q���ɂ�菤�W�o�^���邱�Ƃ��ł�����̂ł���B��
�����ԍ��F�@�@ ����18�N(�s�P)��10555��
�������F�@ �@ �@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����19�N06��27��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F �@
TM-H18-Gke-10555.pdf�@�@
TM-H18-Gke-10555-1.pdf
�@���i���̗��̌`����Ȃ鏤�W���g�p�ɂ�莩�����i���ʗ͂��l���������ǂ����́A���Y���W�Ȃ������i�̌`��A�g�p�J�n�����y�юg�p���ԁA�g�p�n��A���i�̔̔����ʁA�L����`�̂��ꂽ���ԁE�n��y�ыK�́A���Y�`��ɗގ��������̏��i�̑��ۂȂǂ̎���𑍍��l�����Ĕ��f����̂������ł���B�@�����āA�g�p�ɌW�鏤�W�Ȃ������i���̌`��́A�����Ƃ��āA�o��ɌW�鏤�W�Ǝ����I�ɓ���ł���A�w�菤�i�ɑ����鏤�i�ł��邱�Ƃ�v����B�����Ƃ��A���i���́A���̔̔����ɓ������āA���̏o�������Ɠ��̖��̂�L���E����������Ȃ�W�͂Ȃǂ��t�����̂��ʏ�ł��邱�ƂɏƂ点�A�g�p�ɌW�闧�̌`��ɁA����炪�t����Ă����Ƃ�������݂̂ɂ���Ē����Ɏg�p�ɂ�鎯�ʗ͂̊l����ے肷�邱�Ƃ͓K�ł͂Ȃ��A�g�p�ɌW�鏤�W�Ȃ������i���̌`��ɕt����Ă������́E�W�͂ɂ��āA���̊O�ρA�傫���A�t����Ă����ʒu�A���m�E�������̒��x���̓_���l�����A���Y���́E�W�͂��t����Ă����Ƃ��Ă��Ȃ��A���̌`���v�҂̖ڂɂ��Ղ��A������ۂ�^������̂ł��������������Ă�����ŁA���̌`�Ɨ����Ď������i���ʋ@�\���l������Ɏ����Ă��邩�ۂ��f���ׂ��ł���B
�i�����j�@
�@�{�����i�ɂ��ẮA���a�T�X�N�i�����ł͏��a�U�P�N�j�ɔ������J�n����Ĉȗ��A��т��ē���̌`����ێ����Ă���A�����Ԃɂ킽���āA���̃f�U�C���̗D�G�������������K�͂ȍL����`���s���A�����̏��i���̔����ꂽ���ʁA���v�҂ɂ����ď��i�̌`��𑼎А��i�Ƌ�ʂ���w�W�Ƃ��ĔF������Ɏ����Ă�����̂ƔF�߂�̂������ł���B�{�����i�ɁuMINI
MAGLITE�v�y�сuMAG INSTRUMENT�v�̉p�������t����Ă��邱�Ƃ́A�{�����i�ɓ��Y�p�����̕t����Ă���O�L�F��̑ԗl�ɏƂ点�A�{�菤�W�ɌW��`�������i���ʋ@�\���l�����Ă���ƔF�߂��ł̖W���ƂȂ���̂Ƃ͂����Ȃ��i�Ȃ��A�{�菤�W�ɌW��`�A���i���̋@�\���m�ۂ��邽�߂ɕs���ȗ��̓I�`��݂̂���Ȃ鏤�W�Ƃ����Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�j�B
����N�Q�B
�{�������ɌW���{������(��Q�W�O�R�Q�R�U��)�́A�����@�Q�X���Q���Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂ł���A���������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂ƔF�߂���Ƃ����ׂ��ł���A�������҂ł����T�i�l�́A���@��P�O�S���̂R��P���ɏ]���A�T�i�l�ɑ��A�{�����������s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��
�����ԍ��F�@�@ ����17�N(�l)��10040��
�������F�@ �@ �@�������N�Q���~�����T�i����
�ٔ��N�����F�@����17�N09��30��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ����@
�����f�[�^�F �@
PAT-H17-ne-10040.pdf
��Q�@���Ă̊T�v
�P�@���Ă̗v�|
(1)�@�{���́A�T�i�l���ʎ��C�������ژ^�y�у��������ژ^�i�������ʎ��ژ^�Ɠ����B�j�L�ڂ̊e���i�i���i���u�ꑾ�Y�v�y�сu�Ԏq�v�B�ȉ��A�������āu�T�i�l���i�v�Ƒ��̂���B�j�̐����A���n�����͏��n���̐\�o�����Ă���Ƃ���A��T�i�l���A�T�i�l�̑O�L�s�ׂ������@�P�O�P���Q���A�S���ɊY�����A��T�i�l�̗L�����������N�Q����Ǝ咣���āA�T�i�l�ɑ��A�����@�P�O�O���Ɋ�Â��A�T�i�l�̑O�L�s�ׂ̍��~�ߋy�эT�i�l���i�̔p�������߂����Ăł���B
(���|)
�@�{�������o�蓖���A����̏���@�\�����s���邽�߂̎�i�Ƃ��āu�A�C�R���v�͎��m�̋Z�p�����ł���A�܂��A�؋��i���P�R�����A���P�W�����j�ɂ��A���l�̎�i�Ƃ��āu���j���[�A�C�e���v�����m�̋Z�p�����ł��������Ƃ��F�߂���B�����ł���A����̏���@�\�����s���邽�߂̎�i�Ƃ��āA�u�A�C�R���v���́u���j���[�A�C�e���v�̂�������̗p���邩�́A�K�v�ɂ�蓖�Ǝ҂��K�X�I�����邱�Ƃ̂ł���Z�p�I�Ȑv�����ł���Ƃ����ׂ��ł���B�@���ɁA�A�C�R���̋@�\������\��������@�\�����s���邽�߂̎�i�ɂ��Ă݂Ă��A�{�������o��O�̂P�X�W�W�N�i���a�U�R�N�j�V���ɔЕz���ꂽ���P�Q�����i�u�n�C�p�[�v���O���}�[�̂��߂̃n�C�p�[�c�[���v�j�ɂ́A�u�n�C�p�[�c�[���́A���Ȃ����قȂ�c�[���Ɋւ������f�������邱�Ƃ��\�Ƃ���A�g�ݍ��݃w���v�@�\���܂݂܂��B���̃X�N���[����̃c�[���ɂ��ăw���v��ɂ́A�w���v�E�A�C�R�����N���b�N���܂��B�����Ď����ꂽ�c�[���̃A�C�R���̂��������ꂩ���N���b�N���܂��B�v�i�k�b�P�X�l�P�S�ʼn�����V�s�ڂȂ���������S�s�ځj�ƋL�ڂ���Ă��邩��A�{�������o�蓖���A�w���v�邽�߂̃A�C�R���A���Ȃ킿�A�@�\������\��������@�\�����s������A�C�R�����A���Ɍ��m�̎�i�ł��������Ƃ��F�߂���B
�@�����ł���A���P�W�����ɂ����āA�A�C�R���̋@�\������\��������@�\�����s������u�@�\�����\����i�v�Ƃ��āA�u�X�N���[���^���j���[�E�w���v�v�A�C�e���ɑウ�āu�A�C�R���v���̗p���邱�Ƃ́A���Ǝ҂��e�Ղɑz�������邱�ƂƂ����ׂ��ł���B
�@�����āA�{�������̍\���ɂ���Ă����炳����p���ʂ́A�A�C�R���̋@�\������\��������@�\�����s������u�@�\�����\����i�v�Ƃ��Ď��m�́u�A�C�R���v���̗p���邱�Ƃɂ�蓖�R�\���������x�̂��̂ł����āA�i�ʌ����Ȃ��̂Ƃ͂����Ȃ��B
�i�����j
�@�ȏ�ɂ��A�{�������A���Ȃ킿�A�{����P�����Ȃ����{����R�����́A���P�W�����y�ю��m�̋Z�p�����Ɋ�Â��ē��Ǝ҂��e�Ղɔ��������邱�Ƃ��ł������̂ł��邩��A�{�������ɌW��{�������́A�����@�Q�X���Q���Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂ł���A���������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂ƔF�߂���Ƃ����ׂ��ł���B���������āA�������҂ł����T�i�l�́A���@�P�O�S���̂R��P���ɏ]���A�T�i�l�ɑ��A�{�����������s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@
�������ًc�\���ɂ��
�{������(��R�R�Q�V�S�Q�R��)�̎������̔��f�Ɍ��͂Ȃ��B�L�ڕs���B�����@����R�U���T����P���Ɉᔽ��
�����ԍ��F�@ �@����17�N(�s�P)��10042��
�������F�@�@ �@ ���������������������
�ٔ��N�����F�@����17�N11��11��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F�@
PAT-H17-Gke-10042.pdf�@�@�@
PAT-H17-Gke-10042-1.pdf
�@��������\����L�߂̎����ȊO�ɂ��A���̐����ɂ�钼�����͋Ȑ���`�����Ƃ��\�ł��邱�Ƃ͎����ł��邵�A���������A���w�x���ʏ�A���炩�̒������͋Ȑ������E���Ƃ��āA���]�̌��ʁi���\�j�������邩�ۂ�����ʂ��꓾�邱�Ǝ��̂����ł��Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ł��邩��A��L�l�̋�̗�݂̂������āA��L�߂̎������A���]�̌��ʁi���\�j��������͈͂��悷�鋫�E���ł��邱�Ƃ�I�m�ɗ��t���Ă���Ƃ͓��ꂢ�����Ƃ��ł��Ȃ��B�i�����j
�@�����L(4)�A�̂Ƃ���A�����l��\����̋Z�p�I�ȕϐ��i�p�����[�^�j��p�������̐����ɂ�莦�����͈͂������ē��肵�������\���v���Ƃ���A�{�������̂悤�Ȃ�����p�����[�^�����ɂ����āA���������͈̔͂̋L�ڂ��A�����̃T�|�[�g�v���ɓK�����邽�߂ɁA�����̏ڍׂȐ����ɁA�����o�莞�̋Z�p�펯���Q�ނ��Ă݂āA�p�����[�^�i�Z�p�I�ȕϐ��j��p�������̐����������͈͓��ł���A���]�̌��ʁi���\�j��������Ɠ��Ǝ҂ɂ����ĔF���ł�����x�ɁA��̗���J�����ċL�ڂ��邱�Ƃ�v����Ɖ�����̂́A�������悤�Ƃ��锭���̋Z�p�I���e����ʂɊJ������ƂƂ��ɁA�������Ƃ��Đ���������ɂ��̌��͂̋y�Ԕ͈́i���������̋Z�p�I�͈́j�𖾂炩�ɂ���Ƃ��������̖{���̖����Ɋ�Â����̂ł���A����́A���R�̂��ƂȂ���A���̐����̎����͈͂��P�Ȃ鉯���ł͂Ȃ��A�������ʂɗ��t����ꂽ���̂ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ�����|���܂ނ��̂ł���B�����ł���A�����̏ڍׂȐ����ɁA���Ǝ҂����Y�����̉ۑ�������ł���ƔF���ł�����x�ɁA��̗���J�������A�{���o�莞�̓��Ǝ҂̋Z�p�펯���Q�ނ��Ă��A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����͈̔͂܂ŁA�����̏ڍׂȐ����ɊJ�����ꂽ���e���g���Ȃ�����ʉ��ł���Ƃ͂����Ȃ��̂ɁA�����o���Ɏ����f�[�^���o���Ĕ����̏ڍׂȐ����̋L�ړ��e���L�ڊO�ŕ⑫���邱�Ƃɂ���āA���̓��e����������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����͈̔͂܂Ŋg���Ȃ�����ʉ����A�����̃T�|�[�g�v���ɓK�������邱�Ƃ́A�����̌��J��O��ɓ�����t�^����Ƃ����������x�̎�|�ɔ���������Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�@�ȏ�̎���ŁA�{�������̓��������͈̔͂̋L�ڂ��A�����̃T�|�[�g�v���ɓK�����Ă��炸�A�����@���R�U���T���P���Ɉᔽ�����Ƃ�������̔��f�̌��i������R�P�j�����������̎咣�́A���R���Ȃ�����A�{�������̔����̏ڍׂȐ����̋L�ڂ������S���Ɉᔽ����Ƃ�������̔��f�Ɍ�肪���邩�ۂ��ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A�����咣�̎�����R�͗��R���Ȃ��A���Ɍ�����������ׂ����r�͌�������Ȃ��@
�������ٔ����ɂ�鋑��R�����������j��������R���K�@��
�����ԍ��F�@�@ ����16�N(�s�q)��4��
�������F�@ �@�@ �R�������������
�ٔ��N�����F�@����17�N07��14��
�@�얼�F�@ �@ �@�ō��ٔ�����ꏬ�@��
�@
�@����R���ɑ���i�����ٔ����ɌW�����Ă���ꍇ�ɁA���W�@�P�O���P���̋K��Ɋ�Â��ĐV���ȏ��W�o�^�o�肪����A���Ƃ̏��W�o�^�o��ɂ��Ċ菑����w�菤�i�����폜���������ꂽ�Ƃ��ɂ́A���̕�̌��ʂ����W�o�^�o��̎��ɂ����̂ڂ��Đ����邱�Ƃ͂Ȃ��A�R�������ʓI�Ɏw�菤�i���Ɋւ��锻�f����������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
���������ɂ�鋑��R�����ێ��B
�{�菤�W�́A����L���b�`�t���[�Y�Ƃ��Ă̂@�\����Ƃ��킴����A���W�@��R���P����U���ɊY������B��
| �����ԍ� |
�@����19�N(�s�P)��10127�� |
| ������ |
�@�R������������� |
| �ٔ��N���� |
�@����19�N11��22�� |
| �ٔ����� |
�@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�菤�W
�����f�[�^�F�@
TM-H19-Gke-10127.pdf
�@�{�菤�W�́A�������c�Ƃ���S���e�n�ɂ����鑽���́u���؉��v�A�u�Ώv�̊e�X�܂̊Ŕɕ\�����Ďg�p����Ă���A���̂��߁A�{�菤�W�ɂ�����u�V�����^�C�v�̋������v�Ƃ̕\���́A���X�܂̂���n�����������l�⓯�X�܂̗��p�҂ɂƂ��Ėڗ����̂Ƃ������Ƃ��ł���B�������A�{�菤�W�̓��e�́A�Ԓn�ɔ������̕����Łu�V�����^�C�v�̋������v�ƋL�ڂ��ĂȂ���̂ł���A���ꎩ�̂���́A���Y���W���t���ꂽ���H�X�ł��鋏�����������̋������Ƃ͈قȂ�V��̂��̂ł��邱�Ƃ����v�҂ɐ����Ȃ����A�s�[������Ƃ����ϔO��z�N����ɂƂǂ܂�A���ꂪ�����ɓ���̏o����\���������̂Ƃ͒ʏ�ϔO�������̂Ƃ��킴��Ȃ��B�݂̂Ȃ炸�A��L�Ŕɂ�����{�菤�W�̎g�p�ԗl�́A��������u���؉��v�A�u�Ώv�̓X�ܖ��ɕ��L���ꂽ���̂ł���A���ꎩ�̂��X�ܖ�����藣���ꂽ�P�Ƃ̂��̂Ƃ��Ďg�p���ꂽ��͌�������Ȃ��i��L�Q(2)�G�j�̂ł����āA�{�菤�W�̎w��ł�����H���̒��s���X�ܓ��ɂ����āA���X�ƍ��ʉ����邽�߁A�u�V�����^�C�v�́����v�Ƃ������傪��`���ɗp�����邱�Ƃ͑���������Ƃ���ł��邱�Ɓi��L�Q(2)�N�j���������l������ƁA�{�菤�W�ɂ�����u�V�����^�C�v�̋������v�Ƃ̌�́A��ʂɋ������ł���u���؉��v��u�Ώv���A���j���[��T�[�r�X�̓��e�A�X�܂̓������ɂ����āA�����̋������ƈقȂ�V�����^�C�v���̗p���Ă���Ƃ����̓�����\������`����Ɨ�������A�{�菤�W�͂���L���b�`�t���[�Y�Ƃ��Ă̂@�\����Ƃ��킴��Ȃ��̂ł��邩��A���ꎩ�̂ɓƗ����Ď������ʗ͂�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�@���������āA�{�菤�W�͖@�R���P���U���ɊY�����A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�������ٔ����ɂ��i���̋p��������j�����A���R�ɍ����߂����B���W���̋��L�҂̂P�l�́A���L�ɌW�鏤�W�o�^�̖����R�������ꂽ�Ƃ��́A�P�ƂŖ����R���̎���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ɖ�����̂������ł���B��
�����ԍ��F�@ �@����13�N(�s�q)��142��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����14�N02��22��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����@��
�����f�[�^�F�@
TM-H13-Ghi-142.pdf
�@�����R���́A���W���̏��Ō�ɂ����Ă��������邱�Ƃ��ł���Ƃ���Ă���i���W�@�S�U���Q���j�A���W���̐ݒ�o�^���璷���Ԍo�߂�����ɑ��̋��L�҂����ݕs�����̎��ԂɊׂ�ꍇ��A�܂��A���L�ɌW�鏤�W���ɑ��鋤�L�҂��ꂼ��̗��v��S�̏��قȂ邱�Ƃ��炷��A�i�ג�N�ɂ��đ��̋��L�҂̋��͂������Ȃ��ꍇ�Ȃǂ��l������Ƃ���A���̂悤�ȏꍇ�ɁA���L�ɌW�鏤�W�o�^�̖����R���ɑ������i�ׂ��ŗL�K�v�I�����i�ׂł���Ɖ����āA���L�҂̂P�l���P�ƂŒ�N�����i���͕s�K�@�ł���Ƃ���ƁA�o�i���Ԃ̖����Ɠ����ɖ����R�����m�肵�A���W�������߂��瑶�݂��Ȃ��������ƂƂȂ�A�s���Ȍ��ʂƂȂ茓�˂Ȃ��B�@���W���̋��L�҂̂P�l���P�ƂŖ����R���̎���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ɖ����Ă��A���̑i�ׂŐ����F�e�̔������m�肵���ꍇ�ɂ́A���̎�����̌��͂͑��̋��L�҂ɂ��y�сi�s�������i�ז@�R�Q���P���j�A�ēx�A�������ŋ��L�ґS���Ƃ̊W�ŐR���葱���s���邱�ƂɂȂ�i���W�@�U�R���Q���̏��p��������@�P�W�P���Q���j�B�����A���̑i�ׂŐ������p�̔������m�肵���ꍇ�ɂ́A���̋��L�҂̏o�i���Ԃ̖����ɂ��A�����R�����m�肵�A�����͏��߂��瑶�݂��Ȃ��������̂Ƃ݂Ȃ���邱�ƂɂȂ�i���W�@�S�U���̂Q�j�B������̏ꍇ�ɂ��A����m��̗v���ɔ����鎖�Ԃ͐����Ȃ��B����ɁA�e���L�҂��������Ė��͊e�ʂɎ���i�ׂ��N�����ꍇ�ɂ́A�����̑i�ׂ́A�ގ��K�v�I�����i�ׂɓ�����Ɖ����ׂ��ł��邩��A�����̏�R�����f����邱�ƂɂȂ�A����m��̗v���͏[�������B
�@�ȏ���������Ƃ���ɂ��A���W���̋��L�҂̂P�l�́A���L�ɌW�鏤�W�o�^�̖����R�������ꂽ�Ƃ��́A�P�ƂŖ����R���̎���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ɖ�����̂������ł���B
�Q�l����
���������̋��L�҂̈�l�����������������ɑ���R������i�ׂ̒�N���K�@�Ƃ��ꂽ����B�����ٔ����ɂ��i���̋p��������j�����A���R�ɍ����߂����B��
�����ԍ��F�@�@�@ ����13�N(�s�q)��154��
�������F�@�@�@�@�@���������������������
�ٔ��N�����F�@�@����14�N03��25��
�@�얼�F�@�@�@�@�@�ō��ٔ�����@��
�����f�[�^�F�@�@
PAT-H13-Ghi-154.pdf
�@�������錠�������L�ɌW��Ƃ��́A�e���L�҂́A���̋��L�҂Ƌ����łȂ���Γ����o������邱�Ƃ��ł����i�����@�R�W���j�A���L�ɌW��������錠���ɂ��ĐR���𐿋�����Ƃ��́A���L�҂̑S�����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă��邪�i���@�P�R�Q���R���j�A����́A���L�҂̗L����P�̌����ɂ��ē������悤�Ƃ���ɂ͋��L�ґS���̈ӎv�̍��v��v���������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��B����ɑ��A��������������̐ݒ�o�^�����ꂽ��́A�������̋��L�҂́A�����̏��n���p���{���̐ݒ蓙�̏����ɂ��Ă͑��̋��L�҂̓��ӂ�K�v�Ƃ�����̂́A���̋��L�҂̓��ӂȂ��œ��������̎��{�����邱�Ƃ��ł���i���@�V�R���j�B
�@�Ƃ���ŁA��������o�^���ꂽ�������ɂ��ē����̎�����肪���ꂽ�ꍇ�ɁA����ɑ������i�ׂ��N���邱�ƂȂ��o�i���Ԃ��o�߂����Ƃ��́A�����������߂��瑶�݂��Ȃ��������ƂƂȂ�A���������̎��{�����錠�����k�y�I�ɏ��ł�����̂Ƃ���Ă���i���@�P�P�S���R���j�B���������āA�������̋��L�҂̂P�l�́A���L�ɌW������̎�����肪���ꂽ�Ƃ��́A�������̏��ł�h���ۑ��s�ׂƂ��āA�P�ƂŎ������̎���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ɖ�����̂������ł���i
�ō��ٕ����P�R�N�i�s�q�j��P�S�Q�����P�S�N�Q���Q�Q����@�씻���E�ٔ�������P�R�P�O���T�Łk�Ғ��F���W�T�U���Q���R�S�W�Łl�Q�Ɓj�B�Ȃ��A�����@�P�R�Q���R���́u�������̋��L�҂����̋��L�ɌW�錠���ɂ��ĐR���𐿋�����Ƃ��v�Ƃ́A�������̑������Ԃ̉����o�^�̋��⍸��ɑ���s���̐R���i���@�U�V���̂R��P���A�P�Q�P���j������̐R���i���@�P�Q�U���j���̏ꍇ��z�肵�Ă���̂ł����āA��ʓI�ɁA�������̋��L�̏ꍇ�ɏ�ɋ��L�҂̑S�����������čs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ܂ŗ\�肵�Ă�����̂Ƃ͉�����Ȃ��B
�@�������̋��L�҂̂P�l���P�ƂŎ������̎���i�ׂ��N���邱�Ƃ��ł���Ɖ����Ă��A����m��̗v���ɔ�������̂Ƃ͂����Ȃ��B�܂��A�e���L�҂��������Ė��͊e�ʂɎ���i�ׂ��N�����ꍇ�ɂ́A�����̑i�ׂ͗ގ��K�v�I�����i�ׂɓ����邩��A�������ĐR�����f����邱�ƂɂȂ�A����m��̗v���͏[�������B
�@�S�@��������ƁA�{���i����s�K�@�Ƃ������R�̔��f�ɂ́A�����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̈ᔽ������B�Ȃ��A
�ō��ُ��a�R�T�N�i�I�j��U�W�S�����R�U�N�W���R�P����ꏬ�@�씻���E���W�P�T���V���Q�O�S�O�ŁA�ō��ُ��a�T�Q�N�i�s�c�j��Q�W�����T�T�N�P���P�W����@�씻���E�ٔ��W�����P�Q�X���S�R�ŋy��
�ō��ٕ����U�N�i�s�c�j��W�R�����V�N�R���V����O���@�씻���E���W�S�X���R���X�S�S�ł́A�{���Ǝ��Ă��قɂ��K�łȂ��B���������āA��������j�����A�{�Ăɂ��ĐR�������邽�߁A�{�������R�ɍ����߂����ƂƂ���B
�t���b�h�y���[�����i�^�����i�̕��s�A���̗v���j
�����W���̐N�Q��F��B�������̐����y�щ����̐����Ɉᔽ���Đ�������{���W�͂��t���ꂽ�{�����i�́A���W���҂ɂ��i���Ǘ����y���A������^�����i�̕��s�A���ƔF�߂��Ȃ��B��
�����ԍ��F �@ ����14�N(��)��1100��
�������F�@�@�@ ���Q�����A���W���N�Q���~����������
�ٔ��N�����F ����15�N02��27��
�@�얼�F�@�@�@ �ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F
TM-H14-Ju-1100.pdf
�@���W���҈ȊO�̎҂��A�䂪���ɂ����鏤�W���̎w�菤�i�Ɠ���̏��i�ɂ��A���̓o�^���W�Ɠ���̏��W��t�������̂�A������s�ׂ́A�������Ȃ�����A���W����N�Q����i���W�@�Q���R���A�Q�T���j�B�������A���̂悤�����i�̗A���ł����Ă��A�i�P�j���Y���W���O���ɂ����鏤�W���Җ��͓��Y���W���҂���g�p���������҂ɂ��K�@�ɕt���ꂽ���̂ł���A�i�Q�j���Y�O���ɂ����鏤�W���҂Ɖ䂪���̏��W���҂Ƃ�����l�ł��邩���͖@���I�Ⴕ���͌o�ϓI�ɓ���l�Ɠ���������悤�ȊW�����邱�Ƃɂ��A���Y���W���䂪���̓o�^���W�Ɠ���̏o����\��������̂ł����āA�i�R�j�䂪���̏��W���҂����ړI�ɖ��͊ԐړI�ɓ��Y���i�̕i���Ǘ����s�����闧��ɂ��邱�Ƃ���A���Y���i�Ɖ䂪���̏��W���҂��o�^���W��t�������i�Ƃ����Y�o�^���W�̕ۏ���i���ɂ����Ď����I�ɍ��ق��Ȃ��ƕ]�������ꍇ�ɂ́A������^�����i�̕��s�A���Ƃ��āA���W���N�Q�Ƃ��Ă̎����I��@�����������̂Ɖ�����̂������ł���B�������A���W�@�́A�u���W��ی삷�邱�Ƃɂ��A���W�̎g�p������҂̋Ɩ���̐M�p�̈ێ���}��A�����ĎY�Ƃ̔��B�Ɋ�^���A���킹�Ď��v�҂̗��v��ی삷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ���v���̂ł���Ƃ���i���@�P���j�A��L�e�v������������^�����i�̕��s�A���́A���W�̋@�\�ł���o���\���@�\�y�ѕi���ۏ؋@�\���Q���邱�Ƃ��Ȃ��A���W�̎g�p������҂̋Ɩ���̐M�p�y�ю��v�҂̗��v�Ȃ킸�A�����I�Ɉ�@�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł��邩��ł���B
�@�S�@�����{���ɂ��Č���ɁA�O�L�����ɂ��A�{�����i�́A�V���K�|�[�����a���O�R�����ɂ����Ė{���o�^���W�Ɠ���̏��W�̎g�p���������I�V�A�Ђ��A���W���҂̓��ӂȂ��A�_��n��O�ł��钆�ؐl�����a���ɂ���H��ɉ����������������̂ł���A�{���_��̖{�����������ɒ�߂�ꂽ�����͈̔͂���E���Đ�������{���W�͂��t���ꂽ���̂ł����āA���W�̏o���\���@�\���Q������̂ł���B
�@�܂��A�{�������������̐������̐����y�щ����̐����́A���W���҂����i�ɑ���i�����Ǘ����ĕi���ۏ؋@�\���\�S�Ȃ炵�߂��ŋɂ߂ďd�v�ł���B�����̐����Ɉᔽ���Đ�������{���W�͂��t���ꂽ�{�����i�́A���W���҂ɂ��i���Ǘ����y���A�{�����i�Ɣ�㍐�l�q�b�g���j�I�����{���o�^���W��t���ė��ʂɒu�������i�Ƃ��A�{���o�^���W���ۏ���i���ɂ����Ď����I�ɍ��ق���\��������A���W�̕i���ۏ؋@�\���Q����邨���ꂪ����B
�@���������āA���̂悤�ȏ��i�̗A����F�߂�ƁA�{���o�^���W���g�p����e�o�r�Ћy�є�㍐�l�q�b�g���j�I�����z���グ���A�u�t���b�h�y���[�v�̃u�����h�ɑ���Ɩ���̐M�p�����Ȃ�ꂩ�˂Ȃ��B�܂��A���v�҂́A��������s�A���i�ɑ��A���W���҂��o�^���W��t���ė��ʂɒu�������i�Əo���y�ѕi���ɂ����ē���̏��i���w�����邱�Ƃ��ł���|�M�����Ă���Ƃ���A��L�e�����Ɉᔽ�����{�����i�̗A����F�߂�ƁA���v�҂̐M���ɔ����錋�ʂƂȂ邨���ꂪ����B
�@�ȏ�ɂ��A�{�����i�̗A���́A������^�����i�̕��s�A���ƔF�߂��Ȃ�����A�����I��@���������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�A���Ǝ҂́A�A���\���̍ۂɗA�����i�̐����n�𖾂炩�ɂ���K�v�����邩��i�Ŗ@�U�V���A�Ŗ@�{�s�߂T�X���P���Q���j�A�O���ɂ����鏤�W���Ҏ��g�ł͂Ȃ��A���l����g�p���������҂��䂪���ɂ�����o�^���W�Ɠ���̏��W��t�������i��A������ꍇ�ɂ����ẮA���Ȃ��Ƃ��A�g�p�����_���A�틖���҂��������ɂ����ē��Y���i�������Y���W��t���邱�Ƃ��ł��錠����L���邱�Ƃ��m�F������œ��Y���i��A�����ׂ��ł���B��L�`����s��������Ŗ{�����i��A���������Ƃ̗��̂Ȃ��㍐�l�ɂ��A�ߎ��̐���i���W�@�R�X���ɂ����ď��p��������@�P�O�R���j�����Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�T�@�ȏ�ɂ��A�㍐�l�̖{�����i�̗A���̔��s�ׂ��{�����W����N�Q����Ƃ��āA�㍐�l�̐��������p���A��㍐�l�q�b�g���j�I���̐������ꕔ�F�e���ׂ����̂Ƃ������R�̔��f�́A�����Ƃ��Đ��F���邱�Ƃ��ł���
�����W���̐�p�g�p���Ɋ�Â����~��������L���Ȃ����Ƃ��m�F�B�̔��n�搧�������Ɉᔽ�B��
�����ԍ��F�@ �@����15�N(��)��3396��
�������F�@�@�@�@�A�����~�������s���݊m�F��������
�ٔ��N�����F�@����15�N06��30��
�ٔ������F�@ �@�����n���ٔ���
�����f�[�^�F�@
TM-H15-wa-3396.pdf�@�@�@
TM-H15-wa-3396-1.pdf
��Q�@���Ă̊T�v
�@�@�@�{���́A�ʎ����W�ژ^�P�L�ڂ̊e���W�i�ȉ��u�}���[�V�A���W�v�Ƒ��̂���B�j�̕t���ꂽ�e�B�[�V���c�y�у|���V���c��A�������������A�}���[�V�A���W�Ɠ��ꖔ�͗ގ��̏��W�ɂ��Ă̏��W���̐�p�g�p���҂ł���퍐�ɑ��āA��L���i�̗A���͐^�����i�̕��s�A���ł��邩���@�����j�p�����Ƃ��āA�����i�̗A���y�є̔��������~�߂錠����L���Ȃ����Ƃ̊m�F�����߂����Ăł���B
(���|)
�@�퍐�́A�@�a�f�h�Ƃa�f�l�Ƃ̊Ԃ̃��C�Z���X�_��ɂ����Ă͔̔��n��̎挈�߂����邱�ƁA�A�{�����i�́A�����̔����Ɋ�Â��A���������{�Ŕ̔����邽�߂ɐ������ꂽ���̂ł���A�����͖{�����i���a�f�l���璼�ڍw���������Ƃ�O��Ƃ��āA��L�̔̔��n�搧�������Ɉᔽ���邩��A�{�����i��A�����錴���̍s�ׂ́A�����I�Ȉ�@���������Ƃ͂����Ȃ��|�咣����B�������A�퍐�̎咣�́A�ȉ��̗��R�ɂ�莸���ł���B�@�܂��A�{���S�؋��ɂ����A�@�a�f�l�Ƃa�f�h�Ƃ̑O�L���C�Z���X�_��ɂ����āA�a�f�l�̏��i�̔̔��n�悪�}���[�V�A�ɐ�������Ă����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�܂��A�A�O�L�̂Ƃ���A�����́A�{�����i���}���[�V�A�̖@�l�ł���`�[�t���\�[�X�C�Y�Ђ���w�������̂ł���A�a�f�l���璼�ڍw�������̂ł͂Ȃ��̂ł��邩��A�����̎咣�͂��̑O���������������B
�@�����āA���ɁA�a�f�l�Ƃa�f�h�Ƃ̑O�L���C�Z���X�_��ɂ����āA�a�f�l�̏��i�̔̔��n�悪�}���[�V�A�ɐ��������|�̍��ӂ��������Ƃ��Ă݂Ă��A���C�Z���X�_��ɂ�����̔��n��̐����ɌW��挈�߂́A�ʏ�A���W���҂̔̔������̗��R�ł��ꂽ�ɂ������A���i�ɑ���i�����Ǘ����ĕi����ێ�����ړI�Ɖ��炩�̊W������Ƃ͉�����Ȃ��B��L�挈�߂Ɉᔽ���ď��i���̔����ꂽ�Ƃ��Ă��A�s��Ɋg�z���ꂽ���i�̕i���ɉ��炩�̍��ق������邱�Ƃ͂Ȃ�����A�{�����i�̗A���ɂ���āA�a�f�h�̏o���ɌW�鏤�i�̕i���Ȃ����M�p�̈ێ����Q���錋�ʂ��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@������̗��R�ɂ���Ă��A�������{�����i��A�����邱�Ƃ������I�Ɉ�@�ł���Ƃ͂����Ȃ��B
�@�Ȃ��A�퍐�́A�����͂a�f�l�ɂa�f�h�Ƃ̃��C�Z���X�_��ɂ�����̔��n������Ɉᔽ����s�ׂ������A�����ɔF�߂��Ă��鑍�㗝�X�V�X�e�����Q���Ă��邩��A�{�����i�̗A���̈�@�����j�p����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ��咣����B�������A�����������㗝�X�V�X�e�����̗p���邱�Ƃɂ��A���W���҂����ۓI�ȉ��i������ێ��ł��闘�v�́A���W�@��ی�ɒl���闘�v�ł���Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̓_�̔퍐�̎咣�͎����ł���B
�p�[�J�[����
�����W���̐�p�g�p���Ɋ�Â����~��������L���Ȃ����Ƃ��m�F�B��
�����ԍ��F�@ �@�@���a43�N(��)��7003��
�ٔ��N�����F�@�@���a45�N02��27��
�ٔ������F�@�@�@ ���n���ٔ���
�����f�[�^�F�@�@
TM-S43-wa-7003.pdf
�@����l�����ꏤ�W�ɂ������y�ъO���ɂ����ēo�^�Ă���ꍇ�ɁA�O���ɂ����Č����҂ɂ�萳���ɂȂ��ꂽ���i�̊g�z�ɂ��O�����W���̏��Ղ͓������W���ɂ��Ă������ɏ��Ղ̌��ʂ������炷�Ɖ����A����̓p�����ɂ������W���Ɨ��̌����Ƃ͊W���Ȃ��Ƃ̌����ɗ����ٔ��Ⴊ���[���c�p�ɂ͑����������A�����͉E���_�����p���A�{���p�[�J�[���i�́A�p�[�J�[�Ђ��č��ɂ����āA�u�o�`�q�j�d�q�v�̏��W���Đ������A��������`�ɗA�o���A���`�̎戵�Ǝ҂��瓯�n�̃����A���X�E�J���p�j�[�ɔ���n���ꂽ���̂ł��邩��A�E���i�ɂ��ẮA����ɕ����ꂽ���W�ɂ��Ă̌����́A�č���荁�`�ɑ���A�o�̍ۂɁA���͏��Ȃ��Ƃ����`�ɂ�����戵�̍ۂɏ��s���ꂽ�Ǝ咣���邯��ǂ��A�E�̗��_�ɂ͂��₷���^�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�������A�����҂����W���N�Q�𗝗R�ɑ�O�҂̍s�ׂ����~�߂�ɂ́A���̍s�ׂ��`���I�ɖ������҂̍s�ׂł��邱�Ƃ̂ق��A�����I�ɂ���@�ȍs�ׂł��邱�Ƃ��K�v�ł���Ɖ����ׂ��ł���B����l�����E�I�ɒ����ȏ��W�ɂ��A�O���y�ѓ����ɓo�^�Ă���ꍇ�ɁA��O�҂����̓o�^���W�������i��A������s�ׂ������I�ɂ���@�ȍs�ׂł��邩�ǂ����f����ɓ����āA���̏��W�����E�I�ɒ����ȏ��W�ł��邱�ƁA�E���i���O���ɂ����Č����҂ɂ�萻�����ꐳ���ɏ��W��������ď��n���ꂽ���̂ł��邩�ȂǁA�O���ɂ����鎖���Ȃ����s�ׂ����₭���邱�Ƃ́A�Ȃ�珤�W���Ɨ��̌����ɂ��Ƃ���̂ł͂Ȃ��Ɖ�������B
�i�O�j�@�����ŁA�����ɂ��^���p�[�J�[���i�̗A���̔��s�ׂ��{���o�^���W�̋@�\�y�ъW�����v�ɂ����Ȃ�e�����y�ڂ����̂ł��邩�����Ɍ�������B
�@���s���W�@�͏��W���Ɖc�ƂƂ�s���̂��̂Ƃ����A���W���ɂ���p�g�p�����邢�͒ʏ�g�p���̐ݒ��F�߂Ă��邪�A���ꏤ�W�ɂ�����l�������y�ъO���ɂ����ď��W����L���A��ɂ��̏��W���{���u�o�`�q�j�d�q�v���W�̂悤�ɐ��E�I�ɒ����ȏ��W�ł���ꍇ�ɂ́A���W���҂��������W���ɂ���p�g�p����ݒ肷��̂́A�w��ǂ̏ꍇ��p�g�p���҂ɑ��O���ɂ����Đ����������i�̓����ɂ�������̔�����^���邽�߂݂̖̂ړI�ōs�Ȃ�����̂ł���A�{���ɂ����Ă����̗�O���Ȃ����̂ł͂Ȃ����A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A���Y�������W�ɂ�Ď��ʂ���鏤�i�̏o���́A���ʂ̎���̂Ȃ�����E���i�̐��Y���ł��āA�����̔̔����ł͂Ȃ��ƍl������B
�@���ɖ��炩�ɂ����Ƃ���A�퍐�͕č����珤�W���҂���p�[�J�[�Ђɂ����āu�o�`�q�j�d�q�v�Ȃ鏤�W�������i��A�����A����������Ŕ̔����Ă��邾���ł���A���{�ɂ����āu�o�`�q�j�d�q�v�̏��W�����w�菤�i�����Ă�����̂ł͂Ȃ����A�킪���ɂ����Ă͑����ȑO����u�o�`�q�j�d�q�v�̏��W�������N�M�Ƃ����A�E���W�͐��p�[�J�[�Ђ̐����̔��ɂ����锕���i�̕W���Ƃ��Ď��v�҂ɔF������Ă������Ƃ͌��m�̎����ł���A�ؐl�y�a�z�̏،��ɂ��ƁA�퍐�͏��a�O��N�������X�I�Ƀp�[�J�[���N�M�A�p�[�J�[�C���N���̃p�[�J�[�А��i�̗A�����J�n���A���ݔN�Ԏ��`���Z�Z�Z���~�̔�p�𓊂��ē��А��i�̍L����`���s�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��F�߂��邯��ǂ��A�E�̎����݂̂ɂ���ẮA�u�o�`�q�j�d�q�v���W�����{�ɂ��������̗A���̔��Ǝ҂���o�����i�̕W���ł��邱�Ƃ������̎��v�҂̈ӎ��ɐZ�����Ă�����̂Ƃ͖����F�߂�ɑ���Ȃ��B
�@�������Ƃ���A
�O�q�̂悤�Ɍ����̗A���̔����悤�Ƃ���p�[�J�[�Ђ̐��i�Ɣ퍐�̗A���̔�����p�[�J�[�Ђ̐��i�Ƃ͑S������ł����āA���̊Ԃɕi���㍱���̍��ق��Ȃ��ȏ�A�u�o�`�q�j�d�q�v�̏��W�̕����ꂽ�w�菤�i�������ɂ���ėA���̔�����Ă��A���v�҂ɏ��i�̏o���i���ɂ��Č�F���������߂�댯�͑S�������Ȃ��̂ł��āA�E���W�̉ʂ��@�\�͏������Q����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł����B���̂悤�ɁA�E���W�������i�ɑ�����v�҂̐M���������邨���ꂪ�Ȃ��Ƃ���A���Ȃ��Ƃ����v�҂̕ی�Ɍ�����Ƃ���͂Ȃ��݂̂Ȃ炸�A���W���҂���p�[�J�[�Ђ̋Ɩ���̐M�p���̑��c�Ə�̗��v�����Ȃ��Ȃ����Ƃ͎����ł��낤�B�܂��{�����W�̔@�����E�I�ɒ����ȏ��W�ɂ��ẮA�e���̎��v�҂͂��̏��W�������̓o�^���W�ł��邩�O���̂���ł��邩����Ƃ����A���W����������\������_���d�����ē��Y���W�̕����ꂽ���i���w������̂��ʏ�ł���A�퍐���������W�̐�p�g�p���҂Ƃ��ėL����Ɩ���̐M�p�́A�p�[�J�[�Ђ��E���W�̎g�p�ɂ�Ēz���グ���p�[�J�[���i�̐��E�s��ɂ����閼���ƕ\����́A�s���̊W�ɂ����āA����Ƃ͕ʌ̓Ɨ��������݂ł���Ƃ͉�����ꂸ�A�O�����b���A�̊e��Ȃ����O�A�ؐl�y�a�z�̏،��ɂ�ĉM������̎����A���Ȃ킿�A�p�[�J�[�Ђ��A�퍐�ɑ����W��p�g�p����ݒ肵����ɂ����Ă��A�퍐�̓��{�ɂ����ĂȂ��p�[�J�[���i�̐�`�L����p�̘Z�Z���S���A���{�ɂ�����p�[�J�[���i�̖����̕ێ��ɓw�߁A���A�č��y�э��`�ɂ����Ĕz�z����Ă����`�p���t���c�g�ƌ���A�������قȂ邾���ŕ��͂̈Ӗ����e�������A�f�ڎʐ^�A���C�A�E�g���̑��̑̍ق͂������肻�̂܂܂̓��{������`�p���t���c�g��č��ɂ����Ĉ�����������A�������{�ɑ��t���Ĕ퍐�̎�ɂ��z�z�����Ă��鎖���́A�퍐�̗L����Ɩ���̐M�p�ƃp�[�J�[�Ђ̗L����Ɩ���̐M�p�Ƃ���̕s���̊W�ɂ��邱�Ƃ𗠕t���鎑����������Ȃ�Ȃ��̂ł���B
���������āA�����̂Ȃ��^���p�[�J�[���i�̗A���̔��ɂ���āA�퍐�͓����s��̓Ɛ�I�x�z����������邱�Ƃ͂����Ă��A�p�[�J�[�Ђ̋Ɩ���̐M�p�����Ȃ��邱�Ƃ��Ȃ��ȏ�A�퍐�̋Ɩ���̐M�p���܂����Ȃ��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��A�ނ���A��O�҂ɂ��^�����i�̗A����F�߂�Ƃ��́A�����ɂ����鉿�i�y�уT�[�r�X���Ɋւ�������Ȏ��R�����������A���v�҂ɗ��v�������点���邱�Ƃ��l������ق��A���ۖf�Ղ����i����A�Y�Ƃ̔��B���h�������Ƃ����ϋɓI���_������A�p���ď��W�@�̖ړI�ɂ��K�����錋�ʂ���̂ł���B
�����̈�푝�B�@�����i�����̔����\���j
�����������R���̐����s�����R�����ێ����鍂�ٔ����F�������������R������
�����ԍ��F�@ �@����10�N(�s�c)��19��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����12�N02��29��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H10-Gtsu-19.pdf
�@�����́A���R�@���̗��p�Ɋ�b�t����ꂽ���̋Z�p�Ɋւ���n��I�Ȏv�z�ł��邪�A���̑n�삳�ꂽ�Z�p���e�́A���̋Z�p����ɂ�����ʏ�̒m���o�������҂ł���Ή��l�ł���������{���Ă��̖ړI�Ƃ���Z�p���ʂ������邱�Ƃ��ł�����x�ɂ܂ŋ�̉�����A�q�ω����ꂽ���̂łȂ���Ȃ�Ȃ�����A���̋Z�p���e�����̒��x�ɍ\������Ă��Ȃ����̂́A�����Ƃ��Ă͖������̂��̂ł����āA�����@����ꍀ�ɂ����u�����v�Ƃ͂����Ȃ��i�ō��ُ��a�O��N�i�s�c�j�������l�l�N�ꌎ����O���@�씻���E���W��O���ꍆ�l�ŎQ�Ɓj�B���������āA�����ɂ����u���R�@���𗘗p�����v�����ł��邽�߂ɂ́A���Ǝ҂���������{���邱�Ƃɂ�蓯�ꌋ�ʂ��邱�ƁA���Ȃ킿�A�����\���̂��邱�Ƃ��K�v�ł���B�����āA���̔����\���́A�u�A���̐V�i�����킵���B������@�v�ɌW�锭���̈��ߒ��Ɋւ��ẮA���̓����ɂ��݁A�Ȋw�I�ɂ��̐A�����Č����邱�Ƃ����Ǝ҂ɂ����ĉ\�ł���Α���A���̊m�����������Ƃ�v���Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B�������A�E�����ɂ����ẮA�V�i�킪��킳���A���̌�͏]���p�����Ă��鑝�B���@�ɂ��Đ��Y���邱�Ƃ��ł���̂ł����āA�m�����Ⴍ�Ă��V�i��̈�킪�\�ł���A���Y�����̖ړI�Ƃ���Z�p���ʂ������邱�Ƃ��ł��邩��ł���B�@�l�@�����{���ɂ��Ă݂�ƁA�O�L�̂Ƃ���A�{�������̈��ߒ��́A��������{���ĉȊw�I�ɖ{�������Ɠ����`����L���铍���Č����邱�Ƃ��\�ł��邩��A���Ƃ����̊m�����������̂Ƃ͂����Ȃ��Ƃ��Ă��A�{�������ɂ͔����\��������Ƃ����ׂ��ł���B�Ȃ��A�����̔����\���́A�����o�蓖���ɂ���Α���邩��A���̌�e�i��ł���Ӊ��������ݕs���ɂȂ������Ƃ́A�E���f�����E������̂ł͂Ȃ��B�@
���������̐N�Q��F��B��
�����ԍ��F�@ �@����8�N(�l)��2394��
�������F�@�@�@�@�������N�Q���~��������
�ٔ��N�����F�@����9�N01��30��
�ٔ������F�@ �@���������ٔ����@
�����f�[�^�F�@
PAT-H08-ne-2394.pdf�@�@
PAT-H08-ne-2394-1.pdf
�@�T�i�l�́A�u���L�\�v���t�F���i�g���E���������v�́u���L�\�v���t�F���i�g���E���a���v�ƕ������Ⴂ�A��܂Ƃ��Ă̐����A�g�p���l������ƁA���҂͎����I�ɓ���Ƃ͂����Ȃ��|�咣����B�@���{�̑��y�ѐ����ɑ����̂Ȃ��b���ꍆ�؋y�ѐ����ɑ����̂Ȃ�����ꍆ�A����ɂ��A���L�\�v���t�F���i�g���E���a����L�������Ƃ��ĊܗL�����T�i�l�̐��܁i���L�\�j���j�́A�l�̓��ɂ����ẮA���L�\�v���t�F���ƂȂ��ď����ǂ���z������A���̌㊈����ӕ��k�����������\�n�g�́i�r�q�r�z�ʁj�l�ɕω����āA�R���ǁA���ɋy�щ�M��p���������̂ł���A�{�����������̑Ώە����̈��Ƃ��Ă̗L�p���͂��ׂċ�����Ă����A���̃J�^���O�y�ш��i�C���^�r���[�t�H�[���ɂ����ẮA���i�Ƃ��Ă̗p�ʂ��A�������Ƃ��Ă̎��ʂɊ��Z���ĕ\�����Ă��邱�Ƃ��F�߂���B
�@�E�����ɂ��A���L�\�v���t�F���i�g���E�����������ł��邩�a���ł��邩�́A�R���ǁA���ɋy�щ�M��p�Ƃ������Ƃ��Ă̌��\�ɂ͉e�����Ȃ����̂ƔF�߂��A���Ƃ��Ă̊ϓ_����݂�Ƃ��A�u���L�\�v���t�F���i�g���E���������v�Ɓu���L�\�v���t�F���i�g���E���a���v���A�قȂ鉻�w�����Ƃ��Ď�舵�����R�͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@���Ƃ��u���L�\�v���t�F���i�g���E���a���v�Ɓu���L�\�v���t�F���i�g���E���������v�Ƃ͈قȂ镨���ł��邩��A�O�L�̂悤�ȍR���ǁA���ɋy�щ�M��p�Ƃ���������ꎩ�̂ɉe�����y�ڂ��Ȃ������ɍ������邱�Ƃ͓��R�\�������Ƃ���ł���A���̂悤�ȑ���ɗR�����āA���܉��̗e�Ր����ɂ��ė������ɍ��ق�������̂ƍl�����邪�A���̂悤�Ȃ��Ƃ́A�E���҂��{�����������̑Ώە����ł��郍�L�\�v���t�F���i�g���E�����ɊY�����邩�ۂ����l����ꍇ�ɖ��ƂȂ�Ȃ������ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@
�������n�̖��̓����ڋq�z���͂�L����Ƃ��Ă��A�����n�̖��̓��̖��f���p�s�ׂɊւ���s�@�s�ׂ̐��ۂɂ��Ĉ�@�Ƃ����s�ׂ͈̔́A�ԗl�����@�ߓ��ɂ�薾�m�ɂȂ��Ă���Ƃ͂����Ȃ������_�ɂ����āA�����n�̖��̓��̎g�p�ɂ����~�ߖ��͕s�@�s�ׂ̐������m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����13�N(��)��866��
�������F�@�@�@�@����̔����~����������
�ٔ��N�����F�@����16�N02��13��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����@��
�����f�[�^�F�@
CP-H13-Ju-866.pdf
�@�P�R������́A�{���e�����n�����L���A���͏��L���Ă����҂ł��邪�A�����n���̕��̏��L���́A���̕��̗L�̕��Ƃ��Ă̖ʂɑ���r���I�x�z���\�ł���ɂƂǂ܂�A���̕��̖��̓��̖��̕��Ƃ��Ă̖ʂڔr���I�Ɏx�z���錠�\�ɋy�Ԃ��̂ł͂Ȃ�����A��O�҂��A�����n�̗L�̕��Ƃ��Ă̖ʂɑ��鏊�L�҂̔r���I�x�z���\��N�����ƂȂ��A�����n�̖��̓����L����ڋq�z���͂Ȃǂ̋����n�̖��̕��Ƃ��Ă̖ʂɂ�����o�ϓI���l�𗘗p�����Ƃ��Ă��A���̗��p�s�ׂ́A�����n�̏��L����N�Q������̂ł͂Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���i
�ō��ُ��a�T�W�N�i�I�j��P�V�P�����T�X�N�P���Q�O����@�씻���E���W�R�W���P���P�ŎQ�Ɓj�B�{���ɂ����ẮA�O�L�����W�ɂ��A�P�R�퍐�́A�{���e�Q�[���\�t�g��A�̔������ɂƂǂ܂�A�{���e�����n�̗L�̕��Ƃ��Ă̖ʂɑ���P�R������̏��L���Ɋ�Â��r���I�x�z���\��N�������̂ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��邩��A�P�R�퍐�̏�L����A�̔��s�ׂ́A�P�R������̖{���e�����n�ɑ��鏊�L����N�Q������̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@(2)�@
���s�@��A���̖��̂̎g�p�ȂǁA���̖��̕��Ƃ��Ă̖ʂ̗��p�Ɋւ��ẮA���W�@�A���쌠�@�A�s�������h�~�@���̒m�I���Y���W�̊e�@�����A���͈̔͂̎҂ɑ��A���̗v���̉��ɔr���I�Ȏg�p����t�^���A���̌����̕ی��}���Ă��邪�A���̔��ʂƂ��āA���̎g�p���̕t�^�������̌o�ϊ����╶���I�����̎��R���ߓx�ɐ��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ɂ��邽�߁A�e�@���́A���ꂼ��̒m�I���Y���̔��������A���e�A�͈́A���Ō��������߁A���̔r���I�Ȏg�p���̋y�Ԕ͈́A���E�m�ɂ��Ă���B
�@��L�e�@���̎�|�A�ړI�ɂ��݂�ƁA�����n�̖��̓����ڋq�z���͂�L����Ƃ��Ă��A���̖��̕��Ƃ��Ă̖ʂ̗��p�̈�ԗl�ł��鋣���n�̖��̓��̎g�p�ɂ��A�@�ߓ��̍������Ȃ������n�̏��L�҂ɑ��r���I�Ȏg�p������F�߂邱�Ƃ͑����ł͂Ȃ��A�܂��A�����n�̖��̓��̖��f���p�s�ׂɊւ���s�@�s�ׂ̐��ۂɂ��ẮA��@�Ƃ����s�ׂ͈̔́A�ԗl�����@�ߓ��ɂ�薾�m�ɂȂ��Ă���Ƃ͂����Ȃ������_�ɂ����āA������m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B���������āA�{���ɂ����āA���~�ߖ��͕s�@�s�ׂ̐������m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�@
���ÃQ�[���\�t�g����
����N�Q�B�f��̒��앨�ɊY��
�B�������A�Еz���̂������n���錠���͂��̖ړI��B���������̂Ƃ��ď��s���A���͂⒘�쌠�̌��͂́A�Q�[���\�t�g�̒��Õi�����O�ɍď��n����s�ׂɂ͋y�Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����13�N(��)��952��
�������F�@�@�@�@���쌠�N�Q�s���~��������
�ٔ��N�����F�@����14�N04��25��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F�@
CP-H13-Ju-952.pdf
�@�������Җ��͓������҂��狖���������{���҂��䂪���̍����ɂ����ē��Y�����ɌW�鐻�i�����n�����ꍇ�ɂ́A���Y�������i�ɂ��Ă͓������͂��̖ړI��B���������̂Ƃ��ď��s���A���͂�������̌��͂́A���Y�������i���ď��n����s�ד��ɂ͋y�Ȃ����Ƃ́A���R�̔���Ƃ���Ƃ���ł���i�ō��ٕ����V�N�i�I�j��P�X�W�W�����X�N�V���P����O���@�씻���E���W�T�P���U���Q�Q�X�X�Łj�A���̗��́A���앨���͂��̕����������n����ꍇ�ɂ��A�����Ƃ��đÓ�����Ƃ����ׂ��ł���B�������A(�A)�@���쌠�@�ɂ�钘�쌠�҂̌����̕ی�́A�Љ�����̗��v�Ƃ̒��a�̉��ɂ����Ď�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A(�C)�@��ʂɁA���i�����n����ꍇ�ɂ́A���n�l�͖ړI���ɂ��ėL���錠��������l�Ɉړ]���A����l�͏��n�l���L���Ă����������擾������̂ł���A���앨���͂��̕����������n�̖ړI���Ƃ��Ďs��ł̗��ʂɒu�����ꍇ�ɂ��A����l�����Y�ړI���ɂ����R�ɍď��n�����邱�Ƃ��ł��錠�����擾���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA����s�ׂ��s������̂ł����āA���ɁA���앨���͂��̕������ɂ��ď��n���s���s�x���쌠�҂̋�����v����Ƃ������ƂɂȂ�A�s��ɂ����鏤�i�̎��R�ȗ��ʂ��j�Q����A���앨���͂��̕������̉~���ȗ��ʂ��W�����āA�������Ē��쌠�Ҏ��g�̗��v���Q���邱�ƂɂȂ邨���ꂪ����A�Ђ��Ắu����ғ��̌����̕ی��}��A�����ĕ����̔��W�Ɋ�^����v�i���쌠�@�P���j�Ƃ������쌠�@�̖ړI�ɂ������邱�ƂɂȂ�A(�E)�@�����A���쌠�҂́A���앨���͂��̕�������������n����ɓ������ď��n������擾���A���͂��̗��p����������ɓ������Ďg�p�����擾���邱�Ƃ��ł���̂ł��邩��A���̑㏞���m�ۂ���@��͕ۏႳ��Ă�����̂Ƃ������Ƃ��ł��A���쌠�Җ��͋��������҂�����n���ꂽ���앨���͂��̕������ɂ��āA���쌠�ғ�����d�ɗ����邱�Ƃ�F�߂�K�v���͑��݂��Ȃ�����ł���B�@�Ƃ���ŁA�f��̒��앨�̔Еz���Ɋւ��钘�쌠�@�Q�U���P���̋K��́A���w�I�y�є��p�I���앨�̕ی�Ɋւ���x���k���i�P�X�S�W�N�U���Q�U���Ƀu���b�Z���ʼn������ꂽ�K��j���f��̒��앨�ɂ��ĔЕz����݂��Ă������Ƃ���A���s�̒��쌠�@���莞�ɁA����̋`���̗��s�Ƃ��ċK�肳�ꂽ���̂ł���B�f��̒��앨�ɂ̂ݔЕz�����F�߂�ꂽ�̂́A�f�搻��ɂ͑��z�̎��{����������Ă���A���ʂ��R���g���[�����Č����I�Ɏ��{���������K�v�����������ƁA���쌠�@���蓖���A����p�f��̎���ɂ��ẮA�O�L�̂Ƃ����畡���i�̐����ɂ킽��ݗ^��O��Ƃ��邢����z�����x�̊��s�����݂��Ă������ƁA���쌠�҂̈Ӑ}���Ȃ���f�s�ׂ��K�����邱�Ƃ�����ł��邽�߁A���̑O�i�K�ł��镡�����̏��n�Ƒݗ^���܂ޔЕz�s�ׂ��K������K�v�����������Ɠ��̗��R�ɂ����̂ł���B���̂悤�Ȏ����A���@�Q�U���̋K��̉��߂Ƃ��āA��L�z�����x�Ƃ���������Ԃ̂���f��̒��앨���͂��̕������ɂ��ẮA�����̒��앨�������O�ɒ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ď��n���A���͑ݗ^���錠���i���@�Q�U���A�Q���P���P�X����i�j�����s���Ȃ��Ɖ�����Ă������A���@�Q�U���́A�f��̒��앨�ɂ��Ă̔Еz�������s���邩�ۂ��ɂ��āA����̒�߂����Ă��Ȃ��ȏ�A���s�̗L���́A�����߂ɂ䂾�˂��Ă���Ɖ������B
�@�����āA�{���̂悤�Ɍ��O�ɒ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ȃ��ƒ�p�e���r�Q�[���@�ɗp������f��̒��앨�̕������̏��n�ɂ��ẮA�s��ɂ����鏤�i�̉~���ȗ��ʂ��m�ۂ���ȂǁA��L(�A)�A(�C)�y��(�E)�̊ϓ_����A���Y���앨�̕����������O�ɏ��n���錠���́A��������K�@�ɏ��n���ꂽ���Ƃɂ��A���̖ړI��B���������̂Ƃ��ď��s���A���͂⒘�쌠�̌��͂́A���Y�����������O�ɍď��n����s�ׂɂ͋y�Ȃ����̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@�Ȃ��A�����P�P�N�@����V�V���ɂ�������̒��쌠�@�Q�U���̂Q��P���ɂ��A�f��̒��앨���������앨�ɂ����n�����F�߂��A�����Q���ɂ��A��������K�@�ɏ��n���ꂽ�ꍇ�ɂ�������n���̏��s���K�肳�ꂽ���A�f��̒��앨�ɂ��Ă̔Еz���ɂ͏��n���錠�����܂܂�邱�Ƃ���A���n�����K�肷�铯���P���͉f��̒��앨�ɓK�p����Ȃ����ƂƂ���A�����Q���ɂ����āA��L�̂悤�ȏ��s�̌������m�F�I�ɋK�肵�����̂ł����āA�����P�A�Q���̔��Ή��߂ɗ����Ė{���e�Q�[���\�t�g�̂悤�ȉf��̒��앨�̕������ɂ��ď��n���錠���̏��s���ے肳���Ɖ�����̂͑����łȂ��B
�@��������ƁA�{���e�Q�[���\�t�g���A�㍐�l������Ƃ��ēK�@�ɔ̔�����A�����X����Ď��v�҂ɍw�����ꂽ���Ƃɂ��A���Y�Q�[���\�t�g�ɂ��ẮA�Еz���̂������n���錠���͂��̖ړI��B���������̂Ƃ��ď��s���A���͂⒘�쌠�̌��͂́A��㍐�l��ɂ����ē��Y�Q�[���\�t�g�̒��Õi�����O�ɍď��n����s�ׂɂ͋y�Ȃ��B
���������R�����݂��邱�Ƃ����炩�ȓ������Ɋ�Â����~�߁A���Q�������̐����́A�����̗��p�ɓ����苖����Ȃ��B���̔����������������@�������s���A��P�O�S���̂R���K�肳�ꂽ�B��
�����ԍ��F�@ �@����10�N(�I)��364��
�������F�@�@�@�@���s���݊m�F��������
�ٔ��N�����F�@����12�N04��11��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H10-o-364.pdf
�@�����̖����R�����m�肷��ȑO�ł����Ă��A�������N�Q�i�ׂ�R������ٔ����́A�����ɖ������R�����݂��邱�Ƃ����炩�ł��邩�ۂ��ɂ��Ĕ��f���邱�Ƃ��ł���Ɖ����ׂ��ł���A�R���̌��ʁA���Y�����ɖ������R�����݂��邱�Ƃ����炩�ł���Ƃ��́A���̓������Ɋ�Â����~�߁A���Q�������̐����́A���i�̎���Ȃ�����A�����̗��p�ɓ����苖����Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B���̂悤�ɉ����Ă��A�������x�̎�|�ɔ�������̂Ƃ͂����Ȃ��B
�����@�@��P�O�S���̂R�i�������ғ��̌����s�g�̐����j
�P ���������͐�p���{���̐N�Q�ɌW��i�ׂɂ����āA���Y���������������R���ɂ�薳���ɂ����ׂ����̂ƔF�߂���Ƃ��́A�������Җ��͐�p���{���҂́A������ɑ����̌������s�g���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�Ɋ�Â��������F�\���̂��߂̎���
����N�Q�B�������͌����̂��߂ɂ�����������̎��{�ɊY���B��
�����ԍ��F�@ �@����10�N(��)��153��
�������F�@�@�@�@���i�̔����~��������
�ٔ��N�����F�@����11�N04��16��
�ٔ������F�@�@ �ō��ٔ�����@��@
�����f�[�^�F�@
PAT-H10-Ju-153.pdf
�@����҂����w�������͂����L�������Ƃ�����i�ɂ��Ă̓�������L����ꍇ�ɂ����āA��O�҂��A�������̑������ԏI����ɓ��������ɌW����i�ƗL������������������i�i�ȉ��u�㔭���i�v�Ƃ����B�j�����Ĕ̔����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āA���̐����ɂ��@��l������̏��F�\�������邽�߁A�������̑������Ԓ��ɁA���������̋Z�p�I�͈͂ɑ����鉻�w�������͈��i�Y���A������g�p���ĉE�\�����ɓY�t���ׂ�������̂ɕK�v�Ȏ������s�����Ƃ́A�����@�Z����ꍀ�ɂ����u�������͌����̂��߂ɂ�����������̎��{�v�ɓ�����A�������̐N�Q�Ƃ͂Ȃ�Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B
���̗��R�͎��̂Ƃ���ł���B
�P�@�������x�́A���������J�����҂ɑ��A���̊��Ԃ��̗��p�ɂ��Ă̓Ɛ�I�Ȍ�����t�^���邱�Ƃɂ���Ĕ��������シ��ƂƂ��ɁA��O�҂ɑ��Ă��A���̌��J���ꂽ�����𗘗p����@���^���A�����ĎY�Ƃ̔��B�Ɋ�^���悤�Ƃ�����̂ł���B���̂��Ƃ��炷��A�������̑������Ԃ��I��������́A���l�ł����R�ɂ��̔����𗘗p���邱�Ƃ��ł��A����ɂ���ĎЉ��ʂ��L���v�����悤�ɂ��邱�Ƃ��A�������x�̍����̈�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�Q�@�@�́A���i�̐����ɂ��āA���̈��S�������m�ۂ��邽�߁A���炩���ߌ�����b�̏��F��ׂ����̂Ƃ��Ă��邪�A���̏��F��\������ɂ́A�e��̎������s������A�������тɊւ��鎑������\�����ɓY�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B�㔭���i�ɂ��Ă��A���̐����̏��F��\�����邽�߂ɂ́A���炩���߈��̊��Ԃ������ď���̎������s�����Ƃ�v����_�ł͓��l�ł����āA���̎����̂��߂ɂ́A�������҂̓��������̋Z�p�I�͈͂ɑ����鉻�w�����Ȃ������i�Y���A�g�p����K�v������B���������@��A�E�����������@�Z����ꍀ�ɂ����u�����v�ɓ�����Ȃ��Ɖ����A�������������Ԓ��͉E���Y�����s���Ȃ����̂Ƃ���ƁA�������̑������Ԃ��I����������A�Ȃ������̊��ԁA��O�҂����Y���������R�ɗ��p�����Ȃ����ʂƂȂ�B���̌��ʂ́A�O���������x�̍����ɔ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�R�@�����A��O�҂��A�������������Ԓ��ɁA�@�Ɋ�Â��������F�\���̂��߂̎����ɕK�v�Ȕ͈͂��āA�����ԏI����ɏ��n����㔭���i�Y���A���͂��̐����Ƃ��邽�ߓ��������ɌW�鉻�w�����Y�E�g�p���邱�Ƃ́A��������N�Q������̂Ƃ��ċ�����Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�����āA�������������A�������҂ɂƂ��ẮA�������������Ԓ��̓��������̓Ɛ�I���{�ɂ�闘�v�͊m�ۂ����̂ł����āA����������A�����Ԓ��͌㔭���i�̐������F�\���ɕK�v�Ȏ����̂��߂̉E���Y�������r����������̂Ɖ�����ƁA�������̑������Ԃ𑊓����ԉ�������̂Ɠ��l�̌��ʂƂȂ邪�A����͓������҂ɕt�^���ׂ����v�Ƃ��ē����@���z�肷��Ƃ��������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
������@�ɌW��������̌���(����������������@)
����N�Q�B���i�̕i���m�F�Ɏg�p���Ă��鑪����@�̓������̌���
�́A���i�̐����y�т��̌�̔̔��s�ׂɋy�Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����10�N(�I)��604��
�������F�@�@�@�@�������N�Q�\�h��������
�ٔ��N�����F�@����11�N07��16��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H10-o-604.pdf
�@�{�����@�͖{������(�J���N���C�������j�Q�\����@)�̋Z�p�I�͈͂ɑ�����̂ł��邩��A�㍐�l���㍐�l���i�̐����H���ɂ����Ė{�����@���g�p���邱�Ƃ́A�{����������N�Q����s�ׂɓ�����B���������āA��㍐�l�́A�㍐�l�ɑ��A�����@��Z�Z���ꍀ�ɂ��A�{�����@�̎g�p�̍��~�߂𐿋����邱�Ƃ��ł���B�������A�{�������͕��Y������@�̔����ł͂Ȃ�����A�㍐�l���A�㍐�l���i�̐����H���ɂ����āA�{�����@���g�p���ĕi���K�i�̌���̂��߂̊m�F���������Ă���Ƃ��Ă��A���̐����y�т��̌�̔̔����A�{����������N�Q����s�ׂɓ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�{�[���X�v���C������(�ϓ��_)
�����R�̔��f�ɂ́A�@�߂̉��ߓK�p�̌��A�Ђ��Ă͐R���s�s�A���R�s���̈�@������A�������͔j����Ƃ�Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����6�N(�I)��1083��
�������F�@�@�@�@�������N�Q���~��
�ٔ��N�����F�@����10�N02��24��
�ٔ������F�@�@ �ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H06-o-1083.pdf
�@�������N�Q�i�ׂɂ����āA������������������鐻�i���͗p������@�i�ȉ��u�Ώې��i���v�Ƃ����B�j�����������̋Z�p�I�͈͂ɑ����邩�ǂ����f����ɓ������ẮA�菑�ɓY�t���������̓��������͈̔͂̋L�ڂɊ�Â��ē��������̋Z�p�I�͈͂��m�肵�Ȃ���Ȃ炸�i�����@���Z���ꍀ�Q�Ɓj�A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\�����ɑΏې��i���ƈقȂ镔����������ꍇ�ɂ́A�E�Ώې��i���́A���������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\�����ɑΏې��i���ƈقȂ镔����������ꍇ�ł����Ă��A�@�i�P�j�E���������������̖{���I�����ł͂Ȃ��A
�@�i�Q�j�E������Ώې��i���ɂ�������̂ƒu�������Ă��A���������̖ړI��B���邱�Ƃ��ł��A����̍�p���ʂ�t������̂ł����āA
�@�i�R�j�E�̂悤�ɒu�������邱�ƂɁA���Y�����̑�����Z�p�̕���ɂ�����ʏ�̒m����L����ҁi�ȉ��u���Ǝҁv�Ƃ����B�j���A�Ώې��i���̐������̎��_�ɂ����ėe�Ղɑz�����邱�Ƃ��ł������̂ł���A
�@�i�S�j�Ώې��i�����A���������̓����o�莞�ɂ�������m�Z�p�Ɠ��ꖔ�͓��Ǝ҂����ꂩ��E�o�莞�ɗe�Ղɐ��l�ł������̂ł͂Ȃ��A���A
�@�i�T�j�Ώې��i�������������̓����o��葱�ɂ����ē��������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���ꂽ���̂ɓ�����Ȃǂ̓��i�̎�����Ȃ��Ƃ��́A�E�Ώې��i���́A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\���Ƌϓ��Ȃ��̂Ƃ��āA���������̋Z�p�I�͈͂ɑ�������̂Ɖ�����̂������ł����B�������A�i��j�����o��̍ۂɏ����̂�����N�Q�ԗl��\�z���Ė����̓��������͈̔͂��L�ڂ��邱�Ƃ͋ɂ߂č���ł���A������ɂ����ē��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\���̈ꕔ������o���ɖ��炩�ƂȂ��������E�Z�p���ɒu�������邱�Ƃɂ���āA�������҂ɂ�鍷�~�ߓ��̌����s�g��e�ՂɖƂ�邱�Ƃ��ł���Ƃ���A�Љ��ʂ̔����ւ̈ӗ~�����E���邱�ƂƂȂ�A�����̕ی�A�����ʂ��ĎY�Ƃ̔��B�Ɋ�^����Ƃ��������@�̖ړI�ɔ��������łȂ��A�Љ�`�ɔ����A�t���̗��O�ɂ��Ƃ錋�ʂƂȂ�̂ł����āA�i��j���̂悤�ȓ_���l������ƁA���������̎����I���l�͑�O�҂����������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\�����炱��Ǝ����I�ɓ���Ȃ��̂Ƃ��ėe�Ղɑz�����邱�Ƃ̂ł���Z�p�ɋy�сA��O�҂͂����\�����ׂ����̂Ɖ�����̂������ł���A�i�O�j�����A���������̓����o�莞�ɂ����Č��m�ł������Z�p�y�ѓ��Ǝ҂����ꂩ��E�o�莞�ɗe�Ղɐ��l���邱�Ƃ��ł����Z�p�ɂ��ẮA�����������l���������邱�Ƃ��ł��Ȃ������͂��̂��̂ł��邩��i�����@�����Q�Ɓj�A���������̋Z�p�I�͈͂ɑ�������̂Ƃ������Ƃ��ł����A�i�l�j�܂��A�����o��葱�ɂ����ďo��l�����������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O�����ȂǁA�������҂̑��ɂ����Ă���������������̋Z�p�I�͈͂ɑ����Ȃ����Ƃ����F���邩�A���͊O�`�I�ɂ��̂悤�ɉ������悤�ȍs�����Ƃ������̂ɂ��āA�������҂���ɂ���Ɣ�����咣�����邱�Ƃ́A�֔����̖@���ɏƂ炵������Ȃ�����ł���B
�@�Q�@�����{���ɂ��Ă݂�ƁA���R�́A�{�������̓��������͈̔͂̋L�ڂ̂����\���v���`�y�тa�ɂ����ď㍐�l���i�ƈ�v���Ȃ�����������Ƃ��Ȃ���A�\���v���a�̕ێ���̍\���ɂ��Ė{�������Ə㍐�l���i�Ƃ̊Ԃɒu���\���y�ђu���e�Ր����F�߂���Ȃǂ̗��R�ɂ��A�㍐�l���i�͖{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ɣ��f�����B
�i�����j�@
�@��������ƁA�����׃{�[���̉~�������z�y�ѕ���^�C�v�̃A���M�����R���^�N�g�\����������{�[���X�v���C������̋Z�p���{�������̓����o��O�Ɍ��m�ł������Ƃ���A���R�̔F��ł͕ێ���̍\���̓{�[���̐ڐG�\���ɂ���č��{�I�ɈقȂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����̂ł��邩��A�㍐�l���i�́A���m�̖����׃{�[���̉~�������z�y�ѕ���^�C�v�̃A���M�����R���^�N�g�\����������{�[���X�v���C������Ɍ��m�̕����\���̕ێ����g�ݍ��킹�����̂ɂ����Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B�����āA���̑g�����ɑz�����邱�Ƃ��{�������̊J����҂����ɓ��Ǝ҂ɂ����ėe�Ղɂł������̂ł���A�㍐�l���i�́A�{�������̓����o��O�ɂ�������m�Z�p����E�o�莞�ɗe�Ղɐ��l�ł����Ƃ������ƂɂȂ邩��A�{�������̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\���Ƌϓ��Ƃ������Ƃ͂ł����A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�������̂Ƃ͂����Ȃ����ƂɂȂ�B
�@�{���ł́A�O�L�̂Ƃ���A�{�������̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\�����ɏ㍐�l���i�ƈقȂ镔����������Ƃ���A���R�́A���E�����Ə㍐�l���i�̍\���Ƃ̊Ԃɒu���\���y�ђu���e�Ր����F�߂��邩�ǂ����Ƃ����_�ɂ��Č�������݂̂ł����āA�㍐�l���i�Ɩ{�������̓����o�莞�ɂ�������m�Z�p�Ƃ̊Ԃ̊W�ɂ��ĉ��猟�����邱�ƂȂ��A�����ɏ㍐�l���i���{�������̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\���Ƌϓ��ł���A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����Ɣ��f�������̂ł���B���R�̉E���f�́A�u���\���A�u���e�Ր����̋ϓ��̂��̗]�̗v���ɂ��Ă̔��f�̓��ۂ���������܂ł��Ȃ��A�����@�̉��ߓK�p����������̂Ƃ����ق��͂Ȃ��B�@
�Q�l��������
�����������̓����o��葱�ɂ����ē��������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���ꂽ���̂ł���Ƃ��ċϓ���ے肵������B��
| �����ԍ� |
�@����18�N(��)��11429�� |
| ������ |
�@�������N�Q���~�� |
| �ٔ��N���� |
�@����21�N04��07�� |
| �ٔ����� |
�@���n���ٔ��� |
�����f�[�^�F�@�@
PAT-H18-wa-11429.pdf
�R ���_�Q�i�f�q�|�����͖{���e���������Ƌϓ��Ȃ��̂Ƃ��Ă��̋Z�p�I�͈͂ɑ����邩�j
�@�O�L�P �̂悤�ɁA�f�q�|�����͍\���v���a����[�����Ȃ��̂ŁA�����̗\���I�咣�Ƃ��Ă̋ϓ��N�Q�̐��ۂɂ��Č�������B
(1) �ō��ٔ��������U�N�i�I�j��P�O�W�R�����P�O�N�Q���Q�S����O���@�씻�����W�T�Q���P���P�P�R�ŎQ�Ɓj�́A���������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�\�����ɑΏې��i���ƈقȂ镔����������ꍇ�ɁA�Ȃ��ϓ��Ȃ��̂Ƃ��ē��������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����ƔF�߂��邽�߂̗v���̂P�Ƃ��āA�u�Ώې��i�������������̓����o��葱�ɂ����ē��������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���ꂽ���̂ɓ�����Ȃǂ̓��i�̎�����Ȃ��v���Ƃ��f���Ă���A���̗v�����K�v�ȗ��R�Ƃ��āA�u�����o��葱�ɂ����ďo��l�����������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O�����ȂǁA�������҂̑��ɂ����Ă���������������̋Z�p�I�͈͂ɑ����Ȃ����Ƃ����F���邩�A���͊O�`�I�ɂ��̂悤�ɉ������悤�ȍs�����Ƃ������̂ɂ��āA�������҂���ɂ���Ɣ�����咣�����邱�Ƃ́A�֔����̖@���ɏƂ炵������Ȃ�����ł���v�Ɣ������Ă���B
�@��������ƁA�������҂ɂ����ē��������̋Z�p�I�͈͂ɑ����Ȃ����Ƃ����F�����Ƃ�������ϓI�ȈӐ}���F�肳��Ȃ��Ă��A��O�҂��猩�āA�O�`�I�ɓ��������͈̔͂��珜�O���ꂽ�Ɖ������悤�ȍs�����Ƃ����ꍇ�ɂ́A��O�҂̗\���\����ی삷��ϓ_����A��L���i�̎��������̂Ɖ�����̂������ł���B�����ŁA��������߂�O��ɁA�{���ɂ����ď�L���i�̎���F�߂��邩�ǂ����ɂ��Č�������B
(2) �{���ɂ�����o��o�߂ɂ��ẮA�O�L�P �ɂ����ĔF�肵���Ƃ���ł���A�{���������ɓ������Ă̌����̎�ϓI�Ӑ}�͂Ƃ������A���Ȃ��Ƃ��\���v���a���������{������O�`�I�Ɍ���A�J�b�v�����O�������ꂽ�M�`�������@�t�B���[�̑̐ϕ��������肵�����̂Ɖ������B���������āA�����́A�M�`�������@�t�B���[�̑̐ϕ������u�S�Ovol���`�W�Ovol���v�͈͓̔��ɂ�����̈ȊO�̍\�����O�`�I�ɓ��������͈̔͂��珜�O�����Ɖ������悤�ȍs�����Ƃ������̂ł���A��L���i�̎���ɓ�����Ƃ����ׂ��ł���B�Ȃ��A�{�����◝�R�ʒm�́A�P�ɑg�����ɌW�锭��������Ƃ������R�ŁA���̑g����̋L�ڂ��Ȃ��{���o��́A�����@�R�U���U���Q���ɋK�肷��v�����[�����Ȃ��Ɣ��f���Ă���Ƃ���A���̔��f�̑Ó����ɂ͋^��̗]�n���Ȃ��ł͂Ȃ��B�������A��O�҂ɋ��◝�R�̑Ó����ɂ��Ă̔��f�̃��X�N�킹�邱�Ƃ͑����łȂ��A�����Ƃ��Ă��A�P�ɔM�`�������@�t�B���[�̑��ʂ��߂�Ӑ}�������Ƃ����̂ł���A���̈Ӑ}�����m�ɂȂ�悤�ȕ�����邱�Ƃ͂ł����͂��ł���A����ɂ�������炸�A����̈Ӑ}�Ƃ͈قȂ���߂����꓾��悤�ȁi�ނ��낻�̂悤�ɉ�����������R�ȁj���������͈̔͂ɕ�����̂ł��邩��A����ɂ��s���v�͌����ɂ����ĕ��S���ׂ��ł���B
(3) �ȏ�ɂ��A�f�q�|�����ɂ��āA�u�Ώې��i�������������̓����o��葱�ɂ����ē��������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���ꂽ���̂ɓ�����Ȃǂ̓��i�̎�����Ȃ��v���ƂƂ����v�����[�����Ȃ�����A������{���e���������Ƌϓ��Ȃ��̂Ƃ��āA���̋Z�p�I�͈͂ɑ�����ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
���m��������
��
���Q�̔������Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ȏꍇ�A���Q���������͔F�߂��Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����6�N(�I)��1102��
�������F�@�@�@�@���W���N�Q�֎~��
�ٔ��N�����F�@����9�N03��11��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
TM-H06-o-1102.pdf�@�@
TM-H06-o-1102-1.pdf�@�@
TM-H06-o-1102-2.pdf
�@���W�@�O����́A���W���҂́A�̈Ӗ��͉ߎ��ɂ�莩�Ȃ̏��W����N�Q�����҂ɑ��A���̓o�^���W�̎g�p�ɑ��ʏ��ׂ����K�̊z�ɑ�������z�̋��K���A���Ȃ������Q�̊z�Ƃ��Ă��̔����𐿋����邱�Ƃ��ł���|���K�肷��B�E�K��ɂ��A���W���҂́A���Q�̔����ɂ��Ď咣������K�v�͂Ȃ��A�����N�Q�̎����ƒʏ��ׂ����K�̊z���咣������Α������̂ł��邪�A�N�Q�҂́A���Q�̔��������蓾�Ȃ����Ƃ��R�قƂ��Ď咣�����āA���Q�����̐ӂ߂�Ƃ�邱�Ƃ��ł�����̂Ɖ�����̂������ł���B�������A���W�@�O����́A�����ꍀ�ƂƂ��ɁA�s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������ɂ����đ��Q�Ɋւ����Q�҂̎咣���ؐӔC���y�������|�̋K��ł����āA���Q�̔������Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ȏꍇ�ɂ܂ŐN�Q�҂ɑ��Q�����`��������Ƃ��邱�Ƃ́A�s�@�s�ז@�̊�{�I�g�g�݂�����̂Ƃ����ق��Ȃ��A����̉��߂Ƃ��č̂蓾�Ȃ�����ł���B�@���W���́A���W�̏o�����ʋ@�\��ʂ��ď��W���҂̋Ɩ���̐M�p��ی삷��ƂƂ��ɁA���i�̗��ʒ������ێ����邱�Ƃɂ���ʎ��v�҂̕ی��}�邱�Ƃɂ��̖{��������A����������p�V�Č����̂悤�ɂ��ꎩ�̂����Y�I���l��L������̂ł͂Ȃ��B���������āA�o�^���W�ɗގ�����W�͂��O�҂����̐����̔����鏤�i�ɂ����W�Ƃ��Ďg�p�����ꍇ�ł����Ă��A���Y�o�^���W�Ɍڋq�z���͂��S���F�߂�ꂸ�A�o�^���W�ɗގ�����W�͂��g�p���邱�Ƃ���O�҂̏��i�̔��グ�ɑS����^���Ă��Ȃ����Ƃ����炩�ȂƂ��́A���ׂ��肵���v�Ƃ��Ă̎��{�������z�̑��Q�������Ă��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�������F�@�@�@�@�������N�Q���~��
�ٔ��N�����F�@����9�N07��01��
�ٔ������F�@�@ �ō��ٔ�����O���@��@
�����f�[�^�F�@
PAT-H07-o-1988.pdf
�@���n��`�̌����Ƃ́A�������ɂ��Ă����A�e���̓��������A���̐����A�ړ]�A���͓��ɂ����Y���̖@���ɂ���Ē�߂��A�������̌��͂����Y���̗̈���ɂ����Ă̂ݔF�߂��邱�Ƃ��Ӗ�������̂ł���B�@�䂪���̓������Ɋւ��ē������҂��䂪���̍����Ō������s�g����ꍇ�ɂ����āA�����s�g�̑ΏۂƂ���Ă��鐻�i�����Y�������ғ��ɂ�荑�O�ɂ����ď��n���ꂽ�Ƃ���������A�������҂ɂ��������̍s�g�̉ۂ̔��f�ɓ������Ăǂ̂悤�ɍl�����邩�́A���䂪���̓����@�̉��߂̖��Ƃ����ׂ��ł���B�E�̖��́A�p�����⑮�n��`�̌����Ƃ͖��W�ł����āA���̓_�ɂ��Ăǂ̂悤�ȉ��߂��̂����Ƃ��Ă��A�p�����l���̓�y�ё��n��`�̌����ɔ�������̂ł͂Ȃ����Ƃ́A�E�ɐ��������Ƃ��납�疾�炩�ł���B
�@�������҂́A�ƂƂ��ē��������̎��{�����錠�����L������̂Ƃ���Ă���Ƃ���i�����@�Z�����Q�Ɓj�A���̔����ɂ��Ă����A���������ɌW�镨���g�p���A���n�����݂͑��n���s�ד��́A���������̎��{�ɊY��������̂Ƃ���Ă���i���@����O���ꍆ�Q�Ɓj�B��������ƁA�������Җ��͓������҂��狖���������{���҂��瓖�Y���������ɌW�鐻�i�i�ȉ��u�������i�v�Ƃ����B�j�̏��n�����҂��A�ƂƂ��āA���炱����g�p���A���͂�����O�҂ɍċc�n����s�ׂ�A����l����������i���������O�҂��A�ƂƂ��āA������g�p���A���͍X�ɑ��҂ɏ��n���Ⴕ���݂͑��n���s�ד����A�`���I�ɂ����A���������̎��{�ɊY�����A��������N�Q����悤�ɂ݂���B�������A�������Җ��͎��{���҂��䂪���̍����ɂ����ē������i�����n�����ꍇ�ɂ́A���Y�������i�ɂ��Ă͓������͂��̖ړI��B���������̂Ƃ��ď��s���A���͂�������̌��͂́A���Y�������i���g�p���A���n�����݂͑��n���s�ד��ɂ͋y�Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B�������A(�P)�����@�ɂ�锭���̕ی�͎Љ�����̗��v�Ƃ̒��a�̉��ɂ����Ď�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł���Ƃ���A(�Q)��ʂɏ��n�ɂ����ẮA���n�l�͖ړI���ɂ��ėL���邷�ׂĂ̌���������l�Ɉړ]���A����l�͏��n�l���L���Ă������ׂĂ̌������擾������̂ł���A�������i���s��ł̗��ʂɒu�����ꍇ�ɂ��A����l���ړI���ɂ��������҂̌����s�g�𗣂�Ď��R�ɋƂƂ��Ďg�p���ď��n�������邱�Ƃ��ł��錠�����擾���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA����s�ׂ��s������̂ł����āA���ɁA�������i�ɂ��ď��n�����s���s�x�������҂̋�����v����Ƃ������ƂɂȂ�A�s��ɂ����鏤�i�̎��R�ȗ��ʂ��j�Q����A�������i�̉~���ȗ��ʂ��W�����āA�������ē������Ҏ��g�̗��v���Q���錋�ʂ𗈂��A�Ђ��Ắu�����̕ی�y�ї��p��}�邱�Ƃɂ��A���������サ�A�����ĎY�Ƃ̔��B�Ɋ�^����v�i�����@����Q�Ɓj�Ƃ��������@�̖ړI�ɂ������邱�ƂɂȂ�A(�R)�����A�������҂́A�������i��������n����ɓ������ē��������̌��J�̑Ή����܂߂����n������擾���A���������̎��{����������ɓ������Ď��{�����擾����̂ł��邩��A���������̌��J�̑㏞���m�ۂ���@��͕ۏႳ��Ă�����̂Ƃ������Ƃ��ł��A�������Җ��͎��{���҂�����n���ꂽ�������i�ɂ��āA�������҂����ʉߒ��ɂ����ē�d�ɗ����邱�Ƃ�F�߂�K�v���͑��݂��Ȃ�����ł���B
�@�������Ȃ���A�䂪���̓������҂����O�ɂ����ē������i�����n�����ꍇ�ɂ́A�����ɉE�Ɠ���ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���Ȃ킿�A�������҂́A�������i�����n�����n�̏��݂��鍑�ɂ����āA�K�������䂪���ɂ����ėL����������Ɠ���̔����ɂ��Ă̓������i�ȉ��u�Ή��������v�Ƃ����B�j��L����Ƃ͌���Ȃ����A�Ή���������L����ꍇ�ł����Ă��A�䂪���ɂ����ėL����������Ə��n�n�̏��݂��鍑�ɂ����ėL����Ή��������Ƃ͕ʌ̌����ł��邱�ƂɏƂ点�A�������҂��Ή��������ɌW�鐻�i�ɂ��䂪���ɂ����ē������Ɋ�Â��������s�g�����Ƃ��Ă��A����������Ē����ɓ�d�̗��������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B
�@�����ŁA���ێ���ɂ����鏤�i�̗��ʂƓ������҂̌����Ƃ̒����ɂ��čl������ɁA����Љ�ɂ����č��یo�ώ�����ɂ߂čL�͈́A���A���x�ɐi�W������ɏƂ点�A�䂪���̎���҂��A���O�Ŕ̔����ꂽ���i���䂪���ɗA�����Ďs��ɂ����闬�ʂɒu���ꍇ�ɂ����Ă��A�֓����܂߂����i�̗��ʂ̎��R�͍ő�����d���邱�Ƃ��v������Ă�����̂Ƃ����ׂ��ł���B�����āA���O�ł̌o�ώ���ɂ����Ă��A��ʂɁA���n�l�͖ړI���ɂ��ėL���邷�ׂĂ̌���������l�Ɉړ]���A����l�͏��n�l���L���Ă������ׂĂ̌������擾���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA����s�ׂ��s������̂Ƃ������Ƃ��ł���Ƃ���A�O�L�̂悤�Ȍ���Љ�ɂ����鍑�ێ���̏ɏƂ点�A�������҂����O�ɂ����ē������i�����n�����ꍇ�ɂ����Ă��A����l���͏���l����������i���������O�҂��A�ƂƂ��Ă�����䂪���ɗA�����A�䂪���ɂ����āA�ƂƂ��āA������g�p���A���͂�����X�ɑ��҂ɏ��n���邱�Ƃ́A���R�ɗ\�z�����Ƃ���ł���B�@�E�̂悤�ȓ_�����Ă���ƁA�䂪���̓������Җ��͂���Ɠ���������҂����O�ɂ����ē������i�����n�����ꍇ�ɂ����ẮA�������҂́A����l�ɑ��ẮA���Y���i�ɂ��Ĕ̔���Ȃ����g�p�n�悩��䂪�������O����|������l�Ƃ̊Ԃō��ӂ����ꍇ�������A����l����������i���������O�ҋy�т��̌�̓]���҂ɑ��ẮA����l�Ƃ̊ԂʼnE�̎|�����ӂ�����������i�ɂ���m�ɕ\�������ꍇ�������āA���Y���i�ɂ��ĉ䂪���ɂ����ē��������s�g���邱�Ƃ͋�����Ȃ����̂Ɖ�����̂������ł���B���Ȃ킿�A(�P)�����ɐ��������Ƃ���A�������i�����O�ɂ����ď��n�����ꍇ�ɁA���̌�ɓ��Y���i���䂪���ɗA������邱�Ƃ����R�ɗ\�z����邱�ƂɏƂ点�A�������҂����ۂ�t���Ȃ��܂ܓ������i�����O�ɂ����ď��n�����ꍇ�ɂ́A����l�y�т��̌�̓]���҂ɑ��āA�䂪���ɂ����ď��n�l�̗L����������̐������Ȃ��œ��Y���i���x�z���錠����َ��I�Ɏ��^�������̂Ɖ����ׂ��ł���B(�Q)�����A�������҂̌����ɖڂ�������Ƃ��́A�������҂����O�ł̓������i�̏��n�ɓ������ĉ䂪���ɂ�����������s�g�̌����𗯕ۂ��邱�Ƃ͋������Ƃ����ׂ��ł���A�������҂��A�E���n�̍ۂɁA����l�Ƃ̊Ԃœ������i�̔̔���Ȃ����g�p�n�悩��䂪�������O����|�����ӂ��A���i�ɂ���m�ɕ\�������ꍇ�ɂ́A�]���҂��܂��A���i�̗��ʉߒ��ɂ����đ��l����݂��Ă���Ƃ��Ă��A���Y���i�ɂ����̎|�̐������t����Ă��邱�Ƃ�F����������̂ł����āA�E�����̑��݂�O��Ƃ��ē��Y���i���w�����邩�ǂ��������R�Ȉӎv�ɂ�茈�肷�邱�Ƃ��ł���B�����āA(�R)�q��Ж��͊֘A��Г��œ������҂Ɠ���������҂ɂ�荑�O�ɂ����ē������i�����n���ꂽ�ꍇ���A�������Ҏ��g���������i�����n�����ꍇ�Ɠ��l�ɉ����ׂ��ł���A�܂��A(�S)�������i�̏���l�̎��R�ȗ��ʂւ̐M����ی삷�ׂ����Ƃ́A�������i���ŏ��ɏ��n���ꂽ�n�ɂ����ē������҂��Ή���������L���邩�ǂ����ɂ��قȂ���̂ł͂Ȃ��B
���[���f���^������
�����W�o�^�����R���̐����s�����R�����ێ����鍂�ٔ�����j�������W�@��S���P����15���̖������R����B��
�����ԍ��F�@ �@����10�N(�s�q)��85��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����12�N07��11��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
TM-H10-Ghi-85.pdf
�@�P�@���W�@�l���ꍀ��܍��ɂ����u���l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i���͖ƍ������邨���ꂪ���鏤�W�v�ɂ́A���Y���W�����̎w�菤�i���͎w��i�ȉ��u�w�菤�i���v�Ƃ����B�j�Ɏg�p�����Ƃ��ɁA���Y���i�������l�̏��i���͖i�ȉ��u���i���v�Ƃ����B�j�ɌW����̂ł���ƌ�M����邨���ꂪ���鏤�W�݂̂Ȃ炸�A���Y���i�����E���l�Ƃ̊Ԃɂ�����e�q��Ђ�n���Г��ٖ̋��ȉc�Ə�̊W���͓���̕\���ɂ�鏤�i�����Ƃ��c�ރO���[�v�ɑ�����W�ɂ���c�Ǝ�̋Ɩ��ɌW�鏤�i���ł���ƌ�M����邨����i�ȉ��u�L�`�̍������邨����v�Ƃ����B�j�����鏤�W���܂ނ��̂Ɖ�����̂������ł���B�������A�����̋K��́A���m�\�����͒����\���ւ̂������i������t���[���C�h�j�y�ѓ��Y�\���̊�߉��i������_�C�����[�V�����j��h�~���A���W�̎������ʋ@�\��ی삷�邱�Ƃɂ���āA���W���g�p����҂̋Ɩ���̐M�p�̈ێ���}��A���v�҂̗��v��ی삷�邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����̂ł���Ƃ���A���̎�|���炷��A��ƌo�c�̑��p���A����̕\���ɂ�鏤�i�����Ƃ�ʂ��Č��������ƃO���[�v�̌`���A�L���u�����h�̐������A��Ƃ�s��̕ω��ɉ����āA���m���͒����ȏ��i���̕\�����g�p����҂̐����ȗ��v��ی삷�邽�߂ɂ́A�L�`�̍������邨���ꂪ���鏤�W�������W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ƃ��ׂ��ł��邩��ł���B�@�����āA�u�������邨����v�̗L���́A���Y���W�Ƒ��l�̕\���Ƃ̗ގ����̒��x�A���l�̕\���̎��m�������y�ѓƑn���̒��x��A���Y���W�̎w�菤�i���Ƒ��l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i���Ƃ̊Ԃ̐����A�p�r���͖ړI�ɂ�����֘A���̒��x���тɏ��i���̎���ҋy�ю��v�҂̋��ʐ����̑�����̎���ȂǂɏƂ炵�A���Y���W�̎w�菤�i���̎���ҋy�ю��v�҂ɂ����ĕ��ʂɕ����钍�ӗ͂���Ƃ��āA�����I�ɔ��f�����ׂ��ł���B
�@�Q�@�{���o�^���W�́A�{���e�g�p���W�̂����u���[���E�f���E�^���v�̏��W�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ��̌Ăɂ����ē���ł����āA�O�ςɂ����Ă��ގ����Ă���A�������A���p���W�̕\�L���̋y�т��̎w�菤�i����݂āA���p���W����t�����X��ǂ݂ɂ��u���[���f���^���v�̏̌Ă���������̂Ƃ����邩��A�{���o�^���W�́A���p���W�Ƃ��̌Ăɂ����ē���ł���B�܂��A�{���e�g�p���W�y�ш��p���W�́A��������舵���Ǝ҂⍂���ȍ����ɊS�������v�҂ɂ́A�㍐�l�̍����̈��\��������̂Ƃ��Ē����ł���A���A�Ƒn�I�ȏ��W�ł���B����ɁA�{���o�^���W�̎w�菤�i�̂��������R�������ɌW��u���ϗp��A�g���i�A�����i�A����ށA�ܕ��v�ƍ����Ƃ́A��Ƃ��ď����̑����Ƃ����p�r�ɂ����ċɂ߂Ė��ڂȊ֘A����L���Ă���A�����i�̎��v�҂̑������������ʂ���B�ȏ�̎���ɏƂ点�A�{���o�^���W���u���ϗp��A�g���i�A�����i�A����ށA�ܕ��v�Ɏg�p����Ƃ��́A���̎���ҋy�ю��v�҂ɂ����āA�E���i���㍐�l�ƑO�L�̂悤�ȋٖ��ȊW�ɂ���c�Ǝ�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�ƍL�`�̍������邨���ꂪ����Ƃ������Ƃ��ł���B�Ȃ��A�{���e�g�p���W�y�ш��p���W��������y�b�g�}�[�N�Ƃ��Ďg�p����Ă��邱�Ƃ́A�{���e�g�p���W���̒������y�і{���e�g�p���W���Ɩ{���o�^���W�ɌW��e���i�Ԃ̖��ڂȊ֘A���ɏƂ点�A�O�L���f�����E����ɑ���Ȃ��B
�u�k�[�u���v�s�������s���~����������
���퍐�ɂ��C�������̔̔��s�ׂ́A�s�������h�~�@��Q���P����R������̕s�������s�ׂ��\������B
�@�������i�̏��i�`�Ԃ́A�����̏o����\�����钘���Ȃ������m�̏��i�`�Ԃł���Ƃ͔F�߂�ꂸ�A�����̕s�������h�~�@��Q���P����Q���Ȃ�����P���Ɋ�Â������́A���R���Ȃ���
�����ԍ��F �@�@����16�N(��)��1671��
�������F�@�@�@�@�s�������s���~����������
�ٔ��N�����F�@����18�N03��30��
�ٔ������F�@ �@���n���ٔ����@
�����f�[�^�F�@
UF-H16-wa-1671.pdf�@�@�@
UF-H16-wa-1671-1.pdf
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�������A�u���W���[��A���A�̔����Ă���퍐�ɑ��A�i�P�j�������A���A�̔����Ă���u���W���[�̌`�Ԃ͐V�K�̂��̂ł���A���A�퍐���A���A�̔����Ă���u���W���[�̌`�Ԃ́A�������A���A�̔����Ă���u���W���[�̌`�Ԃ�͕킵�����̂ł��邩��A�퍐�ɂ�铖�Y�u���W���[�̗A���A�̔��́A�s�������h�~�@�Q���P���R������̕s�������s�ׂł���A�܂��A�i�Q�j�������A���A�̔����Ă���u���W���[�̌`�Ԃ́A�����̏��i�\���Ƃ��Ē����Ȃ������m�ł���A���A�퍐���A���A�̔����Ă���u���W���[�̌`�Ԃ́A�������A���A�̔����Ă���u���W���[�̌`�ԂƗގ����A����ƍ��������邨���ꂪ���邩��A�퍐�ɂ�铖�Y�u���W���[�̗A���A�̔��́A���@�Q���P���Q�����͂P���̕s�������s�ׂł���Ǝ咣���āA�@���@�Q���P���Q�����͂P���y�ѓ��@�R���Ɋ�Â��āA�퍐�ɂ�铖�Y�u���W���[�̗A���A�̔��̍��~�ߋy�єp�������߂�ƂƂ��ɁA�A��ʓI�ɓ��@�Q���P���R���A�\���I�ɓ��@�Q���P���Q�����͂P���y�ѓ��@�S���Ɋ�Â��āA���Q�����𐿋��������Ăł���B
(���|)
�@�C�������̌`�Ԃ́A�������i�̌`�ԂƁA�J�b�v�̕\�ʂ̐F�y�ѓ������ɂ����đ��Ⴗ�邪�A����ȊO�͓���Ƃ�����قǂɍ������Ă��邱�ƂɏƂ点�A�C�������̌`�Ԃ́A�������i�̌`�ԂɈˋ����č��ꂽ���̂Ɛ��F���邱�Ƃ��ł���B�i�����j
�@�J���҂��J���ɌW�鏤�i���s��W�J����`�Ԃ́A���Ȃ̎�ɂ����Ĕ̔����s�����̂Ɍ���ꂸ�A�l�X�Ȍ`�Ԃ����蓾��̂ł����āA���̒��ɂ́A���n��ɂ��āA���Y���i�̓Ɛ�I�̔��_���������A�����ɁA�J���Ҏ��g�͓��Y�n��ɂ����ē��Y�J�����i�̎���������s��Ȃ��Ƃ����`�������Ƃɂ���ꍇ������B���̂悤�ȏꍇ�A�Ɛ�I�̔�����F�߂�ꂽ�҂́A���ʂƂ��āA���Y�n��ɂ����铖�Y�J�����i�̎s�ꗘ�v��Ɛ�ł���n�ʂ邱�ƂɂȂ邪�A�Ɛ�I�̔����҂��L���邱�̂悤�ȓƐ�I�n�ʂȂ������v�́A��s�҂��͕�s�ׂ��s�����Ƃɂ���Ă��̉~���ȋ����W�����鐫����L������̂ł���B�����āA���̓Ɛ�I�n�ʂȂ������v�́A��L�̂悤�ȓ������ی삵�悤�Ƃ����J���҂̓Ɛ�I�n�ʂɊ�b��L���A������̈ꕔ�����^���ꂽ���̂Ƃ������Ƃ��ł��邩��A��O�҂Ƃ̊W�ł��@�I�ɕی삳���ׂ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@�܂��A�Ɛ�I�̔����҂́A�Ɛ茠�邽�߂ɁA�J���҂ɑ��A���Y�J�����i�𗬒ʒi�K�Ŏ�舵���P�Ȃ�̔��҂ɂ͉ۂ���Ȃ������̕��S�i�Œ�w���ʂ̒�߂Ȃǁj���Ă���̂��ʏ�ł���A�J���҂͏��i���̂��߂̎����A�J�͋y�у��X�N���A���i�̓Ɛ�̑Ή��̌`�ʼn�����A�Ɛ�I�̔����҂͂����̈ꕔ�������肵�Ă��邱�ƂɂȂ邩��A�Ɛ�I�̔����҂�ی�̎�̂Ƃ��āA����ɓƐ���ێ������邱�Ƃ́A���i�����邽�߂̎����A�J�͂𓊉��������ʂ�ی삷��Ƃ����_�ł��A�����̗��@��|�ɓK��������̂ł���B
�@����ɁA�@�������Ă��A�s�������h�~�@�́A���̂Q���P���ɂ����āu�s�������v���`���A�����R���ł́A���l�̏��i�̌`�Ԃ�͕킵�����i�����n������s�ׂ�s�������Ƃ��A���~�����̎�̂ɂ��āA�R���P���ɂ����āA�u�s�������ɂ���ĉc�Ə�̗��v��N�Q����A���͐N�Q����邨���ꂪ����ҁv�Ƃ��Ă���A���Q���������̎�̂ɂ��ẮA�S���ɂ����āA�s�������ɂ��u�c�Ə�̗��v��N�Q�v���ꂽ�҂Q���������̎�̂Ƃ��ė\�肵�Ă�����̂Ɖ�����A�Ⴆ�Γ����@�P�O�O���P�������~�����̎�̂��u�������Җ��͐�p���{���ҁv�Ƃ��Ă���̂Ƃ͈قȂ����K��̎d�������Ă���B���������āA�Ɛ�I�̔����҂��A�s�������h�~�@�Q���P���R������̕s�������ɂ���ĉc�Ə�̗��v��N�Q����A���͐N�Q����邨���ꂪ����҂ɊY������Ɖ������Ƃ��Ă��A�@���̕�����̖W���͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�ȏ�̓_���l������ƁA�Ɛ�I�̔����҂̗L����Ɛ�I�n�ʂȂ������v�́A�����ɂ���ĕی삳���ׂ����v�ł���Ɖ�����̂������ł���A�Ɛ�I�̔����҂������ɂ��ی삳����̂��蓾����̂Ɖ�����̂������ł���B
�i�����j
�@�ȏ�ɂ��A�{���ɂ�����퍐�ɂ��C�������̔̔��s�ׂ́A�s�������h�~�@�Q���P���R������̕s�������s�ׂ��\������Ƃ����ׂ��ł���B�����āA�O�L�i�P�j�Ȃ����i�R�j�F��̎������炷��A�퍐�ɂ͏�L�s�������ɂ��ĉߎ�������A�����́A���̕s�������s�ׂɂ���Đ��������Q�ɂ��āA�퍐�ɑ��A���Q������������L����Ƃ����ׂ��ł���B
�i�����j
�@��ɔF�肵���G���̋L���̒��ɂ́A�����P�T�N�P�O������̎��_�ŁA�������i�́A�ቿ�i�̗ގ��i���o��钆�ł�������t���Ȃ������̍��@�\���x������ăq�b�g�𑱂��Ă���Ƃ̋L�ڂ����邪�i�O�L�A�i�A�j���j�A�ގ��i�̌`�Ԃ��������i�̌`�ԂƂ悭���Ă���ȏ�A���̂悤�ȏ���҂���̎x���̍��́A���i���\�̍��Ɋ�Â����̂ł���ƍl������B���������āA���̎��ʂ́A���i�`�Ԃł͂Ȃ��A���i���ɂ���čs���Ă�����̂ƍl����̂������ł���B
�@���������āA�������i�̏��i�`�Ԃ��A�����̏o����\��������m�ȏ��i�\���ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�i�Q�j ��L�i�P�j�ŏq�ׂ��Ƃ��납�炷��ƁA�������i�̏��i�`�Ԃ��A�����̏o����\�����钘���ȏ��i�\���ł���ƔF�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�i�R�j �ȏ�̂Ƃ���A�������i�̏��i�`�Ԃ́A�����̏o����\�����钘���Ȃ������m�̏��i�`�Ԃł���Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A������
�s�������h�~�@�Q���P���Q���Ȃ����P���Ɋ�Â������́A���R���Ȃ��B
�R������i�ׂɂ�����g�p�ؖ����̒�o
���㍐���p�B���قɂ��R������F�B��
�����ԍ��F�@ �@���a63�N(�s�c)��37��
�������F�@�@ �@ �s�g�p����R���̎��
�ٔ��N�����F�@����3�N04��23��
�@�얼�F�@�@ �@ �ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
TM-S63-Gtsu-37.pdf
�@���W�o�^�̕s�֗p����R���ŐR���̑ΏۂƂȂ�̂́A���̐R�������̓o�^�O�O�N�ȓ��ɂ�����o�^���W�̎g�p�̎����̑��ۂł��邪�A���̐R������i�ׂɂ����ẮA�E�����̗��͎����R�̌����٘_�I�����Ɏ���܂ŋ��������̂Ɖ�����̂������ł����B
�i�����j
�@�ٔ������`�v�̔��Έӌ��́A���̂Ƃ���ł���B
�@���́A�����ӌ����A���W�o�^�̕s�g�p����R�������ɂ��Ă����R���̎���i�ׂɂ����ẮA�o�^���W�̎g�p�̎����̗��́A�����R�̌����٘_�I���Ɏ���܂ŋ��������̂Ɖ�����̂������ł���A�Ƃ��Ė{���R���������������������x�����ׂ����̂Ƃ���邱�ƂɎ^�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�����ӌ��́A���W�@�܁Z��{���ɂ��āA�u����́A�o�^���W�̎g�p�̎����������ď��W�o�^�̎������Ƃ�邽�߂̗v���Ƃ��A���̑��ۂ̔��f�����̎��W�ɂ����W���҂ɂ��ӔC�̈�[�S�����A�����ĉE�R���ɂ�����R�����̐E���ɂ��؋����ׂ̕��S���y�����������̂ł���A���W���҂��R�����ɂ����ĉE�g�p�̎������ؖ��������Ƃ������āA�E�������Ƃ�邽�߂̗v���Ƃ������̂ł͂Ȃ��Ɖ������v�Ƃ����B�o�^���W���g�p���Ȃ��҂ɏ��W���Ƃ����r���Ɛ�I�Ȍ�����^���Ă����K�v�͂Ȃ��Ƃ����_���炷��A�u�o�^���W�̎g�p�̎����������ď��W�o�^�̎������Ƃ�邽�߂̗v���v�Ƃ�����̂ł���Ɖ�����Ƃ����̂͗����ł��邱�Ƃł͂��邪�A���̂��Ƃ̌̂ɁA����̐������Ȃ��ɓo�^���W�̎g�p�̎����̗��͎����R�̌����٘_�I���Ɏ���܂ŋ������A�Ƃ��邱�Ƃɂ͋^���悹����Ȃ��B���W�@�܁Z��{�����u�O���̐R���̐������������ꍇ�ɂ����ẮA�c�c�o�^���W�c�c�̎g�p�����Ă��邱�Ƃ�퐿���l���ؖ����Ȃ�����A���W���҂́A���̎w�菤�i�ɌW�鏤�W�o�^�̎������Ƃ�Ȃ��B�v�ƁA�킪���̖@�̌n�����̏��Ȃ��v�����߂��̂́A���W���̕ی�Ɗ��p�A���ɒ����̕s�g�p�ɂ��x�����W���̔r���Ɏ����邽�߂ł���A�����ӌ��̂����Ƃ���́u�o�^���W�̎g�p�̎����������ď��W�o�^�̎������Ƃ�邽�߂̗v���Ƃ��A���̑��ۂ̔��f�����̎��W�ɂ����W���҂ɂ��ӔC�̈�[�S�����A�����ĉE�R���ɂ�����R�����̐E���ɂ��؋����ׂ̕��S���y�����������̂ł���v�̂́A���W�s���i�R���j�̉~���Ȏ{�s�̂��߁A�����̔퐿���l�Ɏ��Ȃ̌�������邽�߂̐����ȑΉ������߂���̂ɊO�Ȃ�Ȃ��B���W���҂́A���W�@����Ɋ�Â��o�^���W�̎g�p���L����Ƃ������T��^�����A������炻�̎g�p�̎������ł��悭�m�薔�͒m�蓾�闧��ɂ����āA�e�ՂɎg�p�����̏ؖ������邱�Ƃ̂ł���҂ł��邩��A���W�@�܁Z���ꍀ�Ɋ�Â��s�֗p����R���̐������������ꍇ�ɂ́A�퐿���l�i���W���ҁj�́A����̌�������菤�W�o�^�̎������Ƃ�邽�߂ɂ́A������̏������Ȃ��ׂ����ۂ������߂�R���ɂ����āA�O�L�v���ɂ�����o�^���W�g�p�̎����ɂ��ďؖ����邱�Ƃ�v����Ƃ����̂��A���W�@�܁Z��{���̖@�ӂł���Ǝv���A����ɂ��A�퐿���l���R���ɂ����ė��͂��납�A�������炵�Ȃ��Ƃ����悤�ȏꍇ�ɂ��A����i�ׂ̎����R�̌����٘_�I���܂ŐV���ȗ����������Ƃ����悤�ȉ��߂͍̂�ׂ��ł͂Ȃ��B
�@�Ƃ��낪�A�{���ł́A��㍐�l���L����{�����W�o�^�ɂ��āA�㍐�l�����W�@�܁Z���ꍀ�Ɋ�Â��s�g�p����R���𐿋������̂ɑ��A�퐿���l�ł����㍐�l���A�R���ɂ����ď��W�@�܁Z��̗v���ɂ�����咣�A�����Ȃ��������Ƃ���A�����ǂ���{�����W�o�^���������|�̐R�����������Ƃ����̂ł���B���ɁA�@�����W�o�^�̎������Ƃ�悤�Ƃ���퐿���l�ɋ��߂��Ή���S�����������̂ł���B������퐿���l�i��㍐�l�j�̌�����i�삷��K�v�͂Ȃ��Ǝv���A�����̎���������߂�i�ׂɂ������ʌ����ɏ]���āA���R�ɂ����ė��������ׂ����Ăł���Ƃ͍l�����Ȃ��B������ɁA���R�́A�V���ɖ{���o�^���W�̎g�p�̎����ɂ��Ă̗��������A�o�^���W�̎g�p�̎������ؖ����ꂽ�Ƃ��āA�{���R���������������̂ŁA�������ɂ́A�@�߂̉��ߓK�p����蔻���ɉe�����y�ڂ����Ƃ̖��炩�Ȉ�@������Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B�_�|�́A���R������A�������͔j����Ƃꂸ�A�{�i�����͊��p�����ׂ����̂ł���B
�u�������g���v���W�s�g�p�����������
���������ɂ�鏤�W�o�^����R��������B
�w�菤�i�ɂ��Ă̓o�^���W�̎g�p�ɊY���B��
�����ԍ��F�@�@�@ ����19�N(�s�P)��10008��
�������F�@�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@�@����19�N9��27��
�@�얼�F�@�@�@�@�@�m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F �@�@
TM-H19-Gke-10008.pdf
�@�{���V���̂悤�Ȗ������ł����Ă��A������̑Ώۂł��鏤�i�ł����āA�o���\���@�\��ی삷��K�v�̂�����̂Ƃ������Ƃ��ł��邩��A���W�@��́u���i�v�ɊY������Ƃ������Ƃ��ł���B���������āA�L���ƂƂ��ɍL�����f�ڂ����������ɏ��W��t���A�L���������ɂ���Čo���d���A�ǎ҂ɂ͖����Ŕz�z����s�ׂ́A�u�V���v�Ƃ����w�菤�i�ɂ��Ă̏��W�̎g�p�ł���Ƃ������Ƃ��ł���B�{�����W�ɂ��ẮA�O�L�P�̂Ƃ���A�g�p�����P���F�߂��邩��A�{���\���o�^�O�R�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����āA�w�菤�i�ɂ��{�����W���g�p�������Ƃ��F�߂��A���W�@�T�O���P���̗v���͖�������Ă��Ȃ��B
�؎��������y�т��̐������@����
���������ɂ�鋑��R��������B��
�����ԍ��F�@ �@����17�N(�s�P)��10395��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����18�N12��20��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ����@
�����f�[�^�F�@
PAT-H17-Gke-10395.pdf
�@�R���́A����_c �ɂ��āA��L���m���p�Z�p��K�p���Ė{�蔭���̍\���Ƃ��邱�Ƃ̗e�Ցz�������m�肷�锻�f���������̂ł��邪�A���◝�R�ʒm�ɂ����ẮA��L���m���p�Z�p�̓��e���̂͂��납�A���̍����ƂȂ��������ɂ��A���y���炵�Ă��Ȃ��̂ł��邩��A�����@�P�T�X���Q���ŏ��p���铯�@�T�O���Ɉ�w�����@������A���A���̈�@�͖��炩�Ɍ��_�ɉe��������ꍇ�ɓ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B���������āA���̗]�̎�����R�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A�R�����f�P�͎������Ƃ�Ȃ��B
�|�p�C����
���A�ږ���̒��쌠�B�I���앨�̒��쌠�́A�I���앨�ɂ����ĐV���ɕt�^���ꂽ�n��I�����݂̂ɂ��Đ�����B��
�����ԍ��F�@ �@����4�N(�I)��1443��
�������F�@ �@�@ ���쌠�N�Q���~��
�ٔ��N�����F�@����9�N07��17��
�@�얼�F�@�@ �@ �ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F�@
CP-H04-o-1443.pdf�@�@�@
CP-H04-o-1443-1.pdf
�@���쌠�@��̒��앨�́A�u�v�z���͊����n��I�ɕ\���������́v�i���@����ꍀ�ꍆ�j�Ƃ���Ă���A���̖��́A�e�e�A�������̓�����L����o��l�����������ĕ`����Ă����b�����`���̘A�ږ���ɂ����ẮA���Y�o��l�����`���ꂽ�e��̖��悻�ꂼ�ꂪ���앨�ɓ�����A��̓I�Ȗ���𗣂�A�E�o��l���̂�����L�����N�^�[�������Ē��앨�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�i�����j
�@�A�ږ���ɂ����ẮA�㑱�̖���́A��s���閟��Ɗ�{�I�Ȕ��z�A�ݒ�̂ق��A��l�����n�߂Ƃ����v�ȓo��l���̗e�e�A���i���̓����������A����ɐV���ȋ؏���t����ƂƂ��ɁA�V���ȓo��l����lj�����Ȃǂ��č쐬�����̂��ʏ�ł����āA���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�㑱�̖���́A��s���閟���|�Ă������̂Ƃ������Ƃ��ł��邩��A��s���閟��������앨�Ƃ���I���앨�Ɖ������B�����āA
�I���앨�̒��쌠�́A�I���앨�ɂ����ĐV���ɕt�^���ꂽ�n��I�����݂̂ɂ��Đ����A�����앨�Ƌ��ʂ����̎����������镔���ɂ͐����Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B
�i�����j
�@���앨�̕����Ƃ́A�����̒��앨�Ɉˋ����A���̓��e�y�ь`�����o�m������ɑ������̂��Đ����邱�Ƃ������Ƃ���i�ō��ُ��a�܁Z�N�i�I�j��O��l�����O�N�㌎������ꏬ�@�씻���E���W�O�Z�����l�ܕŎQ�Ɓj�A�����Ƃ������߂ɂ́A��O�҂̍�i������̓���̉�ʂɕ`���ꂽ�o��l���̊G�ƍו��܂ň�v���邱�Ƃ�v������̂ł͂Ȃ��A���̓������瓖�Y�o��l����`�������̂ł��邱�Ƃ�m�蓾����̂ł���Α����Ƃ����ׂ��ł���B
�i�����j
�@�O�L�̌��R�F�莖���ɂ��A�{���}����́A�����i�ɂ����ĕ\������Ă���|�p�C�̊G�̓��������ׂċ������Ƃ����ɐs���A����ȊO�̑n��I�\��������L���Ȃ����̂ł����āA���Ɍ㑱��i�̂������܂����쌠�̕ی���Ԃ̖������Ă��Ȃ����̂�����Ƃ��Ă��A�㑱��i�̒��쌠��N�Q������̂Ƃ͂����Ȃ�����A��㍐�l�L���O�E�t�B�[�`���[�Y�́A���͂�㍐�l�̖{���}����̎g�p�������~�߂邱�Ƃ͋�����Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�����E���C�j�[�E�i�C�g�E�C���E�g�[�L���[����
�����ٔ������F�B���쌠��N�Q��
| �����ԍ� |
�@���a50�N(�I)��324�� |
| ������ |
�@���쌠�s���ݓ��m�F�y�ђ��쌠���Q���� |
| �ٔ��N���� |
�@���a53�N09��07�� |
| �@�얼 |
�@�ō��ٔ�����ꏬ�@�� |
�����f�[�^�F�@�@
CP-S50-o-324.pdf
�@�����쌠�@�i�����O��N�@����O�㍆�j�̒�߂�Ƃ���ɂ��A����҂́A���̒��앨�����錠�����L���A��O�҂����쌠�҂ɖ��f�ł��̒��앨������Ƃ��́A�U��҂Ƃ��Ē��쌠�N�Q�̐ӂɔC���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă��邪�A�����ɂ������앨�̕����Ƃ́A�����̒��앨�Ɉˋ����A���̓��e�y�ь`�����o�m������ɑ������̂��Đ����邱�Ƃ������Ɖ����ׂ��ł��邩��A�����̒��앨�Ɠ��ꐫ�̂����i���쐬����Ă��A���ꂪ�����̒��앨�Ɉˋ����čĐ����ꂽ���̂łȂ��Ƃ��́A���̕������������Ƃɂ͂����炸�A���쌠�N�Q�̖�����]�n�͂Ȃ��Ƃ���A�����̒��앨�ɐڂ���@��Ȃ��A�]���āA���̑��݁A���e��m��Ȃ������҂́A�����m��Ȃ��������Ƃɂ��ߎ�������ƔۂƂɂ�����炸�A�����̒��앨�Ɉˋ�������i���Đ�����ɗR�Ȃ����̂ł��邩��A�����̒��앨�Ɠ��ꐫ�̂����i���쐬���Ă��A����ɂ�蒘�쌠�N�Q�̐ӂɔC���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂ł͂Ȃ��B
FM�M���������u����(�����@)
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@***�Q�l���� �F �����@Vol.100�@2003-6�@�ؒI �ƈ� �����@����]��***�@
�����ԍ��F�@ �@����12�N(��)��580��
�������F�@�@�@�@���Q��������������
�ٔ��N�����F�@����14�N09��26��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H12-Ju-580.pdf
�@(1)�@�{�����Q���������́A�{���������҂��Z�����͖{�X���ݒn���䂪���Ƃ�����{�l�y�ѓ��{�@�l�ł���A�䂪���ɂ�����s�ׂɊւ��鐿���ł͂��邪�A��N�Q���v���č��������ł���Ƃ����_�ɂ����āA�O�I�v�f���܂ޖ@���W�ł���B�{�����Q���������́A���l�̗L������Y���̐N�Q�𗝗R�Ƃ�����̂ŁA���l�Ԃɂ����đ��Q�����������̑��ۂ����ƂȂ���̂ł����āA�����@�����肷��K�v������B
�@�����āA�������N�Q�𗝗R�Ƃ��鑹�Q���������ɂ��ẮA���������L�̖��ł͂Ȃ��A���Y���̐N�Q�ɑ��閯����̋~�ς̈�ɂق��Ȃ�Ȃ�����A�@���W�̐����͕s�@�s�ׂł���A���̏����@�ɂ��ẮA�@��P�P���P���ɂ��ׂ��ł���B���R�̏�L�P(1)�̔��f�́A�����ł���B
�@(2)�@�{�����Q���������ɂ��āA�@��P�P���P���ɂ����u�����^�������m�����V�^���n�v�́A�{���č��������̒��ڐN�Q�s�ׂ��s���A�����N�Q�Ƃ������ʂ��������A�����J���O���Ɖ����ׂ��ł���A�����̖@���������@�Ƃ��ׂ��ł���B�������A(�)�@�䂪���ɂ������㍐�l�̍s�ׂ��A�A�����J���O���ł̖{���č��������N�Q��ϋɓI�ɗU������s�ׂł������ꍇ�ɂ́A�����N�Q�Ƃ������ʂ͓����ɂ����Ĕ����������̂Ƃ������Ƃ��ł��A(�)�@�����@�ɂ��ăA�����J���O���̖@���ɂ��Ɖ����Ă��A��㍐�l���A�č��q��Ђɂ��A�����J���O���ɂ�����A���y�є̔���\�肵�Ă������A��㍐�l�̗\���\�����Q���邱�Ƃɂ��Ȃ�Ȃ�����ł���B���̏����@���䂪���̖@���ł���Ƃ������R�̏�L�P(2)�̔��f�́A�����łȂ��B
�@(3)�@�č������@�Q�W�S���́A�������N�Q�ɑ��閯����̋~�ςƂ��đ��Q����������F�߂�K��ł���B
�@�{���č����������A�����J���O���ŐN�Q����s�ׂ��䂪���ɂ����ĐϋɓI�ɗU�������҂́A�č������@�Q�V�P��(b)���A�Q�W�S���ɂ��A���Q�����ӔC���m�肳���]�n������B
�@�������Ȃ���A���̏ꍇ�ɂ́A�@��P�P���Q���ɂ��A�䂪���̖@�����ݐϓI�ɓK�p�����B�{���ɂ����ẮA�䂪���̓����@�y�і��@�ɏƂ炵�A�������N�Q��o�^���ꂽ���̗̈�O�ɂ����ĐϋɓI�ɗU������s�ׂ��A�s�@�s�ׂ̐����v����������邩�ۂ����������ׂ����ƂƂȂ�B
�@���n��`�̌������̂�A�č������@�Q�V�P��(b)���̂悤�ɓ������̌��͂������̗̈�O�ɂ�����ϋɓI�U���s�ׂɋy�ڂ����Ƃ��\�Ƃ���K��������Ȃ��䂪���̖@���̉��ɂ����ẮA�����F�߂闧�@���͏��̂Ȃ�����A�������̌��͂��y�Ȃ��A�o�^���̗̈�O�ɂ����ē������N�Q��ϋɓI�ɗU������s�ׂɂ��āA��@�Ƃ������Ƃ͂ł����A�s�@�s�ׂ̐����v�������������̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA�{���č��������̐N�Q�Ƃ��������́A�@��P�P���Q���ɂ����u�O���j���e�����V�^�������J���{�m�@���j�˃��n�s�@�i���T���g�L�v�ɓ����邩��A��㍐�l�̍s�ׂɂ��č������@�̏�L�e�K���K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(����)
������R�A�Q�ɂ��Ă̍ٔ����䓈��F�̕⑫�ӌ��́A���̂Ƃ���ł���B
�@�{���č��������N�Q�𗝗R�Ƃ��鑹�Q���������ɂ��ẮA�A�����J���O���̖@���������@�Ƃ��ׂ��ł��邪�A���̏ꍇ�́A�@��P�P���Q���ɂ��A�䂪���̖@�����ݐϓI�ɓK�p����邱�ƂɂȂ邩��A���̓_�ɂ��ĕ⑫�I�Ɏ��̈ӌ����q�ׂ邱�ƂƂ���B
�@�P�@�@��P�P���Q���ɂ����u�O���j���e�����V�^�������J���{�m�@���j�˃��n�s�@�i���T���g�L�v�Ƃ́A�s�@�s�ׂ̐����v���̑S�Ăɂ��āA�����@�i�s�@�s��ʖ@�݂̂Ȃ炸�A�����@��������@���܂ށB�j�̐����v�����Ƃ��ɋ�����Ȃ���A�s�@�s�ׂ͐������Ȃ��Ƃ̈Ӗ��ɉ����ׂ��ł���B���̓_�ɂ��ẮA�����ӌ��̔�������Ƃ���ł���B
�@�Q�@�������ɂ��Ă̑��n��`�̌����ɂ��A�䂪���̗̈�O�ɂ����ĉ䂪���̓������̐N�Q�ɓ�����s�ׁi�Ⴆ�ΐN�Q�i��������A�̔������肷��s�ׂȂǁj�����Ă��A���̂��Ǝ��͉̂䂪���̓�������N�Q���邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ����A�������䂪���̗̈�O�ʼn䂪���̓������̐N�Q�ɓ�����s�ׂ����Ă��A���̐N�Q�̌��ʂ��䂪���̍����ɋy�сA���ꂪ�����̒��ڐN�Q��ϋɓI�ɗU������s�ׂɓ�����ꍇ�A���O�ɂ������L�̍s�ׂɂ��āA�䂪���̖��@��̋������͛ɓ�����Ƃ��āA�����s�@�s�אӔC��F�߂邩�ۂ��͊ȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B
�@���n��`�������Ƃ���e�������@�ɂ���ċK������Ă��錻�݂̓������Ɋւ��鍑�ے����̉��ł́A�������҂́A���������o�^���ꂽ�b���̓����@�ɂ���čb�����ɂ����钼�ڐN�Q�ɂ��ĕی�����߂����A�����ɂ����āA���l�̕ی�����߂�̂ł���A�����ɂ����ē���̔����ɂ��ē�������ݒ肵�ĉ����ɂ�����N�Q�ɂ��ĕی�����߂邱�ƂƂ��Ă���B�Ƃ���ŁA�č������@�Q�V�P��(b)���́A��L�̂悤�ɁA�������N�Q��ϋɓI�ɗU������҂͐N�Q�҂Ƃ��ĐӔC���|�K�肵�A���ڐN�Q�s�ׂ��A�����J���O���̗̈���ōs������肻�̗̈�O�ŐϋɓI�U�����s����ꍇ�����܂ނ��̂Ɖ�����A�����̗̈�O�̍s�ׂ����������Ƃ��đ��Q�����ӔC���m�肵�Ă��邪�A����́A��L�̍��ے����̉��ő����Ƃ͈قȂ闧����̗p���Ă�����̂ƌ��킴����A���̂悤�ȋK��������Ȃ��䂪���̓����@�́A�䂪���̗̈�O�ɂ�����ϋɓI�U���s�ׂɉ䂪���̓������̌��͂��y�ڂ����Ƃ��m�肵�Ȃ�������̂��Ă�����̂Ɖ�����ق��͂Ȃ��B�Ƃ���A�䂪���̖��@�̉��ߘ_�ɂ���āA�����s�@�s�҂Ƃ݂Ȃ��āA���O�ɂ����ĐϋɓI�U���s�ׂ������҂̑��Q�����ӔC���m�肵�A�܂��A�����A�s�ׂ̔ƍߒn�Ɋւ���Y����������p���āA���O�ɂ����čs��ꂽ�ϋɓI�U���s�ׂ������ɂ����钼�ڐN�Q�ƈ�̂̂��̂Ɖ����āA���Q�����ӔC���m�肷�铡��ٔ����̔��Έӌ��ɂ͓������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������A�Ⴆ�A���L���̂悤�ɖ������ʂ̎����Ƃ��ĔF�߂��錠���̐N�Q���A�䂪���̗̈�O�ŋ����A����s�ׂɂ��āA�䂪���̖��@�̋����s�@�s�ׂ̗��_�ɂ��A�䂪���̍����̒��ڐN�Q�҂ƂƂ��ɑ��Q�����ӔC���m�肷�邱�Ƃɂ͈٘_�̂Ȃ��Ƃ���ł��邪�A�������́A�e���̎Y�Ɛ���ɏ]���āA�e���ʂɐݒ�o�^����A���̌��͓͂��Y���̗̈���ɂƂǂ܂邱�Ƃ������Ƃ��錠���ł��邩��A���L���̂悤�ȕ��ՓI�Ȍ����̐N�Q�̏�ʂƓ���ɘ_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̂悤�ɁA�䂪���̓����@�́A��������N�Q����s�ׂ�o�^���ꂽ���̗̈�O�ŐϋɓI�ɗU������s�ׂɂ��ĕs�@�s�אӔC���m�肷�闧����̂��Ă��Ȃ��Ɖ�����ȏ�A���ɂ��̓_�Ɋւ��闧�@����A���蓙�̒�߂��Ȃ����݂̍��ے����̉��ł́A�䂪���̖@��ɂ����āA�č������@��K�p���āA�A�����J���O�����̒��ڐN�Q�҂ɂ��đ��Q�����ӔC���m�肷�邱�Ƃ͂Ƃ������A�{���̂悤�ɁA�䂪���̗̈���ɂ����čs��ꂽ�����A�A�o���̍s�҂ɂ��āA�č������@�̋K�肷��ϋɓI�U���s�ׂɓ�����҂Ƃ��ĕs�@�s�אӔC���m�肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�@������R�A�Q�ɂ��Ă̍ٔ������䐳�Y�̔��Έӌ��́A���̂Ƃ���ł���B
�@���́A�{���������N�Q�𗝗R�Ƃ��鑹�Q���������ɂ��ẮA�����ӌ��̌��_�Ɏ^�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̗��R�́A���̂Ƃ���ł���B
�@�P�@�{�����Q���������̖@���W�̐����͕s�@�s�ׂł���A���̏����@�͖@��P�P���P���ɂ��ׂ��ł��邱�ƁA�����ɂ����u�����^�������m�����V�^���n�v�́A�{���č��������̒��ڐN�Q�s�ׂ��s���A�������N�Q�Ƃ������ʂ��������A�����J���O���Ɖ����ׂ��ł���A�����̖@���������@�ƂȂ邱�Ƃɂ��ẮA�����ӌ��ƌ�����������B�����āA�č������@�Q�V�P��(b)���y�тQ�W�S���ɂ��A�č������������ŐN�Q����s�ׂ����O�ɂ����ĐϋɓI�ɗU�������҂́A���Q�����ӔC���Ƃ���Ă���B�@�Q�@�s�@�s�ׂɂ��ẮA�@��P�P���Q���ɂ��A�@��n�ł���䂪���̖@�����ݐϓI�ɓK�p�����B�{���ɂ����āA�����ɂ����u�O���j���e�����V�^�������v�ɓ�����̂́A�{���č��������̐N�Q���䂪���̗̈���ɂ����ĐϋɓI�ɗU�����ăA�����J���O���ɂ����ĐN�Q�̌��ʂ��������Ƃ��������ł���A���̎������������������n�@�Ɖ䂪���̖@���̕s�@�s�ׂ̐����v�����Ƃ��ɖ������ď��߂ĕs�@�s�ׂ��������邱�ƂɂȂ�̂ł���B�����āA���̏ꍇ�ɂ����āA�䂪���̖@����K�p����ɓ�����A��N�Q���v�ł���č��������̑��݂͐挈���ł���A���̌��������ꎩ�̂̏����@�ɂ���Đ����������̂ł������A��������^�̑O��Ƃ��āA���̎�̌����̐N�Q���䂪���̖@����s�@�s�ׂƔF�߂��邩�ǂ����f���ׂ��ł���i�č����������䂪���ɂ����Ă͌��͂�L���Ȃ����Ƃ̌̂ɁA���ꂪ�����Ƃ��đ��݂��Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ��Ĕ��f���ׂ��ł͂Ȃ��B�j�B
�@�䂪���̖��@�V�O�X���A�V�P�X���Q���ɂ��A�������̐N�Q��ϋɓI�ɗU������s�ׂ́A�������N�Q�̋������͛ɓ�����Ƃ����ׂ��ł���A���̍s�ׂ��s�����҂́A�����s�҂Ƃ݂Ȃ���A���ڐN�Q�҂ƘA�т��đ��Q�����ӔC�����Ƃ͖��炩�ł���B���������āA�䂪���̖@���ɂ���Ă��s�@�s�ׂ���������ꍇ�ɓ�����B���̂悤�ɉ����Ă��A�����o�^���̍��O�ɂ�����s���̂ɒ��ڂɕč��������̌��͂��y�ڂ����̂ł͂Ȃ��A�����o�^���ɂ����Đ��������ڐN�Q�Ɋ�Â����Q�̔����ɂ��Ē��ڐN�Q�҂Ƃ̘A�ѐӔC�킹����̂ɂ����Ȃ�����A���n��`�̌����ɔ�����Ƃ͂����Ȃ��B
�f�[�^�`����������
| �����ԍ� |
�@����16�N(��)��10667�� |
| ������ |
�@���Q�������������� |
| �ٔ��N���� |
�@����19�N11��28�� |
| �ٔ����� |
�@�����n���ٔ��� |
�����f�[�^�F�@�@
PAT-H16-wa-10667.pdf
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�f�[�^�`�������Ɋւ��锭���ɂ��Ă̓������̋��L������L���Ă��錴�����A�ʎ��퍐�����ژ^�L�ڂ̂`�c�r�k���f���p�̃`�b�v�Z�b�g�i�ȉ��u�퍐���i�v�Ƃ����B�j�̐����A�̔������Ă���i���̐����A�̔������{�ōs���Ă���ƕ]���ł��邩�ɂ��Ă͑���������B�j�A�A�����J���O���i�ȉ��u�č��v�Ƃ����B�j�@�l�ł���퍐�Z���e�B���A���E�R�~���j�P�[�V�����Y�E�C���R�[�|���C�e�b�h�i�ȉ��A�u�퍐�b�b�h�v�Ƃ����B�j�y�т��̓��{�ɂ�����q��Ђł���퍐�Z���e�B���A���E�W���p��������Ёi�ȉ��A�u�퍐�b�i�v�Ƃ����B�j�ɑ��A�퍐���i������������f���ɂ��`�c�r�k�ʐM�́A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ����邩��A�퍐���i�̐��Y�A���n�A�A���A���n�̐\�o�̊e�s�ׂ́A�����P�T�N�P���P���Ȍ㓯�N�W���R�O���܂ł̍s�ׂɑ��ẮA�����P�W�N�@����T�T���ɂ������O�̓����@�P�O�P���R���i�ȉ��u�����@�P�O�P���R���v�Ƃ����B�j�y�ѓ����S���i�ȉ��u�����@�P�O�P���S���v�Ƃ����B�j�ɂ��A�����P�S�N�P�Q���R�P���ȑO�̍s�ׂɑ��ẮA�����P�S�N�@����Q�S���ɂ������O�̓����@�P�O�P���Q���i�ȉ��u�����P�S�N�����O�����@�P�O�P���Q���v�Ƃ����B�j�ɂ��A��������A�{���������̊ԐڐN�Q�s�ׂɓ�����Ƃ���A�@�Z�F�d�@�H�Ɗ�����Ёi�ȉ��u�Z�F�d�H�v�Ƃ����B�j�y�ѓ��{�d�C������Ёi�ȉ��u�m�d�b�v�Ƃ����B�j�́A�퍐���i���͂������������`�c�r�k���f����A�����A�퍐���i����������`�c�r�k���f���𓌓��{�d�M�d�b������Ёi�ȉ��u�m�s�s�����{�v�Ƃ����B�j�y�ѐ����{�d�M�d�b������Ёi�ȉ��u�m�s�s�����{�v�Ƃ����A�m�s�s�����{�Ƃm�s�s�����{���āu�m�s�s�v���́u�m�s�s�����n���Ёv�Ƃ����B�j�֏��n���Ă���A�Z�F�d�H�y�тm�d�b�́A��L�e�s�ׂɂ��āA�{���������̊ԐڐN�Q�ɂ��s�@�s�אӔC�����A�퍐��ɂ́A��L�e�s�ׂɂ��āA��L�e�ЂƋ����s�@�s�ׁi���@�V�P�X���P�����͂Q���j���������邱�Ɓi��ʓI�咣�j�A�A�퍐��ɂ��A�퍐���i���͂������������`�c�r�k���f���̏��n�s�ׂ́A���{�����ōs���Ă���ƕ]���ł��邱�Ɓi�\���I�咣�P�j�A�B�퍐��́A���{�����ɂ����āA�퍐���i���͂������������`�c�r�k���f���̏��n�̐\�o�����Ă��邱�Ɓi�\���I�咣�Q�j�A�C�퍐��́A�퍐���i�̐S�����ł���E�G�n���A�O�H�d�@������Ёi�ȉ��u�O�H�d�@�v�Ƃ����B�j�ɓ��{�����Ő��������Ă��邪�A�O�H�d�@�̓��{�����ł̏�L�s�ׂ́A�퍐��ɂ����̂ƕ]���ł��邱�Ɓi�\���I�咣�R�j���咣���āA�������N�Q�̕s�@�s�ׂɊ�Â����Q���������y�ѕs�������ԊҐ����A���тɔ퍐�b�b�h�ɂ��ẮA�i�B�̓��̗����ł��镽���P�U�N�X���P������A�퍐�b�i�ɂ��ẮA�i�B�̓��̗����ł��铯�N�W���R�����疯�@����N�T���̊����ɂ��x�����Q���̐��������Ă��鎖�Ăł���B
(���|)
(2) ����
�@�ȏ�̎�����O��ɁA�퍐�b�b�h�ɑ���i���ɂ��āA�䂪���̍ٔ����ɍ��ۍٔ��NJ����F�߂��邩�ۂ�����������B
�A���ۍٔ��NJ��̔��f�
�@�䂪���̍ٔ����ɒ�N���ꂽ�i�ׂ̔퍐���A�O���ɖ{�X��L����O���@�l�ł���ꍇ�ɂ́A���Y�@�l���i��ŕ�����ꍇ�̂ق����{�̍ٔ������y�Ȃ��̂������ł��邪�A��O�Ƃ��āA�퍐���䂪���Ɖ��炩�̖@�I�֘A��L���鎖���ɂ��ĉ䂪���̍��ۍٔ��NJ����m�肷�ׂ��ꍇ�̂��邱�Ƃ́A�ے肵���Ȃ��Ƃ���ł���B�������A�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɉ䂪���̍��ۍٔ��NJ����m�肷�ׂ����ɂ��ẮA���ۓI�ɏ��F���ꂽ��ʓI�ȏ��������݂����A���ۓI���K�@�̐��n���\���łȂ����߁A�����ҊԂ̌�����ٔ��̓K���E�v���̗��O�ɂ��𗝂ɏ]���Č��肷��̂������ł���B�����āA�䂪���̖��i�@�̋K�肷��ٔ��Ђ̂����ꂩ���䂪�����ɂ���Ƃ��ɂ́A�����Ƃ��āA�䂪���̍ٔ����ɒ�N���ꂽ�i�����ɂ��A�퍐���䂪���̍ٔ��Ђɕ�������̂������ł��邪�i�ō���
���a�T�T�N(�I)��P�R�O�����T�U�N�P�O���P�U����@�씻���E���W�R�T���V���P�Q�Q�S�Łj�A�䂪���ōٔ����s�����Ƃ������ҊԂ̌����A�ٔ��̓K���E�v����������Ƃ������O�ɔ�������i�̎������ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A�䂪���̍��ۍٔ��NJ���ے肷�ׂ��ł���i�ō���
�����T�N(�I)��P�U�U�O�����X�N�P�P���P�P����O���@�씻���E���W�T�P���P�O���S�O�T�T�Łj�B
�@�����ŁA�{���ɂ����āA�퍐�b�b�h�ɑ���i���ɂ��āA���i�@�̋K�肷��ٔ��Ђ��F�߂��邩���A�ȉ���������B
�C���i�@�S���P���A�T���ɂ���
�@��L(1)�̂Ƃ���A�퍐�b�b�h1 �́A�č��ɖ{�X��L����č��@�l�ł���A���{�����ɂ́A�x�X���c�Ə����L���Ă��Ȃ��̂ł��邩��A���i�@�S���P���A�T���ɂ��ٔ��Ђ͉䂪�����ɔF�߂�ꂸ�A���������āA�퍐�b�b�h�ɑ���i���ɂ��āA�䂪���̍ٔ����ɍ��ۍٔ��NJ���F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(����)
�E���i�@�V���ɂ���
�@���i�@�V�����������A�R�W��O�i�ɂ��A�i�ׂ̖ړI�ł��錠�����͋`�������l�ɂ��ċ��ʂł���Ƃ��A���͓���̎�����y�і@����̌����Ɋ�Â��Ƃ��́A���̐��l�́A�����i�אl�Ƃ��đi�����邱�Ƃ��ł��邪�A���̂悤�ɂ��čٔ��Ђ��F�߂���ɂ����Ȃ��ꍇ�ɁA�����ɍ��ۍٔ��NJ���F�߂�ƁA�퍐���g�ɑ��鐿���Ƃ͉���֘A����L���Ȃ����ł̉��i���������邱�ƂɂȂ�A���i�@��̑��̋K��ɂ��ٔ��Ђ��F�߂��邱�Ƃɂ�荑�ۍٔ��NJ����m�肷��ꍇ�ɔ�ׂāA�퍐�̎�s���v���傫���A�����҂̌�����ٔ��̓K���E�v���̗��O�Ɋ�Â��𗝂ɂ�����Ȃ����ƂƂȂ�B�����Ƃ��A���퍐�ɑ��鐿���Ɠ��Y�퍐�ɑ��鐿���Ƃ̊ԂɁA�ŗL�K�v�I�����i�ׂ̊W�Ȃ�������ɗގ�������x�̋��łȊ֘A�������邱�Ƃ��F�߂���ꍇ�ȂǁA���ɉ䂪���̍ٔ����ɍ��ۍٔ��NJ���F�߂邱�Ƃ������ҊԂ̌����A�ٔ����̓K���E�v����������Ƃ������O�ɍ��v������i�̎��������ꍇ�ɂ́A�䂪���̍ٔ��NJ���F�߂邱�Ƃ��𗝂ɓK���Ɖ������B�����ŁA���i�@�V�����������A�R�W��O�i�̋K��Ɉˋ��������ۍٔ��NJ��́A�����Ƃ��ĔF�߂�ꂸ�A��L�̂悤�ȋ��łȊ֘A�����F�߂���ꍇ�ɂ̂ݔF�߂���Ɖ�����̂������ł���B
(����)
�@�ȏ�̂��Ƃ��l������ƁA�퍐�b�b�h�ɑ��鐿���Ɣ퍐�b�i�ɑ��鐿���Ƃ̊ԂɁA�����֘A��������Ƃ��āA�퍐�b�b�h�ɑ���i���ɂ��āA���i�@�V���Ɉˋ��������ۍٔ��NJ���F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA���i�@�V���̋K��Ɉˋ����āA�퍐�b�b�h�ɑ���i���ɂ��āA�䂪���̍ٔ����ɍ��ۍٔ��NJ���F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�G���i�@�T���X���ɂ���
�@���i�@�T���X���̕s�@�s�גn�̍ٔ��Ђ̋K��Ɉˋ����ĉ䂪���̍��ۍٔ��NJ����m�肷�邽�߂ɂ́A�����Ƃ��āA�@�����咣�ɌW��s�@�s�ׂ̋q�ϓI�����̑��y�чA���̂����̎��s�s�גn���͑��Q�̔����n�����{�����ł��邱�Ƃ��ؖ������Α���A��@����̈Ӊߎ��ɂ��Ă͗�����K�v�͂Ȃ��Ɖ�����̂������ł���i
�ō��ٕ����P�Q�N(�I)��X�Q�X�����P�R�N�U���W����@�씻���E���W�T�T���S���V�Q�V�Łj�B�����āA�����s�@�s�ׂɂ����ẮA��L�@�̍��ۍٔ��NJ����m�肷�邽�߂ɗ����ׂ��q�ϓI�����́A���Y�s�@�s�ׂ̎��s�s�ׁA�q�ϓI�֘A����������b�t���鎖�����͛Ⴕ���͋����s�ׂɂ��Ă̋q�ϓI�����A���Q�̔����y�ю����I���ʊW�ł���Ɖ�����̂������ł���B
(�A) ��ʓI�咣�ɌW��i���ɂ��Ă̍��ۍٔ��NJ��̗L��
�� �����́A��ʓI�ɁA�Z�F�d�H�y�тm�d�b���퍐���i��A���������ƁA�y�ѓ��Ђ��퍐���i������������f�����m�s�s�֏��n�������Ƃɂ��āA�퍐��ɂ́A�Z�F�d�H�y�тm�d�b�ƁA���@�V�P�X���P���̋����s�@�s�ׁi��ʓI�咣�P�j ���͓����Q���̋����s�@�s�ׁi��ʓI�咣�Q�j����������|�咣����B
�� �����ŁA��������ɁA�{���ɂ����ẮA��L(1)�Ŕ��������悤�ɁA�Z�F�d�H�y�тm�d�b�́A�퍐���i���͔퍐���i��g�ݍ��`�c�r�k���f����A�����A���`�c�r�k���f�����m�s�s�ɔ̔����Ă���̂ł��邩��A���ɁA�{�������������ƂȂ炸�A�퍐���i�̗A���A�̔������{���������̐N�Q�s�ׂɊY������̂ł���A�Z�F�d�H�y�тm�d�b�̏�L�s�ׂ́A�{����������N�Q����s�@�s�ׂ��\�����A�܂��A�{����������L���Ă��錴���ɁA�䂪���ɂ����āA���Q�͔������Ă�����̂ƔF�߂���B
�@���ɁA�q�ϓI�֘A�������̑��ۖ��͛E�����s�ׂ̋q�ϓI�����̑��ۂɂ��ẮA��L(1)�Ŕ��������Ƃ���A�Z�F�d�H�y�тm�d�b�ɂ��u�A���v�y�сu���n�v�̖ړI�ƂȂ��Ă���퍐���i�́A�퍐�b�b�h�������������̂ł���Ƃ���A��L(1)�̂Ƃ���A�퍐�b�b�h�́A�Z�F�d�H�Ƃ̊ԂŁA���c�r�k�Z�p�ɗp�����A���A�`�c�r�k�p�̐M�������̂��߂̃C���^�[�t�F�[�X�f�o�C�X�̊J�������͂��čs�����Ƃ���e�Ƃ���_���������A���_��Ɋ�Â��J���ɂ��A�퍐���i�̂����̏��Ȃ��Ƃ��P�̃V���[�Y�̐���������Ă��邱�ƁA�m�d�b�Ƃ̊ԂŁA�f�D�k�������y�тi�c�r�k�̊J�������͂��čs���|�̌_���������A���_��Ɋ�Â��J���ɂ��A�퍐���i�̂����̏��Ȃ��Ƃ��P�̃V���[�Y�̐���������Ă��邱�ƁA�O�H�������m�s�s�Ƃ̊ԂŁA�m�s�s�ɑ��āA�h�r�c�m�̊����ɂ����Ă��c�r�k�Z�p�̗��_�I�݊����ɂ��ẴR���T���e�B���O������|�̌_��i �m�s�s�E�l �b�_��j������������Ƃ�O��Ƃ��āA�O�H�����Ƃ̊ԂŁA���Ђɑ��āA��L�̂m�s�s�E�l�b�_��Ɋ�Â����Ђ��m�s�s�ɑ��Ē���Z�p�������|�̃R���T���^���g�_���������Ă��邱�ƁA���тɔ퍐�b�b�h�́A�Z�F�d�H���g�A���͂m�d�b�̊֘A��Ђł���m�d�b�A�����J�ɑ��āA�퍐���i��̔����Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA���퍐�́A���Ђ��Z�F�d�H�y�тm�d�b�A�����J�ɑ��Ĕ̔������퍐���i���A���̂܂܂Ŗ��͂`�c�r�k���f���ɑg�ݍ��܂�āA�Z�F�d�H�y�тm�d�b�ɂ���ėA������A����ɁA�`�c�r�k���f���ɑg�ݍ��܂ꂽ�`�łm�s�s�ɏ��n����邱�Ƃ�F�����Ă���A���̂悤�ȔF���̉��ɁA�Z�F�d�H�y�тm�d�b�ɑ��āA�ϋɓI�ɔ퍐���i�̔̔��̂��߂̊������s�������̂Ɛ�������邩��A�퍐�b�b�h�ɂ́A�Z�F�d�H�y�тm�d�b�̏�L�s�@�s�ׂɂ��āA���Ȃ��Ƃ��q�ϓI�֘A���������F�߂��A�܂��A�퍐�b�b�h�̏Z�F�d�H�y�тm�d�b�ɑ���퍐���i�̔̔��s�y�т��̑O��Ƃ��Ẳc�ƍs�ׂ́A�Z�F�d�H�y�тm�d�b�̏�L�s�@�s�ׂ̛Ȃ��������s�ׂƕ]���ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�@���������āA�����̎�ʓI�咣�ɌW��i���ɂ��ẮA�䂪���̍ٔ����ɊNJ����m�肷��ɑ����L�̋q�ϓI�����y�ѓ��{�����ł̑��Q�̔�����F�߂邱�Ƃ��ł���B
�� �����āA��L���Ŕ������������W���炷��ƁA�퍐�b�b�h�Ƃ��ẮA���Ȃ̐����A�̔������퍐���i�����{�����ɗ��ʂ��A���{�̓�������N�Q����\�������邱�Ƃ��\���\�����������̂ƔF�߂���B�܂��A��L( )�̂Ƃ���1 �A�퍐�b�b�h�̑S���㍂�ɐ�߂�Z�F�d�H�y�тm�d�b�ɑ��锄�㍂�̊������A�����P�R�N�Ȃ��������P�T�N�̊Ԃ͂W�O�p�[�Z���g�ȏ�ƁA���ɍ������̂ł��������Ƃ���A�퍐�b�b�h�̎�v�̎s��͓��{�ł������Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�ȏ�̎���炷��A�����̎�ʓI�咣�ɌW��i���ɂ��āA�䂪���ōٔ����s�����Ƃ������ҊԂ̌����A�ٔ��̓K���E�v����������Ƃ������O�ɔ����錋�ʂɂȂ�Ƃ͂������A�䂪���ɂ�����NJ���ے肷�ׂ����i�̎������Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�� ���������āA�����̔퍐�b�b�h�ɑ����ʓI�咣�ɌW��i���ɂ��āA�䂪���̍ٔ����ɍ��ۍٔ��NJ����F�߂���B
(����)
�R����
�@��L�Q�̂Ƃ���A�퍐���@�́A�{�������̖{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�������̂ł͂Ȃ�����A�����̔퍐�b�b�h�ɑ���e�����y�є퍐�b�i�ɑ���e�����́A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A����������R���Ȃ��B
�O���̓������錠��(�E������)
���O���̓������錠���̏��n�ɂ��Ă��A�����̑Ή��̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���B��
�����ԍ��F�@�@�@����16�N(��)��781��
�������F�@�@�@�@ �⏞����������
�ٔ��N�����F�@ ����18�N10��17��
�@�얼�F�@�@�@�@ �ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@�@
PAT-H16-Ju-781.pdf
�@�]�Ǝғ��������@�R�T���P������̐E�������ɌW��O���̓������錠�����g�p�ғ��ɏ��n�����ꍇ�ɂ����āC���Y�O���̓������錠���̏��n�ɔ����Ή������ɂ��ẮC�����R���y�тS���̋K�肪�ސ��K�p�����Ɖ�����̂������ł���B
(����)
�@���������āC��L�e�O���̓������錠���̏��n�ɔ����Ή������ɂ��ẮC�����R���y�тS���̋K�肪�ސ��K�p����C��㍐�l�́C�㍐�l�ɑ��C��L�e�O���̓������錠���̏��n�ɂ��Ă��C�����R���Ɋ�Â������S������̊�ɏ]���Ē�߂��鑊���̑Ή��̎x���𐿋����邱�Ƃ��ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�X�i�b�N�V���l������
���s�������h�~�@��Q���P����P���́u������������s�ׁv�ɊY���B��
�����ԍ��F�@�@ ����7�N(�I)��637��
�������F�@�@�@�@�g�p���~��������
�ٔ��N�����F�@����10�N09��10��
�ٔ������F�@ �@�ō��ٔ�����ꏬ�@��@
�����f�[�^�F�@
UF-H07-o-637.pdf
�@��㍐�l�̉c�Ƃ̓��e�́A���̎�ށA�K�͓��ɂ����Č��ɃV���l���E�O���[�v�̉c�މc�ƂƂ͈قȂ���̂́A�u�V���l���v�̕\���̎��m�����ɂ߂č������ƁA�V���l���E�O���[�v�̑�����t�@�b�V�����֘A�ƊE�̊�Ƃɂ����Ă����̌o�c�����p������X���ɂ��邱�Ɠ��A�{�������W�̉��ɂ����ẮA��㍐�c�ƕ\���̎g�p�ɂ��A��ʂ̏���҂��A��㍐�l�ƃV���l���E�O���[�v�̊�ƂƂ̊Ԃɋٖ��ȉc�Ə�̊W���͓���̏��i�����Ƃ��c�ރO���[�v�ɑ�����W��������ƌ�M���邨���ꂪ������̂Ƃ������Ƃ��ł���B���������āA��㍐�l���㍐�l�̉c�ƕ\���ł���u�V���l���v�Ɨގ������㍐�l�c�ƕ\�����g�p����s�ׂ́A�V�@����ꍀ�ꍆ�ɋK�肷��u������������s�ׁv�ɓ�����A�㍐�l�̉c�Ə�̗��v��N�Q������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�v���[�c�v���[�Y����
���s�������h�~�@��Q���P����P���A��S���A��T���P���Ɋ�Â����Q����������F�߂�B
�@�M�p�[�u�Ƃ��Ă̎ӍߍL�������߂錴���̐����́A���R���Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����7�N(��)��13557��
�������F�@�@�@�@�v���[�c�E�v���[�Y����
�ٔ��N�����F�@����11�N06��29��
�ٔ������F�@�@ �����n���ٔ���
�����f�[�^�F�@
UF-H07-wa-13557.pdf
�R�@�������i�̌`�Ԃ̎��m���i�\�����ɂ���
�@���i�̌`�Ԃ́A�{���I�ɂ͏��i�̋@�\�E���p�̔�������ς̌��㓙�̂��߂ɑI���������̂ł���A���i�̏o����\�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��đI���������̂ł͂Ȃ����A����̏��i�`�Ԃ�����̏��i�Ǝ��ʂ�����Ǝ��̓�����L���A���A�E���i�`�Ԃ��A�����Ԍp���I���Ɛ�I�Ɏg�p����邩�A���͒Z���Ԃł����͂Ȑ�`���������Ďg�p���ꂽ�悤�ȏꍇ�ɂ́A���ʂƂ��āA���i�̌`�Ԃ����i�̏o���\���̋@�\��L����Ɏ���A���A���i�\���Ƃ��Ă̌`�Ԃ����p�҂̊ԂŎ��m�ɂȂ邱�Ƃ����蓾��Ƃ����ׂ��ł���B�����āA���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�E���i�`�Ԃ��A���Y���i�̋Z�p�I�@�\�ɗR������K�R�I�A�s��I�Ȃ��̂łȂ�����A�s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�ɋK�肷��u���l�̏��i���\���Ƃ��Ď��p�҂̊ԂɍL���F������Ă�����́v�ɊY��������̂Ƃ�����B
(����)
�@�������i�́A�i�O�y�`�z�̂����v���[�c��i����Ɍ����ɂ����Ċ��E�l�Ă��A�����l�N��ꌎ�ɊJ�Â��ꂽ�ƎҌ����̔��t�p�W����ŏ��߂Ĕ��\���ꂽ��A�����ܔN����A�i�O��Ђɂ���āA�����s���̓��Ђ̒��c�X�Ȃǐ��X�̕������X�Ŕ̔������悤�ɂȂ����B
�@���̌�A�������i�́A�ɐ��O�A�O�z�A��ۂƂ�������v�S�ݓX�ł��̔������悤�ɂȂ�A�̔��n�����s������ߋE�n���ւƊg�債�A�����Z�N�ɂ́A�i�O��Ђ̒��c�X�O�X�A�S�ݓX���X�̂ق������̃t�@�b�V�������X�ɂ����Ĕ̔�����悤�ɂȂ����B�܂��A���N�O���������́A���É��s���̎O�z���É��X�ɂ����Ă��A�������i�̔̔����J�n���ꂽ�B�����āA�E�̂悤�Ȕ̔��̊g��ɂ���āA�i�O��Ђɂ�錴�����i�̔���z�́A�����X�ւ̉������z�Ƃ��āA�����ܔN�Ă���ɂ͌����ώl�Z�Z�Z���~�Ȃ����܁Z�Z�Z���~�ł��������̂��A���Z�N�܌��ɂ͌���ꉭ�܁Z�Z�Z���~�ɒB������̂ƂȂ����B
�@����ɁA�������i�́A�����ܔN��Z���Ƀp���ŁA���N��ꌎ�ɓ����ŊJ�Â��ꂽ�u�C�b�Z�C�~���P����l�N�t�ăR���N�V�����v�ɂ����āA�i�O�y�`�z�̍�i�Ƃ��Ĕ��\����A�D�]�����B
�@�������i�̎G���E�V���ւ̌f��
�@�������i�́A�����ܔN�̔����������瓯�Z�N�l������܂ł̊ԁA�����u�����h�u�C�b�Z�C�E�~���P�v�ɑ����鏤�i�V���[�Y�Ƃ��āA�ƊE�V���̂ق��A�S���I�ɍL�����s����Ă���w�l�����t�@�b�V�����G�����ʐV���ɂ����āA�Љ�L����L�����p�ɂɌf�ڂ���Ă����B�����āA�����̑����ɂ����ẮA�������i�u���ɂ�����Ԃ��邢�̓��f���ɒ��p��������Ԃ̎ʐ^���f�ڂ���Ă���B
�@�܂��A�E�L���̒��ɂ́A�Ⴆ�Έȉ��̂Ƃ���A�������i�𒍖ڏ��i���邢�̓q�b�g���i�Ƃ��ďЉ����̂��������܂܂�Ă���B
�@�@�G���u�d�k�k�d�@�i�`�o�n�m�v�����ܔN�l���ܓ����ł́A�������i���C�b�Z�C�E�~���P�̐V�u�����h�Ƃ��ďЉ��A�u���̏t�A���ڂ̃u�����h�v�Ƃ���Ă���i�b��Z���j�B
�A�@�����ܔN�㌎�O���t�������V���ł́A������t�@�b�V������܂���܂����i�O�y�`�z�Ɋւ���L�����f�ڂ���A���̒��ŁA�i�O�y�`�z���J�������v���[�c�����܂┚���I�Ȑl�C�ł��邱�Ƃ��Љ��Ă���i�b��O�O���j�B
�i�����j
�@�������i�̌`�Ԃ́A�u���炩�ȃ|���G�X�e���̐��n����Ȃ�w�l�p�ߕ��ɂ����āA�c�����ׂ̍���������̃����_���v���[�c���A�����A�����A���Ȃǂ̖D���ڕ������܂߂đS�̂Ɉ�l�Ɏ{����Ă���A���̌��ʁA�ߕ��S�̂Ɍ��݂��Ȃ��ꖇ�̕z�̂悤�ȕ��ʓI�Ȉӏ����\�����Ă���v�Ƃ����_�ɁA���ɊŎ҂̒��ӂ��Ђ��Ǝ��̓���������A����������I�`�Ԃ����폤�i�Ǝ��ʂ������m�ȏ��i�\���ƂȂ������̂ƔF�߂���Ƃ���A�퍐���i�P�Ȃ����T�i���b��Z���Ȃ������Z���j���������i�ɂ����邱���ɑΉ������A�C�e���ł��錴�����i�P�Ȃ����T�i���b��ꍆ�Ȃ�����܍��j�Ƃ��ꂼ��Δ䂵�ώ@����A�퍐���i�P�Ȃ����T���A��������E�Ƌ��ʂ���`�Ԃ̓�����L���邱�Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���B�����A�������i�P�Ȃ����T�Ɣ퍐���i�P�Ȃ����T�Ƃ̊ԂɁA�퍐�炪�咣����悤�ȑ���_�i�u���������ɑ���F�ۋy�є퍐��̎咣�v�Q�i�O�j�i�R�j�̂��邱�Ƃ��F�߂��邪�A��������ʂ̃A�C�e���ɂ�����ו��̑���ɂ������A���������ׂčl�����Ă��A�O�L�̂悤�ȋ��ʂ��������I�`�Ԃ�������炳���Ŏ҂̈�ۂ̋��ʐ����ے肳�����̂ł͂Ȃ��B
�@���������āA�퍐���i�P�Ȃ����T�̌`�Ԃ́A�����̎��m�ȏ��i�\���ƂȂ����������i�̌`�Ԃɗގ�������̂ƔF�߂���B
�@�E�̂Ƃ���퍐���i�P�Ȃ����T�̌`�Ԃ��������i�̌`�ԂƗގ����邱�Ƃ��炷��A�퍐���i�P�Ȃ����T�́A����҂Ȃ������v�҂ɂ����Č������i�Ƃ̍������邨���ꂪ������̂ƔF�߂���B
�@�Ȃ��A�{���ɂ����ẮA����ɉ����āA�i�P�j�퍐���i�ƌ������i�̔̔��E����@���A�@��������S�ݓX�ɂ������p�̔���ł̔̔����s���Ă���_�A�A�E����ɂ����āA�������i�̏ꍇ�ɂ́u�o�k�d�`�s�r�@�o�k�d�`�r�d�v�Ȃ�啶���̃A���t�@�x�b�g�̃��S���f������Ă���Ƃ���A�퍐���i�ɂ����Ă��A�u�s�g�d�@�o�k�d�`�s�r�v�Ȃ�啶���̃A���t�@�x�b�g�̃��S���f������Ă���_�A�B����������i�̈ꕔ��Ɋ����Ē�Ƃ������@���̗p���Ă���_�i�E�@�Ȃ����B�̎����͓����ҊԂɑ������Ȃ��B�j�ɂ����ėގ����Ă��邱�ƁA�i�Q�j�̔����i�ɂ��Ă��A�퍐���i�P�Ȃ����T�����Z�Z�Z�~����ꖜ�܁Z�Z�Z�~�ł���Ƃ���i���b��Z���Ȃ������Z���j�A����ɑΉ����錴�����i�P�Ȃ����T�͈ꖜ��Z�Z�Z�~����~�ł���i���b��ꍆ�Ȃ�����܍��j�A���҂̉��i�т��قڋ��ʂ��邱�ƂȂǁA���v�҂����ʏ���҂̍������������鎖��̑��݂��邱�Ƃ��F�߂���̂ł����āA�����̎���ɏƂ炵�Ă��A�퍐���i�P�Ȃ����T�ɂ����v�҂ɂ����Č������i�Ƃ̍������邨���ꂪ���邱�Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���B
�u���ێ��R�w���v���W����
�����W�o�^�����W�@��S���P����W���̋K��Ɉᔽ������̂ł��邩�ǂ����ɂ��X�ɐR����s�������邽�߁A�{����m�I���Y�����ٔ����ɍ����߂��B��
�����ԍ��F �@�@����16�N(�s�q)��343��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����17�N07��22��
�ٔ������F�@�@ �ō��ٔ�����@��
�����f�[�^�F�@
TM-H16-Ghi-343.pdf
�@�{�����W�u���ێ��R�w���v���㍐�l���́u���R�w���v���܂ޏ��W�ł��邱�ƁA�㍐�l����㍐�l�ɏ�����^���Ă��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł��邩��A�㍐�l���̂��㍐�l�̖��̂́u�����ȗ��́v�Ƃ�����Ȃ�A�{�����W�́A�W������̏��W�ɓ�������̂Ƃ��āA���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ�B
�@���W�@�S���P���́A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����W���e���ŗ�L���Ă��邪�A���v�҂̊ԂɍL���F������Ă��鏤�W�Ƃ̊W�ŏ��i���͖̏o���̍����̖h�~��}�낤�Ƃ��铯���P�O���A�P�T�����̋K��Ƃ͕ʂɁA�W���̋K�肪��߂��Ă��邱�Ƃ���݂�ƁA�W�����A���l�̏ё����͑��l�̎����A���́A�����ȗ��̓����܂ޏ��W�́A���̑��l�̏����Ă�����̂������A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƋK�肵����|�́A�l�i�@�l���̒c�̂��܂ށB�ȉ������B�j�̏ё��A�����A���̓��ɑ���l�i�I���v��ی삷�邱�Ƃɂ���Ɖ������B���Ȃ킿�A�l�́A����̏����Ȃ��ɂ��̎����A���̓������W�Ɏg���邱�Ƃ��Ȃ����v��ی삳��Ă���̂ł���B���̂ɂ��Ă��A��ʂɎ����A���̂Ɠ��l�ɖ{�l���w���������̂Ƃ��Ď�����Ă���ꍇ�ɂ́A�{�l�̎����A���̂Ɠ��l�ɕی�ɒl����ƍl������B
�@��������ƁA�l�̖��̓��̗��̂��W���ɂ����u�����ȗ��́v�ɊY�����邩�ۂ��f����ɂ��Ă��A��ɁA���Ƃ��ꂽ���W�̎w�菤�i���͎w��̎��v�҂݂̂���Ƃ��邱�Ƃ͑����łȂ��A���̗��̂��{�l���w���������̂Ƃ��Ĉ�ʂɎ�����Ă��邩�ۂ�����Ƃ��Ĕ��f�����ׂ����̂Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�{���ɂ����ẮA�O�L�����W�ɂ��A�㍐�l�́A�㍐�l���̂�����y�т���Ɋ֘A����ɒ����Ԃɂ킽��g�p�������A���̊ԁA���ЁA�V�����œx�X���グ���Ă���A�㍐�l���̂́A����W�҂��n�߂Ƃ���m���l�̊ԂŁA�悭�m���Ă���Ƃ����̂ł���B����ɂ��A�㍐�l���̂́A�㍐�l���w���������̂Ƃ��Ĉ�ʂɎ�����Ă����Ɖ�����]�n������Ƃ������Ƃ��ł���B�����ł���Ƃ���A�㍐�l���̂��{�����W�̎w��̎��v�҂ł���w�����̊ԂōL���F������Ă��Ȃ����Ƃ��傽�闝�R�Ƃ��Ė{�����W�o�^���W���̋K��Ɉᔽ������̂ł͂Ȃ��Ƃ������R�̔��f�ɂ́A�W���̋K��̉��ߓK�p���������@������Ƃ��킴��Ȃ��B
�p�`�X���@(���m)���W���N�Q����
�����W�@��V�W���̏��W���N�Q�̍߂���������Ƃ����������̔��f�́A�����B��
�����ԍ��F�@ �@����8�N(��)��342��
�������F�@�@�@�@���W�@�ᔽ����
�ٔ��N�����F�@����12�N02��24��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F�@
TM-H08-a-342.pdf
�@���́A���m�̖{�̂Ƃ͕ʂɃp�`���R�X�ɔ����u����C�p���i�Ƃ��Ă��̔�����A���m�̎����̏Ⴕ���ꍇ�ɂ���ƌ�������邱�Ƃ��������B���ɑ������ꂽ�{���b�o�t�y�т���ɕt���ꂽ�{�����W�́A���m�̊O�Ϗ�͎��F���邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�E�̂悤�ȃ��m�̗��ʉߒ��ɂ����āA���Ԃ̔̔��Ǝ҂�p�`���R�X�W�҂Ɏ��F�����\�����������B
�@�ȏ�̎����W�̉��ł́A�{�����W�́A�{���b�o�t�����ɑ�������A���̎������m�Ɏ��t����ꂽ��ł����Ă��A�Ȃ��{���b�o�t�ɂ��Ă̏��i���ʋ@�\��ێ����Ă������̂ƔF�߂��邩��A�O�L�N�i�ɌW��퍐�l��̊e�s�ׂɂ��āA���W�@�i�O�L�����O�̂��́j�������̏��W���N�Q�̍߂���������Ƃ����������̔��f�́A�����ł���B
�u�m�e���v������������
�����������R���̐����s�����R��������������������R����B��
�����ԍ��F�@ �@����18�N(�s�P)��10368��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����19�N08��28��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ����@
�����f�[�^�F�@
PAT-H18-Gke-10368.pdf
�@ �O���ɔF�肵���Ƃ���ɂ��A�{�������o��O�̖������Z�p�̈�ʓI�ɂ��ẮA�]���̂q�n����t�e���ł͕������邱�Ƃ��ł��Ȃ����q�ʂP�O�O���琔�P�O�O���x�̕��������邱�Ƃ��ł��閌�����߂��Ă����Ƃ���A���̗v���������̂Ƃ��Ăm�e�����J������A���[�J�[�e�Ђ���Q�O��ނ��鐻�i���̔�����Ă���ɂ���A�b�V�ɂ��ƁA�e�g���A���L���A�����j�E���C�I���ɑ�����e�g�����`���A�����j�E���C�I���̕��q�ʂ͖�X�P�ł��邱�Ƃ��F�߂���̂ł��邩��A�e�g���A���L���A�����j�E���C�I�������邽�߂ɁA�]���̕������ɑウ�Ăm�e�����̗p���Ă݂悤�Ƃ�����x�̂��Ƃ́A���Ǝ҂ɂƂ��ċɂ߂ĕ��ʂ̒��z�ł���Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ɂ��̓_�́A�m�e�����i�ʌ��肷�邱�ƂȂ��m�e����ʂ��\���v���Ƃ���{�������P�ɂ����ẮA�v����ɁA�m�e�������Ƃ��č̗p�����Ƃ����Ɏ~�܂�̂ł��邩��Ȃ�����ł���B�����Ƃ��A�m�e���̓����̂P�Ƃ��ēd�ׂ�L����_���w�E����Ă���A���̓d�ׂ������Ώە����̗L����d�ׂƂ̊W�ŁA���ߐ��ɂ����Ȃ�e�����y�ڂ����ɂ��ẮA�K�������\���ɉ𖾂���Ă��炸�A�@�����������Ă��̉e����\�����邱�Ƃ͍���ȏɂ��������̂ł��邪�A���̓_�́A���O�ɂm�e���̕������ʂ��m�����������ė\������Ƃ����ɂƂǂ܂���̂ł��邩��A�ᕪ�q�ʂ̕�����������ړI�łm�e�����̗p���Ă݂���x�̊�}�ɂƂ��āA��Q�ƂȂ���̂Ƃ܂ł������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA�t�H�g���W�X�g�p�t���̃e�g���A���L���A�����j�E���C�I������ߖ����g�p���ĕ������悤�Ƃ��铖�Ǝ҂��A�]���̖��ɑւ��Ăm�e�����̗p���悤�Ƃ��邱�Ƃ́A�����̎��m�̖������Ɋւ���Z�p���炷��ƁA�i�ʍ���Ȃ��ƂƂ͂����Ȃ�����A�R���̑���_�C�̔��f�͌��Ƃ��킴��Ȃ��B
�U �퍐�́A�{�������P�̑���_�C�ɌW��\���͓��Ǝ҂��e�Ղɑz����������̂ł͂Ȃ��Ǝ咣����B
�@�퍐�̑���ɂ킽��咣�̗v�_�́A�R���Ɠ��l�A�{�������o��O�A���Ǝ҂��e�g���A���L���A�����j�E���C�I���̂m�e���̓��߉\����\�����邱�Ƃ͍���ł������Ƃ����_�ɂ���A���̂悤�ȗ\���\�����Ȃ���m�e�����̗p���悤�Ɠ��@�t�����邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ�����̂ł���B
�@�����Ō�������ɁA�m���ɁA�{�������o��O�ɂm�e�����e�g���A���L���A�����j�E���C�I���߂��邱�Ƃ��w�E�����Z�p�������Ȃ����Ƃ͔퍐�̎咣����Ƃ���ł���B�������A���̂��Ƃ��璼���ɂm�e�����̗p���悤�Ɠ��@�t�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ́A�O���ɐ��������Ƃ���ɏƂ炵�Ė��炩�ł���B�m�e�����L����d�ׂ̉e���������Ώە����̋����ɕ��G�ȉe�����y�ڂ����̂ł���A�e�g���A���L���A�����j�E���C�I���̂m�e���̓��߉\���ɂ��ė\�����邱�Ƃ�����ł������Ƃ��Ă��A���̂悤�Ȏ���́A�m�e���̃e�g���A���L���A�����j�E���C�I���̓��߉\����ے肵�����̂ł͂Ȃ��̂ł��邩��A�m�e���̎��ᕪ�q�ʂ̉������̕����ɋɂ߂ėL���ł���Ƃ����]���̖��ɂȂ���ʓI�����������ɁA�D�ꂽ���ߐ��\�����҂��Ă�������Ƃ��č̗p���Ă݂悤�Ƃ��铮�@�t���̏�Q�ƂȂ���̂ł͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�ȏ�̎���ł��邩��A�m�e�����e�g���A���L���A�����j�E���C�I�������߂��邱�Ƃ̗\��������ł��������Ƃ𗝗R�Ƃ���퍐�̎咣�́A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�u���R�u���b�N�v�������N�Q���~����������
����N�Q�B���������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���Ă��邱�Ƃ����炩�ł���A�ϓ��ł��Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����17�N(�l)��10103��
�������F�@�@�@�@�������N�Q���~�������T�i����
�ٔ��N�����F�@����17�N12��28��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F�@
PAT-H17-ne-10103.pdf
�@�{�������̍\���v���`�́A�u�u���b�N�̕~�ݖʂɐ݂���������v�Ɂu�l�b�g�̌o�����͈��v���u�ʂ��|���ɂ��đ����̃u���b�N���l�b�g�Ɍ����v������̂ł���Ƃ���A��L(3)�J�̂Ƃ���A�{�������́y�����̌��ʁz���ɁA�u�l�b�g�̌o�����͈��Ƀu���b�N�ɐ݂����������ʂ��|���ɂ��đ����̃u���b�N���l�b�g�Ɍ�������\���Ƃ����̂ŁA�{�H�ʂɑ����������ɂ߂ėǍD�ł���A�{�H�ʂ̉��ʂ��z�����Ė����{�H���s�Ȃ��A���L��̎{�H�ʂɑ���u���b�N���H��Ƃ��ɂ߂ėe�Պ��v���ɍs�Ȃ���B�v�ƋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA�L��̎{�H�ʂɑ���u���b�N���H��Ƃ��ɂ߂ėe�Ղ��v���ɍs����Ƃ̌��ʂ́A������Ƀl�b�g�̌o�����͈���ʂ��|������݂̂ő����̃u���b�N���l�b�g�Ɍ������邱�Ƃ��ł���\���Ƃ��Ă��邱�ƂɊ�Â����̂ƔF�߂���B����ɑ��A���R���u���b�N�Ƃ��ėp����ꍇ�ɂ́A���R�̕~�ݖʂɈ������݂��邽�߂ɁA���R�����H���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���A�R���N���[�g�u���b�N�Ƃ͌`��A�d�x���قȂ�A�܂��A���R���Ƃɂ��A�`��A�d�x�A���̑����H��̓������قȂ�̂ŁA������̎�t���@�ɂ����āA�{�������̔����̏ڍׂȐ����ɊJ������Ă���u���b�N���H��ƂƂَ͈��ȋZ�p��K�v�Ƃ��邱�ƂɂȂ�i���P�A�P�R�`�P�T�A�P�X�j�A���̂��߁A�u���b�N�Ɋւ����������p�V�Ă̏o��ɓ������ẮA���Y���������Ȃ����l�Ă����R��ΏۂƂ�����̂ł��邩�ۂ�����������邱�Ƃ������A���R�ƃR���N���[�g�u���b�N�̗�����ΏۂƂ���ꍇ�ɂ����̎|�����L����邱�Ƃ������i�b�R�P�|�P�`�U�A�R�Q�|�P�`�R�A�R�T�|�P�A���Q�O�`�Q�Q�j�B�����̎���ɏƂ炷�ƁA�{�������́u�u���b�N�v�ɐl�H�f�ނ��琬�鐬�`�i�݂̂Ȃ炸�u���R�v���܂߂�̂ł���A���̎|��{�������ɖ��L������ŁA���R���琬��u���b�N�ɑ���u������v�̎�t���@�ɂ��Ă��A�l�H�f�ނ��琬��u���b�N�̏ꍇ�Ƃ͋�ʂ��āA�{�������ɋL�ڂ��ׂ����̂ł���B�Ƃ��낪�A�{�������̔����̏ڍׂȐ����y�і{���}�ʂɁA�u���R�v���u�u���b�N�v�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɐ�������L�̋Z�p�I�����A�Ⴆ�A�ǂ̂悤�Ȏ�@�A�菇�Łu���R�u���b�N�v�̕~�ݖʂɈ������݂���̂����ɂ��ĉ���̋L�ڂ⎦�����Ȃ��B
�i�����j
�@���_�Q�i��T�i�l���i�̍\���́A�{�������̍\���v���`�Ƌϓ����j�ɂ���
(1)�@�T�i�l�́A�{�������̖{���I�����́A�������P�ɋL�ڂ���u�l�b�g�v�Ɂu�u���b�N�v�������ʂ������i�_�����j����\���ɂ��A�s����L����{�H�ʂւ̓���ݕ~�݂��e�Ղł���i�Ǐ����j�A�{�H�ʂ𖧕����A�����ȐA���琬��}��i���j���Ƃ��ł���{�H�ʕ~�݃u���b�N�����_�ɑ����A�u�u���b�N�v���A�u�R���N���[�g�u���b�N�v�Ȃ����u�l�H�f�ނ��琬�鐬�`�i�Ƃ��Ẵu���b�N�v�ł��邩�A�u���R�v�ł��邩�̍ގ��̑���́A�{�������̖{���I�����ɂ͓�����Ȃ��Ƃ��āA��T�i�l���i�́u���R�v�̍\���́A�{�������̍\���v���`�́u�u���b�N�v�Ƌϓ��Ȃ��̂ł���|�咣����B
�@�������Ȃ���A�{�������̍\���v���`�́u�u���b�N�v�́A�R���N���[�g�u���b�N�Ȃǂ̐l�H�f�ނ��琬�鐬�`�i�Ƃ��Ẵu���b�N�ł���A���R�͂���Ɋ܂܂�Ȃ��Ɖ����ׂ��ł��邱�ƁA��T�i�l���i�́A����������R���g�p������̂ł��邩��A�{�������̍\���v���`���[�����Ȃ����ƁA�{�������́A��L�̂Ƃ���l�H�f�ނ��琬�鐬�`�i�ł���u�u���b�N�v���u������v�Ƀl�b�g�̌o�����͈���ʂ��|���ɂ���݂̂ŁA�����̃u���b�N���l�b�g�Ɍ�������~�݃u���b�N���e�Ղɐ�������A�u���b�N���H��Ƃ��ɂ߂ėe�Ղ��v���ɍs���邱�Ƃ��A���̔����̖{���I�����Ƃ�����̂ł��邱�Ƃ́A�O�L�F��̂Ƃ���ł���B�����āA��L�P(6)�G�̂Ƃ���A���H�u���b�N�Ƃ��āA�u�R���N���[�g�u���b�N�v��u���R�v��p���邱�Ƃ́A�{���o�蓖���A���Ǝ҂ɂ����Ď����ł��������Ƃɉ����A��L�P(4)�̂Ƃ���A�u�u���b�N�v�Ɏ��R���܂܂�邩�ɂ��ẮA�{�������̔����̏ڍׂȐ����ɂ��{���}�ʂɂ��A�������������L�ڂ��Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�u���R�v���u�u���b�N�v�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɐ�������L�̋Z�p�I�����ɂ��Ă̋L�ڂ⎦�����Ȃ��A�{�������y�і{���}�ʂɂ́A�u�R���N���[�g�u���b�N�v�y�т���ɗނ���l�H�f�ނ��琬�鐬�`�i�ɌW��Z�p�݂̂��J������Ă���̂ł��邩��A���Ȃ��Ƃ����̓_�͖{�������̖{���I�����Ƃ����ׂ��ł���B
�@�܂��A��L�̂Ƃ���A�u���R�v���u�u���b�N�v�Ƃ��Ďg�p����ꍇ�ɐ�������L�̋Z�p�I�����ɂ��Ă̋L�ڂ⎦�����Ȃ��ȏ�A�u�R���N���[�g�u���b�N�v�y�т���ɗނ���l�H�f�ނ��琬�鐬�`�i�̍\�����A�u���R�v���u�u���b�N�v�Ƃ��Ďg�p����\���ɑウ�邱�Ƃ��e�ՂłȂ����Ƃ́A���炩�ł���B
�@����ɁA�{�������̏�L�L�ڂɂ��A�T�i�l�́A���H�u���b�N�̂����A�u�R���N���[�g�u���b�N�v�y�т���ɗނ���l�H�f�ނ��琬�鐬�`�i���̗p���Ă���̂ł��邩��A�u���R�v����������͈̔͂���ӎ��I�ɏ��O���Ă��邱�Ƃ́A���炩�ł���B
�����W�t�[�h�t�B���^����(�ڋq�ɑ���x���̈�@��)
���{�������́A�����Ƃ����ׂ����̂ł���A�퍐���i�̐����̔����{���������̐N�Q�ł���|�̋��U�̎��������m�A���z����s�ׂ́A�s�������h�~�@��Q���P����P�S���̕s�������s�ׂɊY������B
�@���R�����ɑ��A�ӍߍL���y�ё��Q���������߂錴�R�퍐��̐����͗��R���Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����17�N(�l)��10119��
�������F�@�@�@�@�������N�Q���~����������
�ٔ��N�����F�@����19�N05��15��
�ٔ������F�@ �@�m�I���Y�����ٔ����@
�����f�[�^�F �@
PAT-H17-ne-10119.pdf
�R ���_�T�i���R�������A���R�퍐��ɂ��퍐���i�̐����̔����{���������̐N�Q�ł���|�̋��U�̎��������m�A���z����Ƃ����A�s�������h�~�@�Q���P���P�S���ɊY������s�������s�ׂ��������B�܂��A����ɂ��āA���R�����Ɍ̈Ӗ��͉ߎ������邩�B�j�ɂ���
(1) ��L��Q�̂P��(1)�̎����ɂ��A���R�����ɂƂ��āA���R�퍐��́u�����W�ɂ��鑼�l�v�ɓ�������̂ƔF�߂���B
�܂��A��(7)�̎����ɁA����Q�U�A��Q�W�A��S�X�A��T�O���A��T�R���̂P�A�Q�y�ѕ٘_�̑S��|�𑍍�����A���R�����́A�{���������̓o�^��ł��镽���P�U�N�P�O���ȍ~�A���R�퍐��̔퍐���i�̔���ł�����{���������g���A����A�R�[�v��B���ƘA���A�R�[�v�����ƘA���y�ѐ���ɑ��A���ڏ��ʂɂ��A���͑��҂���āA�퍐���i���{����������N�Q������̂ł���|�̍��m���������Ƃ��F�߂���Ƃ���A��L�P�̂Ƃ���A�{�������ɌW������́A�����R���ɂ����Ė����Ƃ����ׂ����̂ł����āA�퍐���i���{����������N�Q����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@��������ƁA���R�����ɂ���L�s�ׂ́A�s�������h�~�@�Q���P���P�S���̕s�������s�ׂɊY��������̂ƔF�߂���B
�@���������āA���@�R���P���Ɋ�Â��A���̍��~�߂����߂錴�R�퍐��̐����͗��R������B
(2) �������Ȃ���A
���R�����ɂ���L�s�ׂ��A�s�������h�~�@�Q���P���P�S���̕s�������s�ׂɊY��������̂ƔF�߂���̂́A�{�������ɌW��������A�����R���ɂ����Ė����Ƃ����ׂ����̂ł���Ƃ����_�ɂ���B�����āA�������҂ɂ����āA����̎҂̐������镨�i�����Y�������̐N�Q�i�ł���|���O�҂ɑ��x������ꍇ�ɂ́A���̐����҂ɑ��x������ꍇ�Ɣ�ׁA����w�̐T�d�����v�������Ƃ��Ă��A��L�P�̖{�������ɌW�閳�����R�̓��e�ɏƂ炵�A�܂��A��L�Q�̂Ƃ���A�퍐���i�́A�{�������̋Z�p�I�͈͂ɑ�����ƔF�߂��邱�Ƃɂ��݂�ƁA�{���ɂ����ẮA�������҂ł��錴�R��������̓I�Ȗ������R�ɂ��o�莞���͂���ȍ~�ɂ��̑��݂��^���Ē������������邱�Ƃ����҂��邱�Ƃ��ł���悤�Ȏ���͔F�ߓ����A���R�����ɂ���L�s�ׂɂ��A�̈Ӊߎ����������Ƃ܂ł͒����ɔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�Ȃ��A��L��Q�̂Q��(7)�̎����ɏ�f�؋��𑍍�����A���R�����́A��L�s�ׂɂ����āA���{���������g���A����A�R�[�v�����ƘA���Ȃǂɑ����t�������ʂɁA�{�������ɌW������ƁA�{�������o��ɌW����J����i���J���P�P�|�R�O�O�P�R�O���j��Y�t�������Ƃ��F�߂��A���̎����ɂ��A���t�������{���������g���A����́A���R�������A��L���J����L�ڂ̔����ɂ��ē��������擾�������̂悤�Ɍ�F���邨���ꂪ������̂Ɛ��F����邪�A�����ł��邩��Ƃ����āA�{�������ɌW��������A�����R���ɂ����Ė����Ƃ����ׂ����̂ł���Ƃ������R�ɂ��A�퍐���i���{���������̐N�Q�i�ɓ�����Ȃ��Ƃ����_�Ɋւ��錴�R�����̌̈Ӊߎ�����b�t����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
( 3) ���������āA���R�����ɑ��A�ӍߍL���y�ё��Q���������߂錴�R�퍐��̐����͗��R���Ȃ��B�@
�������F�@�@�@�@���쌠�N�Q���~�������T�i����
�ٔ��N�����F�@����13�N06��21��
�ٔ������F�@ �@���������ٔ���
�����f�[�^�F�@
CP-H12-ne-750.pdf�@�@�@�@
CP-H12-ne-750-1.pdf
�@�O�q�����Ƃ���A�{���ʐ^�́A��҂ł���T�i�l�̎v�z���͊���\��Ă�����̂ł��邩��A���앨�����F�߂�����̂ł���A��T�i�l�ʐ^�́A�{���ʐ^�ɕ\�����ꂽ���͈͓̂̔��ŁA���������Αe�G�ɍĐ����͉��ς����ɂ����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B���̂悤�ȍĐ����͉��ς��A���쌠�@��A��@�Ȃ��̂ł��邱�Ƃ͖��炩�Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�@���������āA��T�i�l�a�̍s�ׂ́A����҂ł����T�i�l�̏������͒��쌠�@�̒�߂�K�p���O�K��ɊY�����鎖�R���Ȃ�����A�{���ʐ^�ɂ��čT�i�l���L���铯�ꐫ�ێ�����N�Q������̂ƂȂ�i���쌠�@�Q�O���j�B�Ƃ��낪�A��T�i�l�a�ɂ��A�T�i�l�̏����Ă���Ƃ��A���쌠�@�̒�߂�K�p���O�K��ɊY�����鎖�R������Ƃ��F�߂��Ȃ�����A��T�i�l�a�̍s�ׂ́A�{���ʐ^�ɂ��čT�i�l���L���铯�ꐫ�ێ�����N�Q������̂ł���B
(����)
�V�@�ӍߍL���ɂ����@�٘_�̑S��|�ɂ��A��T�i�l�ʐ^�́A��T�i�l�J�^���O�Ɍf�ڂ��ꂽ�݂̂ł���A�T�i�l���A�Вc�@�l���{�L���ʐ^�Ƌ���̒��쌠�ψ���ɏ�������ʐ^�Ƃ�Ƌ��c���d�˂������A�{�i�𐿋��������̂ł��邱�Ƃ��F�߂��A���̎���̉��ł́A�����ɂ���čT�i�l�̖��_������邱�ƂɂȂ�A���̑��X�ɖ��_�����邽�߂̊i�ʂ̏����𖽂���K�v���͂Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�@�؋��i�b��T���A��P�Q���A��R�T���j�ɂ��A�T�i�l�́A�o�ŗp�H�i�L�����̎ʐ^�Ƃł���A�Ɠ��̎�@�ɂ��A�ʐ^�f���ɂ���ĐH�ނ̂��������A�݂��݂������Ȃǂ�\�����Ƃɏ�M�𒍂��A�䂪���݂̂Ȃ炸�č��ł������]�����Ă���ʐ^�Ƃł��邱�Ƃ��F�߂���B�����āA�{���ʐ^���A�T�i�l�̏�L��@�f�����ʐ^�̈�ł���A���Z�����i���`�[�t�j�Ƃ��āA���Ă̐�̉��ł݂̂��݂��������Z�����o������i�ł������̂ł���B�{���ʐ^���A���}�Ȏʐ^�ɍĐ����͉��ς���Ă��܂����̂ł��邩��A�T�i�l�́A���Ȃ̈ӂɔ����邱�̂悤�ȍĐ����͉��ςɂ���āA���_�����ʑ�����A���_�I�ȑ��Q���������̂ƔF�߂���B�����āA���ς̏y�і{���Ɍ��ꂽ��������l������ƁA�T�i�l�̔�������_�I�ȑ��Q�ɑ���Ԏӗ��Ƃ��ẮA���P�O�O���~�������ł���A�������A��T�i�l��ɘA�ѕ��S������̂������ł���ƔF�߂���B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{���ʐ^�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
��T�i�l�ʐ^
�������F�@�@�@�@���W���N�Q���~����������
�ٔ��N�����F�@����18�N12��22��
�ٔ������F�@ �@�����n���ٔ����@
�����f�[�^�F�@
TM-H17-wa-18156.pdf�@�@
TM-H17-wa-18156-1.pdf
�@�퍐�W�͂T(2)�y�т��̎g�p�ԗl�Ɩ{���o�^���W�Ƃ́A��������O�ρA�ϔO�̑���A���ɊϔO�̑��Ⴊ�傫���A����̎���ɏƂ炵�Ă��o���̌�F�������邨����͔F�߂��Ȃ�����A�̌Ă�����ł��邱�Ƃ��l�����Ă��A�ގ����Ȃ����̂ƔF�߂���B
�i�����j
�@�퍐�W�͂U�y�т��̎g�p�ԗl�Ɩ{���o�^���W�Ƃ́A��������̌āA�ϔO������ł���A�O�ςɂ����ėގ����Ă���B�������A�u�I�V���������́g���u�h�Ɓg�x���[�h�v�̃L�����N�^�[�����m�ł���Ƃ��Ă��A�퍐�W�͂U�ɐڂ����ʏ�̎��v�҂��퍐�W�͂U�̎g�p�ԗl����A�u�I�V���������́g���u�h�Ɓg�x���[�h�v�̃L�����N�^�[�ɊW���邱�Ƃ��Ŏ�ł���Ƃ͔F�߂��Ȃ����A�퍐�Q�[���@�̉ċx�݃L�����y�[���ł̔̔����@���A����Ƃ��i������̔����@�ł���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āA�퍐�W�͂U�y�т��̎g�p�ԗl�́A�{���o�^���W�ɗގ�����ƔF�߂�ׂ��ł���B
�i�����j
�@�ȏ�̂Ƃ���A�퍐�W�͂Q�A�S(1)�A�T(1)�y�тU�́A���̎g�p�ԗl���܂߁A�{���o�^���W�ɗގ����邪�A���̗]�̔퍐�W�͂́A���̎g�p�ԗl���܂߁A�{���o�^���W�Ɨގ����Ȃ��B
�����ݒ�|���Q������������
��
�������̒S���E���̉ߎ��ɂ���������Q�ɂ��āA���Ɣ��������߂邱�Ƃ��ł����B��
�����ԍ��F�@ �@����17�N(��)��541��
�������F�@�@�@�@���Q������������
�ٔ��N�����F�@����18�N01��24��
�@�얼�F�@�@�@�@�ō��ٔ�����O���@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H17-Ju-541.pdf
�@�\���ɂ��o�^�́A��t�̏����ɏ]���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ƃ���Ă���i���߂R�V���P���j�A�������̒S���E�������̒�߂ɔ����Ď�t�̏����ɏ]�킸�A��Ɏ�t�̂��ꂽ���ɑ���������ړ]�o�^�葱���ɂ������߂ɁA��Ɏ�t�̂��ꂽ���ɑ��鎿���ݒ�o�^�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����ꍇ�ɂ́A���́A�������̒S���E���̉ߎ��ɂ��A�{���L���Ɏ擾���邱�Ƃ̂ł����������擾���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������̂ł��邩��A����ɂ���Ĕ�������Q�ɂ��āA���Ɣ��������߂邱�Ƃ��ł���B
�i�����j
�@�㍐�l�ɂ͓������̒S���E���̉ߎ��ɂ��{���������擾���邱�Ƃ��ł��Ȃ��������Ƃɂ�葹�Q�����������Ƃ����ׂ��ł��邩��A���̑��Q�z���F�肳��Ȃ���Ȃ炸�A���ɑ��Q�z�̗����ɂ߂č���ł������Ƃ��Ă��A���i�@�Q�S�W���ɂ��A�����٘_�̑S��|�y�я؋����ׂ̌��ʂɊ�Â��āA�����ȑ��Q�z���F�肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
����L�����̍��ߎ��������B�{�����������܂ނe�r���Ŏ��Ƃ̕]���z�Ƃ��Ă͂R���R�O�O�O���~�ƔF�肵����A����ɑ��A�Z�p�̊�^�x���Q�T���A���������̒��̖{���������̊�^���S���̂P�Ƃ݂����Q�z�ɂ��ĎZ�肵���B��
| �����ԍ� |
�@����18�N(�l)��10008�� |
| ������ |
�@���Q���������T�i�E�����эT�i���� |
| �ٔ��N���� |
�@����21�N01��14�� |
| �ٔ����� |
�@�m�I���Y�����ٔ��� |
�����f�[�^�F�@�@
PAT-H18-ne-10008.pdf
�ٔ����̔��f
�@�Ӓ�̌��ʂɂ��A���Ƃ���̗��v�̂S���̂P�i�Q�T���j���Z�p�̊�^�x�Ƒz�肵�ċZ�p�̉��l�𑪒肷����@�ł��邢����Q�T�����[���Ɋ�Â��āA�{�����������܂ޓ����Ԃɂ��āA�R���R�O�O�O���~�̂Q�T���ł���W�Q�T�O���~�Ƃ����]���z�������邱�Ƃ��F�߂���B
(2) �Ӓ菑�̋L�ڂ̊T�v
�A�@�{���������́A���̋Z�p�I�ی�͈͂����������A���̑�Z�p���o���������߃��C�t�T�C�N�����Z���A�ߋ����Ƃɂ����Ď����I�Ɋ��p���ꂽ�`�Ղ��Ȃ��B���̓_��z������ƁA�{���������̕]���ɂ��ẮA��������A���z���������Ȃ킿�����Ԃ̕]�����s���āA���̌�ɖ{���������̉��l�]�����s���̂������ł���B
�C�@�{���ɂ����ẮA�{�����������܂ނe�r���Ŏ��Ƃ̕]���z����b�ɁA�����Z�p�̏��Ɖ������������ꍇ�A���Ƃ���̎��v�̂S���̂P�i�Q�T���j���Z�p�̊�^�x�Ƒz�肵�āA�Z�p�̉��l�𑪒肷����@�ł���u�Q�T�����[���v���̗p���邱�ƂƂ��A���̑Ó�����ʂ̊ϓ_����m�F���邽�߂ɁA���{���̊ϓ_���猟����B
�E�@�܂��A��L�u�Q�T�����[���v�ɂ��A�{�����������܂ނe�r���Ŏ��Ƃ̉��l�]���z�Ɛ��肳���R���R�O�O�O���~�ɂQ�T�����悶��ƁA�{�����������܂ޓ����Ԃ̕]���z�́A�W�Q�T�O���~�ƂȂ�B
�G�@������A���{�����̊ϓ_���猟����B�܂��A�Ӓ������̗ގ�����ЂP�S�Ђ̔��㑍���v���̕��ς́A���ςłP�R.�P���ł���A���Ƃɂ�������{�����́A�T�˂R������S���̕��Ɛ��肷�邱�Ƃ��ł���B�����ŁA������O��ɁA���㍂�ɑ�����{�����㑍���v�ɑ�����{�����Ɋ��Z���āA���{�������狁�߂���{�����������܂ޓ����Ԃ̕]���z���v�Z����ƁA�V�T�T�V���~�`�P���O�O�U�T���~�Ƃ����]������������B��L�E�̂W�Q�T�O���~�́A���{�����̎��Ԓ������ʂ����ƂɎ��{������L�̕]�����ʂ̕��ɓ�����̂ł���B
�R���������(����)����
���ӏ��o�^�o��̓������ɂ�鋑��R�����ێ��B�{��ӏ��́A�}�ʂ��s����傤���͕s���m�ł��邽�߁A�ӏ�����肵�ĔF�肷�邱�Ƃ��ł����A���܂���̓I�Ȃ��̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����A�ӏ��@�R���P���������ɋK�肷��u�H�Ə㗘�p���邱�Ƃ��ł���ӏ��v�ɊY�����Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@�@ �@�@ �@����18�N(�s�P)��10451��
�������F�@�@�@�@�@�@�@ �@ �R�������������
�����٘_�I�����F�@�@�@�����P�W�N�P�Q���Q�T��
�ٔ������F�@�@ �@�@ �@�@ �m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F�@ �@�@�@�@
DE-H18-Gke-10451.pdf
�@�������o��i�K�̈ӌ�����o���y�ѐR���������ɂ����Ē�o�����Ǝ咣���錻���́C�ӏ��@�U���Q���̂ЂȌ`�C���{�Ƃ��Ē�o���ꂽ���̂Ƃ͔F�߂��Ȃ�����C���̌����Ɋ�Â��{��̈ӏ������肳���Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�����́C�������錩�{�͏��Ȃ��Ƃ��f�B���v�����̌`���c������ꏕ�ɂ͂Ȃ�Ƃ����ׂ��ł���Ǝ咣���邪�C�����{���菑�ɓY�t����}�ʂɑウ�Ē�o���ꂽ���̂ł͂Ȃ��ȏ�C�����{�Ɋ�Â��{��ӏ���F�肷�邱�Ƃ͂ł����C�����̎咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�u���t�ގ��ʑ��u�v����R���������
�������o��̓������ɂ�鋑��R��������B�i��������B��
�����ԍ��F �@�@����17�N(�s�P)��10490��
�������F�@�@�@�@�R�������������
�ٔ��N�����F�@����18�N06��29��
�ٔ������F�@�@ �m�I���Y�����ٔ���
�����f�[�^�F�@
PAT-H17-Gke-10490.pdf
�@�R���́A����_�R�ɂ��āA�u�����f�q�Ŏ��t�ނ̈ꕔ�ɏƎ˂����A���ߌ�������f�q�Ŏ�����ĂȂ�A���t�ގ��ʑ��u�̌��w���o���́A�{��o��O���m�ȋZ�p�����ł���A���p��ɋL�ڂ̔��������t�ނ��������̂ł���A�����f�q�A����f�q�ɂ�莆�t�ނ̓��ߌ������o������̂ł��邩��A���p��ɋL�ڂ̔�������L���m�����ɓK�p���Ď��t�ގ��ʑ��u�̌��w���o���Ƃ��邱�Ƃ́A���Ǝ҂��K�v�ɉ����e�ՂɂȂ����邱�ƂƔF�߂���B�v�i�R�����{�S�ōŏI�i���j�Ƃ���B
�@�������A��L(5)�̂Ƃ���A���t�ނ̐ϑw��Ԍ��m���u�y�ю��t�ގ��ʑ��u�́A�ߐڂ����Z�p����ł���Ƃ��Ă��A���̍��ق�������悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�\���ɂ����āA���t�ނ̐ϑw��Ԍ��m���u�����t�ގ��ʑ��u�ɒu��������̂��e�Ղł���Ƃ������߂ɂ́A����Ȃ�̓��@�t����K�v�Ƃ�����̂ł����āA���p�����y�і{�����m���u�Ƃ��Ɂu���t�ނ��������́v�A�u�����f�q�A����f�q�ɂ�莆�t�ނ̓��ߌ������o������́v�ł���Ƃ������ƂŁA�����ɁA���t�ނ̐ϑw��Ԍ��m���u�����t�ގ��ʑ��u�ɒu�������邱�Ƃ����Ǝ҂ɂ����ėe�Ղł���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(8) �퍐�́A�{�����m���u�ƈ��p�����́A���w���o���̍\�����̂ɍ��ق��Ȃ��A���p�����ɂ����āA���������ɂ킽���Ď��t�ނɓ��߂������\�����A�{�����m���u�ɓK�p�����ɂ����đj�Q�v�����Ȃ��|�咣����B
�@�퍐�̏�L�咣�́A����p������p��������{�����m���u�ɍ����ւ��A����p��Ƃ����{�����m���u�ɑj�Q�v�����Ȃ��Ƃ��Ă�����̂Ǝv���邪�A�R���̗��R�ɂ����āA�u�����f�q�Ŏ��t�ނ̈ꕔ�ɏƎ˂����A���ߌ�������f�q�Ŏ�����ĂȂ�A���t�ގ��ʑ��u�̌��w���o���́A�{��o��O���m�ȋZ�p�����v�i�R�����{�S�ōŏI�i���j�Ɛ������Ă���Ƃ���A�{�����m���u�́A�R���i�K�ɂ����ẮA�O���܂ł��u�{��o��O���m�ȋZ�p�����v�ł����āA�{�蔭���ƑΔ䂳���ׂ����p��Ƃ���Ă����̂ł͂Ȃ��A�܂��āA�{�蔭���Ƃ̑Δ䔻�f�ɌW�錟�����o�Ă����킯�ł��Ȃ��Ƃ���A���̂悤�Ȏ���̉��ŁA�i�גi�K�Ɏ����āA����p��̍��ւ��̎咣���������Ƃ́A�ō��ُ��a�T�P�N�R���P�O����@�씻���E���W�R�O���Q���V�X�ł̔�������R������i�ׂ̐R���͈͂���E������̂Ƃ����ׂ��ł����ċ�����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B�݂̂Ȃ炸�A���ɔ��������Ƃ���A�{�蔭���ƈ��p�����Ƃ́A�������������̉ۑ�y�іړI�����Ⴕ�A����_�P�y�тR�ɌW��{�蔭���̍\�����A���p�����y�і{�����m���u�ɊJ��������������Ă��炸�A������g�ݍ��킹�ē��\���邱�Ƃ̓��@�t��������������B
�@������ɂ���A�퍐�̏�L�咣�́A�����ł���B
�R�������������(�ꎖ�s�ė�)
���ꎖ�s�ė����̋K��̎�|�B��
�����ԍ��F�@ �@����7�N(�s�c)��105��
�������F�@�@�@�@�R��������������i�N�����_���痿����т��̐��@�j
�ٔ��N�����F�@����12�N01��27��
�ٔ������F�@ �@�ō��ٔ�����ꏬ�@��
�����f�[�^�F�@
PAT-H07-Gtsu-105.pdf
�@�����@��Z�����́A�������Ƃ���R���̐����i�ȉ��u�����R�������v�Ƃ����B�j�ɂ��Ċm��R���̓o�^���������Ƃ��́A����̎����y�ѓ���̏؋��Ɋ�Â��Ė����R�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƋK�肷��Ƃ���A���̎�|�́A��������ɂ������R�����������藧���Ȃ��|�̐R���i�ȉ��u�����s�����R���v�Ƃ����B�j���m�肵�A���̎|�̓o�^�����ꂽ�Ƃ��́A���̓o�^�̌�ɐV���ɉE�����R�������ɂ�����̂Ɠ���̎����y�ѓ���̏؋��Ɋ�Â������R�����������邱�Ƃ�������Ȃ��Ƃ�������ł���A������āA�m�肵�������s�����R���̓o�^�ɂ��A���̎��_�ɂ����Ċ��ɌW�����Ă��閳���R���������s�K�@�ƂȂ���̂Ɖ����ׂ��ł͂Ȃ��B���������āA�b�����R�����������ꂽ��ɂ���Ɠ���̎����y�ѓ���̏؋��Ɋ�Â��������R�����������藧���Ȃ��|�̊m��R���̓o�^�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�b�����R���������s�K�@�ƂȂ���̂ł͂Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B
�`�F�������ړ]�o�^��������
���{���ɂ����ẮA�^�̌����҂ł���ɂ�������炸�A���������擾������@���Ȃ��Ƃ����s�����Ȍ��ʂ��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B��
�����ԍ��F�@ �@����13�N(��)��13678��
�������F�@�@�@�@�������ړ]�o�^��������
�ٔ��N�����F�@����14�N07��17��
�ٔ������F�@�@ �����n���ٔ����@
�A�@�������錠���̋��L�҂Ƃ��Ď�������o������Ă��������҂̏o��l���`���A���n�؏����U������Ȃǂ��Ď��ȂɕύX���A�������̎����̐ݒ�o�^�����`�F�҂ɑ��A�����҂����Y�������̎����̈ړ]�o�^�葱�𐿋����������ɂ����āA�ō��ٕ����P�R�N�U���P�Q����O���@�씻���i�ȉ��u�����P�R�N�ō��ٔ����v�Ƃ����B�b�X�j�́A�����҂���̈ړ]�o�^�葱������F�e�����B
�@�{�����ẮA�ȉ��̂Ƃ���A�����P�R�N�ō��ٔ������O��Ƃ��������o�܂Ɠ����ł���A�������̎˒��ɓ�����̂ł��邩��A�������̖@���Ɋ�Â��A�����́A�{���������̈ړ]�o�^�葱��������L����Ƃ����ׂ��ł���B
(����)
�i�ٔ����̔��f�j
�@
�����́A�{�����������ɂ��Ė`�F�o�肪���ꂽ���Ƃ�m������A�x���Ƃ������P�P�N�S���܂ł̊ԂɎ���{�����������ɂ��ē����o������Ă���A�퍐�̂��������o�薔�͍����D�挠�o���r�����邱�Ƃ��ł��A�{�����������ɂ��āA������������擾���邱�Ƃ��ł������̂Ƃ�����B��������ƁA�����ɂ͎���{�����������ɂ��ē��������擾����@��������Ƃ�����B���������āA�{���ɂ����ẮA�^�̌����҂ł���ɂ�������炸�A���������擾������@���Ȃ��Ƃ����s�����Ȍ��ʂ��������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A��O�I�ɓ������̈ړ]�o�^������F�߂Đ^�̌����҂̋~�ς�}��K�v���́A�ɂ߂ĒႢ�Ƃ����ׂ��ł���B
�E�@��L�C�ɏq�ׂ��Ƃ���𑍍�����A�{���͕����P�R�N�ō��ٔ����Ƃ͎��Ă��قɂ���Ƃ������Ƃ��ł��邩��A�����̏�L�咣�͍̗p�ł��Ȃ��B
�����@
���p�V�Ė@
�ӏ��@
���W�@
���쌠�@
�s�������h�~�@
�m�I���Y�����T�C�g�@�s�n�o�y�[�W
�@




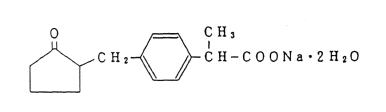
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@