�ԐڐN�Q�s�ׂɂ��Ă̐N�Q�߂̐���
�u�c�`�j�r�v���W����
�t�q�k �E ���h �ɂ�����W�͂̎g�p
��g�p�ɂ�鏤�W�̎g�p�����錠��
���W�@��S���P����10���̋K��̉���
�����R���̐����o�^�O�̎g�p�ɂ�鏤�W�̎g�p�����錠��
���W��p�g�p���N�Q���~����������(�u�ԕ��̂Lj��v����)
�u�C���i�[�g���b�v��F���C���^�[�i�V���i���v����
�s�g�p�ɂ�鏤�W�o�^�̎���R���̎������
�u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�v�s�g�p�����������
�uPAPA�@JOHN'S�v���W�s�g�p�������
�E�������`���̕s���s�̈�@���ɂ���
�u�L���[�s�[�v�}�`���W�R�������������
�u�L�V���g�[���^�w�x�k�h�s�n�k�v���W����
�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v���W�s���g�p�����������
�u�A�C�s�[�t�@�[���v�����R�������������
�ԐڐN�Q�s�ׂɂ��Ă̐N�Q�߂̐���
�����W�@��V�W���ɂ������W���̐N�Q�Ƃ́A���@�R�U���ɂ����N�Q�s�ׂɂƂǂ܂炸�A���@�R�V���̋K��ɂ��N�Q�Ƃ݂Ȃ����s�ׂ��܂ނ��̂Ɖ������B��
| �����ԍ� | �@���a56�N(��)��1596�� |
|---|---|
| ������ | �@���W�@�ᔽ�A�s�������h�~�@�ᔽ�퍐���� |
| �ٔ��N���� | �@���a58�N11��07�� |
| �ٔ������E�� | �@���������ٔ��� ��O�Y���� |
�@���A�@�@�ߓK�p�̌��̎咣�ɂ��āB
�@��A�@���W�@�O�����ɂ����N�Q�Ƃ݂Ȃ��s�ׂ̉����B
�@�_�|�́A�v����ɁA�������́A�������߂ƂȂ�ׂ����đ��̊W�ɂ����āA�퍐��Ђ��g�p�����ʎ��C�A���A�n�A�j�̏��W�ƁA�a�Q�̕ʎ��b��̓o�^���W�Ƃ͏��Ȃ��Ƃ��ގ����W�ƔF�߂���Ɣ��f���A�E�C�A���A�n�A�j�̏��W�̎g�p�s�ׂ͏��W�@�O�����ꍆ�ɊY������Ƃ��āA���@��������K�p���퍐�l������f�������A���@�������ɂ������W���̐N�Q�Ƃ́A���@�O�Z���ɂ����{���̐N�Q�s�ׁA���Ȃ킿�A�����Ȍ������Ȃ��̂ɁA���l�̏��W�o�^�ɂ�����w�菤�i�ɂ��ēo�^���W���g�p���邱�Ƃ������̂ł��āA�o�^���W�ɗގ����鏤�W�̎g�p�s�ׂ̂悤�ɁA���@�O�����ꍆ�ɂ�ď��W���̐N�Q�s�ׂƂ݂Ȃ����ɂ����Ȃ��s�ׂ́A�܂܂�Ȃ��Ɖ����ׂ��ł���B�����N�Q�Ƃ݂Ȃ��s�ׂ��N�Q�߂��\������Ƃ���A���@�O����Z���̂悤�ɖ{���̐N�Q�s�ׂ̗\���̗\���ɑ�������s�ׂ܂ł��{���̐N�Q�s�ׂƓ��l�ɏ������邱�ƂɂȂ�A�����̓_����݂Ă��ɂ߂ĕs���Ȍ��ʂƂȂ���肩�A�ގ����ۂ��̔��f�͑����ɔ��f����҂̎�ςɂ�Ē�܂���̂ł���A�ƍ߂̍\���v���Ƃ��Ċm�肳��Ȃ����̂ł��āA�ߌY�@���`�ɔ�����B�������āA�������ɂ͔����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߂̉��ߓK�p�̌�肪����Ƃ����̂ł���B
�@�����Ō�������ƁA�Ȃ�قǁA���W�@�������́A�u���W���i�����j��N�Q�����҂́A�ܔN�ȉ��̒��͌\���~�ȉ��̔����ɏ�����B�v�ƋK�肷��݂̂ŁA�����Ώۂ̐N�Q�s�ׂ���̓I�ɖ������Ă��Ȃ��̂ŁA�����ɂ����u�N�Q�v�Ƃ́A���W���{���̌��͔͈͂ɑ���N�Q�i�����钼�ڐN�Q�j�������A�N�Q�Ƃ݂Ȃ��s�ׁi���@�O�����A������ԐڐN�Q�j�͊܂܂�Ȃ��Ɖ�������]�n���Ȃ��ł͂Ȃ��B
�@�������Ȃ���A���s���W�@�́A�H�Ə��L�����x�����R�c����a�O��N���l���t�ł������W����W���\�Ɋ�Â��A�����W�@��S�ʓI�ɉ������ď��a�O�l�N�@�������Ƃ��Č��z�{�s���ꂽ���̂ł��邪�A�����W�@�́A�O�l���ɂ����āA���W���̖{���̌��͔͈͂ɑ���N�Q�ł��鑼�l�̓o�^���W�Ɠ���̏��W��̏��i�Ɏg�p�����s�ׁi���ڐN�Q�j�̂ق��A�{���̂悤�ȑ��l�̓o�^���W�Ɨގ��̏��W�ꏤ�i�Ɏg�p�����s�ׁA���̑�����ɂ킽��\���I�s�ׂȂǁA���s�@���O�����ɂ����āu�N�Q�Ƃ݂Ȃ��s�ׁv�i�ԐڐN�Q�j�Ƃ��Ă���s�ׂ̂قƂ�ǂ��Y�������̑ΏۂƂ��Ė������Ă����B�Ƃ��낪�E�̉����ɂ��A���s���W�@�ɂ́A�V���ɍ��~��������N�Q�Ƃ݂Ȃ��s�ׂȂǂ̋K�肪�V�݂���A�����N�Q�Ɋւ���K��̐������Ȃ��ꂽ�W����A�N�Q�߂Ƃ��ċ��@�O�l���e���Ɍf����ꂽ�s�ׂ́A���̂قƂ�ǂ��{���̐N�Q�s�ׂƂ��āA�܂��͐N�Q�Ƃ݂Ȃ��s�ׂƂ��āA���s�@�O�Z������юO�����Ɉڂ����Ƃ���ƂȂ��̂ł���B
�@���̂悤�Ȗ@�����̌o�߂ɒ����čl����ƁA���s���W�@�������ɂ������W���̐N�Q�Ƃ́A���@�O�Z���ɂ����N�Q�s�ׂɂƂǂ܂炸�A���@�O�����̋K��ɂ��N�Q�Ƃ݂Ȃ����s�ׂ��܂ނ��̂Ɖ�����̂������ł���B
�@���̂悤�ɉ����邱�Ƃɂ��A���@�O�����e���̋K�肪�K�p��s���m�ōߌY�@���`�ɔ����邱�ƂɂȂ�Ƃ͎v��ꂸ�A�܂��A�ԐڐN�Q�̗\���I�s�ׂɂ��Ė{���̐N�Q�s�ׂƓ���̔����ɂ�ď��f���邱�Ƃ��A���̎펖�Ƃ��ƂƂ��đ�ʂɁA�p���A�������čs�Ȃ��邱�Ƃ���Ƃ��邻�̓��ꐫ�ɂ��݂�A�����ĕs���Ȃ��ƂƂ͎v���Ȃ��B�����v����ɁA���W�@�O�����ꍆ�̍s�ׂɂ��A���@�������ɊY������Ƃ��ē��@����K�p�����������ɁA���_�̂悤�Ȗ@�ߓK�p�̌��͂Ȃ��A�_�|�͗��R���Ȃ��B
�@��A�@�s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�ɂ����u���l�m���i�g���������[�V�����s�ׁv�̉��߁B
�@�_�|�́A�v����ɁA�������́A�������߂ƂȂ�ׂ��������̊W�ɂ����āA�s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�́u���l�m���i�g���������[�V�����s�ׁv�Ƃ́A�������������̓I�댯�����邩����A�K�����������ɍ����������Ƃ�K�v�Ƃ��Ȃ��Ɖ��߂��ē��@����K�p���f���Ă��邪�A���Ȃ��Ƃ����@��̓K�p���s�Ȃ��ꍇ�ɂ́A�����̍������Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���Ɖ����ׂ��ł��邩��A���̓_�ɂ��������ɂ͔����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȗ@�߉��߂̌�肪����Ƃ����̂ł���B
�@�������A�Y���@�K�Ƃ��Ẳ��߂ɂ����Ă��A�s�������h�~�@����ꍀ�ꍆ�́u���l�m���i�g���������[�V�����s�ׁv�Ƃ́A�������ɂ�����Ƃ���A����҂��ʎ��v�҂����đ��݂̏��i��̂��Ȃ킿���i�̏o��������ł��邩�A�܂��͗��҂ɂȂ�炩�̉c�Ə�̊W������ƌ�F������ɑ����s�ׂ��w�̂��A�������������̓I�댯���������A�K�����������ɍ����������Ƃ�K�v�Ƃ��Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B�������̂��̓_�̔����͑����ł���A�������ɏ��_�̂悤�Ȗ@�߉��߂̌��͂Ȃ��A�_�|�͗��R���Ȃ��B
�@�@�ߓK�p�Ɋւ��邻�̗]�̘_�|�́A��������A���W�̓��ꐫ�Ȃ����ޔۂ̔��f�̌����������̂ŁA���ǂ͎�����F�̎咣�ɋA����Ƃ���A�����̓_�ɂ��Ă͂��łɐ��q�����Ƃ��납�疾�炩�ȂƂ���A�������ɂ��̔��f�̌��͂Ȃ��B
�u�c�`�j�r�v���W����
<�M�p�ʑ��ɂ�閳�`���Q�ƕٌ�m��p�������Q�z��F��B����ɁA�M�p�[�u�����Ƃ��Ă̎ӍߍL����F�߂�B>
| �����ԍ� | �@����19�N(��)��4692�� |
|---|---|
| ������ | �@���W���N�Q���~���������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N03��11�� |
| �ٔ����� | �@���n���ٔ��� |
��Q ���Ă̊T�v��
�@�{���́A��L�̖{�����W���@�A�A��L���錴���_�b�N�X�V���v�\���O���[�v�p�u���b�N���~�e�b�h�J���p�j�[�y�ѓ������ƃ��C�Z���X�_���������A�{�����W���@�ɂ��Đ�p�g�p�����A�{�����W���A�ɂ��ēƐ�I�ʏ�g�p�������ꂼ��L���錴���O������������Ђ��A��L�W�͂�t�����u�p��������p�B�c�`�j�r�Ѓ��o�[�V�u���x���g�v�Ə̂���x���g���؍����A�����A�̔����Ă���퍐�ɑ��A��L�x���g�̗A���E�̔��͌�����̗L����{�����W���@�A�A�y�я�L��p�g�p������N�Q����Ƃ��āA���W�@�R�U���P���A�Q���A�R�V���P���Ɋ�Â��A�����̕W�͂��x���g���ɕt���A���͂����̕W�͂�t�����x���g���̗A���y�є̔��̍��~�ߕ��тɂ����̕W�͂�t�����x���g�̔p�������߁A�����ē��@�R�X���ɂ�菀�p���������@�P�O�U���Ɋ�Â��A�M�p�[�u�����Ƃ��Đ����̎�|��R���L�ڂ̎ӍߍL�������߂�ƂƂ��ɁA�{�����W���@�A�A�y�т��̐�p�g�p������N�Q�����s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����Ƃ��ĂP���U�T�O�O���~�i������̏��W�����N�Q�ɂ�鑹�Q�T�O�O�O���~�A�M�p�ʑ��ɂ�鑹�Q�P���~�y�ѕٌ�m��p�����̑��Q�P�T�O�O���~�j�y�т���ɑ��閯�@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߁A�����O������������Ђ��퍐�ɑ��A�i�O�v�����[�V�~�Y������Ђ����������Q�����������ɌW����Y��̑��Q�S�V���X�W�V�P�~�y�т���ɑ��閯�@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߂����Ăł���B
(���|)
�@���_
�@�ȏ�̂Ƃ���A������̖{�������́A�퍐�ɑ��A�{�����W���y�т��̐�p�g�p���Ɋ�Â��A�퍐�W�͂��x���g���ɕt���A���͂����̕W�͂�t�����x���g���̗A���y�є̔��̍��~�ߕ��тɂ����̕W�͂�t�����x���g�̔p�������߁i�������A�퍐�W�͂Q�A�S�ɂ��Ă͌����_�b�N�X�̂݁j�A�����ď��W�@�R�X���ɂ�菀�p���������@�P�O�U���Ɋ�Â��A�M�p�[�u�����Ƃ��Ď啶��R���f�L�̎ӍߍL�������߁A����ɁA���W���N�Q�̕s�@�s�ׂɊ�Â����Q�����Ƃ��āA�����_�b�N�X�����W���N�Q�̕s�@�s�ׂɊ�Â����Y��̑��Q�S���U�R�P�X�~�y�т���ɑ���i�B�̓��̗����ł��镽���P�X�N�T���R������x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߁A�����O�����������W���N�Q�̕s�@�s�ׂɊ�Â����Y��̑��Q�S���U�R�P�X�~�ƁA�v�����[�V�~�Y�����������Q�����������ɌW����Y��̑��Q�R�P���V�Q�R�S�~�̍��v�R�U���R�T�T�R�~�y�т��̂����S���U�R�P�X�~�ɑ���i�B�̓��̗����ł��镽���P�X�N�T���R������A�R�P���V�Q�R�S�~�ɑ���i���̕ύX�\�������B�̓��̗����ł��镽���P�X�N�P�Q���Q������A�e�x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������߁A�����炪�M�p�ʑ��ɂ�鑹�Q�Q�O�O���~�ƕٌ�m��p�����̑��Q�T�O���~�̍��v�Q�T�O���~�y�т���ɑ���i�B�̓��̗����ł��镽���P�X�N�T���R������x���ς݂܂Ŗ��@����̔N�T���̊����ɂ��x�����Q���̎x�������ꂼ�ꋁ�߂���x�ŗ��R�����邩�炱���F�e���A���̗]�͗��R���Ȃ����炱������p���邱�ƂƂ��āA�啶�̂Ƃ��蔻������B
�t�q�k �E ���h �ɂ�����W�͂̎g�p
| �����ԍ� | �@����15�N(��)��11661�� |
|---|---|
| ������ | �@���W���N�Q���~�� |
| �ٔ��N���� | �@����18�N04��18�� |
| �ٔ����� | �@���n���ٔ��� |
�@�퍐���A�����P�S�N�S���P�O���܂Ŕ퍐�̃z�[���y�[�W�ɂ����āA�퍐�W�͂Q�i���[�ł�j�A�퍐�W�͂U�i�x���������j�A�퍐�W�͂P�R�i�r�����x���������j�̊e�W�͂�p���Ă����s�ׂ́A���W�@�Q���R���W������́A���i�Ɋւ���L������e�Ƃ�����ɕW�͂�t���ēd���I���@�ɂ�����s�ׂɊY������B
�@�����A�퍐�����̂t�q�k�Ɂu�����������v�Ȃ镶�����p�������Ƃ��A���W�Ƃ��Ă̎g�p�ɊY�����邩�ۂ��͑���������B
�@���W�̖{���́A���Ȃ̉c�ƂɌW�鏤�i�𑼐l�̉c�ƂɌW�鏤�i�Ǝ��ʂ��邽�߂̕W���Ƃ��ċ@�\���邱�Ƃɂ��邩��A�o�^���W�Ɠ��ꖔ�͗ގ��̏��W�̎g�p�����W���̐N�Q�ɂȂ�Ƃ������߂ɂ́A��O�҂̎g�p���鏤�W���P�Ɍ`���I�ɏ��i���ɕ\������Ă��邾���ł͑��肸�A���ꂪ�������i�̎��ʕW���Ƃ��Ă̋@�\���ʂ����ԗl�ŗp�����Ă��邱�Ƃ�v����Ɖ����ׂ��ł���B
�@�퍐�̂t�q�k�ɂ�����u�����������v�Ȃ镶����̎g�p�ԗl�́A�h���C�����ɂ�����g�p�ł͂Ȃ��A�퍐�ɗ^����ꂽ�h���C�����i�Ⴆ�A�uesuroku.co.jp�v�j������U��ꂽ�T�[�o�[�ɃA�N�Z�X���A�����Łuunder�v�ȂǂƂ����f�B���N�g�����ɂ���ugoods�v�ȂǂƂ����f�B���N�g���̒��́uyodel_a.html�v�ȂǂƂ����t�@�C�����擾���ău���E�U�ɕ\�����邽�߂̕�����̕\���ł���A���̉�ʏ�̕\�������������Ȃ��̂ł���B�����Ƃ��A�t�q�k�ɗp����ꂽ�����A���̂t�q�k�ɂ���ĕ\��������ʂɕ\�����ꂽ���i�Ȃ����Ɗ֘A���镶����ł���Ɖ{�������҂��F��������ꍇ�ɂ́A���Y�t�q�k�̕�����ɂ�����g�p���A���W�Ƃ��Ă̎g�p�ɊY������ƍl����]�n�͂���B�������A�O�L�F��̂Ƃ���A�{���ɂ����Ė��ƂȂ��Ă���z�[���y�[�W�̉�ʂ́A�����W���i�̎ʐ^�⌻���W���f�ڂ���A���邢�́A�V���W���i�̎ʐ^���f�ڂ���A�V���W���\������Ă�����̂ł���̂ŁA�퍐�W�͂V�Ɋi�ʂ̎��m��������Ƃ͔F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��{���ɂ����ẮA�����̉�ʂ��{�������҂��A�t�q�k�̔퍐�W�͂V�i�����������j�����āA��ʂɌf�ڂ���Ă���퍐���i�̎��ʕW���i�W�́j�ł���ƔF������Ƃ͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA�{���ɂ����ẮA�t�q�k��\������E�B���h�E�Ɂuyodel�v�Ȃ镶�����p�������Ƃ́A���W�Ƃ��Ă̎g�p�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�uyodel.gif�v�Ȃ镶������A����������҂́A���l�ɒP�Ȃ�t�@�C����\�����邽�߂̕�����ɂ����Ȃ��ƔF������̂ł��邩��A����������z�[���y�[�W�ɕ\�����Ă��A���W�Ƃ��Ă̎g�p�ɂ͊Y�����Ȃ��B
�@����ɁA�퍐�̋Ɩ������̖��h�Ɂu�x�n�c�d�k �c�h�d�s�v�i�퍐�W�͂Q�P�j�Ƃ̋L�ڂ��������_�ɂ��ẮA���W�@�Q���R���W���̍L���I�g�p�ɊY�����邩�ۂ������ƂȂ�B�������A�{���Ŗ��ƂȂ��Ă��閼�h�ɂ͔퍐�W�͂Q�P���P�Ƃŗp�����Ă���ɂ������A��`���哙�̋L�ڂ��Ȃ����Ƃɂ��A���W�͂��퍐���i�Ɋւ��ĕt���ꂽ���̂ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�܂��A�{���ɂ����ĔF�肷�邱�Ƃ��ł��閼�h�̎g�p�ԗl�́A��L�F��̂Ƃ���A�����P�S�N�U���P�X���ɁA�����E�R���@���������ɂ�����ʒk�̍ۂɁA�퍐�Ɩ������̂b���u�x�n�c�d�k �c�h�d�s�v�̕W�͂��L�ڂ��ꂽ���h����t�����Ƃ������̂ł��邪�A���ꂪ�퍐���i�̐�`�L���̂��߂ɖ��h���g�p���ꂽ�ꍇ�ɊY�����Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A���̑��A�퍐���i�̍L����`�̂��߂ɖ��h���g�p���ꂽ�ƔF�߂�ɑ����I�m�ȏ؋��͂Ȃ��B�܂��A����������L�̑ԗl�̖��h�͎�����ނɊY�����Ȃ��B���������āA��L���h�ɂ�����퍐�W�͂Q�P�̎g�p�́A���W�Ƃ��Ă̎g�p�ɊY�����Ȃ��B
��g�p�ɂ�鏤�W�̎g�p�����錠��
�����W�@��R�Q���P���̋K��ɂ����u���v�҂̊ԂɍL���F������Ă���Ƃ��v�y�сu�p�����Ă��̏��i�ɂ��Ă��̏��W�̎g�p������ꍇ�v�̉��߁B��
| �����ԍ� | �@����1�N(��)��11631�� |
|---|---|
| ������ | �@���~�������s���݊m�F |
| �ٔ��N���� | �@����3�N12��20�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
���@���Ă̊T�v
��@�����̂Ȃ�����
�P�@�퍐�́A�o�^�ԍ����Z���Z�l�������W���i�{�����W���B���̓o�^���W�i�{���o�^���W�j�̍\���́A�ʎ����W����L�ڂ̂Ƃ���B�j��L���Ă���B
�Q�@�퍐�́A�������핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɕʎ��W�͖ژ^�P�Ȃ����R�L�ڂ̕W�́i�����W�́j���g�p����s�ׂɂ��āA�����ɑ��A�{�����W���Ɋ�Â����~��������L����|�咣���Ă���B
��@���_
�P�@�����W�͂��{���o�^���W�ɗގ����邩�ۂ��B
�Q�@�������A���W�@�O����ꍀ�̋K��Ɋ�Â��A��g�p�ɂ�錴���W�͂��g�p���錠����L���邩�ۂ��B
(���|)
�T�@�����́A�E�S�i��j�Ȃ����i�O�j�̐�`�L���������Ȃ���A�����W�͂�t�����u�[���_�v�u�����h�̔핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނ�̔����A���a�l�N��ꌎ�Ɂu�[���_�v�u�����h�\���Ă��瓯�܌ܔN�����܂ł̊ԂɁA��~�̔�����v�サ�A�܂��A���������ɂ́A�u�[���_�v�u�����h�̉E���i�̔̔��̂��߂ɁA���S�ݓX�𒆐S�ɒ��c�X���X�܋y�уt�����`���C�Y�X�X�܂��o�X����܂łɎ������i�ؐl�y�a�z�A�٘_�̑S��|�j�B
�U�@�����āA�����́A���̌���A��L�V�i�O�j�̂Ƃ���A�������N�Ɂu�[���_�v�u�����h���u�l�`�q�h�j�n�@�j�n�g�f�`�v�u�����h�ɕύX����܂ŁA�����W�͂�t�����u�[���_�v�u�����h�̔핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނ�̔����Ă��Ă���A���������ɂ́A�u�[���_�v�u�����h�̉E���i�̔̔��̂��߂ɁA���S�ݓX�𒆐S�ɒ��c�X�l�l�X�܋y�уt�����`���C�Y�X�O��X�܂��o�X���Ă����i�b���A�b��O�A�b��l�A�b��܂̈�Ȃ����O�A�ؐl�y�a�z�j�B
(����)
�i�O�j�@�Ƃ���ŁA�����́A�����W�͂̎g�p���p�����邱�Ƃɂ���āA�퍐�炩��S�ݓX���̑��̎���擙�ɑ��Č����W�͂̎g�p�𒆎~����悤�x���������Ȃǂ��āA����擙�ɖ��f�������邱�Ƃ����O���A�����W�͂̎g�p���ꎞ���~���������ŁA���̕����̉����ɓ����邱�Ƃɂ����B�����ŁA�����́A���a�Z�O�N����A�u�����h�����u�[���_�v����u�l�`�q�h�j�n�@�j�n�g�f�`�v�ɕύX���邱�Ƃ�m�点�鈥�A����쐬���āA����������y�ьڋq���ɔz�t���A�������N�ȍ~�́A�u�l�`�q�h�j�n�@�j�n�g�f�`�v�̃u�����h�����g�p���Ă��邪�A�E���������������Ƃ��ɂ́A�핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɌ����W�͂��g�p����ӎv��L���Ă���A���̂��߂ɁA���N�㌎�l���A�{���i�ׂ��N�����i����A�ؐl�y�a�z�j�B
�O�@�E��P�Ȃ����T�̔F�莖���ɂ��A�����́A������Ѓu���[�j���̖{���o�^���W�ɌW�鏤�W�o�^�o��̓��ł��鏺�a�܌ܔN�����l���O����A���{�����ɂ����āA�s�������̖ړI�łȂ��A�E���W�o�^�o��̎w�菤�i�͈̔͂ɑ�����핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɂ��Č����W�͂̎g�p�����Ă������ʁA�E���W�o�^�o��̍ہA���ɁA�����W�͂������̋Ɩ��ɌW�鏤�i��\��������̂Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă�����̂ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B�����Ƃ��A���O��ɂ��A�O�N�Ԃ̕��ϗ��v�����Z���ȏ�̍����v���f�B�X�A�p�����l�Z�Ёi�������܂ށB�j�̓��l�N�ɂ����鑍���㍂�̍��v�́A�l�Z���Z�Z���~�ł��邱�Ƃ��F�߂���Ƃ���A�E��T�̔F�莖���ɂ��A���N��ꌎ���瓯�܌ܔN�����܂ł̊Ԃ́u�[���_�v�u�����h�̏��i�̔��㍂�͖�~�ł��邩��A��~�̔��㍂�́A�E�̃��f�B�X�A�p�����l�Z�Ђ̓��l�N�ɂ����鑍���㍂�̍��v�z�ɔ䂵�ċ͏��ł���Ƃ��킴������Ȃ����A�E��S�y�тT�̔F�莖���ɂ��A�E�̂Ƃ���A�����W�͂́A�{���o�^���W�ɌW�鏤�W�o�^�o��̍ہA���ɁA�����̋Ɩ��ɌW�鏤�i��\��������̂Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă�����̂ƔF�߂���Ƃ���ł����āA�u�[���_�v�u�����h�̏��i�̔��㍂���E�̃��f�B�X�A�p�����l�Z�Ђ̓��N�ɂ����鑍���㍂�̍��v�z�ɔ䂵�ċ͏��ł��邱�Ƃ������ẮA���̔F������E����ɑ���Ȃ��B�܂��A���O��ɂ��A������Ж��o�ό��������A�S���̏����X��Z�Z�Z�X�܂ɁA������s���Ă��郁�[�J�[�A�≮�̂��ׂẴu�����h�̕]�������Ă��炢�A������W�v�����u�W�P�N�Ń��f�B�X�u�����h�̋����͒����v�Ƒ肷����i���ܘZ�N�l����ܓ����s�j�ɂ́A�����̃u�����h�Ƃ��āA�u�j�R���v�Ɓu�}�_���E�j�R���v���f�ڂ���A�u�[���_�v���f�ڂ���Ă��Ȃ����Ƃ��F�߂��邪�A�E��S�y�тT�̔F�莖���ɂ��A�E�F��̎����́A�����W�͂��A�{���o�^���W�ɌW�鏤�W�o�^�o��̍ہA���ɁA�����̋Ɩ��ɌW�鏤�i��\��������̂Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă���Ƃ̑O�F������E����ɂ͑���Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����āA�E��U�y�тV�̔F�莖���ɂ��A�����́A�{���o�^���W�ɌW�鏤�W�o�^�o��̓��ł��鏺�a�܌ܔN�����l�����畽�����N�܂ł̊ԁA�u�[���_�v�u�����h�̔핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɌ����W�͂̎g�p�����Ă������A�����ȍ~�́A�u�����h�����u�l�`�q�h�j�n�@�j�n�g�f�`�v�ɕύX���āA�����W�͂̎g�p�𒆎~���Ă�����̂ł���Ƃ���A�����������W�͂̎g�p�𒆎~�����̂́A����̔��ӂɂ��̂ł͂Ȃ��A������Ѓu���[�j���炩��A�������핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɌ����W�͂��g�p����s�ׂ͖{�����W���̐N�Q�ɂȂ�Ƃ��āA�����W�͂̎g�p�𒆎~����悤�x���������߁A�����W�͂̎g�p���p�����邱�Ƃɂ���āA�퍐�炩��S�ݓX���̑��̎���擙�ɑ��Č����W�͂̎g�p�𒆎~����悤�x���������Ȃǂ��āA����擙�ɖ��f�������邱�Ƃ����O�������Ƃɂ����̂ł���A�����́A�{�����������������Ƃ��ɂ́A�핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɌ����W�͂��g�p����ӎv��L���Ă���̂ł���B��������ƁA�����́A�E�̂悤�ȑ����ȗ��R�Ɋ�Â��A���A���̌��x�ɂ����āA�����W�͂̎g�p���ꎞ���~���Ă���ɂ����Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł����āA���̂悤�ȏꍇ�́A���W�@�O����ꍀ�̋K��ɂ����u�p�����Ă��̏��i�ɂ��Ă��̏��W�̎g�p������ꍇ�v�ɊY��������̂Ɖ�����̂������ł���B
�l�@���������āA�����́A��g�p�ɂ�錴���W�͂��g�p���錠����L���邩��A�������핞�A�z���g��i�y�ѐQ��ނɌ����W�͂��g�p����s�ׂ́A�{�����W���̐N�Q���\�����Ȃ��B
���W�@�@��R�Q���i��g�p�ɂ�鏤�W�̎g�p�����錠���j
�P ���l�̏��W�o�^�o��O������{�����ɂ����ĕs�������̖ړI�łȂ����̏��W�o�^�o��ɌW��w�菤�i�Ⴕ���͎w����͂����ɗގ����鏤�i�Ⴕ���͖ɂ��Ă��̏��W���͂���ɗގ����鏤�W�̎g�p�����Ă������ʁA���̏��W�o�^�o��̍ہi�����̎l�̋K��ɂ��A���͑�\�����̓��ꍀ�Ⴕ���͑�\���̓��O���i��Z�\���̓��ɂ����ď��p����ꍇ���܂ށB�j�ɂ����ď��p����ӏ��@��\�����̎O��ꍀ�̋K��ɂ��A���̏��W�o�^�o�肪�葱������o�������ɂ������̂Ƃ݂Ȃ��ꂽ�Ƃ��́A���Ƃ̏��W�o�^�o��̍ۖ��͎葱������o�����ہj���ɂ��̏��W�����Ȃ̋Ɩ��ɌW�鏤�i���͖�\��������̂Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă���Ƃ��́A���̎҂́A�p�����Ă��̏��i���͖ɂ��Ă��̏��W�̎g�p������ꍇ�́A���̏��i���͖ɂ��Ă��̏��W�̎g�p�����錠����L����B���Y�Ɩ������p�����҂ɂ��Ă��A���l�Ƃ���B
���W�@��S���P����10���̋K��̉���
�����W�@��S���P����10���̋K��ɂ����u���v�҂̊ԂɍL���F������Ă��鏤�W�v�̉��߁B��
| �����ԍ� | �@���a57�N(�s�P)��110�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@���a58�N06��16�� |
| �ٔ����� | �@���������ٔ��� |
�Q�@�����g�p�̂c�b�b�̕\����p�������W�̎��m���̐���
�@�����ɑ����̂Ȃ��b��O���̎O�l�A�O�܋y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�R�[�q�[�́A���̌��ޗ��ł���R�[�q�[�����䂪���ŎY�o���邱�Ƃ��ł����A���ׂėA���i�Ɉˑ����Ă���A���̍���□�o�͕i��ɂ�����������A�����ł���F�����r�҂�����������@�ɂ��قȂĂ�����̂ł��邪�A�������ƓI�ȋi���X�݂̂Ȃ炸�H���A���X�g�����A�O������ʂł��c�Ɨp�ɋ�����A��ʉƒ�ł������y�ɏ�����n�D�i�ł����āA�S���I�ɗ��ʂ��A�n��I�n�D�������i�ʔF�ߓ���i�ł��邱�Ƃ��F�߂���B�������A�������i���Ǝ��̌��ޗ��̓Ɛ�A�����������������@�A���������Ă܂��A����Ɋ�Â����ƍۗ������Ɠ��̕����������Ēm���Ă���Ƃ̗����Ȃ��B
�@�������S���I�ɗ��ʂ������g�p�̈�ʓI���i�ɂ��āA���W�@��l���ꍀ���Z�����K�肷��u���v�҂̊ԂɍL���F������Ă��鏤�W�v�Ƃ����邽�߂ɂ́A���ꂪ���o�^�̏��W�ł���Ȃ���A���̎g�p�����ɂ��݁A��ɏo�肳��鏤�W��r�����A�܂��A���v�҂ɂ������F�����̂����ꂪ�Ȃ����̂Ƃ��āA�ی������̂ł��邱�Ƌy�э����ɂ����鏤�i���ʂ̎��ԋy�эL���A��`�}�̂̌����Ȃǂ��l������Ƃ��A�{���ł́A���W�o�^�o��̎��ɂ����āA�S���ɂ킽���v�����̓��폤�i�戵�Ǝ҂̊Ԃɑ������x�F������Ă��邩�A���邢�́A�����Ƃ��ꌧ�̒P�ʂɂƂǂ܂炸�A���̗אڐ����̑����͈͂̒n��ɂ킽���āA���Ȃ��Ƃ����̓��폤�i�戵�Ǝ҂̔��ɒB������x�̑w�ɔF������Ă��邱�Ƃ�v������̂Ɖ����ׂ��ł���B
�@������ɁA�O�L�F�莖���ɂ��A�����̎g�p�ɂ���Ăc�b�b���A��Ƃ��Đ�ƓI�ȋi���X���͂��߂Ƃ��铖�Y�p���I�����̑������̎戵�Ǝ҂̊ԂŁA�����̉c�ƂȂ��������戵���̃R�[�q�[���̏��i��\��������̂Ƃ��ĔF������Ă������Ƃ������������邯��ǂ��A���̎�Ȕ̔��n��ł���L�������ł���ƓI�ȋi���X���ɑ�������L���͍��X�O�Z�p�[�Z���g���x�ɉ߂����A�����ɑ����̂Ȃ�����܍��Ȃ����掵���ɂ�ĔF�߂���E�ȊO�̈�ʓI�ȐH���A�O�����A���X�g�������̑��݂����l������ƁA�c�b�b�������̋Ɩ��ɌW�鏤�i��\��������̂Ƃ��ĔF�����Ă������폤�i�戵�Ǝ҂̔䗦�͍X�ɉ��܂����̂Ƃ���˂Ȃ炸�A�אڌ��ł���R�����A���R�����ɂ����邻���̔䗦�͗y���ɍL�����ɋy�Ȃ����̂ł��邩��A���W�@��l���ꍀ���Z���ɋK�肷��悤�Ȏ��v�҂̊ԂɌ����̋Ɩ��ɌW�鏤�i��\�����鏤�W�Ƃ��čL���F������Ă������̂Ƃ܂ł͂�����B
�@���������āA�{�����W�����̓o�^�o����O�Ɍ����̉c�ƂɌW�鏤�i���������W�Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă����Ƃ͔F�߂��Ȃ��Ƃ����R���̔��f�Ɍ��͂Ȃ��A���̔F�莖����O��Ƃ��āA�����咣�̖������R�̑��݂�ے肵���R���ɁA��@�̓_�͂Ȃ��B
���W�@��S���i���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����W�j
��P���@���Ɍf���鏤�W�ɂ��ẮA�O���̋K��ɂ�����炸�A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@��10���@���l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�Ⴕ���͖�\��������̂Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă��鏤�W���͂���ɗގ����鏤�W�ł��āA���̏��i�Ⴕ���͖��͂����ɗގ����鏤�i�Ⴕ���͖ɂ��Ďg�p���������
�����F�@���W�@��32���P���ɂ�������m���́A�g�p�p����F�߂��|�����n���ɂ�������m�ł����Ă��悢�Ɖ������B����A���W�@��S���P����10���ɂ�������m���́A�����͈͂̒n��ɂ����Ď��m�ł��邱�Ƃ����߂��A���W�@��32���P���ɂ�������m�̒��x�����������̂ł��邱�Ƃ��K�v�ł���Ɖ������B
�����R���̐����o�^�O�̎g�p�ɂ�鏤�W�̎g�p�����錠��(���p��)
���u��H�e�v���W�ɂ��ẮA���W�@��33���̎g�p����L���邪�A�u�̂������v���W�ɂ��ẮA��g�p���A���p���Ƃ��F�߂��Ȃ��B��
| �����ԍ� | �@���a43�N(�l)��1937�� |
|---|---|
| ������ | �@���������ߐ\������ |
| �ٔ��N���� | �@���a47�N03��29�� |
| �ٔ����� | �@��㍂���ٔ��� |
��A������Ƃ���T�i�l�͉E�T�i�l���W����сu�̂������v���W���g�p���錠��������Ƃ��āA�悸���W�@�O����ꍀ�̐�g�p�����A���ɓ��@�O�O���ꍀ�̒��p�����咣����̂ŁA�悸��g�p���̎咣�ɂ��l����ɁA��T�i�l�̗L����{�����W�̏o����͏��a�O�O�N������Z���ł��邩��A�T�i�l�咣�̐�g�p���̐��ۂ͏��W�@�{�s�@�l���ɂ��E���a�O�O�N������Z�����ݎ{�s����Ă��������W�@����ꍀ�ɂ�蔻�肷�ׂ����̂ł���Ƃ���A���@���ɂ́u���l�̓o�^���W�m�o�^�o��O�������ꖔ�n�ގ��m���i�j�t�L����Җ��n���v�҃m�ԃj�L�N�F���Z�����^�����ꖔ�n�ގ��m�W�̓��P�Ӄj�g�p�X���҃n���m���l�m���W�m�o�^�j�S���Y���m�g�p���p���X���R�g�����A�c�Ɩ��n�Ɩ��g���j���m�W�̓m�g�p�����p�V�^�����m�����W�v�ƋK�肹���Ă���̂ŁA���@������̗v���̗L������������ɁA���R�ɂ�����T�i�l��Б�\�҂`�{�l�q��̌��ʂɂ��^���ɐ��������ƔF�߂鉳���Ȃ����O���A��܂Ȃ��������A�攪���̈�A��A���Ȃ������A���O�Ȃ������A��l�O�Ȃ����l�܍��̊e�L�ڂ���ѓ��R�ؐl�b�A�c�A�d�A�e�̊e�،����тɑO�o�`�{�l�q��̌��ʂ̒��ɂ́A�吳�����A�����͏��a��l�N�A���a�N�����Ȃ킿�O�L���a�O�O�N������Z���ȑO�Ɏēc�Ő����i�����͍T�i�l��Аݗ��O�ł���B�j�ŋe�̌`���������R���َq�������̖����́u��H�e�v�u�̂������v�ł������|�̋��q�i�܂��͋��q�L�ځj�������U�����邪�A����݂̂ɂ�Ă͖����E�`�܂��͂��̐��̌l�c�Ǝ���̎ēc�Ő��������فu��H�e�v���T�i�l���W�܂��́u�̂������v���W���g�p���Đ����̔����Ă����ƔF�߂�ɂ͑��肸�A�E�u��H�e�v�����́u�̂������v�̏��W�������s���ӂɂ����Ĉ�ʏ���҂܂��͐��ًƎҁi���Ȃ킿�O�L�@���ɂ������v�҂܂��͎���ҁj�ԂɎ��m����Ă����Ƃ͂Ȃ��X�F�ߓ�A�T�i�l���T�i�l���W���g�p���Ė��فu��H�e�v�̔̔����X�I�Ɏn�߂��͔̂�T�i�l���F�߂�Ƃ��菺�a�O���N��Z��������ł���A��i�F��̂Ƃ���A����������s���ӂ̋ƎҁA����ҊԂɎ��m���ꂽ�̂����̍�����ł���Ƃ���˂Ȃ�Ȃ��B
�@����T�i�l�ɂ����Ă��̋Ɩ������F�����ƔF�߂���`�i�T�i�l�̂�����@�l����̎咣�ɑ��锻�f�͌�ɒ��p���̎咣�ɂ��Ĕ�������Ƃ���ł���B�j���A�T�i�l�̌��ݎg�p���̍T�i�l���W�i�����ɑ����̂Ȃ��b��Z���̈�A��A�O�̃C�A���A�l�̂Ƃ���ł���ƔF�߂�B�j�A�u�̂������v���W�i�E�b��Z���̎O�̃C�̂Ƃ���ł���ƔF�߂�B�j�Ɠ���̋Ǝ҂܂��͏���ҊԂɎ��m���ꂽ���W���T�i�l�̖{�����W�o��O����g�p���Ă����Ƃ̎����͍T�i�l�̑S���ɂ���Ă������F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����O����g�p�̍R�ق͂��łɂ��̓_�ɂ����Ď����ł���B
�@�݂̂Ȃ炸�O�L�����W�@����ꍀ�i���s���W�@�O��������|�j�Ɋ�Â���g�p�ɂ���Đ�g�p���̔F�߂��鏤�W�́A���l�̓o�^�o��O����g�p����Ă������W�Ɠ���̏��W�Ɍ���ꂱ��ɗގ�����ɂ����ʏ��W�͊܂܂�Ȃ��Ɖ����ׂ��Ƃ���A�O�o�`�{�l�q��̌��ʂɂ��ΉE���a�O�O�N������Z���ȑO�Ɍl�c�Ǝ���̎ēc�Ő������g�p���Ă����Ƃ����u��H�e�v���W�͕��ʂ̍s���̂ł������Ƃ����̂ł����āA����ƌ��ݍT�i��Ђ��g�p���̑O�L�b��Z���̈�A��A�O�̃C�A���A�l�Ɍ��o����Ă���T�i�l���W�̈��Ɠ��̏��̂Ƃ̊Ԃɂ́A���̂�S���قɂ��Ă��鑊�Ⴊ���邱�Ƃ��F�߂��邵�A���ȏ����́u�̂������v���W�ɂ��Ă��E�b��Z���̎O�̃C�Ɍ��o����Ă�����قȏ��̂ƍT�i�l�����Ďg�p���Ă������W������\��������̂Ƃ��Ē�o���Ă��鉳�攪���̓�́u�̂������v�̕��}�ȏ��̂̊Ԃɂ͂��Ȃ�̑���̂��邱�Ƃ��F�߂��邩��A�T�i�l�����ݎg�p���̏��W�Ə]�O�g�p���Ă����Ƃ������W�Ƃ͑O���̈Ӗ��ɂ����铯�ꏤ�W�Ƃ͂�����T�i�l�̐�g�p�̍R�ق͂��̓_�ɂ����Ă��̗p����B
�O�A�����Ői��Œ��p���̎咣�ɂ��čl����ɁA�T�i�l�����ݎg�p���́u��H�e�v���W�i�T�i�l���W�j�͍T�i��Б�\������`�����a�O���N����������Z��Z�A��Z�ꍆ�������ēo�^���Ă������̂ł���Ƃ���A��T�i�l���������ɂ��̖����R���𐿋����i���a�O��N�R�����Z�l�����j���a�l��N�㌎��Z���E�����ǂ���̖����R��������A�E�`�͓��������ٔ����ɉE�R������̑i���N�����i�������a�l��N�i�s�P�j���l�j���������p�̔��������n����m�肵�����Ƃ͓����ҊԂɑ������Ȃ��A�E�����R���̐����̓o�^�����a�O��N�l���O���{�����������s���Ȍ�ł��邱�Ƃ͔�T�i�l�̎��F����Ƃ���ł���A�����ȑO�i���a�O���N��Z�����ȍ~�j����T�i�l���E�u��H�e�v�̍T�i�l�o�^���W��p���ĉَq�̐����̔����Ă��邱�Ƃ͓����ҊԂɑ������Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��T�i�l�́A�T�i�l�̉E��Z��Z�A��Z�ꍆ���W�̎g�p�͂��̏��W���҂`�̎g�p�Ɠ��ꎋ��������̂ł���Ƃ��āi��j�Ȃ����i�l�j�̗��R�����I�Ɏ咣���Ă���̂ł��̒��́i��j������@�l����̎咣�ɂ��čl����ɁA�O���`�{�l�q��̌��ʂɂ���ɂ��^���ɐ��������ƔF�߂��鉳���㍆�A��l�܍��ɂ��A�ēc�Ő����͉E�`�̑c���f��������Z�N���َq�̐����̔����n�߂������s�̘V�܂œ��a�A�O��`�Ƒ������l��Ƃł������ŗ��m�g�̂����߂Őŋ���̈��a�O�Z�N�O����������̍T�i�l��Ёi�����͂`�̌l��Ёj��ݗ����ē��l����\������ƂȂ�l�c�Ǝ���̈�̍��������p���]���Ɠ����c�Ƃ𑱂��Ă�����̂ł����āA���̉c�Ƃ̎��Ԃɂ����Ă͌l�c�Ǝ���ƑS������ł��邱�Ƃ��F�߂�ꂱ��ɔ�����؋��͂Ȃ��B
�@�E�̂悤���l��Ƃ����̎��Ԃ̓��ꐫ��ۂ��܂ܖ@�l�i���擾�����l��Ђɂ����āA���W���҂ł��邻�̑�\������̊Ǘ��A�ē̉��ɓ��Y���W���g�p����Ă����ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A���W���҂ł����\������ɂƂ��Ă����Ȃ̏��W��P�ӂŎg�p���Ă�����̂Ƃ��ď��W�̌p���g�p�A�M�p�ێ��ׂ̈̒��ӂ������Ă����Ɛ��F�ł��邩��A���l�����W���҂Ƃ��ĉE�l��Ђƕ������ɂ�閾���̏��W���g�p�����_�����������������Ȃ��Ƃ��Ă��A���Y���W���̎����I�Ȏg�p�����_�����ƔF�߂�ɖW���Ȃ��Ƃ����ׂ��A���p�����x�̎�|�ɏƂ炷�ƍT�i��Ђ̑O�L��Z��Z�A��Z�ꍆ���W�̎g�p�͏��W���҂`�̎g�p�Ɠ������č��x�Ȃ����̂Ɖ�����𑊓��Ƃ���B
�@�����đO�i��f�L�̊e�؋��ɕ٘_�̑S��|�ɂ��^���ɐ��������ƔF�߂��鉳��O�l�Ȃ����l�Z��������A�T�i�l�͏��a�O���N��Z���ȍ~������Ɠw�͂Ƌ��Ƀ��a�I���Ő�`������A�V���L���ŏЉ�ꂽ��A����܂����肵�����ƂƑ��܂��āA�O�L���a�O��N�l���������̐����ɂ����铍�R���َq�u��H�e�v�͕��Ɍ����������������n���ɂ����Ă͐��ًƎ҂݂̂Ȃ炸��ʏ���ҊԂɂ����m����Ă������ƁA�T�i�l�͓�����T�i�l���{�����W��L���邱�Ƃ�m�炸�E�u��H�e�v�̐����̔��ɓw�߁A�E���a�O��N�����ɂ����Ă͂��̔��オ�T�i�l���̔��㍂�̎��Z�Ȃ������Z�p�[�Z���g�ɒB���X�ɔ����L���ׂ��w�͒��ł��������Ɠ��̎������F�߂邱�Ƃ��ł��邩��A�T�i�l�̑��̑���I�Ȏ咣�ɑ����f������܂ł��Ȃ��T�i�l�͏��W�@�O�O���ɂ��E�u��H�e�v���W�̎g�p����L������̂ł���B
�@�������Ȃ���A���ȏ����́u�̂������v���W�ɂ��Ă͑O�L���a�O��N�l�����T�i�l�ɂ��g�p����Ă����ƔF�߂�ɑ���؋����Ȃ������ɁA�����W�ƑO�L��Z��Z�A��Z�ꍆ�u��H�e�v���W�Ƃ͏̌Ă���ъϔO�����ʂɂ���ގ����W�Ƃ͔F�߂��邪�A��҂Ɠ���Ȃ����͓��ꐫ�̂��鏤�W�Ƃ͔F�ߓ�i���̓_�̍T�i�l�̎咣�͍̗p����B�j�̂ʼnE�u�̂������v�ɂ��Ă͒��p���̎咣�������ł���B
�l�A���Ă݂�Α�Z��Z�A��Z�ꍆ�u��H�e�v���W�ɂ��Ă͍T�i�l�̂��̗]�̎咣�ɑ��锻�f���Ȃ��܂ł��Ȃ����̍��~�����͎����ł���A�{���������͓����W�Ɋւ��邩����������Ƃ�Ȃ����A���ȏ����́u�̂������v���W�ɂ��Ă͍T�i�l�̐�g�p���A���p���͂Ƃ��ɔF�߂��Ȃ��̂ŁA���i�̎��R�̑a���Ȃ�������{���������͂��̕K�v����������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
��R�R���i�����R���̐����o�^�O�̎g�p�ɂ�鏤�W�̎g�p�����錠���j
�P ���̊e���̈�ɊY������҂���l�\�Z���ꍀ�̐R���̐����̓o�^�O�ɏ��W�o�^�������e���̈�ɊY�����邱�Ƃ�m��Ȃ��œ��{�����ɂ����Ďw�菤�i�Ⴕ���͎w����͂����ɗގ����鏤�i�Ⴕ���͖ɂ��ē��Y�o�^���W���͂���ɗގ����鏤�W�̎g�p�����A���̏��W�����Ȃ̋Ɩ��ɌW�鏤�i���͖�\��������̂Ƃ��Ď��v�҂̊ԂɍL���F������Ă����Ƃ��́A���̎҂́A�p�����Ă��̏��i���͖ɂ��Ă��̏��W�̎g�p������ꍇ�́A���̏��i���͖ɂ��Ă��̏��W�̎g�p�����錠����L����B���Y�Ɩ������p�����҂ɂ��Ă��A���l�Ƃ���B
�_�_�F�@���p���ƃp�����S��B�Ƃ̊W
�@�����@��W�O���A���W�@��R�R���Ȃǂ̂����钆�p���̋K�肪�p������S��B�̋K��ɔ�����̂ł͂Ȃ����Ƃ̖�肪���邽�߁A�D�挠���Ԓ��ɂ��ꂽ�o��ɂ��Ă̓����E�o�^�������Ƃ��ꂽ�ꍇ�ɂ́A������@�ɗD�悵(���@��X�W���Q���A�����@��Q�U��)�A���p�����������Ȃ��Ɖ�����ׂ��ł���B
���W��p�g�p���N�Q���~����������(�u�ԕ��̂Lj��v����)
| �����ԍ� | �@����14�N(��)��10522�� |
|---|---|
| ������ | �@���W��p�g�p���N�Q���~���������� |
| �ٔ��N���� | �@����15�N06��27�� |
| �ٔ����� | �@�����n���ٔ��� |
��Q�@���Ă̊T�v
�@�@�{���́A���W���҂���o�^���W�ɂ������Ɛ�I�ʏ�g�p���̋������A�����Ő�p�g�p���̐ݒ�����������A�퍐�ɑ��A�퍐���ʎ��퍐�W�͖ژ^�P�Ȃ����R�L�ڂ̕W�́i�ȉ��A�u�퍐�W�͂P�v�ȂǂƂ����A�������āu�퍐�W�́v�Ƒ��̂���B�j���̂Lj��ɕt���āA�����̔��W��������s�ׂ͌����̓Ɛ�I�ʏ�g�p���Ȃ�����p�g�p����N�Q����Ǝ咣���āA��p�g�p���Ɋ�Â��̔��W�����̍s�ׂ̍��~�ߋy�я��i�̔p�������߂�ƂƂ��ɑ��Q�����i�������Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ł��������Ԃ̕����܂ށB�j�����߂Ă��鎖�Ăł���B
�@�퍐�́A����ɑ��āA�@�@�퍐�W�͓͂o�^���W�ɗގ����Ȃ��A�A�@�퍐�W�͂͏��i�̌��\�A�p�r���ʂɗp��������@�ŕ\��������̂ł���A���W���̌��͂͋y�Ȃ��i���W�@�Q�U���P���Q���j�A�B�@��������p�g�p���̐ݒ����Ɏ������o�ߓ��ɏƂ点�A�����̔퍐�ɑ��錠���s�g�͌����̗��p�ɓ�����ȂǂƎ咣���āA�����̐����𑈂��Ă���B
(���|)
�E�@�퍐�W�̗͂v��
�@�퍐���i���̂Lj��ł��邱�ƂɏƂ点�A�퍐�W�͂̂����u�̂Lj��v�̕����́A�W�͂̕t���ꂽ���Y���i�̓��e�A�������������ʖ��̂ł��邩��A�������i���ʋ@�\��L���Ȃ������ł���B�܂��A�퍐�W�͂R�̂��������́u�Q�v�́A�����ł����āA���i���̖����ɕt���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�ʏ�A���҂Ȃ������ǐ��i���ł��邱�Ƃ��������̂ł���A���ꎩ�̂Ƃ��Ă͎������i���ʋ@�\��L������̂ł͂Ȃ��B
�@�����A�퍐�W�͂̂����u�ԕ��v�̕����ɂ��ẮA�퍐���i�̑�����A�̂Lj��Ȃ����L�����f�B�[�̕���ɂ����āA�ʏ�A���i�̌��ޗ�����\�E�p�r���Ӗ������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@��������ƁA�퍐�W�͂ɂ����ẮA�u�̂Lj��v�Ȃ����u�̂Lj��Q�v�̕������������u�ԕ��v�̕������������i���ʋ@�\��L���镔���Ƃ��āA����҂̒��ӂ��Ђ������Ƃ����ׂ��ł���B
�@��L�̂Ƃ���A�퍐�W�͂ɂ����ẮA�u�ԕ��v�̕����������ėv���Ƃ������Ƃ��ł���B
(3)�@�{���o�^���W�Ɣ퍐�W�̗͂ޔ�
�A�@�{���o�^���W�ɂ����ẮA�����Łu�ԕ��v�Əc�P��ɑ发�������������W���̑傫�ȕ������߁A�E���ɏ������łӂ肪�ȗl�ɂЂ炪�ȁu���ӂ�v���L�ڂ��������Ɣ�ׂāA����҂̒��ӂ����������ƔF�߂���B
�@ �����A�O�L�̂Ƃ���A�퍐�W�͂́A�c�����P�͉������P��Ɂu�ԕ��̂Lj��v�Ȃ����u�ԕ��̂Lj��Q�v�ƋL�ڂ������̂ł���A�����̂����v���ł���u�ԕ��v�̕����́A�퍐�W�͂P�A�Q�ɂ����Ă͊����̌`��₻�ꂪ���������ł���_�ňقȂ�A�܂��A�퍐�W�͂Q�A�R�ɂ����ẮA�����P��ɋL�ڂ���Ă���_�ňقȂ邪�A��������u�ԕ��v�̕����̋L�ڂ�����_�ɂ����Ė{���o�^���W�Ƌ��ʂł���B�@
�@�����āA�퍐�W�͂ɂ����Ă͑O�L�̂Ƃ���u�ԕ��v�̕������������i���ʋ@�\��L����v���Ƃ����ׂ��Ƃ���A���Y�����́A�{���o�^���W�Ə̌ċy�ъϔO������ł���B
�@��L�ɂ��A�퍐�W�͂́A�{���o�^���W�ƊO�ςɂ����ėގ����A���̗v���̏̌āA�ϔO������ł��邩��A��������{���o�^���W�ɗގ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�C�@���̓_�Ɋւ��āA�퍐�́A�@�@�퍐�W�͂ɂ����Ắu�ԕ��v�̕����Ɓu�̂Lj��v�̕���������̑傫���y�я��̂ł���A���Ԋu�Ŕz��Ă��邩��A�u�ԕ��v�̕����Ɓu�̂Lj��v�̕����Ƃɕ������ĂƂ炦��ׂ��ł͂Ȃ��A�u�ԕ��̂Lj��v�Ƃ�����̂̂��̂Ƃ��Ĕc�����ׂ��ł���A�A�@���̂悤�ȗ����ɂ��A�퍐�W�͂���́u�ԕ��ǂɌ����̂Lj��v�Ȃ����u�ԕ��Ǒ��p�̂Lj��v�Ƃ����ϔO��������ȂǂƎ咣����B
�@�������A���W�̗v���̔F��ɓ������Ă͊O�ς݂̂���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ���A�{���ɂ����ẮA�O�L�̂Ƃ���퍐�W�͂̂����u�̂Lj��v�̕����͎������i���ʋ@�\��S�������Ȃ������ł��邩��A�u�ԕ��v�̕����Ɏ������i�̎��ʋ@�\��F�߂���Ȃ����̂ł���A�܂��A�퍐�W�͂��O�ςɂ����āu�ԕ��v�ȊO�̕��������Ɍ���҂̖ڂ��Ђ��悤�ȍ\���ƂȂ��Ă���킯�ł��Ȃ�����A�u�ԕ��v�̕�����퍐�W�̗͂v���ƔF�߂��ŖW���ƂȂ���̂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�؋��i���P�V�A�T�T�A�U�S�Ȃ����U�V�A�U�X�Ȃ����V�T�A�W�P�j�ɂ��u�r�o�`�I�v�A�u�҂��v�Ƃ�������ɂ����āA�����P�O�N���납��ԕ��Ǒ�̏��i�Ƃ��ă}�X�N��_��̂ق��A�L�����f�B�[�i�̂Lj��j��K���Ȃǂَ̉q�ނ��A��y�ɉԕ��Ǒ���s�����Ƃ̂ł���@�\���H�i�Ƃ��ďЉ��L�����f�ڂ���A���̌㌻�݂܂ŁA���N�A�ԕ��ǂ̋G�߂ł���Q����R������ɔ���������ɁA�u�ԕ��V���b�g�v�A�u�ԕ��{�܁v�Ƃ������W�͂�t�����ԕ��Ǒ��p�̈��Ȃǎ�X�̏��i���f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��F�߂��邪�A�u�ԕ��̂Lj��v�̌ꂪ�A�u�ԕ��ǂɌ����̂Lj��v�Ȃ����u�ԕ��Ǒ��p�̂Lj��v���Ӗ�����P�̓Ɨ�������Ƃ��Ĉ�ʓI�Ɏg�p����Ă������Ƃ܂ł͔F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@����ɁA�؋��i���S�A�R�S�A�S�X�A�T�O�A�T�P�j�ɂ��A�����P�S�N�W�����납��A�ԕ��ǜ늳�҂�ΏۂƂ����E�F�u�T�C�g��ɂ����āA�u�ԕ��̂Lj��v�̌ꂪ�u�ԕ��Ǒ��p�̂Lj��v�̈Ӗ��ŗp����ꂽ�Ⴊ����A�ԕ��ǜ늳�҂��E�F�u�T�C�g��̌f���Ɂu�ԕ��̂Lj��v�̌��|�ŗp�������͂̏������݂����Ă���Ⴊ���݂��邱�Ƃ��F�߂���B�������Ȃ���A�����A�؋��i���S�U�Ȃ����S�W�j�ɂ��A�S�����ʂ��ẴX�M�ԕ��ǂ̜늳���͂P�T�`�P�U���ɂƂǂ܂���̂ł��邱�Ƃ��F�߂�����̂ł���A�����̎���ɏƂ点�A�u�ԕ��̂Lj��v�̌ꂪ�u�ԕ��Ǒ��p�̂Lj��v���Ӗ�������̂ł���ƈ�ʓI�ɔF������Ă���Ƃ܂ł͔F�߂��Ȃ��B
�@���������āA�u�ԕ��̂Lj��v����̂Ƃ��ĂƂ炦�Ė{���o�^���W�Ƃ̊O�ρA�̌āA�ϔO�̗ޔۂf����ׂ��ł���Ƃ̔퍐�̎咣�́A�̗p�ł��Ȃ��B
�@�@����ɁA�퍐�́A�u�ԕ������v�̍\������Ȃ�W�͂ŁA���W�o�^���Ȃ���Ă�����̂������邱�Ƃ������āA�{���o�^���W�Ɣ퍐�W�͂Ƃ̔�ގ����咣���Ă��邪�A�퍐�̌f����u�ԕ������v�Ƃ����o�^���W�́A��������u�����v�ɓ����镔���ɁA�u�Ƀ~���g�v�A�u�̋G�߁v�A�u�r�s�n�o�v�A�u�u���b�N�v�A�u���߂̂�����v�A�u���ӕ�v�A�u�x��v�A�u�O���v�Ƃ����A���ꂾ���ł͈Ӗ����Ȃ����A�u�ԕ��v�Ƃ�����ƌ��т��Ĉ��̈Ӗ�����ꂩ�A���邢�͑Ώۏ��i�̓��e���Ƃ͖��W�Ȍꂪ�u����Ă�����̂ł���B���������āA�����̓o�^���W��������Ƃ��Ă��A�u�ԕ��v�̌�ɑ����đΏۏ��i���ꎩ�̂ł���u�̂Lj��v�̌ꂪ�t����Ă���퍐�W�͂ɂ��āA�{���o�^���W�Ɨގ�����Ƃ̔��f���W��������̂ł͂Ȃ��B
�E�@�ȏ�̂Ƃ���A�퍐�̎咣�͂�������̗p�ł��Ȃ��B
�Q�@���_�Q�i�퍐�W�͂͏��i�̕��ʖ��́A���\�A�p�r�A�g�p�̎����ʂɗp��������@�ŕ\�����鏤�W�ɓ����邩�j�ɂ���
�@�O�L�P(3)�C�ɂ����ĔF��̂Ƃ���A�u�r�o�`�I�v�A�u�҂��v���̏�ɂ����āA�����P�O�N���납��ԕ��Ǒ�̏��i�Ƃ��ăL�����f�B�[�i�̂Lj��j��K���Ȃǂَ̉q�ނ��A��y�ɉԕ��Ǒ���s�����Ƃ̂ł���@�\���H�i�Ƃ��ďЉ��L�����f�ڂ���A���̌㌻�݂܂ŁA���N�A�ԕ��ǂ̋G�߂ł���Q����R������ɔ���������ɁA�u�ԕ��V���b�g�v�A�u�ԕ��{�܁v�Ƃ������W�͂�t�����ԕ��Ǒ��p�̈��Ȃǎ�X�̏��i���f�ڂ���Ă��邱�Ƃ��F�߂��A�܂��A�����P�S�N�W�����납��A�ԕ��ǜ늳�҂�ΏۂƂ����E�F�u�T�C�g��ɂ����āA�u�ԕ��̂Lj��v�̌ꂪ�u�ԕ��Ǒ��p�̂Lj��v�̈Ӗ��ŗp����ꂽ�Ⴊ���݂��邱�Ƃ��F�߂��邪�A�u�ԕ��̂Lj��v�̌ꂪ�A�u�ԕ��ǂɌ����̂Lj��v�Ȃ����u�ԕ��Ǒ��p�̂Lj��v���Ӗ������Ƃ��āA��ʓI�ɔF������A�g�p����Ă���Ƃ܂ł͔F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�܂��A�O�L�P(2)�A�ɂ����ĔF�肵���퍐�W�͂̎g�p�ԗl�ɏƂ点�A�퍐�W�͂P�A�Q�́A�퍐���i�̑�܂̕\���������y�ї����㑤�̂��ꂼ��ڂɂ������ɑ发����Ă�����̂ł����āA�u���ʂɗp����������@�ŕ\������v���̂Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B
�@��L�ɂ��A�퍐�W�́i�u�ԕ��̂Lj��v�j�Ȃ������̂����́u�ԕ��v�������A�u�w�菤�i�̕��ʖ��́A���\�A�p�r����\�����鏤�W�v�i���W�@�Q�U���P���Q���j�ɓ�����Ƃ���퍐�̎咣�i�R�فj�́A�̗p�ł��Ȃ��B
�i�����j
(2)�A�@�������p�̎咣�ɂ���
�@�O�L(1)�ŔF�肵�������ɂ��A�����́A���i���Ƃ��āu�ԕ��̂Lj��v��p���邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�u�j�����������^�ԕ��̂Lj��v�̏��W�o�^�o����������A���̉ߒ��Ŗ{���o�^���W�̑��݂�m��A�{���o�^���W�̏��W���҂ł���M�B�I���{�܂Ƃ̊ԂŃ��C�Z���X�擾�̌����s���A�����Ɛ�I�ʏ�g�p���̋������A�����Ő�p�g�p���̐ݒ���āA�퍐�ɑ��Čx�����𑗕t���A���̌�A�{���i�ׂ��N�������̂ł���B���̂悤�Ȍo�܂ɏƂ点�A�����̖{�i��N�́A�{���o�^���W�̏��W���҂��琳���Ȍ������擾���Ă̌����s�g�ł����āA�����̗��p�ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@��L�ɂ��A�����̖{�i��N���������p�ɓ�����Ƃ̔퍐�̎咣�i�R�فj�́A�̗p�ł��Ȃ��B
�C�@�M���@�P�P���ᔽ�̎咣�ɂ���
(�A)�@�����́A�퍐�̐M���@�P�P���ᔽ�̎咣�́A�����٘_���I������i�K�Ɏ����Ă��̂悤�Ȏ咣��������̂ł���A���@�Ɍ�ꂽ���̂Ƃ��ċp�����ׂ��ł���Ǝ咣����B
�@�m���ɁA�퍐�̏�L�咣�́A�٘_�����葱�I����A�٘_�I�����\�肳��Ă�����T������٘_�����ɂ����ď��߂Ď咣���ꂽ���̂ł���A���@�Ɍ��Ē�o���ꂽ���̂Ƃ����ׂ��ł��邪�A�퍐�̏�L�咣�́A�ȉ��̂Ƃ��肱��܂ł̐R���̌��ʂɂ��e�Ղɔ��f�ł��邩��A�i�ׂ̊�����x����������̂ł͂Ȃ��B�����ŁA��L�咣�ɂ��ẮA������p�����邱�ƂȂ��A���f�������B
(�C)�@�M���@�P�P���́A�傽��ړI�Ƃ��đi�s�ׂ������邽�߂ɍ��Y�̊Ǘ����������ړ]���邱�Ƃ��֎~���Ă��邪�A��L(1)�ŔF�肵���o�܂ɏƂ点�A�����́A����u�ԕ��̂Lj��v�̕W�͂��g�p���邽�߂ɑ����̑Ή����x�����ĐM�B�I���{�܂���Ɛ�I�ʏ�g�p���̋����A�����Ő�p�g�p���̐ݒ���āA���ۂɏ�L�W�͂�t�����������i��̔����Ă�����̂ł���A�܂��A�{���i�ׂɂ��Ăٌ͕�m�ł���i�ב㗝�l�ɈϔC���A���㗝�l�������٘_�����ɏo�����đi�ׂ�Ǎs���Ă�����̂ł���B�����̓_�ɏƂ点�A�M�B�I���{�܂ɑ����Ĕ퍐�ɑ���i�s�ׂ��s�����Ƃ��傽��ړI�Ƃ��āA�������M�B�I���{�܂����p�g�p���̋��������̂ł���Ƃ͓���F�߂��Ȃ��B
�@��L�ɂ��A�������M�B�I���{�܂����p�g�p���̐ݒ�������Ƃ��M���@�P�P���Ɉᔽ���A�����ł���Ƃ̔퍐�̎咣�i�R�فj���̗p�ł��Ȃ��B
�i�����j
(2)�@�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ɂ�鑹�Q���������̋���
�A�@�ʏ�g�p���҂́A���l�̓o�^���W�̎g�p�ɑ��Ă͏��W���Ɋ�Â������s�g�����Ȃ��|�̍��ӂ����W���Җ��͐�p�g�p���ҁi�ȉ��u���W���ғ��v�Ƃ����B�j�Ƃ̊Ԃœ��āA���W���ғ��ɑ��ē��Y���ӂɊ�Â����I��������L������̂ł���A�Ɛ�I�ʏ���{���҂́A����ɉ����đ��҂ɓ��Y�o�^���W�̎g�p���������Ȃ��|�̍��ӂ����W���ғ��Ƃ̊Ԃœ��Ă�����̂ł���B
�@�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂́A���W���ғ��ɑ��Č_��Ɋ�Â����I��������L����ɂ����Ȃ����A���W�@�͏��W���ғ��ɑ��ēo�^���W�̐�p����ۏႵ�Ă���i���W�@�Q�T���A�R�U���j�A���W���ғ��́A�_���Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ɑ��ē��Y�o�^���W��B��g�p������n�ʂ��O�҂Ƃ̊W�ł��m�ۂ��ׂ��`�����Ă�����̂ł��邩��A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂́A���̂��Ƃ�ʂ��āA���Y�o�^���W��Ɛ�I�Ɏg�p���A������g�p�������i���s��Ŕ̔����邱�Ƃɂ�闘�v��Ɛ�I�ɋ�����n�ʂɂ�����̂ƕ]�����邱�Ƃ��ł���B
�@���̂悤�ɓƐ�I�ʏ�g�p���҂��_���̒n�ʂɊ�Â��ēo�^���W�̎g�p�����L���Ă���Ƃ���������Ԃ����݂��邱�Ƃ�O��Ƃ���A�Ɛ�I�ʏ���{���҂����̎�����ԂɊ�Â��ċ��闘�v�ɂ��Ă��A���̖@�I�ی��^����̂������ł���B���Ȃ킿�A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂����ɏ��W���ғ�����B�ꋖ�������҂Ƃ��ē��Y�o�^���W��t�������i������s��ɂ����Ĕ̔����Ă���ꍇ�ɂ����āA�������̑�O�҂����Y�o�^���i���g�p�����������i���s��ɂ����Ĕ̔����Ă���Ƃ��ɂ́A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂́A�ŗL�̌����Ƃ��āA���瓖�Y��O�҂ɑ��đ��Q�����𐿋���������̂Ɖ�����̂������ł���B�����āA���̏ꍇ�A���Y��O�҂��A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ɂ�铖�Y���i�̎s��ɂ�����̔���F��������ɂ��������̂ł���A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ɑ���W�ɂ����Ă��A���W�@�R�X���ɂ��ߎ������肳�����̂Ɖ�����̂������ł���B
�@�����Ƃ��A���@�R�W���P���Ȃ����R���̋K��́A���W���ғ����o�^���W�̎g�p�����I�����Ƃ��Đ�L���A���l�ɑ��Ă�����Ɋ�Â�����������s�g���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���W���ғ��̌����s�g��e�ՂȂ炵�߂邽�߂ɐ݂���ꂽ�K��ł��邩��A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂̑��Q�ɂ��Ă����̋K���ސ��K�p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���������āA�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂́A��O�҂̐N�Q�s�ׂƑ������ʊW�ɂ���͈͂̑��Q�ɂ��A���̔����𐿋����邱�Ƃ��ł���ɂƂǂ܂���̂Ɖ�����̂������ł���B
�C�@�{���ɂ����ẮA�O�L�����ҊԂɑ����̂Ȃ������i��Q�A�P(2)�C�j�̂Ƃ���A�����́A�����P�R�N�W���P���A�M�B�I���{�܂Ƃ̊ԂŁA�{���o�^���W�ɂ��g�p�����_�������������̂ł���Ƃ���A���_�i�b�Q�j�ɂ����ẮA���W���҂ł���M�B�I���{�܂́A�����ɑ��āA�������g�p���鏤�W�̑ԗl���u�ԕ��̂Lj��v�Ǝw�肵�A�g�p���i���u�L�����f�B�v�Ƃ��Ēʏ�g�p�����������Ă��邪�i���_��P���j�A���W���҂́A�O�L�g�p���i�i�L�����f�B�[�j�ɂ����ẮA�{���o�^���W���O�҂Ɏg�p�������Ȃ��|����߂��Ă���i����T���j����A�����́A�{���o�^���W�ɂ��A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ł������ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B
�@�����āA�؋��i�b�T�̂P�A�Q�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�����́A�����P�R�N�P�Q������A�{���g�p�����_��ɏ]���A�u�ԕ��̂Lj��v�̏��W��t�����̂Lj��i�L�����f�B�[�B�������i�j������̔����Ă������̂ł���A�������i�Ɣ퍐���i�Ƃ͓����e�̏��i�Ƃ��Ďs��ɂ����ċ������Ă������̂ƔF�߂���B
�@�������Ȃ���A�؋��i�b�W�A���S�S�A�S�T�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�t���䐻�ق́A�����P�S�N���߂��납��u�ԕ��̂Lj��v�̕W�͂�t�����̂Lj��i�L�����f�B�[�j��̔����Ă����Ƃ���A�M�B�I���{�܂́A�����Ƃ̊Ԃ̏�L�g�p�����_��i��T���j�Ɉᔽ���āA�x���Ƃ������P�S�N�S���܂łɁA�t���䐻�قɑ��āA�T�O���~�̎g�p���ŁA���N�W�������܂Ŗ{���o�^���W�̎g�p���������i���̂��Ƃ́A�������g���i��P�T�łɂ����Ď��F���Ă���B�j�A����Ɋ�Â��ďt���䐻�ق́u�ԕ��̂Lj��v�̕W�͂�t�����̂Lj��i�L�����f�B�[�j���s��ɂ����Ĕ̔����Ă������Ƃ��F�߂���B��������ƁA�����͏��W���҂Ƃ̊ԂŖ{���o�^���W�ɂ��Ɛ�I�ʏ�g�p���̋�������|�̌_�������������̂́A���_��ɂ�鋖�����Ԃɂ����āA���ۂɂ͖{���o�^���W�͋��Ƒ��Ђɑ��Ă��g�p��������A���Ђɂ��{���o�^���W��t�������i���s��ɂ����Ĕ̔�����Ă����̂ł��邩��A�{���ɂ����ẮA�����́A���W���ғ�����B�ꋖ�������҂Ƃ��Ė{���o�^���W��t�������i���s��ɂ����Ĕ̔����Ă����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�O�q�̂Ƃ���A�Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ɌŗL�̑��Q������������F�߂�ɂ��Ă��A����͓Ɛ�I�ʏ�g�p���҂��_���̒n�ʂɊ�Â��Ď�����{���o�^���W�̎g�p�����L���Ă���Ƃ���������Ԃ����݂��邱�Ƃ�O��Ƃ�����̂ł���Ƃ���A�{���ɂ����ẮA�����͂��̂悤�ȑO����������̂ł���B���������āA���̂悤�Ȍ������Ɛ�I�ʏ�g�p���̐N�Q�𗝗R�Ƃ��đ��Q�����𐿋����邱�Ƃ͋�����Ȃ��B
�E�@��L�ɂ��A�Ɛ�I�ʏ�g�p���̐N�Q�𗝗R�Ƃ��錴���̑��Q���������͊��ɗ��R���Ȃ����̂ł��邪�A�����āA�{���ɂ����ẮA�퍐���퍐���i���s��ɂ����Ĕ̔��������Ƃɂ��A�������ʊW�͈͓̔��ɂ����Č�������������Q���m�肷�邱�Ƃ��s�\�ł��邩��A���̓_���炵�Ă��A�����̏�L�����͗��R���Ȃ��B
�@���Ȃ킿�A�؋��i�b�W�A���T�Ȃ����P�P�A�Q�O�A�Q�R�A�R�Q�A�R�R�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�@�����P�S�N�t���s����O�ɂ����āA�u�ԕ��v�Ƒ��̕�����Ƃ̑g��������Ȃ�W�͂�t�����̂Lj��i�L�����f�B�[�j�Ƃ��āA�u�ԕ����߂̂�����v�A�u�ԕ��{�܁v�A�u�ԕ��N�[���A�b�v�^�C���v�A�u�ԕ��Ƀ~���g�K���v�A�u�u�ԉԕ��r�s�n�o�I�v�A�u�ԕ��ގ��v�A�u�ԕ����ӕ�v�Ƃ��������i���̔�����Ă������ƁA�A�����P�S�N�t���s��ɂ����ẮA�O���l�̏��i�Ƃ��āA������А���{�܂́u�ԕ��N�[���A�b�v�^�C���v�A���C�I���َq������Ђ́u�V���K�[���X�ԕ���L�����f�B�[�v�A�u�ԕ��{�܁v�A������Ѓ��{���́u�ԕ�����v�Ȃǂ��̔�����Ă����ق��A�u�ԕ��̂Lj��v�̕W�͂�t�����̂Lj��i�L�����f�B�[�j�Ƃ��āA�������i�A�퍐���i�ɉ����āA�t���䐻�ق́u�ԕ��̂Lj��v�A�u�m���V���K�[�ԕ��̂Lj��v�A������ЃI�����W�[���[�{�܂́u�ԕ��̂Lj��v���̔�����Ă������Ƃ��F�߂���B���̂悤�ɁA�u�ԕ��v�̕������܂ޕW�͂�t���ꂽ�����̋������i���A�������i�y�є퍐���i�ɐ�s���Ĕ̔�����A���邢�͓������ɔ̔�����Ă������̂ł���A�܂��A����ɉ����āA�O�L�̂Ƃ���{���o�^���W��t�����������i�������P�R�N�P�Q���ɏ��߂Ĕ������ꂽ���̂ł��邱�ƂɏƂ点�A�{���o�^���W�́A���ꎩ�̂Ƃ��ċ������i�o�����ʋ@�\��L������̂ł͂Ȃ��A�܂��A����̏��i�ɂ������Ԍp���I�Ɏg�p���ꂽ���Ƃ�ʂ��Ďs��ɂ�����M�p�Ȃ����ڋq�z���͂���������̂Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ��B��L�̂悤�ȋ������i�̑��y�і{���o�^���W�̎������ʗ͂̐Ǝ㐫�ɉ����āA����ɁA�؋��i�b�T�̂P�A�Q�A�U�̂P�A�Q�A���S�T�j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�퍐���i�͌������i�Ɠ����̓��e�ł���A�����e�ʂ������i�V�O���j�ł���ɂ�������炸�A�������i�ɂ����Č������i�i�Q�O�O�~�j�����Q�T�����������i�i�P�T�O�~�j�Ŕ̔�����Ă����Ƃ����̂ł��邩��A�퍐���i�͏������i������ł��邱�Ƃɂ�����҂ɍD��ōw�����ꂽ�Ɛ��������B
�@��L�̊e����𑍍�����A�퍐���퍐���i���s��ɂ����Ĕ̔��������Ƃɂ��A�������i�̔���ɉ��炩�̕s���v�ȉe�������������Ƃ����������Ƃ��Ă��A�퍐�̍s�ׂƑ������ʊW�̂�����̂Ƃ��Č������ǂꂾ���̌������i�̔�����������̂����m�肷�邱�Ƃ͓���s�\�ł���B
�G�@��L�ɂ��A�������{���o�^���W�ɂ��Ɛ�I�ʏ�g�p���҂ł��������Ԃɂ��āA�Ɛ�I�ʏ�g�p���̐N�Q�𗝗R�Ƃ��đ��Q�̔��������߂鐿���́A���R���Ȃ��B
�i�����j
�@��������ƁA�퍐�̍s�ׂɂ���p�g�p����N�Q���ꂽ���Ƃɂ���Č����̔�������Q�́A�U�Q�X�P�~�i�v�Z���F�W�R���W�W�Q�O�~�~�O�D�P�T�~�O�D�O�T���U�Q�X�P�~�j�Ɛ��肳���i���W�@�R�W���Q���j�B
(4)�@�ٌ�m��p�����z�ɂ���
�@�������{�i�̒�N�������i�ב㗝�l�ɈϔC�������Ƃ͓��ٔ����Ɍ����ł���Ƃ���A�{�����Ă̐����A�����̓��e�A�R���̌o�߂��̑����ʂ̎���𑍍����Ă���A�{���ɂ����Ăٌ͕�m��p�̂����T�O���~�������āA�퍐�̐N�Q�s�ׂƑ������ʊW�̂��鑹�Q�ƔF�߂�B
�u�C���i�[�g���b�v��F���C���^�[�i�V���i���v����
���{�����W�́A�{���o�^�ًc�̐\���l�ł����F��̖��̂��܂ނ��̂ł����āA���̏����Ă��Ȃ����߁A�{�����W�̓o�^�́A���W�@��S���P����W���Ɉᔽ���Ă��ꂽ�ƔF�߂���B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10142�� |
|---|---|
| ������ | �@���W�o�^����������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N09��17�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
���Ă̊T�v
�@�{���́A��L�{�����W�̏��W���҂ł��錴�����A�o�^�ًc�̐\���Ă����������ɂ��{�����W�̓o�^���������|�̌��肪���ꂽ���߁A������̎���������߂����Ăł���B
�P �������ɂ�����葱�̌o��
(1) �{�����W�i�b��P�A��T�V���j
�@�����́A�{�����W�ɌW�鏤�W�o�^�o������A���̓o�^�����ۓc���ꂩ��A�{�����W�ɌW�鏤�W���̓��菳�p�����҂ł���B
�@���W���ҁF�w�i�����j
�@�o����F�����P�V�N�P���V���i����Q�O�O�T�|�X�V�O���j
�@�ݒ�o�^���F�����P�X�N�Q���X��
�@�o�^�ԍ��F���W�o�^��T�O�Q�S�U�Q�T��
�@���W�̍\���F���L�̂Ƃ���i�{�����W�̍\�����̊��������̂����A��P���ڂ́u��i�ˁj�v�́A��R���ڂ́u��i���j�v�̂��ꂼ��ّ̕����ƔF�߂���B�ȉ��A�{�����W�̍\�����̊����������u��F���v�ƕ\�L����B�j
�@�@�@�@
�@�w�菤�i�y�іFTMR5024625.txt
(2) �{���葱
�@�o�^�ًc�����ԍ��F�ًc�Q�O�O�V�|�X�O�O�Q�Q�W��
�@�o�^�ًc�\���l�F��F��A������Ђ���Ȃ��Ƃ���Վ�
�@�\�����F�����P�X�N�T���P�P��
�@������F�����Q�O�N�Q���Q�U��
�@����̌��_�F�u�{�����W�̏��W�o�^���������B�v
�@���蓣�{���B���F�����Q�O�N�R���Q�Q���i�����ɑ��j
�Q ����̗��R�̗v�_
�@����́A�{�����W���A�{���o�^�ًc�̐\���l�ł����F��̖��̂��܂ނ��̂ł����āA���̏����Ă��Ȃ�����A�{�����W�̓o�^�́A���W�@�S���P���W���Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂ł���A���@�S�R���̂R��Q���̋K��Ɋ�Â��A�������ׂ����̂ł���Ƃ����B
�@�{�����W�̓o�^�����W�@�S���P���W���Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂ł���Ƃ�������̔��f�̕����́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�u�P �\���l��F��y�ъ�����Ђ���Ȃ��Ƃ���ՎЂ���o�����b��P�T���̂P�͕����P�X�N�Q���W���t���̓o�L�듣�{�i�ʂ��j�ł���B����ɂ��A�\���l�̈�l�ł��閼�́i�\���l��F��j���w��F��x�ł��邱�Ƃ��F�߂���B�����āA�w��F��x�́A���a�Q�V�N�P�P���Q�P���ɏ@���@�l�Ƃ��Đݗ�����A���̖ړI��B�����邽�߂ɕK�v�ȋƖ��Ƃ��Č��v���Ɠ����s���Ă��邱�Ƃ��F�߂���B
�@�������āA�{�����W�͑O�L��P�̂Ƃ���w�C���i�[�g���b�v��F���C���^�[�i�V���i���x�̕������Ȃ�A�\���S�̂��ɂ߂ď璷�ł���A�������Љ��������̒��ԕ��Ɋ����́w��F���x�̕�����L���ĂȂ邩��A���o��\�����̊Y���������w��F���x������ҁA���v�҂ɓ��ɒ��ڂ����Ƃ�������̂ł���A���A��L�R�̂Ƃ���w��F��x�͒����ł���B�����āA�\�����̊Y���������w��F���x�́A���l�i�\���l�w��F��x�j�̖��̂����̍\�����Ɋ܂ޏ��W�ł���A�������A���̑��l�i�\���l�w��F��x�j�̏����Ă��Ȃ����̂ł���B
�@���������āA�{�����W�����W�@��S���P����W���Ɉᔽ����Ƃ̑O�L��R�̎��������R�͑Ó��Ȃ��̂ł����āA����ɂ��ďq�ׂ�E�E�E���W���҂̈ӌ��́A�ȉ��̗��R�ɂ��̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�Q ���W���҂́w�w��F��x�̖��̂ƁA�{�����W�Ƃ̖��̂��A������킵�����ۂ��ɂ��āA�{�����W���������W�ł�����̂́A�\����A���������哯���ɂ��Ĉ�A��̂ɕ\�������̂ł��邩��A��̕s���ɊO�ρA�̌Ă������̂ł���ƍl����B�x�|�q�ׂĂ���B�������Ȃ���A�O�L�P�̂Ƃ���A�{�����W�͍\���S�̂��ɂ߂ď璷�ł���A�������Љ��������̒��ԕ��Ɋ����́w��F���x�̕�����L���ĂȂ邩��A���o��\�����̊Y���������w��F���x������ҁA���v�҂ɓ��ɒ��ڂ����Ƃ�������̂ŁA���A��L�R�̂Ƃ���w��F��x�͒����ł��邩��A���̓_�Ɋւ��鏤�W���҂̎咣�͍̗p�ł��Ȃ��B
�R �܂��A���W���҂́A�w�V���������x�̕s�������i�h�~�j�@�ɂ�閼�̎g�p�����~�������������ɋ����A�{�����W�̓o�^���A�\���l�́w��F��x�Ƃ������̂ɌW��@�l�̐l�i�I���v��N�Q������̂łȂ�����A�{�������l�ɔ��f���ׂ��ł���|�q�ׂĂ���B�������Ȃ���A�{���͕s�������i�h�~�j�@�łȂ��A���W�@�ł����āA���W�@��S���P���́A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����W���e���ŗ�L���Ă��邪�A������W�����A���l�̏ё����͑��l�̎����A���́A�����ȗ��̓����܂ޏ��W�́A���̑��l�̏����Ă�����̂������A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��ƋK�肵����|�́A�l�i�@�l���̒c�̂��܂ށB�ȉ������B�j�̏ё��A�����A���̓��ɑ���l�i�I���v��ی삷�邱�Ƃɂ���Ɖ������B���Ȃ킿�A�l�́A����̏����Ȃ��ɂ��̎����A���̓������W�Ɏg���邱�Ƃ��Ȃ����v��ی삳��Ă���̂ł���i�����P�V�N�V���Q�Q���ō��ٔ������������P�U�N�i�s�q�j��R�S�R���Q�Ɓj�B�����āA�{�����W�Ɂw��F���x�̑��l�i�\���l�w��F��x�j�̖��̂��܂܂�邱�Ƃ͕�����Ȃ������ł���B�܂��A�\���l�́A�{�����W���l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ���邩��A����̖{�����W�����W�@��S���P����W���Ɉᔽ����ƈًc�\�����Ă��s�������̂Ɛ��F�ł�����̂ł���B����ɁA�i�P�j�w��F��x�������ł��邱�Ɓi���̓_�ɂ��āA�\���l�A���W���҂ɑ������Ȃ��B�j�A�i�Q�j�\���l���o�蒆�̏���Q�O�O�U�|�W�P�T�V�T���i�b��P�S���̂P�y�эb��P�S���̂Q�j�ɂ��āA�{�����W�����p���ꂽ���◝�R�ʒm�����邽�߁A�\���l�ɏ��Ȃ���ʕs���v�������邱�ƁA�i�R�j�\���l���A�w��F��x�̖��̂ɑ��̗p���t���������̂�`�p����Ȃ�������L���邱�Ɓi���̓_�ɂ��āA���W���҂́w�٘_�͂Ȃ��B�x�Əq�ׂĂ���B�j�A�i�S�j�w��F��x�̖��̂Ɩ{�����W������킵�����ƁA�����𑍍��I�ɔ��f����A�{�����W���l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ����ƔF�߂��邩��A���̓_�Ɋւ��鏤�W���҂̎咣���̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���������āA�{�����W�̓o�^�́A��q����������R�ɂ�菤�W�@��S���P����W���Ɉᔽ���Ă��ꂽ�ƔF�߂��邩��A�\���l�̂��̗]�̐\�����R�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A���@��S�R���̂R��Q���̋K��Ɋ�Â��A�������ׂ����̂ł���B�v
(����)
���ٔ����̔��f
�P ������R�ɂ���
(1) ���W�@�S���P���W���́A�u���l�̏ё����͑��l�̎����Ⴕ���͖��̎Ⴕ���͒����ȉ덆�A�|���Ⴕ���͕M���Ⴕ���͂����̒����ȗ��́v���܂ޏ��W�ɂ��āA���̑��l�̏����Ă�����̂������A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ�����̂ł��邪�A���̋K��̎�|�́A�l���A����̏����Ȃ��ɁA���̏ё��A�����A���̓������W�Ɏg���邱�Ƃ��Ȃ��l�i�I���v��L���Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���̂悤�Ȑl�i�I���v��ی삷�邱�Ƃɂ�����̂Ɖ�����̂������ł���i�ō��ٕ����P�V�N�V���Q�Q�������E�W���Q�P�V���T�X�T�Łj�B
�@�����āA�����錩�n���炷��A�ё��A�����A���̂̂ق��A�����Ɠ��l�A����l�̓��ꐫ��F��������@�\��L����덆�A�|���A�M���ɂ��āA�܂��A�����A���́A�덆�A�|���A�M���̊e���̂ɂ��Ă��A�����ɂ��ی���y�ڂ��K�v�������邪�A�����A���̂��A�قƂ�ǂ̏ꍇ�ɁA�o���͏o��o�L�\�����̏���̎葱���o�Č��肳��A�ːЕ��o�L�듙�̌���ɂ��m�F���邱�Ƃ��ł���̂ɑ��A�덆�A�|���A�M�����L�e���̂́A�������Ō��肳��A������m�F�����܂�����i�����Ȃ��̂��ʏ�ł����āA���̂悤�ȈӖ��Ŝ��ӓI�Ȃ����B���ȕ������c���A���l�̔F���Ǝ��͂̔F���Ƃ̊ԂɐH���Ⴂ��������悤�ȏꍇ�����蓾�邱�Ƃ��l�����āA�����́A�덆�A�|���A�M���y�ю����A���́A�덆�A�|���A�M���̊e���̂ɂ��ẮA�����ɂ��ی�̗v���Ƃ��āA�����ł��邱�Ƃ�K�v�Ƃ����̂ɑ��A�����A���̂ɂ��ẮA�����ł��邱�Ƃ�v���Ȃ����̂Ƃ����Ɖ����邱�Ƃ��ł���B
�@�����Ƃ��A�����̓K�p�ɓ�����A���l�̎����A���̓����܂ޏ��W�ɂ��āA���Y���l�̐l�i�I���v��N�Q���邨����̂����̓I�Ȏ�����݂��邱�Ƃ́A��������v����덆�A�|���A�M���y�ю����A���́A�덆�A�|���A�M���̊e���̂Ɋւ��āA�������̗L���f����ۂ̂P�v�f�ƂȂ蓾�邱�Ƃ͊i�ʁA�����̋K���A�l�i�I���v�̐N�Q�̂����ꂻ�ꎩ�̂��A�Ɨ������v���Ƃ���Ă�����̂ł͂Ȃ��B
(2) ������Ƃ���A��L��Q�̂P��(1)�̂Ƃ���A�{�����W�̍\�����̊��������̂����A��P���ڂ́u��i�ˁj�v�́A��R���ڂ́u��i���j�v�̂��ꂼ��ّ̕����ƔF�߂��邩��A�������͎����I�Ɂu��F��v�Ə�����Ă���̂Ɠ����Ƃ����ׂ��ł���A���̓_�́A�����������Ă��Ȃ��B
�@�����āA�u��F��v�́A�{���̓o�^�ًc�\���l�ł����F��̖��́i�t���l�[���B�b��P�T���̂P�A�Q�j�̕\�L���̂��̂ł��邩��A�{�����W���A���l�̖��̂��܂ނ��̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���A���A���Y�u���l�v�ł����F��̏����Ă��Ȃ����Ƃ́A���������F����Ƃ���ł���B��������ƁA�{�����W�́A���W�@�S���P���W���ɂ�菤�W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
(3) �����́A���W�̎g�p�ɂ�葼�l�̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ����ꍇ�ɏ��߂āA���Y���W�����W�@�S���P���W���́u���l�̏ё����͑��l�̎����Ⴕ���͖��̎Ⴕ���͒����ȉ덆�A�|���Ⴕ���͕M���Ⴕ���͂����̒����ȗ��́v���܂ޏ��W�ɊY��������̂Ɖ����ׂ��ł���|�咣����B
�@�������Ȃ���A�����̗��@��|���A�����A���̓����A�����Ȃ����W�Ɏg���邱�Ƃ��Ȃ��Ƃ����l�i�I���v��ی삷�邱�Ƃɂ�����̂Ƃ��Ă��A��L�̂Ƃ���A�����̋K���A���l�̎����A���̓����܂ޏ��W���A���Y���l�̐l�i�I���v��N�Q���邨����̂����̓I�Ȏ�����݂��邱�Ƃ́A�����K�p�̗v���Ƃ���Ă�����̂ł͂Ȃ��B���Ȃ킿�A�����́A���l�̏ё��A�����A���̂��܂ޏ��W�A���тɑ��l�̒����ȉ덆�A�|���A�M���y�ю����A���́A�덆�A�|���A�M���̒����ȗ��̂��܂ޏ��W�ɂ��ẮA���̂��Ǝ��̂ɂ���āA��L�l�i�I���v�̐N�Q�̂������F�߁A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ƃ��Ă�����̂Ɖ������̂ł���B
�@���������āA�����̏�L�咣�͎����ł���B
(4) ���ɁA���l�̎������܂ޏ��W�ł����Ă��A���̎g�p�����Y���l�̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ�S���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���W�@�S���P���W���̓K�p���Ȃ��A���Y���W�̓o�^���邱�Ƃ��ł���Ɖ�����Ƃ��Ă��A�{���ɂ����ẮA�{�����W�̎g�p����F��̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ�S���Ȃ��Ƃ̎�����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��B
�@���̓_�ɂ��A�����́A�V���������ō��ٔ��������p���A���������A�@���@�l�̖��̂ɌW��l�i�I���v�i���̌��j�ɂ��Ĕ����������̂ł���A���W�@�S���P���W���Ƃ̊W�ɂ����āA�{�����W�̎g�p�ɂ��@���@�l�ł����F��̐l�i�I���v���N�Q����邨���ꂪ���邩�ۂ��̔��f�̎Q�l�ƂȂ���̂ł���Ƃ�����A�u��F��v�́A�����̑�����h�s�q�h���{�Z���^�[�̏@����̋��`���w�W������̂ł����āA���̊����ɂ����ċ��`�𖾂炩�ɂ��閼�̂�I�肵�悤�Ƃ���A�u��F��v�Ƃ̖��̂��܂ޏ��W���̑�������Ȃ����ƁA�h�s�q�h���{�Z���^�[�́A��F��ƂƂ��ɂ`�̋����ɏ]���ď@���������s���@���c�̂ł���A���̐M�鋳�`�́A�Љ��ʂ̔F���ɂ����Ắu��F��v�ɂق��Ȃ�Ȃ����ƁA�����Ȃ����h�s�q�h���{�Z���^�[���A��F��̖��̂̒���������X�ɗ��p���悤�Ƃ���s���ȖړI�͂Ȃ����ƂȂǂ������āA�{�����W�̓o�^����F��̐l�i�I���v��N�Q������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝ咣����B
�@�������Ȃ���A�V���������ō��ٔ����̌����̈��p���锻�������́A�@���@�l���A���̖��̂𑼂̏@���@�l���ɖ`�p����Ȃ�������L���A�������@�ɐN�Q���ꂽ�Ƃ��́A�l�i���Ɋ�Â����̐N�Q�s�ׂ̍��~�߂����ߓ��邱�Ƃ���ʓI�ɍm�肵����A�����ŁA�@���@�l�́A���̖��̂ɌW��l�i�I���v�̂P���e�Ƃ��āA���̎g�p�i���`���Ȍ��Ɏ���������������̂̎g�p���܂ށB�j�̎��R��L���邩��A�b�@���@�l�̖��̂Ɠ��ꖔ�͗ގ��̖��̂����@���@�l���g�p���Ă���ꍇ�ɂ����āA���Y�s�ׂ��b�@���@�l�̏�L��������@�ɐN�Q������̂ł��邩�ۂ��́A���@���@�l�̖��̎g�p�̎��R�ɔz�����A�b�@���@�l�̖��̂̎��m���≳�@���@�l�����Y���̂��g�p����Ɏ������o�ܓ��̏�����𑍍����Ĕ��f���ׂ��ł���Ƃ��A���Y���ĂɌW���̓I����̉��ł́A���@���@�l�ɑ��������㍐�l�̖��̎g�p���A�b�@���@�l�ɑ�������㍐�l�̖��̂�`�p����Ȃ���������@�ɐN�Q������̂ł͂Ȃ��Ɣ��f�������̂ł���B���Ȃ킿�A�V���������ō��ٔ������A�@���@�l�̖��̂ɌW��l�i�I���v�i���̌��j�ɂ��Ĕ����������̂ł��邱�Ƃ͂��̂Ƃ���ł���Ƃ��Ă��A�@���@�l�̖��̂ɌW��l�i�I���v�i���̌��j����@�ɐN�Q���邩�ۂ�������Ă���̂́A���̏@���@�l�̖��̂̎g�p�s�ׂł���A���Y���̏@���@�l���A���̐l�i�I���v�̂P���e�Ƃ��āA���̎g�p�i���`���Ȍ��Ɏ���������������̂̎g�p���܂ށB�j�̎��R��L����䂦�ɁA���Y���̎g�p�s�ׂ���@�ȐN�Q�s�ׂƂ���邩�ۂ��̔��f�ɓ������ẮA���̖��̎g�p�̎��R�ɔz�����A��L��������l�����ׂ����̂Ƃ��Ă���̂ł���B����ɑ��A�{���ɂ����āA�@���@�l�̖��̂ɌW��l�i�I���v�i���̌��j��N�Q���邨���ꂪ�Ȃ��Ƃ����邩�ǂ��������ƂȂ�̂́A���W�̓o�^�Ȃ������̎g�p�s�ׂł���A������s�ׂ́A���W���g�p����҂̋Ɩ���̐M�p�i���W�@�P���Q�Ɓj�Ƃ����A����Љ�ɂ�����o�ϓI���v�ɌW����̂ł����āi���ɁA�{�����W�ɌW��w�菤�i�y�юw��̑啔���́A�@���@�l�̖{���I�ȏ@�������₱��Ɩ��ڕs���ȊW�ɂ��鎖�Ƃƒ��ڂ̊W��L������̂ł͂Ȃ��B�j�A�@���@�l�̖��̂̎g�p�����̐l�i�I���v�Ɋ�Â��̂Ɣ�ׁA�@�I���v�̐�����S���قɂ�����̂ł���Ƃ��킴��Ȃ��B
�@��������ƁA�V���������ō��ٔ������w�E�����̂Ɠ��l�̏�����ɂ��A�{���ɂ�����A�{�����W�̎g�p����F��̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ�Ȃ��Ƃ����邩�ۂ��̔��f���Ȃ�����Ƃ������̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���A������Ӗ��ŁA�V���������ō��ٔ����́A�{���Ǝ��Ă��قɂ�����̂ł���B
�@������Ƃ���A�������A�{���ɂ����Ď咣�����L�e����́A�V���������ō��ٔ������w�E��������̈ꕔ�Ɠ��l�̎���ł���A���Y�咣�ɌW�鎖����݂��邩��Ƃ����āA�{�����W�̎g�p����F��̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ�S���Ȃ��Ƃ̎�����F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���ɁA�{�����W�̎g�p����F��̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ�S���Ȃ��Ƃ̎����𗠕t����ɑ����悤�Ȏ���̑��݂��F�߂��Ȃ��B
�@���������āA�{�����W�̎g�p����F��̐l�i�I���v��N�Q���邨���ꂪ�S���Ȃ��Ƃ̎����́A�����F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ����ƂɋA����B
�Q ���_
�@�ȏ�ɂ��A������ɂ��挴���̎咣�͗��R���Ȃ��A�����̐����͊��p�����ׂ��ł���B
�s�g�p�ɂ�鏤�W�o�^�̎���R���̎������
���{�����W�̎g�p�����Ă���Ƃ̎����́A�퍐�ɂ����Ď咣���ؐӔC�S���鎖���ł���A�R������i�ׂɂ����āA�퍐�́A�������ɂ��āA����̎咣�������Ȃ��������߁A�{���R�����F�肵���u�퍐�́A�{���R���̐����̓o�^�O�R�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����āA�{�����W�𐿋��ɌW��w�菤�i���́w��܁x�ɂ��Ďg�p�����v�Ƃ̎������F�肳�ꂸ�A�R�����������ꂽ�B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10308�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N10��30�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@�@�@��@�@��
�P ������������Q�O�O�V�|�R�O�O�T�X�W�������ɂ��ĕ����Q�O�N�S���V���ɂ����R�����������B
�Q �i�ה�p�͔퍐�̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�@�����y�ї��R
��P ����
�@�啶��P���Ɠ��|
��Q �����̎咣
�@�����́A�{�������٘_�����ɂ����āA���̂Ƃ���q�����B
�P �������ɂ�����葱�̌o��
�@�퍐�́A�o�^��U�S�O�P�X�Q�����W�i���a�R�V�N�W���R���o��A���a�R�X�N�S���S���ݒ�o�^�B�ȉ��u�{�����W�v�Ƃ����B�j�̏��W���҂ł���B
�@�����́A�����P�X�N�T���P�P���A�{�����W�̎w�菤�i���A��T�ށu��܁v�ɂ��Ă̓o�^�����������Ƃ����߂ĐR���̐����i����Q�O�O�V�|�R�O�O�T�X�W�������B�ȉ��u�{���R���v�Ƃ����B�j�������B
�@�������́A�����Q�O�N�S���V���A�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R���i�ȉ��u�{���R���v�Ƃ����B�j�����A�����P�W���A���̓��{�������ɑ��B�����B
�Q �{���R���̗��R
�@�{���R���̗��R�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) �퍐�́A�{���R���̐����̓o�^�O�R�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����āA�{�����W�𐿋��ɌW��w�菤�i���́u��܁v�ɂ��Ďg�p���Ă������Ƃ��ؖ������B
(2) ���W�@��T�O���̋K��ɂ��A�{�����W�̎w�菤�i���́u��܁v�ɂ��Ă̓o�^�����������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�R �{���R���̎�����R�Ɋւ��錴���̎咣
�@�{�����W�̏��W���҂ł���퍐�A��p�g�p���Җ��͒ʏ�g�p���҂̂�������A�{���R���̗\���o�^�����ꂽ�����P�X�N�T���Q�X�����O�R�N�ȓ��ɁA���{�����ɂ����āA�{���R���̐����ɌW��w�菤�i�i��T�ށu��܁v�j�ɂ��āA�{�����W�̎g�p�����Ă��Ȃ��B�{���R���́A���������ׂ��ł���B
��R ���ٔ����̔��f
�@�퍐�́A�K���̌ďo���i�������B�ɂ����̂ł͂Ȃ��B�j�������A�{�������٘_�����ɏo�������A���ُ����̑��̏������ʂ̒�o�����Ȃ��B���������āA�O�L��Q�L�ڂ̌����̎咣�i�������A��L�̂Ƃ���A�퍐�ɂ����Ď咣���ؐӔC�S����A�{�����W�̎g�p�ɌW�鎖���͏����B�j�������������̂Ƃ݂Ȃ����B
�@�Ȃ��A�{�����W�̏��W���҂ł���퍐�A��p�g�p���Җ��͒ʏ�g�p���҂̂����ꂩ���A�{���R���̗\���o�^�����ꂽ�����P�X�N�T���Q�X�����O�R�N�ȓ��ɁA���{�����ɂ����āA�{���R���̐����ɌW��w�菤�i�i��T�ށu��܁v�j�ɂ��āA�{�����W�̎g�p�����Ă���Ƃ̎����́A�퍐�ɂ����Ď咣���ؐӔC�S���鎖���ł��邪�i���W�@�T�O���Q���j�A�퍐�́A�������ɂ��āA����̎咣�������Ȃ��B
�@���������āA�{���R�����F�肵���u�퍐�́A�{���R���̐����̓o�^�O�R�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����āA�{�����W�𐿋��ɌW��w�菤�i���́w��܁x�ɂ��Ďg�p�����v�Ƃ̎����́A�����F�肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@����āA�����̐����͗��R�����邩��A�����F�e���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B
�u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�v�s�g�p�����������
���o�^���W�̎g�p��F�߂Ȃ������R���������������B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10317�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N01��28�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��Q �����̂Ȃ�����
�P �{�����W
�@�o�^��Q�P�X�S�U�W�X�����W�i�ȉ��u�{�����W�v�Ƃ����B�j�́A�u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�v�̉������Ɓu���i�b�V�����g�v�̕Љ��������Ƃ��㉺��i�ɉ��������ĂȂ�A���a�U�Q�N�V���V���ɓo�^�o�肳��A��P�V�ށu�핞�A�z���g��i�A�Q��ށv���w�菤�i�Ƃ��āA�������N�P�Q���Q�T���ɐݒ�o�^����A���̌�A���W���̑������Ԃ̍X�V�o�^������A���������W���҂Ƃ��āA���ɗL���ɑ������Ă���i�b�P�A�Q�j�B
�Q �������ɂ�����葱�̌o��
�@�퍐�́A�����P�X�N�P�O���Q���A���W�@�T�O���P���Ɋ�Â��A�{�����W�̎w�菤�i���u��P�V�ޔ핞�v�ɂ��āA���W�o�^�̎���������߂�R���i����Q�O�O�V�|�R�O�P�Q�U�T�������B�ȉ��u�{���R���v�Ƃ����B�j�𐿋����A���N�P�O���P�X���A���̎|�̗\���o�^�i�ȉ��u�{���\���o�^�v�Ƃ����B�j�����ꂽ�i�b�Q�j�B
�@�������́A�����Q�O�N�V���P�U���A�u�o�^��Q�P�X�S�U�W�X�����W�̎w�菤�i���u�핞�v�ɂ��Ă̓o�^���������B�v�Ƃ̐R���i�ȉ��u�R���v�Ƃ����B�j�����A���̓��{���Q�W���Ɍ����ɑ��B�����B
�i�����j
��S ���ٔ����̔��f
�P ���ٔ����́A�ȉ��̂Ƃ���A�{���R���̐����ɌW��{���\���o�^�O�R�N�ȓ��ɁA�{�����W�ƎЉ�ʔO�㓯��̏��W�u�q�����`�������l���������v��t�������i�u�X�[�c�v�������������A�̔����Ă��鎖����F�肷�邱�Ƃ��ł��邩��A���̎������F�߂��Ȃ��Ƃ����R���ɂ͌�肪����Ɣ��f����B���̗��R�́A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1) ���W�u�q�����`�������l���������v�̎g�p�̎���
�A�؋��i�b�P�Ȃ����P�T�j�ɂ��A�ȉ��̎������F�߂���B
�@�����́A�����P�T�N�S������A�ɐ��O�V�h�X�����Y�قS�K�̓X�܂ɂ����āA���Ђ��A������C�[�W�[�I�[�_�[���i�i���W���[���C�h�j�Ƃ��Ĕ̔�����u�X�[�c�v�ɂ��āA���Ђ��璍�����čٖD���A���W�u�q�����`�������l���������v��t������A���������u�X�[�c�v�Ђɔ[�i���A�̔����Ă���B
�@���̔̔��ԗl�̏ڍׂ́A�@�����̒���X�[�c�̃T���v����X���œW�����A�A�ڋq�́A�W������Ă���T���v���̃f�U�C��������A�D�݂̃X�[�c�̐��n�A�f�U�C������I�����A�̔��S���҂��A�ڋq�̍̐������āA�I�v�V�������̒������m�F���A�B�����́A����������ɁA�����ɉ������X�[�c�����A��L�̂Ƃ���A�����n�ɏ��W�u�q�����`�������l���������v��t������ŁA�ɐ��O�ɁA�[�i�A�̔�������̂ł���B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�����́A���̐����A�̔��ɌW��X�[�c�ɁA��L���W��t���Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���A����ɔ�����؋��͂Ȃ��B
�@�Ȃ��A�b�P�T�ł́A�ڋq�ɃX�[�c��̔������̂́A�����ł����āA�ɐ��O�ł͂Ȃ����̂悤�ȋ��q�L�ڂ����邪�A�b�P�O�A�b�P�P�̎���`�[�ɂ����āA�u����v�Ɩ�������Ă��邱�ƂɏƂ炵�āA���L�q�����͍̗p�̌���łȂ��i�퍐���A�ڋq�ɃX�[�c��̔������̂́A�ɐ��O�ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��āA���L�̂Ƃ���̔��_�����Ă���Ƃ���ł���B�j�B
�C����ɑ��āA�퍐�́A�ȉ��̂Ƃ���咣���邪�A����������R���Ȃ��B
�@�܂��A�퍐�́A�����͈ɐ��O�ɑ��Ĕ̔����Ă��鏤�i�́A���n�ł����āA�u�X�[�c�v�ł͂Ȃ��Ǝ咣����B
�������A�O�L�F��̂Ƃ���A�����́A�ɐ��O�V�h�X�ɂ����Čڋq���I���n�ɂ��āA���Ȃ̎��Ə��ɂ����ĖD�����ď��W�u�q�����`�������l���������v��t�������i�u�X�[�c�v���A���������A������ɐ��O�ɑ��Ĕ̔��[�i���Ă���B���̓_�́A�����ƈɐ��O�Ƃ̊Ԃ̎���̎d���`�[�i�b�P�P�j�ɂ����āA���̎d����`�Ԃ̗��Ɂu����v�Ƃ̕���������A�u�i���v�Ƃ��āu�V���O���X�[�c�v�ƋL�ڂ���A�S���~�䂩��V���~��̂P�_������̌������z���L�ڂ���Ă��邱�ƂɏƂ炷�Ȃ�A�d���čς݂́u�X�[�c�v�i��P�V�ޔ핞�j���̔����ꂽ���̂Ƃ����ׂ��ł���A���n�̔̔��ɉ����āu���H�����v�i�S�O�ށj������Ă���Ɖ�����]�n�͂Ȃ��B
�@�܂��A�퍐�́A�b�X�i�����`�[�j�ƍb�P�O�i�[�i�`�[�j�Ƃ̕i�Ԃ��A�{�����W��t�������i�ł��邱�Ƃ̗��t�����Ȃ����ƁA�b�P�O�i�[�i�`�[�j�̓`�[�ԍ����菑���ł��邱�ƁA�b�P�O�i�[�i�`�[�j�ƂP�P�i�d���`�[�j�ɂ����ē_�����قȂ邱�Ɠ��A�M�p���ɋ^�`������Ǝw�E����B�������A������o�ɌW��`�[�ɂ����āA���t�A���z�A�i�����̓_�Ŗ�������悤�ȕs���R�ȓ_�͑��݂��Ȃ��B
�@����ɁA�퍐�́A�����ƈɐ��O�Ƃ̎���W�����v�҂ɑ���W�ł͓����W�ł̏��i�ړ��ɂ������A���̂悤�ȓ����W�ł̏��i�̈ړ��ɂ����āA���W���t���ꂽ�Ƃ��Ă��A��ʎ���s��ɂ�������̂Ƃ͈قȂ�A���W�̎g�p�ɓ�����Ȃ��Ǝ咣����B�������A�����̏��W��t�������i�̔̔��悪�A�ŏI���v�҂łȂ�����A���W��t�������i�̔̔��ɊY�����Ȃ��Ƃ̎咣�́A���̑O��ɂ����č̗p�ł��Ȃ��̂ŁA�퍐�̏�L�咣�͗��R���Ȃ��B
(2) �����咣�̎g�p���W�Ɩ{�����W�Ƃ̎Љ�ʔO��̓��ꐫ�ɂ���
�@���ɁA�����咣�̎g�p���W�u�q�����`�������l���������v���{�����W�ƎЉ�ʔO�㓯��̏��W�i���W�@�T�O���P���j�ł���Ƃ�����̂��ǂ����ɂ��Č�������B
�A�O��
�@�{�����W�i�u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�v����i�ɁA�u���i�b�V�����g�v�����i�ɉ������������W�j�̂�����i�����u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�v�́A��A�̉���������Ȃ�B����ɑ��A�g�p���W�u�q�����`�������l���������v�́A�u�q�v�A�u�`�v�y�сu�l�v�݂̂��啶���ŕ\�L����Ă��邱�Ƃ���i�b�S�Ȃ����U�A�X�A�P�R�A�P�S�j�A�R�̑啶������������邽�߁A��قȂ��ۂ�^����]�n���Ȃ��Ƃ͂����Ȃ����A�����A�������̂��ׂĂ������ԂȂ��A���I�ɒԂ��Ă��邱�ƁA�e�啶������n�܂�R�̕����u�q�����v�A�u�`�������v�y�сu�l���������v�̂�������ŗL�̊ϔO��L���Ȃ����ƂɏƂ炷�Ȃ�A�u�d���ăX�[�c�v�Ɏg�p����ۂ̑����I�Ȋϓ_����̕ύX�ɂ����Ȃ��Ɖ�����̂������I�ł���B�ȏ�̂Ƃ���A�g�p���W�Ɩ{�����W�Ƃ́A�O�ςɂ����āA�Љ�ʔO�㓯��ł���B
�C�̌�
�@�{�����W�̉����������u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�v�́A���i�̃J�^�J�i�����ƕ����āu���i�b�V�����g�v�Ƃ̏̌Ă�������B�����A�g�p���W�u�q�����`�������l���������v�ɂ��Ă��A���ԂȂ��A���I�ɕ\�L����Ă���_�ɏƂ炷�ƁA�u���i�b�V�����g�v�Ȃ����u���i�V�����g�v�Ƃ̏̌Ă�������B�ɐ��O�V�h�X�z�[���y�[�W�̃t���A�ē��ɂ����ẮA�u�q�����������������������^���i�V�����g�v�Ƃ����\��������Ă��邱�Ƃ��炷��ƁA���t���A�̓X�܂ɂ����Ĕ̔�����Ă��錴���D���́u�X�[�c�v���u���i�V�����g�v�ƌĂ�Ă��邱�Ƃ𐄔F���邱�Ƃ��ł���B�ȏ�̂Ƃ���A�g�p���W�Ɩ{�����W�Ƃ́A�̌Ăɂ����āA�Љ�ʔO�㓯��ł���B
�E�ϔO
�@�g�p���W�u�q�����`�������l���������v���{�����W�����ɉ䂪���ɂ����Đe���܂ꂽ�O����ł͂Ȃ��A����̊ϔO���Ȃ��B�ϔO�ɂ����鑊��͂Ȃ��B
�@�ȏ�̂Ƃ���A�g�p���W�u�q�����`�������l���������v�Ɩ{�����W�u�q�h�m�`�r�b�h�l�d�m�s�n�^���i�b�V�����g�v�Ƃ́A�O�ρA�̌Ă���������Љ�ʔO�㓯��ł���A�ϔO�ɂ����鑊��͂Ȃ��A�Љ�ʔO�㓯��̏��W�ł���ƔF�߂���B
(3) ����i�ׂɂ�����؋��̒�o�ɂ���
�퍐�́A�R������i�ׂɂ�����V���Ȏg�p�����̎咣�y�т���ɉ������V�؋��̒�o�͖����i�ז@�̐��_�i���@�P�T�U���A�P�T�V���j�ɏƂ炵�p�������ׂ��ł���Ǝ咣����B
�@�������A���W�o�^�̕s�g�p����R���̐R���ɑ������i�ׂɂ����铖�Y�o�^���W�̎g�p�̎����̗��́A�����R�̌����٘_�I�����Ɏ���܂ŋ��������̂Ɖ������Ƃ���i�ō��ٔ�����O���@�쏺�a�U�R�N�i�s�c�j��R�V�������R�N�S���Q�R�������E�ō��ٔ�����������W�S�T���S���T�R�W�ŎQ�Ɓj�A�{���ɂ����ẮA�����ɂ��V���Ȏg�p�����̎咣�y�т���ɉ������V�؋��������i�ז@�P�T�V���ɂ������@�Ɍ�ꂽ�U���h�����@�ł����āA�i�ׂ̊�����x�������邱�ƂƂȂ�ƔF�߂�ɑ���鎖����F�߂��Ȃ�����A�퍐�̏�L�咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�Q �ȉ��A�R���ɂ�����R�����̋L�ڎ����y�ѐR���̂�����ɂ��ďq�ׂ�B
(1) �{���R���́A���W�@�T�O���Ɋ�Â����W�o�^�ɂ��Ă̕s�g�p�𗝗R�Ƃ��������̐R���ł���B�����Q���́A�u�R���̐����̓o�^�O�R�N�ȓ��ɁE�E�E���W���ҁE�E�E���A���̐����ɌW��w�菤�i�E�E�E�ɂ��Ă̓o�^���W�̎g�p�����Ă��邱�Ɓv�ɂ��Ă̎咣���ؐӔC�́A���W���҂ɂ����ĕ��S���ׂ��|�K�肷��B�Ƃ���ŁA�����́A�������ׂ��ꍇ�̗v�����A��ʓI���ۓI�Ȍ`���ɂ��K�肵�Ă���B�����ŁA�o�^���W�s�g�p�����R�����f����R���̂Ƃ��ẮA�@�܂��A�咣���ؐӔC�S���鏤�W���҂ɑ��āA���Y�@�K�̗v���i�������Ƃ��v���j�ł���u�R���̐����̓o�^�O�R�N�ȓ��ɁE�E�E���W���ҁE�E�E���A���̐����ɌW��w�菤�i�E�E�E�ɂ��Ă̓o�^���W�̎g�p�����Ă���v�Ƃ̒��ۓI�������̂��̂ł͂Ȃ��A���v���ɊY�������̓I�����i���ؖ���j���咣�����A�A�������ɁA���W���҂̎咣�ɌW��A�@�K�̗v���ɊY�������̓I�������؋��ɂ���ė��t�����邩�ۂ���R�����邱�Ƃ��s���ƂȂ�i�����l�ɑ��āA���_�̎咣�y�є��̋@���^����K�v�����邱�Ƃ͓��R�ł���B�j�B
�@�܂��A�R�����ɂ́A�u���_�v�݂̂Ȃ炸�A���_���u���R�v���L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��|�K�肳��Ă���i���W�@�T�U���A�����@�P�T�V���Q���j�B�o�^���W�s�g�p����̐R���ɂ����錋�_�����߂̘_���́A��L�ɏq�ׂ��Ƃ���ł��邩��A�R�����́u���R�v�ɂ́A�@�@�K�̗v���ɊY�������̓I�Ȏ����咣�i���ؖ���j�����ł��邩�A�A��̓I�Ȏ����咣�i���ؖ���j���A�؋��ɂ���ė��t�����邩�ۂ̔��f���A�_���I�ɉߕs���Ȃ��L�ڂ���邱�Ƃ��K�v�ƂȂ�B
(2) �{���R�����ł́A���R���ɁA�u�����҂̎咣�v�Ƃ��āu��Q �����l�̎咣�v�y�сu��R �퐿���l�̎咣�v���A���ʂ̒�o���ꂽ���n��ɂ����ċL�ڂ���A�܂��A�u�R���̂̔��f�v�Ƃ��āu��S ���R�̔��f�v���L�ڂ���Ă���B
�@�������A�R�����ɁA��̓I�ȗv�������Ɩ��W�Ȏ咣���A���̂܂܋L�ڂ���Ӗ��͂Ȃ��݂̂Ȃ炸�A�{���R�����̑S�̂��݂Ă��A�R���̑Ώۂł��錴���i�퐿���l�j�̎咣�ɌW��u���W���ҁA��p���{���Җ��͒ʏ���{���҂̂����ꂩ���A�E�E�E�w�菤�i�E�E�E�ɂ��Ă̓o�^���W�̎g�p�����Ă���i�����j�v�ɊY�������̓I�����i���ؖ���j�����ł��邩�ɂ��āA���m�ȋL�ڂ�����Ă��Ȃ��B
�@��L�̂Ƃ���A�{���R�����ł́A�R���ɂ����āA�������ǂ̂悤�ȋ�̓I�����咣���������ɂ��Ă̖��m�ȋL�ڂ�����Ă��Ȃ����߁A�{������i�ׂɎ����āA�R���i�K�ɂ����Č��������W���g�p������̓I�����̎咣�i���ؖ���j�ƁA����i�גi�K�ɂ����Č������g�p������̓I�����咣�i���ؖ���j�Ƃ��A����̂��̂ł��邩�ۂ������_�ƂȂ������A���̓��ۂ�I�m�ɔ��f���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@�܂��A�R�����́u�R���̂̔��f�v�ɂ����āA�����҂���o�����X�̏؋��ɑ���]���Ɋւ���L�ڂ͂�����̂́A��̓I�咣�Ɋւ��閾�m�ȋL�ڂ��Ȃ����߁A�����̎咣�ɌW��ǂ̂悤�ȋ�̓I�Ȏ����������r�˂��ꂽ���߂ɁA�R���̌��_�Ɏ��������ɂ��āA���̘_���̓��ۂf���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
�@���̓_�ɂ����āA�R�����̋L�ڂɂ��āA�H�v�̗]�n��������̂Ƃ�����B
(3) �܂��A�{���R���ɂ����ẮA���������P�Ȃ����S�i�{�i�b�S�Ȃ����W�j�Ɋ�Â��Ă������ɑ��āA�u�X�[�c�̋�̓I������ނł���A�Ⴆ�A�������A�[�i���A�x���`�[���̒��Ȃ��v���Ƃ��傽�闝�R�Ƃ��āA�r�˂��Ă���B
�@�������A�@�����n�Ɏg�p���W�u�q�����`�������l���������v�y�сu�����̏����̋L�ڂ��ꂽ�^�O�v���t���ꂽ�X�[�c�̎ʐ^�A�A�u�q�����������������������v���\�L����Ă���ɐ��O�V�h�X�̃t���A�[�}�b�v�̃z�[���y�[�W�̎ʂ��A�B�������ɐ��O�V�h�X�ɂ����āA���W�u�q�����`�������l���������v���g�p���Ă���Ƃ̒q���ʓ����A���������o����Ă���̂ł��邩��A�����𑍍�����A������x�̐S���`�����邱�Ƃ͂ł���Ɖ�����̂������I�ł���B����ɂ�������炸�A�R���̂��A������ނ̒�o���Ȃ��Ƃ����o�܂������āA���W�g�p�̎�����r�˂���̂ł���A���Ȃ��Ƃ��A�R���ɍۂ��āA�����ɑ��āA������ނ̒�o�̉ہA�s��o�̗��R���ɂ��āA�ߖ������߂�ׂ��ł���B���̓_�ɂ����āA�R���^�c�ɂ��Ă��A�H�v�̗]�n��������̂Ƃ�����B
�R ���_
�@�ȏ�ɂ��A�{���\���o�^�O�R�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����āA���W���҂ł��錴�������̐����ɌW��w�菤�i���u�핞�v�ɂ��āA�{�����W�ƎЉ�ʔO�㓯��̏��W���g�p���Ă��邱�Ƃ��ؖ��������̂ł���ƔF�߂邱�Ƃ��ł��邩��A�퍐����̏��W�s�g�p���������F�߂��R���͌��ł����āA���̎������Ƃ�Ȃ��B����āA�����̖{�i�����͗��R�����邩��A�����F�e���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B
�uPAPA�@JOHN'S�v���W�s�g�p�������
���o�^���W�̎g�p��F�߂Ȃ������R�����ێ���������B��
| �����ԍ� | �@����17�N(�s�P)��10095�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����17�N12��20�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��Q�@���Ă̊T�v
�@�@�{���́A�퍐�̗L����{�����W�ɂ��āA���������W�@�T�O���P���Ɋ�Â��s�g�p�ɂ�鏤�W�o�^������̐R���𐿋������Ƃ���A���������R�������s�����̐R�����������Ƃ���A���������R���̎���������߂����Ăł���B
�i�����j
�Q�@�퍐�ɂ��{�����W�̎g�p�̗L���i�R��(1)�j
(1) �{�����W��\�����Ă̎w�菤�i�̒�
�A�@�퍐�́A���{�ɂ�����t�����`���C�Y�W�J�̋��c�̂��߂Ɋ֘A�Ǝ҂��č���K�ꂽ�ۂɂ́A�{�����W��\�������X�܂Ɉē����A�s�U�A�̔����i�i������Ă���Ǝ咣����B
�C�@�؋��i���P�A�Q�A�T�`�V�j�ɂ��A�@�퍐�́A�P�X�W�T�N�i���a�U�O�N�j�ɑn�Ƃ����s�U�̔��Ǝ҂ł���A�P�X�W�U�N�i���a�U�P�N�j����t�����`���C�Y�X�̓W�J���J�n���A�Q�O�O�Q�N�i�����P�S�N�j�P�Q���Q�X���̎��_�ɂ����āA�퍐�y�т��̉����X�̃��X�g�����́A�퍐�ɂ����̂��A�č��ɂT�W�T�X�܁A�p���ɂX�X�܁A�t�����`���C�Y�ɂ����̂��A�č��i�A���X�J�y�уn���C�������B�j�Q�O�O�O�X�܁A�A���X�J�ɂR�X�܁A�J�i�_�ɂV�X�܁A�R�X�^���J�ɂP�P�X�܁A�O�A�e�}���ɂS�X�܁A�n���C�ɂP�T�X�܁A�z���f�����X�ɂS�X�܁A���L�V�R�ɂR�W�X�܁A�v�G���g���R�ɂP�O�X�܁A�T�E�W�A���r�A�ɂP�S�X�܁A�x�l�Y�G���ɂQ�Q�X�܁A�p���ɂV�O�X�܁A���v�Q�V�X�Q�X�܂ł��邱�ƁA�A�퍐�́A�P�X�X�S�N�i�����U�N�j������{�ɂ�����Ɩ��g��̌v���L���A���{�̑����̃t�����`���C�W�[���҂ɑ��c�Ɗ������s���Ă������ƁA�B�����̉c�Ɗ����ɂ����āA�Q�O�O�P�N�i�����P�R�N�j�P���P�P�����瓯���P�R���̊ԁA�ɓ��������̒S���҂�JETRO NY�̒S���ҋy�є퍐������{�ɂ�����t�����`���C�Y��̏Љ���˗����ꂽ�u���[�J�[�ł���`�Ƌ��ɕč��P���^�b�L�[�B���C�X�r�[�����݂̔퍐�{�Ђ�K�₵�A�{�݂����w���Ĕ퍐�̃s�U�����H���A�{�����W��t�����e�B�[�V���c�A�}�O�J�b�v���̔̔����i�i���̒������ƁA�C���N�R���ɂ��A�ɓ��������y�ѓ��{��Ƃ̒S���҂炪��L�퍐�{�Ђ�K�₵�A���l�Ɏ{�݂����w���퍐�̃s�U�����H�������ƁA�D���N�S���ɂ��ɓ��������̒S���҂炪��L�퍐�{�Ђ�K�₵�A���̍ہA�퍐�s�U�̃T���v���̒������ƁA�ȏ�̎�����F�߂邱�Ƃ��ł���B
�E�@�Ƃ���ŁA���W�̕s�g�p�ɂ��o�^����̐R���������������ꍇ�A���W�@�T�O���Q���{���́A�u�O���̐R���̐������������ꍇ�ɂ����ẮA���̐R�������̓o�^�O�O�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����ď��W���ҁA��p�g�p���Җ��͒ʏ�g�p���҂̂����ꂩ�����̐����ɌW��w�菤�i���͎w��̂����ꂩ�ɂ��Ă̓o�^���W�̎g�p�����Ă��邱�Ƃ�퐿���l���ؖ����Ȃ�����A���W���҂́A���̎w�菤�i���͎w��ɌW�鏤�W�o�^�̎������Ƃ�Ȃ��v�Ƃ��Ă��邩��A�����ɂ����u�g�p�v�͓��{�����ɂ�����g�p�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ɖ�����ق��Ȃ��B�������A��L�C�ɔF�肵���g�p�́A��������č��ɂ�������̂ł���A���{�����ɂ�����g�p�Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�@�퍐�́A�����̒��Ȃ��ꂽ�̂͊C�O�ł��邪�A���{�ɂ����鎖�ƓW�J�Ɋւ�����̂ł�������ł̎g�p�Ɠ������ׂ��ł���Ǝ咣���邪�A�̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
(2) �{�����W��t����������ނ̔Еz
�A�@�퍐�́A�t�����`���C�W�[�̊J��c�Ɖߒ��ɂ����āA���L�@�Ȃ����I�̂Ƃ���{�����W�̕t���ꂽ�w�菤�i�̃J�^���O����{�����̎����Ɏ�n���A�܂��A�{�����W�̕t���ꂽ�N�������A�s�U�y�ш��H���Ɋւ���t�����`���C�Y�̋K�́A�y�ыƖ����j�̐����̂��߂Ɏ�n�����Ǝ咣����B
�@�@�@�@�L
�u�@ JETRO NY�i�Q�O�O�O�N�P�O���j
�@�A �ɓ��������i�Q�O�O�O�N�P�Q���^�Q�O�O�P�N�P���j
�@�B �A���A�P�W���p���i�Q�O�O�P�N�P���j
�@�C �p�V�t�B�b�N�A���C�A���X�i�Q�O�O�P�N�P���j
�@�D �v���U�N���G�C�g�i�Q�O�O�Q�N�P���^�Q���j
�@�E �A�N�A�l�b�g�i�Q�O�O�Q�N�V���P���j
�@�F �W���X�g�v�����j���O�i�Q�O�O�Q�N�W���Q�U���j
�@�G �X�g���x���[�R�[���Y�i�Q�O�O�Q�N�P�O���P�W���j
�@�H ���m�t�[�h�V�X�e���i�Q�O�O�R�N�Q���R���j
�@�I �I���b�N�X�A���t�@�i�Q�O�O�R�N�S���Q�Q���j�v
�C�@�m���ɁA�؋��i���P�A�Q�A�T�`�V�j�ɂ��A�퍐�́A���{�ɂ�����t�����`���C�Y�W�J�̂��߂̉c�Ɗ����Ƃ��āA��L�A�@�Ȃ����I�̎����ɁA��L�@�Ȃ����B�ɂ��Ă͕č���K�ꂽ������ɑ��A�{�����W�ƎЉ�ʔO�㓯��ƔF�߂��鏤�W�̕t���ꂽ�w�菤�i�̃J�^���O�i�{�i���U�E�R�����P�Q�j�A�����W�̕t���ꂽ�N�����i�{�i���P�E�R�����P�j���A�s�U�y�ш��H���Ɋւ���t�����`���C�Y�̋K�́A�y�ыƖ����j�̐����̂��߂Ɏ�n�������Ƃ��F�߂���B
�E�@�������A��L�@�Ȃ����B�́A��������č��ɂ����Ď�n���ꂽ���̂ł���A��L(1)�E�Ɠ��l�̗��R�ɂ��A���{�����ɂ�����g�p�Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�܂��A��L�C�Ȃ����E�ɂ��Ă��A���ꂪ���{�����ɂ����Ď�n���ꂽ���Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��i���W�@�T�O���Q���ɂ��A�����̎�����퐿���l����퍐���ؖ�����ӔC������Ɖ������B�j�B
�@�@�����āA��L�@�Ȃ����I�ɂ����ĔЕz���ꂽ�J�^���O�i���U�j�y�єN�����i���P�j�́A���{������t�����`���C�Y�W�J�̂��߂ɍs��ꂽ���̂ł����āA�퍐�̉�Ў��̂̐�`�A�t�����`���C�Y���Ƃ̕��@�E�������̐������s�����̂ł���ƔF�߂���B�����āA�퍐�́A���{�����ɂ����Ďw�菤�i�ł���u�s�U�v�Y�E�̔��������Ƃ͂Ȃ��A���{�̎��v�҂͔퍐�̃s�U�̒��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��邩��A��L�J�^���O�y�єN���������W�@�Q���R���W���́u������ށv�ɊY������Ƃ��Ă��A���̔Еz�́A�w�菤�i�ł���u�s�U�v�Ɋւ�����̂ł���Ƃ͔F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��B
(3) �E�F�u�y�[�W�ɂ��L��
�A�@�퍐�́A�����W�N�P�Q���Q�O�����猻�݂Ɏ���܂ŁA�E�F�u�y�[�W�ɂ���Ďw�菤�i�ł���s�U�y�уs�U�̒Ɋւ���L�����s���Ă���i���W�A�X�j�Ǝ咣����B
�C�@�m���ɁA�؋��i���W�A�X�A�Q�S�j�ɂ��A�퍐�́A�C���^�[�l�b�g�̃E�F�u�y�[�W�i�{�i���W�E�R�����R�A�{�i���X�E�R�����S�j�ɂ����āA�{�����W�ƎЉ�ʔO�㓯��ƔF�߂��鏤�W��\�����ăs�U�Ɋւ���L�����s���A�t�����`���C�W�[�̕�W���s���Ă��邱�ƁA��L�E�F�u�y�[�W�ɂ͓��{������A�N�Z�X���\�ł��邱�ƁA��L�E�F�u�y�[�W�́A���{�̌����G���W���uMSN�T�[�`�v�A�u�A�b�v���E�G�L�T�C�g�v���ɂ����āupapajohns�v�A�upapa john's�v�̌�Ō��������ꍇ�ɒ����Ɍ����ł���i�{�i���Q�S�E�R�����T�A�U�j���Ƃ��F�߂���B
�E�@�������A��L�E�F�u�y�[�W�́A�č��T�[�o�[�ɐ݂���ꂽ���̂ł����A���̓��e�����ׂĉp��ŕ\�����ꂽ���̂ł����āA���{�̎��v�҂�ΏۂƂ������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B��L�E�F�u�y�[�W�͓��{������A�N�Z�X�\�ł���A���{�̌����G���W���ɂ���Ă������\�ł��邪�A���̂��Ƃ́A�C���^�[�l�b�g�̃E�F�u�y�[�W�ł���ȏ㓖�R�̂��Ƃł���A�������ɂ���Ă͏�L�E�F�u�y�[�W�ɂ��L������{�����ɂ��g�p�ɊY��������̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@�퍐�́A�d���I���@�ɂ��L���Ɋւ��鏤�W�@�����́A���W�́u�g�p�v�ɂ��ꂪ�܂܂�邱�Ƃm�ɂ��邽�߂̂��̂ł���A�������@�{�s�O�̍L���s�ׂɂ����R�ɓK�p�����Ǝ咣����B�m���ɁA�E�F�u�y�[�W�ɂ��L���́A�����P�S�N�@����Q�S���ɂ��������ꂽ���W�@�Q���R���W���̂����A�u�L���v���u���e�Ƃ�����ɕW�͂�t���ēd���I���@�ɂ�����s�ׁv�ɊY��������̂Ƃ������Ƃ��ł���B�������A���s�ׂ���{�����ɂ��g�p�ɊY��������̂Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͏�L�̂Ƃ���ł��邩��A�퍐�̏�L�咣�͗��R���Ȃ��B
(4) �G���ɂ��L��
�A�@�퍐�́A�j���[�Y�E�E�B�[�N���̐��E�I�ɒ����ȎG���ɖ{�����W��t���ď��ƍL�����o���Ă���A����炪���{�ɂ����ĔЕz����Ă��邱�Ƃ͖����ł��邩��A����́A���i�Ⴕ���͖Ɋւ���L���ɊY�����A���W�@�Q���R���W���́u�g�p�v�ɊY������Ǝ咣����B
�C�@�؋��i���P�O�`�P�V�j�ɂ��A�퍐�́A�j���[�Y�E�E�B�[�N�Q�O�O�R�N�R���R�����i�{�i���P�O�E�R�����Q�T�j�A���R���P�O�����i�{�i���P�P�E�R�����Q�U�j�A���R���Q�V�����i�{�i���P�Q�E�R�����Q�V�j�y�ѓ��R���Q�S�����i�{�i���P�R�E�R�����Q�W�j�A�C���^�[�i�V���i���E�t�����`���C�W���O�Q�O�O�O�N�č��i�{�i���P�S�E�R�����Q�X�j�A�R�}�[�V�����E�j���[�X�E���[�E�G�X�E�G�[�Q�O�O�O�N�P�O�����i�{�i���P�T�E�R�����R�O�j�y�ѓ��Q�O�O�Q�N�R�����i�{�i���P�U�E�R�����R�P�j���тɃ��e�C���E�A�W�A�Q�O�O�R�N�X�����i�{�i���P�V�E�R�����R�Q�j�ɁA�{�����W�ƎЉ�ʔO�㓯��ƔF�߂��鏤�W��\�����ăs�U�Ɋւ���L�����s���A�t�����`���C�W�[�̕�W���s���Ă��邱�Ƃ��F�߂���B
�E�@�������A��L�G���́A���{�����ɂ����ĔЕz���ꂽ�Ƃ��Ă��A���{�����Ŕ��s���ꂽ���̂Ƃ͔F�߂��Ȃ���A���̓��e�����ׂĉp��ŕ\�����ꂽ���̂ł����āA���{�̎��v�҂�ΏۂƂ������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B
�@�@�����āA��L�G���̍L���́A�t�����`���C�Y�W�J�̂��߂ɍs��ꂽ���̂ł����āA�퍐��Ў��̂̐�`�A�t�����`���C�Y���Ƃ̍L���ł���ƔF�߂���B
�@�@�����āA�퍐�́A���{�����ɂ����Ďw�菤�i�ł���s�U�Y�E�̔��������Ƃ͂Ȃ��A���{�̎��v�҂͔퍐�̃s�U�̒��邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��邩��A��L�G���̍L���́A�w�菤�i�ł���s�U�Ɋւ����{�����ɂ����ĂȂ��ꂽ�L���ł���Ƃ͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�@���������āA��L�G���ɂ��L���́A���W�@�Q���R���W���́u�g�p�v�ɊY������Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
(5) �ȏ�Ɍ��������Ƃ���ɂ��A�{�����W�́A�w�菤�i�u�s�U�v�ɂ��ĐR�������̓o�^�O�R�N�ȓ��ɓ��{�����ɂ����Ĕ퍐�ɂ���Ďg�p���ꂽ�ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�E�������`���̕s���s�̈�@���ɂ���
�����W�̕s�g�p����R���ɂ��ď��W�o�^���ێ�����|�̐R���ɑ��Ă��ꂽ�ĐR�����ɂ��āA���������u�{���R���̐������p������B�v�Ƃ̐R�������A���̍ĐR�̐R���̎����������߂��i�����B
�@�����́A�{������R���ɂ����ĐR�����c�̂��t�B�b�c�i�ׂ̑i�����ɂ��ĐE���؋��������Ȃ��������Ƃ������Ė{���m��R���ɍĐR���R���锻�f�̈�E��������~�X�咣������̂ł��邪�A���̎咣�̎����́A�{�����W�̎g�p������F�肵���{���m��R���̏؋��]���̌��Ȃ����͎�����F���咣����ɉ߂��Ȃ����̂ł���B�����āA�R���̎����F��ɑ���s���́A�����Ƃ��āA�R������i�ׂɂ����Ă��̐��������߂�ׂ����̂ł��邩��A�{���m��R�����t�B�b�c�i�ׂ̑i�����ɂ��Ĕ��f�����Ȃ��������Ƃ́A�ĐR���R����u�m��R���ɉe�����y�ڂ��ׂ��d�v�Ȏ����ɂ��Ĕ��f�̈�E�����������Ɓv�ɊY��������̂łȂ��B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10282�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N12��24�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@�@�@��@��
�@�����̐��������p����B
�@�i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�@�@�����y�ї��R
��P ����
�@���������ĐR�Q�O�O�V�|�X�T�O�O�O�W�������ɂ��ĕ����Q�O�N�U���P�V���ɂ����R�����������B
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�������A�m��R���ɑ��čĐR�̐����������Ƃ���A�������p������Ƃ̐R�������ꂽ�̂ŁA���R���̎���������߂鎖�Ăł���B
�P �������ɂ�����葱�̌o�܁i�����̂Ȃ������j
(1) �퍐�́A���̏��W���i�ȉ��u�{�����W���v�Ƃ����A���̓o�^���W���u�{�����W�v�Ƃ����B�j��L����B
�@���W�o�^��Q�S�R�P�U�P�V��
�@�o��N�������a�S�W�N�T���P�O��
�@�o������N���������R�N�W���P�U��
�@���i�̋敪��S��
�@�w�菤�i���݂����A���ϕi�A������
�@�o�^�N���������S�N�V���R�P��
(2) �����́A�����P�V�N�W���R�O���A���W�@�T�O���P���Ɋ�Â��A�{�����W�̎w�菤�i�ł���u���ϕi�v�ɌW�鏤�W�o�^�̎���R���i�ȉ��u�{������R���v�Ƃ����B�j�𐿋������B
�@�������́A�{������R������������Q�O�O�T-�R�P�O�U�R�������Ƃ��ĐR�����A�����P�W�N�R���R�P���A�u�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R�������A���N�T���P�Q���A���R���͊m�肵���i�ȉ��A���̐R�����u�{���m��R���v�Ƃ����B�j�B
(3) �����́A�����P�X�N�P�Q���S���A���W�@�T�V���P���Ɋ�Â��A�{���m��R���ɑ���ĐR�𐿋������B
�@�������́A��L�ĐR�������ĐR�Q�O�O�V�|�X�T�O�O�O�W�������Ƃ��ĐR�����A�����Q�O�N�U���P�V���A�u�{���R���̐������p������B�v�Ƃ̐R�������A���̍��A���̓��{�������ɑ��B�����B
�Q �ʌ��i�ד��̌W��
(1) ���W���N�Q�i��
�@�퍐�́A������Ѓt�B�b�c�R�[�|���[�V�����i�ȉ��u�t�B�b�c�R�[�|���[�V�����v�Ƃ����B�j���{�����W���y�є퍐�̗L����ʎ����W���ژ^�P�A�Q�L�ڂ̊e���W����N�Q���Ă���Ƃ��āA�����P�U�N�V���U���A�t�B�b�c�R�[�|���[�V������퍐�Ƃ��ď��W���N�Q�i�ׂ���n���ٔ����ɒ�N�����i���������P�U�N(��)��V�U�U�R�������B�ȉ��u�t�B�b�c�i�ׁv�Ƃ����B�b�P�Q�j�B
�@���n���ٔ����́A�����P�X�N�P�P���T���A�t�B�b�c�i�ׂɂ��Ĕ����������n�����i�b�P�j�B
(2) ���W�o�^�����R������
�@�퍐�́A�����P�W�N�Q���P�V���A�t�B�b�c�R�[�|���[�V���������W����L���鏤�W�o�^��S�X�Q�T�T�S�U�����W�ɂ��āA�����R���𐿋��i�����Q�O�O�U�|�W�X�O�P�X�������Ƃ��ČW���B�ȉ��u�t�B�b�c�����R���v�Ƃ����B�j���A�������́A���N�P�O���Q�V���A�������ɂ��āu�{���R���̐����́A���藧���Ȃ��B�v�Ƃ̐R���������i�b�V�A�P�P�j�B
�R �R���̗��R�̗v�|
�@�R���́A�{���ĐR�̐����́A�K�@�ȍĐR���R�̎咣���������s�K�@�Ȑ����ł����āA���̕�����邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ɊY�����邩��A���W�@�U�P���ɂ����ď��p��������@�P�V�S���Q���ɂ����ď��p���铯�@�P�R�T���̋K��ɂ���Đ������p�����ׂ����̂Ƃ����B
(����)
��T ���ٔ����̔��f
�P �{���Ō������R��������R�Ƃ��āA���Ȃ킿�{���m��R���̍ĐR���R�Ƃ��Ď咣����Ƃ���́A�v�|�A�ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@ �R���ɂ����Ă͐E����`���̗p����Ă��邩��A�R�����͐ϋɓI�ɐE���R�����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�A �{������R���ɂ����āA�퍐���{������R�������̓o�^���O�R�N�ȓ��̊��ԁi�ȉ��u�{��������ԁv�Ƃ����B�j�ɖ{�����W���g�p�����������ؖ����邽�߂ɒ�o�����{���؋��ɂ͋^�킵���_���������B
�B �{������R���Ɠ������ɍٔ����ɌW�����Ă����t�B�b�c�i�ׂł́A�퍐�͖{��������ԓ��ɖ{�����W���g�p���Ă��Ȃ��������Ƃ����F���Ă�������A���W�@�T�U���̏��p��������@�P�U�W���̉^�p�ɂ��A�R�����c�̂��t�B�b�c�i�ׂ̑i�����ɂ��Ă̐E���؋����ׂ��s���Ă���A�{���؋����퍐�̖{�����W�̎g�p�̎�����F�肷��̂ɕs�K�ȏ؋��ł��邱�Ƃ��e�Ղɔ��������B
�C ������ɁA�{������R���̐R�����c�̂́A�t�B�b�c�i�ׂ̑i�����ɂ��ĐE���؋����ׂ��s��Ȃ��������߁A�{���؋��݂̂Ɋ�Â��Ĕ퍐�̖{��������Ԓ��̖{�����W�̎g�p�̎�����F�肵�A�{���m��R�������ꂽ�B
�D �ȏ�̂Ƃ���A�{���m��R���͕s�\���ȐR���Ɋ�Â��Ă��ꂽ���̂ł��邩��A�����i�ז@�R�R�W���P���X���̍ĐR���R������B
�Q �������Ȃ���A�����̏�L�咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̗��R�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
�@���W�@�T�V���Q�������p���閯���i�ז@�R�R�W���P���X���́u�����ɉe�����y�ڂ��ׂ��d�v�Ȏ����ɂ��Ĕ��f�̈�E�����������Ɓv�i�{���ł́A���p�̌��ʁA�u�m��R���ɉe�����y�ڂ��ׂ��d�v�Ȏ����ɂ��Ĕ��f�̈�E�����������Ɓv�Ɠǂݑւ��邱�ƂɂȂ�B�j�Ƃ́A�E�����������ł���ƔۂƂ��킸�A���̔��f�̔@���ɂ�蔻���̌��ʂɉe�����y�ڂ��ׂ��d�v�Ȏ����ł����āA�����҂������٘_�ɂ����Ď咣�����͍ٔ����̐E�������𑣂��Ă��̔��f�����߂��ɂ�������炸�A���̔��f��E�R�����ꍇ���������̂Ɖ������i��R�@���a�V�N�T���Q�O���������W�P�P���P�O���P�O�O�T�ŎQ�Ɓj�B�����āA�����������W�@�̊m��R���ɏ��p���ꂽ�ꍇ�ɂ����l�ɉ�����̂������ł��邩��A�O�R�ɓ�����R���ɂ����ē����҂��咣���Ă��Ȃ����������ɂ��Ċm��R�������f�����Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A�ĐR���R���锻�f�̈�E�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@������ɁA�����́A��L�̂Ƃ���A�{������R���ɂ����ĐR�����c�̂��t�B�b�c�i�ׂ̑i�����ɂ��ĐE���؋��������Ȃ��������Ƃ������Ė{���m��R���ɍĐR���R���锻�f�̈�E��������~�X�咣������̂ł��邪�A���̎咣�̎�|�́A�{���؋��̕]���ɓ�����A�t�B�b�c�i�ׂɂ����Ĕ퍐���{��������Ԓ��ɂ�����{�����W�̕s�g�p�̎��������F���Ă����������l�����ׂ��ł������|�̎咣�ɋA������̂ł���A�������{������R���ɂ����Ď��炻�̂悤�Ȏ咣�����Ȃ��������Ƃ͌����̎��F����Ƃ���ł��邩��A���ǁA�����̑O�L�咣�̎����́A�{���؋��Ɋ�Â��Ĕ퍐�̖{�����W�̎g�p������F�肵���{���m��R���̏؋��]���̌��Ȃ����͎�����F���咣����ɉ߂��Ȃ��̂ł���A�R���̎����F��ɑ���s���́A�����Ƃ��āA�R������i�ׂɂ����Ă��̐��������߂�ׂ����̂ł��邩��A��L�����̂Ƃ���A�{���m��R�����t�B�b�c�i�ׂ̑i�����ɂ��Ĕ��f�����Ȃ��������Ƃ́A�ĐR���R���锻�f�̈�E�ƂȂ���̂łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@���������āA�����̎咣���������R�́A���̎咣���̂ɏƂ炵���R���Ȃ��Ƃ����ق��Ȃ��A���ꂱ����̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�t�@������ɁA�����͖{������R���ɂ����Ĕ퍐��o�ɌW��{��������ԓ��ɂ�����{�����W�̎g�p�𗠕t����{���؋��̐M�p���ɂ��ċ^�`��悵�A������̗p���ׂ��ł͂Ȃ��|���咣���Ă������̂ł��邪�A�{���؋��̐M�p���̗L������������@�̓t�B�b�c�i�ׂɂ�����퍐�̒q�ȊO�ɂ��l�X�ȕ��@�����݂���̂ł���A����ɖ{���m��R���������{�����W�̎g�p�̎����ɌW�鎖���F��ɕs��������̂ł���A���̐��������߂ĐR������i�ׂ��N���Ė{���؋��̐M�p����e�N����r���L�����̂ł���B�܂��A�����́A�퍐���t�B�b�c�i�ד��̌W���̎�����F�����Ă������Ƃ�O��Ƃ��āA���̐E�������`�����������邪�A���W�o�^�̎���R���̐��x�ɂ����ẮA������ԓ��ɂ����鏤�W�g�p�̎����̑��ۂ����ƂȂ�Ƃ���A�����鎖���͏��W���Ҏ��g���ł��悭�m��Ƃ���ł��邩��g�p�����̎咣�E���ؐӔC�����W���҂ɉۂ����̂Ƃ����i���W�@�T�O���Q���j���ʁA���W���҂̎咣�E���ɂ�菤�W�g�p�̎�������̓I�ɓ��肳���ƂƂ��ɂ��̗��t���ƂȂ�؋�����o����A����ɑ��锽�؊����̑Ώۂ����m������A����R���̐������҂̔��؊����ɂ�菤�W���҂̎g�p�����ɌW�鎖���咣�̓��ۂ����������̂ł���B���̂悤�ȍ\���̏�L����R�����x�ɂ����ẮA�����Ƃ��āA�����҂̎咣�E���؊��������S�ɂȂ邱�Ƃ��\�肳��Ă���A�{���ɂ����Ă�����ƈقȂ���i�̎���̑��݂��M���Ȃ��̂ł��邩��A�퍐�̐E�������`���̕s���s����@������邱�Ƃ͂Ȃ����̂Ƃ����ׂ��ł���B����āA�����̏�L�咣�͎����ł���B
�R �ȏ�ɂ��A�{���ĐR�����́A���̑O��ƂȂ�ĐR���R�̎咣���咣���̗��R�̂Ȃ����̂ł��邩��A���ꂪ�s�K�@�Ȑ����ł����Ă��̕���ł��Ȃ����̂ɊY�����A���W�@�U�P���̏��p��������@�P�V�S���Q���ŏ��p����P�R�T���̋K��ɂ��p�����ׂ����̂Ƃ����R���̔��f�Ɍ��͂Ȃ����̂ƔF�߂��A���ɐR������@�Ƃ��鎖�R���Ȃ�����A�R���͓K�@�ł���A�{�������͗��R���Ȃ��B
�u�L���[�s�[�v�}�`���W�R�������������
���������ɂ�閳���R�������̐����s�����R�����������������B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10139�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N12��17�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@��@��
�@�������������Q�O�O�V�|�W�X�O�O�S�V�������ɂ��ĕ����Q�O�N�R���V���ɂ����R�����������B
�@�i�ה�p�͔퍐�̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�����y�ї��R
��P �����̋��߂��ٔ�
�@�啶���|
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�������A���L�P(1)�̔퍐�̏��W�i�ȉ��u�{�����W�v�Ƃ����B�j�́A���W�@�S���P���P�P�����͓����P�T���ɊY�����邩�炻�̏��W�o�^�͏��W�@�S�U���P���ɂ�薳���Ƃ����ׂ��ł���Ƃ��āA���L�P(2)�̂Ƃ��薳���R���i�ȉ��u�{���R���v�Ƃ����B�j�𐿋������Ƃ���A���������������R�������͐��藧���Ȃ��Ƃ̐R�����������߁A���������̎���������߂鎖�Ăł���B
(���|)
(3) �{�����W�̏̌ċy�ъϔO�ɂ���
�@�A�@�{�����W�̍\���́A�O�L��Q�̂P(1)�̂Ƃ���A�������̔��Ǝv�������������A�p�b�`���Ƃ����傫�Ȗڂ������c���̓�����`�����}�`�ł���Ƃ���A�����̓����I�e�p�͏�L(2)�̂Ƃ���䂪���ɂ����Ă����m�ƂȂ��Ă����u�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[�̓����ƕ���������̂ł��邩��A�{�����W�ɐڂ�������ҁE���v�҂��A�{�����W�ɌW��}�`���u�L���[�s�[�v�ƔF������ł��낤���Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���Ƃ����ׂ��ł���B���������āA�{�����W����́u�L���[�s�[�v�̏̌Ă���ƂƂ��ɁA���̐�̔��Ǝv�������������A�ڂ��p�b�`���Ƒ傫�����̗̂c�����͂��̐l�`�ł���u�L���[�s�[�v�̊ϔO������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@�C�@�퍐�́A�{�����W����u�L���[�s�[�v�̏̌Ă�������Ƃ������Ƃ��ł��邪�A�{�����W���琶����ϔO�́u���[�Y�E�I�j�[���̑n�삵���I���W�i���̃L���[�s�[�v�ł���|�咣����̂Ō�������ɁA�䂪���ɂ����āu�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[�����m�ƂȂ����o�܂���L(1)�A(2)�̂Ƃ���ł��邱�Ƃɉ����A�����S�N�R���P��������Џo�Ō|�p�Д��s�̑��V�G�s���u�L���[�s�[�]�́v�i�b��V�S���j�U�W�łɁu�E�E�E�L���[�s�[�����߂ē��{�ɂ��ڌ������A�����Ƃ����܂ɍ����I�ɕ��y���Ă���ł�����҃��[�Y�E�I�j�[���̑��݂͂��Ƃ��A���O����S���Ƃ����Ă悢�قǓ`�����Ȃ������B�h�͂��߂ɃL���[�s�[���肫�h�Ƃł��������A���Ȃ�̃L���[�s�[���D�Ƃł������[�Y�E�I�j�[���Ɋւ��Ă͖��m�ɂЂƂ��������Ƃ����邾�낤�B�����������ɂ��Ă��A�q�ǂ��̍��͓��R�Ƃ��āA��l�ɂȂ葊�����̃L���[�s�[���W�܂�悤�ɂȂ��Ă�����b���́A�����l�ł������B�������[�Y�E�I�j�[�����j�̖��O��m��A����Ɉӎ����͂��߂��̂͏\���N�O�ŁA�C�O����L���[�s�[�W�̎����ȂǂƂƂ��ɔޏ��̕����ނ���ɓ���A�m��Βm��قNj��������܂��Ă��Ă���̂��Ƃł���B�E�E�E�v�Ƃ��邱�Ƃ��l������ƁA����T�V�`��U�P���ɂ��F�߂���퍐�ɂ�郍�[�Y�E�I�j�[���̌����I�����Ȃ����͎��Ƃ̑��݂��l�������Ƃ��Ă��A�䂪���ɂ����āA�{�����W�̏o��o�^���͂��Ƃ�肻�̍��莞�ɂ����Ă��A�u�L���[�s�[�v�ɂ��āA�u���[�Y�E�I�j�[�����n�삵���I���W�i���̃L���[�s�[�v�Ƃ���ȊO�́u�L���[�s�[�v�Ƃ��B�R�Ƌ�ʂ��ĔF�m����Ă����Ƃ܂ł͓���F�߂邱�Ƃ��ł��Ȃ����A�{���S�؋��ɂ���Ă������鎖����F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A�퍐�̏�L�咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(4) ���p���W�P�`�U�̏̌ċy�ъϔO�ɂ���
�@�A�@���p���W�P�`�U�̍\���́A���ꂼ��O�L��Q�̂Q(1)�`(6)�̂Ƃ���ł���B
�@��L���p���W�̂����A�u�j�d�v�o�h�d�v�̉����W�������������ĂȂ���p���W�R�y�сu�L���[�s�[�v�̕Љ��������������ĂȂ���p���W�S����u�L���[�s�[�v�̏̌Ă������邱�Ƃ͖��炩�ł���A��L(2)�̂Ƃ���́u�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[�����m�ƂȂ��Ă������ƂɏƂ炷�ƁA�����̏��W����́A���̐�̔��Ǝv�������������A�ڂ��p�b�`���Ƒ傫�����̗̂c�����͂��̐l�`�ł���u�L���[�s�[�v�̊ϔO���邱�Ƃ����炩�ł���B
�@�܂��A���p���W�U�̍\���́A�������̔��Ǝv�������������A�ڂ��p�b�`���Ƒ傫�����̗̂c���̐l�`��͂��ĂȂ���̂ł���Ƃ���A��L(2)�̂Ƃ���́u�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[�����m�ƂȂ��Ă������ƂɏƂ炷�ƁA���p���W�U����́u�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO����Ƃ����ׂ��ł���B
�@����ɁA���p���W�P�A�Q�y�тT�̍\���́A�O�L��Q�̂Q(1)�A(2)�ɂ���Ƃ���A���p���W�U�̍\���ƂȂ��Ă���l�`�̊�̗��j�t�߂���˂��o�����Z���r�̐�ɂT�{�w���J�������肪�O���ɍ����o����A�r�Ɉߕ��Ǝv�������̂𒅂��Ă�����̂ł���i�Ȃ��A���p���W�Q�y�тT�ɂ��Ă͏�L�̗���ʒu�ɍ��E�ɐL�т鏰�ʂƎv���������`����Ă���B�j�Ƃ���A�u�L���[�s�[�v�̍ۗ������������u�������̔��Ǝv�������������A�ڂ��p�b�`���Ƒ傫���v�Ƃ����e�p�ɂ��邱�Ƃ��炷��ƁA����ƕ�������\����L������p���W�P�A�Q�y�тT������u�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO��������ƔF�߂���B
�@�C�@�퍐�́A���p���W�P�`�U����u�L���[�s�[�v�̏̌Ă�������Ƃ������Ƃ��ł��邪�A���p���W�P�`�U���琶����ϔO�́u�L���[�s�[�}���l�[�Y�̃L���[�s�[�v�ł���|�咣����̂ŁA���̓_�ɂ��Č�������B
�@�m���ɁA���a�T�X�N�R���T��������Ѝu�k�Д��s�̑��V�G�s���u�L���[�s�[����v�i�b��V�T���j�S�T�łɂ́u���{�I�ȁA���{�Ńf�U�C�����ꐶ�Y���ꂽ�L���[�s�[�̓Z�����C�h���̑��̂��l�`�����łȂ��A�����̏��i�̃u�����h����A�L���ނ̃C���X�g�Ƃ��āA����ɗe���P�[�X�Ƃ��Ă��L���g��ꂽ�B�A�����J�Ɠ��l�ł���B���̋L���Ƀn�b�L��������̂ł́A���ŁA�p�o�������B������A�L���[�s�[�̌`�̂��̂���A���������̃x�r�[����̔��ɂ܂Ńf�U�C������Ă���B���t���C�p�����A�����łp�o����A�w��P���[�g�������肻���ȑ傫�ȃL���[�s�[���A�t���C�p�����f���Ē��̋������̓X���ɗ����Ă����̂��v���o���B�v�Ƃ̋L�ڂɑ����āu���݂��A���{�ŃL���[�s�[�Ƃ����A�N�ł��������Ȃ̂��A�}���l�[�Y���낤�B���̉�Ђ́A���ɎЖ��܂Łw�L���[�s�[������Ёx�Ƃ��ĂQ�T�N�ȏ�ɂȂ�B�䂪���̃}���l�[�Y���[�J�[�̍ő��ŁA�ʋl�ɂ���]������B���{�l�̐H�����̑��l���ɍ��킹�A�}���l�[�Y��h���b�V���O�̑��A�e��x�r�[�t�[�h�ȂǁA���������s��ɑ���o���Ă���B�ߋ��ɁA���i�i�Ƃ��ĐV�����f�U�C�������L���[�s�[�l�`���A�召�o���Ă���A���̒��̓��ɑ�^�̂��̂́A�������X���X�Ō�������B�܂��A�ȑO�ɂQ�O�Z���`���̃L���[�s�[�Ƀ}���l�[�Y���l�߁A���̂܂܃`���[�u����݂����Ɏg���鏤�i������o���ꂽ���Ƃ��������B���̉�ЂƃL���[�s�[�Ƃ̏o��͌Â��A��Ђ̗��j�ƂƂ��ɓ`�����Ă���B�v�Ƃ̋L�ڂ�����悤�ɁA�L���[�s�[�����i���̐�`�L���Ɏg�p�����Ⴊ�l�X���钆�ŁA�u�L���[�s�[�}���l�[�Y�v�͋ɂ߂Ē����ł���Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�������Ȃ���A��L(3)�Ɠ��l�̗��R�ɉ����A��L(1)�A(2)���тɍb��V�T��������p������L�L�ڂ̂����O�i�̕����ɂ�����Ƃ���A�䂪���ɂ����ẮA�����̊�Ƃ��u�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[���`�L���Ɏg�p���Ă��������ɏƂ炷�ƁA�䂪���ɂ����āA�u�L���[�s�[�v���������x���ՓI�Ȃ����͈�ʓI�ȃL�����N�^�[�Ƃ��ĔF�m����Ă���������ے肷�邱�Ƃ͍���ł��邩��A����̊�Ƃƌ��т��Ȃ��u�L���[�s�[�v�̊ϔO�����p���W�P�`�U���琶���邱�Ƃ���T�ɔے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���������āA�퍐�̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�E�@�܂��A�퍐�́A���ɁA���p���W�P�`�U����u�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO��������Ƃ��Ă��A���p���W�P�`�U���琶����u�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO�́A�����̎w�菤�i�ɌW�鏤�i�݂̂��������̂ł͂Ȃ��A�u���[�Y�E�I�j�[���̑n�삵���L�����N�^�[��l�`�����łȂ��A����ɗނ���L�����N�^�[��l�`��ʁv���������̂ł��邩��A���̂悤�ȏ̌ċy�ъϔO�Ɍ����̏��i���������̂Ƃ��Ă̎��ʗ͂͂Ȃ��̂ł���A�{�����W�ƈ��p���W�P�`�U�̗ޔۂ���������ɓ������ẮA���ʗ͂�L����O�ς݂̂�v���Ƃ��đΔ䂷�ׂ��ł���|�咣����B
�@�������Ȃ���A��L�C�̂Ƃ���A�������u�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[���}���l�[�Y�̐�`�L���Ɏg�p���邱�Ƃɂ���āA�u�L���[�s�[�}���l�[�Y�v�Ƃ��Ē����ƂȂ�A�u�L���[�s�[�v�̕t���ꂽ�}���l�[�Y�𑼂��环�ʂ��邱�Ƃ��\�Ƃ��Ă��鎖����������炩�Ȃ悤�ɁA�u�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO�ɉ��环�ʗ͂��Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���A�퍐�̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(5) �{�����W�ƈ��p���W�P�`�U�̗ޔۂɂ���
�@��L(3)�A(4)�ɂ��ƁA�{�����W�ƈ��p���W�P�`�U����́A���Ɂu�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO������̂ł���A���A�����ɐ�������Ƃ��肻�ꂼ��̎w�菤�i�͓��ꖔ�͗ގ��̊W�ɂ��邩��A�{�����W�ƈ��p���W�P�`�U�́A�݂��ɑ�����邨����̂���ގ��̏��W�Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̓_�ɂ��āA�퍐�́A���݂ł́A���퍐�ȊO�ɂ������̎҂��u�L���[�s�[�v�Ɋ֘A���鏤�W�o�^�āA���i������Ȃǂ��Ďg�p���Ă���Ƃ�������̎�����l������ƁA�{�����W���w�菤�i�Ɏg�p�����Ƃ��Ă��A���p���W�P�`�U��t�������i�Əo���̌�F�������邨����͂Ȃ��|�咣����̂ŁA��������B
�@����̎�����l�����邱�Ƃɂ��A�ގ����鏤�W��t�������i�ɂ��ďo���̌�F�������邨���ꂪ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��ł��邽�߂ɂ́A���Y�w�菤�i�ɌW�����̎����O��Ƃ��āA��F�����̂����ꂪ�Ȃ����̂ƔF�߂��邱�Ƃ��K�v�ł���B
�@�{���ɂ����ẮA�m���ɁA��L(1)�A(2)��(4)�C�̂Ƃ���A�����̊�Ƃ��u�L���[�s�[�v�̃L�����N�^�[�����i���̐�`�L���Ɏg�p���Ă�����̂ƔF�߂��邪�A�{�����W�ɌW��w�菤�i�ł���u���������A�ʎ������A���������A�����p��W���[�X�v�̎������ɂ��Ă݂�ƁA�{���S�؋����������Ă��A�Ⴆ�A���W�ȊO�̖ڈ�ɂ���ďo�������ʂ��Ď�����s���Ă���Ƃ��A���邢�͋t�ɁA�����̎҂��u�L���[�s�[�v���͂���ɗނ���W�͂�t�������i��̔����Ă���A�u�L���[�s�[�v�̊O�ς̔����ȑ���ɂ��o�������ʂ��Ď�����s���Ă���Ȃǂ̎���̎���F�߂��邱�Ƃɂ��A����̏̌ċy�ъϔO���鏤�W��t�������i�ɂ��ďo���̌�F�������邨���ꂪ�Ȃ��ƔF�߂�ɑ���Ȃ��B
�@�ނ���A��L�w�菤�i�ɌW�鏤�i�́A�����̏ꍇ�A�d����̒i�K�ɂ����āA�����Ɛ��ʂ��w�肵�āA�������͕����ɂ���������ق��A�����X���ɂ����āA���i���̊ȗ��ȕ\�L��t���Ē�A��ʏ���҂ɂ���čw������邱�Ƃ��ʏ�̎���ԗl�ł��邱�Ƃ͌o�����㖾�炩�ł��邩��A����ߒ��̂�����i�K�ɂ����āA��L�̎������ɂ����ẮA�̌ĂƂ���Ɋ�Â��\�L�����i�̏o���f�����ł̏d�v�ȗv�f�ƂȂ���̂ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B
�@��������ƁA��L�̂Ƃ��蓯��̏̌ċy�ъϔO�i�u�L���[�s�[�v�j����{�����W�ƈ��p���W�P�`�U�̗ގ����ɂ��āA�{�����W�̎w�菤�i�ɌW�����̎�����l�����邱�Ƃɂ��A�����ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł��邩��A�퍐�̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
(6) �{�����W�ƈ��p���W�P�`�U�̎w�菤�i�́A�O�L��Q�̂P(1)�y�тQ(1)�`(6)�̂Ƃ���ł���A�{�����W�̎w�菤�i�ł���u���������A�ʎ������A���������A�����p��W���[�X�v�ɂ��ẮA���̂��ׂĂ��A���p���W�R�A�S�y�тU�̎w�菤�i�Ɋ܂܂�Ă���A���p���W�P�A�Q�y�тT�̎w�菤�i�ɂ͂�������H���i���܂܂�Ă��邱�Ƃ���A�{�����W�ƈ��p���W�P�`�U�̎w�菤�i�͓��ꖔ�͗ގ�����Ƃ����ׂ��ł���B
�@��������ƁA�{�����W�́A���̓o�^�o��̓��O�̓o�^�o��ɌW�鑼�l�̓o�^���W�ł�����p���W�P�`�U�Ɨގ����鏤�W�ł����āA���̏��W�o�^�ɌW��w�菤�i���͂���ɗގ����鏤�i�ɂ��Ďg�p������̂Ƃ��ďo�肳�ꂽ���W�ł��邩��A���W�@�S���P���P�P���Ɋ�Â��ď��W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���A���̓o�^�͓����Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂Ƃ��킴��Ȃ��B
�@���������āA�{�����W�̓o�^�����W�@�S���P���P�P���Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����R���̔��f�͌��ł���B
�Q �퍐�̎咣�ɂ���
(1) ���W�@�Q�X���Ɋ�Â��咣
�퍐�́A���p���W�P�A�Q�A�T�y�тU�́A���[�Y�E�I�j�[�����n�삵���L���[�s�[�l�`���������Ǝ��ɐ}�ĉ����ď��W�o�^�o����������̂ł���A���o��̓��O�ɐ����Ă������[�Y�E�I�j�[���̒��쌠�ƒ�G������̂ł��邩��A�����������̈��p���W���g�p���Ė����R�������y�ѐR������i�ׂ̒�N�����邱�Ƃ͏��W�@�Q�X���Ɉᔽ����|�咣����B
�@���W�@�Q�X���́A�u���W���ҁE�E�E�́A�w�菤�i�E�E�E�ɂ��Ă̓o�^���W�̎g�p�����̎g�p�̑ԗl�ɂ��E�E�E���̏��W�o�^�o��̓��O�ɐ��������l�̒��쌠�ƒ�G����Ƃ��́A�w�菤�i�E�E�E�̂�����G���镔���ɂ��Ă��̑ԗl�ɂ��o�^���W�̎g�p�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�ƋK�肵�A���W�@�ɂ�����i���W���܂ށj�W�͂́u�g�p�v�ԗl�ɂ��ẮA���@�Q���R���P�`�W���Ɍ���I�ɗ���Ă���Ƃ���A�����R�������y�ѐR������i�ׂ̒�N�́A��L�e������̍s�ׂ̂�����ɂ��Y�����Ȃ�����A���쌠�Ƃ̒�G�̗L����_����܂ł��Ȃ��A���W�@�Q�X���Ɋ�Â��퍐�̎咣�͎����ł���B
�@�Ȃ��A���W�@�Q�X���́A���W���҂̏��W�̎g�p�����W�o�^�o��O�̏o��┭���ɌW�鑼�l�̌����ƒ�G���Ȃ��͈͂Ɍ��肷�邱�Ƃɂ��A���W���Ƒ��̌����Ƃ̒�����}��K��ł���A���W���҂��ގ����鑼�l�̏��W�o�^�̖����𐿋�����ꍇ�ł���{���ɗސ����ׂ���b�ƂȂ鎖����F�߂��Ȃ��B
(2) �������p�̎咣
�@�퍐�́A���[�Y�E�I�j�[���̒��앨�ł���u�L���[�s�[�v�̒����������p���W�P�`�U�ɂ����Ė����ŗ��p���Ă��錴�����A�u�L���[�s�[�v�̒��쌠���������A�{�����W�̓o�^�����퍐�ɑ��Ă��̖������咣���邱�Ƃ́A�����ȋ��������ɔ�������̂ł���A�����̗��p�ł���|�咣����̂ŁA�ȉ��ɂ����Č�������B
�@�A�@���W�@�́A��L(1)�̂Ƃ���A���쌠���Ƃ̒�G������K���u������A���@�S�U���ɂ����āA���W�o�^���Ƃ��邱�Ƃɂ��ĐR���𐿋����邱�Ƃ��ł���|��߁A���̂��߂̗v���Ƃ��Ė������R���K�肵�Ă���Ƃ���A�����R�������̎�̂ɂ��ď��W�@��̖����̐����͂Ȃ��B�����āA���W�@�͏��W�o�^�ɂ��Đ���`���̗p���Ă��邩��A����o�^���W�̏��W���҂��A���Y�o�^���W�͈��p���W�Ɨގ��̏��W�ł���Ƃ̖������R�i���W�@�S���P���P�P������̖������R�j��������邽�߂ɂ́A���̒n�ʂ�L������p���W�̏��W�o�^�ɂ��Ė����R�����������A������Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ邪�A���l�̒��쌠�ƒ�G���邱�Ƃ͏��W�o�^�̖������R�Ƃ͂���Ă��Ȃ��B
�@��������ƁA���W�@��A���l�̒��쌠�ɒ�G���鏤�W�ł����Ă��A���ꂪ��U�o�^�����A��G�̈ꎖ�������Ė����Ƃ���邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł���A���̂悤�ȏ��W���A���Y���W�o�^�o��̓�����̏o��ɌW�鏤�W�Ƃ̊W�ł́A���p���W�ƂȂ蓾��̂ł���A���p���W�̏��W���҂��A���W�@�S���P���P�P���ᔽ�����R�Ƃ��āA����Ɨގ��̏��W�ɌW�鏤�W�o�^�̖����R�����������邱�Ƃɏ��W�@��̖��͂Ȃ��B
�@�Ƃ���ŁA���W�@�S���P���P�P���́A���ꖔ�͗ގ��̏��W�������o�^����Ă��܂����ꍇ�ɂ����āA����炪���ꖔ�͗ގ��̏��i���Ɏg�p�����A����ҁE���v�҂ɂ����ď��i���̏o���ɂ��Č�F�����������A���W�g�p�҂̋Ɩ���̐M�p�̈ێ���}��A�����ĎY�Ƃ̔��W�Ɋ�^���A���킹�Ď��v�҂̗��v��ی삷��Ƃ������W�@�̖ړI���B�����Ȃ��Ȃ邱�Ƃ���A�����o�^��Q���R�Ƃ��ċK�肵�A���l�̎�|�œ��@�S�U���P���P���ɂ����Ė������R�Ƃ���Ă�����̂ƍl������B�����āA���̂悤�ȏꍇ�ɂ����āA���i���̏o���ɂ��Č�F�����������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́A�����R�������ɌW�鏤�W�o�^�����p���W�ɌW�鏤�W�o�^�̂����ꂩ������Ƃ���K�v������Ƃ���A���W�@�ɂ����ẮA��L�̂Ƃ���A���ɌW�鏤�W�o�^�ɂ��Ă̖����R��������҂��Ė������R�̗L����R�����A�����Ƃ��鐧�x���̗p���Ă�����̂ł���B
�@�C�@�ȏ��O��Ƃ��Ė{���ɂ��Ă݂�ƁA�{�����W�����p���W�P�`�U�Ɨގ��̏��W�ł��邱�Ƃ͏�L�P�̂Ƃ���ł��邩��A�������퍐�ɑ��Ė{�����W�o�^�������ł���Ƃ̎咣�����邱�Ƃ�������Ȃ��Ƃ���A�����͖{�����W�o�^�̖����R�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ����ƂƂȂ�A���p���W�P�`�U�Ƃ����Ɨގ�����{�����W���������邱�ƂƂȂ�Ƃ���A�{�����W�ƈ��p���W�����Ɏg�p�����ƁA���i�̏o���ɂ��Ď���҂���v�҂̊ԂŌ�F�����������A���W�@�̏�L�ړI�ɔ����鎖�Ԃ������\����ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�܂��A�٘_�̑S��|�ɂ��ƁA�����́A���[�Y�E�I�j�[�����͂��̈�Y���c���L���[�s�[�̒��쌠�̏��n�����퍐����A�L���[�s�[�̃L�����N�^�[�̎g�p�ɂ��ċ������Ă��Ȃ��ƔF�߂�����̂́A���[�Y�E�I�j�[���̃L���[�s�[�ɂ��Ă̒��쌠�͊��ɂ��̕ی���Ԃ��o�߂��Ă���ƔF�߂���B
�@����ɁA�٘_�̑S��|���тɏ�L�P(4)�C�ŔF�肵���Ƃ���ɂ��ƁA�������L���[�s�[�̃L�����N�^�[���}���l�[�Y�̐�`�L���ɐ��\�N�̒����ɂ킽��p���I�Ɏg�p���Ă������Ƃɂ��A�䂪���ɂ����āu�L���[�s�[�}���l�[�Y�v���ɂ߂Ē����ƂȂ������Ƃ���A�u�L���[�s�[�v�̏̌ċy�ъϔO������p���W�P�`�U�́A�{�����W�̎w�菤�i�ɂ��Ċi�ʂ̎������ʗ͂��l������Ɏ����Ă���ƔF�߂���B
�@�E�@��L�A�̂Ƃ���̏��W�@���̗p���鐧�x��O��Ƃ��āA��L�C�̊e������l������ƁA�{���ɂ����āA�퍐�����[�Y�E�I�j�[���ɗR�����钘�쌠�Ɋ�Â��Ĉ��p���W�P�`�U�ɌW�鏤�W�o�^���Ƃ��邱�Ƃ�����ł��邱�Ƃ��l�����Ă��A���W�@�ɓK�����錴���̖����R�������y�т��̐R���ɑ���{������i�ׂ̒�N�������̗��p�ł����ċ�����Ȃ��Ƃ�����A����҂���v�҂̊ԂŌ�F�������邨����������邱�ƂƂȂ��Ă���ނȂ��Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����āA���Ɍ����̌����̗��p�������t�����̓I�Ȏ����̎咣���͂Ȃ�����A�퍐�̎咣���̗p���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�R ��L�P�̂Ƃ���A�{�����W�̓o�^�͏��W�@�S���P���P�P���Ɉᔽ���Ă��ꂽ���̂Ƃ͂����Ȃ��Ƃ����R���̔��f�͌��ł��邩��A������R�P�͗��R������A��L�Q�̂Ƃ���A�퍐�̎咣�͂�������̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ�����A�R���ɂ͌��_�ɉe�����y�ڂ���@������Ƃ��킴��Ȃ��B
��U ���_
�@�ȏ�̎���ł��邩��A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A�R���͎�������Ƃ�Ȃ��B
�@�@�@�@�@

�@�{�����W�o�^�@��S�X�S�W�Q�P�O��
�@�w�菤�i�@��R�Q�ށu���������C�ʎ������C���������C�����p��W���[�X�v
�@�o����F�����P�U�N�P�P���Q�Q��
�@�o�^���F�����P�W�N�S���Q�W��
�@ �@�@�@

�@���p���W�P�@�o�^��S�X�T�P�W�U��
�@�w�菤�i
�@��S�T�ށ@���ނɑ����Ȃ��H���i�y�щ����i
�@�o�^�o����F���a�R�P�N�S���U��
�@�ݒ�o�^���F���a�R�Q�N�P���Q�X��
�@�@�@
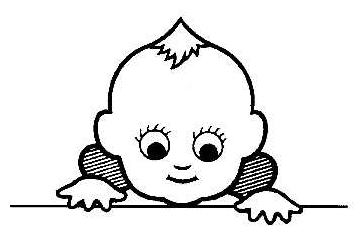
�@���p���W�Q�@�o�^��S�S�O�W�O�V�T��
�@�w�菤�i
�@��R�O�ށ@�R�[�q�[�y�уR�R�A�C�R�[�q�[���C���C�������C���h���Ȃ�
�@�o�^�o����F�����P�P�N�W���Q�O��
�@�ݒ�o�^���F�����P�Q�N�W���P�P��
�@�@�@�@�@�@�@�j�d�v�o�h�d
�i�W�������j
�@���p���W�R�@�o�^��S�T�T�V�O�T�P��
�@�w�菤�i
�@��R�Q�ށ@�r�[���C���������C�ʎ������C�����p��W���[�X�C���������C�r�[�������p�z�b�v�G�L�X
�@�o�^�o����F�����P�R�N�U���P��
�@�ݒ�o�^���F�����P�S�N�S���T��
�u�L�V���g�[���^�w�x�k�h�s�n�k�v���W����
���������ɂ�閳���R�������̐����s�����R�����ێ����������B��
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10086�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����20�N11��27�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@��@��
�P ������̐���������������p����B
�Q �i�ה�p�͌�����̕��S�Ƃ���B
�@�@�@�����y�ї��R
��P ����
�@�������������Q�O�O�U�|�W�X�P�S�T�������ɂ��ĕ����Q�O�N�P���Q�Q���ɂ����R���̂����u�o�^��P�U�X�Q�P�S�S���̂Q�ɂ��Ă̐R�������͐��藧���Ȃ��B�v�Ƃ̕������������B
(����)
��T ���ٔ����̔��f
�P ������R�P�i���W�@�S���P���P�U���Ɋւ��锻�f�̌��j�ɂ���
(1) ���i�̕i�����͖̎��i�ȉ��ł́A���i�ɂ��Ă̂ݏq�ׂ�B�j�̌�F���邨���ꂪ���鏤�W�ɂ��ẮA���v�ɔ�����Ƃ̎�|����A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��|�K�肳��Ă���i���W�@�S���P���P�U���j�B����|�ɏƂ炷�Ȃ�A���i�̕i���̌�F���邨���ꂪ���鏤�W�Ƃ́A�w�菤�i�ɌW�����̎���̉��ŁA����Җ��͎��v�҂ɂ����āA���Y���W���\�����Ă���ƒʏ헝�������i���Ǝw�菤�i���L����i���Ƃ��قȂ邽�߁A���W��t�������i�̕i���̌�F�������邨���ꂪ���鏤�W���w�����̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@�{���ɂ��Ă݂�ƁA�o�^��P�U�X�Q�P�S�S���̂Q�̏��W�́A�ʎ��@�̂Ƃ���A�u�L�V���g�[���v�y�сu�w�x�k�h�s�n�k�v�̕������Q�i�ɉ������������̂ł��邩��A�w�菤�i�ɌW�����̎���̉��ŁA����Җ��͎��v�҂́A���̎g�p����鏤�i�́A�L�V���g�[�����܂܂�Ă�����̂ƔF���A��������B�����A�w�菤�i�́A�ʎ��B�u�w�菤�i�ژ^�Q�v�L�ڂ̂Ƃ���A��������L�V���g�[�����g�p�������i�Ɍ��肳��Ă���B���������āA�����W�́A���̎w�菤�i�ɌW�����̎���̉��ŁA����Җ��͎��v�҂ɂ����ē����W���\�����Ă���ƒʏ헝�������i���Ǝw�菤�i�̗L����i���Ƃ��قȂ邱�Ƃ͂Ȃ��A�����W��t�������i�̕i���̌�F�������邨����͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�@���̓_�ɂ��āA������́A�퍐�͐����̂P�O�O�����L�V���g�[���łȂ��Ö�����Y�������`���[�C���K�����ɂ��A�o�^��P�U�X�Q�P�S�S���̂Q�̏��W���g�p���Ă��邩��A���W�@�S���P���P�U���ɊY������Ǝ咣����B
�@�������A���v�ɔ����鏤�W�̓o�^��r������Ƃ������W�@�S���P���P�U���̎�|�ɏƂ炷�Ȃ�A���W�@�S���P���P�U���ւ̊Y�����̗L���́A���W���\�����Ă���ƒʏ헝�������i���Ǝw�菤�i�̗L����i���Ƃ��قȂ�A���W��t�������i�̕i���̌�F�������邨���ꂪ���邩�ۂ�����Ƃ��Ĕ��f�����ׂ����̂ł���A���ۂɏ��W���g�p�������i���ǂ̂悤�ȕi����L���Ă��邩�́A���W�@�S���P���P�U���ւ̊Y�����̗L���ɉe�����y�ڂ����̂ł͂Ȃ��B���������āA������̏�L�咣�́A���̎咣���̎����ł���B
�@�܂��A����Җ��͎��v�҂́A����̎���̉��ŁA�o�^��P�U�X�Q�P�S�S���̂Q�̏��W���\������i���ɂ��āA�L�V���g�[�����g�p�����Ö������Y�����ꂽ���̂ƔF������Ɖ�����A�L�V���g�[���P�O�O������Ȃ�Ö����݂̂��Y�����ꂽ���̂ƔF�����邱�Ƃ͂Ȃ����̂Ɖ������B���������āA������̏�L�咣�́A���̓_����������ł���B
(2) ���������āA�R�����A�o�^��P�U�X�Q�P�S�S���̂Q�ɌW�鏤�W�ɂ��āA���W�@�S���P���P�U������̏��i�̕i���̌�F���邨���ꂪ���鏤�W�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ɣ��f�����_�Ɍ��͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł����āA������R�P�͗��R���Ȃ��B
�Q ������R�Q�i���W�@�R���P���U���̊Y�����ɂ��Ĕ��f���Ȃ��������j�ɂ���
�@�O�L��Q�A�P�̂Ƃ���A������́A�����P�W�N�P�O���P�O���A�o�^��P�U�X�Q�P�S�S�����W�o�^�ɂ��āA���W�@�S���P���P�U���ɊY������Ƃ̖������R������Ǝ咣���Ė����R���������������Ɓi�b�a��Q�V���؋y�ѕ٘_�̑S��|�j�A���̌�A�����P�X�N�P���P�T���t���R�������ٔ����ɂ����āA���W�@�R���P���U���ɊY�����邱�Ƃ����������R�ɒlj����A�����̗��R��lj��I�ɕύX�������Ƃ��F�߂���i�b�a��Q�W���؋y�ѕ٘_�̑S��|�j�B
�@���W�@�T�U���P���A�����@�P�R�P���̂Q��P���́A�R���������̕�́A���̗v�|��ύX������̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��|�K�肵�Ă���B���K��́A�R�������ҊԂ̍t���ƐR�����Ԃ̒Z�k��}���|�ŋK�肳�ꂽ���̂ł���B
�@������̍s������L�������R�̒lj��́A�R���������ɋL�ڂ��ꂽ�������R�Ƃ͓��e�̈قȂ閳�����R��lj�������̂ł���A�퐿���l�̖h��ɑ傫�ȉe����^���A�ēx���_�̋@���^���Ȃ��Ɩh��̋@������킹�邨����̂�����̂Ƃ������Ƃ��ł���B���������āA�R�����A������ɂ�鐿���̗��R�̕ύX���A���W�@�T�U���P���E�����@�P�R�P���̂Q��P���̋K��ɂ�苖����Ȃ����̂Ƃ��āA�����̗��R�̕ύX�ɂ��lj����ꂽ�������R�ł��鏤�W�@�R���P���U���ւ̊Y�����ɂ��Ĕ��f���Ȃ������_�ɁA�葱��̌��͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł����āA������R�Q�͗��R���Ȃ��B
�R ���_
�@�ȏ�̂Ƃ���A������咣�̎�����R�͂���������R���Ȃ��B������͂��̑��~�X�咣���邪�A�R���ɂ�����������ׂ����̑��̈�@���Ȃ��B
�@�@�@�@

�@�@�@�@�{���o�^���W�F�@��P�U�X�Q�P�S�S���̂Q
�@�@�@�@�w�菤�i�@�@�F�@�@��30�ށ@�L�V���g�[�����g�p�����`���[�C���K���C�L�V���g�[�����g�p�����`���R���[�g�Ȃ�
�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v���W�s���g�p�����������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10347�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N02��24�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
��Q ���Ă̊T�v
�P �{���́A�������L���鉺�L���W�o�^�i�{�����W�o�^�j�ɂ��āA�퍐�����W�@�T�P���i�s���g�p�ɂ�鏤�W�o�^�̎�����j�Ɋ�Â����W�o�^�̎���R���𐿋������Ƃ���A�������������F�e����R�����������Ƃ���A���������̎���������߂����Ăł���B
�Q ���_�́A�����ɂ��Ȃ���Ă��鉺�L�\���i�{���g�p�\���j�̎g�p���A�@���W�I�g�p�ɓ����邩�A�A���L���p���W���g�p����퍐�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�Ⴕ���͖ƍ���������̂��A�y�сA�B���ꂪ�����ɂ��̈ӂɂȂ��ꂽ���̂ł��邩�A�ł���i���W�@�T�P���P���j�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L
�y�{�����W�z

�E���W�E�w�菤�i�y�юw���
��X��
�u�^���ς݂̎��C�e�[�v�E�R���p�N�g�f�B�X�N�E���f�B�X�N���̑��̃��R�[�h�C�^��ς݂̃r�f�I�f�B�X�N�E�r�f�I�e�[�v�E�R���p�N�g�f�B�X�N�E���f�B�X�N�v
��S�P��
�u���y�̉��t�v
�E�o�^�������P�S�N�V���T��
�E���W�o�^��S�T�W�Q�O�V�S��
�y�{���g�p�\���z

�E�g�p�ԗl
�̔�����Ă���u�^���ς݂̃R���p�N�g�f�B�X�N�v�̕\�ʓ��ɕ\����
�y���p���W�z
�@

�i���|�j
�� �ȏ�̎����ɂ��A���p���W�́A�䂪���ɂ����Ă��G���u�d�k�k�d�v�̊��s�⑽���̃��C�Z���X��ʂ��Ă��̃u�����h���L���Z�����Ă���Ƃ������Ƃ��ł��A�x���Ƃ��{���R���p�N�g�f�B�X�N�̔̔����J�n���ꂽ�����P�S�N�S���R�������i������\��A�쐬�̕����P�T�N�Q���U���t�����k�b�V�U�l�ɂ��A�����͕����P�S�N�S���R���������Ƃ��ĂP�Q�U�S�U���̃R���p�N�g�f�B�X�N���o�ׂ��Ă��邱�Ƃ��F�߂���j�ɂ͒����ł������Ƃ������Ƃ��ł���B
�@�����Ƃ��A�u�d�k�k�d�v�Ƃ�����̓t�����X��Ƃ��Ă͋ɂ߂ď����I�ȑ㖼���i�u�ޏ��v���̈Ӂj�ł���A�퍐���u�d�k�k�d�v�u�����h���`������ߒ��ɂ����ẮA���C�Z���X������e��̏��i�Ɉ��p���W��t���A�h���u�����h�̏��W�ɂ��Ă����p���W�ƌ����������W���g�p����Ȃǂ��ē���I�ȃu�����h�C���[�W��Z�������Ă������̂ł���A�u�d�k�k�d�v�u�����h�̒������͈��p���W�Ɩ��ڕs���Ȃ��̂Ƃ��ēW�J���Ă������̂ƔF�߂邱�Ƃ��ł���B
(�) �ȏ��O��Ƃ��āA�{���g�p�\���ƈ��p���W�Ƃ̗ޔۂɂ���������B
�@�{���g�p�\���́A�O�L(�)�̂Ƃ���A�u�d�k�k�d�v�Ɓu�f�`�q�c�d�m�v���Q�i�ɕ\�L���Đ�����̂ł���Ƃ���A�u�f�`�q�c�d�m�v�̕����́u�d�k�k�d�v�̕����Ɉ͂܂��悤�ɂ��ď����ȕ����ŕ\�L����Ă��邱�Ƃ���A�{���g�p�\���̑S�̂ɐڂ����Ƃ��ɋ�����ەt������̂́u�d�k�k�d�v�̕����ł���B
�@�����āA�{���g�p�\���ɂ�����u�d�k�k�d�v�̕����́A���p���W�̂悤�ȏ㉺�ɍג������̂ɂ��\�L����Ă���킯�ł͂Ȃ����A�S�̂Ƃ��Ă݂�Έ��p���W�Ǝ��ʂ�����ۂ�^������̂ł���A�{���g�p�\�������p���W�Ɨ���ČʂɊώ@����Ȃ�A�{���g�p�\�������̎w�菤�i���͎w��Ɏg�p�����ꍇ�ɂ́u�d�k�k�d�v�̔h���u�����h�Ȃ����u�d�k�k�d�v�u�����h�Ɖ��炩�̊W��L������̂ƌ�F���������邨���ꂪ����B���������āA�{���g�p�\���͈��p���W�Ɨގ�������̂Ƃ����ׂ��ł���B
�@�����ŁA�i��ŁA�{���g�p�\���̋�̓I�\���ԗl�̌��n���猟������B
�E�{���g�p�\���̋�̓I�\���ԗl�ɂ�
(�) �{���g�p�\���́A�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v�i�G�����K�[�f���j�Ƃ������̖̂{�����b�N�o���h�̉��t�����^�����uDON�fT TRUST ANYONE BUT US�v�Ƃ����\��̃R���p�N�g�f�B�X�N�i�{���R���p�N�g�f�B�X�N�A�b�Q�j���ɂ����ĕ\�����ꂽ���̂ł���B
(�) �{�����b�N�o���h�́A�����P�O�N�P�Q���R�P���Ƀ����o�[�S�l�ɂ�茋�����ꂽ�o���h�ŁA������������u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v�i�J�^�J�i�\�L�Łu�G�����K�[�f���v�j�Ƃ̖��̂ʼn��y�������s���Ă����B
�@�o���h�̌�����܂��Ȃ��A���y�A�[�e�B�X�g�̃}�l�[�W�����g��b�c���̌��Ղ̊�搧����s�������̏����ƂȂ�A���C�u�����𒆐S�Ƃ������y�����ɂ���҂𒆐S�ɃN�`�R�~�Ől�C���L�������B�����āA���y�ƊE���u�I���W�i���E�R���t�B�f���X�v�ɂ�����b�c�A�c�u�c���̐���T�Ԕ��㐔�ɂ�郉���L���O�i�I���R���E�`���[�g�j�ɂ����āA�{�����b�N�o���h�̂Q���ڂ̃A���o�����V�T�ʂƂȂ��Ĉȍ~�A�����ɔ����L�������A�S���ڂ̃A���o���i�����P�V�N�S���Q�O�������j����������T�D�V�������L�^���ĂR�ʂɂȂ�A�����P�W�N�W���X�������̂c�u�c���P�ʂƂȂ������A�����Q�O�N�P�O���ȍ~�A�������x�~���Ă���i�b�W�Q�`�W�S�A�P�S�U�A������\��A�j�B
�@�{���R���p�N�g�f�B�X�N�́A�{�����b�N�o���h�����\�������߂ẴA���o���ŁA�����P�S�N�S���R���ɔ̔����J�n���ꂽ���̂ł���B
(�) �{���R���p�N�g�f�B�X�N�ɂ�����{���g�p�\���̋�̓I�\���ԗl�́A���̂悤�Ȃ��̂ł���i�b�Q�A���P�Q�j�B
��(a) �{���R���p�N�g�f�B�X�N�̕\���̕\���i�b�Q�A�P���ځj�ɂ́A���u���L����������ɗV���n�炵�����̂��]�܂�镗�i���`����A���̍��㕔���ɁuDON�fT TRUST ANYONE BUT US�v�Ƃ����{���R���p�N�g�f�B�X�N�̕\�肪�L�ڂ���Ă���Ƃ���A�{���g�p�\���́A��L���i��̈ꕔ�Ƃ��ĕ\������Ă���B���Ȃ킿�A���u�̎�O���ɒu���ꂽ�ē��̂悤�Ȃ��̂ɁA�V���n�̕������������Ƌ��ɖ{���g�p�\�����`����Ă���B
(b) �����Ė{���R���p�N�g�f�B�X�N�̕\���̗����i�b�Q�A�W���ځj�ɂ́A�����[�S�[���E���h�̎ʐ^��w�i�ɁA�������̕����ŁA�{���R���p�N�g�f�B�X�N�̕\���A�{�����b�N�o���h�̃����o�[�̎����i�A���t�@�x�b�g�\�L�j�A���^��i�̑薼�Ȃǂ��L�ڂ���Ă���A���̂P�ԏ�ɖ{���g�p�\�����\������Ă���B
(c) �{���R���p�N�g�f�B�X�N�ɕt�����сi�b�Q�A�U���ځj�ɂ́A�\���̕\���ɓ����镔���ɁA�{���g�p�\���Ɓu�G�����K�[�f���v�Ƃ����J�^�J�i���������ɕ���ʼn���������Ă���B�u�G�����K�[�f���v�̕����́A�{���g�p�\���Ɠ����x�̑傫���ɂ��A������������������̕����Ŗڗ��悤�ɋL�ڂ���Ă���B
(d) �܂��A��L�т̂����{���R���p�N�g�f�B�X�N�̔w���ɓ����镔���ɂ́A�uDON�fT TRUST ANYONE BUT US�v�Ƃ����{���R���p�N�g�f�B�X�N�̕\��Ɓu�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v�Ƃ����A���t�@�x�b�g�������A�قȂ鏑�̂ɂ��P�s�ɕ���ʼn���������Ă���i�Ȃ��A�т��͂������ꍇ�ł��A�{���R���p�N�g�f�B�X�N�̔w���ɂ́uDON�fT TRUST ANYONE BUT US�v�Ɓu�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v����L�Ɠ��l�ɕ���ŕ\�L����Ă���k�b�Q�A�W���ځl�B�j�B
(e) �Ȃ��A��L�т̗��\�����ɓ����镔���ɂ́A�L����ЃO���[�C���O�A�b�v�����W���҂ƂȂ��Ă���o�^���W�i�b�W�U�j�Ɠ��l�́u�c���������������v�̕������A�Ԃ���̂悤�Ȍ`�������}�`�Ƌ��ɕ\������A�����}�`���\���̗����A�w�����ɂ��\������Ă���B�܂��A���\���̂P�ԉ��̕����ɂ́uManufactured by Dynamord Label�v�Ƃ̋L�ڂ�����B
�� �ȏ�ɂ��A�{���R���p�N�g�f�B�X�N���w�����悤�Ƃ�����v�҂́A�{���R���p�N�g�f�B�X�N�ɑт��t����ē����r�j�[���ŕ���ꂽ��ԁi���P�Q�Q�Ɓj�ł́A�т̔w���ɕ\�L���ꂽ�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v�̕����A�т̕\���ɕ\�L���ꂽ�u�G�����K�[�f���v�̕�����ڂɂ��邱�ƂƂȂ�A�т��͂����ꂽ���Õi�̏ꍇ�ł��A�{���R���p�N�g�f�B�X�N�̔w���ɕ\�L���ꂽ�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v�̕�����ڂɂ��邱�ƂƂȂ�B
(�) �ȏ��O��Ƃ��āA�{���g�p�\���̋�̓I�\���ԗl���퍐�̋Ɩ��ɌW�鏤�i���Ƃ̍����������邨�����L���邩�ɂ��Č�������B
�@���v�҂��{���R���p�N�g�f�B�X�N���w�����悤�Ƃ���Ƃ��ɂ́A�{���g�p�\���Ƌ��Ɂu�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v��u�G�����K�[�f���v�̕��������邱�ƂƂȂ�B�����Ĉ�ʂɉ��y��i�A���Ƀ��b�N�o���h�̉��t�����^�����R���p�N�g�f�B�X�N�ɂ́A���Y�A�[�e�B�X�g���i���b�N�o���h���j�Ɠ��Y�R���p�N�g�f�B�X�N�̕\�肪���L�����̂��ʏ�ł��邱�Ƃ���A�{���R���p�N�g�f�B�X�N�ɕ\�L���ꂽ�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v�uDON�fT TRUST ANYONE BUT US�v�̈�����A�[�e�B�X�g���������A�������\����������̂ł��邱�Ƃ��e�Ղɐ����ł��A�u�d�k�k�d�v�Ɓu�f�`�q�c�d�m�v��g�ݍ��킹�Đ���{���g�p�\�����A�[�e�B�X�g���Ȃ����\��ł���u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v��\�����̂ł��邱�Ƃ��e�Ղɗ��������B
�@���������āA�u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�v���{�����b�N�o���h�̖��̂ł��邱�Ƃ�m���Ă�����v�҂͂������A�����m��Ȃ����v�҂ł����Ă��A�{���R���p�N�g�f�B�X�N�ɐڂ����ꍇ�ɖ{���g�p�\�����u�d�k�k�d�v�u�����h�Ɖ��炩�̊W��L������̂ƌ�F�������邨����͂Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
(�) �Ȃ��A�������^�c����z�[���y�[�W��ł��{���g�p�\�����g�p���ꂽ�i�b�R�̂Q�j���A��L�z�[���y�[�W�ɂ́u�d�k�k�d�f�`�q�c�d�m�̃z�[���y�[�W�ւ悤�����B���̃y�[�W�̓o���h�̍ŐV����X�P�W���[�������J����ƂƂ��ɁA�������Ă����݂�Ȃ��𗬂ł�����݂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ĉ^�c����Ă��܂��B�v�ƋL�ڂ���A�{�����b�N�o���h�������P�O�N�P�Q���R�P���Ɍ�������Ă���̊����̕��݂ɂ��Ă̐��������f�ڂ���Ă���i�b�R�̂P�A�Q�j���Ƃ���A�{�����b�N�o���h�y�т��̊������Љ�邽�߂̂��̂ł��邱�Ƃ����炩�ł���A��L�z�[���y�[�W��ɂ�����{���g�p�\���̎g�p���퍐�̋Ɩ����ɌW�鏤�i���ƍ����������邨�����L������̂ł͂Ȃ��B
�G�ȏ�ɂ��A�{���g�p�\���͈��p���W�ɗގ�������̂́A�{���R���p�N�g�f�B�X�N���ɂ������̓I�\���ԗl�͔퍐�̋Ɩ��ɌW�鏤�i���ƍ����������邨�����L������̂Ƃ͂����Ȃ�����A���W�@�T�P���P���ɂ����u���l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�Ⴕ���͖ƍ���������́v�Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�R ����
�@�ȏ�̂Ƃ���A�{���g�p�\���̖{���R���p�N�g�f�B�X�N�ɂ������̓I�\���ԗl���퍐�̋Ɩ��ɌW�鏤�i���ƍ����������邨�����L������̂łȂ�����A������m�肵���R���̔��f�́A���̗]�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ����ł��邱�ƂɂȂ�B
�u�A�C�s�[�t�@�[���v�����R�������������
| �����ԍ� | �@����20�N(�s�P)��10371�� |
|---|---|
| ������ | �@�R������������� |
| �ٔ��N���� | �@����21�N03��24�� |
| �ٔ����� | �@�m�I���Y�����ٔ��� |
�@�@�@�@��@��
�@�����̐��������p����B
�@�i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B
�@�����y�ї��R
��P �����̋��߂��ٔ�
�@�u�������������Q�O�O�V�|�W�X�O�P�S�W�������ɂ��ĕ����Q�O�N�X���W���ɂ����R�����������B�v�Ƃ̔���
��Q ���Ă̊T�v
�@�{���́A�����̉��L�P(1)�̏��W�o�^�i�ȉ��u�{�����W�o�^�v�Ƃ����A�{�����W�o�^�ɌW�鏤�W���u�{�����W�v�Ƃ����B�j�ɂ��āA�퍐���A���L�P(2)�̂Ƃ��薳���R�������������Ƃ���A���������{�����W�o�^���Ƃ���|�̐R�����������߁A���������̎���������߂鎖�Ăł���B
�P �������ɂ�����葱�̌o��
(1) �{�����W�o�^
�@�o��l�F����
�@�{�����W�̍\���F�u�A�C�s�[�t�@�[���v�i�W�������j
�@�w��F��S�Q�ށu�H�Ə��L���Ɋւ���葱�̑㗝���͊Ӓ肻�̑��̎����A�i�������̑��Ɋւ���@�������A���쌠�̗��p�Ɋւ���_��̑㗝���͔}��v
�@�o����F�����P�T�N�P�P���Q�O��
�@�ݒ�o�^���F�����P�U�N�V���Q��
�@�o�^�ԍ��F��S�V�W�R�P�R�S��
�i�����j
�@�{�����W�̍\���́u�A�C�s�[�t�@�[���v�̕Љ�����W�������ŕ\���ĂȂ���̂ł���A�{�����W����u�A�C�s�[�t�@�[���v�̏̌Ă������邱�Ƃ͖��炩�ł���B�����āA�u�A�C�s�[�v����̓A���t�@�x�b�g�́u�h�o�v���e�Ղɑz�N����A�u�t�@�[���v����͉p��́u�e�h�q�l�v���́u�e�`�q�l�v���z�N�����B
�@�܂��A�u�A�C�s�[�v�ɂ��Ă݂�ɁA�b��R�U�y�ё�R�V���ɂ��ƁA�u�m�I���Y�v���Ӗ�����p��́uIntellectual Property�v���u�h�o�v�Ɨ����Ďg�p����邱�Ƃ��F�߂���Ƃ���A���̂��Ƃ́A�{�����W�ɌW��w��̎��v�҂̑����ɂƂ��Ă͂悭�m��ꂽ�����ł���Ƃ����ׂ��ł���B
�@���Ɂu�t�@�[���v�ɂ��Ă݂�ɁA�P�X�X�X�i�����P�P�j�N�S��������Ќ����Д��s�́u���[�_�[�Y�p�a���T�v�ɂ́A�ufirm�v�ɂ��āu�����o�c�̏���A���X�A ��ʂ̉�ЁA��ƁG�������ē�����c�̐l�тƁA�i���Ɂj��Ã`�[���G�s���t�ƍߎ҂̈�c�A�M�����O�G�s���t�meuph�n�i�閧�j�g�D����@�ցE�閧�{���ǂȂǁFa law �`�@���������D�E�E�E�v�i�X�P�T�Łj�ƋL�ڂ���A�ufarm�v�ɂ��āu�P���_�n�A�_��A�_���E�E�E�G�_�Ɓifarmhouse�j�E�E�E�������A�{�B��E�E�E�v�i�W�V�X�Łj�ƋL�ڂ���Ă���Ƃ���A�u�e�h�q�l�v����Г��̐l�I�g�D���Ӗ������ł���A�u�e�`�q�l�v���_���_�����Ӗ������ł���ƔF�߂���Ƃ���A�����̌�͂����������̉䂪���ɂ����čL���m���Ă�����̂ƔF�߂���B
�@��������ƁA�{�����W�ɌW��w��̎��v�҂��{�����W�i�A�C�s�[�t�@�[���j�ɐڂ���A�܂��A�u�A�C�s�[�v����u�h�o�v�A���Ȃ킿�A�u�m�I���Y�v��z�N������̂ƔF�߂���B
�@�����āA���̌�ɑ����u�t�@�[���v����́A��L�̂Ƃ���A�u�e�h�q�l�v�����łȂ��A�u�e�`�q�l�v���z�N���꓾�邪�A�����̌�̈Ӗ���m���Ă���{�����W�̎w��ɌW���L���v�҂ɂƂ��āA�u�m�I���Y�v�Ɓu�e�`�q�l�i�_��j�v�����т��邱�Ƃ���ʓI�ł���Ƃ͍l���ɂ������ʁA�u�k�`�v �e�h�q�l�v�i�@���������j�̗p�Ⴊ�������x�Z�����Ă��邱�Ƃ����l������ƁA�{�����W�ɌW��w��̎��v�҂́A�u�A�C�s�[�v�ɑ����u�t�@�[���v����A��Ƃ��āu�e�h�q�l�v��z�N������̂ƔF�߂���B
�@��������ƁA�Ⴆ�A��L�u�k�`�v �e�h�q�l�v�̌ꂩ��@���������A���Ȃ킿�A�@���W�Ɩ�����舵���������̊ϔO��������悤�ɁA�{�����W�i�A�C�s�[�t�@�[���j����́u�h�o �e�h�q�l�v�A���Ȃ킿�A�u�m�I���Y�W�Ɩ�����舵���������v�̊ϔO������̂ƔF�߂���B
�@���������āA�{�����W�̕\�L�́A���̎w��̎��v�҂ɂƂ��āA���̎w��ɌW��Ɩ��̓��e��\�������̂ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ����ׂ��ł���B
�m�I���Y�����T�C�g�@�s�n�o�y�[�W