立体商標と平面商標の類否判断
無効不成立審決の取消事件(ひよ子事件)
「筆記用具」立体商標出願拒絶審決取消請求事件
「ひよこちゃん」商標拒絶審決取消事件
商標の類否判断(SINKA-シンガー事件)…最判
商標の類否判断(「氷山」事件)…最判
商標の類否(大森林-木林森事件)…最判
損害賠償等請求事件(スーパーフコイダン事件)
損害賠償請求事件( UNDER THE SUN 事件 )
「GEORGIA」商標事件…最判
「ALWAYS」商標事件
「ELLEGARDEN」商標事件
著作権使用料請求事件(ロゴ)
印刷用書体(「ゴナU」事件)…最判
著作権侵害差止等請求事件(著作権の存続期間)…最判
著作権侵害事件(キャンディ・キャンディ事件)…最判
広告差止等請求控訴事件(キシリトールガム事件)
不正競争行為差止等請求控訴事件(カメヤマ vs 日本香堂)
不正競争防止法違反(アルミホイール販売差止め請求事件)
不正競争行為差止等請求事件(「正露丸」事件)
名称使用差止等請求事件(「天理教豊文教会」事件)…最判
異議申立棄却決定取消等請求控訴事件(品種登録)
種苗生産・譲渡行為差止等請求控訴事件
まいたけ育成者権侵害差止等請求事件
立体商標と平面商標の類否判断
| 事件番号 | 平成12年(行ケ)第234号 |
|---|---|
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成13年01月31日 |
| 裁判所名 | 東京高等裁判所 |
審決は、本願商標と引用商標との類否判断に当たり、「平面商標も立体商標も、ともに視覚を通じて認識されるものであり、それにより両者が類似することがあることは明らかであって、立体商標を特定の方向から観た場合に、その視覚に映る姿と同一又は近似する平面商標が存在するときには、当該立体商標はその平面商標と外観において類似する商標とみるのが相当である」(審決書2頁26行目~30行目)とした上で、本願商標につき本願正面外観図をもって引用商標と対比するものである。
ところで、立体商標は、立体的形状又は立体的形状と平面標章との結合により構成されるものであり、見る方向によって視覚に映る姿が異なるという特殊性を有し、実際に使用される場合において、一時にその全体の形状を視認することができないものであるから、これを考案するに際しては、看者がこれを観察する場合に主として視認するであろう一又は二以上の特定の方向(以下「所定方向」という。)を想定し、所定方向からこれを見たときに看者の視覚に映る姿の特徴によって商品又は役務の出所を識別することができるものとすることが通常であると考えられる。そうであれば、立体商標においては、その全体の形状のみならず、所定方向から見たときの看者の視覚に映る外観(印象)が自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たすことになるから、当該所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似する場合には、原則として、当該立体商標と当該平面商標との間に外観類似の関係があるというべきであり、また、そのような所定方向が二方向以上ある場合には、いずれの所定方向から見たときの看者の視覚に映る姿にも、それぞれ独立に商品又は役務の出所識別機能が付与されていることになるから、いずれか一方向の所定方向から見たときに視覚に映る姿が特定の平面商標と同一又は近似していればこのような外観類似の関係があるというべきであるが、およそ所定方向には当たらない方向から立体商標を見た場合に看者の視覚に映る姿は、このような外観類似に係る類否判断の要素とはならないものと解するのが相当である。特許庁の商標審査基準が、立体商標の類否判断につき、「立体商標の類否は、・・・次のように判断するものとする。ただし、特定の方向から観た場合に視覚に映る姿が立体商標の特徴を表しているとは認められないときはこの限りでない。(イ) 立体商標は、原則として、それを特定の方向から観た場合に視覚に映る姿を表示する平面商標(近似する場合も含む。)と外観において類似する。」と規定するのは以上の趣旨であると解される。
そして、いずれの方向が所定方向であるかは、当該立体商標の構成態様に基づき、個別的、客観的に判断されるべき事柄であるが、本願商標のように生物等を擬人化して成るものであれば、看者がこれを観察する場合に、人に擬して形成された顔面に正対する方向が当該立体商標の特徴的な部分を視認し得るものとなるから、特段の事情のない限り、所定方向の少なくとも一つに当たるものと解すべきところ、本願商標については、本願正面外観図が、擬人化された蛸の顔面に正対する方向より見た場合に視覚に映る姿であることは明白である。
無効不成立審決の取消事件(ひよ子事件)
<特許庁は、商標登録無効審判において、本件立体商標についての商標法第3条第2項の適用を認め、商標登録を維持する請求不成立の審決をしたが、知財高裁にて当該審決が取り消された事件。>
| 事件番号 | 平成17年(行ケ)第10673号 |
|---|---|
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年11月29日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
(2) 法3条2項の趣旨と立体商標
法3条2項は、法3条1項3号等のように本来は自他商品の識別性を有しない商標であっても、特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用され、宣伝もされてきたような場合には、結果としてその商品形態が商品の出所表示機能を有し周知性を獲得することになるので、いわゆる特別顕著性を取得したものとして、例外的にその登録を認めようとしたものと解される。
そして、この理は、平成9年4月1日から施行された立体商標についてもそのまま当てはまると解されるが、この場合に留意すべきことは、本件事案に即していえば、法3条2項の要件の有無はあくまでも別紙「立体商標を表示した書面」による立体的形状について独立して判断すべきであって、付随して使用された文字商標・称呼等は捨象して判断すべきであること、商標法は日本全国一律に適用されるものであるから、本件立体商標が前記特別顕著性を獲得したか否かは日本全体を基準として判断すべきであること等である。
そこで、以上の見解に立って、本件事案について検討する。
(中略)
(4) 当裁判所の判断
当裁判所は、被告の文字商標「ひよ子」は九州地方や関東地方を含む地域の需要者には広く知られていると認めることはできるものの、別紙「立体商標を表示した書面」のとおりの形状を有する本件立体商標それ自体は、未だ全国的な周知性を獲得するまでには至っていないと判断する。その理由は、以下に述べるとおりである。
(中略)
ウ さらに、被告以外の鳥の形状の和菓子についてみると、菓子の老舗である虎屋が、江戸時代(正徳年間)から、目と嘴をつけ、鳩笛のような形にした、鳥の形状の「鶉餅」を作っており、最近では、平成16年に、同様の形状で販売したこと、他の鳥の形状の和菓子としては、京都の三宅八幡宮ゆかりの菓子「鳩餅」も存在すること、が認められる。これに、前記のように、現在でも鳥の形状の和菓子が各地に存在することを併せ考慮すれば、鳥の形状を有する和菓子は、わが国において伝統的なものということができる。しかるに、本件立体商標に係る鳥の形状は、上記「鶉餅」よりも単純な形状であるから、本件立体商標に係る鳥の形状自体は、伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として、ありふれたものとの評価を受けることを免れないものである。
エ 以上のア~ウによれば、被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであり、さらに、本件立体商標に係る鳥の形状と極めて類似した菓子が日本全国に多数存在し、その形状は和菓子としてありふれたものとの評価を免れないから、上記「ひよ子」の売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。
したがって、本件立体商標が使用された結果、登録審決時において、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができたと認めることはできず、本件立体商標は、いわゆる「自他商品識別力」(特別顕著性)の獲得がなされていないものとして、法3条2項の「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」との要件を満たさないというほかない。
(5) 被告の主張に対する補足的説明
ア 被告は、同種の形状の鳥の菓子が多数存在するという主張それ自体は意味がなく、これらの形状が使用された結果、他者の製造販売する菓子として需要者の間に広く認識されているという事実を主張立証しない限り、本件立体商標の、使用による出所識別力を減殺することはできない旨主張する。
しかし、当裁判所の上記判断は、同種の形状の菓子が多数存在することのみで本件立体商標が自他商品識別力を欠くとしたものではなく、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等をも考慮して検討したものであり、また、鳥の形状を有する和菓子が伝統的に存在することにも照らし、鳥の形状が菓子として特徴的なものとはいえないこと、被告の菓子「ひよ子」の販売、広告宣伝において、菓子「ひよ子」の形状が単独で用いられているといえるものは見当たらないことをも考慮した上で、かかる状況においては、本件立体商標については全国的な周知性を獲得するに至っていないとしたものである。そして、被告に本件立体商標の使用を独占させることが、特徴的なものといえない形状につき、一定の販売期間、販売規模を有する業者を含め多数の業者のかかる形状の使用を排除する結果を招来することにも鑑みると、公益上望ましいとは言い得ないことは明らかと言わざるを得ない。これらに鑑みると、使用による出所識別力を否定できる場合が、被告のいうような事実の主張立証があった場合に限られると解さなければならない理由はないから、被告の上記主張は採用することができない。
イ 次に被告は、いかに著名な商標が付された商品であっても、酷似する商標の付された模造品とともに置かれた場合に、どれが本物の商品かを認識することはできないはずであり、本件立体商標の類似商品は、すべて本件立体商標にフリーライドしたものである旨主張する。
しかし、当裁判所の上記判断は、それのみを根拠として自他商品識別力を欠くとしたものではなく、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等をも考慮して検討したものであり、また、鳥の形状を有する和菓子が伝統的に存在することにも照らし、鳥の形状が菓子として特徴的なものとはいえないこと、被告の菓子「ひよ子」の販売、広告宣伝において、菓子「ひよ子」の立体形状のみが単独で用いられているといえるものは見当たらないことをも考慮した上で、かかる状況においては、本件立体商標については全国的な周知性を獲得するに至っていないとしたものである。そして、かかる判断は、同種の形状の菓子の数、全国への分布度、その販売期間、販売規模等に鑑みれば、被告の菓子「ひよ子」を模倣したものかどうかによって左右されるものではない。
以上によれば、被告の上記主張は採用することができない。
(中略)
オ 次に被告は、本件立体商標の商標登録が認められても、法は、鳥の形状をかたどった菓子は、法3条1項3号の記述的商標に該当するとした上で、記述的商標であっても、企業努力によって出所識別力を獲得した商標は、法3条2項により商標登録を認めているのであるし、さらに、立体商標制度施行前からの立体商標の正当使用は、継続的使用権が付与されることによって保護されているのであるから、和菓子文化の承継と発展の伝統を否定するとはいえない旨主張する。
しかし、当裁判所の前記判断は、本件立体商標の商標登録を認めることは和菓子文化の継承と発展の伝統を否定することになるから許されないと説示したものではなく、わが国において鳥の形状の和菓子が伝統的に存在することにも照らし、本件立体商標もありふれたものとの評価を受けることを理由の一つとしたものにすぎない。また、前記のとおり被告の企業努力が多大なものであったことは認められるものの、被告の直営店舗の多くは九州北部、関東地方等に所在し、必ずしも日本全国にあまねく店舗が存在するものではなく、また、菓子「ひよ子」の販売形態や広告宣伝状況は、需要者が文字商標「ひよ子」に注目するような形態で行われているものであるから、その売上高の大きさ、広告宣伝等の頻繁さをもってしても、文字商標「ひよ子」についてはともかく、本件立体商標自体については、いまだ全国的な周知性を獲得するに至っていないものというべきである。
また、継続的使用権につき、平成8年改正法附則2条1項、2項は、不正競争の目的でなく改正法の施行前から立体商標の使用をしていた者は、継続してそれを使用する場合には、たとえ他人がその立体商標について登録を受けたとしても、施行の際現にその立体商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内で、その立体商標の使用をする権利(継続的使用権)を有するとし、また、当該商標権者等が継続的使用権を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができるとしているのであって、かかる継続的使用権の規定内容に照らせば、継続的使用権を有すると考えられる者であっても、不正競争の目的でないことの立証の負担を負い、施行の際現にその立体商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内での保護が受けられるに止まり、しかも混同防止表示を付すよう請求されるおそれがあるものである。したがって、附則所定の要件を満たすことを立証できれば、立体商標制度施行前からの正当使用は継続的使用権により保護されることにはなるが、上記に述べたことに照らせば、継続的使用権が認められるためには相当の経済的負担が必要になる側面があることもまた否定できないところである。
(中略)
3 結論
以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、本件立体商標は商標法3条2項に定める要件を具備するものとした本件審決の判断は誤りである。
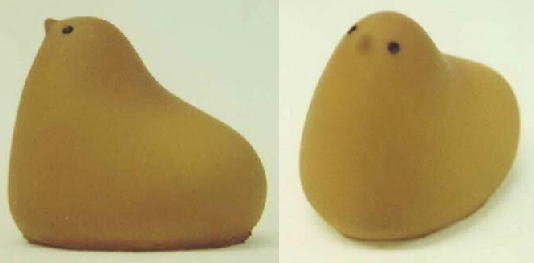
商標登録第4704439号(平成15年8月29日 登録、 平成19年11月26日 本権利消滅)
指定商品
第30類 まんじゅう
「筆記用具」立体商標出願拒絶審決取消請求事件
| 事件番号 | 平成11年(行ケ)第406号 |
|---|---|
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成12年12月21日 |
| 裁判所名 | 東京高等裁判所 |
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1、2(商標法3条1項3号関係)について
(1) 本願商標は、指定商品を「鉛筆、ボールペン、その他の筆記用具」として、別紙のとおりの立体的形状のみから成る立体商標として登録出願されたものであるところ、検証甲第1号証の1、2、乙第3号証の1ないし6及び弁論の全趣旨に照らすと、取引者、需要者が本願商標に係る形状に接した場合、最下部が細い筆記用の芯部分で、その上の中間部は指で挟み持つことのできる丸い棒状の支持部分となっており、上部は平板で幅広に拡大していて、その中央部は紙片等を挟み得るほぼ長方形のクリップ状になっていることを認識することができ、簡便な鉛筆又はボールペンという筆記用具が一般的に有するものとして予想し得る形状の特徴を備えているものと感得することができるものと認められる。そして、その形状は、全体としてまとまりがよくスマートな印象を与え、主としてゴルフスコアカード記入用等の筆記用具として用いられる鉛筆又はボールペンであることを推認させるものとなっている。
本願商標に係る立体的形状は、このようにまとまりがよくスマートな印象を与え、それなりの特徴を有するものであるものの、簡便な鉛筆又はボールペンという筆記用具の用途、機能から予測し難いような特異な形態や特別な印象を与える装飾的形状等を備えているものとは認められず、取引者、需要者にとっては、本願商標から、これらの筆記用具が一般的に採用し得る機能又は美感を感得し、筆記用具の形状そのものを認識するにとどまるものと認められ、その形状自体が自他商品の識別力を有するものと認めることはできない。
(2) そして、本件全証拠によるも、「本願商標は、前記認定のとおり、筆記用具の形状の特徴を備えたものであり、後部を平たいクリップ状としたのは、紙片等を挟みやすく、落ちにくくする等の機能を効果的に発揮させるために採択されたとみるのが相当であり、それが直ちに本願商標に関し自他商品の識別性に影響を与えるとは認め難く、需要者もまた、筆記用具の形状の範囲のものと認識するにすぎないとみられるものである。」とした審決の判断を覆すべき事実関係を認めることはできない。したがって、本願商標は、その指定商品である鉛筆、ボールペン、その他の筆記用具の形状の域を出るものではなく、指定商品の物の形状の範囲を出ないと認識する形状のみから成る立体商標にすぎないというべきであり、指定商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみから成る商標に該当する。
(3) よって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当するとした審決の判断に誤りはなく、取消事由1、2は理由がない。
2 取消事由3(商標法3条2項関係)について
(1) 甲第2号証の1ないし43は、別紙の本願商標の図示をそのまま引用して、本願商標が付された筆記具を、① 製造販売者である原告から平成5年5月21日から平成9年5月20日までの期間に毎年16万個ないし34万個購入したこと、② 平成5年には、上記図示に表された商標は、原告の製造販売に係る商品「筆記具」について広く知られており、引き続きその度合が高まりつつ現在に至っていること、③ 遅くとも・・・年には、上記図示に表された商標は、原告の製造販売に係る商品「筆記具」について広く一般に知られていたこと(・・・の年については、各証明書によって昭和56年から平成9年まで各別の記載がある。)、などの事実評価についての卸売業者の証明書であるが、その形式は、原告が上記事項を記載したものに「上記の通りであることを証明する。」というものになっているものであって、上記②、③の総合的な判断を要する事実評価については客観的に記載されているものと直ちに認めることはできない。甲第18、第19号証にも、上記③と同様の事実評価を証明するゴルフ用品販売業者と思われる会社担当者の証明記載があるが、同様、原告が記載したものに証明する形式となっており、そこに記載の事実評価を直ちに採用することはできない。
(2) 上記①の販売個数については他にこれを覆すべき証拠もないので、そこに記載のとおりの相当数の個数の筆記具が、原告により本願商標を付して製造販売されたものと推認されるが、他方、甲第4号証の1ないし38、第5号証の1、2、第12号証の1、2、第13ないし第16号証、第24号証、甲第25号証(原告代表取締役【A】の陳述書)によれば、原告により製造販売された本願商標に係る形状の鉛筆には、表に「OKAYA」「Pegcil」裏に「JAPAN」「pegcil」との表示が付され、ボールペンには表に「OKAYA」「Pegcil」裏に「JAPAN」と表示されていることが認められる。しかし、原告が本願商標を付して製造販売した鉛筆やボールペンで、「OKAYA」「Pegcil」の文字標章が付されていないもの、すなわち、本願商標のみが付された筆記具が製造販
売されたことを認めるべき証拠はなく、また、これらの文字標章が識別標章として格別の機能を有するものではないとすべき理由は見いだし難い。
甲第25号証には、上記の鉛筆、ボールペンは、本願商標を付した筆記具として広く認識されているとの記載部分があるが、本願商標の立体形状が、前判示のとおり、指定商品である筆記用具としての物の形状の範囲を出ないものであることを前提にしてみると、本願商標に係る形状の鉛筆やボールペンでこれらの文字標章が付されないものが、原告の製造販売に係るものであると広く認識されていたものとはにわかに認め難く、他に、そのような事実関係を認めるべき客観的な証拠はない(取消事由3の(5)で原告が挙示する甲号各証をもってしても、これを認めるに足りるものではない。)。
したがって、原告の製造販売に係る鉛筆やボールペンに使用されてきた標章のうち、本願商標の立体的形状のみが独立して自他商品の識別力を有しているものということはできないから、本願商標が使用により自他商品の識別機能を有するに至ったものと認めることはできない。
(2)-1 よって、本願商標は商標法3条2項に該当しないとした審決の認定、判断に誤りはなく、取消事由3も理由がない。
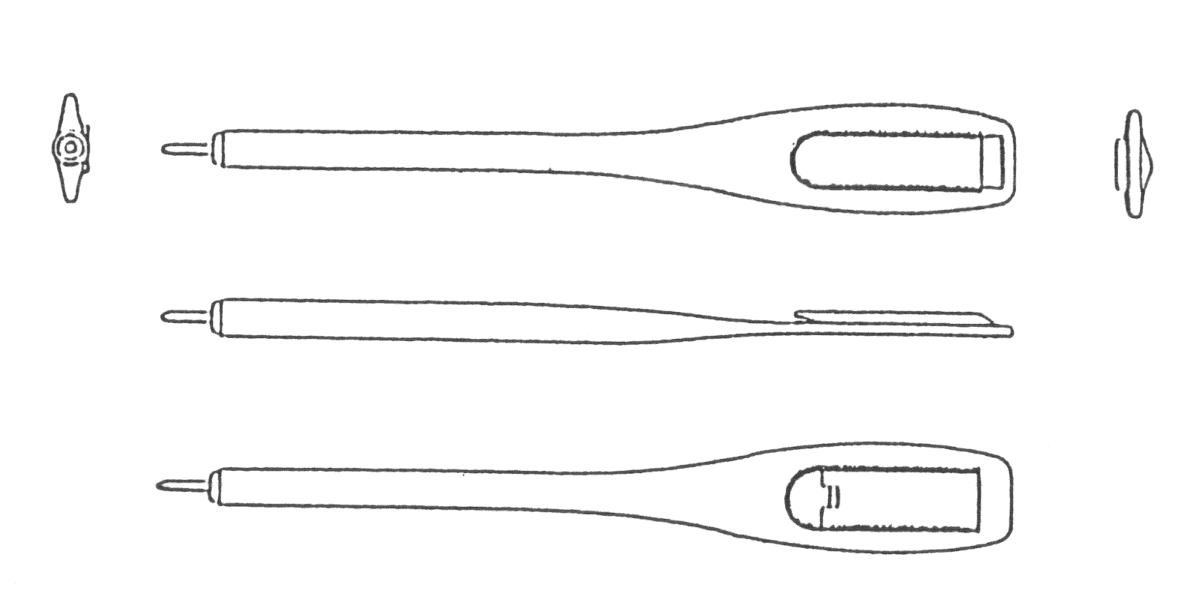
「ひよこちゃん」商標拒絶審決取消事件
| 事件番号 | 平成16年(行ケ)第18号 |
|---|---|
| 事件名 | 審決取消請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成16年09月16日 |
| 裁判所名 | 東京高等裁判所 |
1 特許庁における手続の経緯
原告は、平成10年5月20日、「ひよこちゃん」の平仮名文字を標準文字で横書きして成る商標(以下「本願商標」という。)について、指定商品を第30類「即席中華そばのめん」(補正後のもの)として、商標登録出願(以下「本件出願」という。)をし、平成13年4月9日に拒絶査定を受けたので、平成13年5月14日、これに対する不服の審判を請求した。特許庁は、これを不服2001-7911号事件として審理し、その結果、平成15年12月2日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本を、同年12月12日ころ、原告に送達した。
2 審決の理由
審決は、別紙審決書の写しのとおり、本願商標は、登録第524914号の商標権者である株式会社ひよ子が、商品「菓子」に使用する「ひよ子」の文字から成る登録商標(以下、審決と同様に「引用商標」という。)と類似する商標であって、これを本願指定商品について使用するときは、当該商標権者の製造販売に係る商品、あるいは、当該商標権者と何らかの関係ある商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、商標法4条1項15号に該当する、と認定判断した。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(混同を生ずるおそれについての判断の誤り)について
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである(最判平12・7・11民集54巻6号1848頁)。
(1) 本願商標と引用商標の類似性について
本願商標は、「ひよこちゃん」の文字から成るものであり、引用商標は、「ひよ子」の文字から成るものである。
本願商標は、「ひよこ」の文字と、愛称で呼ぶときにしばしば使用される「ちゃん」の文字とから成るものである。「○○ちゃん」のように、「ちゃん」を他の語に付して使用した場合は、「○○」の部分が取引者又は需要者の注意を引く部分となることは当然である。したがって、本願商標の「ひよこちゃん」は、「ひよこ」の部分が取引者又は需要者の注意を惹く部分であるから、同商標については、普通名詞の「ひよこ【雛】」から「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」(広辞苑第5版)との観念が生じ、また、「ひよこちゃん」との称呼のみならず、「ヒヨコ」との称呼も生じ得るものである。
これに対し、引用商標の「ひよ子」は、普通名詞である「ひよこ」の「こ」を漢字の「子」にしたものであるから、文字どおり、「ひよこ【雛】」を連想させるものであり、「鳥の子。特にニワトリの子。ひな」との観念及び「ヒヨコ」との称呼を生ずるものである。
以上からすれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するところがあるとしても、「ひよこ【雛】」の観念及び「ヒヨコ」の称呼を共通にするものであり、商標のみを比較した場合は、互いに類似する商標であると認められる。
ただし、上に述べたところから明らかなとおり、引用商標の「ひよ子」は、普通名詞の「ひよこ」の「こ」を「子」としただけであり、また、本願商標の「ひよこちゃん」も、普通名詞の「ひよこ」に「ちゃん」を付しただけの商標であるから、いずれも普通名詞の「ひよこ」と類似するものであって、独創的な商標ということはできず、その商標としての自他識別力は本来的に弱いものである。
(中略)
(3) 本願商標の指定商品と引用商標に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度、取引者、需要者の共通性並びに取引の実情について(ア) 本願商標の指定商品である「即席中華そばのめん」(インスタントラーメン)は、一般消費者がスーパーマーケットやコンビニ等の小売店で購入し、日常の食事の場で普通に食される商品であり、単価は少額で日常的に購入される商品である。
これに対して、引用商標が使用されている「ひよ子の形をしたお菓子」は、一般の消費者が、主として、旅行又は仕事等で訪れる際のお土産品あるいは贈答品として、駅や空港の売店、百貨店やスーパーマーケットなどの大規模店舗の専門店、贈答品コーナー、あるいは株式会社ひよ子の直営店等で購入するお菓子であり、お土産品・贈答品として食することが多いお菓子であって、日常的に食される「即席中華そばのめん」とは相当に異なる食品である(乙22ないし25号証、乙29ないし31号証、乙33ないし35号証、乙47ないし49号証)。
(イ) 審決は、「補正後の本願指定商品「即席中華そばのめん」と引用商標の使用に係る商品「菓子」とは、共に食品であるところを共通にし、販売店、販売場所においても、共に「食料品店」「食品売場」で扱われる商品であり」(審決書3頁下から2行~4頁1行)と認定する。
しかし、駅や空港の売店等で、お土産品、贈答品として、「即席中華そばのめん」が販売されていることを認めるに足りる証拠はない。
(中略)
(4) 総合的判断
以上に認定したところからすれば、引用商標「ひよ子」が普通名詞の「ひよこ」と顕著な差がなく、自他識別性が強くはないこと、引用商標「ひよ子」の周知著名性は、お土産品・贈答品に頻繁に利用される、「ひよこの形をしたお菓子」という商品と密接に結合したものであり、当該商品を連想させる商標として周知著名なものであるから、その周知著名性が及ぶのはせいぜい「菓子」の範囲までであり、食肉、野菜、果実などの生鮮食料品から、様々なものが含まれる加工食料品など食品全般にまで広く及ぶと解することはできない。
前記のとおり、本願商標の指定商品である「即席中華そばのめん」(インスタントラーメン)は、一般消費者がスーパーマーケットやコンビニ等の小売店で購入し、日常の食事の場で普通に食される商品であり、単価は少額で日常的に購入される商品であるのに対して、引用商標が使用されている「ひよ子の形をしたお菓子」は、一般の消費者が、主として、旅行又は仕事等で訪れる際のお土産品あるいは贈答品として、駅や空港の売店あるいは百貨店やスーパーマーケットなどの大規模店舗の専門店、贈答品コーナー、あるいは株式会社ひよ子の直営店等で購入するお菓子であり、お土産品・贈答品として食することが多いお菓子であって、一般消費者が日常的に食する「即席中華そばのめん」とは、商品自体が相当に異なり、販売経路、売場などからも、明りょうに区別することができる食品であることからすれば、「即席中華そばのめん」に本願商標を使用しても、その取引者及び需要者である一般消費者が、同商品を、引用商標「ひよ子」の業務主体又は同社と何らかの関係にある者の業務に係るものと混同するおそれがあるとみることはできない。審決の「本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、商品の出所について混同を生じさせるおそれのあるものと認められる」(審決書4頁16行~17行)との認定判断は誤りであるといわざるを得ない。
商標の類否判断(SINKA-シンガー事件)
| 事件番号 | 昭和33年(オ)第766号 |
|---|---|
| 事件名 | 商標登録願拒絶査定抗告審判審決取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和35年10月04日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
上告代理人和久井宗次の上告理由第一点について。
商標法二条九号の関係では、当該登録商標が周知・著名のものであることは同号適用の要件ではなく、その適用を肯定するためには、商標自体が同一若しくは類似する場合でなければならないことは所論のとおりである。しかし、原審も、商標が周知・著名であることが九号適用の要件であるとしたものではなく、また、「シンガー」の商標と「シンカ」の商標とが商標自体として同一若しくは類似のものと認められないにかかわらずその適用があるとしたわけではない。原審は右両商標の呼称を抽象的に対比すれば(すなわち「シンガーミシン」がその呼称で世界的に著名な裁縫機械として取引されているという具体的取引事情をはなれて抽象的に比較考察すれば)必ずしも類似するとはいえないかもしれないが、右のような具体的取引事情を背景として考えれば、「シンガー」と「シンカ」は紛らわしいこととなり、結局、具体的取引事情の下では、両商標は呼称が類似するものと認むべきである、との趣旨の判断をしたものである。原審の右認定は相当であり、右認定が経験則に反するとはいい得ない。
なお原審認定の事情の下では「シンカ」の商標は九号に該当すると同時に一一号にも該当することとなるが、九号と一一号との競合的適用を否定すべき理由はない。所論引用の判例は、商標の呼称が類似するかどうかを判断するについて具体的取引事情を考慮に容れてはならない趣旨を判示したものとは解されず、また、同一事実につき九号と一一号の競合的適用があることを否定する趣旨とも解されない。それ故論旨はすベて理由がない。
同第二点について。
所論のような登録例がある以上本件両商標の類似性を否定しなければならないというような経験則は存在せず、これら登録例の存在は本件両商標の類似性を肯定することの妨げとなるものではないから、原審がこれら登録例の存在にかかわらず、本件の具体的事情の下で右両商標の呼称が類似すると判断したことは何等違法ではなく、所論の甲号証を排斥する理由の如きは必ずしも説示しなければならないものではない。
商標の類否判断(「氷山」事件)
| 事件番号 | 昭和39年(行ツ)第110号 |
|---|---|
| 事件名 | 商標登録出願拒絶査定不服抗告審判審決取消請求 |
| 裁判年月日 | 昭和43年02月27日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
商標の外観、観念または称呼の類似は、その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、従って、右三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら商品の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標と解すべきではない。
本件についてみるに、出願商標は氷山の図形のほか「硝子繊維」、「氷山印」、「日東紡績」の文字を含むものであるのに対し、引用登録商標は単に「しょうざん」の文字のみから成る商標であるから、両者が外観を異にすることは明白であり、また後者から氷山を意味するような観念を生ずる余地のないことも疑なく、これらの点における非類似は、原審において上告人も争わないところである。そこで原判決は、上記のような商標の構成から生ずる称呼が、前者は「ひょうざんじるし」ないし「ひょうざん」、後者は「しょうざんじるし」ないし「しょうざん」であって、両者の称呼がよし比較的近似するものであるとしても、その外観および観念の差異を考慮すべく、単に両者の抽出された語音を対比して称呼の類否を決定して足れりとすべきでない旨を説示したものと認められる。そして、原判決は、両商標の称呼は近似するとはいえ、なお称呼上の差異は容易に認識しえられるのであるから、「ひ」と「し」の発音が明確に区別されにくい傾向のある一部地域があることその他諸般の事情を考慮しても、硝子繊維糸の前叙のような特殊な取引の実情のもとにおいては、外観および観念が著しく相違するうえ称呼においても右の程度に区別できる両商標をとりちがえて商品の出所の誤認混同を生ずるおそれは考えられず、両者は非類似と解したものと理解することができる。原判決が右両者は称呼において類似するものでない旨を判示した点は、論旨の非難するところであるが、硝子繊維糸の取引の実情に徴し、称呼比考察を比較的緩かに解して妨げないこと前叙のとおりであって、この見地から右の程度の称呼の相違をもってなお非類似と解したものと認められる右判示を、あながち失当というべきではない。
商標の類否(大森林-木林森事件)
| 事件番号 | 平成3年(オ)第1805号 |
|---|---|
| 事件名 | 製造販売等差止請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成4年09月22日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第三小法廷 |
1 商標の類否は、同一又は類似の商品に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものであって(最高裁昭和三九年(行ツ)第一一〇号同四三年二月二七日第三小法廷判決・民集二二巻二号三九九頁参照)、綿密に観察する限りでは外観、観念、称呼において個別的には類似しない商標であっても、具体的な取引状況いかんによっては類似する場合があり、したがって、外観、観念、称呼についての総合的な類似性の有無も、具体的な取引状況によって異なってくる場合もあることに思いを致すべきである。
2 本件についてこれをみるのに、本件商標と被上告人標章とは、使用されている文字が「森」と「林」の二つにおいて一致しており、一致していない「大」と「木」の字は、筆運びによっては紛らわしくなるものであること、被上告人標章は意味を持たない造語にすぎないこと、そして、両者は、いずれも構成する文字からして増毛効果を連想させる樹木を想起させるものであることからすると、全体的に観察し対比してみて、両者は少なくとも外観、観念において紛らわしい関係にあることが明らかであり、取引の状況によっては、需要者が両者を見誤る可能性は否定できず、ひいては両者が類似する関係にあるものと認める余地もあるものといわなければならない。
損害賠償等請求事件(スーパーフコイダン事件)
| 事件番号 | 平成18年(ワ)第28323号 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成19年07月26日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
第2 事案の概要
本件は、被告がモズク加工食品に付している標章が原告の商標権を侵害しているとして、原告が被告に対し、被告の標章の使用差止め及び損害賠償を求めた事案である。被告は、(1)原告の商標と被告の標章が類似しないこと、(2)被告の標章につき先使用権が成立することを主張して、原告の請求を争っている。
1 判断の前提となる事実(当事者間に争いがないか、後掲各証拠によって認められる。)
(1) 当事者
原告は、健康食品の製造、販売を主たる業務とする株式会社である(弁論の全趣旨)。
被告(旧商号・株式会社沖縄発酵化学)は、昭和63年9月に設立された、食品の販売及び清涼飲料水等の製造及び販売を主たる業務とする株式会社である(乙2)。
(2) 原告の商標権
原告は、次の商標権を有している(以下「本件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。)。
登録番号第4862117号
出願年月日平成16年10月13日
登録年月日平成17年5月13日
登録商標「自然健康館」と「スーパーフコイダン」からなり、両者を2段併記したもの(別紙登録商標目録記載のとおり)
指定商品並びに商品の区分
第29類海藻エキスを主材料とする液状又は粉状の加工
食品
第32類清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース
(3) 被告の使用する標章
被告は、遅くとも平成18年5月ころから、その製造するモズク加工食品(以下「被告商品」という)。の容器、包装に別紙被告標章目録記載2の標章(以下「被告標章」という。)を付して販売し、被告商品の広告にも被告標章を付している。
被告標章は、「SUPER」、「FUCOIDAN」及び「スーパーフコイダン」の文字と6本の横線を菱形状に表した二つの図形とを組み合わせたものである(別紙被告標章目録記載2参照)。
なお、被告は、平成18年8月29日、被告標章を商標登録出願した。
(4) 本件商標権の指定商品と被告食品との同一性
被告商品は、本件商標権の指定商品である「海藻エキスを主材料とする液状又は粉状の加工食品」に含まれる。
(判旨)
本件商標の要部について
ア 証拠(乙4ないし9)によれば、いわゆる健康食品の分野では、「スーパー・ルテイン」、「スーパー・イソフラボン」、「スーパーDHA」、「スーパーコエンザイムQ10」、「スーパープロポリス粒」、「スーパーレシチン」のように、原材料の名称に「スーパー」を付した商品が多数販売されていることが認められる。
イ 証拠(乙10ないし19(各枝番を含む。))によれば、いわゆる健康食品を指定商品とした商標登録出願において、原材料の名称に「スーパー」の文字を付した商標は、「スーパー」の文字が商品の誇称表示として一般的に使用されていることから、商標法3条1項3号に該当するとして登録に至らなかった例が、多数あることが認められる(具体例として、「スーパーアガリスク」、「スーパー・ルテイン」、「スーパーイソフラボン」、「スーパーダイズ」、「SUPER/COLLAGEN/スーパーコラーゲン」)。
また、「ピュアフコイダン/PUREFUCOIDAN」、「ナノフコイダン」、「ダブルフコイダン」、「トリプルフコイダン」、「プラチナフコイダン」が商品の品質、原材料を表示するものにすぎず、商標法3条1項3号に該当するとして拒絶査定を受けていることが認められる。
ウ 既に述べたとおり「フコイダン」は、海藻類の成分を抽出して作られた健康食品の原材料を表示する用語である。そして、いわゆる健康食品において、「スーパー」は、商品の誇称表示として一般的に使用されている用語である。したがって、本件商標権の指定商品である「海藻エキスを主材料とする液状又は粉状の加工食品」又は「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」の分野では、「スーパーフコイダン」という用語は、高品質の「フコイダン」、すなわち、高品質な、海草類に含有される硫酸化多糖類が含有されていることを記述するにすぎないのであって、それ自体では出所識別力を有せず、本件商標の要部とはなり得ないというべきである。そして、「フコイダン」を名称に含む様々な健康食品が販売されている状況に照らせば、本件商標は、「自然健康館」という製造元の表示と相まって初めて出所識別力が生じるというべきであり、「自然健康館スーパーフコイダン」という本件商標全体が要部であると解するのが相当である。
損害賠償請求事件( UNDER THE SUN 事件 )
| 事件番号 | 平成6年(ワ)第6280号 |
|---|---|
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成7年02月22日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
第二 事案の概要
本件は、原告が被告に対して、被告が、業として製造、販売している商品であるCD(シンガーソングライターである【A】の楽曲を収録したコンパクト・ディスク。以下「本件CD」という。)について、別紙目録記載の「UNDER TEH SUN」という標章(以下「被告標章」という。)を付する行為が、原告の後記の登録商標に類似する商標の使用であり、原告の商標権を侵害する(商標法三七条一号、以下同法の条文の引用は単に条文のみで表示する。)と主張して、被告が平成五年九月一五日ころから平成六年二月末日までの間に被告標章を付して製造販売した本件CD四〇万枚について、通常受けるべき使用料相当額の一億〇四八六万八〇〇〇円の損害賠償と不法行為後の民法所定の遅延損害金の支払を求める事案である。
一 前提となる事実
1 原告は、次の商標権(以下「本件商標権」といい、その登録商録を「本件登録商標」という。)を有している(争いがない。)。
登録番号 二一五七八六三
出願 昭和六二年五月二九日
出願公告 昭和六三年一二月二日
登録 平成元年七月三一日
商品の区分 第二四類(平成三年政令第二九九号による改正前の商標法施行令別表による。)
指定商品 おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く。)、レコード、これらの部品及び付属品
登録商標 別紙添付の商標公報(商標出願公告昭六三ー九七二八四)記載のとおり
2 被告は、業として製造、販売している商品である本件CDに、被告標章を付している(争いがない。)。
3 被告標章は、本件登録商標と同一の文字構成であり(甲二)、かつ、本件商標権の指定商品の「レコード」は、蓄音機用音盤、録音テープ、その他の物に音を固定したものであると認められるから(商標法施行規則三条別表九類一四号参照)、本件CDはこれに該当する。
(判旨)
以上によれば、被告標章並びにフォーライフ商標及び被告の社名の具体的な表記の態様をみると、被告標章は、前記認定のアルバムタイトルの一般的な表記の態様と何ら異なることはなく、また、フォーライフ商標及び被告の社名も、前記認定のアルバムにおける製造、発売元の一般的な表記の態様と何ら異なることはないのであり、したがって、本件CDに表示されている被告標章は、専ら本件CDに収録されている全一一曲の集合体すなわち編集著作物である本件アルバムに対して付けられた題号(アルバムタイトル)であると認められ、本件CDの需要者としても、被告標章を、専ら本件CDの内容である複数の収録曲の集合体すなわち編集著作物である本件アルバムについて付けられた題号(アルバムタイトル)であると認識し、有体物である本件CDを製造、販売している主体である被告を表示するのは、アルバムタイトルとは別に本件CDに付されているフォーライフ商標や被告の社名であると認識することは明らかである。よって、本件CDに使用されている被告標章は、編集著作物である本件アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものにすぎず、有体物である本件CDの出所たる製造、発売元を表示するものではなく、自己の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する標識としての機能を果たしていない態様で使用されているものと認められる。
「GEORGIA」商標事件
| 事件番号 | 昭和60年(行ツ)第68号 |
|---|---|
| 事件名 | GEORGIA商標事件 |
| 裁判年月日 | 昭和61年01月23日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第一小法廷 |
商標登録出願に係る商標が商標法三条一項三号にいう「商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するというためには、必ずしも当該指定商品が当該商標の表示する土地において現実に生産され又は販売されていることを要せず、需要者又は取引者によって、当該指定商品が当該商標の表示する土地において生産され又は販売されているであろうと一般に認識されることをもって足りるというべきである。原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、本件商標登録出願に係る「GEORGIA」なる商標に接する需要者又は取引者は、その指定商品であるコーヒー、コーヒー飲料等がアメリカ合衆国のジヨージアなる地において生産されているものであろうと一般に認識するものと認められ、したがって、右商標は商標法三条一項三号所定の商標に該当するというべきである。
「ALWAYS」商標事件
| 事件番号 | 平成9年(ワ)第10409号 |
|---|---|
| 事件名 | 「ALWAYS」商標事件 |
| 裁判年月日 | 平成10年07月22日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
第二 事案の概要
本件は、原告が、被告に対し、後記商標権に基づき、「オールウェイズ」等の標章を付した缶入りコーラの販売等の差止め、及び被告による右商標権の侵害により弁護士・弁理士費用相当額の損害を被ったとして、損害賠償を、それぞれ求めた事案である。
一 争いのない事実等(証拠を掲記した事実以外は、当事者間に争いがない。)
1 原告の商標権
原告は、次のとおりの商標権(以下「本件商標権」といい、その 登録商標を「本件登録商標」という。)を有する。
登録番号 第一六四三九三○号
登録日 昭和五八年一二月二六日
存続期間の更新登録 平成六年五月三○日
指定商品 コーヒー、その他旧第二九類に属する商品
登録商標 別紙登録商標目録記載のとおり
2 被告の行為
(一) 被告は、業として、清涼飲料コカ・コーラを製造販売している。
(二) 被告は、平成五年から、右コカ・コーラの缶に、「ALWAYS」ないし「always」なる欧文字(以下「本件欧文字表記」という。)を付している。その態様は、別紙被告標章目録一記載のとおり、缶上に一か所、小さく白抜きの円弧が描かれ、その中に、コカ・コーラのボトルの図柄を背景とした「Coca-Cola」という文字が記載され、その上部に、円弧に沿って、小さな字で「ALWAYS」という白抜き文字が記載されている図柄(以下「被告図柄一」という。)のものである(甲三の1)。
(三) 被告は、平成九年四月から、右コカ・コーラの缶に、本件欧文字表記及び「オールウェイズ」なるカタカナ文字(以下「本件カタカナ表記」という。)を付している。その態様は、別紙被告標章目録二記載のとおり、缶上に大きな円弧の上下一部が缶の大きさに収まらない形で描かれ、円弧の中心に、コカ・コーラのボトルの図柄が描かれ、それを背景として円弧の中央を横切るように「Coca-Cola」という文字が記載され、円内のその周辺に、日本語「オールウェイズ」、英語「always」、スペイン語「Siempre」、ポーランド語「zawsze」及びフランス語「Toujours」が記載されている図柄(以下「被告図柄二」という。)のものである(甲三の2、乙一、一三)。
(判旨)
①コカ・コーラについては、従来から、「Come on in.Coke」、「Yes Coke Yes」、「Coke is it!」、「I feel Coke.」、「さわやかになる、ひととき」等の様々なキャッチフレーズによるキャンペーンが実施されていたこと、「Always Coca-Cola(オールウェイズ コカ・コーラ)」のキャッチフレーズは、これらのキャンペーンの一環として、平成五年から長期間にわたり、大規模に広告宣伝活動が行われてきたこと、②被告図柄一及び二において、前記のとおり、本件欧文字表記及び本件カタカナ表記は、いずれも、著名商標である「Coca-Cola」に隣接した位置に、一体的に記載されていること、③「Always」ないし「オールウェイズ」が、「常に、いつでも」を意味することは、一般に知られているものと解されること、特に、被告図柄二においては、同一の意味を指すスペイン語「Siempre」、ポーランド語「zawsze」及びフランス語「Toujours」の語とともに記載されていること、④右キャッチフレーズは、ごく短い語句であるが、需要者が、いつも、コカ・コーラを、飲みたいとの気持ちを抱くというような、商品の購買意欲を高める効果を有する内容と理解できる表現であること等の事情に照らすならば、コカ・コーラの缶上に記載された本件欧文字表記及び本件カタカナ表記を見た一般顧客は、専ら、ザ・コカ・コーラ・カンパニーがグループとして実施している、販売促進のためのキャンペーンの一環であるキャッチフレーズの一部であると認識するものと解される。したがって、本件欧文字表記及び本件カタカナ表記は、いずれも商品を特定する機能ないし出所を表示する機能を果たす態様で用いられているものとはいえないから、商標として使用されているものとはいえない。
「ELLEGARDEN」商標事件
| 事件番号 | 平成18年(ワ)第4029号 |
|---|---|
| 事件名 | 商標権侵害差止等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成19年05月16日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
第2 事案の概要
本件は、「ELLE」等の商標につき商標権を有するとともに、「ELLE」等の商標を周知又は著名商標として使用する原告が、「ELLEGARDEN 」との被告標章を付した被告商品を販売する被告に対し、①上記商標権、②不正競争防止法3条及び2条1項1号又は③同法3条及び2条1項2号に基づき(ただし、被告標章(10)については、不正競争防止法3条及び2条1項1号又は2号のみに基づく。)、①被告商品への被告標章の使用等の差止め、並びに②被告商品からの被告標章の抹消及び③被告ウェブサイトからの被告標章を付した被告商品の広告表示の削除を求めた事案である。
1 前提事実
(1) 当事者
ア原告
原告は、1945年12月14日、フランス法に基づき設立された会社であり、女性向けファッション雑誌「ELLE 」(以下「原告雑誌」という。)の発行を世界各国において行っている。
また、原告は、世界各国において商標「ELLE 」を管理し、商標登録を受け、当該商標を付した各種商品の製造、販売及び各種役務の提供を展開している。
イ被告
被告は、音楽録音物・映像物の原盤の企画制作・製造・宣伝・頒布・販売・利用・開発及び歌手・音楽実演家・芸能タレントのマネージメント等を目的とする株式会社である。
ロックバンド「ELLEGARDEN 」(以下「本件ロックバンド」という。)は、被告に所属する。
(以上、争いのない事実)
(2) 当事者の有する商標権
ア原告の商標権
原告は、以下の商標権を有する(以下、各商標権を「原告商標権1」のようにいい、各登録商標を「原告登録商標1」のようにいう。また、原告商標権1~5を併せて「原告商標権」といい、原告登録商標1~5を併せて「原告登録商標」という。)。
(ア) 原告商標権1
商標登録第1978528号(甲3)
登録商標別紙原告登録商標目録1のとおり
商品の区分第26類(旧々々類)
指定商品雑誌、その他本類に属する商品
(以下、略)
(判旨)
確かに、証拠(乙1~16、67、68)及び弁論の全趣旨によれば、本件ロックバンドが音楽CD の販売やメディアにおける活動において一定の実績を挙げており、相当の知名度を獲得したことが認められる。しかし、弁論の全趣旨によれば、ロックバンドに関心を持つ人は若者等一部の年代の者に限られると認められるところ、本件ロックバンドが、被告商品の需要者であると考えられる一般消費者の多くが本件ロックバンドを想起するといえるほどの知名度を有するに至ったとまで認めるに足りる証拠はない。
また、被告標章がまとまりよく構成されているといっても、単語として固有の意味を有しないことを考慮すると、上記のとおり「ELLE 」の部分と「GARDEN 」の部分とに分離して把握されると認めざるを得ない。実際に、証拠(甲94、乙2)によれば、本件ロックバンドは「ELLE 」又は「エルレ」と「GARDEN 」の部分を除く形で略称されることがあることが認められる。
(中略)
(イ) 需要者
a ウェブ検索
証拠(甲86の1~3、87の1~4)及び弁論の全趣旨によれば、現在のようにウェブページが氾濫する状況にあっては、消費者が目的のウェブサイトを発見するためには、検索サイトにおいて、自己が興味を有する単語をキーワードとして検索し、検索結果として表示されたウェブサイトを訪れるところ、原告の著名な商標「ELLE 」に関連した商品を探す需要者が、「ELLE 」をキーワードとしてウェブサイトを検索した場合、被告ウェブサイトが、原告の正規のウェブサイトや原告の商品を扱うウェブサイトと並列的に表示されること、その結果、原告の商品を探している消費者であっても、被告ウェブサイトに容易に到達し得ることが認められる。また、上記(ア)に認定の事実によれば、被告は、誰もがアクセス可能な被告ウェブサイトにおいて、被告商品の広告等を行っており、被告商品の購入申込みは誰でも行うことができるものである。
b ポスト・セールス・コンフュージョン
さらに、仮に購入者自身は、被告ウェブサイト中の説明内容により、被告商品を本件ロックバンドに関連するものであるということを認識できたとしても、当該商品を身に付けた者を更に他の第三者が見ることも当然あり得るところであり、そのような第三者は、当該商品が本件ロックバンドに関連するものであるとの認識を有することができず、当該商品の出所が原告であると誤認するおそれがあると認められる。
c 現在の販売方法の永続性
また、弁論の全趣旨によれば、被告商品が本件ロックバンドの人気上昇等に従い、デパートや衣料品の通販チャネルで販売されることも十分あり得ると認められるから、ライブ会場や被告ウェブサイトを通じて販売されるとの現在の販売方法が今後とも永続する販売方法であるとまで認めることはできない。
(中略)
仮にこれらが商標として使用されたものだとしても、これらのT シャツには、いずれも、その前面及び/又は背面に、被告標章のほか、ツアー名及び/又はライブ会場・ライブ日程と理解される表示がされており、このような表示が存在する場合、これに接した需要者は、被告標章によって当該商品に表示される主体の音楽活動を想起すると考えられること、被告標章(10)を除く被告標章は、本件ELLE 商標の特徴的な字体を有するものではないこと等の事情にかんがみると、これらのT シャツに接した需要者が、これらを原告又は原告と経済的若しくは組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品ではないかとその出所について誤認混同するおそれがあるとは認められない。
著作権使用料請求事件(ロゴ)
| 事件番号 | 平成12年(ワ)第2415号 |
|---|---|
| 事件名 | 著作権使用料請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成12年09月28日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
第二 事案の概要
本件は、原告が、著作物であるロゴを被告に使用させたと主張して、被告に対し、右ロゴにつき著作物使用料の支払を求めている事案である。
一 争いのない事実
1 原告は、被告ないしその前身の会社から、被告の使用するロゴの有償での制作を依頼され、これを別紙一のとおり制作した(以下「本件ロゴ」という。制作時期については、争いがある。)。
2 被告ないしその前身の会社は、原告に対し、右制作の対価の少なくとも一部として、八五万円を支払った。
3 被告は、現在まで本件ロゴを使用し続けている。
(判旨)
著作権法二条一項一号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を、著作物とすると規定し、さらに同条二項は、「この法律にいう『美術の著作物』には、美術工芸品を含むものとする。」と規定している。右規定は、意匠法等の工業所有権制度との関係から、著作権法により著作物として保護されるのは、純粋な美術の領域に属するものや美術工芸品であって、実用に供され、あるいは産業上利用されることが予定されている図案やひな形など、いわゆる応用美術の領域に属するものは、鑑賞の対象として認められる一品製作のものを除き、原則として、これに含まれないことを示しているというべきである。ところで、本件で著作物性が問題となっている文字の書体についていえば、文字は万人共有の文化的財産であり、もともと情報伝達という実用的機能を有することをその本質とするものであるから、そのような文字そのものと分かち難く結びついている文字の書体も、その表現形態に著作物としての保護を与えるべき創作性を認めることは、一般的には困難であって、仮に、デザイン書体に著作物性を認め得る場合があるとしても、それは、当該書体のデザイン的要素が、見る者に特別な美的感興を呼び起こすに足りる程の美的創作性を備えているような、例外的場合に限られるというべきである。
印刷用書体(「ゴナU」事件)
| 事件番号 | 平成10年(受)第332号 |
|---|---|
| 事件名 | 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件 |
| 裁判年月日 | 平成12年09月07日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第一小法廷 |
著作権法二条一項一号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物と定めるところ、印刷用書体がここにいう著作物に該当するというためには、それが従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。この点につき、印刷用書体について右の独創性を緩和し、又は実用的機能の観点から見た美しさがあれば足りるとすると、この印刷用書体を用いた小説、論文等の印刷物を出版するためには印刷用書体の著作者の氏名の表示及び著作権者の許諾が必要となり、これを複製する際にも著作権者の許諾が必要となり、既存の印刷用書体に依拠して類似の印刷用書体を制作し又はこれを改良することができなくなるなどのおそれがあり(著作権法一九条ないし二一条、二七条)、著作物の公正な利用に留意しつつ、著作者の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与しようとする著作権法の目的に反することになる。また、印刷用書体は、文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために、必然的にその形態には一定の制約を受けるものであるところ、これが一般的に著作物として保護されるものとすると、著作権の成立に審査及び登録を要せず、著作権の対外的な表示も要求しない我が国の著作権制度の下においては、わずかな差異を有する無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される。
著作権侵害差止等請求事件(著作権の存続期間)
| 事件番号 | 平成19年(受)第1105号 |
|---|---|
| 事件名 | 著作権侵害差止等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成19年12月18日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第三小法廷 |
本件経過規定における本件文言についても、本件文言の一般用法と異なる用いられ方をしたものと解すべき理由はなく、「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」とあるのは、本件改正前の著作権法に基づく映画の著作物の保護期間が、本件改正法の施行日においても現に継続中である場合を指し、その場合は当該映画の著作物の保護期間については本件改正後の著作権法54条1項が適用されて原則として公表後70年を経過するまでとなることを明らかにしたのが本件経過規定であると解すべきである。そして、本件経過規定は、「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が消滅している映画の著作物については、なお従前の例による」と定めているが、これは、本件改正法の施行日において既に保護期間の満了している映画の著作物については、本件改正前の著作権法の保護期間が適用され、本件改正後の著作権法の保護期間は適用されないことを念のため明記したものと解すべきであり、本件改正法の施行の直前に著作権の消滅する著作物について本件改正後の著作権法の保護期間が適用されないことは、この定めによっても明らかというべきである。したがって、本件映画を含め、昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は、本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく、その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了し消滅したというべきである。
著作権侵害事件(キャンディ・キャンディ事件)
| 事件番号 | 平成12年(受)第798号 |
|---|---|
| 事件名 | 著作権侵害事件 |
| 裁判年月日 | 平成13年10月25日 |
| 裁判所名 | 最高裁判所第一小法廷 |
原審の適法に確定したところによれば、本件連載漫画は、被上告人が各回ごとの具体的なストーリーを創作し、これを400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿にし、上告人において、漫画化に当たって使用できないと思われる部分を除き、おおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返すことにより制作されたというのである。この事実関係によれば、本件連載。漫画は被上告人作成の原稿を原著作物とする二次的著作物であるということができるから、被上告人は、本件連載漫画について原著作者の権利を有するものというべきである。そして、二次的著作物である本件連載漫画の利用に関し、原著作物の著作者である被上告人は本件連載漫画の著作者である上告人が有するものと同一の種類の権利を専有し、上告人の権利と被上告人の権利とが併存することになるのであるから、上告人の権利は上告人と被上告人の合意によらなければ行使することができないと解される。したがって、被上告人は、上告人が本件連載漫画の主人公キャンディを描いた本件原画を合意によることなく作成し、複製し、又は配布することの差止めを求めることができるというべきである。
以上によれば、被上告人が本件連載漫画の一部である本件コマ絵及び本件連載漫画の主人公キャンディの絵の複製である本件表紙絵につき原著作者の権利を有することの確認と、本件原画を作成し、複製し、又は配布することの差止めを求める被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる
広告差止等請求控訴事件(キシリトールガム事件)
| 事件番号 | 平成17年(ネ)第10059号 |
|---|---|
| 事件名 | 広告差止等請求控訴事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年10月18日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
上記①の本件比較表示の記載及び②の記載中の「一般的なキシリトールガム」がキシリトール+2を指すことは、上記第2の1(原判決5頁24~25行)のとおりであるから、本件比較広告の本件比較表示や②の棒グラフは、被控訴人の製品であるポスカムが、控訴人の製品であるキシリトール+2の約5倍の再石灰化効果を有することを表示するものである。しかしながら、その根拠であるD-2-3 実験が合理性を欠くものといわざるを得ないことは、上記2の(5)のとおりであり、他にポスカムの再石灰化効果がキシリトール+2の約5倍であるということの根拠は何ら主張されていないから、ポスカムが、キシリトール+2の約5倍の再石灰化効果を有するというのは、客観的事実に沿わない虚偽の事実というべきであり、被控訴人が、上記①の本件比較表示や②の棒グラフを含む本件比較広告を実施した行為は、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為として、不正競争防止法2条1項14号に該当するものである。
また、本件比較広告がポスカムに関するものであることは明らかであるところ、上記のとおり、①の本件比較表示や②の棒グラフは、ポスカムがキシリトール+2の約5倍の再石灰化効果を有することを表示するものであり、かつ、それが客観的事実に沿わないのであるから、本件比較広告のこれらの部分は、ポスカムの品質を誤認させるものというべく、したがって、被控訴人が、これらの部分を含む本件比較広告を実施した行為は、同項13号に該当するものである。
不正競争行為差止等請求控訴事件(カメヤマ vs 日本香堂)
| 事件番号 | 平成16年(ネ)第2208号 |
|---|---|
| 事件名 | 不正競争行為差止等請求控訴事件 |
| 裁判年月日 | 平成17年04月28日 |
| 裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
第2 事案の概要
1 本件は、ろうそくの製造・販売業者である原告が、被告に対し、被告がその販売するろうそくに、燃焼時に発生するすすの量が90%減少している、火を消したときに生じるにおいが50%減少しているなどという表示をしていることは、不正競争防止法2条1項13号(品質等誤認表示)及び同項14号(営業誹謗行為)に該当すると主張して、①同法3条1項に基づき、上記の表示をし、又は上記の表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示すること(以下「譲渡等」という。)の差止め、②同条2項に基づく上記表示の廃棄、③同法4条に基づく損害賠償3000万円の支払、④同法7条に基づく謝罪広告の掲載を求めた事案である。
原審は、上記表示は同法2条1項13号(品質等誤認表示)に該当するが、同項14号(営業誹謗行為)には該当しないとした上で、原告の請求のうち、①上記の表示をし、又は上記の表示をした商品の譲渡等の差止め、②上記表示の廃棄、③損害賠償300万円の請求を認容し、その余の請求をいずれも棄却した。
これに対し、原告及び被告が、各敗訴部分につきそれぞれ控訴を提起した。(以下、原判決引用部分中、「別紙」とあるのを、いずれも「原判決別紙」と読み替える。)
(判旨)
(2) 信用毀損に係る損害 0円
被告がその販売するろうそく及びその広告に原判決別紙被告表示目録記載1ないし4、6ないし8の表示をすること又はその各表示をした商品を譲渡等することは、前記5(3)のとおり、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為(同項14号。以下「営業誹謗行為」という。)には当たらない。
また、被告の行為は、前記4(3)のとおり、商品又はその広告に商品の品質について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡等する行為(不正競争防止法2条1項13号。以下「品質等誤認表示」という。)に当たるが、このことから直ちに原告の信用が毀損されたということはできない(被告のした品質等誤認表示が、一般消費者にとって、原告の商品の品質が劣っているという趣旨に受け取られるものでないことは、前記5(2)イのとおりである。)。
したがって、原告の信用の毀損に係る損害が発生したとは認められない。
(3) 営業上の損害 300万円
ア 前記基礎となる事実(2)のとおり、原告の商品と被告新商品は競争関係にある。また、前記5(2)イのとおり、神棚、仏壇用ろうそく市場における原告の商品の占有率は、約50ないし60%である。
イ 前記4のとおり、被告は、被告新商品はすすの量が90%、消しにおいが50%減少しているなどと品質等誤認表示をしたものであるから、一般消費者は、被告新商品は被告従来商品に比べてすすの量が90%、消しにおいが50%減少していると信じて被告新商品を購入し、これと競合する原告の商品を購入しないという消費行動をとることがあるものと推認され、これを覆すに足りる証拠はない。
なお、原判決別紙被告表示目録記載1ないし4、6ないし8の表示は、被告新商品と原告の商品とを直接比較するものではないけれども、上記表示は、少なくとも、これを見た一般消費者に対し、被告新商品は上記表示に記載された品質を持つ優れた商品であるという認識を与えることは明らかであるから、上記の認識を持っていなければ被告新商品以外の商品(原告の商品を含む。)を購入したであろう消費者が、上記の認識を持ったがゆえに、被告新商品を選択し購入するということは十分に考えられるので、上記表示が被告新商品と原告の商品とを直接比較するものではないことは、上記推認を覆す事情には当たらない。
してみると、被告の不正競争行為により、原告に営業上の損害が生じたことが認められる。
ウ しかしながら、前記表示により、どの程度の消費者が原告の商品ではなく被告新商品を購入し、原告が幾らの損害を受けたかについては、これを認定するに足りる的確な証拠がなく(原告提出に係る各陳述書(甲第9号証及び第42号証)中、原告が3000万円に相当する営業上の損害を受けたとする部分は、直ちに採用することができない。)、原告の営業上の損害は、その額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難なものであるといえる。
したがって、不正競争防止法6条の3に基づき、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果(特に、被告の品質等誤認表示の態様、原告の商品の占有率)を考慮して、原告の損害額は300万円であると認めるのが相当である。
(なお、甲第42号証、第53号証ないし第58号証によれば、被告新商品の発売後、原告の市場占有率が低下したことが認められなくもないが、その低下割合はせいぜい1%程度にすぎない上、前記1(5)、4(1)ア(イ)のとおり、被告新商品は、そのカット率はともかく、ある程度はすすが減少していることがうかがわれ、また、部屋の空気を爽やかにする効果があるため、消費者がこれらの被告新商品の特長を考慮して被告新商品を選択したことも十分に考えられることからすれば、上記占有率の低下分全額が、被告の品質等誤認表示により生じた損害であるということまではできない。)
(4) 有形損害 413万1259円
ア 人件費 150万円
甲第59号証の1・2、第61ないし第63号証、第69号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告の不正競争行為に関する調査、実験等を行い、人件費を支出したことが認められるところ、このうち150万円の範囲において、被告の不正競争行為の存在を立証するために要した費用として、被告の不正競争行為との間の相当因果関係を認める(なお、裁判所への出頭に要した旅費等については、訴訟費用の負担の裁判により決すべきことであるので(民事訴訟費用等に関する法律2条参照)、ここでは考慮しない。)。
イ 環境保全事業団への実験委託費 150万4146円
甲第59号証の1、第60号証、第70ないし第72号証の各1・2及び弁論の全趣旨によれば、原告は、環境保全事業団に対し、実験委託費として150万4146円を支払ったことが認められ、これは、被告の不正競争行為の存在を立証するために要した費用というのが相当である。
ウ 機材費 3万6960円
甲第38号証、第60号証、第73号証の1・2及び弁論の全趣旨によれば、原告は、オリックス・レンテック株式会社に対し、電子天秤レンタル料等として3万6960円を支払ったことが認められ、これは、被告の不正競争行為の存在を立証するために要した費用というのが相当である。
エ 調査活動費 0円
甲第59号証の1、第69号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、営業担当従業員に命じて、被告商品が量販店等で販売されている状況について調査させたことが認められるが、上記調査は通常の営業活動の中ですることも可能なものであり、原告が上記調査のために別途費用を支出すべき必要性が存在したとは認めるに足りない。
オ ローソク購入費 9万0153円
甲59号証の1・3、第69号証及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告商品を購入するために9万0153円を支払ったことが認められ、これは、被告の不正競争行為の存在を立証するために要した費用というのが相当である。
カ 弁護士費用 100万円
本件訴訟の難易度、認容額など諸般の事情を総合的に考慮し、原告が本件訴訟の提起追行のために支出した弁護士費用のうち、100万円の範囲において、被告の不正競争行為との間の相当因果関係を認める。」
不正競争防止法違反(アルミホイール販売差止め請求事件)
| 事件番号 | 平成3年(ネ)第1071号 |
|---|---|
| 事件名 | アルミホイール事件 |
| 裁判年月日 | 平成5年11月30日 |
| 裁判所名 | 大阪高等裁判所 |
四 不正競争防止法の請求権
1 以上に判断したところによると、原告は、本件被告商品の販売によって、営業上の利益を害されるおそれがあるものと認められる。
2 被告は、本件原告商品の形態は、「ミニライト」の模倣で、原告の本訴差止請求はアン・クリーンハンドだと主張する。
なるほど、本件原告商品が「ミニライト」にヒントを得て開発されたことは想像に難くない。しかし、前説示のとおり本件原告商品は、ミニライトに触発されて創案されたにしても、スポークタイプホイールにおいて識別上重要な基準となるスポークの型と色彩及び全体の印象において同商品にない特徴を備えたことにより、その点において、独創的なものとなり、商品表示性と周知性を獲得したと認められるのであるから、それに基づく本訴請求が、ミニライトの持つ特徴そのものに騎乗した不当なものということはできない。被告の主張は理由がない。
3 クリーンハンドの原則に関する被告の主張について判断する。
検丙第一一号証の二、五、六、丙第五七号証、第六〇~第六二号証、第六五号証の一、二並びに弁論の全趣旨によれば、全国のアルミホイールの発売会社で組織された「ジャパン・ライトアロイ・ホイール・アソシエーション」が昭和五三年に制定した「自動車軽合金鋳物製ディスクホイールの技術基準」(略称・JWL基準)があり、社団法人日本車両検査協会の検査でこの技術基準を充足しているとされたホイールには、「JWLマーク」を付することが許されていること、本件原告商品は昭和五四年、五六年、平成三年の試験で右基準に適合しないとの結果を得たのに、原告は、本件原告商品の包装(段ボール箱)に「JWLマーク」をデザイン化して付したことが認められる。
しかし他方、丙第六四号証によれば、本件被告商品は右基準に適合していることが認められるので、本件原告商品及び本件被告商品が共通して有する形態に技術的欠陥があって右基準に適合することができないものではないことが明らかである。
現に、甲第三七九~第三九四号証によれば、平成四年には、本件原告商品も右基準の適合試験に合格していることが認められる。そして、本訴請求は、商品形態が周知であり、これと誤認、混同を生じさせる商品の販売の差止め等を求めるものであるところからすると、その品質表示に誤解を与えるものであったとしても、このことだけから、原告の請求が許されないとすることはできないというべきである。もちろん、クリーンハンドの原則あるいは権利の濫用法理によって、請求権の行使が許されないことのあり得ることは否定できないとしても、「JWLマーク」が私的な取決めに基づくものであって、その意味が一般にどの程度知れ渡っているかは疑問であり、また本件原告商品の表示が商品そのものに付されたのではなく、包装に付されたにとどまること、本件原告商品の周知性が、JWLマークによって獲得されたものと認めるべき証拠はなく、前記認定事実によれば、形態によって取得されたものといえること(あるいは、本件原告商品の標章によるものとみる余地もある)、他方、本件被告商品の形態は、本件原告商品の独特の形態に酷似していることなどを総合勘案すると、原告の本訴請求権の行使が許されないとすることはできない。
不正競争行為差止等請求事件(「正露丸」事件)
| 事件番号 | 平成17年(ワ)第11663号 |
|---|---|
| 事件名 | 不正競争行為差止等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年07月27日 |
| 裁判所名 | 大阪地方裁判所 |
第2 事案の概要
本件は、原告が、
① いずれも原告が製造販売する胃腸薬(止瀉薬)の商品表示として著名であり、又は周知性を取得している包装全体の表示態様及びそのうちの「正露丸」「SEIROGAN」の各表示と類似する包装全体の表示態様及び「正露丸」「SEIROGAN」の各表示をその製造販売する胃腸薬(止瀉薬)の包装に使用し、同包装を使用した胃腸薬(止瀉薬)を製造販売している被告の行為が、不正競争防止法2条1項2号又は1号の不正競争に当たると主張して、同法3条に基づき、被告に対し、上記表示態様及び各表示の使用及びこれらを使用した胃腸薬(止瀉薬)の製造販売の差止め及び同表示等を付した包装の廃棄を求めるとともに、同法4条に基づく損害賠償(訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)を請求し、
② クレオソートを主剤とする胃腸用丸薬に「正露丸」「SEIROGAN」の各表示を使用し、同表示を使用した胃腸薬(止瀉薬)を製造販売している被告の行為が、原告の有する後記商標権を侵害すると主張して、商標法36条に基づき、上記各表示の使用及びこれらを使用した胃腸薬(止瀉薬)の製造販売の差止め及び同表示を付した包装の廃棄を求めるとともに、商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償(訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を含む。)を請求した事案である。
(判旨)
しかし、他方、上記(2)の認定事実によれば、「正露丸」あるいは「SEIROGAN」の名称で本件医薬品の製造販売を行っている業者は複数存在し、その包装箱の表示態様として、遅くとも昭和30年代ころから、主要な点、すなわち、①包装箱の形状、包装箱全体の地色、②正面の「正露丸」の文字、図形及び周縁の模様の表示、配色及び配置、③背面の「SEIROGAN」の文字、図形及び周縁の模様の表示、配色及び配置、④左右側面の表示、以上の点において原告表示1と共通する特徴を有する包装箱を用いており、「ラッパの図柄」の表示を度外視すれば(原告が包装箱に表示された「大幸薬品株式会社」との表示を原告表示1から除外していることは前記のとおりである。)、原告のみがその包装箱の表示態様として、原告表示1あるいはこれに類似するものを独占的に使用してきたという事実はない。
また、上記のとおり、売上金額ベースでみた原告製品のシェアは80%を超える圧倒的なものということができるものの、販売数量ベースで見た原告製品のシェアは、売上金額ベースで見た上記シェアをかなり下回り、市中に出回っている他社製品の数量は、本件医薬品全体の中で無視できない割合を占めているものと認められる。さらに、後記2のとおり、「正露丸」「SEIROGAN」の表示は、それだけでは現在においてもなお原告製品を示す商品表示性を取得したものとはいえない。
したがって、原告表示1は、「正露丸」の製造販売に携わる取引業者はもとより、一般消費者においても、「ラッパの図柄」を度外視した包装態様のみでは、これが原告の商品であることを認識することができるものとは認められず、商品の出所表示機能を有するものとはいえない。原告製品と他社製品との識別は、原告製品の包装箱に記載された原告の社名とラッパの図柄によって初めて可能になるということができ、事実、原告も、包装箱にラッパの図柄が記載されていることを強調するような宣伝広告活動を行っている。
そうすると、原告表示1の中で自他商品識別機能を有するのは「ラッパの図柄」(及び原告の社名)のみということになるところ、前記認定のとおり、被告表示1において「ラッパの図柄」に相当する部分は「瓢箪の図柄」にほかならず、この点において原告表示1と類似しないことが明らかであるから、被告製品が原告製品と誤認混同を生ずるおそれがあるとは認められない。
(中略)
次に、原告表示2(「正露丸」又は「SEIROGAN」)が不正競争防止法2条1項1号、
2号にいう「商品等表示」といえるか否かについて判断する。
(1) まず、原告表示2のうち「正露丸」について判断する。
証拠(乙3)及び弁論の全趣旨によれば、原告を当事者とする商標登録無効審判についての審決取消訴訟の判決(東京高等裁判所昭和46年9月3日判決・無体財産関係民事・行政裁判例集第3巻第2号293頁、その上告審である最高裁判所昭和49年3月5日第三小法廷判決)において、明治37、38年の日露戦争の際、陸軍が本件医薬品を創製し、これを「征露丸」と命名して、戦場において一般将兵に服用させたこと、日露戦争後、帰還将兵からの言い伝えなどにより、このような「征露丸」の創製及び命名に関する経緯が広く国民の間に知られるようになったこと、その後多数の業者が「征露丸」の名称をもって本件医薬品を製造販売し、本件医薬品を指す名称として「征露丸」の名が日本国内に周知されるようになったこと、しかし、大正13年に、「征露丸」は本件医薬品の慣用商標又は普通名称であること等を理由として同商標の登録無効の審判が請求され、大正15年6月28日に大審院において、上記理由により同商標の登録を無効とする判決がされ、同商標権は失効したこと、第2次大戦後、厚生省薬務局が業者からの「征露丸」の製造許可申請に対し、その名称を「正露丸」に改めるように行政指導をしたことから、「征露丸」の商品名称を用いる業者は減少し、代わって「正露丸」の語が本件医薬品の名称として不特定かつ極めて多数の業者により全国的に用いられるようになったこと、その結果、「正露丸」の語は、遅くともその商標登録時である昭和29年10月30日当時には、本件医薬品の一般的な名称として国民の間に広く認識されていたこと等の事実が認定された上、ごく普通の書体で「正露丸」の文字に「セイロガン」の文字を振り仮名のように付記したにすぎない商標は、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示したにすぎない標章であると判断され、同商標登録が無効とされたことが認められる。
(2) 不正競争防止法2条1項1号、2号所定の「商品等表示」というためには、当該表示が出所表示機能を有することが必要であるところ、普通名称は、自他識別力がなく出所表示機能を有しないから、そもそも「商品等表示」とはいえず、また、商品若しくは営業の普通名称を普通に用いられる方法で使用等する行為については、同法19条1項1号により、同法3条、4条等の適用を除外される。
そして、ある表示が普通名称であるか否かは、もっぱら需要者(取引者及び一般消費者)の認識に関する問題であるといえるから、ある時期において普通名称であるとされた表示であっても、その後の取引の実情の変化により特定の商品を指称するものとして需要者に認識され、出所表示機能を有するに至る場合があり得ないわけではないというべきである。
(3) そこで、「正露丸」の語が、遅くとも昭和29年10月30日当時には本件医薬品の一般的な名称として国民の間に広く認識されていたとしても、今日、原告製品を指称するものとして需要者に認識されるに至ったものかどうかについて検討する。
ア 証拠(甲1、2の1・2、43)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、昭和29年以前から「正露丸」の名称を使用して本件医薬品の製造販売を行っていたものであり、その後も、全国の各都道府県に代理店を置き、年間約2000万円の宣伝広告費を投じてその製品の宣伝広告をした結果、昭和40年ころまでには、本件医薬品の需要の約90%を占めるにまで至ったこと、東京地方裁判所昭和40年10月5日判決(判例タイムズ188号211頁)は、これらの事実を認定して「正露丸」の語は本件医薬品を指称する普通名称とはいえず、原告の商品の標章としてその商品識別の標識力を有し、かつ、その標識力は漸次増大しているものということができる旨判示したことが認められる。そして、その後も原告が多額の費用を投じて宣伝広告活動を行い、本件医薬品市場において、原告製品が今日でもなお売上金額ベースで80%を超える高いシェアを占めていることは、前記1(1)認定のとおりである。
また、証拠(甲55、56の1・2)によれば、Ipsos日本統計調査株式会社が平成17年10月から同年11月にかけて関東(東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城の各都県)及び関西(大阪、兵庫、京都、奈良、和歌山、滋賀の各府県)の20歳から69歳の男女合計500名を対象にしてweb調査の方法により実施した「正露丸」の認知度等に関する調査によれば、「『正露丸』は下痢止め薬ですが、あなたはこの『正露丸』は特定の会社の商品名であると思われますか。それとも下痢止め薬全般の一般名称であると思われますか。」という質問に対し、「正露丸」を特定の会社の商品名として認識していると回答した者が約86%、一般名称と認識している者が約14%、また同質問に対して特定の会社の商品名であると回答した者に対してさらに「あなたは『正露丸』を製造・販売している会社名をご存じですか。」との質問をしたところ、427名中54.6%の者が知っていると回答し、さらに「正露丸」について思いつくことを自由に筆記させたところ、497名中、51.5%の者が想起することとして原告の名称あるいは「ラッパのマーク」を挙げたとの結果が出たことが認められる。
もっとも、上記アンケート調査については、調査対象がたかだか500名にすぎないことや、その調査方法が「正露丸」の名称を認知している者に対し、「正露丸」を「特定の会社の商品名か下痢止め薬全般の一般名称か」という二者択一の方法で尋ねるというものであって、他の選択肢すなわち本件医薬品を指す普通名称が「正露丸」の他にもあり得ることを調査対象者の念頭に置かせた上でなされたものではないことなどから、上記調査結果に調査対象者の認識が正確に反映されているのかについて疑問を抱かせるところもないわけではないが、このような点を考慮しても、上記調査結果からすると、一般消費者の間では、「正露丸」から原告(ないしラッパのマーク)が想起される割合が高く、むしろそれが一般的であるとすらいえる傾向を有すること自体は認められる。
イ しかし、特定の業者の製造販売する普通名称を付した商品が大量の広告宣伝等を通じて大半のシェアを有するに至ったとしても、それだけで直ちにその普通名称がその業者の製造販売する商品を識別する機能を有する商品表示性を取得するものでないことは明らかである。前記認定のとおり、昭和29年10月30日以降も「正露丸」等の名称で本件医薬品の製造販売を行っている業者が複数存在し、売上金額ベースで高いシェアを誇る原告製品と比較して少額ではあるものの、本件医薬品全体の中で決して無視できない割合を占めている(原告製品と他社製品とでは相当の販売価格差があり、甲57に基づく被告の試算によれば、数量ベースでみれば原告製品のシェアは約60%になると認められることは前記のとおりであるから、それ以外の他社製品の販売シェアは相当大きなものであるこということができる。)。そして、現に、他社製品は、少なからぬ薬局・薬店・ドラッグストア等において、原告製品と並べて陳列され、それぞれ相当の価格差のある価格表示がなされていて、一般消費者に対して原告製品とはそれぞれが別個の商品であることを明示して販売されていることが認められる(甲33ないし35、36ないし38の各1・2、乙16の1~4)。
また、上記アンケート結果についても、その正確性に上記のような疑問があるほか、一般消費者が「正露丸」について思いつくことを自由に筆記させれば、その大量の宣伝広告活動やシェアの大きさ等から、まず原告の社名や「ラッパのマーク」を想起するのは当然というべきであり、そのことから直ちに一般消費者が「正露丸」をもって原告製品の識別表示として認識していると速断することはできず、かえって、一般消費者による上記連想からすれば、原告の社名やラッパの図柄をもって原告製品の識別表示として認識しているとの評価もできるのである。
ウ また、「正露丸」の語は、少なくとも「正露丸」の製造販売に携わる取引者の間では、前記のとおり、本件医薬品の一般的な名称として認識されており、原告製品を指称する商品表示として認識されているものではないというべきである。このことは、本件医薬品の小売業者が原告製品と他社製品とで販売価額に顕著な差異を設けていることや、原告製品と他社製品が薬局・薬店・ドラッグストア等においてそれぞれ別個の商品として並べて陳列販売されていることからみて疑うことができないことであると解される。そうである以上、一般消費者の間において「正露丸」の語から原告が想起される割合が比較的高いからといって、「正露丸」の語が原告製品を指称するものとして、取引者を含む需要者全体に認識されるに至ったものということはできない。
以上の点に加え、昭和52年以降本件訴え提起までの間に、原告が「正露丸」の名称で本件医薬品の製造販売を行っている他の業者に対し、その名称の使用を排除するための措置をとり、実際にその使用を中止させたことは一度しかないこと、原告は、原告製品の宣伝広告活動において、「正露丸」の表示とともに「ラッパのマーク」を強調していることなど、前記1(2)及び2(1)で認定した諸事実を総合すると、原告が巨額の宣伝広告費を投じてその製品の宣伝広告を行った結果、原告の製品は、昭和40年ころまでには、本件医薬品の需要の約90%を占めるに至ったこと、その後も原告は多額の費用を投じて宣伝広告活動を行い、本件医薬品市場において、原告製品は今日でもなお高いシェアを占めていることなど、前記認定の諸事実を考慮しても、「正露丸」の語が本件医薬品の製造販売に携わる取引者に対し本件医薬品を指称する一般的名称として受け取られていて、原告製品を指称する商品表示としては認識されていないことはもとより、一般消費者においても、それが本件医薬品の一般的名称ではなく原告製品を指称するものとして認識されるに至ったものとはいまだ認めるに足りないといわざるを得ない。
(4) 以上によれば、「正露丸」の語は、昭和29年10月30日以降の事情の変化により原告製品を識別する商品表示性を取得したものということはできず、現在においてもなお、本件医薬品を指称する普通名称であることを免れることはできないというべきである。
(5) また、「SEIROGAN」は、「正露丸」を単に欧文字で表したにすぎないから、これもまた本件医薬品を指称する普通名称というべきである。
(6) そうすると、原告表示2は、いずれも本件医薬品を指称する普通名称であって、商品の出所表示機能を有するものとはいえないから、不正競争防止法2条1項1号、2号所定の「商品等表示」には該当せず、また、被告が「正露丸」「SEIROGAN」を普通の方法で使用等する行為は、同法19条1項1号所定の除外事由に当たるものというべきである。
(7) したがって、その余の点について判断するまでもなく、不正競争防止法に基づく原告の請求は理由がない。
3 争点(3)のイ(商標権の効力制限)について
(1) 本件商標1は、普通の手書き書体の漢字「正露丸」の文字を縦書きにしてなるものであり、本件商標2は、普通の手書き書体の欧文字「SEIROGAN」の文字を横書きにしてなるものであるところ(甲10、11の各1)、前記2で説示したとおり「正露丸」及び「SEIROGAN」の語は、いずれも本件医薬品の普通名称である。被告標章1は、被告製品の包装箱正面に普通の毛筆体で漢字「正露丸」を縦書きしたものであり、被告標章2は、被告製品の包装箱背面に普通の書体で欧文字「SEIROGAN」を横書きしたものである。
そうすると、被告標章は、いずれも本件医薬品の普通名称を普通に用いられる方法で表示したものにすぎないから、本件商標権の効力は、被告標章には及ばない(商標法26条1項2号)。
(2) したがって、その余の点について判断するまでもなく、本件商標権に基づく原告の請求は理由がない。
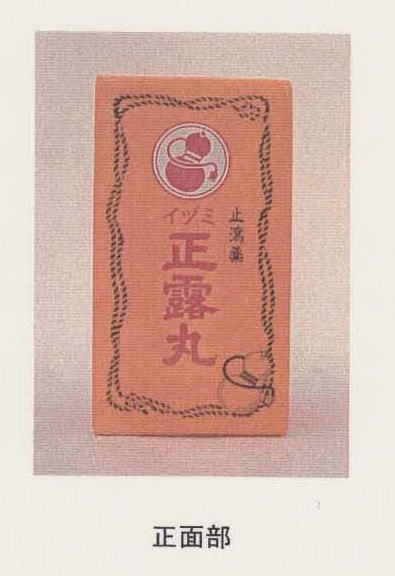

被告製品 原告製品
名称使用差止等請求事件(「天理教豊文教会」事件)
| 事件番号 | 平成17年(受)第575号 |
|---|---|
| 事件名 | 名称使用差止等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年01月20日 |
| 法廷名 | 最高裁判所第二小法廷 |
不正競争防止法は、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提に、経済活動を行う事業者間の競争が自由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ、あるいは、社会全体の公正な競争秩序を破壊するものである場合に、これを不正競争として防止しようとするものにほかならないと解される。そうすると、同法の適用は、上記のような意味での競争秩序を維持すべき分野に広く認める必要があり、社会通念上営利事業といえないものであるからといって、当然に同法の適用を免れるものではないが、他方、そもそも取引社会における事業活動と評価することができないようなものについてまで、同法による規律が及ぶものではないというべきである。これを宗教法人の活動についてみるに、宗教儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活動に関しては、営業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提とするものではなく、不正競争防止法の対象とする競争秩序の維持を観念することはできないものであるから、取引社会における事業活動と評価することはできず、同法の適用の対象外であると解するのが相当である。また、それ自体を取り上げれば収益事業と認められるものであっても、教義の普及伝道のために行われる出版、講演等本来的な宗教活動と密接不可分の関係にあると認められる事業についても、本来的な宗教活動と切り離してこれと別異に取り扱うことは適切でないから、同法の適用の対象外であると解するのが相当である。これに対し、例えば、宗教法人が行う収益事業(宗教法人法6条2項参照)としての駐車場業のように、取引社会における競争関係という観点からみた場合に他の主体が行う事業と変わりがないものについては、不正競争防止法の適用の対象となり得るというべきである。
(中略)
1 氏名は、その個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、その氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁昭和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号27頁参照)ところ、これを違法に侵害された者は、加害者に対し、損害賠償を求めることができるほか、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることもできると解するのが相当である(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁参照)。宗教法人も人格的利益を有しており、その名称がその宗教法人を象徴するものとして保護されるべきことは、個人の氏名と同様であるから、宗教法人は、その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し、これを違法に侵害されたときは、加害者に対し、侵害行為の差止めを求めることができると解すべきである。
他方で、宗教法人は、その名称に係る人格的利益の一内容として、名称を自由に選定し、使用する自由(以下「名称使用の自由」という。)を有するものというべきである。そして、宗教法人においては、その教義を簡潔に示す語を冠した名称が使用されることが多いが、これは、宗教法人がその教義によって他の宗教の宗教法人と識別される性格を有するからであると考えられるのであって、そのような名称を使用する合理性、必要性を認めることができる。したがって、宗教法人の名称使用の自由には、その教義を簡潔に示す語を冠した名称を使用することも含まれるものというべきである。そして、ある宗教法人(甲宗教法人)の名称の保護は、他方において、他の宗教法人(乙宗教法人)の名称使用の自由の制約を伴うことになるのであるから、上記差止めの可否の判断に当たっては、乙宗教法人の名称使用の自由に対する配慮が不可欠となる。特に、甲、乙両宗教法人の名称にそれぞれその教義を示す語が使用されている場合、上記差止めの可否の判断に際し、単に両者の名称の同一性又は類似性のみに着目するとすれば、名称使用の自由を制限される乙宗教法人は、その宗教活動を不当に制限されるという重大な不利益を受けることになりかねず、また、宗教法人法が宗教法人の名称につき同一又は類似の名称の使用を禁止する規定を設けなかった立法政策にも沿わないことになる。
したがって、甲宗教法人の名称と同一又は類似の名称を乙宗教法人が使用している場合において、当該行為が甲宗教法人の名称を冒用されない権利を違法に侵害するものであるか否かは、乙宗教法人の名称使用の自由に配慮し、両者の名称の同一性又は類似性だけでなく、甲宗教法人の名称の周知性の有無、程度、双方の名称の識別可能性、乙宗教法人において当該名称を使用するに至った経緯、その使用態様等の諸事情を総合考慮して判断されなければならない。
(中略)
被上告人は、宗教法人法に基づく宗教法人となってから約50年にわたり「天理教豊文分教会」の名称で宗教活動を行ってきたのであり、その前身において「天理教豊文宣教所」等の名称を使用してきた時期も含めれば80年にもわたってその教義を示す「天理教」の語を冠した名称を使用していること、このような中で、被上告人が従前の名称と連続性を有し、かつ、その教義も明らかにする名称を選定しようとすれば、現在の名称と大同小異のものとならざるを得ないと解されること、被上告人は、上告人との被包括関係の廃止により上告人と一線を画することになったとはいえ、中山みきを教祖と仰ぎ、その教えを記した教典に基づいて宗教活動を行う宗教団体であり、その信奉する教義は、社会一般の認識においては、「天理教」にほかならないと解されること、被上告人において、上告人の名称の周知性を殊更に利用しようとするような不正な目的をうかがわせる事情もないこと等が明らかである。そうすると、被上告人がその名称にその教義を示す「天理教」の語を冠したことには相当性があり、また、そのような名称の使用ができなくなった場合、被上告人の宗教活動に支障が生ずることは明らかであり、その不利益は重大というべきである。「天理教」の語が教義を示すものである以上、教義の普及と拡散に伴い、上告人において「天理教」の語を含む名称を独占することができなくなったとしても、宗教法人の性格上やむを得ない面があることも認めざるを得ない。
異議申立棄却決定取消等請求控訴事件(品種登録)
| 事件番号 | 平成17年(行コ)第10001号 |
|---|---|
| 事件名 | 異議申立棄却決定取消等請求控訴事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年12月25日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
本件は、りんどうの品種改良、生産、販売等を行っている控訴人らが、「芸北の晩秋」という名称のりんどうについて被控訴人がした別紙品種登録(本件処分)に、重大かつ明白な瑕疵が存在すると主張して、本件処分の無効確認を求めたものである。
(中略)
なお、確かに、控訴人らが主張するように、開花時期が異なる等の理由で、母系品種の花の形状、色等を直接確認することが困難である場合には、母系品種の開花時期に合わせて現地調査を再度実施するか、出願者に公証人関与などの厳格な条件下で撮影した写真を追加提出させるなど、安定性を確認するに万全な方法を講ずるのが望ましかったということはできる。
しかしながら、そのような万全な方法を常に講ずることは、いささか望蜀であるというべきであり、本件処分において、C審査官が行ったように出願者から慎重に事情聴取を行ったということでも、具体的に安定性を否定するような状況が生じたとは認められないのであるから、必要な調査は行われているということでき、控訴人らの主張するように手続上違法があった、とはいうことができない。
種苗生産・譲渡行為差止等請求控訴事件
| 事件番号 | 平成18年(ネ)第10059号 |
|---|---|
| 事件名 | 種苗生産・譲渡行為差止等請求控訴事件 |
| 裁判年月日 | 平成18年12月21日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
ところで、特許権に関しては特許無効審判を経なくても、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者は特許権の侵害に係る訴訟において相手方に対してその権利を行使することができないとされており(特許法104条の3第1項)、この規定は実用新案権、意匠権、商標権の侵害訴訟にも準用されているが、種苗法の育成者権の侵害訴訟には準用されていない。しかし、これは種苗法が特許法のような独自の無効審判制度を設けていないことによるものと考えられるが、種苗法においても、品種登録が上記①ないし⑤の規定に違反してされたものであり、農林水産大臣により取り消されるべきものであることが明らかな場合(農林水産大臣は、品種登録が上記①ないし⑤の規定に違反してされたことが判明したときはこれを取り消さなければならないのであって、その点に裁量の余地はないものと解される。)にまで、そのような品種登録による育成者権に基づく差止め又は損害賠償等の請求が許されるとすることが相当でないことは、特許法等の場合と実質的に異なるところはないというべきである。けだし、上記①ないし⑤の規定に違反し、取り消されるべきものであることが明らかな品種登録について、その育成者権に基づいて、当該品種の利用行為を差し止め、又は損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、育成者権者に不当な利益を与え、当該品種を利用する者に不当な不利益を与えるものであって、衡平の理念に反する結果となるし、また、農林水産大臣が品種登録の取消しの職権発動をしない場合に、育成者権に基づく侵害訴訟において、まず行政不服審査法に基づく異議申立て又は行政訴訟を経由しなければ、当該品種登録がその要件を欠くことをもって育成者権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、訴訟経済に反するといわざるを得ないからである。したがって、品種登録が取り消される前であっても、当該品種登録が上記①ないし⑤の規定に違反してされたものであって、取り消されるべきものであることが明らかな場合には、その育成者権に基づく差止め又は損害賠償等の権利行使(補償金請求を含む。)は、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である(最高裁判所平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁参照。なお、品種登録に重大かつ明白な瑕疵がある場合には、育成者権に基づく侵害訴訟においても、当該品種登録の当然無効を主張することができると解されるが、行政処分の当然無効は、行政処分時において重大かつ明白な瑕疵がある場合に限られるところ、当該品種登録が上記①ないし⑤の規定に違反してされた場合に、仮にそれが重大な瑕疵に当たると解し得るとしても、その瑕疵が品種登録時において常に明白であったとは限らないから、上記①ないし⑤の規定に違反してされた品種登録が常に当然無効であるとまではいえない。本件において、被控訴人は、ホクト2号の品種登録時において種苗法3条1項1号に違反することが明白であったことまでを主張立証するものではなく、被控訴人の前記主張は、種苗法3条1項1号所定の品種登録の要件を欠いていることを理由に、ホクト2号の育成者権の行使の権利濫用を主張する趣旨を含むものと解されるところ、このように解することについては、控訴人も争っていないと認められる。)。
まいたけ育成者権侵害差止等請求事件
| 事件番号 | 平成20年(ワ)第23647号 |
|---|---|
| 事件名 | 育成者権侵害差止等請求事件 |
| 裁判年月日 | 平成21年02月27日 |
| 裁判所名 | 東京地方裁判所 |
第2 事案の概要
本件は、種苗法に基づき品種登録されたまいたけの育成者権を有する原告が、被告らにおいて、購入した上記まいたけの種菌を自家増殖し、まいたけを生産及び販売した行為が、原告の上記育成者権を侵害するとして、被告らに対し、種苗法33条1項、2項に基づく上記まいたけの種苗の生産、譲渡等の差止め及び廃棄、同法44条に基づく信用回復措置としての謝罪広告の掲載並びに民法709条に基づく損害金及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みに至るまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(判旨)
第3 争点に対する判断
1 争点1(被告ワイフーズによる本件登録品種の種苗の利用が、種苗法21条2項の自家増殖に該当するか)について
種苗法21条2項の自家増殖の特例が認められるためには、「農業を営む個人」又は農地法2条7項にいう「農業生産法人」であることが必要である(種苗法施行令5条)ところ、証拠(乙1の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば、被告ワイフーズが株式会社であること、平成20年7月25日に常陸太田市農業委員会より、同市に所在する4筆の畑の賃借につき、同法3条1項の許可を受けたことが認められる。しかしながら、本件全証拠によっても、被告ワイフーズの株主構成及び同被告の唯一の取締役であるAが常時従事者であるかは明らかではなく、同法2条7項に規定されたその他の要件に該当する事実を認めることはできず、また、上記畑の賃借につき同法3条1項の許可を受けたからといって、直ちに同被告が農業生産法人に該当すると認めることはできない。
したがって、その余について検討するまでもなく、被告ワイフーズによる本件登録品種の種苗の利用について、種苗法21条2項の適用を認めることはできず、この点に関する被告らの主張は理由がない。
2 争点2(被告環による被告ら商品の販売について、原告の許諾があるか)について
弁論の全趣旨によれば、原告と被告環との間において、本件契約が締結された事実は認められるものの、平成18年7月20日付け覚書には、自家増殖によって得た被告ら種苗を用いて生産された被告ら商品についての販売の許諾に関する記載はなく、他に本件契約によって原告が当該許諾をしたと認めるに足る証拠もない。
したがって、この点に関する被告環の主張は理由がない。
3 争点3(被告ら商品の生産及び販売を差し止める必要があるか)について 上記前提となる事実等(4)のとおり、被告ワイフーズ及び被告環は、少なくとも平成19年1月から平成20年7月末日までの間、被告ら種苗を用いて被告ら商品を生産し、これを販売したのであるから、現在及び将来にわたって、同様の行為を継続するものと推認することができ、その推認を覆すに足りる証拠はない。
したがって、被告らによる被告ら商品の生産及び販売を差し止める必要があると認めることができる。
4 争点4(損害の発生及びその額)について
(1)上記前提となる事実(1),(4)及び弁論の全趣旨によれば、被告らの間において、被告ワイフーズが生産した被告ら商品を被告環が販売するという関連共同性を認めることができ、また、これまで認定した事実を総合すれば、被告らにおいて、少なくとも、本件育成者権侵害についての過失を認めることができる。
したがって、被告らによる被告ら商品の生産及び販売については、共同不法行為が成立し、被告らは、連帯して本件育成者権侵害と相当因果関係を有する損害を賠償する責任を負うというべきである。
(2)被告ら商品の生産及び販売に係る損害について
上記前提となる事実等(4)、甲第4号証及び第6号証並びに弁論の全趣旨によれば、被告らが譲渡した被告ら商品は、合計76トン(4トン×19か月)であること、それを被告ら種苗の数に直すと、1万3813本であること、原告において、被告らによる侵害行為がなければ販売することができた本件登録品種の種苗1本当たりの利益は、753円であることが認められる。
したがって、種苗法34条1項により、被告ら商品の生産及び販売による損害額については、1040万1189円であると認められる。
(3)本件の調査費用について
証拠(甲6、7、甲8の1、2)及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件の調査費用として、合計5万2400円を費やしたものと認められ、これは、被告らによる被告ら商品の生産及び販売と相当因果関係のある損害であると認められる。
(4)弁護士費用について
本件に表れたすべての事情を総合考慮すれば、被告らによる被告ら商品の生産及び販売と相当因果関係のある弁護士費用額は、50万円であると認められる。
(5)小括
以上によれば、被告らは、原告に対し、連帯して、合計1095万3589円の損害を賠償する責任を負うものと認められる。
5 争点5(信用回復措置の要否)について
原告が求める信用回復措置については、認容された損害賠償の額及び前記認定事実に照らしてその必要性を、 認めるに至らないから、同措置に係る原告の請求は、理由がない。
第4 結論
以上の次第で、原告の被告らに対する種苗法33条1項、2項に基づく差止及び廃棄請求並びに民法709条に基づく損害額1095万3589円及びこれに対する遅延損害金の請求はいずれも理由があるから、これらを認容することとし、その余の請求は理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。